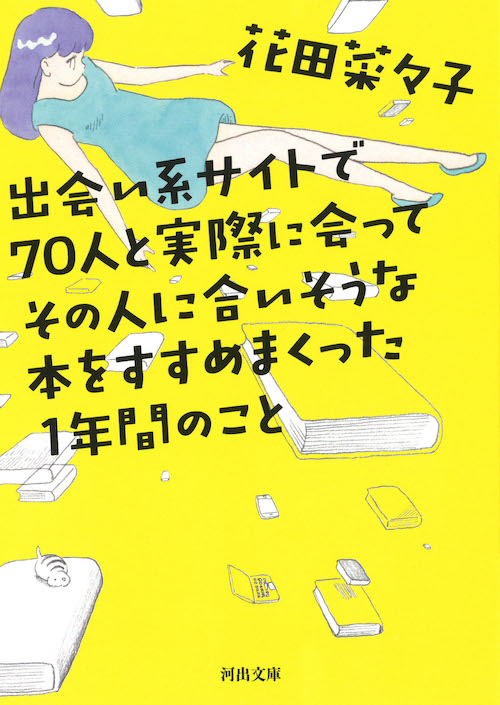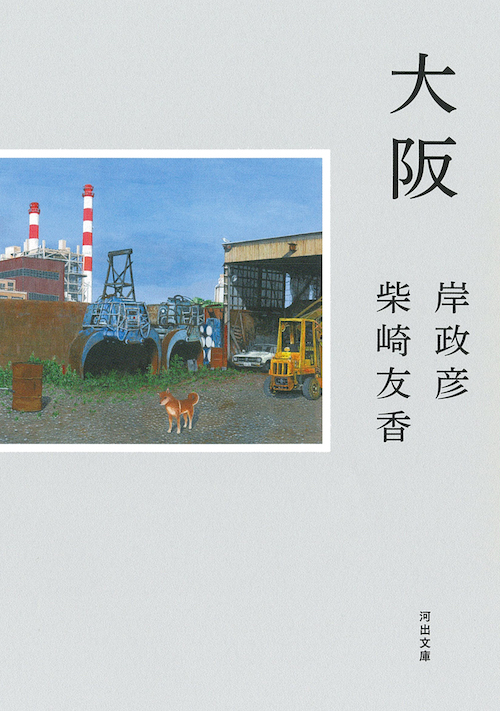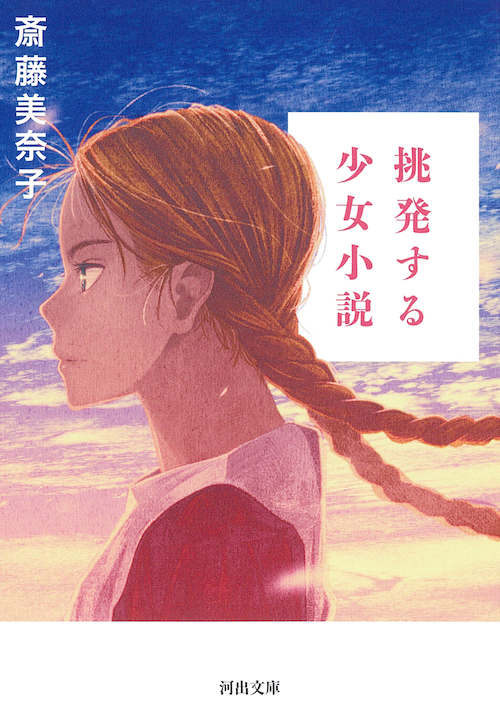単行本 - 日本文学
【試し読み】第2章『シングルファーザーの年下彼氏の 子ども2人と格闘しまくって考えた 「家族とは何なのか問題」のこと』
花田菜々子
2020.02.26
ついにオープンの日、朝。目がさめても涙がこぼれた。いつものように腫れぼったい目で、自転車を漕ぎながら店に向かう。いろんな人のいろんな言葉が頭の中を飛び交っていた。その言葉を聞くでもなく聞きながら、
「まあ、冷蔵庫に豚肉しか入ってないのに、フォアグラのせのステーキなんか作れるわけがないし……ダサくても、ダサいなりに、ありもので自分がやれるベストをやるしかないのだよな……。それでダサいとかつまんないって言われたらそれは事実として受け止めるし。それに今日が結果発表じゃない。ここから、今日からもっとよくなればいいだけだもんな」
と、突然にあきらめがついた。自分がたいしたものじゃないことを受け入れてしまえばよかったのかも。それだけのことだったのだ。なんだか急にすっきりした気持ちで店に到着した。
時間になってガラス戸を開けるとたくさんのお客さんが次々と入ってきた。みんな次々に声をかけてくれるし、さっそく、
「こんな本を探してるんだけど」とか「○○って雑誌をこれから入るようにしてもらえない?」とか話しかけてくれる。
その間にもお客さんがどんどんレジに本を持ってきてくれて、釣り銭に用意していた千円札が足りなくなってしまった。小さな子がベタに「買って買って」と駄々をこねて母親の手をひっぱっている横で、80歳くらいのおばあちゃんがもうずっと『世界でいちばん美しい昆虫図鑑』を立ち読みしている。
お世話になっている人たちも次々と駆けつけてくれて、「すごくいいね」「これ、夢の本屋だね」と声をかけてくれて、自分のことのようにこの光景をいっしょに喜んでくれた。
何人ものお客さんが言ってくれたのが、
「この街には今まで本屋がなくてほんとうに不便だった。だからこんな店ができてうれしい」
という言葉だった。こんなに歓迎されることなのか。すごいよ。街の本屋、切望されてるじゃん。よかった、ほんとうによかった。
そう思ったら、今朝考えてたあれ、何だったっけ……あの中学生みたいなやつ……。と、一生懸命思い出そうとしたけど、もう思い出せなかった。今の自分と、もう噛み合わなかった。
「店に立つことが好きなんだなあ、やっぱり」
それはすごくひさしぶりに、自分の心に自分の魂が戻ってきたような懐かしさだった。床の上に投げ出されてぴちぴち跳ねている金魚を水槽の中に戻したら、金魚は何の喜びも驚きもなく、スーと当たり前に普通に泳ぎだすだろう。まさにそんな感触で、やっと自分の空の水槽に水を注いでもらったような気がした。
「あ、そうそう、わたし水の中の生き物だったんだ、そういえば」と泳ぎながら思った。
そんなふうにして、この店と私はここに居るようになった。
金色の西日が差す店で
お客さんがいる時間も、お客さんがいない時間もどちらもいいものだ。店は一日のうちにいろんな顔になる。たくさんの親子が来店して賑やかなとき。何人かのお客さんが静かに過ごしているとき。1対1でお客さんと話しているとき。
その中でも特別に好きな時間がある。子どもがひとりで店にやってきて、熱心に立ち読みを始めて、完全に自分の世界に入っているときだ。そんなときは、なるべく邪魔をしたくないので、電話をしたりバタバタした作業をしたりはしない。できる限り、自分もカウンターの中のスツールに腰かけて本を読む。10坪のスペースは全体に目が行き届くし、お互いに気配を感じる広さだ。知らない人だけど、子どもだけど、そんなふうに同じように読書をしている人を視界の端に感じながら本に没頭する時間はいいものだ。自分がそういうときになるべく本を読むようにしているのは、「あなたのことを気にしていないよ、立ち読みをやめて出ていってほしいなんて少しも思っていないよ」というメッセージのつもりもある。
子どもは思った以上に臆病で、知らない大人の意向や視線を気にする。場合によっては「上のほうにある本が取れなかったら言ってね」と声をかけるだけでびっくりして帰ってしまうこともある。とてもナイーブな存在なのだ。相手が萎縮しないように受容することが大事だ。
本が好きな親子のお客さんの会話を盗み聞きできるのも、この小さな店の店長の特権だった。そんなお客さんたちの会話は、言葉のはしばしがきらめいていて、理想の関係だった。よく教育関係の本に書いているようなことだけど、親の人たちは子どもが選ぶ本を決して否定しない。漫画っぽい本だったり赤ちゃん向けの本でも「へえ、どんな本? 面白そうだね」「わあ、かわいいねえ」「ああ、これ保育園にあった本だね、好きだったよね」と声をかけて、興味を持ってあげている。そしてそういう親御さんは自分用の本も買っていくことが多い。
本好きの親に育てられた本好きの子どもは、私からみればうらやましいかぎりだけど、そうでない子どもにも平等に窓が開かれているのが本のよいところでもあると思う。
そういう意味では「本好きの親に育てられる生粋の本読みエリート」ではなかったが、子どもの頃は両親が大量に絵本を与えてくれていたし、読み聞かせもずいぶんしてくれた。「せいめいのれきし」や「はじめてのおつかい」「だるまちゃんとてんぐちゃん」などは当時大好きだった絵本だが、大人になって再会するまでは存在すら忘れていた。けれどその表紙に出会った瞬間に、すべてが噴き出すように記憶が蘇った。ページをめくるとどのイラストも、セリフも、鮮やかに思い出せるのが不思議だった。でもそんな体験をしている大人は多いのではないか。一度記憶した絵本のページは、今も開くたびに子ども時代の幸せな記憶を蘇らせてくれるから、同じ宝物を子どもにも渡したいと思う人が多いのだろう。
「子ども」に接客をする日々は、とても新鮮なものだった。
今までの書店員人生では、絵本について特に集中して勉強したことがなかったので、絵本に詳しくなるため、空いた時間に絵本雑誌をすみずみまで読んだり、閉店後に大きな本屋の絵本コーナーに通って、たくさんの絵本に目を通した。
子どもの頃に知らなかった本で、特に印象に残った絵本との出会いがいくつかあった。
そのうちの一冊は、だいぶ昔の絵本。『やっぱりおおかみ』という佐々木マキさんの絵本だ。村上春樹の本の挿絵などを描いている人なので名前だけは知っていたが、絵本の作品はきちんと読んだことがなかった。ひとりぼっちのおおかみが町をさまよい、ともだちがほしくて自分に似た子を探すのだがどこにもいないし、怖がられて逃げられてしまう。家族のだんらんの様子を窓の外からのぞき、「け」と悪態をつくが心の中はさびしさでいっぱいだ。行く場所のない狼は墓地で野宿する。おばけたちが集まってきておおかみを見つめている。仲間でも敵でもない、不思議なやさしさの眼差し。夜が明けて、おおかみはひとりで生きていく決断をするのだが、もうそこに悲しさはなく、愉快さがおおかみの心を満たしている……。
子ども向けの本としてはびっくりするようなラストなのに、独特の明るさと美しさがあった。大人になってからこんな素敵な本に出会えるなんて。絵本も詳しくなると日ごとに魅力がわかるようになって楽しい。「大人向け絵本」なんともはや手垢のつきまくった言葉でもあるが、しかし実際に名作といわれる絵本には大人を魅了する強度があることを、この店での仕事を通して知ることができたのだ。
そしてそれを次の日からお客さんにどんどん紹介していいなんて、なんとありがたすぎる仕事なんだ。
たとえば10歳くらいの男の子。ひとりで長く棚の前で過ごしたあと、椰月美智子の『しずかな日々』のジュニア文庫版をレジに持って来てくれる。好きな本なので思わず「私もこの本が好きなのでうれしいです」と伝えると「僕は長い話のほうが好きなんです」という返事。会話ができたことにうれしさを感じつつ、帰ってからもあれはどういう意味だったのだろうと反芻する。でも私と大人同士のように会話しようとしてくれたのだろう、ということと、おそらくは学校では「そんな長い話の本を読むなんて」とちょっと浮いていたり、あるいはみんなから尊敬されていたりするのかもしれない。噛み合っていない会話のようで、でも何か自分の言葉で答えてくれたということがうれしかった。
子どもらしい騒ぎもある。
「心理テストの本はありますか?」と聞いてきて2人で問題を出し合っていた女子小学生が「はい、次お姉さんが答える番」と突然巻き込んできたり、7人くらいの女の子が一斉にやってきて、全員で座り読みを始めたので、「なぜ」と思ったのだがその姿があまりにかわいくて、「写真撮ってもいい?」と聞いて1枚だけ撮らせてもらったり。一方で無言で店に入り、所定の位置で立ち読みし、一定時間が経つと突然何かに突き動かされるように店を出て行く野武士のようなクールな小学生の常連もいるし、本好きでお母さんといっしょに来る子は、大人のように最近読んだ本について聞かせてくれたりもする。
もちろん面白いのは子どもだけではない。大人のお客さんとも、だんだんと仲が深まっていった。出会い系をしていたときの、短い時間でぱっと仲良くなる関係性も好きだったけど、何度も顔を見て、少しずつやりとりが深まっていく関係性は、またそれとは違った形に育っていく。
レジにいると、「こんなところに本屋があったんですね」あるいは「ここにある本は誰が選んでいるんですか?」「面白い品揃えですね」などと、会話を始めてくださる方が多かった。
私が不思議だったのは、なぜ彼らはこんなにも自分の話をしてくれるのだろうか、ということだった。
私はそれまで自分が「店の人に話しかける」ということをほとんどしたことがなかったので、彼らの自然さや、礼儀正しくも親しみのある態度に驚いたし、単純にうれしかった。会話するって、アリだったのか。
そう気づいてからは、自分からも、棚を長く見てくださっているお客さんや、何か買ってくれるお客さんには「今日は暖かくなりましたね」とか「この本いいですよね」とか、そんなことでも一言付け加えるようにしていた。これは会話をしたくない人には「ええ」「まあ」という返答で済ませられる内容だから、そういう返答の人にはそれ以上話し続けることはしないし、逆に会話をしたい人は「また週末は雨らしいですよ」とか、「知らない本でしたけど手にとって見たら面白そうで」とか答えてくれるのがポイントだ。しかし、そのような話しかけ方をすると不思議なことに、その話しかけについての返答ではなく、自分の話したいことを話し始めるお客さんがけっこうな割合でいるのだった。
「今日は、実は埼玉から来たんです」
「僕は子どもの頃、絵本ってほとんど買ってもらえなくて」
「最近まで入院してたんですよ」
みな、唐突すぎる。だが、こういう展開は正直言って大好きなものだった。
なにか、まあこの人にならちょっと話してみようか、と思う空間・時間であることができたのだろう。なので私も驚くようなそぶりは一切見せずに、極めて普通に「ああ、そうでしたか」と話をつなげる。その先に聞ける話は、どんな話でも面白い。私の知らない世界がどんどん湧き出てくる。
それに、そんなふうに話を聞かせてくれたお客さんは、次からはちょっと慣れた表情でお店に入って来てくれるようになった。
かくして、お客さんがやたらと話し込む本屋に仕上がっていった。友達じゃないし、仕事相手でもない。店員と客、なのだが、その呼び名もちょっとなじまない。何とも名付けられない関係に思えた。
そういう人が増えると、どのお客さんが前回どんな本を買ったか、どんな話をしていたかを覚えておく必要がある、と思い、ノートにメモを取っておくことにした。会話をした人のことは、なるべく全員メモする。名前がわからない人はとりあえずイメージで仮の苗字を当てはめていく。取り寄せの注文をもらうときに始めて名前を知って、「全然違った!」と脳内で答え合わせするのも地味に楽しかった。話す人がどんどん増えて、メモはメモというよりはもはや長文の日記になっていた。
顔なじみの人が店に現れるというのは、今までに体験したことのない感情だった。安心するような、心を許せるような、それだけでいいことがあったような、そんな気持ちになれる。話し込むこともあれば二、三言かわして本を買って帰っていくだけのこともあるけど、そんなつながりが心をちょっとだけ明るく灯してくれるようだった。
こんな人間関係がずっとこの街で続いていくのだろうか。それはすごいことだと思った。オーナーは「いつまででもいてくれていいんだよ。30年とか」と言ってくれていた。そんな人生があるのか。それはきっと今まで見てきた景色と全然違うだろう。まるで絵本の『おおきな木』みたいでもある。木はずっと動かずに、そこに集まる人たちの成長や変化をただ見届ける。
子どもたちが大きくなったり、かつて子どもだったお客さんに子どもが生まれたりもするのだろう。あるいは、話にはときどき聞くが、常連さんの死を、取り寄せの注文や定期購読を買いに来なくなったことから知ってしまったりするのだろう。そんな「街の本屋」として一生を終える─。私は70歳になったとき、どんな本棚を作っているのだろう。それはきっと「私」ではなく、この街の人たちによって作られた本棚とも言えるのだろう。街で本屋の生き字引みたいになっているのか。「この本屋ができた頃は、この辺にもマンションがいっぱいあって、子育てをしているお母さんたちがたくさん来てくれていたんじゃよ」とか老人口調で言ってたりして。その頃この辺りがどうなってるのか想像もできないけど。そんな人生もありかもしれないな。
この店が私の終着点。この街で、この街の人たちといっしょに生きていく。
そんな人生を想像してみたりもした。
リベンジのはじまり
「今日晩ごはん作ったんだけど、よかったら食べに来てよ」
ある日、トンからそんな誘いがきた。
トンの家は職場から自転車で15分ほどのところにある。断ろうと思えばもちろん断れたのだが、なんとなく子どもたちともシラフ(?)でもう1回会ったほうがいいのではないかと思い、再びトンの家に足を踏み入れた。
「こんばんは……」
2人ともこの前とまったく同じ反応だった。構えて緊張しているのがしびれるほど伝わった。けれど私だって同じ気持ちだ。慣れてくれば普通になるのかな、慣れるなんてことあるのかな、と思いつつ、なんでもないように出されたごはんを食べることにする。マルちゃんがまたじっと凝視してくるので、こういうときにオバチャン、もしくは幼稚園の先生感丸出しで「ん〜? なあに? どうしたのかな〜?」とか言うと距離が開いてしまう気がしたのでそのような反応をするのはためらわれた。なにか……なにかこう、面白い人でなければ。必死で考えたあげくに白目で見つめ返す(見えてないけど)ことにした。
「んふっ……こわっ!」
ウケている。はあ。よかった。笑わせ返そうと一生懸命変顔をしてくれているのでそれに反応して笑いつつ、さらにこちらも白目に戻してちょっとだけ薄ら笑いを浮かべるようにする。
「怖い怖い怖い!」
いつでも白目ができる技術、何かの役に立つ日が来るとは思ってもみなかったが、まさかこんなところに使い道があったとは。助かる。
こういう感じかあ。なるほど。よし、この方向性でなんとかがんばってみよう。とにかくオバチャンがやりがちな「猫なで声話しかけ戦法」は絶対に禁止だ。なるべくクールにフラットにいこう。他にもおそらく「学校楽しい?」「学校ではいま何が流行ってるの〜?」みたいなつまらない質問もダメな気がする。いわゆる「つまらん大人」に区分されることは避けなければならない。
壮大な実験が、こうして始まった。
それからも彼らが学校が休みの前の日に、家に遊びに行くことにした。
いっしょに夜ごはんを食べて、彼らが休前日に起きていてもいいと決められている夜23時半までボードゲームやトランプをしたりして遊ぶ、というルーティンが何となくできていった。
11歳と8歳の生活は、私の予想や想像に反することばかりで、いつも驚かされた。まず、彼らはいつもタブレットをさわってゲームをしていた。それに夢中なのだとしたら邪魔しては悪い、と思って遠慮していたが、どうもゲームは暇つぶしで仕方なくやっている時間が多々あり、トンが声をかけると名残惜しそうでもなくすぐにやめることも多い。我々の、ツイッターを見るでもなく見てるときと同じ感覚なのかもしれない。
ゲーム以外には好きなことがあまりなさそうで、なんだかかわいそうに感じる。これは勝手な思い込みだろうか。ゲームをすることとYouTubeで動画を見ること、たまにテレビを見ることで彼らのプライベートは構成されているようだ。
あと、全然ごはんを食べない。小学生男子といえば、ハンバーグ! トンカツ! ステーキ! みたいな感じかと思っていたけど、食べることにはほとんど興味がないらしい。まあ、ごはんが嫌でもお菓子なら食べるのだろう、と思いきや、ミナトにいたってはチョコが食べられないらしい。お菓子をあげれば食いついてもらえるのではないか、という期待(?)は早々に裏切られた。マルちゃんはお菓子に興味がないこともないけど、チョコはやっぱり好きじゃないみたいだし、スナック菓子もほとんど食べなくて、じゃあ何が好きなのかというと、つぶグミかポイフルの2択なのだ。それ以外は一切認められていないようだ。「これもおいしそうじゃない?」と言って果汁グミやHARIBOを買っていってもまったく興味を持たない。保守派?
また、2人とも炭酸のジュースは狂ったように好きで、逆に炭酸の入ってないドリンクはそれだけでものすごく地位が低いようだ。お茶はまったく飲めないらしい。
最初はほぼ同じ生きものに見えていた2人だったが、慣れて見分けがつくようになってくると2人の個性はむしろ真逆だった。
5年生のミナトはシャイで、自分から話しかけてくれることはほとんどないけど、頭が良くて話すことも大人っぽくて、徐々にだけど普通に会話をしてくれるようになった。というか、ゲームというものがあると会話が生まれざるを得ないので、そのおかげで自然に話せる感じがしている。ゲームってすごいね、ゲームありがとう、と思う。そもそもゲームの強さは大人とほとんど変わらないし、大人と話すように話せる。
それに対してマルちゃんは感情豊かで明るくて、こちらが緊張してしまっているときでもあれこれ話しかけたりしてくれるのだけど、ゲームで負けたとき、自分の思い通りにならないとき、すぐに癇癪を起こして泣いて暴れる。こういうのって3、4歳の行動ではなくて小学生でもするものなのか。知らなかった。マルちゃんがそういう状態になるたびに楽しい雰囲気だった時間は中断されざるを得なかった。なので、楽しくゲームをしているつもりがマルちゃんが泣き喚いてなんとなくフェイドアウト、みたいになるのが常だった。
それだけならまだしも、その様子に呆れたミナトの「マルまじでうぜえわ」と挑発するような一言に反応して、マルちゃんが泣きながらミナトを殴る、蹴る。ミナトも最初はマルちゃんの暴力に対して「はあ〜? こいつ馬鹿じゃないの?」みたいな感じでスルーしているのだが、マルちゃんがやめないので最終的に倍の力で殴り返すことになって、かなり強い力で殴り合う展開になる。そういうものをあまり間近で見たことがなかったので「こんなに強い力で躊躇なく殴り合って骨折れたりしないのかな?」とハラハラしたが、トンも放置している。これが日常のようだ。
エスカレートしきったところでトンが「いい加減にしろ」と止め、2人とも消化不良の険悪なムードだけが残る。引き際がわからなくなったマルちゃんが「どうせ俺なんか死ねばいいんでしょ」「も、いいわ、今から外行って車に引かれてくるから」と言って微妙に出て行こうとしたり、それを微妙に止めたり、というのが何回も繰り返されるのである。子どもってこんな感じ? どこの家でも?
しかし、良くも悪くも私にはこの2人以外のサンプルがない。この2人がめちゃ平均的だったとしてもそうでなかったとしても、だからといって何か変わるわけでもない。
この2人をどう理解し、どう関係を築き上げていくかということだけが私の問題だ。
しかしそんな理想論を前に、とにかくいっしょにいることが果てしなく疲れた。
2人の騒ぎというかパワーに疲れる、というのももちろんだったが、たとえば部屋中がガンプラとかドラゴンボールのフィギュアとかにあふれ、そこらじゅうに学校からのプリントやお菓子のごみやバトルゲーム用のカードが散らかっていることや、食器がすべて100円ショップのプラスチックのものや子ども向けの把手のついたカップばかりだったりするのも地味につらかった。
自分だってべつにそれほどセンスがあったり、こだわったものを使っているわけではないが、逆に100円ショップの食器を使うことが自分にとってストレスなのだということを生まれてはじめて知り、そのこともショックだった。なんという心の狭い人間。しかし自由なひとり暮らしが長いとそうなってしまうのかもしれない。
ここ数年のライフスタイルのブームとも言える「私らしい、ていねいな暮らし。」にはとんでもない副作用もあるのだ。台湾旅行中に買ったアンティークの鳥籠をランプシェードにリメイクしたりしてうっとりしていたあの頃(つい最近)からはずいぶん遠くに来てしまったようで、途方に暮れた。
寝ついた2人を確認してから、そっと家を出る。家まで送ってくれるというトンと2人、しんとした深夜の住宅街をのろのろと自転車で走る。
「ほんとにごめんね、あんな感じで……。疲れたでしょう?」
「いや、大丈夫だよ〜(棒)」
「子ども、かわいいんだけどね、かわいいだけじゃないよね」
「……大変だね、ずっといっしょにいるのは」
「そうだね……大変なのはまあいいんだけど、それが全部だとつらくて、だから菜々子さんといられる時間は育児からも離れられて、ほんとうに幸せ感じるなあ」
「……」
「今日はありがとうね、子どもたちと遊んでくれて」
「うん……また、来れるとき来るね、来週はちょっとまだ予定わからないけど」
「そうだね、忙しいときは無理しないで」
予定なんて何もなかったが、来週もまた来る、とはとても言えなかった。
試し読み プロローグはこちら
試し読み 第1章はこちら
予約受付中!!! 花田菜々子
花田菜々子
シングルファーザーの年下彼氏の 子ども2人と格闘しまくって考えた 「家族とは何なのか問題」のこと」
1400円(税別)
46判/224ページ
2020年3月下旬発売予定