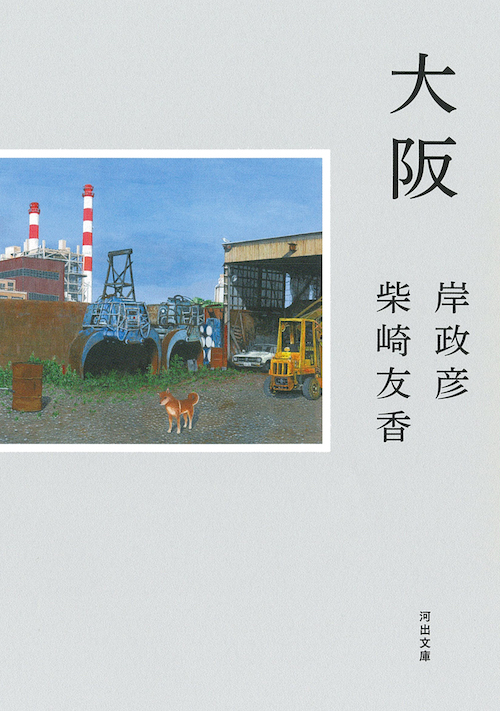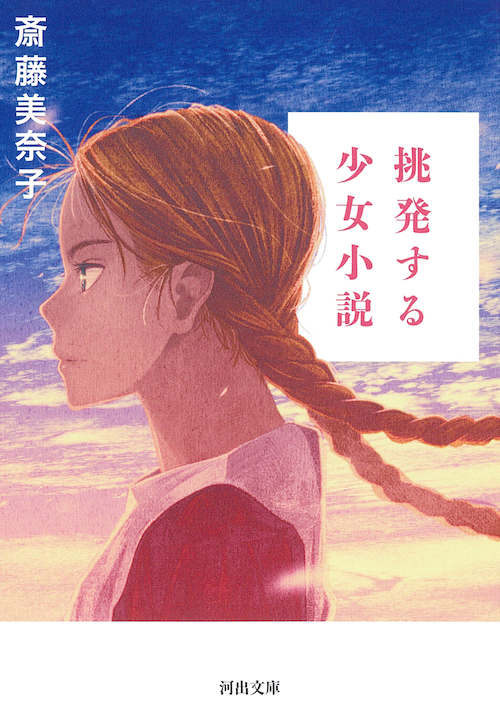「I wrote a book.」──
2019年8月1日、アメリカ国家安全保障局(NSA)の元契約職員で、現在モスクワに亡命中のエドワード・スノーデンがTwitterを介してシンプルなメッセージを世界に向けて発信した。
その生い立ちから、2013年6月に香港から行われたアメリカ国家安全保障局(NSA)による国際的監視網への告発を決意するにいたる心情の変化、ロシア亡命までの道筋が克明に描かれる。
スノーデン本人のみが知りえた情報、そして感情……これは世界最大級のインテリジェンス組織であるNSA、CIAにたった一人で立ち向かった男による、過去に類例を見ることのない第一級のドキュメントだ。
すでに二度にわたって映画化された彼の勇姿だが、潜伏期間を経て亡命先のロシアにたどり着くまでを記した終盤の流れは、それらを凌駕するスリリングな臨場感すら溢れる。
読者は、この混迷をきわめる社会に射す一筋の光の存在に立ち会うことになるだろう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
26カ国で刊行され、世界的な注目を浴びる『スノーデン 独白』。
(原題:Permanent Record)
ここではその序文にあたる、「はじめに」を一挙公開します。

はじめに
ぼくの名前はエドワード・ジョセフ・スノーデンだ。かつては政府のために働いていたけれど、いまは社会のために働いている。この二つがちがうのだということに気がつくまで、三〇年近くかかったし、それに気がついたことで、職場ではちょっとしたトラブルに巻き込まれた。結果として今のぼくは、社会をかつての自分のような人物──中央情報局(CIA)と全米国家安全保障局(NSA)のスパイ、もっとよい世界だと確信していたものを構築しようとする、ただの若き一技術屋──から守ろうとして日々を過ごしている。
アメリカ諜報業界(IC)でのぼくのキャリアは、たった七年しか続かなかった。これが自分で選んだわけでもない国で過ごした亡命生活の年月よりもたった一年長いだけだというのには驚かされる。でもその七年にわたる勤務で、ぼくはアメリカ諜報活動における最大の変化に参加することになった──的を絞った個人の諜報から、全国民の大量諜報への変化だ。ぼくは一国の政府が、全世界のデジタル通信を集め、それを長期にわたり保存して、好きなように検索するのを技術的に可能とする支援を行った。
9・11同時多発テロ以来、ICはアメリカを保護できず、真珠湾以来で最も悲惨かつ破壊的な国土に対する攻撃を、目の前でみすみす容認してしまったことで、深い罪の意識にとらわれていた。これに対処すべきICの指導者たちは、二度と不意を突かれたりしないようにするシステム構築に乗り出した。その基盤にあるのは技術だ。これは政治学専攻やビジネス経営修士(MBA)たちの群れには馴染みがないものだ。その結果、極度の秘密性につつまれた諜報機関の扉が、ぼくのような若い技術屋に大きく開かれた。こうして技術おたくが世界を受けついだのだった。
当時ぼくは、コンピュータについては誰にも負けないほどの知識を持っていたので、すぐに頭角をあらわした。CIAにいたおかげで、地球上で最も秘密裏のネットワークに何でもアクセスできた。唯一の大人の上司はといえば、勤務時間中ずっと、ロバート・ラドラムやトム・クランシーのペーパーバックを読んで過ごすヤツだった。各種諜報機関は、自分たちの内規をすべて無視して技術的な能力をもった人間をなんとか雇おうとしていた。大学も出ていない人や、短大すら出ていない人なんか通常なら絶対に雇わない。ぼくはこのどちらも出ていなかった。本来なら、ぼくはこの建物に足を踏み入れることさえ許されなかったはずだ。
二〇〇七年から二〇〇九年にかけて、ぼくは在ジュネーブのアメリカ大使館に駐在し、外交官という仮面の下で、ヨーロッパの拠点をオンライン化し、アメリカ政府がスパイ活動をするネットワークをデジタル化、自動化することでCIAを未来に送り出す作業を担当した。ぼくの世代がやった作業は諜報作業の再編と改良にとどまらない。諜報とは何なのかを完全に定義し直したのだ。ぼくたちにとって、それは秘密会合だの秘密情報交換場所だのの話ではなく、データについての話なのだった。
二六歳になる頃には、名目上はデル社の社員だったけれど、再びNSAで働いていた。契約作業の実施が見かけの仕事だ。これはぼくの年代の技術系スパイほぼ全員がそうだった。ぼくは日本に送られて、NSAの世界的バックアップに相当するものの設計を手伝った──これは巨大な隠密ネットワークで、NSAの本部が核爆発で灰燼に帰しても、データは一切失われない。当時のぼくは、あらゆる人の生活について永続的な記録を残すようなシステムをエンジニアリングするのがひどいまちがいだということを認識していなかった。
二八歳でアメリカに戻ると、物凄い昇進を受けて、デル社とCIAとの関係を扱う技術リエゾンチームに入った。ぼくの仕事はCIA技術部門の部長と額をつきあわせ、彼らが思いつくありとあらゆる問題について、ソリューションを設計販売することだった。ぼくのチームはCIAが新種の計算アーキテクチャを構築するのを手伝った──いまで言う「クラウド」だ。これはあらゆるエージェントが、物理的にどこにいようと、距離に関係なく必要なデータすべてにアクセスし検索できるようにする最初の技術だった。
まとめると、諜報の流れを管理し接続する仕事から、それを永遠に保存する方法を考案する仕事に移り、さらにそれがあらゆる場所からアクセス検索できるようにする仕事へと進んだわけだ。こうしたプロジェクトが明確になってきたのは、二九歳でNSAとの新規契約のために移ったハワイでのことだった。それまでのぼくは、知る必要のあるものしか教えない、というドクトリンの下で苦闘しており、自分のきわめて専門化され、区分化された作業の背後にある累積的な目的を理解できずにいた。自分の作業すべてがどうはまりあうのか、それらが巨大機械の歯車のようにかみ合って、世界的大量諜報システムを形成しているのだというのを理解する立場になったのは、やっと天国ハワイにきてからのことだった。
あるパイナップル畑の下のトンネル奥深くで──真珠湾時代の元地下飛行機工場だった場所だ──ぼくは端末に向かい、電話をかけたりコンピュータに触ったりした、ほとんど世界中あらゆる老若男女の通信に無限にアクセスできた。そうした人々の中には、同胞たるアメリカ国民三・二億人もいて、彼らは日常生活を送る中で、アメリカの憲法だけでなく、あらゆる自由な社会の基本的価値観を大幅に侵害する形で監視されているのだ。
あなたが本書を読んでいる理由は、ぼくがこうした立場にいる人間としては危険なことをやったからだ。ぼくは真実を語ることにしたのだ。ぼくはアメリカ政府の違法活動の証拠となるIC内部文書を集め、それをジャーナリストに渡し、彼らはそれを検分して公開し、世界は一大スキャンダルに驚いた。
本書は、その決断に到る過程、それを支える道徳・倫理的原則、そしてそれがどうやって生まれたかについてのものだ──つまりはぼくの人生についての本でもあるということだ。
人生を形作るものとは何だろうか? ぼくたちの言うことだけじゃない。やることだけでもない。人生とはまた、ぼくたちが何を愛し、信じるかということでもある。ぼくにとって、自分が何よりも愛して信じるものはつながり、つまり人間とのつながりであり、それを実現する技術だ。こうした技術には本も含まれる。でもぼくの世代にとって、つながりとはおおむねインターネットのことだった。
のけぞらないでほしい。現代のあの場所に巣喰う有害な狂気は十分に知っている。でもぼくがそれを知るようになり始めた頃、インターネットはまったくちがうものだった。それは友だちだったし、親でもあった。それは国境も制限もないコミュニティで、一つの声と一〇〇万の声があり、多様な部族が入植はしていても収奪はしておらず、仲良く共存し、それぞれのメンバーは自分の名前も経歴も習慣も好きに選べた。みんな仮面をかぶっていたけれど、この多様性を通じた匿名性は、ウソよりも真実を生産した。というのもそこは商業的で競争的なところではなく、クリエイティブで協力的な場所だったからだ。確かに紛争はあったが、善意と好意のほうが強かった──これぞ真の開拓精神だ。
だから今日のインターネットが変わり果ててしまったと言ったら、わかってもらえるだろうか。この変化は意識的な選択であり、特権的な少数者による系統的な活動の結果なのだということは認識してほしい。初期の、商業をe‐コマースにしようという騒動はすぐにバブルと化し、そしてちょうど世紀の変わり目直後に崩壊した。その後、企業はオンラインの人々が、共有したいだけでお金を使うことにまるで興味がないことに気がつき、さらにインターネットが実現した人のつながりを金銭化できることにも気がついた。ほとんどの人がオンラインでやりたいのは、家族や友人や見知らぬ人たちに何をやっているか伝え、その家族や友人や見知らぬ人たちが何をしているかをお返しに教えてもらうことだけだ。それなら、企業としてはそうした社会的やりとりの真ん中に自らを置いて、それを利潤に変えればいい。
これが監視資本主義の発端であり、ぼくの知っていたインターネットの終焉だった。
さて、崩壊したのはクリエイティブなウェブだった。無数の美しく、むずかしく、個人的なウェブサイトが閉鎖されてしまった。利便性を約束された人々は、個人サイト──それは絶え間ない面倒な更新を必要とした──をフェイスブックのページとGメールアカウントに換えてしまった。一見すると自分が所有しているように見えるせいで、多くの人は本当にそれを所有していると誤解してしまった。当時はほとんどの人が理解していなかったが、そこで共有するものはすべて、もはや自分のものではなくなっていた。e‐コマース企業は、ぼくたちが買いたがるようなものを何も見つけられずに破綻したけれど、その後継者たちは売り込む新製品を見つけた。
その新製品とはぼくたちだ。
ぼくたちの関心、活動、位置、欲望──ぼくたちが意識的だろうとそうでなかろうと、自分について明かすすべてのことが、監視されこっそり売られて、いずれまちがいなくやってくる侵犯の感覚を鈍らせるようになっていた。そしてその侵犯の感覚が、いまやついにぼくたちを襲い始めている。そしてこの監視は活発に奨励されるようになり、手に入る大量の諜報に飢えた無数の政府から資金さえもらっている。ログインや金融取引以外は、二〇〇〇年代初頭には暗号化されたオンライン通信はほとんどなく、つまり多くの場合に政府は顧客がやっていることを知りたければ、その会社に接触する必要さえなかったということだ。誰にも告げることなく、世界中をスパイできた。
アメリカ政府は、その建国の憲章をまったく無視して、まさにこの誘惑の犠牲となり、いったんこの有毒の果実を味わったら、もはやどうしようもない熱にうかされてしまった。アメリカ政府は秘密裏に大量監視の力を身につけた。これは定義からして、罪人たちよりも無実の人々にはるかに大きく影響する権限だ。
監視とその害についてもっと完全な理解に到達してやっと、ぼくたち市民──ある一国のみならず、全世界の市民──が、このプロセスで投票はおろか、自分の意見を述べる機会さえ与えられなかったという認識につきまとわれるようになった。ほぼ全面的な監視システムは、単に同意なしで設置されたというだけではない。その計画のあらゆる側面を意図的に知らせず隠すような形で設置されたのだった。変化する手順やその影響は、あらゆる段階でほとんどの立法者を含むほとんどの人々から隠された。誰に訴えればいいだろう? 誰に話をすればいいだろう? 真実を囁くだけでも、弁護士や裁判官や議会に対して告げるだけでも、あまりに重い刑事犯罪にされており、最も漠然とした事実の概略ですら連邦刑務所で終身刑となってしまう。
ぼくは途方に暮れ、良心と苦闘する中で暗い気分へと沈んで行った。自分の国は愛しているし、公共への奉仕も信じている──ぼくの家族すべて、何世紀にもわたる祖先はずっと、この国や市民への奉仕に命を捧げた人々ばかりだ。このぼく自身も、奉仕を誓ったのはある機関ではなく、政府に対してですらなく、国民に対してであり、憲法を支持し擁護すると約束したのに、その憲法による市民の自由がここまで露骨に侵害されているのだ。いまやぼくは、その侵犯の一部にとどまらない。その片棒を担いでいるのだ。あの大量の仕事、あの長い年月──ぼくは誰のために働いていたんだろうか? ぼくを雇った機関との守秘契約と、わが国の建国の理念に対して行った誓いとをどうバランスさせればいいのか? 自分が最大の忠誠心を抱くのは、誰に対して、あるいは何に対してだろうか? どの時点でぼくは、道徳的に法を破る義務を負うのだろうか? こうした原理を考察することで答が出た。告発し、ジャーナリストたちに対しわが国の濫用のひどさを開示するのは、別に政府の破壊ではないしICの破壊にすらつながるものではないと気がついた。それはむしろ、政府およびIC自身がはっきり述べている理想追求への回帰となる。
国の自由は、その市民の権利尊重によってしか計測できず、こうした権利は実は国の権力に対する制限であり、政府がずばりいつ、どこで個々人の自由の領域を侵犯してはいけないのか定義しているのだとぼくは確信している。これはアメリカ独立革命では「自由」と呼ばれ、インターネット革命では「プライバシー」と呼ばれるものだった。
世界中の、先進的だと言われる政府がこのプライバシーを守るという約束を軽視しているのを目撃したので、ぼくは告発した。もうすでにそれから六年になる。ぼくは──そして国際連合も──このプライバシーを基本的人権だと考える。だがこの六年にわたり、こうした軽視は続く一方で、その間に民主主義国は専制主義的なポピュリズムへと退行した。この退行が最も露骨に出ているのは、政府とマスコミとの関係だ。
選出された公職者がジャーナリズムを骨抜きにしようとする試みは、真実の原則に対する全面的な攻撃により後押しされ、促進されている。何が本当かが、意図的にフェイクとごっちゃにされ、そこで使われている技術は、その混同を空前の世界的な混乱へとスケールアップできてしまう。
ぼくはこのプロセスを十分身に染みて理解している。というのも非現実の創造は、諜報業界の最も恐ろしい技術だからだ。ぼくのキャリア期間だけですら諜報を操作して戦争の口実を作り出したその機関は──そして違法な政策と影の法廷により、誘拐を「超法規的移送」として、拷問を「拡張された尋問」として、大量監視を「バルク収集」として許容したその機関は──一瞬のためらいもなくぼくを中国の二重スパイ、ロシアの三重スパイ、いやもっとひどい「ミレニアル」呼ばわりさえしたのだった。
彼らがこんなひどいことを、こんなに平然と言えたのは、ぼくが自己弁護しなかったからだ。内部告発に進み出てから現在に到るまで、ぼくは個人生活の詳細については一切明かさないと決意していた。自分の家族や友人たちにこれ以上の苦労をかけかねないからだ。彼らはすでに、ぼくの原理原則のために十分苦しんでいたのだから。
本書執筆をためらったのも、その苦しみを増やしてしまうのではと懸念したからだった。最終的には、政府のまちがった行動を証拠つきで内部告発しようという決意は、自分の生涯についてここで語ろうという決意よりも容易だった。ぼくが目撃した濫用は行動を必要とするものだったけれど、良心の呵責に抵抗できないから回想記を書くという人はいない。だからこそぼくは、本書に登場し、公的に誰だかわかってしまうあらゆる家族、友人、同僚たちの許可を得ようとした。
ぼくは他人のプライバシーの唯一の裁定人となるのを拒否したし、同様にわが国の秘密のうち、どれを世間に報せるべきで、どれを報せるべきでないかについて、自分一人が判断できるなどと考えたこともない。だからこそぼくは、政府の文書をジャーナリストたちだけに開示した。実はぼくが社会に対して直接開示した文書の数は、ゼロだ。
ぼくはそうしたジャーナリストたちと同様に、政府は一部の情報を隠してもいいと信じている。最も透明性の高い民主主義ですら、たとえば秘密エージェントたちの正体や、戦場での兵の動きなどは機密にしても許されるはずだ。本書にはそういう秘密は一切含まれていない。
ぼくの人生について記述しつつ、愛する者たちのプライバシーを守り、正当な政府の秘密は暴露しないというのは単純な作業ではないが、それがぼくの仕事だ。この二つの責任の間──それがぼくの居場所なのだ。