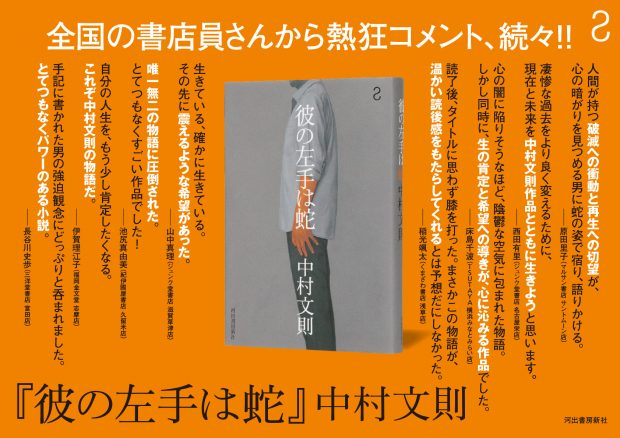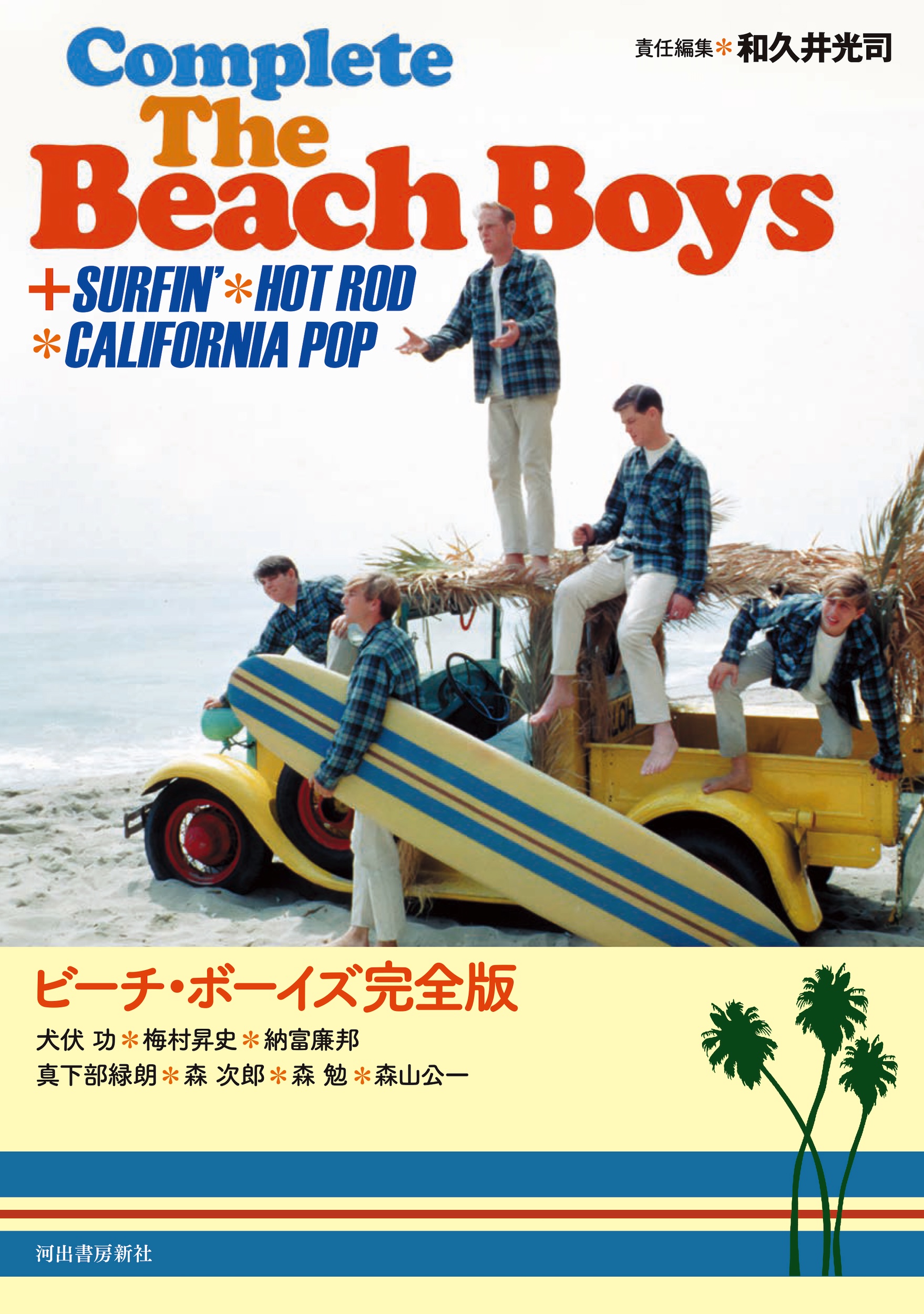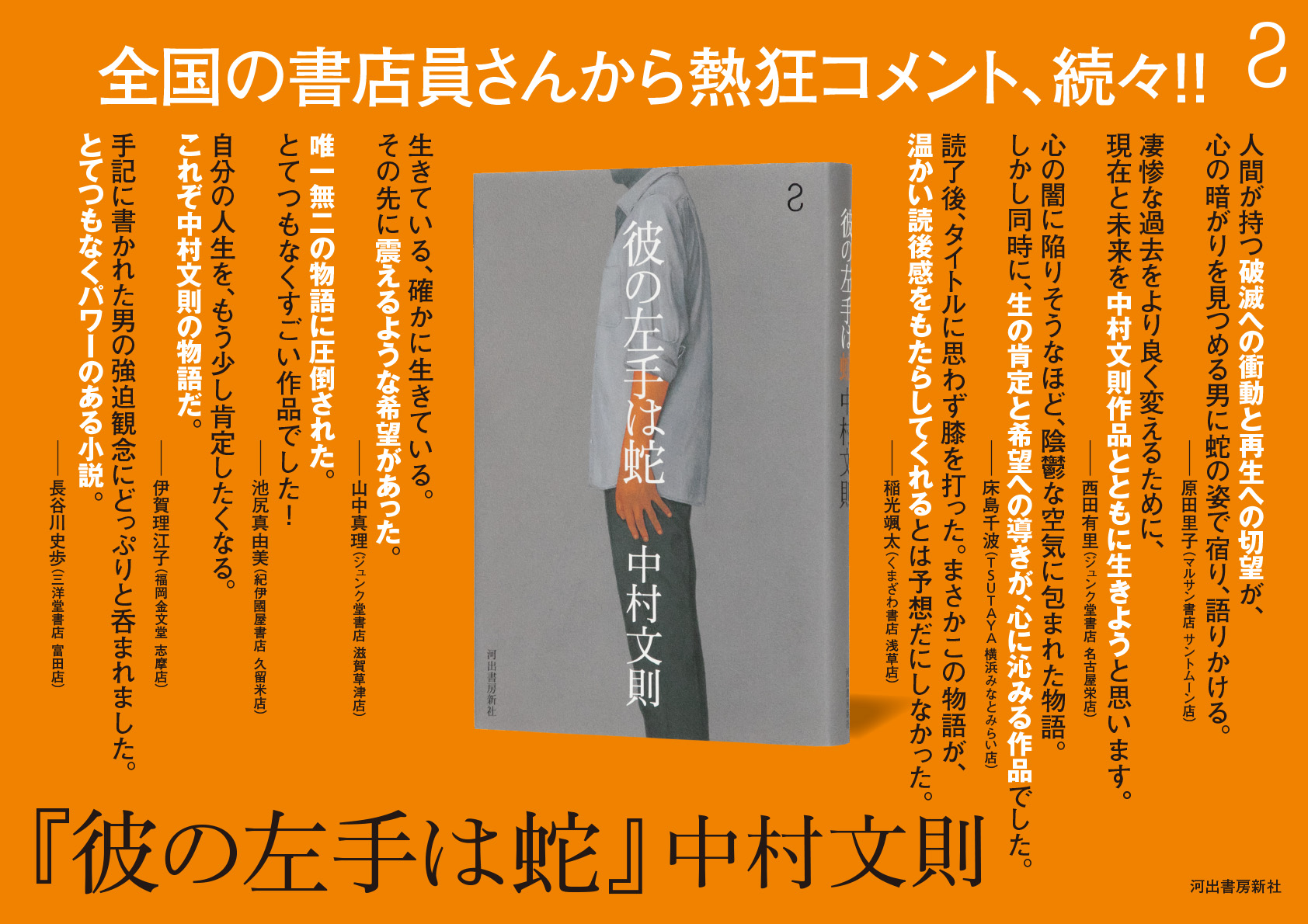
全国書店員から熱いメッセージが続々! 中村文則、2年ぶりの最新小説『彼の左手は蛇』書評
評者=好事家ジェネ(YouTuber)
2025.11.04
中村文則 著
毒蛇のようなやさしさで
評者=好事家ジェネ(YouTuber)
何て不吉なタイトルだろう──『彼の左手は蛇』。蛇が往々にして罪や堕落を暗示することは周知の通りだが、左手もまた、時に抗いがたい欲の暴走を示す悪しき象徴物として扱われることがある。ラテン語で「左」を意味する“sinister”は、現在では「不吉な」という意味だ。本書の表題を目にした瞬間、読者はこれから繰り広げられるであろう邪悪な物語に身構えながら、そしてどこか背徳的な期待を抱きながら、頁(ページ)をめくることになる。
本書は、「私」と名乗る者の手記によって構成されている。「私」は、不幸な生い立ちを持つ男だ。父に顧みられず、母には生まれたことを責め続けられ、自身の存在と欲望を否定しながら育った。家庭に居場所のなかった「私」は、ある日逃げ込んだ山奥で不思議な蛇と対話し、以降、自身の左手に蛇が宿っているかような錯覚に囚われるようになる。そんな「私」が、ある街に引っ越して三か月が経ったところから物語は始まる。
街は混乱のさ中にあった。何者かによって五大陸の毒蛇が放たれ、住民が噛まれる危機に晒されているという。「私」はこう考えている。その毒蛇、「全て私が集めたい」と。
その意図は、散漫で混沌とした手記を読み進めていく内に明らかになってゆく。
「私」は、手記を書くことで自身の正気を確かめたいと言う。なるほど、「私」がペンを握る右手は理性と意識の象徴だ。そして一方で「私」は、「ロー・K」という人物を世界から消すことは可能であるかを考えている。その計画と殺意は、古代エジプトの悪の化身たる大蛇Apep(アペプ)に喩えられながら、徐々に鎌首をもたげていく。蛇が宿る彼の左手が示すところ──無意識の欲望と衝動が目を覚ますかのように。
この本は、テロリストの記録だったのだ。日常に自身を繋ぎとめようとする正気と、殺人を決行するという狂気の狭間を蛇行する「私」の蛇は、果たしてどこへ向かうのか。
頁を捲りながら、幼い頃、ふれあい動物園で出逢った山吹色のビルマニシキヘビのことを思い出していた。同年代の子らに交じって愛らしいモルモットやヒヨコに歓声を上げる気にもなれず、退屈と疎外感を覚えていた中、誰も群がっていないその大蛇が目に留まった。スタッフに促されるまま肩に掛けてみれば、二メートル近い巨躯のわりに驚くほど大人しい。落ち着きのない小動物のように手の内から逃げ出すこともせず、ジッと穏やかに寄り添ってくれる蛇だけが、その居心地の悪い空間で唯一の味方のように感じられたのだが、それを目にした母は眉をひそめていた。その冷たい視線は、蛇によってその場にいる承認を得た気になっていた、私をも否定するものだった。
世界が自分を肯定してくれないならば、自分が世界を否定せねばならない。私は間違ってなんかない、おかしいのは世界の方だ、という風に。本書の「私」も、誰にも認められなかった己を肯定しようと試みるが如く、世界各国の失われた蛇信仰を調べるようになる。一般に知られている神話や伝承には、その地により古くから存在していた蛇信仰が往々に影響していることがあるそうで、この辺りの記述はトリビア的でなかなか面白い。日本にも古くからヤマタノオロチの伝説を有する神道があり、後から輸入された仏教としばしば対立した。それを象徴するかのように、「私」の計画に手を貸す宮司と、一方で「私」を戒めようとする僧という対照的なキャラクターが登場するのは、本書の構成の妙のひとつだろう。「私」は蛇信仰が滅ぼされた歴史に思いを馳せ、価値志向など流転するもので、自分を否定してくる世界もまた今だけの虚像にすぎない、と己を慰める。そして世界を否定するからこそ、その異常の因子たる「ロー・K」を殺すことは、彼の中では正当な行為となりうるのだ。
己を肯定してくれない世界への不満が徐々に社会への義憤とすり替えられていく様は、マーティン・スコセッシの『タクシードライバー』をも想起させる。この映画で、しがないタクシー運転手のトラヴィスが銃を握ったのは、それで悪を成敗してやるという大義が、孤独な彼の自尊心を支えたからだった。そういえば中村氏のデビュー作『銃』でも、思いがけず銃を拾った主人公が、徐々にそれを撃ってみたいという思いに囚われていく様子が描かれていた。そこでの主人公は、銃を手に入れたから悪に染まったのではなかった。銃を得たことで、それまで胸の奥底に眠っていた鬱屈を暴発させる弁解が生まれてしまったのだった。そして最新作たる本書においては、銃は蛇として描かれている。蛇が悪なのではない。蛇に仮託しなければ、自分の欲望も衝動も、自身の存在すらも肯定できなかった弱さが問題なのだ。その悲しみが、まるで毒のように読み手の胸を蝕んでゆく。
別段、人は本来、何かに後押しされる必要も、誰かに励まされる筋合いもない。死が迎えに来るその日までは、望んでも望まなくてもただ生きるしかないのだから。しかし、もしそこに束の間寄り添ってくれるものがあったならば──あの時のビルマニシキヘビのように、孤独にすぼめた肩をそっと抱いてくれるものがあるとするならば、人のそれは一体何なのだろう。
頁を閉じた時、裏表紙に乗った自身の左手を思わず見つめてしまう、余韻のある一冊となっている。
【書店員から絶賛の声続々!】