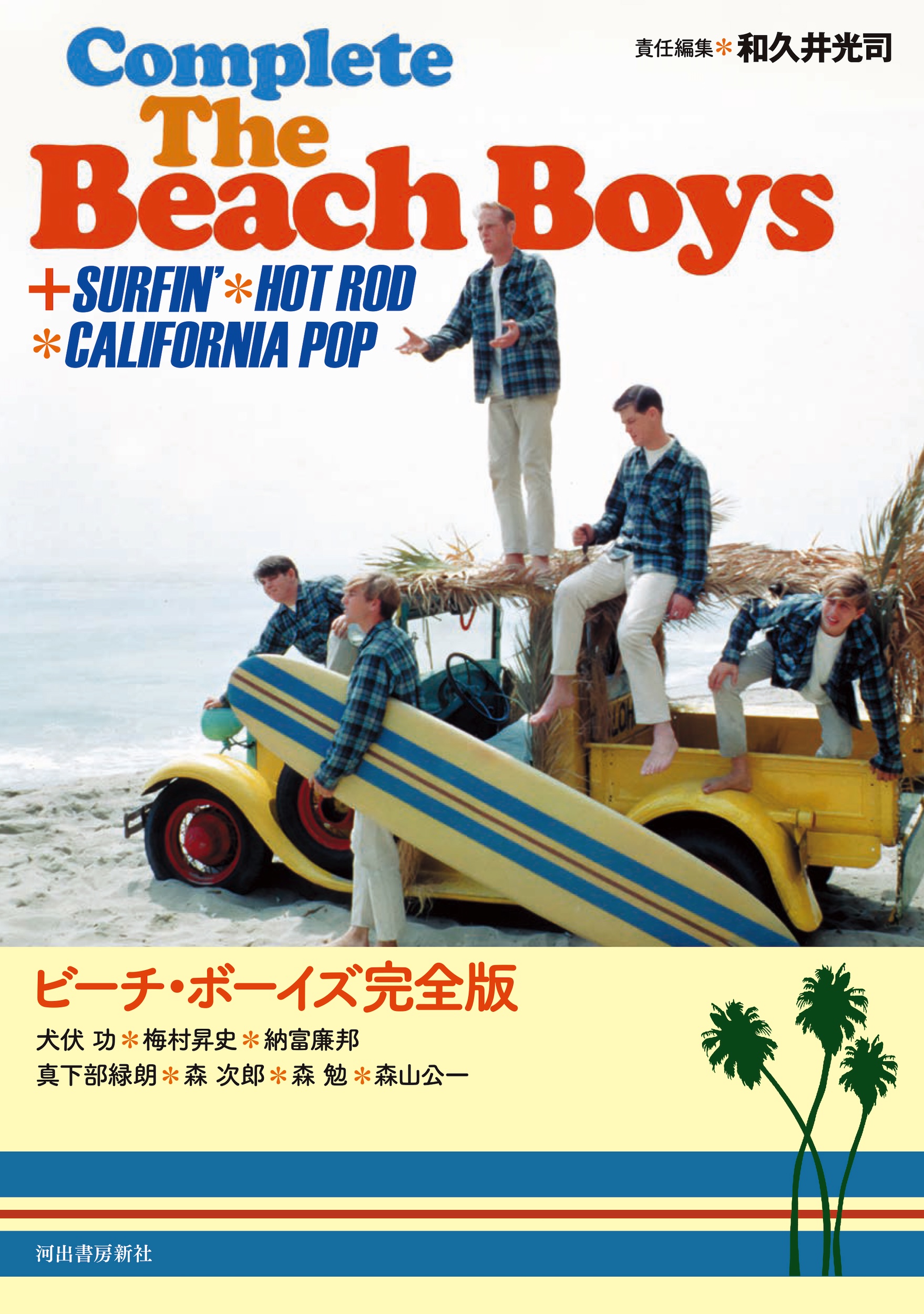山内マリコ『選んだ孤独はよい孤独』から、カツセマサヒコさんもお気に入りに挙げる短篇「おれが逃してやる」を試し読み公開中!
山内マリコ
2021.11.11
“男らしさ”に馴染めない、情けなくも愛すべき男たち――。
孤独や哀しさにそっと明かりを灯す、おかしくも切ない物語集『選んだ孤独はよい孤独』の文庫発売を記念して、本書収録作のなかでもとりわけ人気の高い一篇を無料公開いたします。
*******
「おれが逃がしてやる」
山内マリコ
会社といっても雑居ビルのワンフロア。十人に満たない社員がスチール机を並べて、Dellのパソコンをかちゃかちゃ叩いているようなしょぼいところだった。席に案内してくれた総務のおばちゃんに、「仕事のことは館林さんに教わってね」と言われる。俺の席のとなりが、その館林さんの机だ。ひょろっとした三十代。この零細企業が新しく正社員を雇ったのは、この人以来十年ぶりだとか。「館林さん、部下ができてよかったね」と、総務のおばちゃんがうれしそうに声をかけた。
「よろしく」
そのときはじめて顔を合わせた館林さんは、まさしく人生に敗れた男といった印象だった。よれっとしたスーツに、コシのない髪。顔色も冴えなくて、生気ってものがまるでない。
「お願いします」俺は小さく頭を下げた。
「いくつ?」
「二十六です」
「二十六か」
館林さんはそうかそうかと、頭をしきりに掻いている。
「じゃあ、今日はとりあえず、取引先にあいさつだな」
駐車場に降り、「あれ」と館林さんが指差した。車体の横に社名ロゴが入った白い軽自動車。
「俺、運転しましょうか?」
「いや、いい。乗って」
館林さんが運転席で、俺は助手席。館林さんはエンジンをかけると、車をバックで白枠から出した。
車の中は沈黙がつづく。音楽をかけたいけど、このボロ車にはBluetoothもない。
「アポとか入れなくていいんですか?」
俺が訊くと、
「ただのあいさつ回りだから」とバッサリ。
アポなしで行って、担当者に会えたら名刺交換して、会えなかったら名刺だけ置いて出直す、それだけ。
「営業ってそういう感じなんすね」俺がつぶやくと、
「なんすね……」
語尾を館林さんが嫌味っぽくリピートしたのでヤベえと思い、
「なんですね」焦って言い直すが、別に館林さんは気を悪くしたわけじゃなかった。
「おれにはいいけど、ほかの人には言わない方がいい」
とアドバイスしてくれた。
「なんか照れるんすよ、ちゃんとした敬語って」
俺がジャケットのポケットからタバコを出すと、館林さんは無言でボタンを操作して助手席の窓を少しだけ開けた。
「あ、どうも」
タバコに火を点け、一吸いする。赤信号につかまった館林さんはブレーキを静かに踏み込んで停止すると、ゆったりした口調で言った。
「コツは、芝居だと思うこと」
「えっ?」
俺はどきりとした。芝居って言葉にひどく敏感になっている。この人なにを知ってるんだと焦った。館林さんはつづける。
「会社ってみんな、芝居がかってるだろ? だから芝居だと思った方が楽」
「……そうなんすか?」
別に俺の事情を知って言ったわけではなさそうだ。
館林さんはうなずいて、
「名刺交換なんて完全にサラリーマンコメディだからな。芝居だと思って、思いきり仮面かぶって、演技してみればいい」と言った。
信号が青に変わる。
館林さんはアクセルを踏み込んで言う。
「おれはずっとそうやってるよ」
一軒目も二軒目も担当者が不在。応対してくれた女性社員に、とりあえず名刺を渡した。
「えっと……あのこれ……」
名刺交換にまごついていると、館林さんが俺の背中を軽く小突く。
芝居だ、芝居、芝居するんだ。
そう言われているようで、おかげでにやけたりせずに「頂戴します」とか言えた。なんだよ頂戴しますって。「ごきげんよう」並みの異文化だ。
十二時を回ると、「昼にするか」と館林さん。よく行くという、ラーメン屋に入る。店の中はサラリーマンで満席状態。館林さんは担々麺をすすりながら、当たり前のことだけど、と前置きして言った。
「十二時から一時までが昼休憩。好きなところで好きなもの食べていい。ただしランチ時はどこもこんな感じで混むから気をつけて」
店の中、同じ時間に、同じようなものを着て、同じラーメンをすするサラリーマンを見回す。みんな同じルールの中で生きてるんだなぁと思い、暗澹とした気分になった。
「会社の近くに、安くてうまい店とかありますか?」
少しでも前向きな話題をと思って振ったら、
「そんな店、都合よく近所にはねーな」館林さんは笑った。「うちの会社の人間はみんな出かけるのも面倒がって、あんまり外行って食べないから。弁当とか、コンビニで買ってきたもので済ませてる」
「館林さんは出る派なんすね?」
言葉端に、そういうのが透けて見えた。自分は毛色が違うっていう。
「おれは、営業で外出られる分、そこらへんは自由にやってるかな」
「自由に」
そんなつもりはないが、皮肉っぽく拾ってしまった。これからはじまるサラリーマン生活は、自由なんてどこにもないだろう。
店を出ると館林さんは、コンビニでドリップコーヒーをおごってくれると言う。コンビニの外の灰皿でタバコを吸っていると、コーヒーカップを差し出して、「おれにも一本」と館林さんが言った。「あー、久しぶりに吸うとうまい」、館林さんは今日はじめて破顔した。
人差し指と中指の、深い位置にタバコを挟む持ち方、吸うときの顔のしかめ方、親指で弾くようにする灰の落とし方。館林さんのタバコの吸い方を、すげえいい感じだなと思って眺めた。
「何年くらい吸ってたんすか?」
「吸いはじめたのが高校生で、やめたのは子供生まれたときだから……丸十年」
頭の中で計算する。十六歳で吸いはじめたなら、ガキができたのは二十六。十七なら二十七。十八なら二十八。この人の人生って、たったそんだけだったのか。人生が自分だけのもので、自由に思いきり楽しめた時間は。
「いまの俺くらいの年には、もう結婚してたんすね」
館林さんは紙カップにつけたくちびるを離し、言った。
「ああ、子供できたから」
「できなかったら結婚しなかったっすか?」
「さぁ。ほどほどのタイミングではしたと思うけど」
「ほどほどのタイミングって、いつっすか?」
「早すぎず遅すぎず。無難なとこで」
「無難っすか」
「無難な人間なんだよ」
館林さんはそううそぶいて、吸い終わったタバコを網の穴から落とした。下に張られている水に、ジュッと音を立てて沈む。
俺は自分で自分を無難と言ってしまう館林さんに少々幻滅しながら、助手席でタバコをこれでもかと吸いつづけた。三軒目の会社で挨拶し、四軒目も担当の人がいて挨拶し、名刺交換の演技にはあっという間に慣れた。五軒目、六軒目と回ると、もう日が暮れかかっている。サラリーマン第一日目は、本当になんにも面白いことがなかった。六時半に会社に戻り、七時からは俺の歓迎会。
それは、史上最高に退屈な飲み会だった。社長たち中高年のおっさんノリが炸裂して、まじでひとつも笑えないし楽しくもない。いちばん若い女性社員ですら三十五歳で、しかも育休中と知り、俺は絶望した。話の合いそうな人間が皆無。間違いなく、ここは俺の人生の墓場だ。
トイレに行くふりをして外でタバコを吸う。縁石にしゃがみ込み、本当にいいのか? これでいいのか? と自問自答して、気持ちが悪くなるまでタバコを吸いまくる。スマホをいじってみるが、泣きつけるような友達もいない。仲間はみんなバイトしてる時間だ。バイトか、どこかで飲んで、演劇談義でもしているか。そもそもまだ俺は仲間なのか?
館林さんが出てきて、俺に言った。
「お前、大丈夫か?」
「あ、いや、はい……いや」
アルコールが回ってしどろもどろ。館林さんは俺の背中をさする。
「いや、大丈夫っす」
その手を俺は振り払う。
館林さんはため息をつき、「一本くれ」と言って、俺の横に座った。
館林さんのタバコの吸い方は、またしても俺を魅了する。なんだろう、この良さは。年を取った敗北者だけが漂わせることのできる、この叙情は。
「お前さっき訊いたろ? 子供できなかったら結婚しなかったかって」
「はあ」もう興味ねーし。
「したと思う。二十代のうちに」
「ふーん」
「なんでかっていうと」
館林さんは言葉をゆっくりひねり出す。
「暇だったから」
「ぶっ」思わず噴き出してしまった。
なんだよ、もっといいこと言いそうな雰囲気だったのに。
館林さんはつづける。
「社会人になると、毎日は忙しくなるけど、人生って意味では、暇なんだ。仕事は人生の、便利な暇つぶし。マッチポンプみたいなもんだ。仕事しないと金は稼げない、金がないと生活できない。だから仕事さえしてれば生活できるし、間が持つ。でも、仕事してるだけだから、すぐに飽きてくる。そこそこいい年になると、かなり飽きてくる」
「はあ」
おそらく無口な館林さん、がんばってしゃべってくれているのがわかる。でも、なにが言いたいのかはよくわからない。
「ちょうどそういうタイミングで、上司は、家庭を持つ重要性を説いてくる。こういう飲み会のときとかに。で、結婚すると、子供がいることの重要性を説いてくる。子供はかわいいぞ、かすがいだぞって。子供が生まれると、今度は、早く家を建てた方がいいっていう話をしてくる。家を建ててこそ一人前だぞ、ローンを組むなら早い方がいいぞ、とか言って。それが、普通の男の人生なんだ。働いて、結婚して、子供養って、家建てるのが。そういう話になるのはたいてい飲み会なんだけど、あれってたぶん、ほかに話題がないからだろうな。共通の話題っていうと、それしかないんだ。おれにそういう話をした上司も、きっと若いころ、同じようなことを言われてきたんだろうな」
俺は逆流してきた胃酸をぺっと吐き出した。
館林さんの話はまだつづく。
「おれも何年か前に家のローンを組んだんだけど、その報告したときな、あの人たち、めちゃくちゃうれしそうな顔してた。でもそのうれしそうっていうのが、人の幸せを喜んでるんじゃなくて、おれたちのクラブに入ってくれてうれしいよ、みたいな、そういう喜びなんだ。これで、同じ重荷を背負った仲間だな、っていう。意味わかるか?」
俺は頭を振った。酔いが回っているし、ピンとこない話だ。
館林さんは俺のジャケットのポケットに手を突っ込むと、タバコを出して火を点けた。その遠慮のない行動は、昔からの友達っぽくて、俺はまたしてもぐっときた。館林さんはタバコの煙を夜空に吐き出しながらこう言う。
「自分はなにがしたいんだろうとか、深く考えずに、なんとなく生きてたら、こうなってたんだ。まわりがレコメンしてくる方向に、なんとなくハンドルを切ってたら、こうなってた。まあ、普通の男の人生だ。大勢がそのクラブに入会してるから、連帯意識もある。話す言葉も似てくる。一人じゃない安心感もある。セーフティモードの人生だ」
館林さんは俺に向き直って言った。「ここで訊くが、お前は、そのクラブに入りたいか?」
「……いや。入りたくないっす。死ぬほど入りたくない。でも、館林さんがいまから俺を、説得するんでしょ?」
内心、それを待っていた。会社はいいぞ、結婚はいいぞ、子供はいいぞ、家はいいぞ。そういうオーソドックスな人生に飛び込む、背中を押してくれ。
館林さんは「しないよ」と笑って、こうつづけた。
「自分で自分の人生を切り拓く力のある奴って、案外少ないんだ。なにかやりたいことがある奴も、そんなにいない。二十歳過ぎて夢とかある奴なんて、ほとんどいない。いても、年をとるごとに自然淘汰されて減っていく。そういう、おれみたいに主体性のない奴らは、暇なんだから、クラブに入会すればいいんだ」
だんだん、目が冴えてきた。
となりを振り向き、館林さんと目を合わせる。
「だからな、もしお前が、ずるずる青春を引きずってるだけで、別に無難な人生でいいと心の底から思ってるなら、根性入れ替えさせてこのクソつまんねえサラリーマン生活に一刻も早く染まれるようおれは指導するけど、もしなんかやりたいことがあって、なのに無理して諦めようとしてるんだったら、おれはそれを止めるぞ」
「え?」
「逃げろ」館林さんは言った。「いま逃げろ」
「え?」
「おれが逃がしてやる」
ちょうどそのタイミングで、会計を終えた会社の人たちがわらわらと出てきた。のれんを手で払いながら、社長の「もう一軒行けるかぁ~?」という声が響く。
俺はその瞬間、自分がショーケンか松田優作か、そっち系の俳優になった気分で、わなわなと立ち上がった。それから、刑事に追われている犯人のように、逃げ去った。夜をどこまでも走った。ここがどこだか、わからなくなるまで。
一度は夢を諦めてサラリーマンになったものの、たった一日で会社を辞めて逃亡した話は、インタビューを受けると必ず持ち出されるエピソードになり、いまや俺のウィキペディアにも載っている。あれから十年。俺はウエンツ瑛士にマイクを向けられると、あの日社長がのれんを手の甲で払いながら出てきたときのくだりを寸劇みたいに再現してみせ、笑いを取るタイプの役者になった。小劇団出身の、ドラマで四番目か五番目に名前がクレジットされる役者に。死んだときは〝名バイプレーヤー〟と称されるような。
あのあと劇団に戻り、四年ほど芝居をつづけたところで、テレビドラマのプロデューサーから声をかけられ役をもらえるようになった。バイトを辞めて芝居だけで食えるようになるまでさらに二年。それなりの家賃のマンションに引っ越し、自分で保険料も払って、人としてまともな生活ができるようになったのは、三十二歳のとき。自分の力で人生を切り拓いているぞ、という手応えがあったのは、せいぜいそこまでだ。
軌道に乗ってしまえば役者人生は順調そのものだった。たくさんのドラマや映画に出て、あこがれの監督の作品にも出て、助演男優賞をもらったことも二度ほどある。キャパのでかい劇場で、カーテンコールの拍手をもらうのは快感だ。俺は商売柄、感動中毒ともいえる。何十回何百回も感動したりさせたりすると、麻痺して、だんだん閾値が上がっていく。けど、これだけは言えた。俺の人生で真に感動的だったのは、あの瞬間だけだと。
「おれが逃がしてやる」
そのときのことは、いつまでもいつまでも俺の記憶に残った。心に刻まれた。館林さんは、俺が手を伸ばそうとしていたバトンを──男には必ず回ってくる義務と責任のバトンを──俺の手から華麗に奪って、放り投げてくれたのだ。これは誰にでもできることじゃない。そういう意味で俺は、世話になった劇団でもなく、プロデューサーでもなく、名も無きサラリーマンの館林さんこそが、恩人だと思っている。
あの日、俺が逃げたあと、館林さんがどんな目に遭ったかは知らない。新入社員が逃げましたと、ぜんぶ俺のせいにしてくれてたらいいけど。
食えていない後輩の劇団員が夢を諦めようとしているのを見ると、俺はすかさず寄っていって、館林さんの言っていたことをそのまま反芻して聞かせた。俺が受け取った新しいバトンを、そいつらに手渡すために。
俺は人差し指と中指の深い位置でタバコを持ち、顔を渋くしかめて吸い、後輩の肩を抱く。そして極めつけに、あの言葉をつぶやくのだ。