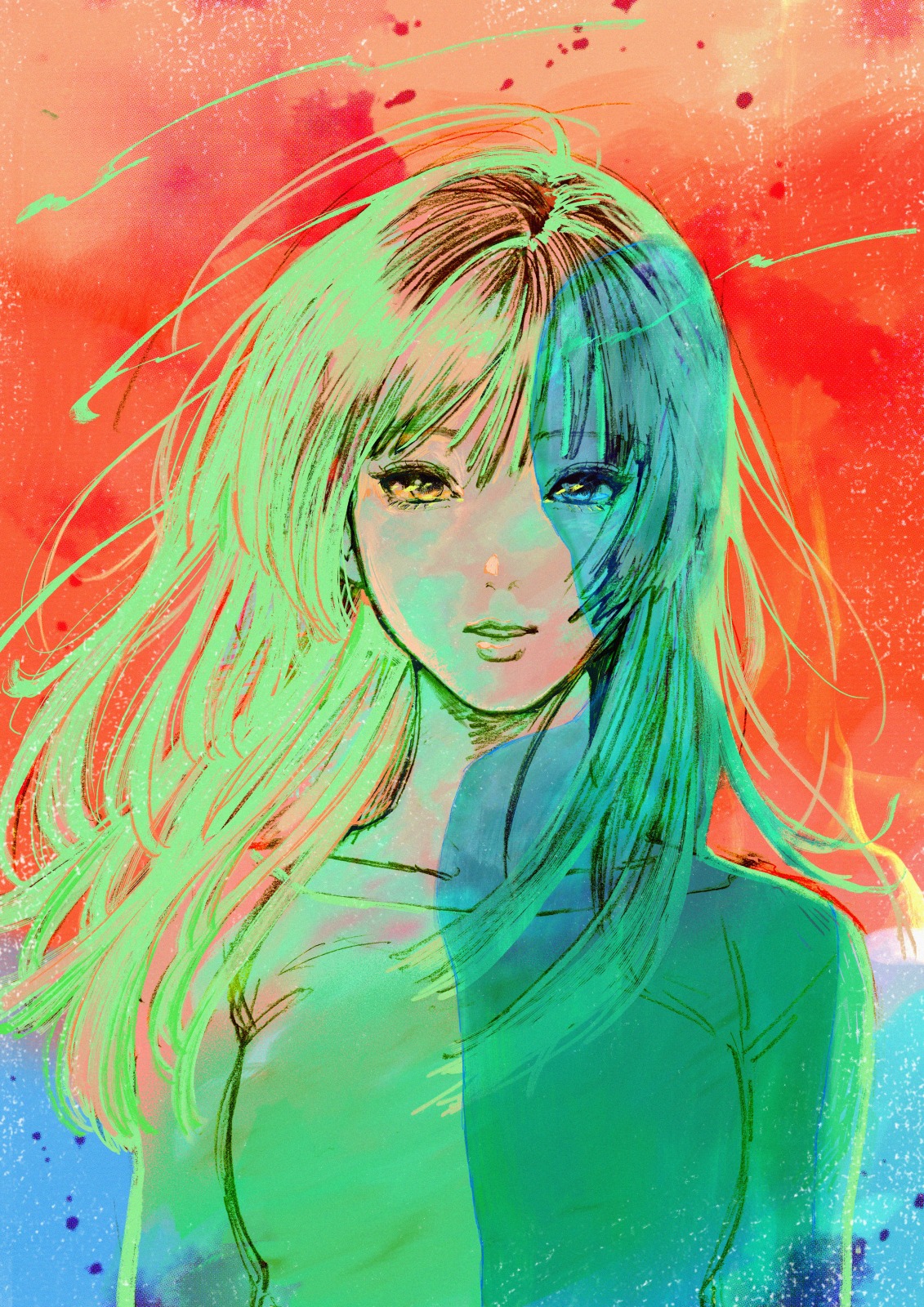特集・コラム他 - 文藝
「『魂の地下室』に眠る言葉を取り出す」村田沙耶香×待川匙『光のそこで白くねむる』文藝賞受賞記念対談
村田沙耶香×待川匙
2024.11.22
記憶と共鳴する物語
村田 「光のそこで白くねむる」を最初に読んだとき、とにかく文章の力を感じました。一行一行の中に光と影の粒子が含まれた、複雑に光る詩を読んでいるような感覚で、何も起きない日常描写が続いたとしても、待川さんの文章をもっと読みたいと思いました。複合的に作品を流れる時間や、自分の記憶とも共鳴する言葉の一つ一つが全部好きだったんです。この作品は、すべての人間の秘密につながる謎の箱に接続していて、ものすごく深く広い「魂の地下室」に眠っている言葉を取り出してつくられているようで、これは絶対に本として存在してほしいと思いました。
待川 ありがとうございます。自分ひとりで読んでは書いてを繰り返してきたので、村田さんに読んでいただけたことが、本当に心から嬉しいなとしみじみ感じています。
村田 私は子供のときから小説を書いていたのですけど、待川さんはこれまで何か書いていましたか?
待川 書くよりも読むほうが好きで、それほど書いてはいませんでした。ただ、書きたいという気持ちは子供のときから持っていて、十代でデビューされる方を見て、「十七歳くらいで自分も作家としてデビューするんだ」と勝手に思い込んでいました。その頃から句読点や改行の位置のようなものが徐々に気になりだし、書き手の目で読んでいるつもりでいたんですけど、一文字も小説を書いたことがない、書かないと賞を獲れないことに、二十代前半になってようやく気づいて(笑)書き始めたんです。
村田 自分も、どこかの賞に応募してるわけでもないのに本屋さんでじっと自分の本を探しているような小学生でした。待川さんも、読んだときにただ物語を与えられるタイプというよりは、物語の影響を受けて自動的に新しい物語が身体の中に発生するタイプの方だったのかなと思いました。
待川 そうかもしれないです。村田さんが「自分の手書きの文字を明朝体にしたかった」とどこかで書かれていたとき、めちゃくちゃわかると思いました。
村田 明朝体になったときって嬉しいですよね。ゲラになると、また全然違います。同じ作品でも単行本と文庫とか、組が違うものの文字の表情を見比べるのが好きです。
待川 わかります。最終選考前にゲラをいただいたとき、一晩中ずっと眺めていました。
村田 短歌もなさっていたとお聞きしました。
待川 十八歳くらいのときに一年だけ、大学で川野芽生さんと同じ短歌サークルに所属していました。千種創一さんとは友人で、十年くらい前に「中東短歌」という同人誌でご一緒しました。
村田 この作品はどのくらい時間をかけて書いたのでしょうか?
待川 半年くらいです。二十代前半のときにも一度だけ文藝賞に応募したことがあったものの、自分は書くよりも読んでいたほうが面白いなと思って、あっさりやめちゃったんです。今回また書こうと思ったのは、ちょうど去年の夏、北海道に珍しく台風が来て、予定していた登山旅行がなくなって、一週間くらいぽっかり時間が空いちゃったからなんです。久しぶりに何か書いてみるかと思って、とりあえず登場人物を乗り物に乗せて移動させておけば何か出てくるだろうと思い、プロットも何も決めないで冒頭をふわっと書き始めました。
村田 何も決めないで、どこに行くかわからない小説を書くのは私も好きです。短編も含め、たぶんほとんどすべての小説で、この先どうなるのかわからずに小説を書いています。小説が終わるときも、あ、たぶんここがラストシーンだ、と書きながら気がつきます。新人賞の選考会では物語の終わり方について議論する機会があるのですが、私自身、子供のころ初めて小説を書いたときも、最初は途中までしか書けず、すぐに他の小説を書き始めてしまってばかりで、一つの小説が終わる、ということが発生するまで時間がかかりました。大人でも、そこにひとつの壁を感じている方がいるとお聞きします。「光のそこで白くねむる」のラストの文章ができたとき、「あ、ここで終われた」と思うような瞬間はありましたか?
待川 ラストはけっこう急いで付け足したんです。一晩で最後に三十枚くらいピュッと書いて、終われないけど締切がきてしまうから唐突にブチッと切ったという感じです。ただ、今までは賞に応募しようと思えるほどのラストを書けないことがほとんどだったので、今回はまがりなりにも書き終えたとき、やっとどこかに行けたかな、という感覚がありました。
村田 選考の中でこの小説のラストを「これは主人公が大量殺人をすることを示唆しているのではないか」という話にもなり、驚きながらも、それは面白い読み方だなあと印象深かったです。私は、確かなものが何もないこの物語のラストで、骨を掘り返せば確かなものが見えるはず、と予感させる結末の付け方をしていることを、すごく面白いと思いました。
待川 前半は自分にしてはよく書けたなと思っているのですが、後半の手ごたえは自分ではよくわからなかったんです。キイちゃんが喋り出したあたりからは、「面白いな」と自分で思うときと、「何だこれ」と自分で乗れないときがありました。「自分の読みたいものを書こう」というのが書くときの最大のモチベーションなので、これは本当に自分の読みたいものなのかなと悩んでしまって。最終選考の結果を待っている間も、今回はないかな、一人でも推してくださる方がいらっしゃれば御の字だな、と失礼ながら勝手に思っていたので、受賞の連絡を受けたときは、驚きました。
偶然が必然となる瞬間
村田 「光のそこで白くねむる」には、暴力、とくに「加害」と「被害」といった現象が存在し、心に残りました。人によっては最初から「暴力」をテーマとして据えて書き始める方も多いと思うんです。けれど本作はそうではなく、小説の中から「暴力」が自然に、真っ白な紙の中にじわじわと、溢れたインクみたいに滲み出てきているような感覚がします。
待川 「加害」と「被害」という言葉は最初から対照に置こうとしたのではなく、バラバラに出てきました。「加害」は、書き始めたときに嫌なおばあちゃんを出そう、おばあちゃんが言って嫌なことって何だろうと思っていたら、「加害者」と言い続ける機械のような存在になりました。ほかはかなり後付けで、土産物屋の店主が無差別殺人を起こす話も、この小説の色がかなり決まってから、最後に何か足そうと思って書き足しました。主人公が受けてきた「被害」もそうです。ただ、最初から、「土地の呪い」みたいなものを出したいなとは思ってはいました。でもなかなか書けなかったですね。なので、後半に置こうと書き始めたシーンをわりと無理やりニュルッと前半に入れる、みたいな作業をすごくたくさんしました。ある文章を別の無関係な文章の中にポンと置くと、何か新しい言葉や場面が出てくるのではという試みをしているうちに、たまたま暴力に関するシーンが削られず残ったのかもしれないです。
村田 主人公の「わたし」を、女性として読む選考委員もいれば、男性として読む方もいました。ジェンダーを限定しないように読める書き方は、意図的になさっているんですか?
待川 はい、そこは明確にそうしました。大人だけど子供の意識と連続的に見せたいなと思って推敲するうちに、視点人物が自らジェンダーを同定するような描写が取れていきました。
村田 不思議でした。選考会では、みんなそれぞれが違うジェンダーを思い浮かべていることに、はじめは気がつかないで読んでいたんです。
待川 「わたし」の性別や、舞台の場所の具体性をなるべくなくす。この二つはけっこう意識していました。最初に書いたとき、「坂」にはもっといろいろ、鯉のぼりや名物の木があって、それを地元の人が「田舎の観光名所」にしようとしている描写があったんですけど、全部削りました。自分は田舎育ちなので、存在しない田舎のイメージはわりとパッと浮かびました。生まれは徳島のはずれにある漁師町で、単線のワンマン電車が走ってて、あとは海と山があるだけのような場所だったんです。
村田 「キイちゃん」という子は、いつ出てきたのでしょうか?
待川 最初、キイちゃんは普通に生きている、地元のお兄ちゃんみたいな感じの人物でした。前半は故郷に行く話を「わたし」の視点で描き、後半は二人で帰る話をキイちゃんの視点から描く構造の作品にすることをなんとなく考えていたんです。作品をパッと書いた後、作品のテキストを並べ替える作業を自分はよくするんですけど、そのとき、入れ替えの順番を間違えたんです。行きパートと帰りパートを間違えて、いきなり「わたし」の語りのパートで「おれは」とキイちゃんが言い出して、本来の語り手とは別の語り手がいきなり出てくるこの感じは面白いかもと思い、一回全部消して書き直したのが始まりでした。
村田 面白いですね、偶然性が物語にとっては必然になったようなお話ですね。小説の文章は、消してもどこかに気配が残っていることもあれば、完全に消えることもあって、興味深いです。「墓参り」はいつ小説の中に出てきたのでしょうか?
待川 けっこう後だったと思います。ただ電車に乗ってるだけの小説だったので「目的、無(な)っ!」と思って。なので墓参りはかなり意識的に、それこそ話を進めるために適切な位置をさがしてポンと置いた感じです。
村田 小学生の描き方が私にとってはリアルで、たとえばその子が給食で飲んだ牛乳の匂いが声からするような、不思議な生々しさがありました。こういうふうに書こうと思ったことは何かありますか?
待川 怖いものを書いてみたかった、ということもありますが、むしろ、ストレートに小学生の会話を書くことは、自分の実力的にできないなと思い、避けて迂回していたらこうなっていました。「わたし」とキイちゃんの語りを簡単に入れ替えられるようにするために、二人称の文を三人称の文のように書いておくとか、本当にあったことをそのまま入れるみたいな、技術的に自分が簡単だと思うことをしていました。中華屋さんのスープの器が小学校の給食のときと同じだったというエピソードがありますが、あれは書いているときに本当にあったんです。書くまでは想像もしなかったところへ、書きながら小説に連れて行ってもらう。でも連れて行かれるままに書くのではなく、技術的にしんどいところを避けつつ、小説と交渉して自分にできることをするという作業をしていました。
村田 子供と大人というところでは、「子供という殻が破られて、すべてがすっかり変質し、ほとんどべつものになることで大人になるのではなくて、子供時代というのは、琥珀のなかに閉じこめられた昆虫のように、ずっとそのままのかたちでそこにあって、その外側をべつのものが包んでいるだけなんだ」という辺りがすごく好きでした。個人的な感覚ともすごく呼応する、共鳴する言葉でした。
待川 この文章、削ろうと思ってたんです。子供時代は琥珀のなかに閉じ込められたもののようである、という言葉の説得力を、その前までの文章で出せている自信がなくて怖くて、これはちょっとやめたほうがいいんじゃないかと最後まで悩んだ一文だったんです。自信がなかったので、村田さんにそうおっしゃっていただけて救われた気持ちになります。
村田 選考会では選考委員のお一人が、「文藝賞をこちらが土下座して、もらってもらうくらいだ」と、ものすごく褒めていらっしゃいました。
待川 畏れ多いです。……ところで失礼ですが、候補作の冊子についた付箋が大量で、すごく気になります。
村田 私は普段は本に付箋はつけないんですけれど、このお話はとにかく文体が素晴らしくて、好きな文章にペタペタ貼っていたら、付箋だらけになりました。待川さんは、随筆を書いても文章に宿るものの力でほとんど小説に近い佇まいになるようなタイプの作家さん、たとえば私自身が大好きな堀江敏幸さんや朝吹真理子さんのような方が頭に浮かんで、そのような文体そのものに大きな力がある書き手さんなのではないかなあ、という勝手な想像がありました。待川さんは、この作家の文体が特に好きとか、そういう感覚が強くあるタイプの読み手ですか?
待川 文章そのものを書き写すことをすごくやります。書きながらちょっと詰まってきたら、手元に全然関係ない小説を置いて、それを同じパソコンの画面で、ファイルだけ切り替えて、キーボードで書き写すことが多いです。かなり分解されてはいるんですけど、「光のそこで白くねむる」も、書き写していたものがなんとなく混ざった文章になったという気はしています。この作品を書いた時は、オーストリアの作家シュティフターの『晩夏』や『水晶』、川上弘美さんの『真鶴』、折口信夫やブルーノ・シュルツらの作品を書き写していました。細密で、マニエリスム的な文章が好きというか。あとはやっぱりフォークナーですね。
 待川匙 1993年、徳島県生まれ。滋賀県育ち。
待川匙 1993年、徳島県生まれ。滋賀県育ち。
2024年、本作で第61回文藝賞を受賞しデビュー。
言語を超えた読書遍歴
村田 待川さんの読書歴がとても興味深いと編集部の方に伺いました。聞かせていただけますか?
待川 読書歴の始まりは小学校一年生になったくらいでした。「ハリー・ポッター」シリーズが流行った時代だったんですけど、ハマらなくて、代わりに、『崖(がい)の国物語』というすごく長い作品が図書館に並んでいるのを見つけて、かっこいいと思って読んでみたのが始まりでした。
村田 純文学というものがこの世に存在するということに気づかない人もいると思うのですけど、きっかけはあったんですか?
待川 噓みたいですけど、「文藝」なんですよ。二〇〇六年冬季号の伊藤たかみさんの特集号が最初だったと思います。伊藤さんはヤングアダルトっぽいのも書かれているので「あ、伊藤さんだ」と思って雑誌を買ったら、綿矢りささんの「夢を与える」が載ってて、「なんだ、これは!」となって。その翌年の冬季号では磯﨑憲一郎さんが「肝心の子供」で文藝賞を受賞しデビューされた。その辺りからずぶずぶとハマって読んでいきました。中学一年生、十三歳のときです。
村田 最初に文芸誌から入るって珍しいですね。私の印象では単行本とか、子供のころは教科書や文庫が多いのかなと感じています。十代のときに文芸誌を手に取っている人がいることが、嬉しいです。海外文学もお読みになると伺いましたが、きっかけはあったんですか?
待川 日本文学と海外文学の位相が違うという認識がないまま、手当たりしだいに読んでいました。こういう人は多いと思うんですけど、大きな本屋さんに行くと一番上の階の端っこから一番下の階の端っこまでバーッと全部の棚を見るタイプなので、自然と面白そうなものは目に入る。だから、何か特定のきっかけはないと思います。小説が好きだから、小説だから読もう、くらいです。
村田 フォークナーと幸田文という、まったく作風の異なる二人の全集を読破したとも聞きました。
待川 フォークナーの全集は二十二歳のとき、小説を書いてない、書かないと賞を獲れないんだと気づいたときに、岩波文庫の『熊』が好きだったので、読んでみようと思って手に取りました。フォークナーは〈移動〉を書くのがすごく上手いと思っていて、『八月の光』の冒頭も妊婦が歩いてくるシーンから始まるのが印象的だったんです。幸田文は本作を書き始めるちょっと前くらいに読みはじめました。『さざなみの日記』が一番好きです。いまは、小学館の「日本古典文学全集」を頭から読んでいます。
村田 英語など、原語で読むみたいなこともなさりますか?
待川 大学の外国語を使う授業の流れで、大人になってから頑張って辞書を引きながら原語を読んでいます。高校生のときは英語しか知らなかったので、フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』を読んだりしていました。大学で習ったフランス語、英語、中国語の他にも、スペイン語、あとはサンスクリット語を勉強しています。最近では、英訳版『マハーバーラタ』十巻を取り寄せたり、ポール・オースターの遺作とか、アルゼンチンの作家マリアーナ・エンリケスの英訳作品を読んでいます。日本の五大文芸誌に加えて、グランタやニュヨーク・タイムズ・ブックレビューを読んだりもします。あとは中国語にハマって、中国資本のゲームを中国語で遊んだり、中国のドラマを見たりもしています。
原書と翻訳書は、それぞれ全くリズムの違う別物として楽しめるものだと思っています。特にフォークナーってすごく変な文を書くので、翻訳者さんによっては原文の段落を途中で切ってわかりやすくしている方もいます。やたらこのフォークナーは改行が多くてスマートだなと思って、原書を読むと段落がつながっていたということもありました。小説の勉強と思って読むというよりも、翻訳を読んで「ああ、そういう意味か!」と思ったりするのが、単に好きなのかもしれません。
小説を書くという呪い
待川 村田さんへの人生相談みたいになっちゃうかもしれないんですけど、今まったく二作目を書ける気がしていなくて、こんなふわふわしてて書き手として大丈夫なんでしょうか?
村田 私も相当ふわふわしていて、むしろ待川さんのほうが、話しているとよほどちゃんとしていらっしゃる気がします。何を書くかはお考えになっておられたりするんですか?
待川 受賞のご連絡をいただくまでは、来年何を新人賞に出そうか、というのを考えていたんですけど、連絡をいただいた瞬間に全部が消えました。やっぱり投稿作と二作目は違うだろうなと思って。
村田 私も二作目を出すまでは、けっこう時間がかかってしまいました。デビュー作の「授乳」から二作目の「ひかりのあしおと」が掲載されるまで、三年半くらいかかりました。
待川 小説を書く人の状態にどうやって入っていくんだろうというのを、今すごく悩んでいるところです。村田さんは、作家としての状態を、どのように身につけられたのですか?
村田 横浜文学学校という勉強会で、恩師の宮原昭夫先生が、「小説は人間の職業ではなく状態ではないでしょうか」とおっしゃっていたことがあって。またご著書で、「作者は作品の奴隷だ」という言葉を教えていただきました。小説を書いていると、だんだんと意味のわからないことが起きて化学変化でまったく違うものに変質していって、そこになんとなく、その小説の本質、根幹、があるのではないかと思って。なので他を全部消して、現れてきた塊のようなものに従う……という書き方を続けていました。そのため、人間としての自分が考えていないようなことが小説の中に発生するのですが、それに従う、自分には手に負えない蠢(うごめ)きに支配される喜びのようなものがいつもあります。
待川 いい意味で小説に呪われた意識ですね。
村田 でもそれが結局一番楽しいというか、どうなっていくのかわからない実験のような喜びがあるんです。
待川 本当にそうなんですよね。今回自分も書いていて、怖くなる瞬間、びっくりする瞬間が初めてすごくいっぱいあったんです。今までそんなことなくて、どちらかというと小説をコントロールして書きたかったんですけど、「こいつ、勝手に動いてる!」と登場人物に恐ろしさを感じたり、気持ち悪い文章を書けると「なんか出ちゃったな」と楽しくてニヤニヤしてしまうことがあったりしました。
村田 大好きです、その感覚が私にとってとても大切です。
待川 小説を書くという行為自体が、自らに進んでかける呪いみたいな、すごく不思議な行為だと思いました。
村田 お話ししていてなおさら感じたのですが、待川さんは何を書いても文章が輝くタイプの方なのではないでしょうか。どんなに文体が好きな作品でも、展開のために入れた文章とか、話を進めるためにざっと書かれた文が、普通はどうしても入り込んでくるはずなのですけれど、「光のそこで白くねむる」は、そういうものが一行もないのではないかというくらい全然見当たらなくて、そのことに感銘を受けました。言葉の選び方が特別で、全部の文章が誰かにとっての詩になりえるような、ちょっと特異な輝きみたいなものを感じます。
待川 そうおっしゃっていただけて、嬉しいです。ありがとうございます。
村田 お話を聞いていて、待川さんは書いていない間も書き手だった方じゃないかと思っています。なので、もうただただ、好きな書き手さんの読み手として、待川さんが自由にお書きになった次の作品が楽しみだなあという気持ちです。この作品に惚れ込んだ人間としては、待川さんが次に何を書いてもその言葉に触れること自体が大きな喜びですし、読んでみたいです。
(二〇二四・八・二七)
写真=川島小鳥