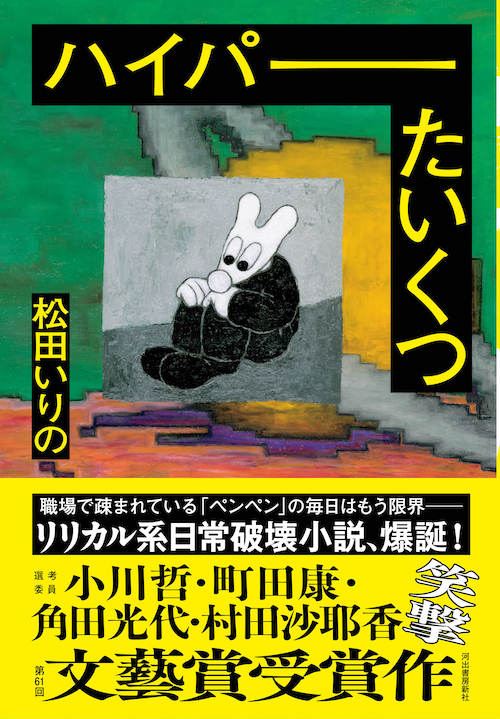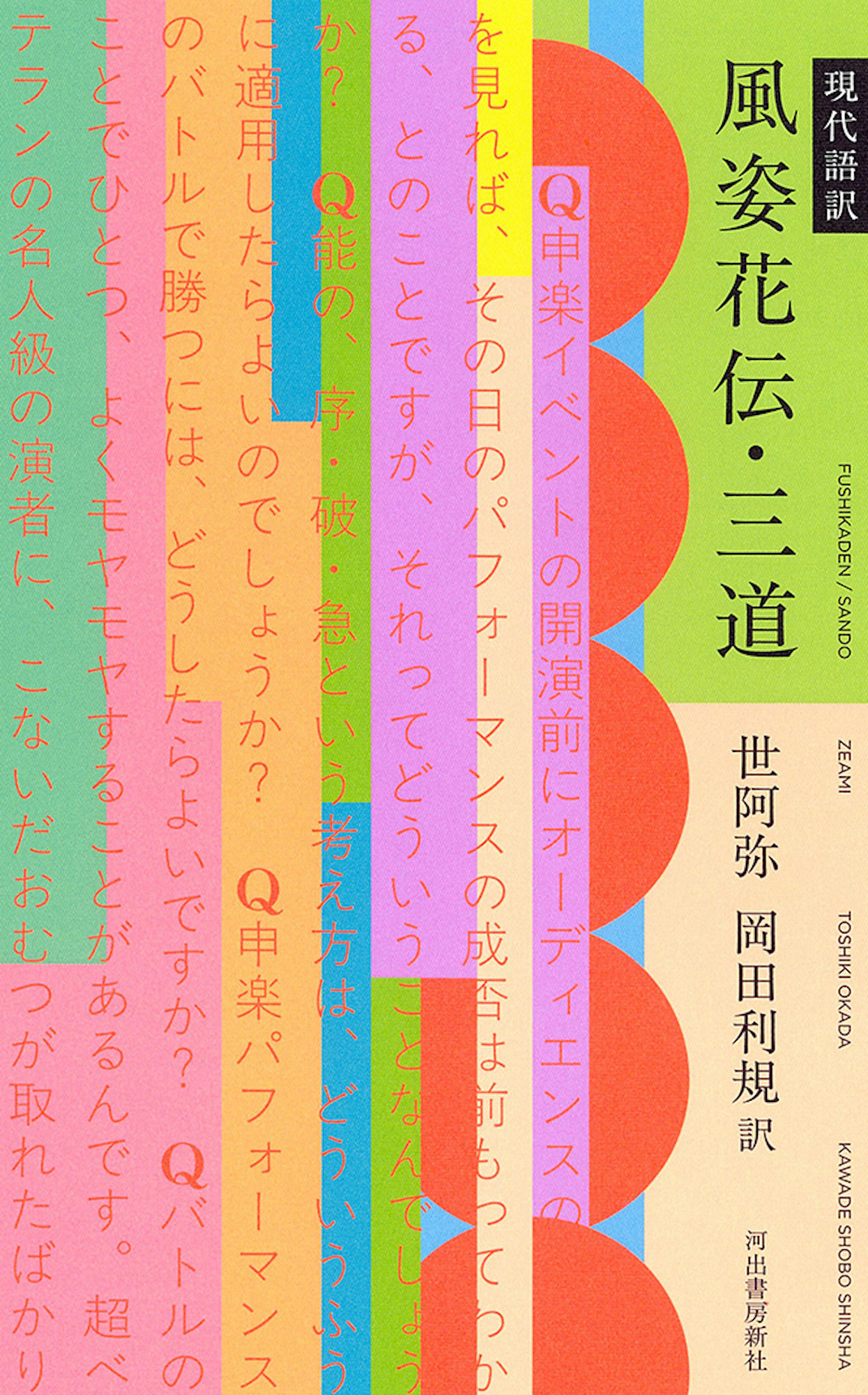ためし読み - 文藝賞
第61回文藝賞受賞作!待川匙『光のそこで白くねむる』試し読み
待川匙
2024.11.21
墓参りに帰郷した「わたし」に語りかける、死んだ幼馴染の声。行方不明の母、蒙昧な神のごとき父、汚言機械と化した祖母……平凡な田舎に呪われた異界が立ち上がる。発表後から各紙誌で絶賛され話題に。圧倒的異才が放つ、衝撃のデビュー作!
待川匙
『光のそこで白くねむる』
あかるい車両だった。くすんだ内壁の塗装が光を鈍く反射する、そのわずかな照り返しを浴びにいくように顔をあげて座っていた。
車内には長細い影がいくつも這い伸び、それぞれが異なる周期で重なっては離れを繰り返す。窓の様子、だんだん位置の高くなる陽光の加減から、電車のなかはあかるくなり、また暗くなった。
景色が青白くひらけているとき、天井の電灯はほとんど発光せず、塗り忘れのような長方形の灰色が浮かぶばかりだ。それがトンネルに入り、すべての窓がべったりと闇一色に染まった途端、生白いあかるさを放ちはじめる。
でも、光の総量はずっと一定にも思えた。ほんとうは、強弱などないと思った。
その明滅を顔に這わせるように座っていた。
墓参りにいく。亡くなったと聞いて十年になる。ずっと意識の隅に引っ掛かっていたような、けれどもほとんど思いつきの旅でしかないような、どちらとも心づもりの据わらないまま、とにかく体が運ばれている。
昨日は飛行機でこちらへ来て、祖母のところに寄った。羽田からの直行便はわたしが上京したころよりずいぶん減っている。機体が高度を下げると、小高い丘の隅にねずみ色に塗られた区画が浮かび、いやに現実味を欠いたままぐいぐいと近づいて、車輪が滑走路に接した瞬間、機体は路面の凹凸をなぞってよく揺れた。
チューブ形の飛行機の空間、整列するシートのはるか前のほうで、子供が声をあげていた。そういえば、上空で揺れたときにも怖がっていた。声は気流のなかで浮いては沈み、言葉が像を結ぶ手前で消散し、意味はつかめなかった。それでも人声であることはわかるので、意識はひとりでに吸い寄せられていき、ふいに数文字のひらがなが明瞭にわかる瞬間があり、すぐにほどけて曖昧な音声の連なりに戻る。
機体が安定すると、声はやんわりと消える。眠ったのだろう。わたしも眠くなり、やがて子供の存在自体を忘れてまどろみ、着陸の直前に覚めて顔を上げるとまた声が聞こえてくるので、そうだった、前のほうに子供が乗っているらしいのだった、と思いだすことになった。あらためて聞いてみれば声は恐怖ではなく、機体の揺れを楽しんでいるのかもしれなかった。旅が怖いのはわたしのほうだ。どうだろう。わからない。車輪は滑走路を急速に転がっていく。
旅慣れた客たちには子供の声など聞こえていないかのようだった。着陸直後のアナウンスも耳に入っていない。客室乗務員が平坦な、しかし抑揚がないわけではない作り声で、機体が完全に停止するまでは座っているよう案内しているのに、客たちは席を立ち、さっさと頭上の荷物棚を探りはじめている。客室乗務員の目にはそれらの動作があきらかに映っているはずなのに、注意はなく、まるですべてが案内通り進行しているかのように、あっさりとマイクを手離す。
わたしは小さな手鞄ひとつきりを抱えて座っていた。
墓参り以外に用のない旅だから、しぜん荷物は小さくなった。しばらくして飛行機が停まる。可動式の階段が出口に設置されるのがわかる。それからさらに、奇妙な待機時間がある。業務連絡が何度か交わされるが、客へはなにも案内されない。長い。それまでも空のうえで長いこと座っていたのに、地表の時間の流れはやたらに間延びして思え、気のせいか少し暑く感じられた。早くに席を立ったものたちは、首をやや低くしてじっと静止している。ようやく扉が開かれて滑走路に足をつけると、どういうわけかみんないったん立ちどまり、すべての肺の空気をいれかえてから、ふたたび建物のほうへと歩き出すのだった。
空港の、到着口と出発口とは分かれておらず、おなじ機体の折り返し運航に乗るらしい数人の姿がすでにある。カウンター式の売店、化粧室のありかを示す看板、昼どきのみ開かれる小さな食堂の入口があり、食堂はすでに営業を終了している。一日の発着便を掲示するディスプレイは残り一行、そのそばを過ぎて少し歩けばもう正面玄関である。
機械があった。ちんまりとした古い空港のなかで、高速バスの券売機だけが新型に置き換えられて、三台も並んでいる。光沢のない黒の筐体の中央で、手触りのよさそうなパネルがあかるい光を放ち、頻繁に表示を切り替え、その明滅がひとつのリズムをなしている。まわりにはだれもいない。ほかのものたちはタクシーか自家用車におさまっていく。結局、バスの乗客はわたしを含めて三人きりで、あの子供のすがたは最後まで目にしなかった。
十年前この空港からあてもなく上京し、ありきたりの貧乏生活を続けた。外に出て働くということが、なんらか自分を被害者の状態に置く行為であるかのように、つねに感じた。アルバイトを転々としたのち、ここ数年は神社の参道に軒を連ねる商店街の土産物屋に落ちついていた。
思いがけず休みになった。どれくらい長い休みになるかはわからない。店はシャッターを閉め、「無期限休業」とわたしの字の張り紙をしたまま一週間以上になる。
店舗は数度移転しつつも、屋号じたいは大正期からあり、昭和の末には火事で全焼したこともあるのだと聞かされた。土産物屋を名乗っているし、和傘や匂い袋の類いもあるにはあるが、目立つところには話題のアニメグッズ、カプセルトイの販売機、壁には世界一周旅行のポスターが貼られ、そもそも売り物は店舗面積の三割程度にとどまり、あとの大半は観光地化した商店街の、観光客が足を休めるための喫茶スペースになっていて、客足の合間に商店街の寄合までなされるのだった。
わたしはそこで、ペットボトルのアイスコーヒーだの、前日の夜から解凍しておいた饅頭だのを、見た目ばかりは小綺麗な器に移しかえて客に出す仕事をしていた。賽銭のための両替も兼ねてわざと半端な値段にし、レジ下の小さな引き出しには棒状にまとまった予備の硬貨が隙間なく並ぶ。客のいないときにはその凹凸のひとつひとつを指でなぞっているのが好きだった。
四代目にあたる店主と、その従兄弟の副店主と、わたし。それから店主の旧友だという、しかしずいぶん歳の離れていそうな、名前もわからないおじさんが年に何度か裏口から入ってきて、野菜や果物の入ったビニール袋を押しつけるように手渡し、しばらく勝手に掃除などして、客がいてもお構いなしで店主をつかまえ、ひとしきり話して帰っていく。おじさんの風体はどことなく狸を思わせる。
面接のときは、店がちょっと怖かった。着いて早々、硯と紙と細い筆を渡され、紙は書道用のものではなくコピー用紙そのもので、営業中の、それなりに客のいる店内のいちばん隅のテーブル席で言われるがまま墨をすり、あらかじめ印刷された活字の内容を転写した。ぎこちなかった。墨は紙のうえで浮き、半端な滲みになった。習字など小学校の授業でやったきりだった。客席のほうから、会話の合間にそれとない一瞥が挟まるのを感じた。
採用します、とだけ言って口を閉ざした目の前の男が、店主だったか副店主だったか、よく覚えていない。ふたりはとても似ていた。よく見れば顔の造作などは細かく違うのに、表情筋の動きや、ふとした呼吸の置きかたなどが奇妙に同期しているふたりなのだった。仕事着のよれた雰囲気もおなじだった。数年働いたあとでもまだ、ふたりのどちらかが薄い背中を向けていると、どちらの名前も呼ばずに、あの、とだけ声をかけることがあった。
朝はわたしひとりでシャッターをあけ、準備がおわるころにどちらかがやってくる。店主も副店主も時間ぴったりに来て、ぴったりに帰る。例外はない。ふたりともおなじ床屋で、おなじかたちの丸坊主にしている。年に一度、商店街の端にあるめがね屋にふたりで行って、揃いのめがねを新調してくるらしいのが、とてもへんだと思った。
店のことは、わりあい好きなほうだった。店には整然としたリズムがあった。客の多寡すらもあらかじめ計画されていたかのように動く。慣れてくると、朝におもてのシャッターを開けた瞬間、繁忙期と閑散期の切りかわる音が聞こえてくる。修学旅行の時期、海外のバックパッカーが多く訪れる時期、休日でもほとんど客のいない時期、それらの境目が空気からわかる。週のはじめにすべての椅子をひっくり返して拭きあげ、水曜日に仕入をおこない、木曜日は必ず店主と一緒のシフトで、店主はお昼に銀行へいくので、わたしひとりで少し忙しい。欠勤も遅刻もしなかった。ふたりとおなじように、時間通りに来て、時間通りに帰った。あの店で働きはじめてから、体調をまったく崩さなくなっていた。
簡単な作業を表向きこなしていれば、頭でなにを考えていてもよかった。とはいえなにも考えてはいなかった。もっぱら前夜に見たアニメを脳内で再生し、重要なシーンの緻密な作画を思いだしてにわかに気持ちが昂っても店の時間は関係なく流れていく、それがよかった。すべては店のリズムのなかにあって、乱さなければ何をしていてもよかった。けれども、リズムは壊れてしまった。その日、わたしは店主に頼まれて、休みをとりかえることになった。
そんなことはそれまで一度もなかった。
どうしても、という念押しがどうにも店主らしくなく、子供相手のように姿勢を低くし、まっすぐ目線を合わせて話されるのも初めてで、どうにもすわりがわるかった。彼は、印象よりも目元のしわが多かった。黒目も大きかった。目線をうまく外すこともできないまま、どうしても、と繰り返し懇願されると、感覚が夢のようにねじれてくる。断わりたかった。いやだった。本当は億劫なだけだった。家で洗濯機をまわすルーティンが一日後ろにずれるのが面倒だという、ただそれだけのことで、恐怖に近い不安を感じた。わたしの情動は店のリズムとほとんど融着してしまって、その程度の乱れも許容できなくなっていたらしい。
口先は、しかし、そのような内心とはまったく無関係に快諾の言葉を述べていた。店主たちの指示にはいつでも、はい、と応じるのが店でのわたしのリズムなのだった。応じながら、このひとの顔はやっぱり店主たちとは似ても似つかない、と思った。目元だけでなく顔面全体のなにもかもが、記憶にある店主や副店主とはちがった。誰だろう。代理出勤当日の朝にシャッターを開け、空調をつけて座席の清掃をはじめると、自分の腕や脚の、とくに関節のあたりが、いつになく重く感じられた。
その日も時間通りに退勤し、自宅の玄関で靴を脱いだとたん、数日分の眠気が正面からのしかかってくる。長いこと、整然とした店のリズムにあわせてきた代償のように、部屋の床には食べのこした弁当や、ペットボトルや、公共料金の支払い用紙などが散らばり、寝起きする時間も毎日ひどくばらばらになっている。すこし休憩するつもりで床に倒れ、すぐに眠りこんでしまった。店からの着信があった。無意識に取ったがまだ目覚めてはおらず、半分眠りのなかで声を聞き、自動的に返事が出た。はい。靴をはいて外に出ると、もう暗くなっていた。
電話の声はひどく低かった。わたしにも客にもまったくおなじように向ける、抑揚ばかりのいつもの愛想のよさは微塵もなく、低く曇った声だった。言われたとおり店に戻ると、一言目に無期限休業を告げられた。用意されていた筆をとって、その言葉通りに字を書いた。机のすみに警察署の電話番号のメモがあった。すでに営業を終えた店の電灯はひとつきりしか点いておらず、すぐ正面にある坊主頭の影が放射状に重なるので、手元が揺らぎ、線が歪んだ。
いつもとくに雑談をするわけでもないので、暗い店内で墨が乾くのをふたりで黙って見つめた。離れて見ても、やっぱりすべての線が微妙に歪んでいると思う。書き直しは申し出なかった。普段から上手なわけではないし、うまくなるつもりもないから毎日書いてもまったく上達していない。
しばらくして、ほとんど歯擦音だけで、っし、と言って立ち上がるので、うしろについて裏口からおもてにまわり、すでに下ろしてあるシャッターに紙をあてがった。
わたしが正面から紙を押さえているあいだ、横から細い体をねじるようにして養生テープをまず四方に貼り、っし、というのでわたしはもう手を離してよく、粘着の強い黒いガムテープが、養生テープの上から几帳面に貼られていくのを、わたしは一歩下がったところで眺めていた。
貼りおわると彼は養生テープの輪っかと、黒いガムテープの輪っかを左右の手首にそれぞれはめ、しゅ、と息を吐いた。それから、しゅううううう、と長く吐いた。吐きつづけた。止まらなかった。しゅううううう、と空気を失う風船みたいな音はいつまでも止まらず、彼の体はじっさいに足元のほうから崩れていって、膝が折れ、腰が落ち、背中が曲がり、首が前におちこんで、ぐんにゃりとその場にへたりこんでしまった。
暗い商店街の、街灯のあたらない部分にわたしたちはいた。地面に手をつき、うつむいて表情の見えない、めがねの縁だけが光っている坊主頭のこの人物が、副店主のようにも、店主のようにも、どちらでもないようにも見えた。そのときになって気づいたことだが、彼は腕が相当長かった。長いというか、重力のままに伸びて垂れて、なんだか水死体の腕みたいだと思った。
その片腕が持ち上がりはじめた。かろうじて体内に残る空気を結集するように、徐々に持ち上げて、こちらに差し伸ばしてくる。細く痩せた腕に沿ってガムテープの輪がずり落ち、肘にかかった。なにか言う。聞きとれない。
はい。
聞こえなかったけれど、とにかく応えて、差し出されたものを受けとった。くしゃくしゃの紙。わたしがくるまえに彼ひとりで書き損じたものだろうか。であれば、後で捨てておけということだろうか。わたしがそれをポケットにしまうと、彼はこちらを一瞥もしないまま長い腕をだらりと降ろして、また動かなくなった。少し待ったが、何も起こらなかった。はい。わたしは言った。言われたこと以外はしなくてよい。わたしはそんな店が好きだった。失礼します。
歩きはじめ、一度だけ振りかえると、影のなかにうずくまった人物の頭頂部が陰のなかに浮かんでいた。よわい輪郭だった。つぎに見たときには消えていてもおかしくなかった。わたしはその日二度目の帰路に向きなおり、それからは振り返らずに歩いた。ポケットに手をいれて、中の紙くずを握ったりゆるめたりした。街灯の下で、自分の足がきちんと動作していることを目視で何度も確認したくなり、実際にそうした。いったん止まってその場で膝を上げたり、ジャンプしてみたり、早足になってみたりした。
気分は奇妙に凪いでいた。
爽やかと言っていいくらいだった。指示通りに働き、指示通りに休む、ただそれだけのことだ。それに、とわたしは思った。いずれにせよ明日はもともと代休の予定だったのだ。
いくつか路地を曲がると、やがて煌々とあかるいスーパーの軒先にいきつく。そのあかるさですこしだけ気持ちがゆるむ。ゆるんだことで、それまでのこわばり具合がようやくはっきりと自覚される。代理出勤を打診されたとき、家についたとき、電話で目覚めたとき、紙くずを渡されたとき、ずっとわたしはこわばっていた。こわばっていることを、ほんとうは知っていて、知らないかのように振る舞ってきた。
スーパーの外壁沿いに大きな丸いごみ箱が、燃えるごみ用、ペットボトル用、ビン・カン用と三つ並んでいる。ポケットから紙くずを取り出す。奇妙な柄だった。書き損じではなかった。どことなく見覚えもあった。丸まりの多少ひらきつつある紙は、光のなかで触るとすこし吸いつくような、ざらりとした感触があって、それにも覚えがあった。広げてみる。一万円札。何枚かある。七枚ある。
わたしはとりあえずごみ箱のそばを離れ、証明写真機のちかくに寄って、紙幣を広げ、手のひらで何度もなぞり、しわをのばした。あたらしい肖像の紙幣。給料ではない。週ごとに現金払いの給料は、おととい退勤する間際にもらったばかりだ。それに、あの店はいつもまっさらな新札をくれる。客から受けとったものもすべて銀行で新札に換えてくる。休業にともなうボーナスのつもりか、あるいは退職金というつもりなのか。わざわざくしゃくしゃにするなんて、もしかして偽札なんじゃないか。でもいずれにせよ、とわたしは思った。翌日はもともと代休の予定だったのだ。家にこもる予定に変わりはない。
スーパーで、いつも買うインスタント食品や、最近よく飲んでいる豆乳、いくらかのお菓子と、煮出して冷蔵庫に置いておくためのお茶パック、レジの手前で奇跡的に思いだしたので、切らしかけていたごみ袋も買って部屋にもどり、もう外出の用がないことに安堵しながら玄関のドアチェーンをかけ、買い物袋を降ろすと、また眠気がやってくる。
今すぐ入浴するべきだという正しい考えを帰路の途中から持っていたが、体はなかなか浴室に向かなかった。いったんキッチンで水を飲んで考え、居間に移動し、もういちど考え、そんなことをしているうちに疲れはどんどん噴き出し、疲れにしてもちょっとおかしくて、これは風邪かもしれないと思い至った。そう思うと、鼻のなかからわずかに変わった匂いがしはじめた。諦めよう。まず眠って、起きてからシャワーを浴びてもよいのだ。わたしは点けたばかりの灯りを消し、寝床に入るとすぐに眠りに落ちた。
目が覚めた。夢をみなかったのでかなり長く眠った気がしていたが、外はまだ暗かった。入浴せずに寝入ったとき独特の、皮膚の表面が張りつめて弛緩しきらない感じがあった。わずかに頭痛の予兆もあった。外着のまま横になっているのが窮屈だった。脱いで、その動きの流れでスマホを取って開いたニュースに、無期限休業、とわたしが書いたとおりの張り紙の画像が載っていた。
ニュース本文は短いものだった。店主の姓名、括弧書きされた実年齢、わたしに休みを交換させ街中に出た彼が起こした行動を端的にあらわす単語、死傷者の数、とりわけ亡くなった数名のうち、身元の判明しているもののおおまかな年代、店主本人については逃走、すこし遅い時間の追記で身柄拘束、とだけあった。
寝なね。
わたしは声を聞いた。わたしが言ったのではなかった。わたしの意識の前提となっている、めったに表にはあらわれずふだんはその存在すら感覚されない、でもずっとついてきていて、人生のうち例外的に数回だけ介入してくることのあるわたし以前のなにものかが、どうやらそのように判断したらしい、とわたしには直感された。
【続きは本書でお楽しみください!】