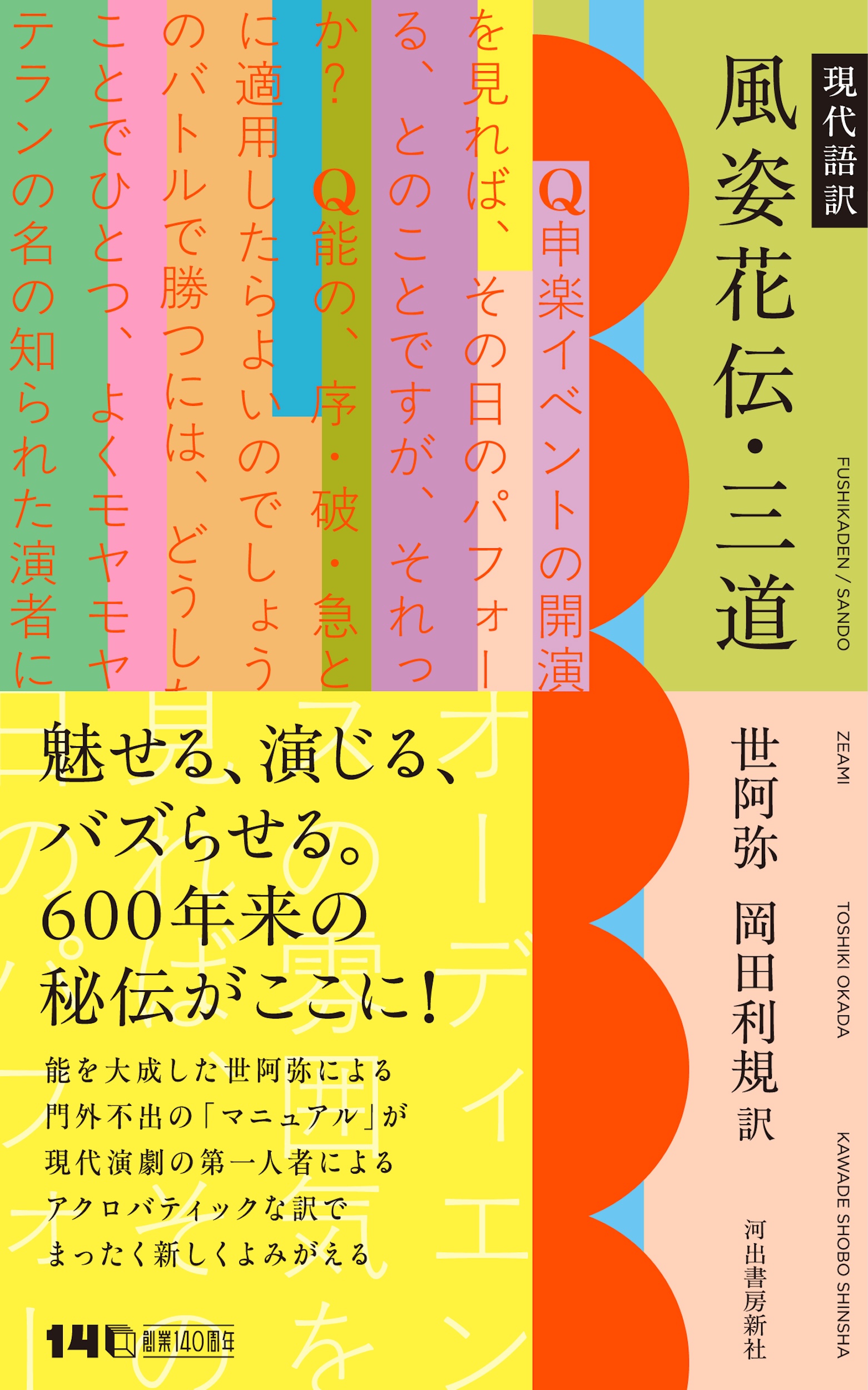ためし読み - 日本文学
実話に基づく敗戦直後のラバウルを舞台とした感動作! 『ラバウルの迷宮』刊行記念 試し読み
鈴木 智
2025.09.02
鈴木智・著
単行本/336ページ
ISBN:978-4-309-03222-1
発売日:2025年8月8日
詳細・購入はこちら
amazonで買う
RakutenBooksで買う
敗戦直後のラバウルに取り残された10万人の日本人捕虜。
元情報将校・霧島に下された密命は、ただ一つ ―― 「禁じられた忠臣蔵を上演せよ」。
暴動の火種がくすぶる舞台に、果たして紙の雪は降るのか。
「手に汗握る反乱劇。映画化を熱望!」
―― 鴻上尚史(作家・演出家)
「異色の舞台と題材、謎を呼ぶストーリー、熱い人間ドラマ。
どれもが面白く、読みどころが多すぎる」
―― 細谷正充(文芸評論家・アンソロジスト)
戦争が終わった時、いかに生きるかの戦いがはじまった。
エンターテインメントで描く〈慟哭〉と〈感動〉の物語。
映画「誰も守ってくれない」(モントリオール国際映画祭 最優秀脚本賞)、「金融腐蝕列島・呪縛」(日本アカデミー賞優秀脚本賞/キネマ旬報最優秀脚本賞)、「青い文学人間失格」(ロッテンダム・フューチャー映画祭グランプリ)、「ローレライ」など数々の作品で脚本を担当してきた鈴木智の小説デビュー作!!
刊行を記念して、手に汗にぎる冒頭部分を公開します。どうぞお楽しみください。
==↓ためし読みはこちらから↓==
第一幕
第九収容所
―― 夜の海に、死者の影が揺れた。
私はあの五〇〇人を救えただろうか?
あるいは、やはりただ見送るだけなのか?
霧島(きりしま)は、その声を振り払うように、重いまぶたを開いた。
夢の中で、遠くで煙が渦を巻いていた。崩れる土壁。密林に飛び散る影。
その印象と現実が混ざった。
天幕の闇に、蚊の羽音がうねり、外では誰かの咳が沈んでいった。空気は生ぬるく、喉が張り付くように渇いている。
額の汗を拭いながら、霧島は静かに上体を起こした。鉄製の水筒を手に取るが中身はすでに空だった。その瞬間、天幕の入口が静かにめくられた。
「起きているか」
引き締まった細身の体に軍服を纏(まと)った男が、冷めた眼差しを向けていた。
「青木中佐からの呼び出しだ。至急、来るように」
低く堅実な口調だった。霧島は無言で頷き、立ち上がると、手製のプレス機に挟んでおいたズボンに手をかけた。
豪軍兵に伴われ、重い足取りで外へと出る。海風が顔を撫で、遠くの海が暗くうねっていた。
収容所の灯りがぼんやりと滲む。ここにいる日本兵たちは皆、明日をも知れぬ身だ。霧島もまた、その一人に過ぎない。
着いたところは司令部の勾留されている施設とあって、有刺鉄線によって囲まれたコンクリートの建物だった。
青木中佐は、木製の扉の向こうで静かに待っていた。
室内は薄暗く、埃と潮の香りの混じった匂いがした。窓から月明かりが差し込んでいた。
青木中佐は霧島を一瞥すると言った。
「相変わらずだな。収容所でズボンにアイロンをかけているのは、君くらいなものだ」
それは、戦前は商社の社員として働いていた霧島の矜持(きょうじ)だった。戦争に染まらず、自分を見失わないための抵抗でもあった。同じように、撫でつけて分けた髪も霧島が軍人らしくないと揶揄(やゆ)される理由になっていた。
青木中佐は、机の上の手書きの地図に指を走らせながら、低く告げた。
「第九収容所に行ってみるか?」
霧島は、なんのことかと言いたげに中佐を見た。
「君は頭のいい男だ。目端が利きすぎると嫌う人間もいるが、君の機転にかけてみようと思ってな」
中佐は視線を霧島の背後の豪軍兵に送った。
豪軍の警備は厳重だったが、日本語を解する兵はほとんどいない。
「第九収容所の永峰(ながみね)中佐から、君を名指しで向こうに回してくれないかと要請が来ている。渉外班の班長だそうだ。永峰中佐は君の元の上官だったな」
「はい……終戦直前まで、情報士官として仕えておりました」
「向こうでは英語を話せる人間が少なくて、豪軍との折衝に支障をきたしているらしい。豪軍側も異動を認めている」
霧島は中佐の真意をはかりかねて、その表情を探るように見た。
「これから始まる極東軍事裁判は数年かかると言われている。その前段階の取り調べも始まったばかりだ。我々司令部の人間は、いずれ戦犯容疑者として長くここに逗留しなければならないだろう」
中佐はいったん、言葉を切って霧島を見た。
「だが、通訳としてここに来てもらった君にその責務はない。この機会に古巣に帰ってみるか? 我々のためにここにいては君も内地に帰れる可能性は薄い。それにあっちの方が君の才能も活かせるはずだ」
「しかし、青木中佐……それではあまりに申し訳ございません」
中佐は含みがあるように霧島の目を見ながらゆっくり首を振ると続けた。
「ただし、ここにきて一つ気がかりがある。暴動計画の不穏な噂があるのだ」
「暴動計画?」
霧島は言葉の意味が飲み込めなくて中佐を見つめた。
「武装解除のおりに何者かが地下要塞のどこかに刀や、砲弾を隠したという情報もあった」
「噂は聞いたことがありますが……戦争は終わっているのに、まさか」
そう言って、霧島はあるいは有り得るか、と思い直した。
本格的な戦闘が行われていないラバウルには、無傷のおよそ一〇万の兵がおり、彼らの中には自分たちは負けていないという想いがくすぶっていた。実際に自分もそうだった。そして、武装は解除されているとはいえ、九つの収容所に分かれて収容されている一〇万の日本人に対して、管理する豪州兵は合計でも五〇〇〇と圧倒的に少ない。
青木中佐はいっそう嗄(しやが)れた声を落とした。
「戦争責任が問われている我々だが、最後の責務が残っている。一〇万の兵を無事日本に送り届けることだ。しかし、もしそんな暴動が起こればそれも無に帰す。なんとしても暴動は止めなくてはならない。君に、暴動計画の兆候を探り、阻止する任務を託したいのだ」
「なぜ私に」
「生き残った意味を知りたい。君がそう思っていることは感じていた」
青木中佐の言葉の重さは、霧島の心に再び深い傷を刻みつける。
一拍、考えたあと霧島は答えた。
「少しでもましなことをしたいと思っていました。行かせてください」
「そうか。君の覚悟が、残されたものたちの支えとなる」
<なぜ保障された場所を捨ててあの地獄に戻る、俺は商社員だぞ?>
もう一人の自分が嗤(わら)った。
私も損な役回りだね―― あの男の囁(ささや)きが蘇った。
「あいつに合わせる顔がないからだ」
そうつぶやく。
月明かりの下、霧島は己の罪に呼び戻されるように、足を進めた。
今から三年と少し前。
昭和一七年の夏、霧島はこのラバウルに着任した。
日本から五〇〇〇キロ。空から見ると、翠玉色の海に浮かぶ細長いブーメランの形の島がニューブリテン島だった。その一角にあるラバウル湾に霧島は目を細めた。
かつてはドイツの植民地だったが、前の戦争で豪州が奪い、今度の戦争で日本が占領した。
軍港には駆逐艦や潜水艦が行き来し、零戦(ゼロセン)部隊が青空をひっきりなしに飛び交っていた。
物資も豊富だった。大きな通りには店が並び、すべてのものが整っていた。陸軍に一〇万、
海軍には三万の兵。それに加えて、医療関係者の女性や商人もいたから休日の通りはにぎわった。喫茶店もデパートもあったし、椰子(やし)の木陰では現地人が果物を敷物の上に並べて売っていた。その様は日本帝国陸海軍の最前線基地に恥じぬものだ。美しい港街を見て霧島も胸の高まりを禁じ得なかった。
しかし、それが一瞬の光芒であったことを霧島はすぐに悟った。
その時すでに、ここから一〇五〇キロの距離にあるガダルカナル島の攻防戦は、行方 (ゆくえ)の見えない消耗戦と化していたのである。
密林の闇が突然途絶えた。
切り拓(ひら)かれた道を土煙を上げてジープは疾走していた。
光を遮るように霧島はその手を目の上にかざした。青さと甘さの入り混じった森の匂いが、潮風にかき消されていく。
隣にいる、迎えに来た通訳の中谷(なかたに)が興味深そうに霧島を見た。
「懐かしいですか。このあたりは」
「密林はどこでも同じだが、最初に着任したのがラバウルだ。日本が一歩近くなったような気がするよ」
中谷はわからんでもない、という風に蔓(つる)の少し曲がった丸眼鏡ごしに微笑んだ。
岬の陰には、沈みかけた米軍戦闘機の残骸が見え、かつてのラバウル航空部隊の栄光をわずかに感じさせる。
ミッドウェー海戦の失敗後、日本軍は常に劣勢に立たされ
霧島はかつて聞いた今村(いまむら)司令官の言葉を思い出した。
「この地を要塞とする」
そう力強く語った司令官の目は、まさに戦場を見据えていた。
第八方面軍の今村均(ひとし)司令官は、太平洋各島に散らばった戦力をすべてラバウル基地に集め、最後の防衛ラインたろうとした。ところが一九年の二月、ずっと後方のトラック島が壊滅的な空襲を受けると、頼みのラバウル航空隊は引き上げてしまい、ラバウルは敵中にあって孤立した。本土からの補給は絶たれ、ラバウルは激しい空襲にさらされた。地上の楽園は焦土と化したのだった。山という山は爆撃によってすべて地獄のようなはげ山へと姿を変えた。
今村均司令官はラバウル基地を地下要塞に変貌させることを急いだ。
蟻の巣のような長いトンネルが掘られ、司令部から居住区、放送局や郵便局、果ては砲台まですべてが地下に引き込まれた。そのトンネルの総長はのべ二五〇キロ。東京から浜松までの距離に匹敵すると言われた。
また、山間(やまあい)の谷や、密林を開拓して畑や農場を作った。化学者たちによって火薬も精製できるようになった。そうして自給自足でそのまま一〇年でも二〇年でも戦える体制を整えたのだった。なんでも自作し、ラバウルで作れないものは赤ん坊だけ、と言われた。
やがて部隊ごとにラバウル各地に山城が作られた。将兵たちの願いは、この地に連合軍を引きつけ決戦に臨むことだ。死して護国の鬼となる……。それがただ一つの彼らの望みだった。
かくして一年半の長きにわたって敵中に一〇万の兵が籠城するという、戦史上類を見ない状況が生まれていた。
しかし、ラバウル攻略は多大な消耗を伴うとみたマッカーサーは、蛙跳(かえると)び 作戦でラバウルを飛び越えて沖縄を急襲した。ラバウルは敵味方の両方から見捨てられたのだった。
昭和二〇年八月、ポツダム宣言を受けて日本は降伏した。
ラバウルにおよそ一〇万の無傷の兵を残したまま。
武装解除のときの情景は、今でも霧島の瞼(まぶた)に焼き付いていた。
山肌のあちこちで爆破による土砂が沸きあがった。地下要塞の入口は日本人自身の手でことごとくダイナマイトで爆破された。
港でも、集積された銃刀や兵器を海に廃棄する作業を日本人が行った。
日本軍の戦車が崖に向かって走っていた。戦車は崖の縁で傾いたかと思うと、大きな水没音とともに飛沫が上がった。
豪軍兵が歓声を上げ、口笛を吹いた。
それをじっと見ている日本兵たちの顔は、皆、失意に打ちひしがれ、あちこちですすり泣きが聞こえた。武装を手放すということはもう戦えないということだ。その頃の日本兵はまさに悲惨で、自殺者も後を絶たなかった。
収容所の設営も日本兵自身の手でやらされた。日本軍はたちまち自分たちの牢である収容所を作り上げた。この第九収容所もそうやって設営された施設の一つである。
門が開いてジープは止まり、霧島と中谷は豪兵に促されて降り立った。
幾重もの有刺鉄線が張りめぐらされた囲みの中の広い敷地である。
四方の角には、自動小銃を設置した見張り楼が立っている。埃が舞い上がり、焼けた砂の匂いが鼻をついた。
正面の奥には椰子の木で組まれた部隊小屋が並んでいた。その周囲には薄汚れた日本人たちの行列ができていた。時々、ハリーアップ、という怒声が響く。
霧島がそれをほろ苦く見ていると、銃を持った豪軍兵士たちが近寄ってきて、霧島の衣
囊(いのう)や雑囊(ざつのう)を調べた。
中谷が人員の異動を記した英文の書類を渡すと、さっさと行け、と顎で命じた。
「集団長の永峰中佐は今の時間、席を外しています。その前に渉外班の部屋を見ますか。ご案内します」
霧島は軽快に前を往(ゆ)く中谷に従った。
所々、自動小銃を持った豪兵が立っていたが、統制を維持するため日本人の軍組織は残されており、将校の行動は比較的自由が許されている。この収容所でもわずか五〇〇人ほどの豪軍の人員で一万人に及ぶ日本人を管理しているので、日本軍の協力は不可欠なのだ。
区画は整然としていたが、同じような小屋が建ち並ぶ様は霧島に軽い目眩(めまい)を起こさせた。
小屋の構造は単純なもので四隅に柱を立て椰子の葉で屋根を葺(ふ)いたものだ。壁は薄く椰子の葉を編んで作られていた。申し訳程度に蝶番(ちょうつがい)で扉がついていた。
常夏のここでは、それで充分だった。室内には裸電球があった。
「電気は近くの川で水力発電してるんですよ。電気技師ができるって言うんで……豪軍との交渉には苦労しました」
中谷は、渉外班の仕事を自慢げに言った。
何度か角を曲がり椰子小屋の一つに着いた。渉外班の事務所だという。
「紹介しておきましょう。あー、集合!」
中谷の掛け声で、霧島の前にのっそりと日本人たちが出てきて整列する。その気だるい空気に、霧島は眉をひそめた。
終戦から間もなく三ヶ月。日本兵たちの意識が緩みきっているのは明らかだった。髪の長さもばらつきがあり、髭面も多かった。それぞれ尾羽うち枯らしたような百舌鳥(もず)色のシャツを着ている。その大きさが違うのは、死期の近い仲間から譲り受けたり、遺体から無断で引き剝がしたりしたからだろう。
「あ、こちらが新しい渉外班長の霧島中尉だ。通訳も兼任する」
霧島が敬礼をすると、男たちもばらばらと手を上げる。
なんとも緩みきっている。軍組織は解かれていないが、末端のここでは規律を引き締めようとする大義も廃(すた)れてきている。整然とした司令部の収容施設から来た霧島には嘆かわしいことばかりだった。
<これが、かつて規律を重んじた日本兵か>
そう思った自分に霧島はさらに舌を打った。霧島は自分はあくまでも商社員であろうとしていたにもかかわらず、軍人としての価値観に知らずのうちに染まっているらしい。
ここには、今や戦意など欠片(かけら)も残っていない。あるのは、ただ生き延びるための疲れ切った本能だけだ。それなら霧島は安堵すればいいものだったが、どこか寂しさを感じる自分がおかしかった。
中谷が班員たちに「名前と所属を」と促した。
「第五中隊砲塔班、佐川上等兵です」
「第三中隊通信隊、尾田二等兵です……」そのように一人ずつ声を上げた。
丸顔の中年男が言った。「所属不詳、浦島太郎です」
最後の一人、貧相な小男が続いた。「同じく桃太郎です」
「ふざけてるのか」
霧島は呆れて中谷の顔を見る。
「どうしても隊の所属と名前を言わないんです。一定数そういう兵隊がいるんです」
中谷によると、戦中の行いや、自分が虜囚になっていることを隠したくて偽名を使う兵隊が少なくない、ということだった。
「いじめをしていた兵隊とか。戦争が終わって、昔の部下に復讐されることもありましてね」
それで身を隠し別の隊に紛れる必要があったのだ。
見回すと小屋の中には、まだ男の影があった。霧島はそっちに足を向けた。
「あ、霧島さん?」
中谷が慌てて追いかける。
奥の壁には人員表や、工事の計画表、豪軍の組織表などが貼ってあった。
卓の陰で男が道具で必死に缶詰を開けていた。霧島が缶詰を取り上げる。
「ああー、何すんだよ」男が叫んだ。
缶詰のラベルは英語である。M&V。肉と野菜の缶詰だった。
「なんでこんなものが」
中谷が飛んできて小声で囁く。
「泥棒ですよ。豪軍倉庫から。我々は自給自足でやっております。でもそれだけじゃ、どうにも足りないんです」
「食事を与えないのは国際条約違反だろう。なぜ待遇の改善を要求しない」
「え? そのために霧島さんがいらしたんじゃ」
「どうなっとるんだ。名前は?」
霧島は目の前の卑屈そうな目の男に聞いた。
「鼠小僧(ねずみこぞう)です」
「おい、いいかげんにしろ」
「そう固いこと言いなさんなよ」
声がした。霧島が顔を上げると、部屋の奥の長椅子で寝ていたのか、一人の男が起き上がってこちらを見ていた。無精髭を生やした口元には皮肉めいた笑みが浮かんでいる。
「霧島中尉だな?」
「ああ、そうだ」
中谷がすかさず耳元で告げる。
「渉外班長の先任の長谷川大尉です。元陸軍中野学校出身で」
陸軍中野学校といえば言わずと知れた陸軍のスパイ養成学校だ。
大尉と聞いて「これは失礼。霧島中尉です」と霧島は敬礼をした。男も敬礼で返す。
「長谷川一夫大尉だ」
「は? 俳優の」
「同姓同名だよ。歓迎するよ。我が第九収容所、渉外班へようこそ。小汚(こぎた)ねぇところだがな」
長谷川は立ち上がり、軽く手を広げてみせた。
「先に言っておくがな、ここのルールは簡単だ。『豪軍には逆らうな』」
「……知っています」
「そりゃ結構。命が惜しいなら、それを肝に銘じておくことだ」
長谷川は口角を上げると、椅子を指さした。
「まぁ座れ。色々教えてやるよ」
霧島は少し迷ったが、促されるまま椰子材の椅子に腰を下ろした。
長谷川は卓の上の紙切れを手にとって、それを指で軽く叩く。
「ここの渉外班の仕事は、豪軍との折衝と報告書作りだ。連中の言うことを聞いて、こちらが“おとなしくしている”ことを確認できりゃ、それで十分」
「なるほど」
「それから ―― 」
長谷川は面倒くさそうに肩をすくめた。
「俺は英語がダメだ。読めるが、聞くのはさっぱりでね」
「……英語がダメ?」
「そうよ。豪軍の連中は、妙な訛(なま)りの英語をしゃべるだろ? 特にヤング少尉なんて、何を言ってるのか半分もわからん」
そう言って中谷に同意を求める。中谷は曖昧に笑った。
「ま、中野学校の英語教育なんてそんなもんだ。だから渉外班長は解任してもらったんだ。お前には期待してる。通訳兼、渉外班長殿としてな」
長谷川は薄く笑いながら、霧島の肩を軽く叩いた。
霧島はその軽薄さに違和感を覚えた。
< ―― 本当に、それだけか?>
豪軍との交渉を担う人間が、「英語がわからない」と堂々と言ってのけるのか?
単なる冗談か、それとも……何かを隠しているのか。
長谷川大尉は、身を乗り出してじっと霧島の顔を見つめると、口の端を上げて言った。
「頼りにしてるぜ、相棒。お前が使えることは永峰さんのお墨付きらしい……まぁ、こっちは楽な仕事がいいんでね、お前が頑張ってくれると助かるよ」
この男、口元は緩むが目の奥は笑っていなかった。
霧島は少しの間、沈黙したあと、静かに頷いた。スパイを養成する陸軍中野学校の出身。それを隠そうともしないし、それに合わせて有名俳優と同姓同名というのも胡散臭(うさんくさ)い。ひょっとしたら名前も階級も陸軍中野学校出身というのも偽証か。油断ならぬ男に見えた。
「そろそろ永峰集団長がお戻りになる頃です」
中谷が言った。
斜陽が、その部屋の扉に斑(まだら)の陰影を与えていた。
集団長室は、他の部隊部屋と同じような椰子小屋だった。
「霧島中尉です。先程到着しました。入ります」
「開いている」
中から聞き覚えのある低い声が響いた。
椰子の扉を開けると分厚い背中と影を帯びた耳が見えた。親しげに振り返る。
「よく来たな。霧島」
永峰中佐はナイフとフォークを使って食事をしていた。永峰の巨大な目と太い眉は包み込むように微笑んでいた。半年前に比べて少し太ったようにも見える。霧島は緊張して敬礼すると、持ってきた異動命令書を永峰に渡した。
永峰はそれを開いて確認し、引き出しにしまった。卓の上の皿を見ると、永峰が食べているのは炒めた蝸牛(かたつむり)である。霧島の視線に気づいて永峰が言った。
「これか? 戦中に密林に放ったものが繁殖していてな。蛋白質の補給だ」
苦笑いする永峰の言葉には少し寂寥(せきりょう)があった。
「そんなものを食べなくとも。豪軍に、食事の改善を要求するつもりですが」
「豪軍の食は受けぬ。我々が率先して自給自足せねば、兵たちに示しがつかんじゃないか。戦中の備えが今役に立つとはな」
「は、確かに」
永峰はフォークで蝸牛を刺し通すと、美味そうに口に放り込み嚙みしめて笑った。
それはかつて霧島が敬愛していた永峰連隊長に違いなかった。
ラバウル地下要塞の提唱者の一人。つねに威厳とともにあったが、いつでも最前線にその姿を晒(さら)していた。農作業においても永峰が率先して毎日、鍬(くわ)や鋤(すき)を振るっている姿を多くの将兵が目にしていた。
「そうは言っても、心配するな。時々、こういうものも食べている」
永峰は机の引き出しを開ける。銀色の缶が見えた。取り出したのは、豪軍のソーセージの缶詰である。
「あ」霧島が戸惑っている間もなく永峰は言った。
「君を呼んだのは他でもない。渉外班長として一〇万の兵たちを一刻も早く、内地に帰還させる方法を考えてもらいたい。待遇の改善も必要だ」
「しかし、先程、長谷川大尉に会いました。あの方を解任してまで……」
永峰は手を後ろに組んで少し考えると言った。
「あの男は腹の底が見えないところがあってな。会ってわかったはずだ」
霧島は、曖昧にうなずくしかなかった。
「軍は残っていると言っても、かつての規律を強制することもできん。貴様のような、気心の知れた男が必要なんだ」
永峰は、ここでの作業は人員を二班に分け、半分は豪軍の要請でキャンプの作業援助に出向かせている、と言う。残る半分は、収容所での留守番だったが、自活のための農作業に従事していた。
豪軍キャンプ組の仕事は宿舎の設営から、皿洗いなどあらゆる作業があった。
永峰は嘆息すると言った。
「最近もコンテナに乗せられて移動するさい、運転している豪軍兵が、急にハンドルを切ってコンテナが横転してな。多くの負傷者を出した。復讐のつもりだろう」
元日本兵たちは、ささいなことで豪州兵に怒鳴られ、尻を蹴飛ばされ、場合によっては足元に自動小銃の弾をばらまかれた。
永峰は、自分の耳たぶをひっぱりながらしみじみとつぶやいた。
「これが負けたということだ……」
霧島はかつての兵たちの姿を思い浮かべる。一人十殺を誓い、決戦に備えていた頃の彼らを。だが今、その誓いは秋の風鈴のように遠くで虚しく響いた。
司令部の施設と違い、ここに来て実情を見聞きするにつれ、亡国の兵たちの悲哀が霧島の胸に実感として染み込んできた。
「集団には目的が必要だ。個々の生きる目標がな」
「目標とは」
「たとえば討ち入りだ」
「討ち入り?」
霧島の額(ひたい)がひりついた。眉をひそめて次の言葉を待つ。
永峰はその顔を見て頰を崩した。
「勘違いするな。ここで兵たちの気持ちを鼓舞する、芝居をやったらどうかと思っとるんだ」
霧島は、気が抜けて復唱する。
「芝居……ですか」
「ああ。忠臣蔵をやりたい、と兵たちからの要望があってな。なかなかよい提案だと思った。
それを豪軍と交渉してもらいたい」
「豪軍にその申請は」
「まだだ」
「さすがに難しいと思いますが」思わずそう答える。
戦って死ぬことだけが目標だった兵士たちに、新たな目標は必要だろう。しかし、それが忠臣蔵の芝居の上演というのは、あまりにもかけ離れてはいないか。忠臣蔵といえば忠義と復讐の物語だ。主君が理不尽な切腹をさせられ、四七人の家臣たちが、苦節を経て復讐を果たし、そのあげく、全員自決する話だ。収容所でそのような血なまぐさい、復讐を煽(あお)るような芝居を上演することに豪軍の許可が下りるだろうか。到底無理だ、と言う声が霧島の脳裏をかすめた。
永峰の怒声が飛んだ。
「難しい? 貴様、戦中のラバウル魂を忘れたのか」
霧島は無意識に背筋を正した。
「なぜ忠臣蔵なのですか?」
霧島は思わず問い返した。
永峰は、しばし黙った。
南方の午後の光が、窓辺に影を落としていた。
永峰の目の奥がわずかに光る。
「ただの復讐劇ではない。忠義とは何か。敗者に誇りはあるのか。その答えを俺はずっと考えている」
「しかし」
「我が第八方面軍に不可能はない。ラバウルでできないものは、赤ん坊だけだぞ」
永峰は笑いかける。霧島も合わせて笑うが、その笑みはすぐ消えた。
物質的な不足を、精神性で補おうとする不合理でこの戦争は負けたのではなかったか。
霧島がそう思っていると永峰は続けた。
「芝居用のカツラだがな。農耕馬が八〇頭いるから、そのしっぽを切らせる。衣装は、病棟の白衣をすべて供出させよう。パラシュートも相当数残してある。あれは絹だからな。いい着物になるだろう」
「豪軍が許可するはずは」
永峰は霧島を咎(とが)めるように見ると語気を強めた。
「単に通訳のために貴様を呼んだわけではないぞ。貴様の交渉能力を高く評価して、重大な任務にあたらせるためだ。内地では、GHQによって忠臣蔵の上演は禁止されているという」
「それはおそらく日本人の暴動などを恐れて……」
「だからやる意味があるのだ。最後の忠臣蔵だ。日本人の魂を見せてやれ」
「はっ」霧島は勢いに巻かれて敬礼した。
霧島は一番、知りたかったことを声に出した。
「……連隊長、青木参謀はここで妙な噂があると心配していました ―― 」
「妙な噂?」
その時、背後から声がした。
「霧島、霧島じゃないか」
振り向くと、入口に革の航空頭巾の男の影があった。
片足を引きずり気味に前に出てくる。窓からの光で左手の石膏(せっこう)ギプスと、傷だらけの顔が浮かび上がった。さすがに暑いのか耳覆いを跳ね上げている。
「あ、伍堂(ごどう)? 無事だったか」
「おお、この怪我だ。まあ、無事ってことはないがね。貴様も元気そうだな」
「海軍のいる、第一収容所に行ったと聞いたが」
「ああ、実家は千葉の農家だ。新たな畑作りのために永峰連隊長に呼び戻されたのよ」
左手首のギプスを掲げて敬礼してみせる。笑うと頰の傷が歪んだ。
伍堂は、海軍の戦闘機部隊の一員としてジャワ攻略作戦では、大きな成果を挙げた。しかしラバウルに着任した頃には、もうラバウル航空隊は、壊滅に近かった。
噂によると、ここでの伍堂の戦法は、足の速い偵察機を使い空中で体当たりするというものであった。戦闘機がなかったから編み出された独創的な戦法と言えた。伍堂は、それを「敵に嚙みつく」と表現した。敵の戦闘機の尾翼や、片羽根をプロペラで削って何度も道連れにしたのだ。伍堂は異常な反射神経の持ち主で、パラシュートでの脱出が巧かった。それによって四回墜落して、四回とも生還していたのだった。
伍堂の噂は、終戦間近に司令部に異動した霧島も耳にしていた。
「最後の体当たりの話は聞いた。ウチに一機だけ残っていた偵察機でやってくれたそうだな」
「ああ、始末したよ。おかげでこのザマだ」
伍堂は自嘲するように笑ってギプスを振った。
ギプスを取らないのは、その方が都合がいいことがあるのだろう、と想像した。
永峰は「今はこの伍堂に畑の管理や、食料、物資の調達を任せている」と言った。
「百姓に戻るしかねえんだ。俺はこの恰好(かっこう)だから働かんがね。もっぱら指導教官だ」
伍堂は洋画の俳優のように片目をつぶってみせた。
「しかし、お前は変わらんな。三日三晩寝ずに作戦を練ってたときと同じ顔してる」
「……あれは、あんたが俺を巻き込んだからだろ」
霧島は、地下要塞の作戦室での議論を思い出した。
「言い訳するな。お前も楽しそうだったじゃないか」
「ふざけるな。あのせいで俺は、上官に散々怒られたんだ」
「だが、結果は出した」
永峰が二人を交互に見た。
「今後、忠臣蔵の実現にあたって二人で協力してほしい」
伍堂は笑って言った。
「畑はともかく、物資の調達は貴様の方が得意そうだな。少し集団長と話があるが、貴様との積もる話もある。今度ラバウル獨酒(どぶろく)で一杯やろう。秘匿(かく)していたやつがあるんだよ」
「いいな。それは」
霧島は、伍堂が酒を飲んで出撃し、相手を落として帰ってきた武勇伝を聞いたことがあった。
永峰の目が用事は済んだと言っている。
敬礼して出ていこうとする霧島の背後から、永峰の言葉が飛んだ。
「ああ、待て。まず、ひと月後をめどに劇場の図面を提出せよ」
霧島は、違和感を覚えて立ち止まり、振り返って永峰を見た。
どうやら、日本人の一部はすでに忠臣蔵の芝居をやる方向で動いているらしい。
永峰は相変わらず柔らかい表情で微笑んでいた。そして、尖(とが)った眼の端でこっちを見ている伍堂を部屋に引き入れると扉を閉めた。
中谷が眼鏡の蔓を修理しながら、外の縁台で待っていた。
「霧島さん。何か言われました?」
「ああ。ここで芝居をやれってよ。忠臣蔵だ」
「忠臣蔵。すばらしいじゃないですか」
中谷は、眼鏡を外していると色白でなかなかの美男だった。まじまじと見ている霧島に恥ずかしくなったのか、中谷は丸眼鏡をかけた。蔓が傾いており、滑稽味が戻った。
霧島は意識を戻し呟いた。
「豪軍が許可するわけがない。もしどさくさに紛れ暴動にでもなったら……」
これが暴動の噂の出どころなのか? 忠臣蔵で兵たちの士気を取り戻すというのは、わからんでもなかったが、その裏に不穏な動機があるとしたら ――
「暴動ですか? どういうことです?」
思わず漏らした言葉に、目ざとく中谷は絡んできた。
「あなたが司令部から、何か特命を受けてきているんじゃないかと思っている人間もいます。
それと引き換えに内地に帰る機会をって。どうせここじゃ、無理ですがね。本当のこと、言ってくださいよ。同じ渉外班なんですから」
「いや……」
霧島はここに来た目的を、容易に話すわけにはいかなかった。中谷がその計画に参加していないとも限らないのだ。全員がすでにそのために動いているかもしれない。敵中に一人飛び込んだようなものだ。戦前にバンコクの名も無い村に飛び込んで、米の買い取りを交渉したことがあった。あのときと同じだった。誰も頼りにできない。しかし、一人ではどうにもならない。
「いいです。言いたくないなら」
霧島は、拗(す)ねたような表情をする中谷の目をじっと見た。この男は信用できるのか。
「なんです」と中谷は、目を逸らす。それをどう判断したらいいのか。
霧島は意を決して口を開いた。
「暴動計画の噂を聞いたことは?」
「いえ」あっけらかんと中谷は言い返す。これが噓ならたいした役者だ。
「忠臣蔵の話の裏で、暴動計画が動いているようなことはないか」
「まさか……何も起こらないと思いますよ。皆、そんな意気地はないですよ」
「ただの噂ならいいが」
「そんなにご心配なら、私もあちこち聞いてみます」
中谷の目は好奇心で笑っていた。
「ああ、そうしてくれ。集団長は、忠臣蔵の上演の話は兵隊から出たものだと言っていたが」
「それならたぶん、神崎(かんざき)さんが言い出したことです」
「神崎?」
「元新国劇の役者ですよ、会ってみますか。今ならまだ食事時です」
暴動計画をあぶり出すために動いてみるか、そう霧島は思った。
集団の厨房になっている小屋が二〇棟ほど並んで煙を上げていた。
その前にも卓が並び食事ができる広場になっており、所々銃を持った豪兵が立っていた。
中谷に案内されて、その一つに霧島がやって来ると、広場の一角で怒声が聞こえた。日本人たちがそこに集まって黒い人垣ができている。
「なんでしょう?」その人垣をかき分けるように中谷と霧島は前に出た。
奥では一人の若い兵隊が、興奮した面持ちで包丁を持って振り回していた。
まだ少年の面影があったが、痩せこけ、飢えた目をした男だった。
「近寄るな」と叫ぶと先の尖った包丁を周囲に向ける。周囲の兵隊たちは、どうすることもできない。手ぬぐいの頰被(ほっかぶ)りをした厨房係が右往左往しているところから見ると、料理で使う包丁を奪ったようだ。
とりなす男たちが遠ざかると、若い男は包丁の切っ先を自分に向け、喉を突こうとする。
だが簡単にできないらしく一瞬、躊躇(ちゅうちょ)した。
自決騒ぎは戦場ではめずらしくない。時々、重圧に耐えられず気がおかしくなる者が出てくるのだ。霧島が止めに出ようとすると、それより先に「やめときなさいよ」と一人の男が囲みから前に出てきた。
歳は三〇を過ぎたくらいで、小太りだが力ある目は歌舞伎役者を思わせる。自作らしい扇子で大きな顔にたかる蠅(はえ)を追っていた。
若い男の声が上ずった。
「死なせてくださいっ」
その小太りの男は若い男を扇子で指しながら言った。
「ああ、どうせ死ぬなら切腹にしろ。一度しかできねえんだ、ぜひ切腹にしようや。その方が男らしいに決まっている」
慌てて駆け寄ってきた豪兵たちに、その男は「アイムゾウリ。ドントオリ、イツ、ショウタイム」などと奇妙な英語で声をかける。どうやら人気者のようで、豪兵たちは、笑みさえ浮かべ、銃を構えたまま立ち止まった。
その男は若い男の前に座った。
「あ、あれが神崎さんです」と中谷は、霧島に囁いた。
「ほら、そうしろ、な、皆が見ている」
若い男は憮然(ぶぜん)とするが、感じるものがあったのか、包丁を持ったままひざまずいた。
汗ばんだシャツの前を開く。へこんだ腹を撫でると、意を決したように包丁を振り上げて腹を突こうとする。
「ああ! 待て。切腹の作法はそうじゃねぇ」
神崎は太い眉の片方を吊り上げて言った。若い男は躊躇する。
「いいか、よく見てろ。真ん中じゃねえ、まず左からだ」
周囲も何が始まるのかと息を吞む。
どうやら、腹の斬り方を指南するらしく、扇子をぱたりと畳んで刀に見立てた。
背筋をピンと伸ばし、右手に持った扇子の先を自分の腹に向ける。
「こう、まず刀を左腹部に突き立てて、右のほうへ引きながら回す。ここで、たいがいは失禁しちまうが……まあ、耐えなさい」
精悍な若い男の顔面が心なしか赤くなる。
「ああ。切腹を勧められちゃ困ります。止めましょう」
中谷が、割って入ろうとするが、霧島は「待て。見届けよう」と押さえた。芝居がかった様子が滑稽だった。
神崎は、若い男の顔を見据えて言った。
「ここからだ、微妙なのは。いったんこれを抜いて取り直し、胸下みぞおちを刺して、心臓を貫く。ぐいっと……あう……でえぇ…うううあぁ」
神崎は顔の筋を震わせた。
「ほら。やってみな。みっともねぇハラキリだと豪軍さんに笑われるぜ。さあ。ぐいっといこう」
若い男はいらだち包丁を取り直すが、気勢を削がれて腹に差し込めない。全身の力が抜けて嗚咽(おえつ)を漏らし崩れ落ちた。
「馬鹿野郎っ。今のは芝居用だ。実際はそんな恰好よくいきやしねぇ」
周囲の兵たちから、ため息が聞こえた。
「お前さん、いい顔しているじゃねえか。体もいいな」
若い男の肩から胸のあたりに手を差し込む。若い男はその手を払い除(の)けた。
「おお、その元気がありゃあ、大丈夫だ。悲しいふりをするな。戦争は終わったんだ。お前も、もっと喜べ。これで芝居ができるぜ」
神崎は包丁を持って立ち上がり、取り巻く兵隊たちの顔を見回した。
「あたしはね、こう、たくさんの人間を見ると、皆観客に見えていけねぇ。どうだい、あたしと一緒に、芝居をやろうじゃねえか。切腹は芝居が一番よ」
周囲に笑いが起こった。
騒ぎを聞いたのか、ギプスに航空頭巾の男が人垣をくぐって前に出てきた。伍堂だった。
「なんの騒ぎだ、皆、作業にもどれ」
伍堂が叫ぶと周囲の男たちは、散り散りになっていく。
実戦経験もある空の暴れん坊は、兵たちに睨(にら)みが利いているようだ。ギプスはその効果もあるのだろう。何より目立った。
霧島の周囲の兵たちに「あれが当たり屋の伍堂中尉だ」と囁きが漏れた。
伍堂は若い男を見下ろすと、「集団長室で話を聞こう、来い」と告げた。
若い男は力なく立ち上がると伍堂に従った。
「あの若い男は?」
霧島の問いに中谷が答えた。
「たしかあいつは、最近、豪軍キャンプからここに来た男です……確か秋草(あきくさ)といったかな……大きな声では言えませんが、ゼングルの生き残りのようです」
ゼングル ―― 。その言葉が霧島の胸に深く突き刺さった。
胃の底から苦い思いが湧き上がる。
「ゼングルの戦場に生き残りがいるのか」
―― まだ記憶に新しい今年の三月。
このラバウルから出発した五〇〇人の大隊が、ゼングルという要衝の地で総員玉砕した。
最後の通信は霧島が受けていた。もう少しうまくやれば止めることができたのではなかったか。思い起こすたびにそう自問した。
その一方で五〇〇人の玉砕、と言われているが五〇〇人の部隊がいっせいに一人残らず死ぬことなどできるのか? というのが、霧島のかすかな違和感の一つだった。
しかしゼングルのことは、司令部では誰も語ろうとはしない。生き残りがいるとしても霧島の罪悪感が軽くなるわけではなかったが、もしそうなら少しは救いがあるのも事実だ。
中谷は声を落とした。
「あの男は部隊から離れ気絶していたところを……豪軍の捕虜になっていたんです」
「捕虜?」
日本兵に捕虜は存在しないことになっている。
「ええ……恥ずべきことです……それで死にたくなったのかも知れませんね」
この収容所にいる日本人は、捕虜と規定されてはいない。『武装解除された日本人』と呼ばれている。それがわずかにここにいる彼らを支えていた。
豪軍の兵士たちは、遠巻きに見ていたが、また退屈そうに、それぞれの持場に戻っていった。見世物に飢えているようにも見えた。
神崎は、気分よさそうに浪曲の鼻歌を歌っていた。
大股で収容所の端までやってくると、付いてくる霧島と中谷を振り返った。擦り切れた兵隊帽のつばをくいと持ち上げる。
「どうです? あたしの喉。内地じゃなかなか聞けませんよ。あたしの歌は」
そう言って太い眉の片方を持ち上げてみせた。中谷と霧島は顔を見合わせる。
「有名なのか、こいつ」
「さあ。元新国劇の役者だとしか」
霧島は単刀直入に聞いてみる。
「永峰連隊長に芝居をやりたいって進言したのは君らしいな」
「へへへっ。あそこです」
神崎が指さすところに収容所と隣接した広い空き地がある。
「いいですか、あのあたりに、五〇〇〇人ほどを収容できるような、立派な劇場を作るんで」
神崎はそこを見渡しながら言った。
「二〇回公演すれば、全収容所の人間がほぼ観られる計算です。さっきの見たでしょう。退屈している豪軍を招待してもいい、きっと成功させます」
「ほう。それはずいぶん大風呂敷だな」
「陸軍式で」
「それで負けた」
「今度は勝ちます」
「しかし、この状況でどうやってやるつもりだ」
「いいですか? ここラバウルにいる一〇万人の男たちの中には、ありとあらゆる本職の職人たちがいるんですよっ!」
神崎は高揚して言い募る。
「大工、家具職人、音楽家に殺陣師(たてし)ね、染物師に、床山に、洋裁屋、画家もいます。どうです。最高の舞台が作れますよっ。そうだ、映画の助監督もいますよ」
「なるほど。軍隊を劇団に変える作戦か。面白い」
霧島は呆れて言ったが、神崎はそれを気にする風もない。
「霧島中尉のことは存じ上げてますよ。ラバウル基地随一の情報将校と言われています」
神崎は、扇子を霧島に向けた。
「それを見込んであなたには制作運営、及び豪軍との折衝調整をお願いしたい。うん、あなたならうってつけだ。これができるのはラバウルでもあなたしかいないでしょう」
どうやら人を持ち上げる幇間(ほうかん)芝居にも長(た)けているらしい。霧島はやれやれと思いながら、額の髪をかきあげた。
「あまり乗り気じゃないようですね。必要な物資の調達は元海軍の伍堂さんがやってくれるはずです」
「伍堂なら知っている。さっき集団長室で話した」
「それなら話は早い。あたしはまず役者の勧誘から始めます。なんてったって忠臣蔵だ。数を揃えないとね」
神崎は、独り合点したように擦り切れた兵隊帽を被り直すと踵(きびす)を返す。
「どうです。裏がありそうですか」
中谷が小声で聞いてくる。
「陰謀を巡らせているようには見えない。単なる役者馬鹿だ」
本気で忠臣蔵をやろうと思っている男はいるらしい。
神崎の大股の後ろ姿に浪曲が小さくなっていった。
「霧島さん、もう一人、引き合わせたい男がいるんですが」
警戒心がもたげ、霧島は中谷の顔を改めて見た。自分は無邪気そうなこの男に転がされているのかもしれない、と思った。
消毒液と湿布の匂いが霧島の鼻をついた。
病棟とはいえ、数十の急拵(きゅうごしら)えの寝台が並べられているだけだった。そこに、痩せこけた日本人たちが横になっている。
中谷に導かれて、霧島は一つの寝台の側に立った。
気だるそうに起き上がった男は、目だけの生き物に見えた。骨と皮ばかりの頰、熱気を帯びた目だけが飛び出して死にかかった野生動物のように光っていた。
「私の砲撃班の同期で沢井(さわい)と言います」
中谷は囁くと、中腰になって男に話しかける。
「わかるか? こちらは前に話した霧島さんだ。今日着任した」
その男はかすかに頷くと、起き上がろうとした。
中谷が支える。骨のようになった腕を持ち上げ震えながら敬礼するので、霧島も敬礼で返した。少し離れた場所で患者を診察していた軍医の岩田(いわた)が声をあげた。
「おい、その患者はマラリアだ。あまり近づくとうつるぞ」
マラリアは熱帯の蚊によって媒介される感染症だ。
密林での戦いは、飢えとともにこのマラリアとの戦いでもあった。
感染すると激しい嘔吐が襲い、意識障害に陥る。多くの日本兵が、飢えにさらされた上にこのマラリアに感染して体力が削られ死んでいった。ガダルカナルでの戦いでは実際の戦闘で死んだ人間より、マラリアにやられた兵の方が多いと言われていた。
マラリアが、人から人にうつらないことは知られている。うつるというのは口の悪い軍医の冗談だったが、どっちにしても霧島はそこに留まるしかなかった。沢井が骨ばった指で必死に枕の横の画帳を開こうとしていたのだ。躊躇している間に腕を摑まれた。
「こ、これ……」
と、画帳の一面を見せる。霧島は、沢井の迫力に押され目を走らせるが、そこに描かれているものにたちまち視線を奪われた。
丸太作りの本格的な野外劇場のデザイン画である。内部は広い舞台で奥行きもある。半円形に席が広がっていた。まだスケッチだが密林の木立をうまく利用した構造が判る。
中谷が丸眼鏡の縁を持って焦点を合わせながら問う。
「本当に、これが作れるのか?」
「兵隊の作る劇場や……要塞みたいな……立派なのができます。実験済みや」
「実験済み?」
霧島の問いに中谷が答えた。
「沢井はこう見えても上野の美学校の出身です。建築が専門ですが、戦前は才能を買われてニューヨークに留学をしたこともあって。彼は、こういう才能があったんで、戦時中は幹部の家ばかり作らされたそうです」
沢井の紙のように薄くなった唇に深い屈辱が浮かんだ。
戦時中に軍の幹部が、密林から切り出した材木で部下に自分の豪邸を作らせていたという話は霧島も聞いており、常々、苦々しく思っていた。上野の美学校を出た建築家の卵に設計させていたとすれば、才能の大いなる無駄遣いと言えた。
「上の人の別荘をたくさん作りました。ほんじゃが……そんなことのために、生まれてきたわけじゃない……」
震える声で沢井は呟いた。
***
続きは単行本『ラバウルの迷宮』にてお楽しみください