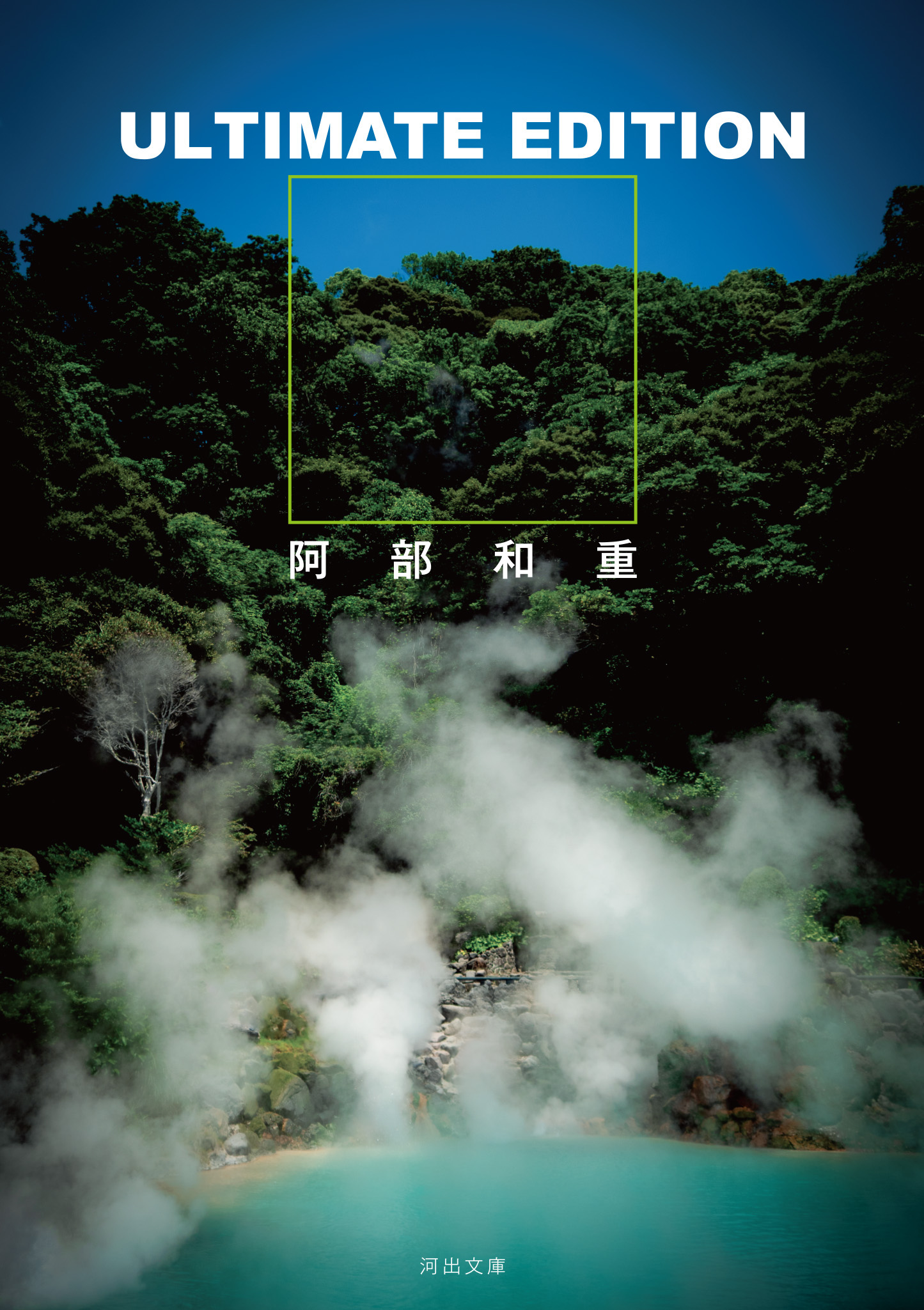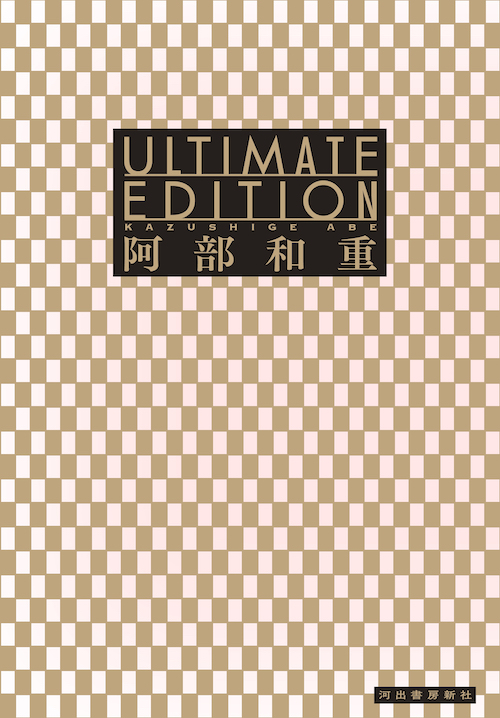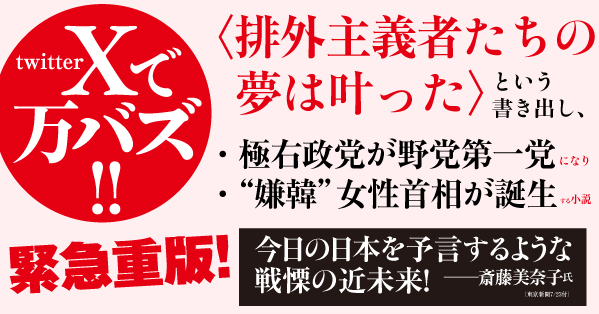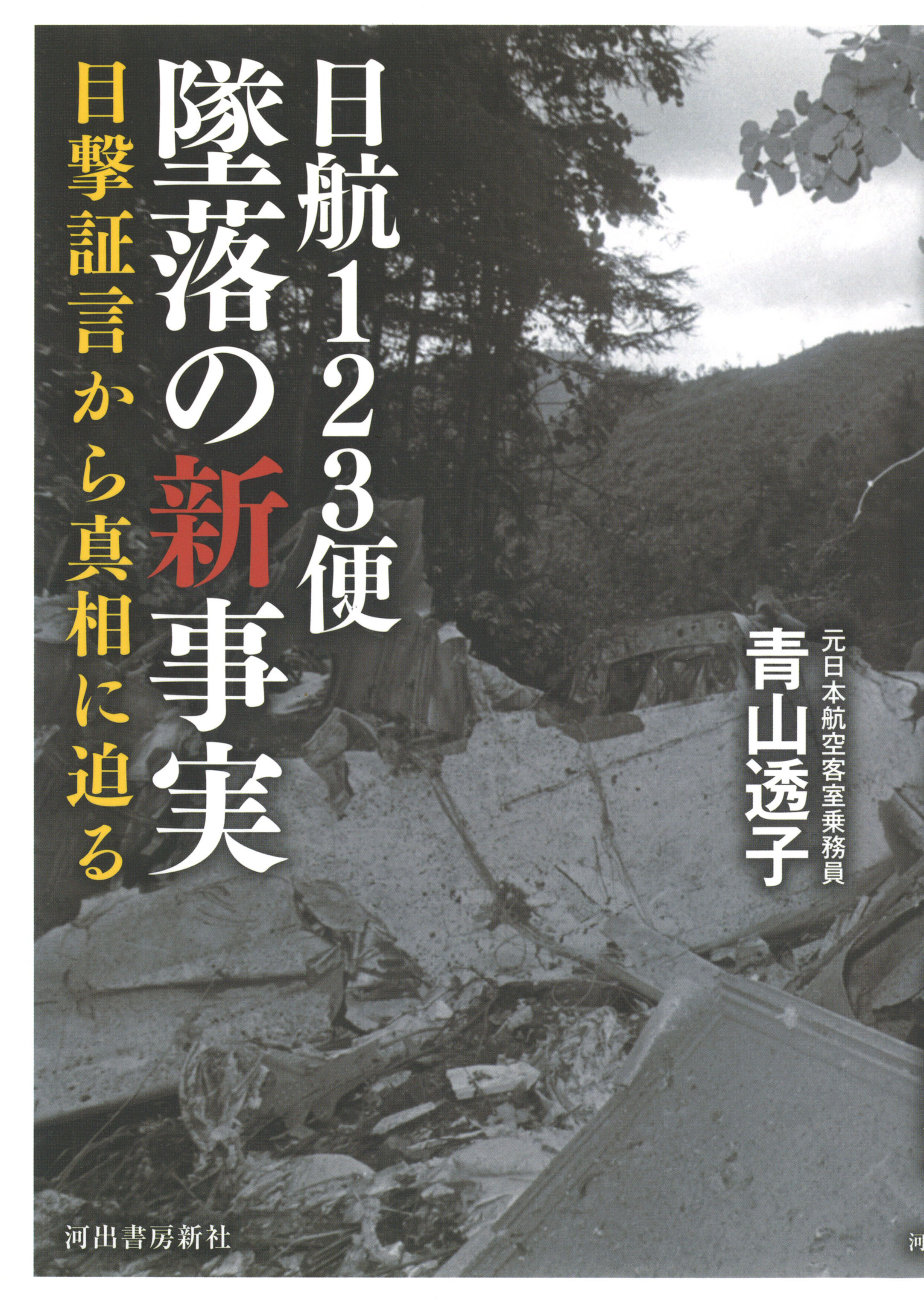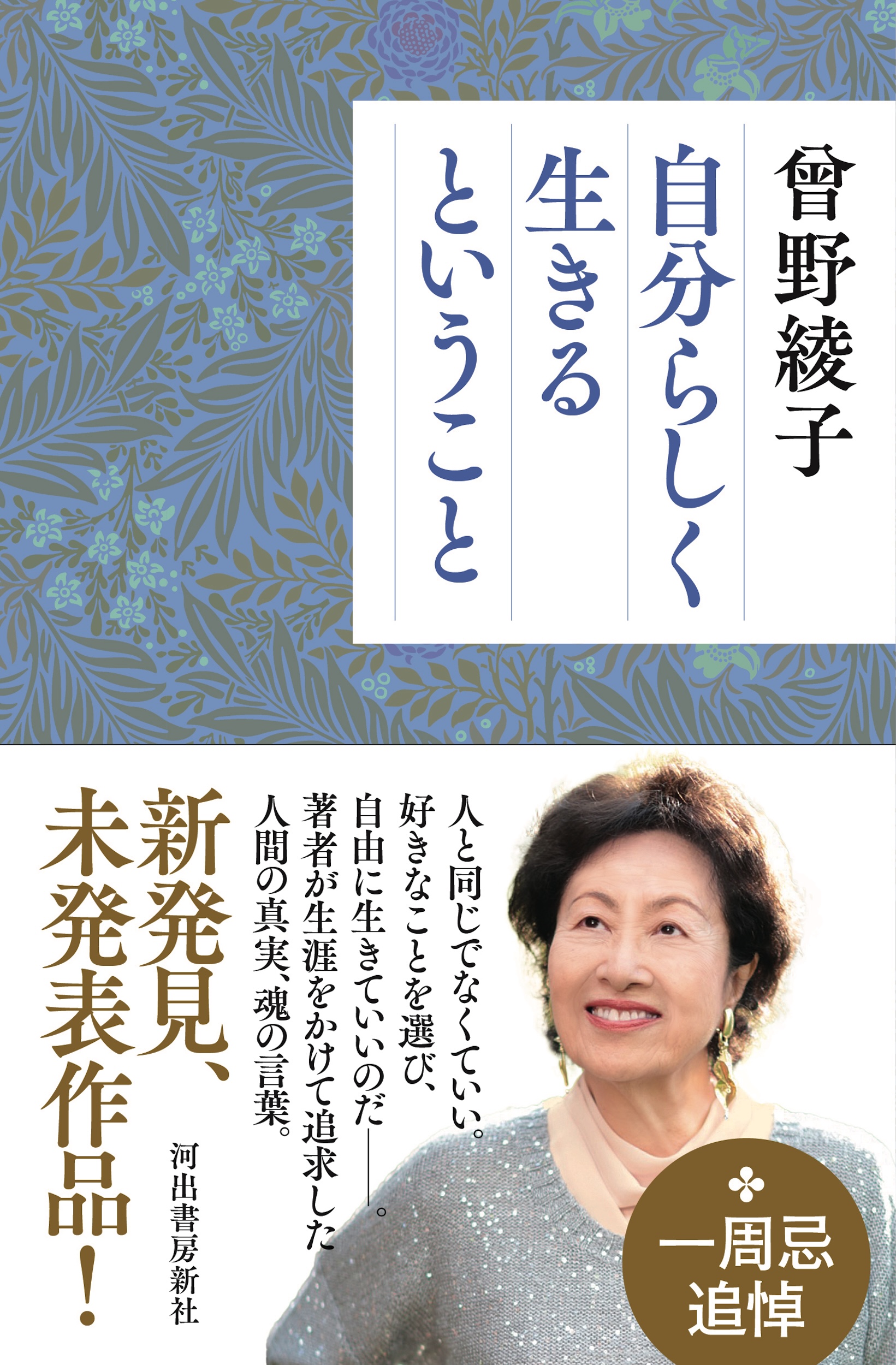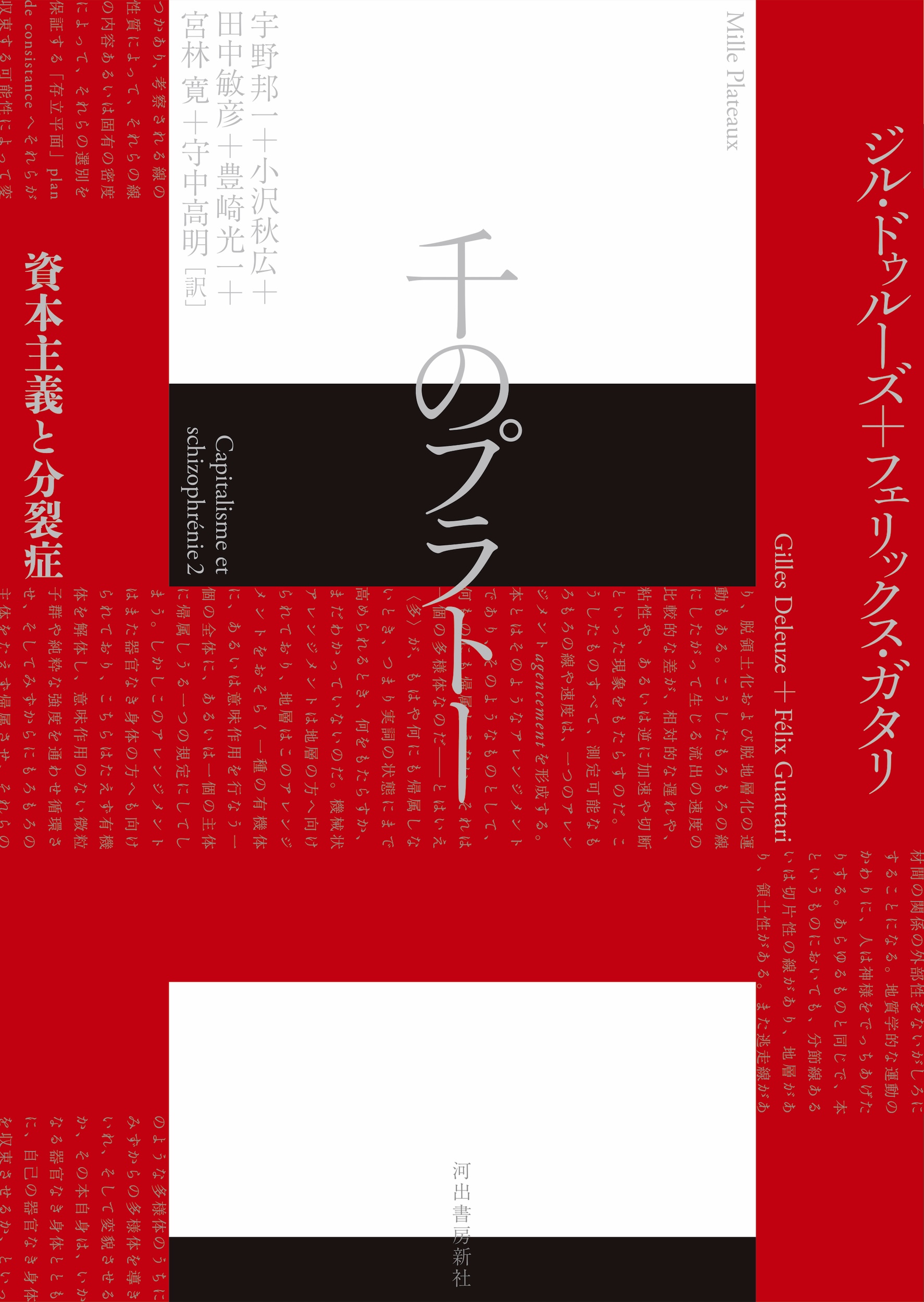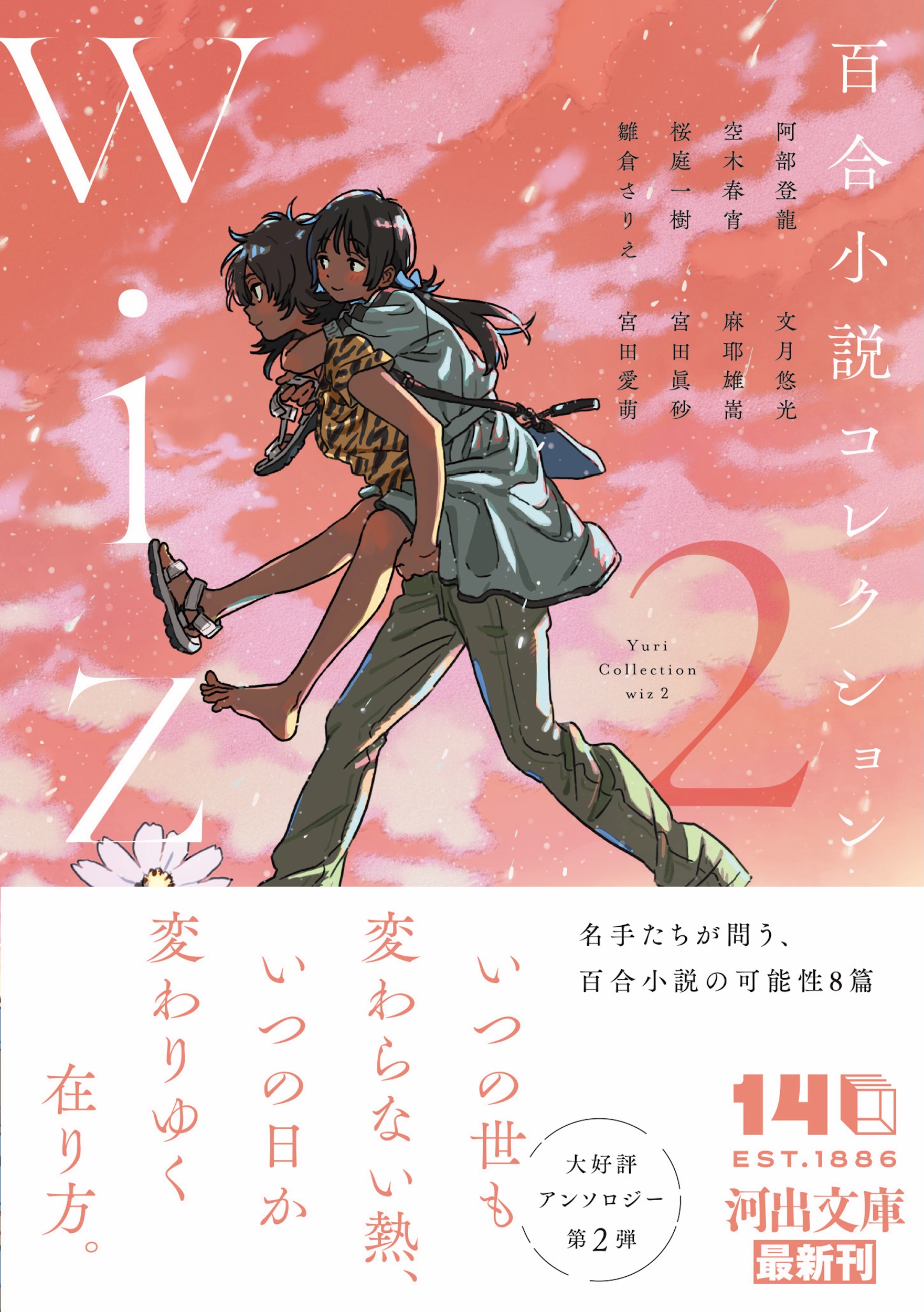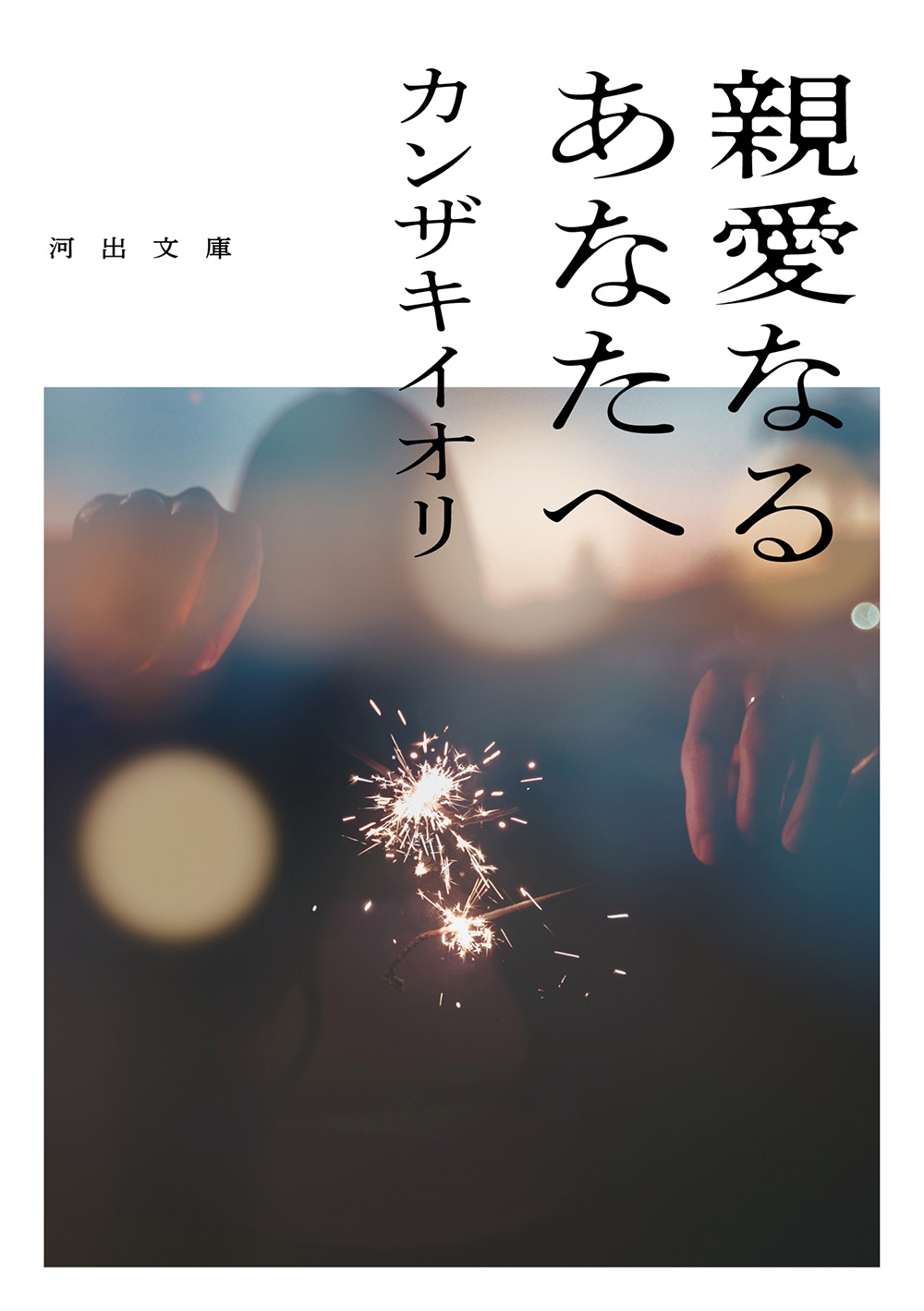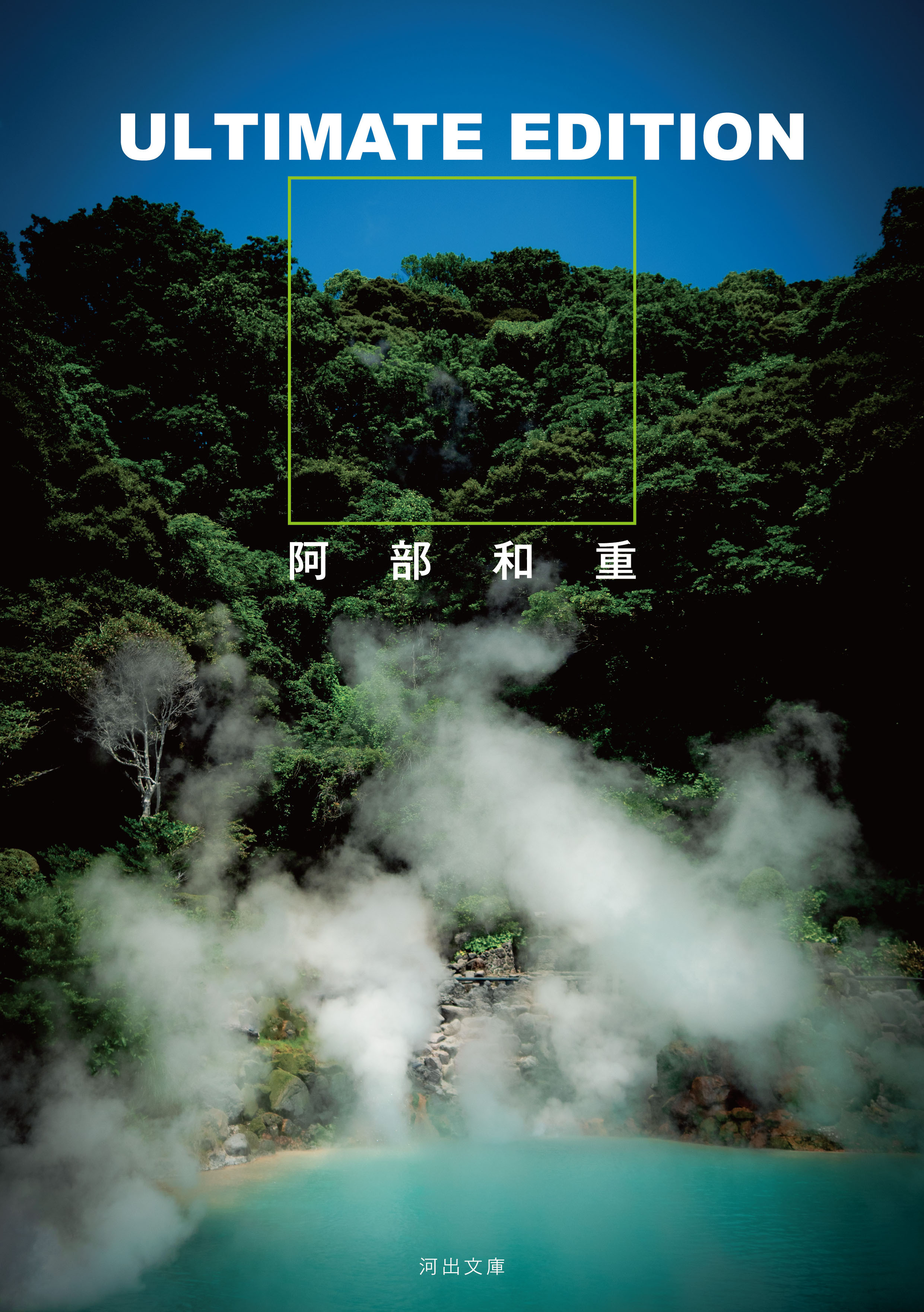
ためし読み - 文庫
阿部和重インタビュー第8回/「Neon Angels On The Road To Ruin」「There’s A Riot Goin’ On」(河出文庫『ULTIMATE EDITION』刊行記念 全作品解説/全8回)
阿部和重
2025.11.25
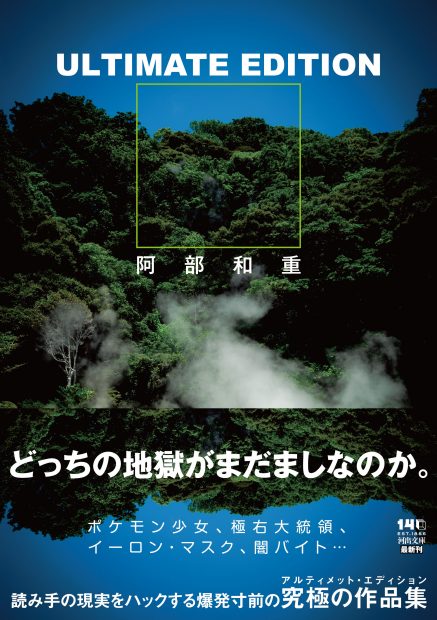
老いた教官を訪ねたロシア軍特殊部隊員、「仮想時空修学旅行」で内戦中のシリアへ降り立つ22世紀の高校生、人生の再起をかけた高級車窃盗闇バイト……。
本書『ULTIMATE EDITION』は、一触即発の現代を生きる者たちの無垢な心を円熟の筆致で描いた、アイドルグループ「嵐」や「A.B.C-Z」とのコラボレーション作品を含む、多彩な第二短編集です。
本書の文庫化を記念して、阿部和重作品を知り尽くしたフィクショナガシンによる全作品解説インタビューを配信します(単行本刊行時のものを再編集したものです)。全8回の最終回となる本記事では、人生の再起をかけた高級車窃盗闇バイトを描いた「Neon Angels On The Road To Ruin」、10月31日ハロウィンに騒ぐ渋谷の夜をめぐる「There’s A Riot Goin’ On」をお届けします。
「Neon Angels On The Road To Ruin」
アメリカのロックバンド「The Runa ways」の楽曲名
https://music.apple.com/jp/album/neon-angels-on-the-road-to-ruin/1444044870?i=1444045406
──ああ、その感じは伝わりますね。『ブレードランナー』のあの形容し難い収斂の仕方と重なってくる。ここからはやや長めの作品が二編続きます。「Neon Angels On The Road To Ruin」には、懐かしい名前も登場しますね。トーマス井口。『グランド・フィナーレ』に収録されていた短編の主人公です。
「よく気付いてくれましたね。おっしゃる通り、『馬小屋の乙女』という短編に出てきます。あれもひどい作品で(笑)」
──芥川賞受賞作を表題作にした本の収録作とは思えぬ、くだらなくてすばらしい作品でしたが、今回は作品としての繫がりを意識されたんですか。
「いえ、内容の繫がりというよりも掲載誌を意識したアイデアです。この作品が掲載されたのが『新潮』の今年の新年号で、『馬小屋の乙女』も『新潮』の二〇〇四年新年号に載せてもらっていたんです。つまりですね、時代を股にかけてトーマス井口が同誌の新年号に登場するという試みがマルチバースっぽくて面白いかなと思いやってみたのですが、誰も気付いてくれませんでした」
──とことんプロジェクトの人ですねえ……。いやはや。この間に何があったのか、トーマス井口はちょっと「出世」していますね。物語の冒頭でテスラCEOのイーロン・マスクの名前が出てきますし、これから何が始まるんだろうという期待感が高まる作品です。
「もともとはイーロン・マスクよりも、カルロス・ゴーンの保釈中逃亡劇について書こうと思っていたんです。そこから日本の自動車産業が直面中の、電気自動車製造・販売への移行にまつわる産業構造の変化という問題を浮き彫りにするつもりでした。その詳細は作中で紹介されているのでここでは繰り返しませんが、それは時代の転換点には違いないので、現在を重視する風刺作家のわたくしとしては当然ながら書くべき題材だったわけです」
──最初はカルロス・ゴーンが中心だったんですね。
「そのつもりだったのですが、いろいろと記事をチェックしてはみたものの、あの逃亡劇はこちらの予定している物語にうまくはまりそうになかったんです。なので、自動車産業の過渡期的問題を念頭に内容をあらためて練り直してみたところ、テスラ対トヨタならいけると思いつき、新興勢力と旧勢力の対立劇という構図ができあがったんです」
──面白いですね。壮大なコンセプトが背景にあることで、実際に物語られる高級車窃盗団の人間模様のコントラストが際立つ。短編というより、長編の呼吸で書かれている印象があります。
「そうですね。テスラ対トヨタの枠組みが生まれた時点で、ガソリンスタンドに勤めていた男が自動車泥棒に転身するというプロットは固まっていました」
──母子が犠牲になった池袋の自動車暴走事故も題材になっていますね。
「当時報道されていたさまざまな自動車関連の出来事を組み合わせて、一作にまとめようと意図していたんです。わたくし自身としても、報じられる加害者の言動に対しては、それなりに負の感情を搔き立てられるものがありました。遺族男性が何度も記者会見を開いていて、同じように妻と幼い子がいる自分を彼に重ねるところもありました。同時に、それとは別に、当事者ではない人たちがネット上で引き起こしている過剰なバッシングの問題もあった。それら全てを含めて描かないと、これを書く意味はないだろうと考えたんです」
──あなたは信頼をとても大事にしてきた作家です。この作品でも信用できない状況や裏切りが描かれる一方、泥棒一味を結び付けているものは信頼ですよね。相手とどう思い合うことができるのかを、しっかり書く。読者が感じるのは、信頼する、あるいは裏切るとはどういうことなのかという問いです。それはこの短編集全体に通底してもいます。
「物語を組み立てたり、キャラクター同士を組み合わせたりする中で、両者を心理的に結び付ける信頼の印のようなものを描かないと、小説として成り立たないとは思っています。ただ、自分自身がそこまで明確に、信頼というものを一貫したテーマのように書いてきた意識はありませんでした。もしかすると、図らずも出てしまった無意識の部分かもしれませんね」
──登場人物同士の信頼だけでなく、著者と読者との間の信頼、あるいは自分が信じるものを書くという著者の自分自身への信頼、それが伝わってくるように思うんですね。長い時間をかけて短編を書き継いでこられたからこそ、じわじわと伝わってくるものもある気がします。
「わたくしが主に書いてきたのは裏側の世界で、犯罪模様とかスパイ劇とか、非常に危うい関係の中で結ばれる人々のやり取りですよね。そこにある人間関係やコミュニティーは、ちょっとしたことで崩れてしまうし、露見したら捕まってしまう。公的に保証され得ない関係性だからこそ、信頼とか信用性を常に確認していなければならない。そういう関係を書きたいから裏社会を書くのか、あるいは裏社会を書きたいから結果的にそういう関係性を書くのか、どちらが先かは分かりませんけどね」
「There’s A Riot Goin’ On」
アメリカのファンクロックバンド「Sly & the Family Stone」のアルバム名
https://music.apple.com/jp/album/theres-a-riot-goin-on/1501778712
──さて、最後の作品です。自分の境遇への不満を募らせた十九歳の若者が、ハロウィンの夜の渋谷で爆破テロを起こそうと企てます。現代の社会では、ちょっとした気の持ちようで誰でもなりうるような主人公とも言えますね。
「自分がこれまで書いてきた中で一番多いのは、この短編の主人公みたいなキャラクターではないかと思います。一番似ているのはたぶん『ニッポニアニッポン』。暴走に至るような不満を抱え、具体的な計画を立て、着々と実行に向けて進んでいく。そういうタイプのキャラクターを繰り返し登場させてきた。結果的には計画が破綻し、これまでの準備は何だったんだろうと虚しさに浸ることになるわけですが、今回はその先へ突き抜けたかったんです」
──自分は死んでもいいんだと自暴自棄になっている主人公の気持ちが徐々に変化していきます。最後を飾るにふさわしい、力のこもった作品だと感じました。
「書く動機になったことは二つあります。ベトナム人技能実習生暴行事件と、この数年続いているいわゆる『ジョーカー事件』です。前者には純粋に憤りを覚えつつ、後者のような事件が起こるたびに複雑な気持ちにさせられました。『ジョーカー事件』といってももちろんそれぞれ中身が異なるわけですが、しかし犯人像はなんとなく、これまで自分が書いてきたキャラクターと遠くないものを感じさせ、共通性がないでもない。そうすると、こちらも勝手になにか応答しなければならない気がしてしまい、すでに起こった事件を無理矢理にでも方向転換させたくなる。現実はもういくつも起こったあとだから変えようがないわけですが、そうであっても今後新たな事件が発生する可能性が少しでもあり、もはや実行を止められないのだとしたら、せめてフィクションで方向性をずらすことで違う選択肢を当事者の意識にのぼらせられないかと。まったくの非現実的な祈願にすぎないとは思いつつ、それで最悪の事態を遠ざけ、全面的にではないにせよ、どこかしらポジティブに見える結果に結びつけられればと希望し、ああいう作品になった次第です」
──主人公は自暴自棄になりながらも、自分だけを見るのではなく、ふと、他人が差別されるのを見てしまう。「見た」ことで変化していくということがとても大事で、それはあなたがずっと書いてきたことでもあるし、読者が常にやっていることでもあると思います。それが折り込まれているから、最後の悲しさみたいなものも受け止められる。〝良識〟ある人たちからは怒られるようなことを、あなたの小説ではポジティブに描けると思うんです。怒られるというのはとても大事なことだと私は思うんです。「怒る」ことではなく、怒られることですね。読者が考える、感じる余白を残すことでもあるから。
「ありがとうございます。非常に誠実にまとめてくださって感謝いたします」
──短編でこんな大きな変化を読み手にもたらしうるのかと、作家としてのすごさを今まで以上に感じました。阿部和重の作品がもともと持っていたものが、より深まった姿で読者の前に現れていることへの感動もあります。あなたの四十代は『ピストルズ』で始まって、『Deluxe Edition』が四十五歳のときですね。四十代の最後に『オーガ(ニ)ズム』があり、五十代の最初の大きな仕事が『ブラック・チェンバー・ミュージック』です。そして、今年五十四歳になられたあなたが最初の短編集から約十年を経て『Ultimate Edition』を出される。感慨深いものがありますね。
「ありますね。『オーガ(ニ)ズム』は終わりでもあり、新しい何かが始まっていくきっかけでもありました。ただ、先ほど話したように、計画通りにはいかないかもしれませんけどね」
──次の長編について、『オーガ(ニ)ズム』の連載が終わったあとの佐々木敦氏によるインタビューで「三〇〇〇枚にはなるだろうという予想がついているんです」と述べておられますね。三年前のコメントですが「もうタイトルも話の内容も決まっていて、そのためのいろんな資料もほぼそろっているんです」とも。
「それが次に予定しているロシアに焦点を当てた長編なんですけど、当初のアイデアから大幅に変更することになったので、そんなに長いものにはなりそうもないです。とはいえ一〇〇〇枚は超えるでしょうけど」
──長編をプロジェクトのように捉えているからこそ、社会情勢によって変更を余儀なくされるわけですね。短編という形で即興的な表現を交えながら、現代の作家として今後も痕跡を残していくのだろうなあと思いました。
「そうですね。短編は短編で書き続けます」
──再来年がデビュー三十周年ですよね。
「わたくしはおそらく恵まれているほうで、デビュー以来、本当に好き勝手にやらせてもらっておりまして、その意味ではあんまり後悔のない仕事ができています。今後もおなじようにできるかどうか楽観はできませんが、どんな状況でも新たなプロジェクトで効果的に対応していきたいと望んでおります」
(完)