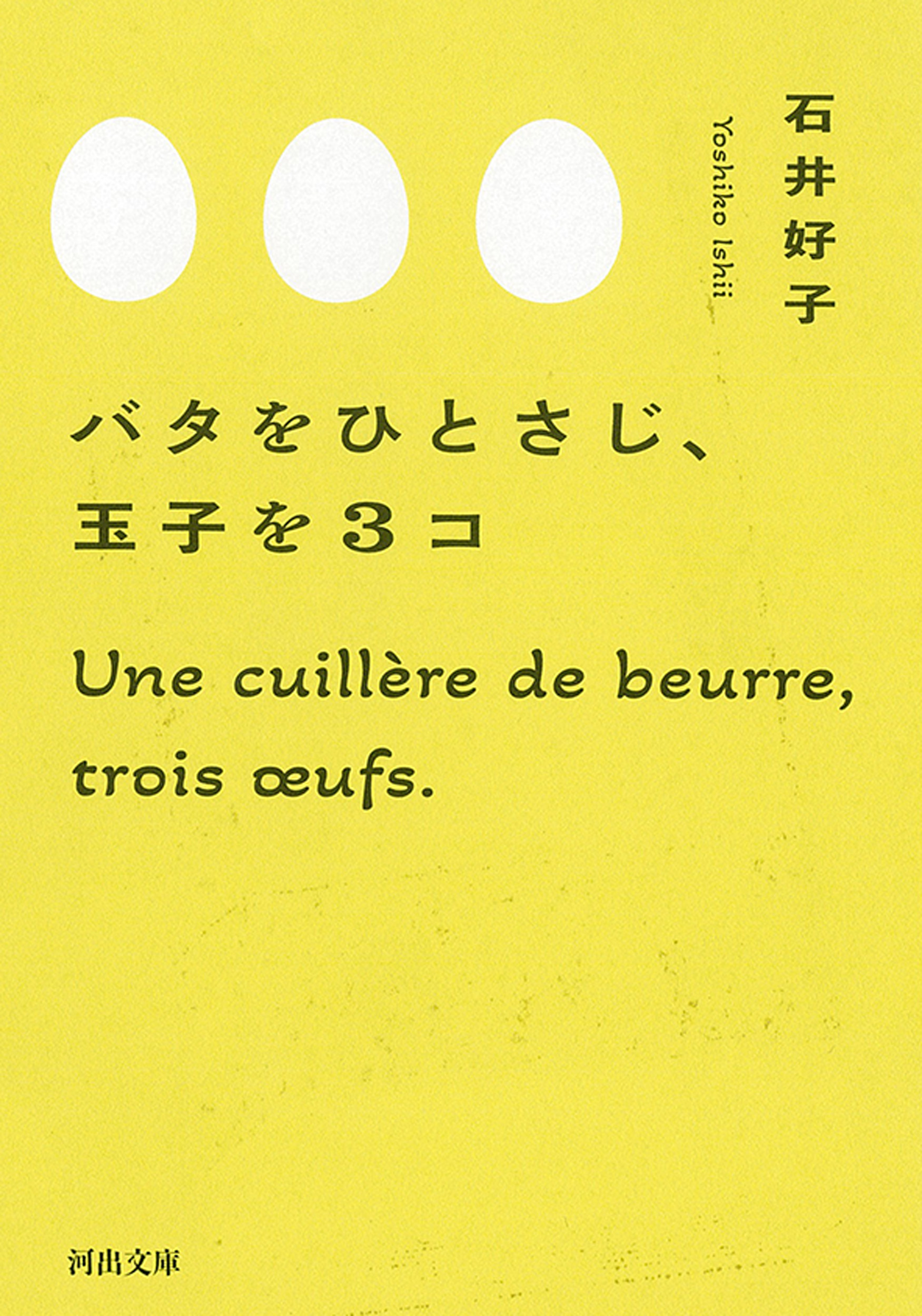文庫 - 随筆・エッセイ
ファミリーヒストリーで紹介された坂本龍一の父 真実の姿を伝える「伝説の編集者 坂本一亀とその時代」
田邊園子
2018.04.23
坂本龍一の父・一亀は「文藝」の編集長を務め、三島由紀夫や高橋和巳を世に送り出した伝説の編集者でした。
本書は坂本編集長による「文藝」復刊時に河出書房新社に入社した文藝スタッフ・田邉園子氏が、なんと子息である坂本龍一氏に直接、「父が生きているうちに父のことを書いて本にしてほしい」と依頼を受け記された一冊です。
本書よりNHK「ファミリーヒストリー」放映を記念し、まえがきを公開します。
*****************************************
はじめに
坂本一亀は、二〇〇二年九月二十八日、八十歳と九か月でその生涯を終えた。何年も透析に通っていた自宅近くの病院で、安らかに息を引きとったという。彼は二十五歳から三十五年間、出版社で文芸編集者として果敢に生きた。
編集者としての坂本一亀は、ファナティックであり、ロマンティストであり、そしてきわめてシャイな人であった。彼は私心のない純朴な人柄であり、野放図であったが、繊細であり、几帳面であり、潔癖であった。
彼の言動は合理性にはほど遠く、矛盾があり、無駄が多いように見えたが、本質を見抜く直感の鋭く働く人であった。言葉を費やして説明することを省き、以心伝心、推して知るべし、あ、うんの呼吸、といった古武士の世界に住んでいるように見えた。坂本さんは古武士のような人ですねえ、と感嘆していたのは、昔、たびたび河出書房新社に見えていた日沼倫太郎だったような気がする。坂本一亀には日本古来の白木の木刀がよく似合いそうだ。彼は〝木刀の味〟の日本男子であった。
「ダメダ」「イヤダ」「アカン」といった否定語を発することが多く、理由を説明しないので、なぜなのか、何を言いたいのか理解できないことが多かった。ずっと後になって解ることもあったが、解らないままのこともあった。
坂本一亀を駆り立てていた、あの狂おしいまでの情熱とは何なのか。それは、戦争体験と無縁ではないように思われる。青少年期に死と向き合って日常を過ごさざるを得なかった世代の人々のなかに、時々、共通するものを感じることがあった。三島由紀夫の狂気、井上光晴の激情、などである。
坂本一亀は、三島由紀夫の回想*のなかで、
きみは兵隊に行ったのかと私に訊く。行ったと答える。そうか、よかったな、うらやましいよ。ちっともよくない、と私は返す。
と記している。軍隊経験をもつ坂本一亀と、もたなかった三島由紀夫の違いがはっきり示されているし、また皇国少年から戦後、共産主義に転じた井上光晴とは、それぞれ信じる方向は相違しているが、彼らが第二次世界大戦中、死を決意して、まっしぐらに生きていたホットな若者たちであったことは共通する。彼らはその性情において、時代に背を向けたり逃げたりしなかった若者たちだ。三島由紀夫は坂本一亀や井上光晴を好きであったし、坂本一亀も三島由紀夫や井上光晴を好きであった。井上光晴は、その思想上の立場から、けして三島由紀夫への好意を表に出すことはなかったが、三島邸のパーティへの招待を断らずに出かけているし、坂本一亀とは取っ組みあってじゃれあう仲であった。純粋で、直情的な、似たような気質をもつ人同士には、暗黙のうちに牽かれあうものがあるのではないかと私には思える。三島由紀夫の書き下ろし長篇小説『仮面の告白』や井上光晴の長篇小説『地の群れ』の成功は、編集者坂本一亀の真摯な情熱が相手に伝播し、彼らのなかに潜んでいた力を引き出したのだと思う。
戦時中は皇国少年であったことを、坂本一亀から打ち明けられた人がいる。それは、さもありなんと納得がいくものだ。しかし彼は軍隊体験によって軍隊を激しく憎悪し、その感情は、野間宏の書き下ろし長篇小説『真空地帯』を世に送りだすことによって幾分かが解消されたのかもしれない。ベストセラーにもなり、高い評価を得た『真空地帯』の成功のあと、目を真っ赤に泣きはらしていた坂本一亀を見た、と当時の同僚は証言する。
坂本一亀は涙もろい人であった。彼が掘り出した新人作家高橋和巳が若くして他界したとき、坂本一亀はどれほど泣いたことか。高橋和巳について彼が書いたいくつかの追悼文はどれも感傷の涙で濡れている。高橋和巳には青い炎のような古風な情念があり、それは坂本一亀のなかで絶えず燃えている小さな炎と触れあい、彼らが相対するとき、炎は大きく揺れるのだった。高橋和巳の早すぎる死は、坂本一亀のなかの燃える炎を一瞬かき消した。だから彼は、しばらくのあいだ立ち直れないほど泣くことで自分を支えなければならなかったのだ。
坂本一亀の無邪気で素朴な面が素直に発揮されたのは、小田実の書き下ろし旅行記『何でも見てやろう』の場合ではないか。ざっくばらんで、言いたいことを忌憚なくしゃべる小田実を、坂本一亀はとても愛していたのではないかと思う。いつも気むずかしい顔をしていた坂本一亀は、小田実が現れると、子供のように邪気のない、人懐っこい可愛い笑顔を見せたのが印象に残っている。
坂本一亀が「文藝」の編集長であったのは、二年たらずの短い期間であるが、彼はその間に中身の濃い凝縮した仕事を残した。半世紀以上前、まだその名が知られていない新人の丸谷才一、辻邦生、山崎正和、黒井千次、日野啓三、竹西寛子などが、すでに誌上に足跡を残している。類い稀なる大努力家だった彼は、寸暇を惜しんで同人雑誌を読みふけり、作家の卵たちを集めて、毎月「文藝」新人の会を開き、意見交換を行っていた。坂本一亀はそうした交流のなかで、刺激しあい、競いあう彼らの将来を期待し、次代を担う若者たちに夢を賭けたのだろう。坂本一亀は文学への高い志を抱き、愚直に夢を追うことの出来た時代の最後の編集者だったといえよう。
* 「仮面の告白」のころ 一九七一・二「文藝」