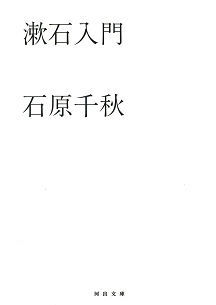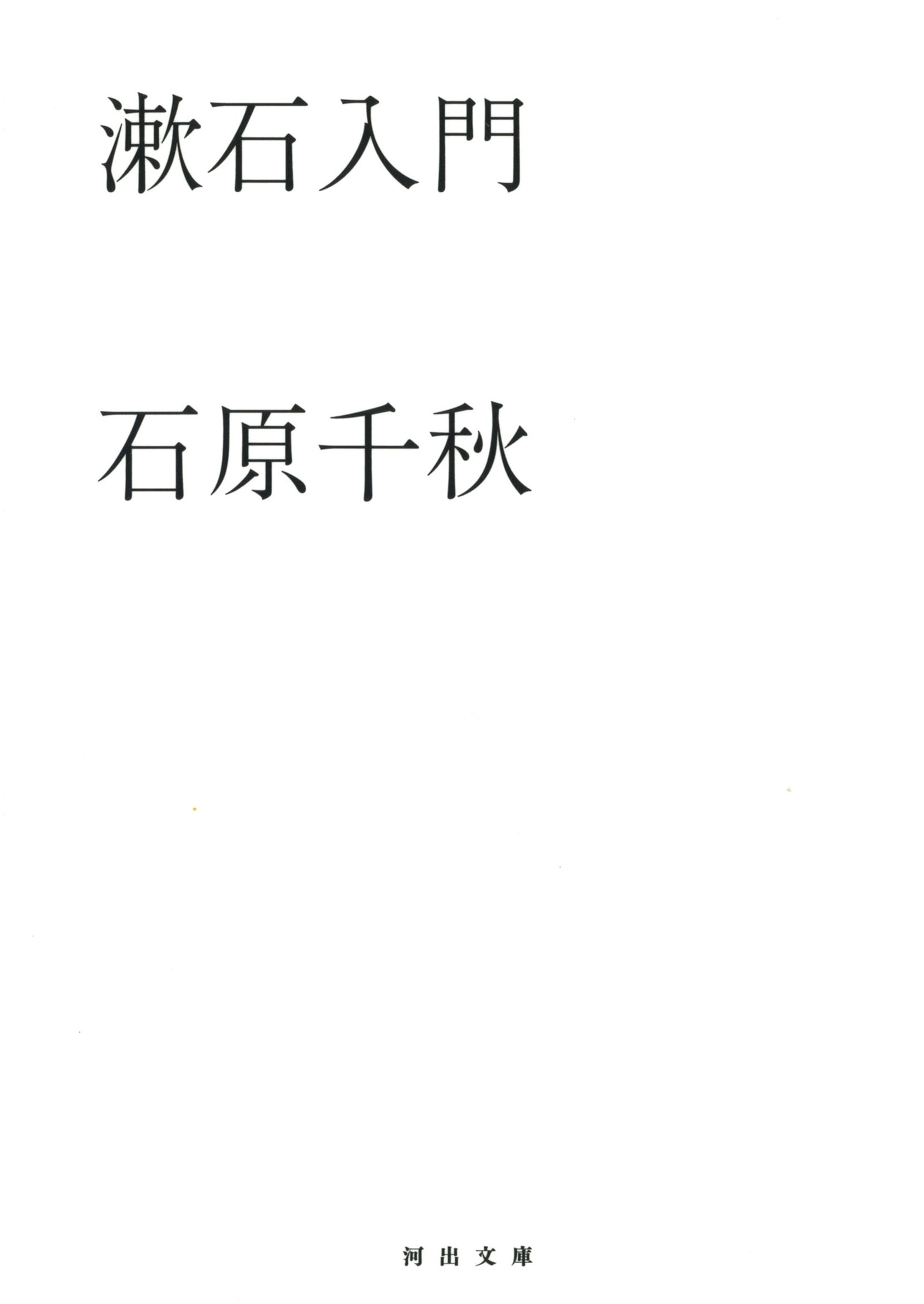
文庫 - 随筆・エッセイ
少し不思議な「漱石入門」
石原千秋
2016.09.30
石原千秋
漱石はなぜ、いつ読んでも「新しい」のか。「次男坊」「長男」「主婦」「自我」「神経衰弱」「セクシュアリティ」の六つのテーマから、深く読むための基礎知識と歴史的背景を解説。これから読む人も、かなり読み込んだ人も──
——————————————————-
文庫版あとがき
少し不思議な「漱石入門」ができあがった。
ふつう「漱石入門」と言えば、漱石文学をあまり読んではいないか、読んではいても深くは理解していない(失礼!)読者を想定して書かれるものだ。しかし、この本はそうではない。漱石文学をこれから読む人にも、もうかなり読み込んだ人にも興味深く読めるようにできあがっていると思う。
この本はもともと『漱石の記号学』と題して講談社選書メチエから一九九九年四月に刊行されたが、その時は私自身が背伸びをして書いたから、専門書的な趣が強く出ていた。専門書は安くても五千円はするが、ほぼ同じレベルの本が講談社選書メチエなら千数百円で買えるから、その頃は「専門書のダンピング」などと言われていた。それを聞きかじって気張って書いたのだった。 それが、いまはかえって「漱石入門」として有効だと思っている。
漱石は、作家生活のほぼすべての時期を「朝日新聞」の専属作家として過ごした。当時の「朝日新聞」はマーケットを下町の商人階層から山の手のエリート階層にシフトチェンジした時期で、まさにその山の手エリートのための新聞という旗印として、東京帝国大学講師だった夏目漱石に白羽の矢を立てたのだった。 だから、漱石は自分の役割に忠実に、山の手のエリート階層のために山の手のエリート階層を書き続けた。
その結果、「朝日新聞」入社後の漱石は、「山の手の家族小説」だけを書いた。それは山の手に育ち、教師以外の職業は知らない人生経験に貧しい漱石にとってリアリティーの持てる唯一のテーマだっただろうし、漱石が高く評価していたイギリスの女性作家ジェーン・オースティンのテーマでもあったから、「朝日新聞」の専属作家として仕事をすることは、漱石にとって願ってもない条件だったかもしれない。
いま明治・大正期の「山の手の家族小説」を読むためには、いくつかの前提になる知識と、それを意味づけていた当時の思想的な背景を知る必要がある。細かく考えれば限りはないが、大まかには六つあればいいというのが私の考えたことだった。それで、第一部には「家族」に関するテーマを三つ並べ、第二部には「個人と他者」に関するテーマを三つ並べた。そして、序章では漱石が小説というジャンルをどう考えていたのかを論じて、終章では東京とそこで生きる若者たちについて論じた。この序章と終章はやや難しさが残っているから、最後に読んでもらえればいいと思っている。
ただ、文章がなんとも硬かった。そこで少しも大げさではなく、「漱石入門」として通用するように、全ページ真っ赤になるくらい朱を入れた。いま国語国文学科の導入教育として大学一年生の「日本文学基礎演習(近代文学)」を担当している。これはもっとも重要な科目で、大学生としての発想の基本と文章の基本をしっかり身につけてもらうのだが、そこで「こういう書き方はダメだよ」と教えている「ダメな書き方」の典型で、私自身が採点したらマイナス一万点ぐらいになるだろう。「学生諸君、ごめんなさい」と心の中で呟きながら朱を入れたものだ。
四十代半ばだった当時、「かっこいいでしょう」と密かに思いながら使っていた用語なども古くなったので、ほぼすべてほかの言葉に置き換えた。そもそもタイトルの「記号学」がいまではもう一般的ではない。「漱石の記号学」では漱石の文学理論だけを論じているような印象を与えるだろう。この本を出したときに、尊敬する年配の研究者に「こういうタイトルは古くなるよ」といわれたのが身にしみた。
ただ教師として言えば、若者が「かっこいいだろう、よく知っているだろう」といま風の言葉を使っているのを責めたりはしない。若者から虚栄心を取り去ったらいったい何が残るのだろう。若者の虚栄心は、彼らが何かを学ぼうとする原動力そのものである。だから、私はそういう若者を「まだ口唇期なんだなあ」、つまり「難しい言葉を口にする喜びを感じる時期なんだなあ」と見守るようにする。いま風の言葉を使っただけで拒絶反応を示す教師も少なくはないが、いったい教育するということがどういうことかわかっているのだろうかと、不思議な気持ちになる。
そんなわけで、この本は漱石文学以前の人にも、漱石文学以後の人にも楽しんでもらえるのではないかと思う。もちろん、漱石文学まっただ中の人にも。漱石文学を離れて、明治・大正期の家族や個人と他者について考えたい人にも役立つのではないかと自負している。