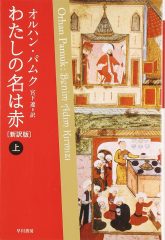特集・コラム他 - 記事
トルコのノーベル文学賞作家オルハン・パムク緊急寄稿!「少女は倒れたコンクリートの下敷きに。男はどうしていいかわからない」
オルハン・パムク 安原和見訳
2023.03.06
イーユン・リー、ホルヘ・ルイス・ボルヘスやミラン・クンデラなど、河出書房新社で翻訳作品のある20名以上の著名な作家と契約を結んでいる英国のザ・ワイリー・エージェンシーより2月にメールが届いた。それは、トルコのノーベル文学賞作家オルハン・パムクが「ニューヨーク・タイムズ」に緊急寄稿した「トルコ・シリア大地震」直後の記事「少女は倒れたコンクリートの下敷きに。男はどうしていいかわからない」だった。
1985年のエルトゥールル号遭難事件、2011年の東日本大震災など、トルコと日本は災害が起こるたび、お互いに助け合ってきた歴史があり、この重要な作家が未曾有の非常時に訴える心からの叫びを日本でも読めるよう緊急翻訳、全文公開する。(編集部)
******
少女は倒れたコンクリートの下敷きに。男はどうしていいかわからない
オルハン・パムク
安原和見訳
少女は悲しげな目をしている。10歳から12歳ぐらいだろうか。ほとんど身動きもせずに、スマートフォンのカメラを見つめている。動くことがあっても、その動作は力なく緩慢だ。撮影している男が、少女に気づいて驚いたように喜びの声をあげる。
「ここに人が! 生きてるぞ!」
しかし、周囲にはだれもいない。空は鉛色の雲に覆われ、静かに雪が降るばかりだ。そこはトルコ南東部のどこか、マグニチュード7.8と7.5の2度の地震に破壊されたばかりの地域だった。
男は少女に近づく。倒壊したコンクリートに胸から下をはさまれて、身動きができないらしい。どう見てもふたりは知りあいではない。
「のど渇いてない?」男は尋ねる。
「寒い」少女は答える。「ここに弟もいるの」
「動ける?」
「ううん」少女は弱々しく答える。消え入りそうな声だが、しまいにはなんとか聞きとれた。しかしその目にはなんの希望もない。最初の地震が襲ってきたのが午前4時、それからすでに半日が過ぎて、また夜が来ようとしている。
「足、動く?」
「あんまり」少女の声はか細くて、なんと言っているかわかりにくい。いまではその顔に別の表情が浮かんでいる。なにかを隠しているかのような、自分のいたらなさを恥じているかのような。
夜から朝にかけて雪は断続的に降りつづき、ゆっくりと毛布をかぶせていく――震災の苦しみに、死者と死にゆく人々に。そして前夜の数秒間に崩れ落ちた、2階から3階建ての家々、15階から16階建てのビルのうえに。
スマホで撮影している男が、どうしていいかわからずにいるのが伝わってくる。彼ひとりの力では、あの恐ろしく重いコンクリートの下から少女を引っ張り出すことはできない。ふたりとも黙り込む。
少女の目が霞んでいく。顔には疲労と苦痛がありありと浮かんでいる。
「ここで待ってて。助けを呼んでくるから。すぐに出してあげるからね」
しかし男の声は自信なさげだ。あたりは地震ですっかりなぎ倒されている。おそらく市の中心からはだいぶ離れているのだろう。道路も橋もすべて崩れて、救助はまだ来ていない。すぐに来るようにも思えない。
ここに住んでいた人々のなかには、崩れた自宅から脱出し、暗い雪の夜に逃げて助かった人もいただろうが、そういう人はどこかに避難して寒さをしのいでいるにちがいない。しかし、この少女と弟の家族はだれも助からなかったのかもしれないし、少女を捜している人はいないのかもしれない。
「置いてかないで!」下敷きになった少女はしまいに言った。
「大丈夫、きっと戻ってくるから!」男は言う。「きみのことは忘れないから、助けを呼んでくるから」
ここに半日以上もひとりぼっちで、身動きできないまま取り残されて、少女はすでに死を覚悟しているのがわかる。もう反論する気力も残っていない。
それでも彼女はまた言う。「置いてかないで」その声はささやくようにかすかだ。
「助けを呼んでくるから!」今度はさっきより大きな声で男は言ったが、その言葉を信じることはできない。
動画はここで終わっている。彼が助けを呼べたのかどうかはわからない。このほかにも、何百という必死の訴えや被災者本人の記録を私は見た──。その最初の日、画面に何時間も釘付けになって。多くの例に漏れず、下敷きになった少女を撮影した男は、その動画をツイッターに投稿した。なにも手を加えず、コメントもつけずに。
少女が救出される動画を私は待ったが、ついに投稿されることはなかった。
スマホを持った男がどう思っていたにせよ、助けを呼ぶのは簡単なことではない。国の発表によれば、この地域では7000棟もの建物が損壊あるいは倒壊している。地震はシリアにも被害を与えている。被害者の実数は報道よりおそらくはるかに多いだろうが(最新の数字では、現時点で死者は2万人を超えている)[現在、死者は5万人を超えた]、それと同じように、倒壊した建物の数も実際にははるかに多いと思われる。道路は通れないし、停電やネットワークの混雑で携帯電話もまともに使えないしで、地方の小さな町々がいまどうなっているのか、情報はほとんど入ってこない。ツイッターなどのソーシャルメディアでは、全滅した村もあるという投稿も見受けられる。ほんとうにそんなことがあるのだろうか。
これほどの規模の地震が襲うのは、トルコでは80年以上なかったことだ。私は子供のころから、近くでまたは遠くで大地震を経験してきて、これが4度目になる。1999年、1万7000人以上が犠牲になったマルマラ地震のあと、私は被災した町のひとつヤロヴァに行ったことがある。コンクリートの廃墟を何時間もさまよい、罪悪感と責任感にさいなまれ、せめて瓦礫の撤去だけでも手伝いたいと思ったが、結局なんの役にも立てないまま帰ってきただけだった。あの日の目を覆う惨状はいまも頭にこびりついている。あの焦燥感と悲しみは忘れたくても忘れることができない。
それがいま、新しい、しかしあまりにも見慣れた光景によって、それが押しのけられようとしている。無力感に胸がつぶれそうだ。
空港が被害を受け、道路がふさがり、最大手のメディアですら、いくつかの大都市にはなかなか到達できなかった。半日かけてようやく着いてみると、そこには地獄絵図が待っていた。震災から半日後、雪に、雨に、風に打たれる街々で、何百万という人々が来ない助けに怒りを募らせていた。トルコ政府の発表によれば、この地域では1350万人が被災しているという。また世界保健機関(WHO)によれば、トルコとシリアで被災者は2300万人にのぼる可能性があるらしい。
最初のマグニチュード7.8の地震は夜中に起こったが、それから9時間後にはマグニチュード7.5の地震が続いて起こり、震災はまさしくこの世の終わりを思わせる規模に達した。2度目の地震――震源は最初の地震のそれから60マイルほど離れていた――があったとき、余震のために戸外に逃げていた何百万という人々は、恐ろしいなど言うもおろかな光景を見せつけられることになった。おおぜいの人々が素手でレンガをひとつひとつどけ、崩壊した16階建てのビルの瓦礫のなかを通り抜け、通りをさまよって助けや食料を求め、暖がとれる屋根のある避難所を求めている。そして「ああひどい、ひどすぎる」と叫びながら、スマートフォンでその惨状を撮影しはじめ、と思うまもなく、カードの家のように建物が次から次に崩れだしたのだ。あとには埃の山が残るばかりだった。
その正視に耐えない恐怖の映像を、多くの人々がソーシャルメディアに投稿している。コメントやキャプションどころか、ひとこと添えることすらせず、そのまま。そうすることでふたつのメッセージを発信しているのだ。ひとつは、人々の受けた衝撃の大きさで明らかなこと――茫然として声をなくすほどの災害の規模。そしてもうひとつは、見捨てられたという絶望感だ。国じゅうがいま感じているそれは、地震そのものに劣らず痛ましい。
この世の終わりのような光景を前にするや、人々は連帯と助け合いの精神を痛烈に呼び覚まされ、それと同時に、これを伝えたい、証拠を集めたい、自分の足跡を残し、自分の声を届けたいという本能を燃えあがらせた。瓦礫の山と化した大都市の中心部では、レポーターのマイクの届く範囲にいるだれもが叫んでいるかのようだ――「撮ってくれ、ここを、これを撮ってくれ。助けが要る、食料が要るんだ。政府はなにをしている、救助隊はどこにいる」
救助隊は派遣されてはいるのだが、物資を積んだトラックは交通渋滞に巻き込まれ、被災地から何百マイルも離れた場所で何時間も立ち往生している。人々は家も家族も大切な人もなくし、持てるものすべてをなくして、そのうえさらに気がついた――自分たちの街で火災が起こりはじめているのに、だれもなにもしていないではないか。それでかれらは、公用車を、警察官を、公務員を見かけるたびに、行く手を遮って抗議しはじめる。わが国の人々がこんなに怒っているのを私は見たことがない。
2日目もあっという間に暮れて、瓦礫やコンクリートの山の立てる音は小さくなり、通りに出ている人々はこの惨状にも慣れていく。パンや食料を配るヴァンの前に人だかりができる。しかし、怒りと口惜しさ、不意打ちを食らったという絶望感は薄れることがない。
翌日ソーシャルメディアの投稿で知ったのだが、被災した大都市にみずから長距離を旅して出向き、手を貸そうとしている医師たちがいた。しかし、到着してみたらそこには権威も責任者もなく、かれらを指揮する者はいないようだった。慄然としたことに、公立病院すら倒壊していたのだ。
2日後、主要都市の中心部にはある程度の援助が届きはじめた。しかし多くの人々にとってそれはあまりに不十分で、またあまりに遅すぎた。
2023.2.11
A Girl Trapped Under Fallen Concrete. A Man Unsure of What to Do.
©︎2023 Orhan Pamuk
The text, first published in THE NEW YORK TIMES, 11, February, 2023, by arrangement through The Wylie Agency.
写真:Koray Şentürk, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Archive