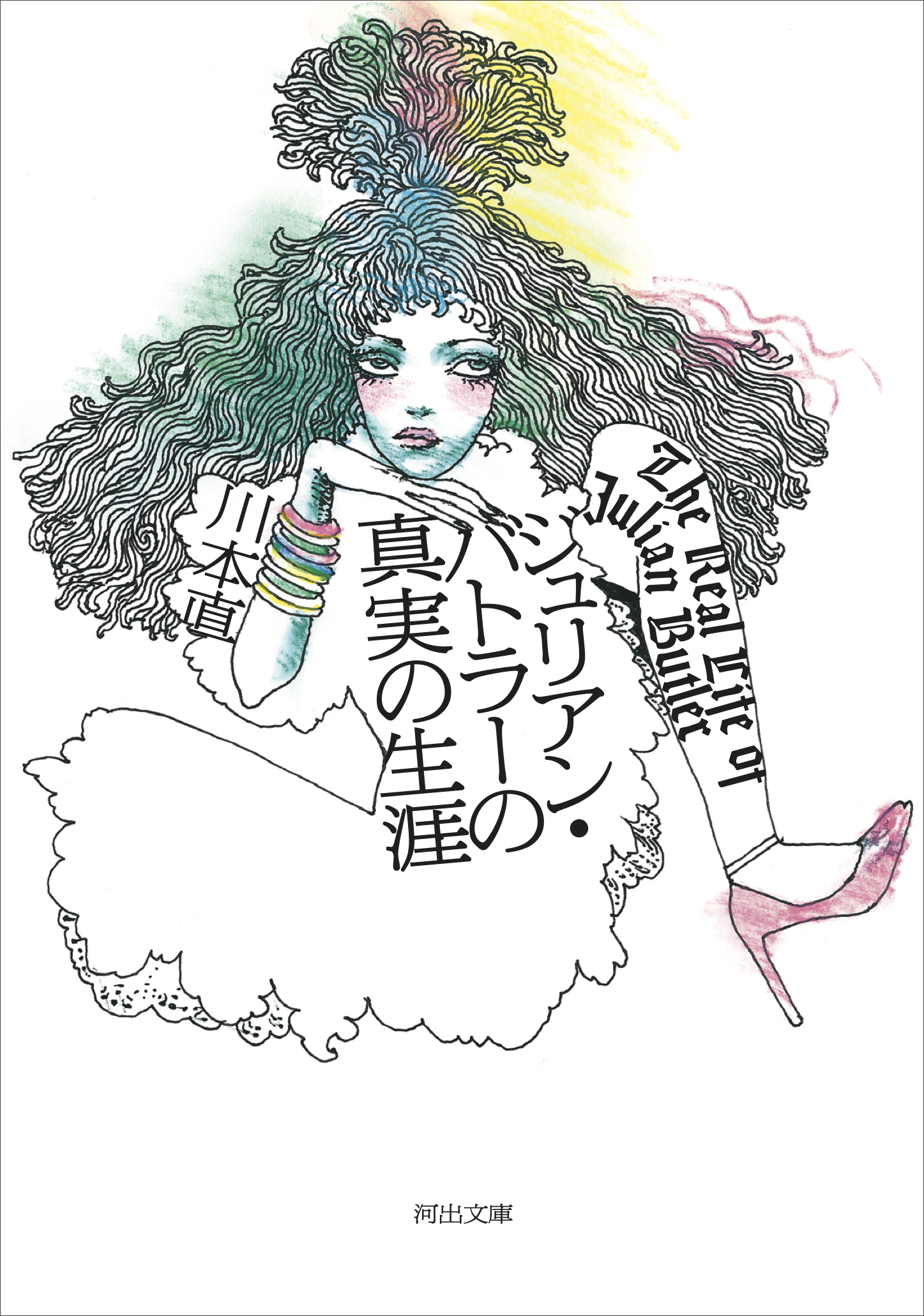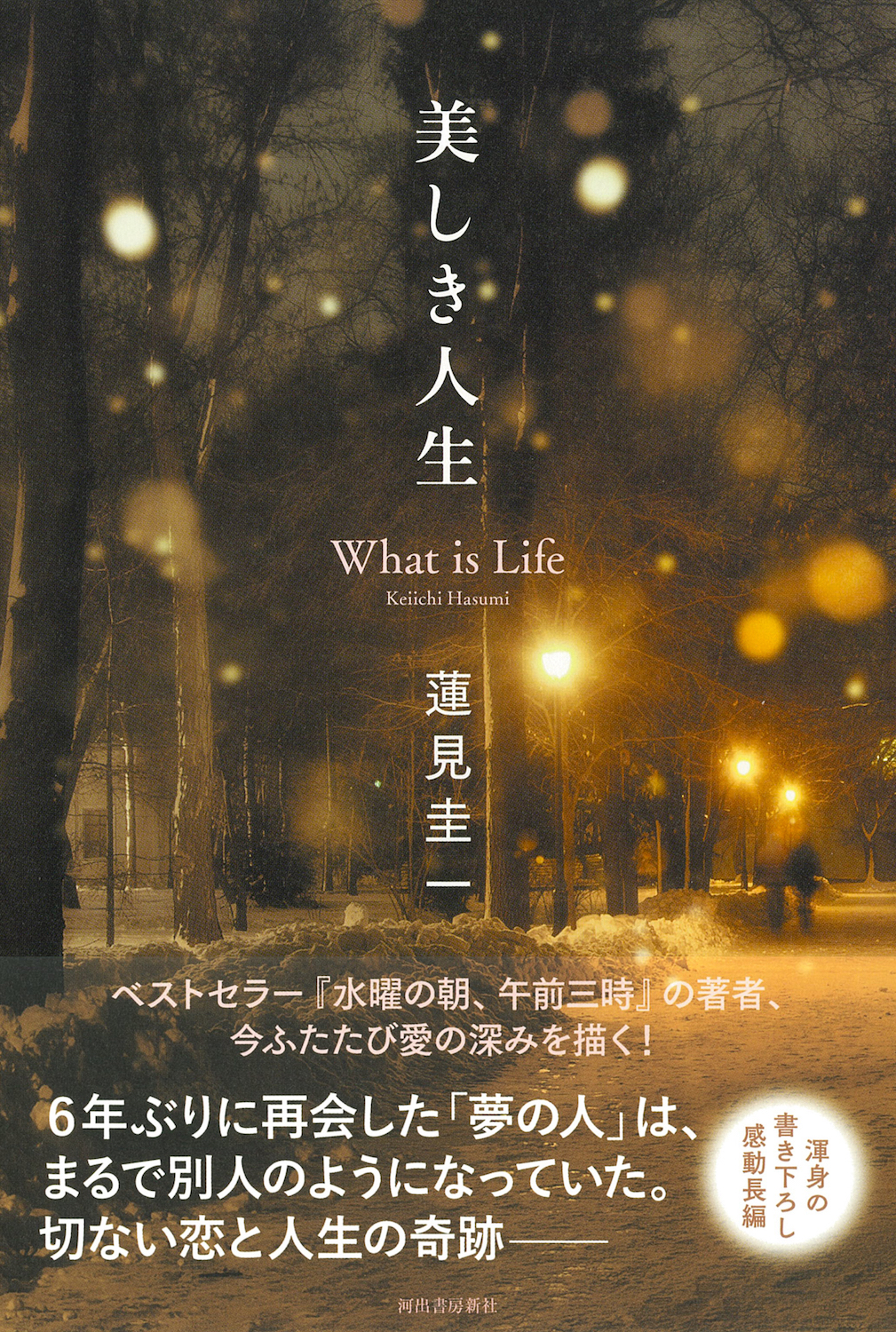書評 - 日本文学
「ちょっとフリージャズとかそういうのの演奏に似ている。」(本文より)――山﨑修平デビュー小説『テーゲベックのきれいな香り』書評
評・高原英理(小説家)
2023.01.23
この詩になりかかりつつ小説であることを堅持している小説の書き方は、自分の『詩歌探偵フラヌール』を書いていた時の息の使い方に似ていると思った。『詩歌探偵フラヌール』は文字で記録をするものの、その言葉の広げ方は一回限りの、ライブのような姿勢で書かれた。
「文学の本領とは、言葉を書き連ねていくごとに世界が立ち現われていく、そして、そこから今度は次の言葉が喚起される、という『一回的な出来事』のうちにある。」(矢野利裕『今日よりもマシな明日 文学芸能論』)これだこれ。
物語は何らかの形で予めの構築が必要だが、小説は出たとこ勝負だと思っている。たまたま得た一語が引き寄せる次の言葉、連想、呼び出される記憶、そこから始まる、一瞬前は知らなかった展開、書くことで何かできてゆく。書いているうちに何かに突き当たる、あるいは何かに触れる、触れたような気になる、触れそうな感じがする、そういう未知の何かを呼び出そうとして現代の小説は書かれるのだと思う。そこにストーリーやプロットを用意しなくても、何か自分なりのルールを用意してから、言葉とともに僅かに触れてくる知らなかったこと、そのための手がかりとしての記憶を伝えるとそれも小説となる。という小説として読んだ。
ちょっとフリージャズとかそういうのの演奏に似ている。
確か国枝史郎が自分の小説はジャズ(の即興演奏)みたいなものだと言っていた。この詩的小説を国枝の大衆的伝奇小説と比べるのは全然違うと思われるかもしれないが、その造り、姿勢のようなものに共通するところがある。国枝は奇想天外な物と人を用意しておいてそれらがどうなっていくかをその場のノリで書き続けていった。
『テーゲベックのきれいな香り』もそれに近いやり方で書かれたと思う。あるシチュエーションを決めて、記憶にある自分、語り手、語り手の分身、記憶にある人々を呼び出し、そこからは言葉の転がりとか連想とか、ふとやってくる思いもよらない記憶の波立ちをそのまま進めてゆくのだ。シチュエーションは2028年に起きた大災害とそこから過去に向かう語り手の意識、というところで始めて、思いつくままに登場人物を呼び込んでくる。中では虎子というのがいい仕事をしている。それは語り手でもあるのだが、ここでは自他の区分も決定的ではない。言語上の自分は「自分」と口にした瞬間、他者であるからだ。
夢が自分の意識を変容させるように、言葉はその場次第に自分を変容させる。
私は(今のところ)詩人ではないが、きっと詩にもこういう部分があるのだろう。どこからが詩になるのかはわからない。これはしかし小説だと思った。手つきというだけのことかも知れないが、言葉の転がし方という流儀のようなものかどうか。そしてその転がりをこんな流儀もあったのだと知ると、そこで癖になってゆく。コーヒーでも酒でも最初口にしたときはなんだこれまずい、と思うかもしれず、しかしあるとき何かを会得するとそれが実にいいものであり、またどういう苦さが自分には好ましいかもわかる。そんな意味で好きになれた。
小説でも詩でもどちらでもよい、私が望むのは知らなかったことに突き当たるときの揺れのようなものだ。と、こんなことをこの小説を読むまで気づかなかった。教わったわけではなく、そうだこういう書き方をしたいのだ自分は、と思ったからだ。それは具体的に似たいのではない。そうでなく、この言葉と意識の角度の合わせ方をするとなんか自分でないところに行けそうに思えたからで、自分が書いている間は小説ではない。自分でない言葉が不意に影を落とした時が小説のあるいは詩の焦点ではないか。
「幾人もの記憶、整合性の取れない会話、文章。それなのに、どうして見えてしまう瞬間があるのだろう。」これはマニフェストかな。この手触りに沿って書かれている。
「虎子、それはわたし」の章は特に、途中から詩となって隆起している気がするが、しかしそれも詩として隆起していく様態を語る小説である、と言うことができる。この小説は詩人が詩のありかに触れようとする、その自身には知覚できないところを狙い続けて、そこに詩に至る幻の経路を見出そうとしている小説なのだ、と、著者に詩集の著作があり、自身、詩人と書かれているから、そんなふうに思えるかもしれないと割り引きしながらもやはりそうだこれは詩のありかを探る小説なのだと言おう。そして知る、切に詩が欲しい。そのことが小説を書かせるのだとしたらそこに小説の自由がある。
一部、2022年末にTV東京BSで三回連続放映されて視聴者が驚愕したというフェイクドキュメントを思い出したところがある。「森鷗外vs森林太郎(あと三回ほど強くなるための変身を残している) 虎子」という一節で、会話する相手が徐々に関連の遠い表現と語を当然のように用い始めるところだった。この後の展開にもその方向は延長されてゆく。フェイクドキュメントの方は最初確かな過去の番組映像発掘という形をとりながら、そのうちにそれが異様な、あるはずのない展開を見せていき、最後にこれはフィクションでしたとテロップされるのだが、その、ドキュメントだと思っていたはずの、昭和時代の俗極まってセクハラ多々で凡庸でなれなれしい会話が、ある瞬間からとてもありえない、いわばアナーキーでシュルレアリスティック(というかロートレアモン的な)な語彙を見せ始め、それが相互に続いていった時の驚愕と不穏、狂気、恐怖とばかばかしい笑いというところに、あるいは詩の要諦もあるのではないか、言語の脅威とはこういうものではないかと思った。
同様にこの小説全体が、恐怖を伴いかねない笑い、その違和、次元的陥没のような瞬間にむけて書かれているようで、その先にあるのが詩なのではないかとやはり思いたいのだった。
細部では「オートバイは買えないから、アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグと名付けた自転車に乗って、」というところがとても好きだ。それが岡井隆の短歌のいわば本歌取りになっているのもいい。「蜂蜜に漬けたナッツのなかに一つだけいじめられそうなくらいに大きいものがあって、二人で手を合わせて拝む。」ここ、最高だと思う。
薩摩軍鶏、もいい。なにげなく差し挟まれる詩論もいい。
「ほお」「ひょいひょ」と叫びたくなるところでは自分かと思った。なんかシモ・ヘイヘって感じもある。
虎子の「一人でも輪唱してみせる」は水原紫苑の
巻貝のしづけく歩む森に入りただひとりなる合唱をせり『さくらさねさし』
が思い起こされる。
「詩は瞬間であるということ」そしてここだ。
後半、本当に詩があらわれる。なんとなく到達感もあるが、しかしそれは一瞬の描出ということでもある。このあたりが一番緊張感ある。なんか散文的なところは笑いと緩み、韻文的なところは緊迫、と思える。詩は読む方にも詩の姿勢を促すからだろうか。
テーゲベックの香りをきっかけに呼び出されてくる言葉という意味では誰もがプルーストのプチット・マドレーヌを思い出すだろうし作者も意識しているはずだ。それは時代を違えても記憶の文学的機能というべきなのだろう。だが、そういうところとは別にプルーストを感じるのは、語り手のそこはかとない文化資産の豊かさで、プチかどうかは知れないが、戦後日本数十年の間に僅かに存在したブルジョワ的な、文化的選良階級のような(幻影の)佇まいが透視されて、こういうところも憎い。憎いなあ。