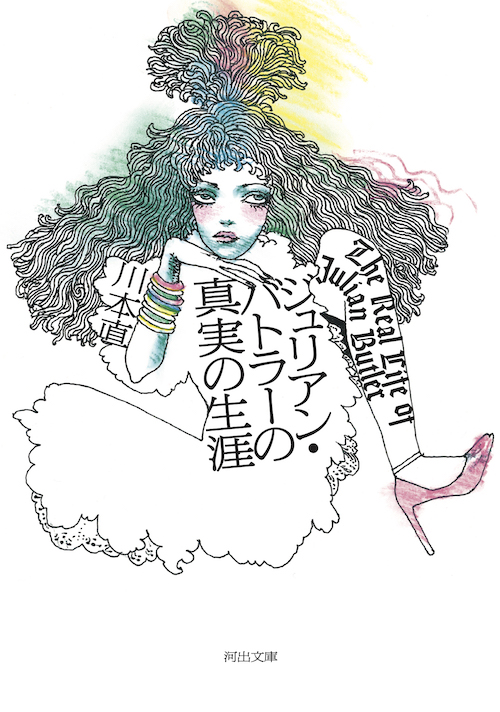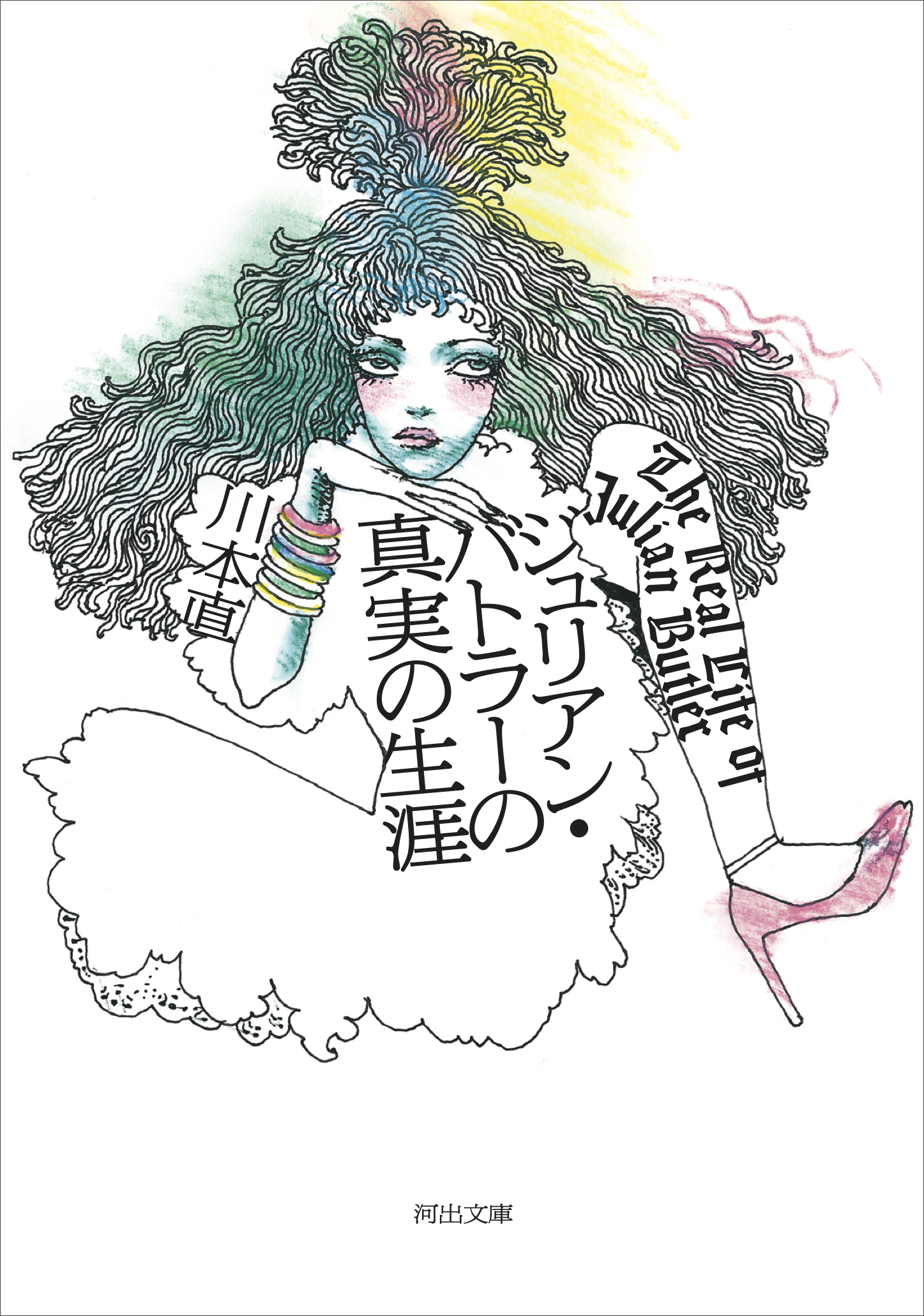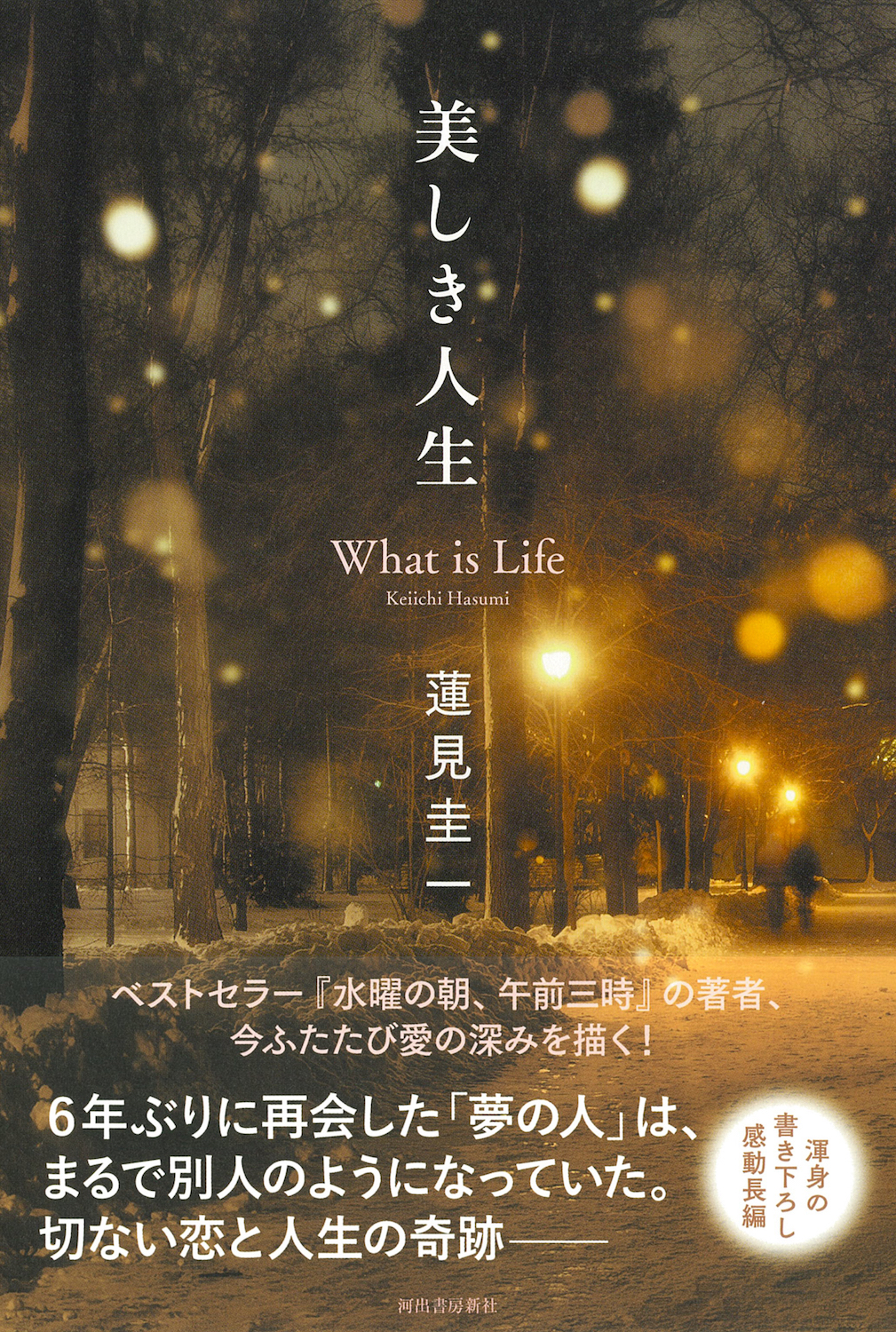書評 - 日本文学
大野露井『塔のない街』刊行記念 「異端にして正統――大野露井論」(13000字)
評者=川本直(小説家・文芸評論家)
2024.04.05
「塔のない街」
評者=川本直(小説家・文芸評論家)
長い間、大野露井に畏敬の念を懐いていた。時代の潮流など気にも掛けずに我が道を行くこの文学者を、私が初めて観測したのは、2014年、とあるWebサイトの辻原登が審査員を務める新人賞でのことだった。大野露井が新人賞を受賞した長編小説『故郷 ―エル・ポアル―』はマルセル・プルーストを自家薬籠中にした者にしか書けない作品だったが、本作は書籍化されていない。他にもWeb上に連載された批評は洋の東西を問わず、古代文学から近代文学までを自由自在に往還するだけではなく、映画から写真から美術をも論じてしまうジャンルの越境振りを示していた。
ネットで検索すると、大野露井はペンネームで露井は雅号、本名はロベルトと言い、国際基督教大学で学び、専攻は日本文学。学位論文「紀貫之の影 日本文学と文化の根本を探る」で博士号を取得 ―― この時点で私の脳内は疑問符で埋め尽くされた。大野の書くものからは深い理解に基づくヨーロッパ文学と日本近代文学からの強い影響が窺えたし、確かに日本の古典文学への言及もあったが、専門が紀貫之とは? いずれにせよ稀に見る万能の文学者が現れたものだ、大野はこれから小説と批評で文壇を席巻していくに違いない、と考えていた。
しかし、大野露井が商業出版の世界にふたたび姿を表したのは翻訳家としてだった。少年愛にまつわる所謂「黒ミサ事件」を引き起こし、作家として正当に評価されなかったフランスの貴族ジャック・ダデルスワル=フェルサンの小説『リリアン卿 ―― 黒弥撒』(国書刊行会、2016年)の翻訳だ。この小説は「遅れてきた世紀末文学者」としてのフェルサンの力量が存分に発揮された、オスカー・ワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』への応答とも取れる、世紀末の唯美主義小説を批評的に書き直したメタ唯美主義小説の傑作だった。世紀末文学の再創造にして集大成である『リリアン卿 ―― 黒弥撒』に私はすっかり魅了され、函入りの華美な装丁も相俟って、今に至るまでこの書物を純粋な歓びのために何度も読み返している。
しかし、特筆すべきは『リリアン卿 ―― 黒弥撒』の優雅で端正な訳文によって綴られた本編だけではなく、40ページにも及ぶ大野自身による「解説」だ。そこで大野は堂々たるジャック・ダデルスワル=フェルサンの作家論を展開している。大野は豊富な写真や図版とともにフェルサンの生い立ちから黒ミサ事件を引き起こしたことによって逮捕・投獄され、釈放後、カプリ島の豪壮なヴィラ、リシス館を拠点とした自主的な追放の日々のなかで、美少年たちと自らの死を招く結果となった薬物に耽溺したこの奇矯な貴族の波乱万丈の生涯を辿りつつ、これまで専ら敵対した作家ジャン・ロランや小説家ロジェ・ペールフィットに「書かれる者」として批判的に描かれてきたフェルサン像を仔細な調査と分析をしたうえで退け、「書く者」「作家」としてのフェルサンの実像を浮かび上がらせて、『リリアン卿 ―― 黒弥撒』は異端のディレッタントの筆によるものではなく、正統な文学的な評価に値する小説だと論じている。
この「解説」は作家論として秀逸なだけではなく、読み物として抜群に面白い。澁澤龍彥の傑作エッセイ『異端の肖像』や『偏愛的作家論』に匹敵する。澁澤と大野とは方法論でも、知られざる作家・忘れ去られた作家を発掘し、その真価を見事な翻訳とエッセイで提示して、甦らせる共通項がある。
今では国書刊行会によって公式名称になってしまったが、「今の時代の諸葛亮(孔明)」に擬えられるほどの知略を発揮した戦国時代の武将・竹中半兵衛がのちに「今孔明」と称された故事に倣い、私が大野露井を「今澁澤」と呼び出したのはこの頃からだ。
その後、大野はロベルト名義で精力的にアカデミシャンとして、ピーター・ノスコ、ジェームス・E・ケテラー、小島康敬編『江戸のなかの日本、日本のなかの江戸―価値観・アイデンティティ・平等の視点から』(柏書房、2016年)、ピーター・ノスコ『徳川日本の個性を考える』(東京堂出版、2018年)、M・ウィリアム・スティール『明治維新と近代日本の新しい見方』(東京堂出版、2019年)の翻訳を出版しつつ、夥しい数の論文・共著・共訳を怒涛のように発表し続け、2019年には博士論文を元にした608ページもある初の単著『紀貫之 ―― 文学と文化の底流を求めて』(東京堂出版)も出版された。日本文学における貫之への研究・批評・言及を全て抑えたうえで、日本文学研究の枠に囚われず、西欧のありとあらゆる文学理論まで援用して、巨視的に貫之を捉え直し、貫之を単なる古典としてではなく、現代に復活させんとする野心的な大著だった。この研究書で紀貫之の専門家として高く評価された大野は、2023年1月10日にNHK Eテレで放送された『先人たちの底力 知恵泉』の「紀貫之 “和歌ブーム”を巻き起こせ!」に出演も果たすことになる。
2020年には正に澁澤龍彥が『異端の肖像』で言及した呪われた作家モーリス・サックスの代表作『魔宴』(彩流社)を大野露井名義で翻訳する。フランス文学史でも傑作の誉れ高いこの小説が、大野の手によって本邦完訳なったのは偉業と言えよう。山師としか言いようがない作者サックスの人柄とは裏腹に、『魔宴』はサックスが酒に溺れ、借金を繰り返しては逃亡する無頼の日々を送りながら、師(メンター)であるジャン・コクトーとアンドレ・ジッドという2人の巨大な存在に振り回され、作家としての自己形成に懊悩しつつも遂には希望を見出す、そしてそれこそが『魔宴』という小説そのものだった、という正攻法の優れた自伝的小説だ。
『魔宴』にも大野自身の手による「訳注」・「付録 ―― 『魔宴』人物帖」・「訳者解説」が付され、「訳者解説」では澁澤と生田耕作によって流布された扇情的なサックス解釈に反論し、『魔宴』がプルーストの『失われた時を求めて』に影響を受けた構造を持つこと、実名の著名人が続々と登場する虚実を混淆した小説であることからトルーマン・カポーティの未完の遺作『叶えられた祈り』との類似性を指摘し、ジャン・ジュネとの共通点、オスカー・ワイルドの影響、そして本邦の太宰治にも通じる小説としての純粋な面白さを強調している。実際、大野の完訳『魔宴』は諷刺的・批判的な筆致の毒々しさこそあるものの、瑞々しい青春小説と言っても過言ではない。大野は日本では異端そのものと考えられていた埋もれた作家をまた1人、正統に復活させたのだった。
私は感嘆するあまり、SNSで「大野露井は『今澁澤』だ」と執拗に繰り返していたが、実のところ、その存在を知ってから7年もの間、2021年の9月まで大野には連絡すらしたことがなかった。当時の大野は公式サイトを持っており、そこには連絡先としてメールアドレスも記されていたのにもかかわらず。その頃の私はマイナーどころかニッチな文芸評論家に過ぎず、この年少ではあるが稀代の文学者と言葉を交わす資格があるとは思えなかった。だが、2021年9月25日、10年掛けて書いた渾身の長編小説を上梓したことで私もようやく覚悟を決め、ドサクサに紛れて無言で拙作を大野に献本した。
それから15日経ったある日、拙作の版元の河出書房新社から1通の封筒が転送されてきた。差出人には「大野露井」とある。おっかなびっくり封を切ると、そこには毛筆で巧みに書かれた優美な字体と洒脱な文体で、私が大野を賞賛していることを知っていたこと、そして拙作への感想が綴られており、大野ロベルト名義の名刺と大野露井名義の名刺が2枚同封されている。早速、大野露井名義のメールアドレス宛に連絡を取ったところ、大野は当時新宿在住で、私の住む東京都下の中央線沿線の街にも大学が近かったことから馴染み深いと返信が来たので、トントン拍子で話は進み、1週間後にコロナ禍もあって拙宅で会うことになった。とはいえ、私は相変わらず大野露井が、いかなる人物か不安に駆られていたのも確かだ。
しかし、拙宅に現れた大野露井を一目見て、私の不安は雲散霧消した。気品のある優しげな雰囲気で、物腰も丁寧、人柄も円満かつ冷静なうえ、飄々としていて、機知に富んだ話し方をする好青年だった。ただし、飄々とした態度のまま的を射た辛辣な評言を口にすることもあるから、もし大野を侮ったりしたら痛い目に遭うことは、この文章を読んでいる者のために付け加えておこう。
私は大野ロベルトがいかにして大野露井になったか、その文学者としての成長過程について幾つか質問した。大野はとても気さくに答えてくれた。
「英語圏出身の家族はいなくて、英語とは縁がなかったんですが、父がこれからはビジネスに役立つのは英語だと言うので、インターナショナル・スクールに入れられてしまったんです。アメリカのジュニア・ハイスクールと同じように中学では原書で『グレート・ギャツビー』とかを読まされるんですよ。それで『僕が読みたいのはこんなものではない。アメリカ文学ではなく、日本文学が読みたい』と思って、ネットを検索していたら、15歳の時に山中剛史さんという愛書家が運営しているサイトに辿り着いたんです。そこに載っている日本文学や翻訳文学の本を片っ端から読んで行きました。山中さんに当時書いていた小説の原稿をメールで送って、感想も戴いたりして。その頃山中さんには実際に会ったことはなかったんですが、ネットを通じて交流していましたね。それからアメリカの大学にビジネスを学ぶために入りましたが、文学がやりたかったから半年で中退して、帰国して国際基督教大学に入り直したんです」
日本文学者であり、三島由紀夫と谷崎潤一郎を専門とし、書物学・書物史・出版史のエキスパートである山中剛史は私の友人でもあるが、「愛書家」などという半端な存在ではない。我が国きっての「愛書狂」だ。日本近代文学の万巻の書に通じているだけではなく、夥しい数の珍本奇書稀覯本を渉猟して所蔵しており、翻訳文学にも詳しい。「今そこでラーメンを食べてきました」と報告するようなさりげない口調で「澁澤と生田耕作の翻訳なら全部読みました」と平然と言ってのける書物の鬼だ。15歳でとんでもない人物に師事したものだと呆然とした。山中剛史と大野露井は、この師にしてこの弟子あり、の典型と言えるだろう。
大野は自分の仕事について淡々と話を続けた。「大野露井名義の翻訳は結局のところ趣味です。ヨーロッパ諸語なら、辞書と文法書さえあればどうにか訳せます。もうすぐ出る翻訳はドイツ文学ですが、その次の翻訳は英文学です。小説ですか? 版元の都合で本が出なくなったんですが、今も書いています」
私は驚きで顎が外れそうになったが平静を装っていると、今度は大野の方が無邪気な表情で心底不思議そうに問い掛けてきた。
「ところで、日本の現代文学で何かお薦めはありますか? 川本さんが日本の小説を最後まで読み通せた一番若い作家です。そもそも澁澤以降に面白い作家なんて存在しますか? 現代小説は何を読んでもつまらなくて」
何たる筋金入りの反時代的な文学者だろう! 日本の現代小説に退屈し切っている私ですら新人賞の下読みをやっている関係上、文芸誌や新刊にも目は通すし、評価している現存の小説家も10人程度はいる。私はその中から大野が好みそうな作家を2、3人挙げた。
最近、元国書刊行会の編集者で、澁澤龍彥最後の担当編集者でもあり、『龍彥親王航海記 ―― 澁澤龍彥伝』の著者でもある礒崎純一が、「大野さんはあれだけダークな作品を翻訳しているのだから、何らかの闇を抱えているに違いない。一緒にお酒を飲んでその闇を聞き出してみよう」という大人気がない陰謀を企てて酒席を設けたことがあったらしいが、「策士策に溺れる」を地で行って酔ってしまったのは礒崎の方で、酒に強い大野は終始いつもどおりだったそうだ。大野は酒癖が良いだけではなく、日常生活でも品行方正そのもので、彼の常人離れした側面は文学のみに発揮されている。
大野と私はその後、盟友と言ってもいい間柄になり、公的にも共著を出し、シンポジウムや学会やトークイベントで共に登壇もしている。だが、断っておきたいのは、私は物書きとはある条件を満たさない限り、決して友人にはならない。私自身が人格的には欠点だらけ且つ浅学非才の身なのに、我ながらいい気なものだとしか思えないが、その条件とは「人間としても物書きとしても尊敬できる者」だ。ほとんどの日本語で書かれた現代小説に倦怠と退屈を感じ、続々と刊行される新作を死んだ魚のような虚ろな目で見ている私にとって、自分と同世代の1980年代生まれで、畏敬の念を懐く作家は大野ともう1人しかいない。つまりこの大野露井論は馴れ合いで書かれたものではない。むしろ親しくない・交流のない作家の書評を執筆する時より、強い緊張感の下で書かれているというのが嘘偽りのない事実だ。
私と初めて出会った年に、大野はロベルト名義で相原朋枝との共編で、日本における舞踏の歴史を総括した『Butoh入門 ―― 肉体を翻訳する』(文学通信、2021年)を出版すると、翌2022年には露井名義でクーデンホーフ光子の長男ヨハネス・エヴァンゲリスト・クーデンホーフ=カレルギーが、ペンネームのチェンティグローリア公爵を名乗って生涯で唯一遺したドイツ語の食人小説『僕は美しいひとを食べた』(彩流社)を翻訳した。この小説は語り手が自らの愛人の夫に、彼の妻を寝取ったうえにその死体を食べたと、夥しい古今東西の食人の逸話と蘊蓄を交えながら、語り掛ける告白小説だ。この小説における大野の文体はこれまでの訳業にも増して流麗かつ優美で、YouTubeチャンネル「ほんタメ」のMCを務める俳優の齋藤明里の目にも留まって紹介されて話題になり、増刷もされた。
大野自身の筆による「解説 さまよえる食人者」はこれまでの訳書解説同様、博学と批評的な知性が冴えを見せる作家論だが、自らについてあまり語りたがらず、謎めいた文学者であることを好んでいた節がある大野が、珍しく自らのルーツを明かしている。チェンティグローリア公爵と重ね合わせている箇所を読んで、翻訳家としてのみならず、ふたたび小説家として再起せんと決意しているのではないか、と私の直観は告げていた。いささか長くなるが、以下の引用は大野が自らの文学観を、身を削って表明したと受け取って良い。
文学とは言うまでもなく言葉の芸術である。日本語であれば、平安時代には漢詩と和歌との邂逅の果てにその潜在能力が解き放たれ、明治時代には、日本を飛び出して外国語を学んだ青年たちの創意工夫によって、西洋の言語と横並びに使用可能な柔軟性を獲得してきたという歴史がある。いずれの言語にも、輝かしい発展と、痛々しい衰退と、騒々しい交錯の局面があり、いつの時代にも、その前衛に立つ「現代文学」があるはずだ。だが、これは理想に過ぎないのかもしれない。現実には、「外国人が書いた日本語の小説」だとか「日本人が書いた外国語の小説」だとかが注目を浴びるのは、ただそれがめずらしいからである。たいていは言語の問題ですらなく、作者がとても若いだとか、老人だとか、はたまた犯罪者だとか、芸能人だとかいうことをもって、作品に付加価値を与えようとする虚仮おどしに、多くの消費者が違和感も抱かずに付き合っているのだ。『僕は美しいひとを食べた』の読者には、どうか著者の実像とうまく付き合いながら作品を愉しんでいただければと思う。
私の直観は2年後に的中することになるが、大野露井は『僕は美しいひとを食べた』を翻訳出版した翌年に、まずはこれも予告どおりイギリスの作家コルヴォー男爵の代表作であり、奇想天外な大長編小説『教皇ハドリアヌス七世』(国書刊行会、2023年)の本邦初訳を出版する。
同年、私が樫原辰郎・武田将明と共編者を務めた『吉田健一に就て』(国書刊行会)に、批評「Queerly Native ―― 奇妙にぺらぺら」を寄稿。明治以来現代に至るまで日本文学は西洋文学を取り込んで歩んで来たことを提示し、英語をネイティヴ並みに使いこなして英文学を知悉した例外的な文学者として崇められてきた吉田健一を「典型的な作家に過ぎない」とあっさり偶像破壊している。しかし、この批評は吉田健一を批判するために書かれたのではなく、吉田健一に対しては偶像破壊を行うだけに留まり、大野は吉田健一を異端的な作家ではなく、日本語で日本の読者に語り掛けた正統な作家として捉え直している。この批評で大野はこれまでの自らの仕事と文学観を総括して語っている。
私にはparty pooper の気がある。これまでに訳した小説の、それまで世間にあまり知られていなかった作者について紹介するときも、なるべく冷静に事実を追いかけ、膨張しがちな幻想を抑制することにある程度の注意を払ってきた。『リリアン卿』を書いたダデルスワル゠フェルサンは「黒ミサ事件」で知られてはいるが、実際に悪魔崇拝の儀式を執り行ったことはただの一度もない。自伝的な性格が強いモーリス・サックスの『魔宴』は、これまた頹廃と悪徳のきわみのような作品であるという、根拠のない伝聞ばかりが広まっていたが、実際には無頼の文学青年の、悲壮なほどに清々しい青春小説である。そして『僕は美しいひとを食べた』のチェンティグローリア公爵は、なるほど奇矯な人物には違いないが、戦争に翻弄された善良な市民であり、混乱のなかで由緒ある家門を守ろうとできるだけの努力をした健気な長男坊でもあった。私は印象論に流れるよりも、ありのままの退屈な姿を見つめたい。大言壮語を鵜吞みにして打ち騒ぐ、沸点の低さというものが耐え難いのだ。
なかなか自らがいかなる文学観の持ち主かを明かしたがらなかった大野のこの文章に触れて、私には初めてこの文学者の真情が見えた気がした。この引用した文章はこれまでの総括であり、次の作品への予告状だったと言えるだろう。
しかし、「これまでの総括」と捉えた面では正しかったが、私が大野という文学者を、更に言えば小説家を大きく誤解していたことを、大野露井が商業出版として小説家デビューを果たした『塔のない街』を読んだ今、思い知らされている。私が大野をどのように誤解していたかは、これからは『塔のない街』を論じながら語っていくことにしよう。
『塔のない街』の時代背景は21世紀初頭。日本の大学を卒業し、就職し損なった「僕」は「日本にいづらくなり」、ロンドンに「日本語で」小説を書きにやってくる。「僕」は十二軒物件を回って週二百十ポンドの広々とした二間の部屋にようやく落ち着く。『塔のない街』は第一章にあたる「劇場」の書き出しから人を食っている。
「ロンドンに雨が降るなんて言ったのはどこのどいつだ?」
賃貸契約書に署名を終えた大家が薄気味悪く笑ったとき、僕も昨日までの朝立や夕立を忘れていた。
ロンドンは霧の都と言われ、曇天の日も多ければ、降水量自体は少ないが、雨の日も多い。冒頭から逆説的な修辞が全開になっている。『塔のない街』は書き出しだけではなく、タイトル自体からして人を食った小説だ。ロンドンには夏目漱石の短編小説『倫敦塔』のタイトルにもなったそのものずばりのロンドン塔の他、ビッグ・ベンにタワー・ブリッジにヴィクトリア・タワーにグレート・パゴタと世界的に有名な塔だらけの街であり、2008年にはロンドン・オリンピックのために建てられたアルセロール・ミッタル・オービットまで加わった。
それでは何故ロンドンは『塔のない街』なのかと言えば、「ロンドンにはエッフェル塔がないからだ。寝ても覚めてもあんな塔が視覚の隅にそびえていたら、きっとどうにかなってしまう」と「僕」は語る。タイトルが名付けられた理由すら人を食っている。
そして「僕」は先日「劇場」で観た映画の話を同じくロンドンに滞在している日本人の友人に話し始めるが、「映画のような世界に生きたいと思っている僕は劇場が好きではなかった。映画だけがあればいいのに、劇場には人間がいるからだ」と言い出す捻くれ振りには笑い出さずにはいられない。
『塔のない街』の辛辣な才気縦横の文体は、増大する経済格差の醜悪さや崩壊寸前の階級社会の腐敗を描くのを好んだイギリスを代表する小説家のマーティン・エイミスの、技巧の限りを尽くしたブラック・ユーモアと言語遊戯溢れる文体を思わせる。
『塔のない街』で描かれるロンドンは、現代の日本人が思い浮かべるような、エリザベス2世の治世を描いたNetflixドラマ『ザ・クラウン』が描く富と権力が集中する首都ではないし、一方『シャーロック・ホームズ』を21世紀に置き換えたBBCドラマ『SHERLOCK』の舞台である暗く憂鬱で陰謀蠢く最先端のテクノロジーが次から次へと登場する現代都市でもない。
つまり大野は『塔のない街』でイギリス文学のお家芸であるうらぶれたロンドンを日本語で描くという離れ業をやってのけているのだ。それはチャールズ・ディケンズの『オリヴァー・ツイスト』や『デイヴィッド・コパフィールド』で描かれた地方出身者が見るロンドン、20世紀末のアーヴィン・ウェルシュ『トレインスポッティング』に至るまで描かれ続けているスコットランドのジャンキーが危険な出稼ぎに来る不穏なロンドン、要はしみったれた貧しく汚らしく治安が悪くこれといった面白味もなく、出会う住民はどいつもこいつもケチでセコくて品がなく、外国人にはろくでもない態度を取る労働者階級のロンドンだ。
だが、僕にはバスを乗り降りする前後に集中する不自由よりも、この街にいるかぎりずっと続くであろう不如意のほうが重くのしかかっていた。(……)すなわち何を買っても五十ペンスの店まで三十分歩き、取って返して最寄駅のスーパー・マーケットで日本の基準では三斤ぐらいの長さのある食パンを大特価十六ペンス=四十円で贖い、映画を観るのはこれで最後にして、そうだ本は図書館で借りればいい。ところがこれだけ倹約しても、(……)二百万円の預金はもって七ヶ月だ。するとどうしてもすこしは働かないといけないが、働くためにここへ来たわけでもない。破産者として帰るのは吝かではないけれど、飛行機代が別にしてあるわけではないから、それだと帰れないかもしれないのである。
全く以てこの「僕」のロンドン暮らしはお先真っ暗で、アイルランド系移民2世とはいえ英国籍の夫がいて、今や押しも押されもせぬベストセラー作家のブレイディみかこのエッセイなど小金持ちの呑気な生活と意見にしか思えない。
しかし、「僕」には仕事もなく、働く気もなく、イギリスに移民する気もなく、日本に帰る気もなく、単にロンドンに住んでただただ小説を書きたいだけとくる。「イギリスは僕のもの 僕を養う義務がある 何故かって聞いてみろ お前の目に唾を吐きかけてやる」、「もし君が明日仕事に行かなくちゃいけないとしたら 僕が君だったら行かないね 人生にはもっと素晴らしい瞬間が待っているはずだから」、「いや、僕は働いたことなんてないよ そんなことはしたくなかったからね」(いずれも拙訳)とサッチャー政権の福祉切り捨てで追い詰められた1980年代イギリスのニート・失業者・無職・引きこもりの不満と絶望をユーモアたっぷりに高らかに謳い上げて人気を博したザ・スミスのモリッシーさえも苦笑いしそうな、モラトリアムここに極まれりの日々で『塔のない街』という小説は幕を開けるのだった。
一体どうするんだよ……と思いきや、「僕」は予定どおりロンドンで小説を書き続ける以外何もしない。『塔のない街』は古くは『千夜一夜物語』、『デカメロン』、イギリス文学ではチョーサーの『カンタベリー物語』、日本文学では『御伽草子』が用い、20世紀のメタフィクションでも盛んに再利用された「枠物語」、つまりは入れ子構造になっている。この中編小説を構成する7つの物語は文体も主題も内容も構造もそれぞれ違う。よくぞここまで異なるスタイルを変幻自在に駆使できたものだと舌を巻かざるを得ない。
「窓通信」はロンドンで無為に過ごしている「僕」が窓から見掛けた向かいの建物に住む女性に宛てた手紙と、それへの女性の返信からなる書簡体小説だ。「僕」は不毛なロンドン生活に押し潰されそうになっており、面識がないことをいいことに偏執的な手紙を送り続けるが、相手の女性も一癖も二癖もある人物で、この物語は驚くべき結末を迎える。奇妙な味わいを持つ窃視症小説ともストーカー小説とも言える1編だ。
続く「狂言・切り裂きジャック」は『シャーロック・ホームズ』のSF版パロディとも言うべき短編で、名探偵ハイランドと助手のハウスンがヴィクトリア朝末期にタイムスリップして、切り裂きジャックが引き起こしたとされる「ホワイトチャペル殺人事件」の真相と切り裂きジャックの正体に挑む。
「舌学者、舌望に悶舌す」では物件探しをしながら、金のない無職の外国人ゆえトラブルに遭遇しがちな「僕」の目から見たロンドンがイギリス英語混じりで諷刺される。ロンドンでの日常を描いた短編だが、その辛辣で苦々しい筆致は抱腹絶倒だ。
「秋の夜長の夢 ド・ポワソン著」は「僕」が、大英図書館の図鑑の間に挟まっていた十枚の紙にフランス語で書かれた、フランスの外交官と名乗るド・ポワソン(フランス語でポワソンは『魚』の意)の日本訪問記を発見して、日本語に翻訳したという設定で、芥川龍之介の『奉教人の死』、『きりしとほろ上人伝』を思わせるが、フランス語、日本語、英語の三言語を往還しつつ、詳細な分析まで付与するという芥川より更に手が込んだ方法論を用いた擬似翻訳小説だ。
「おしっこエリザベス」はがらりと趣向を変えて『不思議の国のアリス』のパロディ。アリスならぬエリザベスは小人の国の危機と魔女征伐をタイトルどおりおしっこでやってのけるのだ! 童話を糞尿譚に書き換える悪ふざけが冴えを見える。
そして最終章「塔のある
友人が帰って行った後、「僕」は荷造りをして、大家に置き手紙を書くと、部屋を出る。『塔のない街』はこの「僕」が書いた大家への置き手紙で終わるが、意表を突いたその手紙の内容は読者の楽しみを奪わないために書かないでおこう。
182ページの短さにかかわらず、枠物語の構造を使い、スタイルを千変万化させたそれぞれ独立して読める各章を、有機的な繋がりをはりめぐらして中編小説として成立させた超絶技巧には感嘆せざるを得ない。
「小説で書かれるエピソード自体がその小説そのものだった」という大野露井が偏愛し、本編でも幾度も言及されるマルセル・プルーストの『失われた時を求めて』と同じ構造が『塔のない街』では採られている。そして再話・翻案・擬似翻訳・パロディ・パスティーシュ・オマージュなどといった大野が用いた技巧は澁澤龍彥の十八番で、『塔のない街』は澁澤の『唐草物語』に比肩し得る傑作だが、澁澤には自意識がほとんどなく、まるで前近代人のように、面白いテクストを渉猟しては自作に組み込み、ひたすら再話を繰り返す、近代的自我と無縁の作家だ。
しかし、『塔のない街』は洗練の極致にある優雅にして華麗な小説だが、自意識が強い「僕」はモラトリアムの只中でひたすら小説を書き続け、文学への強い情熱を懐き続けている。澁澤よりももっと大野に酷似している日本近代文学を代表する小説家を私は思い浮かべずにはいられなかった。それは明らかに近代人だった芥川龍之介だ。
大野が弄ぶ機知に富んだ警句や皮肉や韜晦や逆説や反語や博識に惑わされ、煙に巻かれてはならない。『塔のない街』は芥川がそうだったように純粋な文学への希求によって、このような様式で構築されざるを得なかった言語の塔なのだ。
要するに大野は真摯に創作をしたいがためだけに、それには古代から現代に至るまでの膨大な読書のみならず、文体や構成の技巧、知識、教養、他言語の習得が必要と考え、ひたすら自己修練を詰んで来たに過ぎず、その博覧強記や他言語使用は、大野の核ではない。私は大野露井が本来の目的のために身につけたツールに過ぎないものを本体と誤解していたことになる。大野が優れた小説を生み出すために習熟した武器の数々ばかりに目が行っていたのだ。これほど純粋な小説家には現代では滅多にお目にかかれない。
つまり大野露井は異端では全くない。「異端」と呼ばれて忘れ去られた・埋もれた作品を発掘して、正統的な価値を提示して見せる訳業からも明らかなように、大野露井は文学者としても、更に言えば小説家として紛れもなく「正統」なのだ。
そして芥川龍之介も澁澤龍彥も傑出した作品を生み出しながらも、「未完のプロジェクト」だったことを忘れてはならない。芥川はあれだけの知性と技巧に恵まれ多様な傑作を物しながらも、短編小説しか書けず、長編小説はおろか中編小説すら完成させることもないまま35歳の若さで精神を病んで睡眠薬自殺を遂げた。澁澤は優れた翻訳とエッセイを発表しながら、晩年は徐々に小説に回帰していき、最高傑作にして唯一の長編小説『高丘親王航海記』を完成させた直後、咽頭癌で59歳の早過ぎる死を迎えた。もし生きていればさらなる小説家としての飛躍が続いたことは間違いないだろう。芥川も生きていればいずれは長編小説とは言わずとも中編小説は書けたはずだ。もしかしたら大野は、芥川と澁澤という2人の「未完のプロジェクト」を継承し、完成させようとする野心を抱いているのではないだろうか。
ここまで縦横無尽に異なるスタイルを軽妙洒脱に使いこなしつつも、その奥に純粋な情熱を秘めている大野露井からは、『塔のない街』の舞台がロンドンだからでもあるが、イギリスのミュージシャンのポール・ウェラーをも連想せざるを得ない。ウェラーはモッズ・スーツを身に纏って率いたパンク・バンドのザ・ジャムでデビューしたが、すぐにR&Bに接近していき、ザ・ジャムを解散。その次に結成したユニットは「スタイルの評議会」を意味するスタイル・カウンシルで、ソウル、ジャズ、ポップ、ファンクなど1曲1曲全く違ったスタイルを導入し、ラスト・シングルは当時最新のハウス・ミュージックだった。その後ウェラーはソロに転じて一旦スタンダードなロックに回帰したが、すぐにソウル、フォーク、エレクトロニックまでスタイルを変え続けているものの、その音楽には常に純粋な熱情が漲っているため、表面上どのジャンルを選択しようと彼はいつでも「ポール・ウェラー」だ。大野露井がいかなるスタイルを用いようが、小説・翻訳・批評・学術論文とそれぞれ違ったジャンルを手掛けようと、いついかなる時でも「大野露井/ロベルト」であるように。スタイル・カウンシルという形容が似合う多種多様なスタイルの集積である『塔のない街』と、全編を貫く大野露井の文学へのパッションが、私にポール・ウェラーを想起させたのはごく自然なことだ。
ところで、何故、大野露井は『塔のない街』でここまで21世紀初頭のロンドンの地味なローカル性を描くことが出来たのか。大野とイギリスは文学を除いて縁が無いとばかり思っていたので、先日顔を合わせた時に何気なく海外渡航経験について訊いてみた。
「アメリカにいたのは大学を中退したので半年だけですし、フランスやイタリアやその他の国々は短期滞在か旅行だけ。住んだのはロンドンだけです。1年以上住んでいました」
「やられた!」と思った。大野は日本文学以外ならフランス仕込みだと思ったが、れっきとした英国仕込みだったのだ。そう考えるとロンドンを舞台にそのローカル性と歴史と文化を存分に活かした小説を書いたのも説明がつくし、ブラックなユーモアのセンスもイギリス文学由来だろう。大野と同様、英国仕込みの吉田健一を「典型的な作家」と喝破したのも頷ける。
最後に、傑作『塔のない街』を上梓して、見事な小説家デビューを飾った大野露井の近況をお伝えすることで、このいささか長い作家論を終わりにしよう。
現在、大野は澁澤龍彥が生前翻訳を希望したが、その早逝によって果たせなかった作品群の訳出を行うプロジェクトに着手しつつある。亡き澁澤の妻である澁澤龍子さんにその許可を得るために、北鎌倉の澁澤邸にも大野と同行して赴いた。龍子さんが飼っている柴犬で、天真爛漫で人懐っこいがわがままで人間より主人然としているところが故・澁澤龍彥と酷似している「もみじ」が、大野に異様に懐き、龍子さんが振る舞ってくれた料理で大野が食べるものなら何でも興味を示して口にしようとし、最後には大野に熱を上げるあまり全身で飛びかかってしまって、罰として別室に監禁されたのには笑いをこらえるのに必死になったが、これは飽くまで余談なので、このへんにしておこう。
それにしても大野露井という規格外にして正統派の小説家の登場を心から嬉しく思う。大野露井が20世紀末から退屈が覆う廃墟だった日本現代文学をふたたび活気溢れる「街」に変えていくことは間違いない。
本編は単行本「塔のない街」でお楽しみください。
*******************************************************************
「ジュリアン・バトラーの真実の生涯」
著者:川本直