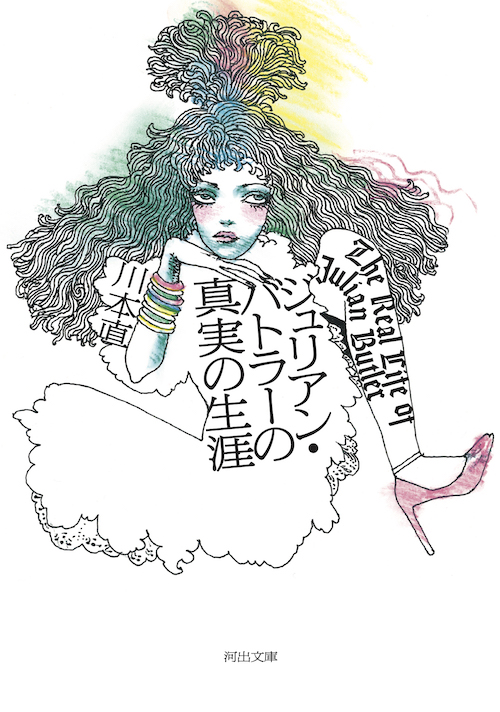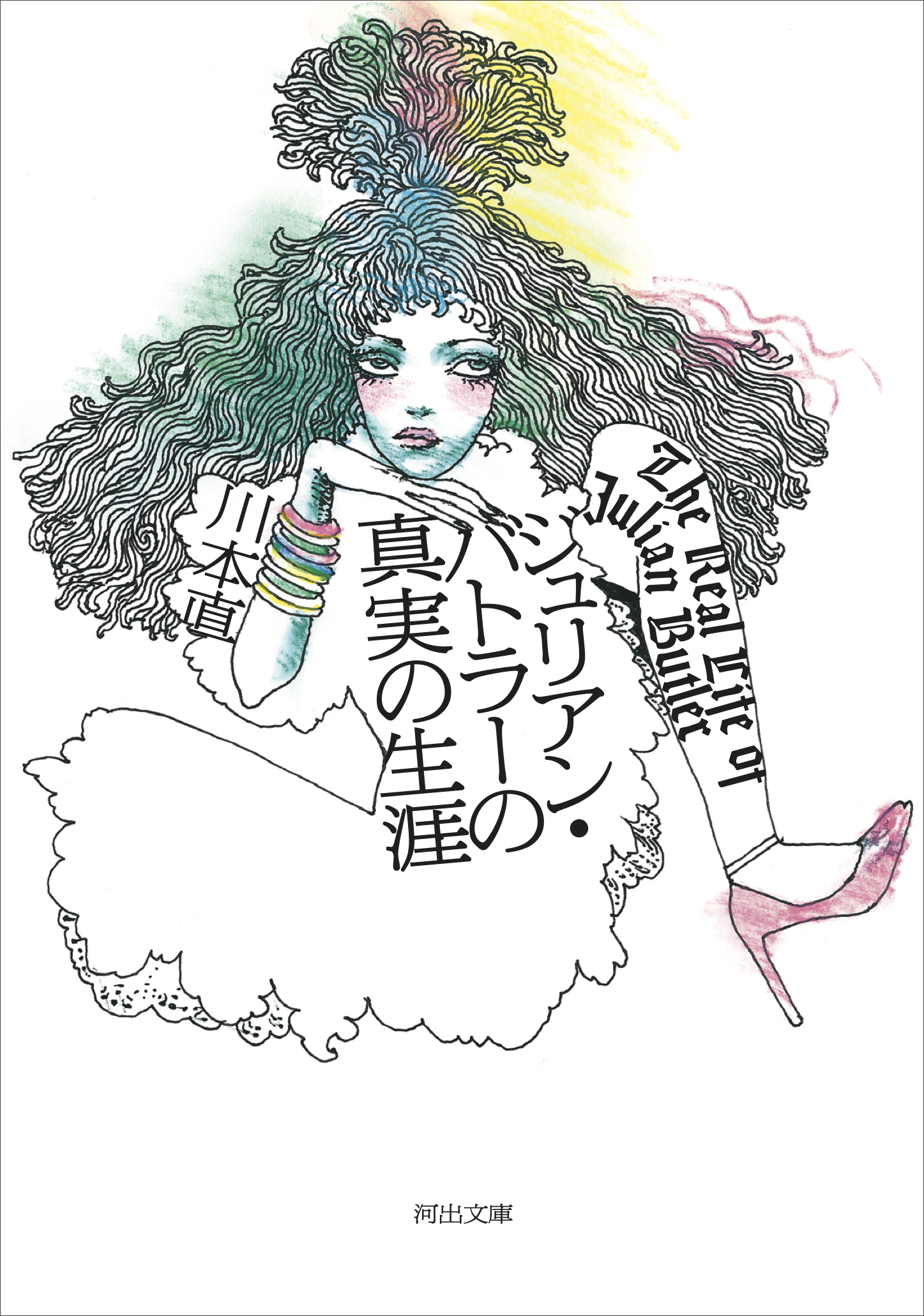
ためし読み - 文庫
初小説が読売文学賞受賞の快挙の話題作が待望の文庫化! 川本直『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』試し読み
川本直
2023.11.07
作風は優雅にして猥雑、生涯は華麗にしてスキャンダラス。トルーマン・カポーティ、ゴア・ヴィダル、ノーマン・メイラーと並び称された、アメリカ文学史上に燦然と輝く伝説の小説家ジュリアン・バトラー。その生涯は長きにわたって謎に包まれていた。しかし、2017年、覆面作家アンソニー・アンダーソンによる回想録『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』が刊行され、遂にその実像が明らかになる ―― 。
宇野亞喜良さんが装画を描き下ろし&魔夜峰央さん、齋藤明里さん、東山彰良さん推薦! もうひとつの20世紀アメリカ文学史を大胆不敵に描く、あまりにも壮大なデビュー作が待望の文庫化。
知られざる作家──日本語版序文
ジュリアン・バトラーの名前を知ったのは一九九五年、十五歳の時だ。トルーマン・カポーティとゴア・ヴィダルを耽読していた僕は、二人と並び称されるジュリアン・バトラーという作家を発見した。戦後アメリカ文学を代表する小説家だが、邦訳は全て絶版になっている。日本では未だ知られざる作家と言っていい。
現在も英語圏ではバトラーの全ての長編小説はペンギン・モダン・クラシックスから再版され、作家自身も著名人としての華麗な遍歴で知られているが、作品論やテクスト論はあっても作家論や評伝はない。バトラーの生涯はその名声に反し、長きにわたって夥しい伝説的なゴシップの靄に包まれていた。
二〇一七年に出版されたアンソニー・アンダーソンの回想録『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』によって、謎めいたバトラーの実像は遂に明らかになった。アンダーソンは覆面作家だったが、この回想録で自らの正体も公にしている。
本書は Anthony Anderson. The Real Life of Julian Butler: A Memoir. (Random House, 2017)の全訳である。『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』は二十世紀アメリカ文学の裏面史であり、「作者とは誰か」「書くとは何か」をめぐる回想録でもある。
アンダーソンは二〇一六年に亡くなり、本書が遺作となった。訳者は奇妙な偶然からアンダーソンに生前唯一のインタビューを行っている。死後の調査も含めて『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』では語られなかった事実も判明した。アンダーソンの遺言執行人である小説家のジーン・メディロス、コロンビア大学の王哉藍教授の意向により、日本語版である本書には後日譚を綴った「ジュリアン・バトラーを求めて」を訳者あとがきに代えて収録した。メディロスと王教授には、バトラーとアンダーソンが知られていない日本では「ジュリアン・バトラーを求めて」の併録を以て完全版、と過大な評価を戴いている。
川本直
* * * * * * * *
ジュリアン・バトラーの真実の生涯
私は自分の名前が嫌いだ。名前への違和感はしつこい靴擦れのように私につきまとっていた。ジョージ・ジョンという、このファースト・ネームを二つ連呼するような名前を呼ばれる度に不快感が押し寄せてくる。ジョンはヘブライ語のヨハナンに由来し、ファースト・ネームが何かの拍子にラスト・ネームに変化したものらしい。洗礼者ヨハネや使徒ヨハネの名と同じく「ヤハウェは恵み深い」を意味するが、生憎私は不可知論者だ。イングランド史上最低の国王の名前と同じなのが気に食わないし、口語や俗語の意味合いは口にしたくないほど酷い。まだ「ジョンの息子」という意味の、ありふれたジョンソンの方がマシだった。ジョンはウェールズに多い姓で、確かにオーガスタス・ジョンという画家はいたが、私の家系は二代前までしか遡れないので祖先についてはわからない。誰だか知らないがジョンというラスト・ネームを一族につけた人間を呪い、アメリカの初代大統領にちなんでジョージという凡庸なファースト・ネームをつけた父を憎んだ。この永続的な苦痛についてジュリアンと話したのはもう七十三年も前になる。
* * * * * * * *
アメリカがジュリアン・バトラーの小説を初めて目にしたのは同性同士のセックスが犯罪とされ、男色家の集うバーがひっきりなしに摘発され、発展場で交わる男たちが四六時中逮捕され、五千人以上の同性愛者が公職を追放されていた時代のさなかだった。「エスクァイア」一九五三年十二月号表紙には『ネオ・サテュリコン』の掲載を告げる文言は何もなく、文芸欄にひっそりと第一章が発表されたにもかかわらず、罵倒と中傷が一斉射撃のようにジュリアンの身に降りかかった。「反アメリカ的で背徳的」「ニューヨーク・タイムズ」)、「性倒錯の見本市」(「タイム」)、「気が触れた頭脳から生み出された猥褻文書」(「ニューヨーク・ポスト」)、「こんなポルノグラフィーを支持するのはホモセクシュアルだけだ」(「デイリー・ニューズ」)。マッカーシズム吹き荒れる一九五〇年代初頭のアメリカ合衆国は保守的で偏狭な国家だった。共産主義者に対する赤狩りと同性愛者に対するラベンダー狩りが同時に進行していた。
災厄は燃え広がり、海外にも飛び火した。多くの書店とニューススタンドは「エスクァイア」の販売を拒否し、プロテスタントの教会では焼かれ、テキサスとマサチューセッツで発禁になった。バチカンではローマ教皇ピウス十二世が、世界中から集まってくるカトリック信者との謁見で「親愛なる兄弟姉妹の皆さん、ジュリアン・バトラーの『ネオ・サテュリコン』を読むべきではありません」と語るに至って、騒動はますます大事になっていった。ホロヴィッツはカーネギー・ホールのコンサートの翌月から鬱病の悪化で隠遁していたが、ホロヴィッツ夫人ワンダから抗議の電話が「エスクァイア」編集部に寄せられるおまけつきだった。しかし、二十一世紀になった今では、結婚していたにもかかわらず、ホロヴィッツが同性愛者だったというのは定説だ。「エスクァイア」はただちに回収されることになったが、引き起こされたスキャンダルによって未曾有の売上を記録し、書店にも版元にも在庫はなかった。
お上品な「ニューヨーカー」には当代きっての批評家であるセオドア・プレスコットが、わざわざジュリアンをこき下ろすために書評と簡単なバイオグラフィーを執筆した。
ジュリアン・バトラーが遂にその姿を現した。一九四七年頃から我々出版界の人間に彼の名前は知れ渡っていた──名声ではなく、悪名で。ジュリアン・バトラーはマサチューセッツ州選出の民主党所属の上院議員、故ロバート・バトラーの息子として一九二五年に生まれた。一九四七年当時、二十二歳だったバトラーは最初の小説『二つの愛』の原稿を抱えて、二十社に及ぶ出版社に持ち込み、その全てから断られて、物笑いの種になっていた。
我々はそれを専らジョークと考えていた。ニューヨークの女装の男娼の性的遍歴を描いた小説は猥褻そのもので、一切の道徳観を欠いた代物だった。バトラーはその小説中で絶えず、自然な性的概念を嘲笑い、同性愛と服装倒錯と薬物中毒を讃えていた。どこにも文学的な価値は見出せなかった。ゴア・ヴィダルが一九四八年に発表したいささか欠陥の多い同性愛小説『都市と柱』ですら、バトラーの『二つの愛』に比較すれば、真摯で視野が広い堂々たる文学に見えてしまう。
だが、公平を期さねばならない。送りつけられてきた原稿を目にすることができた幸運な──否、不運な──編集者が困惑したのは、どこまでも不道徳な物語が才気縦横の文体で書かれていたからだ。バトラーの文才を評価した「マドモアゼル」の名編集者ジョージ・デイヴィスは「女装の男娼」を「売春婦」に置き換えれば出版できるかもしれない、と私に漏らしたことがある。
アメリカ中の出版社から『二つの愛』を拒否されたバトラーはフランスに渡り、ポルノグラフィーを扱う怪しげなパリの出版社オリンピア・プレスから一九四八年にこの小説を発表した。『二つの愛』は英語圏のどの国にも持ち込むことを禁止されているが、密輸入されて今も世界中に行き渡っている。
その後、バトラーはヨーロッパを放浪しているとの情報が入ってきた。『二つの愛』で描かれた吐き気を催すような行為に自ら従事しているのではないか、という噂も流れた。事実がどうあれ、バトラーが放浪生活を送っていたのは間違いないが、彼はその間に作風を一変させた次の小説を書き溜めていた。
第二長編『空が錯乱する』はローマの皇帝ネロと去勢して結婚した少年スポルスの生涯を描いた小説だった。タキトゥス、スエトニウス、カッシウス・ディオの歴史書からの緻密な時代考証に支えられ、著者自身が実際目にしただろうイタリアの遺跡群から再現されたと思しき古代の描写には迫真性が漲っていたが、主題は相も変わらず嘆かわしいほどの倒錯行為の賛美だった。
バトラーは一九五〇年、またもやパリのオリンピア・プレスから『空が錯乱する』を出版し、『二つの愛』と同じくアンダーグラウンド・ベストセラーとなった。それから暫く彼の話は聞かなかった。パリでジャン・コクトーに弟子入りしているだの、ロンドンのピカデリー・サーカスで男娼をしているだの、タンジールで少年を買っているだの、様々な噂が流れたが、どれも確証は得られなかった。
そして、今年が終わりを告げようとしているさなか、突如バトラーは第三長編『ネオ・サテュリコン』の第一章を「エスクァイア」に発表し、遂にアメリカに姿を現した。『ネオ・サテュリコン』は古代ローマの作家ペトロニウスの『サテュリコン』を下敷きにし、舞台を現代のニューヨークに移し替えている。『サテュリコン』は放浪の学生エンコルピウスの一人称だが、『ネオ・サテュリコン』はエンコルピウスの稚児の美少年ギトンにあたる女装の語り手ジュリーの一人称で綴られている。言うまでもなくジュリーはジュリアンの女性形で、主人公と作家自身の混同を狙った嫌らしい目配せに違いない。ジュリーはエンコルピウスにあたる男色相手の大学生のクリスを連れて、ホロヴィッツのコンサートに赴き、猥褻行為に及ぶ。その帰りに立ち寄った成り上がり者のオカマがホストを務める悪趣味なパーティで痴情の縺れから起こった殺人事件に居合わせ、犯人と誤認した警察から追われることになる。この場面は『サテュリコン』の解放奴隷トリマルキオの饗宴にあたる。ジュリーとクリスは面白半分に逃避行を楽しみ、いかがわしいバーで見つけた美少年と三人で性行為に及び、ホモが集まる浴場での乱交に加わったりしながら、マンハッタンを傍若無人にうろつき回る。ここで第一章は終わっている。
ペトロニウスの『サテュリコン』は現代の我々から見れば不道徳極まりないが、小説の礎を作った古典であり、我々はこの小説に倣わねばならない。偉大なるアメリカ小説『グレート・ギャツビー』のジェイ・ギャツビーはトリマルキオを意識して造形され、実際フィッツジェラルドはタイトルの候補として『トリマルキオ』、『ウエスト・エッグのトリマルキオ』を考えていたこともあった。ところが、『ネオ・サテュリコン』は『サテュリコン』から道徳的に堕落した態度ばかりを模倣している。リンカーンのゲティスバーグ演説の「人民の人民による人民のための政治」をパロディにした書き出しから反米的だ。便所でのおぞましい濡れ場ではホロヴィッツが弾くメンデルスゾーンの結婚行進曲が流れる。おまけに登場する成金のオカマはハリー・S・トルーマン大統領と同名で、貞淑なファースト・レディ、ベス・トルーマンに自らをなぞらえ、エリザベスと名乗っている。このような冒涜は枚挙に暇がない。文体にはホモの間でしか通用しないスラングが溢れ返り、これまでの小説よりさらに道徳的な逸脱を強めている。
果たしてこんなものが文学と言えるだろうか? ジュリアン・バトラーは何がしたいのか? 我々を驚かせたいのか? それとも名声を得ることが叶わないならせめて悪名を得たいのか?
バトラーの小説の根本的欠陥は倫理的な理由で不道徳だということに留まらない。美学的な意味においても道徳欠如なのである。何故なら、バトラーは我々の偉大なるアメリカン・カルチャーを嘲笑することに終始しており、その小説は精神的な虚無と腐敗から生み出されたもので、完全に無意味だからだ。
ジュリアンは反撃に出た。創刊間もない「プレイボーイ」が好奇心からジュリアンにインタビューを申し込んできたのだ。「プレイボーイ」一九五四年二月号が掲載した四ページの特集記事のタイトルは「ジュリアン・バトラー──華麗なる背徳者」という仰々しいものだった。特集の一ページ目にはジュリアンの肖像写真がフルカラーで掲載された。ジュリアンは薔薇のコサージュをあしらったミニハットを被り、レースのフリルがついた漆黒のヴィクトリア朝のドレスを着込んでいた。ドレスの裾は短く仕立て直され、膝上までしかない。裾から覗く黒の網タイツに包まれた細く引き締まった脚を見せびらかすように投げ出して、ピンヒールを履いたままロココ調の天蓋つきのベッドにしどけなく寝そべっていた。ウェーヴをかけた二つ結いの深い黒髪に右手を当てたジュリアンは煙草を吸いながら物憂げな眼差しでこちらを見つめている。これ見よがしに両性具有的なオーラを発散しているジュリアンは少女のようにも少年のようにも見え、とても二十八歳だとは思えなかった。以下の文章はそのインタビューの全文だ。
プレイボーイ あなたの小説『ネオ・サテュリコン』の第一章は大きな波紋を呼び、多くの批評家に批判されています。バチカンもプロテスタントも問題視しています。反論はありますか?
バトラー ほとんどの批評は主題が同性愛って決めつけて、ヒステリックに反応してるだけ。連中は愚か過ぎて答える価値がない。だから、僕から言うべきことは何もない。そもそも僕はカトリックだよ。ワシントンD.C.で暮らしていた子供の頃は聖歌隊で歌ってたんだ。バチカンでピウス十二世に拝謁したこともある。この頃はミサに行ってないけど。こっちは敬虔な信者なのに向こうが嫌がるから。でも、僕にお怒りらしい教皇聖下がお望みとあれば、いつでもまたバチカンに告解に行くよ。一世一代の女装でおめかしをして。
プレイボーイ 同性愛は自然ではないと考えられています。肛門性交はほとんどの州で犯罪です。
バトラー アメリカの人間はピューリタニズムに毒されて同性愛を異常だと考えてるけど、一九四八年のキンゼイ博士の『人間における男性の性行動』を読めば同性愛は異常でも何でもないとわかるよ。同性愛者が人口に占めるパーセンテージは高い。アメリカ人の頭の中身が未だに野蛮な十九世紀に留まっているってことは嘆かわしくない?
プレイボーイ セオドア・プレスコットが「ニューヨーカー」に書いた批評をどう思いますか?
バトラー 名誉毀損もの。僕は男娼なんかやってない。ミスター・プレスコットは僕の小説と僕自身の区別がついてない無能だよ。大体あの批評は馬鹿げてるよ。僕は虚無主義に取り憑かれてなんていない。プレスコットが同性愛を不毛だと考えてるだけ。それに彼の文学観は視野が狭いよ。フランス文学の動向を見ていれば、今ジャン・ジュネって同性愛者の泥棒が高い評価を勝ち得ていて、サルトルが彼について『聖ジュネ』って大著を書き上げたことくらい知ってるはず。プレスコットは未だにヘミングウェイやフィッツジェラルドみたいなロスト・ジェネレーションの小説家なんかをアメリカ最高の作家として崇め奉ってる。でも、第一次世界大戦後から第二次世界大戦までで注目すべき小説家はナサニエル・ウエストくらいじゃない? プレスコットが近頃の作家で賞賛してるのはJ・D・サリンジャーやソール・ベローとくる。前者は中流階級の餓鬼の泣き言を人生の真実か何かと勘違いしてる幼稚で哀れな作家で、後者は「今は十九世紀だっけ?」と思っちゃうほど古臭い退屈な作家だよ。他にいくらでもいい作家はいるじゃない? トルーマン・カポーティ、ゴア・ヴィダルやポール・ボウルズの小説は優れている。去年出版された本だとドラッグ中毒を描いたウィリアム・リーの『ジャンキー』が面白かったけど、プレスコットを始め、中流階級の批評家どもはそれを認めない。まあ、せいぜい平民同士仲良くしてればいいんじゃない? ところで、プレスコットが実はその経歴を小説から始めたこと知ってる? ヘミングウェイの下手くそなエピゴーネンで何の話題にもならなかったよ。すぐに絶版。それで、プレスコットは批評家に転じて偉そうなことを言っているわけ。遥かに格下の、小説家になれなかった批評家の批判に抱く感情は怒りじゃない。心からの憐れみだよ。
プレイボーイ あなたの小説は一冊もアメリカで出版されていませんが、何故かあなたはアメリカで有名です。これはどういうことでしょう?
バトラー 『二つの愛』はアメリカの有力な出版社の多くから出版を断られたけど、増刷版の表紙にはジャン・コクトーの賞賛の言葉が載ってるよ。『空が錯乱する』も売れたし、両方ともフランス語に翻訳されてる。海外での僕の評価は高い。この保守的で、文学が何なのか理解できないアメリカというド田舎で理解されないからといって、僕は痛くも痒くもない。僕の本は読者がこっそりフランスから密輸入してるし。ただ、僕が有名なのはそれだけじゃないんじゃない?
プレイボーイ と言いますと?
バトラー 僕が美しいからじゃない? 別にオスカー・ワイルドよろしく向日葵の花束を抱えて半ズボンに白タイツでピカデリー・サーカスを闊歩していたわけじゃないけど、僕はいつも女装している。誰も僕が男だって気づかない。『二つの愛』を持ち込んだ時、いつもの女装でとある出版社に行ったことがあったんだ。それに尾鰭がついて、僕が『二つの愛』の主人公みたいに女装の男娼だった、って根も葉もない噂が広まったんじゃない?
プレイボーイ あなたは同性愛者なのですか? 女性とのロマンスなどはなかったのですか?
バトラー 僕は忘れっぽいから、セックスした相手の性別なんか憶えてない。そんなことは重要じゃないし、どっちでもいい。自分を男とか女とかに分類したことも一度もないけど、別に同性愛者と呼ばれようと服装倒錯者と呼ばれようと気にしないよ。好きに呼んで。
プレイボーイ あなたはこれからどうするつもりですか? 『ネオ・サテュリコン』をアメリカで出版することは不可能だと思います。そもそも『ネオ・サテュリコン』は完成しているのでしょうか?
バトラー 完成してるよ。オリンピア・プレスの社長、モーリス・ジロディアスが出版を決定してる。以前の二作と同じようにパリで出版される。僕にとって書くのは酷く退屈だし、書くのが早いからあっという間に仕上げちゃうんだ。空いている時間はパーティでハメを外してる。
プレイボーイ 現在、アメリカではあなたはポルノ作家として扱われています。あなたが将来、文学的な評価を得ることはあると思いますか?
バトラー もうすぐ時代は変わる。戦時中、それまでは階級や土地によって隔てられて交わらなかった人間が、軍隊で一堂に会してアメリカは変わった。孤立していた同性愛者にも同じことが起こったんだ。マッカーシーなんて一時の反動に過ぎないよ。これからもこの国は変わっていく。それに伴って僕の小説が単なるポルノグラフィーじゃないって理解されていくんじゃない? 少なくとも僕の悪名がプレスコットのわずかな名声より長く保たれることは証明済みの事実だと思うよ。
「プレイボーイ」のインタビューはジュリアンの立場を良くするどころか、却って反感を煽り立てた。有力各紙は「プレイボーイ」のインタビューを取り上げて攻撃を再開した。ジュリアンは毒舌で知られるゴシップ・コラムニスト、ウォルター・ウィンチェルから「カトリックのオカマ野郎」というあだ名を奉られる羽目になった。FBI長官のジョン・エドガー・フーヴァーがブラックリストにジュリアンを入れたというきな臭い情報も入ってきた。状況は切迫していた。ジュリアンはチェルシー・ホテルに住んでいて、晴れた日は五番街を優美に女装して散歩をするのが日課だった。五〇年代のアメリカには変装罪という代物があり、異性装をしていれば逮捕される危険があった。ジュリアンは誰も男だと気づく者がいないのをいいことに、ニューヨークのど真ん中を闊歩していた。しかし、「プレイボーイ」のインタビューで面が割れてしまった。マンハッタンを歩いていると「変態!」「オカマ!」と罵られ、面白半分に殴りかかってくる輩も少なくなかった。初めのうちこそジュリアンはロンドンで購った黒い日傘を振り回して応戦していたが、街に出る度に襲撃されるのにうんざりしてしまい、ニューヨークを去ることに決めた。
災厄は「エスクァイア」の編集者だった私にも訪れた。「モグラ部屋」と呼ばれていた私のオフィスにはエージェントを通じて届けられた新人小説家の原稿やエージェントを介さず送りつけられてくる有象無象の原稿が、デスクのみならず、棚や床の上にも堆く積み上げられていた。社員はそれを「ゴミの山」もしくは「クソの山」と呼んでいた。「エスクァイア」の文芸欄担当編集者は私一人だった。あとはアシスタントとタイピストがいた程度だ。
「エスクァイア」一九五三年十二月号が発売された当日、出版主のアーノルド・ギングリッチが「モグラ部屋」に怒鳴り込んで来た。
「ジョージ! どうしてあんなものを載せたんだ!」
「たまには野心的な作品を載せようかと思いまして。かつて猥褻裁判に勝利した『エスクァイア』にふさわしい小説かと」私は努めて柔和な笑顔を作った。
ギングリッチの顔は紅潮して熟し切ったトマトのようになった。
「もういい! お前はクビだ!」
こうして私は職を失った。当時の「エスクァイア」は四〇年代こそヘミングウェイやフィッツジェラルドのエッセイや短編を掲載して注目されていたが、五〇年代初頭はお寒い限りで、ギングリッチはオルダス・ハクスリーのような大御所に自ら原稿を依頼して回り、涙ぐましい努力を続けてきた。一九五〇年に「ニューヨーカー」から「エスクァイア」に移籍してきた私は、小粒だが良質な新人作家の短編小説やエッセイを採用して彼を補佐した。ギングリッチはすっかり私を自分の片腕と見込んで、近頃は文芸欄の校正刷りをまともに見ようともしなくなった。私は『グレート・ギャツビー』を下敷きに自分ででっちあげた郊外の住人のパーティをめぐる退屈な物語を『ネオ・サテュリコン』の第一章として校正刷りに組んで同僚たちを騙し、校了直前に本物とすり替えたのだ。印刷所の職員にはポケットマネーから口止め料を弾んでおいた。わざわざ「エスクァイア」名義で十二月号を名だたる書評家や編集者に献本もした。以前の職場の「ニューヨーカー」にもプレスコットにも送った。「プレイボーイ」の発行人は「エスクァイア」から独立したヒュー・ヘフナーだったこともつけくわえておこう。つまりはそういうわけだ。ギングリッチは手酷く裏切られたと考えていたようだが、それまでの穏当な編集方針は『ネオ・サテュリコン』を掲載するための偽装工作だった。私はジュリアンをアメリカに紹介したかった。優れた小説家だと考えていたからか? それもある。しかし、最も大きな理由はジュリアンが私の十年来の伴侶だったからだ。
幸いジュリアンと私が学んだフィリップス・エクセター・アカデミーの同窓生、ジョージ・プリンプトンがパリで新しい文芸誌「パリ・レヴュー」を創刊したばかりで、こっちに来ないか、と手紙を送ってきた直後だった。光の都が手招きしていた。ジュリアンと私は荷造りを始め、一九五四年の三月にはパリに向かうエール・フランスの機上の人となっていた。
2
淡い水彩画の色で私のなかに残っている記憶がある。ジュリアンは一九四二年の初夏、「授業を抜け出してエクセター川に散歩に行かない?」と私を誘った。ジュリアンと私が関係を持ってから半年が過ぎていた。エクセター川はキャンパスの脇を流れている。陽光が水面に乱反射し、眩しさに私が目を逸らすと、太い枝に生い茂る葉が小川を覆い尽くすほどになっている楡の大樹が視界に入る。暖かくなると生徒が度胸試しに樹の上から飛び込む姿が見られたものだ。二つの海の向こうでは戦争が続いているのに、フィリップス・エクセター・アカデミーは生徒を外界から庇護し、私たちは平穏な日々を過ごしていた。
「ここでいい?」ジュリアンは楡の幹に寄りかかって座り、持参した籠にぎっしり詰まった蟠桃とシャブリを一瓶取り出した。「桃を食べてから辛口の白ワインを飲むと、甘いのに爽やかな味になるんだよ」
飲酒は校則違反もいいところだ。私たちは桃の果汁が指に滴るのも構わず手掴みで食べ、ワインのボトルに口をつけて回し飲みした。ジュリアンは十七歳、私は十六歳だった。
ほろ酔いになった私は自分の名前について話をした。「ジョージ・ジョンなんて変な名前だ。ファースト・ネームを二つ繰り返しているように聞こえる」
「そんなに悪い名前だとは思わないけど」酒を飲み慣れていたジュリアンは顔を赤らめもせず、穏やかな音を立てて流れる小川を見つめている。「それなら僕の名前の方が酷いよ」
ジュリアンが自分の名前に違和感を覚えているとは思いもしなかった。
「バトラーっていうラスト・ネームは執事と同じスペルじゃない?」ジュリアンは煙草に火をつけた。「バトラーはパパの先祖のアイルランド貴族に由来してるのに、執事と同じスペルなんて。でも、ファースト・ネームがもっとだめ」
「そんなことはない。フローベールの『三つの物語』の聖ジュリアンに限らず、ジュリアンという名前の聖人は多い。元々はラテン語のユリウスに由来している。ユリウス・カエサルがそうだ。ローマの皇帝の多くが名乗っている。それがユリアヌスに変化し、英語圏やフランス語圏ではジュリアンになった」
「それはそうかもしれないけど、パパもママも僕に関心がなかったし、出産が早まって名前も考えてなかったから、おじいちゃんが勝手につけたんだ」ジュリアンは私からシャブリの瓶を奪い、残った液体を一気に飲み干した。「僕の家族は敬虔なカトリックだと思われてる。プロテスタントが多いアメリカでは少数派だけど、差別されるほどじゃない。でも、おじいちゃんはそれで苦労をしたんだよ。おじいちゃんは大金持ちとまではいかないけど裕福な家庭の生まれだったし、ハーバード卒だけど、お金や学歴ではどうにもならないこともあるから。おじいちゃんは議員になりたかったんだ。でも、この国ではカトリックが大統領になったことはないじゃない? 政治の世界では立場が弱いんだよ。結局、イタリア大使止まり。だからパパに自分の意志を継がせるためにあらゆる手段を使ったし、ハリウッドの嫌らしい金持ちの娘だったママと結婚もさせた。真面目なパパは立派におじいちゃんの夢を叶えたけど、パパ自身は別に嬉しくなかったみたい。パパは神経質で気が弱いし、政治家には向いてないから。でも、問題はそこじゃない。僕は十二歳の時におじいちゃんが亡くなるまでワシントンD.C.の彼の家で暮らしてた。挫折は人を変えるって言うけど、僕が生まれた時のおじいちゃんは人間嫌いそのもの。若い頃は『スミス都へ行く』のジェームズ・ステュアートみたいな純朴でアメリカの夢を信じていた理想家だったらしいけど。ずっと書斎に引き籠もって食事の時しか出てこない。僕が生まれた頃には神も信じていなかった。ディナーの時もむっつり押し黙ってるだけ。たまに口を開くと冒涜的な言葉ばかり。信仰が政治家としての出世の邪魔になったと思っていたみたい。おじいちゃんの書庫には本がたくさんあった。一万冊くらいあったんじゃない? 歴史書、哲学書、政治学、経済学、社会学、心理学なんかの本で、文学書は一冊もなかった。ダーウィンもマルクスもフロイトもあった。僕はどれも読んだことがないし、興味もなかったけど」ジュリアンは立ち上がって後ろ手を組み、楡の木に背中を預けた。遠くを見るような焦点が合っていない目をしている。「この前、君が持ってるギボンの『ローマ帝国衰亡史』のページをいい加減にめくってみたんだ。おじいちゃんの書庫にもあったから読んでみた。背教者って呼ばれたユリアヌスって皇帝が出てきた。キリスト教の国教化に最後の抵抗を試みた皇帝だよね? おじいちゃんの書庫には進歩的な本だけじゃなくて、キリスト教以前の異教に関するものもたくさんあった。だから、もしかしたらユリアヌスからジュリアンって僕の名前をつけたんじゃない? でも、僕はおじいちゃんと違って神を信じているし、今でもカトリック。眠れない時は主の祈りを口のなかで唱えたりもしてる。気づいてた?」
「深夜に君がブツブツ呟いているのはそれだったのか?」放埒な暮らしぶりから、私はてっきりジュリアンを無神論者だと思い込んでいた。
「ジョージは鈍いね」ジュリアンは呆れたように微笑んだ。「キリスト教は同性愛を禁じてるじゃない? カトリックも正教会もプロテスタントも英国国教会もその他諸々も。おまけに僕は女装もする。教義に背いてる。ギボンにはユリアヌスが志半ばで命を落とした、って書かれてるじゃない?」ジュリアンは不安げにそう言うと、狂躁的な笑いの発作を起こした。
「それは違う。確かにユリアヌスは伝統的な多神教の復古を目指したが、新プラトン主義を学び、哲人政治を敷く理想を持っていた。単なる背教者として扱うのはお門違いだ。ユリアヌスはストイックな理想主義者だった。道楽者の君とは大違いだ」
歴史好きだった私は正論をぶったが、ジュリアンは笑い続けた。
「不似合いな名前なのは変わらないじゃない? 嫌な名前。僕は小さい頃から男の子にしか惹かれない。男の子同士で愛し合うのは犯罪で、良くて精神病扱いで病院行き。自分の名前を嫌う同盟でも二人で作る?」
「私が自分の名前を嫌いなのは君とは違う。下らない名前だからだ」
「自分の名前が嫌いなのは同じじゃない? 僕らは良い組み合わせだよ」
ジュリアンは座っている私の顔を覗き込んだ。照りつける真昼の太陽はジュリアンの背後で輝き、後光が差しているように見えた。吹いてきた風が楡の枝葉を揺らし、小川に緑の落下物を振りまいていった。
3
二〇一五年の今、ジュリアンは聖人扱いだ。生前にはポルノ作家、カトリックのオカマ野郎と呼ばれ、アメリカの文学史に解き放たれた厄介者扱いだったのに、死んでからは性革命の先駆、同性愛文学のゴッドファーザー、そして二十世紀のオスカー・ワイルドと奉られている。
現在のジュリアンの名声は著作権を遺言で受け継ぎ、その小説を論じた単著も編著もある私の貢献によるもので、間違いなく私が助長してきたものだが、私は聖人伝を書くつもりはない。むしろその逆だ。
私は八十九歳になる。一年前、ジュリアンが死んで以来ずっと暮らしてきたイタリアのラヴェッロを離れ、忌まわしい祖国に帰ってきた。それもよりにもよって、アメリカでも一、二を争う最低の都市ロサンゼルスに。街中に階段が張りめぐらされ、徒歩しか移動手段のないラヴェッロで足が不自由になった私が暮らす術はなかった。一方、だだっ広いロサンゼルスでは車がなければどこにも行けない。外出の度に車を出してもらっている。イタリアに留まろうとしたが、ジュリアンが購入したローマのペントハウスは手狭だった。ニューヨークに戻ることも考えたが、騒がしく落ち着きがない都市は老いぼれには向かない。サンフランシスコも候補だったが、シリコンバレーに巣くう成金どもがあの美しい街を醜く変えてしまった。そこで長らく人に貸していたロサンゼルスのハリウッド・ヒルズにある今の家に移ってきたわけだ。家が森に抱かれた閑静な住宅街にあったのは幸いだった。書斎を取り囲む樹々が照りつける強い日差しを和らげてくれる。私はここで秘書のベルナルド・バリーニと暮らしている。猫のマリリン三世も一緒だ。調理は私の大きな歓びだったが、今はベルナルドが食事を作る。足が悪くてはキッチンに立つのも覚束ない。
ベルナルドはローマ生まれで、私は英語読みのバーナードの愛称でバーニーと呼んでいる。バーニーが生まれる前から母親とは友人だった。バーニーの母はイタリア人で、父はアメリカ人のジャーナリストだ。彼女がバーニーを身籠ると、男は結婚もせず、アメリカに帰ってしまった。私は名付け親だったので、あれこれ面倒を見ていたが、彼女がイタリア人と結婚したのをきっかけに十歳になったバーニーを引き取った。
バーニーはぼんやりした子供で、私の許で育つうちに快活過ぎるほど快活になってきたが、いささかミスをしでかすことがある。満足にPCを使えない私の代わりにEメールでの連絡を担当しているが、常に口語体で書き、ミススペルも文法の誤りもしょっちゅうだ。仕事の交渉をする際に何度トラブルになりかけたかわからない。去年までイタリアで暮らしていたのだから仕方がない。毎日の執筆を終える正午近くになり、リビングからマリリン三世がやってきた。マリリンはノルウェージャン・フォレスト・キャットのなかでも大きな猫で、長い尻尾を入れれば人間の子供ぐらいある。プリンスの「ザ・モスト・ビューティフル・ガール・イン・ザ・ワールド」を口ずさみながら、ティーポットを載せた盆を持ったバーニーがマリリンのあとに続いた。バーニーはプリンス狂だ。この頃はフランス人の女優に夢中になっているせいで、プリンスのラブソングばかり歌う。クラシックを好む私の趣味とはかけ離れている。
「紅茶じゃなくてお酒にしませんか? ギムレットには早過ぎますか、シニョーレ?」
英語の教科書代わりにレイモンド・チャンドラーを読ませて以来、バーニーは『ロング・グッドバイ』に夢中になってしまい、この台詞ばかり口にする。冗談だとはわかっているが、老人に昼酒を勧めるなど殺人行為に等しい。
「ギムレットには早過ぎる」とお約束の答えを返した。
イタリアで私は幸福な世捨て人だったが、アメリカに戻ってきてから大仕事の依頼を二つも受けた。長い原稿を書き終わったばかりなのに人の迷惑を考えない連中だ。
一つは『ネオ・サテュリコン』の映画化にあたって、監督のオリバー・ストーンと共同で脚本を書けという依頼だ。公には二十年近く沈黙していた作家にとっては面倒な話だったが、私はストーンには会わないことを条件に引き受けた。ジュリアンの原作を他人に滅茶苦茶にされるよりは、自分で滅茶苦茶にした方がいい。主人公のジュリーにはBBCのTVドラマで女装の歌手ボーイ・ジョージを演じた二十二歳のダグラス・ブース、恋人のクリストファーにはマッツ・ミケルセンが決まっていた。キャスティングに不満はない。ストーンは時代背景を一九五〇年代から一九八〇年代に移した自分で書いた脚本の草稿を送ってきた。そのうえ主人公はジュリーからクリスに変更されている。ストーン版クリスにはヤク中という設定が付与されていた。そして、コカインでぶっ飛んでストーンお得意の大仰な台詞回しで喋りまくるクリスのナレーションが全編を覆い尽くしている。原作にはない的外れな陰謀論をめぐる会話、過激な暴力も随所に追加されていた。私は八〇年代に変更された時代設定のみそのままにして、主人公を原作通りジュリーに戻し、監督によって付け足された要素を全部削除した二稿を送ったが、ストーンは気に入らず、また自分で書き直してほとんど元の草稿と変わらない状態の決定稿を仕上げてしまった。私は早々に手を引いた。脚本がどうなろうとジュリアンの著作権を持つ私には金が入ってくる。来月公開されるらしい。試写に行くつもりはない。プロデューサーには映像をデータで送るよう言っておいた。
一年掛かりの不愉快な脚本執筆が終わると、今度はペンギン・ブックスと合併したランダムハウスの名誉職に収まっている担当編集者のハーマン・アシュケナージから依頼が来た。「『ネオ・サテュリコン』が映画化されるタイミングに合わせてペンギン・モダン・クラシックスからジュリアンの全小説が再版されるから、ジュリアンについての回想録を書いてくれ」とのことだった。「ジュリアンの作品についてはもう書いた」と返事をすると、「違う。今度はジュリアンの生涯についての本だ」と言う。つまり今書いているこれだ。執筆は物の見事に停滞している。私は男やもめとしてイタリアで暮らすうち、ジュリアンのことを努めて忘れるようにしてきた。実際、記憶はあまり定かではない。そこで十五歳の頃からつけてきた日記を読み返してみた。ジュリアンと共に生きた頃の自分の記述は青臭く、情緒不安定で混乱しており、読むだけで赤面した。私はジュリアンの死と同時に新しい生を歩み始めた。古いページに息づいている若き日の自分は見知らぬ他人だった。ジュリアンの遺品を押し込めてある二階の一室にも赴き、リビングに彼の写真の数々を並べて、どうにか過去を呼び戻そうとしているが、うまくいかない。これまで私はジュリアンの著作権者として、評論家として、彼の神話を守ってきた。ジュリアンの人生について書こうとするものがいれば訴訟をちらつかせて潰し、小説について悪く言うものがあれば評論家として反論した。その私が真実を書けば、自分で創造した虚構をこの手で破壊することになる。人生の終わりに差し掛かっているというのに皮肉な話だ。
今日は昼食を摂ったら出かけなくてはならない。バーニーが懸想しているフランス人の女優とのデートのお付き合いだ。二人の昼下がりの逢引の場所になっているビバリーヒルズ・ホテルのプールサイドへお供する。友人のジーン・メディロスも来るそうだ。私に話があると言っていた。
4
おぞましいピンクに塗装されたビバリーヒルズ・ホテルのプールサイド。スタンダード・ナンバーを弾いているピアニストのジャケットまでピンクだ。このホテルは好きになれない。ピアニストが演奏する曲はジュリアンが歌っていたものばかりなのが、唯一の美点だ。
私はプールバーのカウンターにジーンと座っていた。カリフォルニアの能天気な太陽がプールを照らしている。私は着古したブルックス・ブラザーズのスーツだったが、ジーンはアニエス・ベーの白いTシャツと黒のキュロットスカートというラフな格好だった。私たちの前にはシャンパン・クーラーに入ったクリスタルのボトルがある。ジーンは立て続けに杯を重ねていた。彼女はシャンパン以外のアルコールを飲まない。どんなに懐が寂しい時でもそうだった。「シャンパンがある時は飲んで、シャンパンがない時は飲まない」というのがジーンの怪しげな健康法だ。私はまだ一杯目だった。Tシャツにタイパンツ姿のバーニーは離れた席でギムレットを飲みながら、ガールフレンドといちゃついている。
ジーンは今年の春、パリからここロサンゼルスにやってきて、数多くいるガールフレンドの一人、エイミー・マーカスと婚約した。カリフォルニア州では二年前から同性婚が可能だ。二人は私の近所に住んでいる。エイミーはジーンより五歳年上で、年老いた婚約者の人生の終局を間近にし、土壇場のところで結婚は間に合いそうだ。二人が出会った当時、エイミーは既婚者だったのだが、ジーンはものともせず、不動産企業のCEOを務めている暴力的な夫からエイミーを奪った。二人の恋は一冊の小説が書けるほど波乱に満ちたもので、実際、ジーンは二人の物語を『エミリア』という自伝小説にして今月出版した。婚約で終わる結末以外はとっくに書き終わっていたらしい。今はベストセラー・リストを駆け上がっている。映画化権も売れた。
しかし、ジーンはもう同棲に飽き飽きしているようで、婚姻届の提出を延期し続けている。「結婚って制度自体が嫌いだったのに魔が差したみたい」と愚痴るようにもなった。今日もその話が延々続いている。結婚はジーンの意思ではなく、エイミーが望んでいるもので、今の暮らしは「老人介護のようなもの」らしい。そういうジーンも八十三歳なのだが、彼女は六十年前からほとんど変わっていない。初めて会った時から前髪を左に流したベリーショートだ。溌剌としていて思考も衰えていない。もっとも、ブルネットの髪は加齢で銀髪になってしまっている。
ジーンは生まれついてのボヘミアンで、一つところに腰を落ち着けたことがない。いつも世界中を旅している。例外は拠点にしているパリぐらいだ。ジーンは一九三二年にリスボンでフランス人の父とポルトガル人の母の間に生まれた。一年後、サラザールの独裁が始まり、両親と共にパリへ逃れて暮らしていた。パリで両親は離婚した。八歳の時、ドイツがフランスに侵攻してきたので、親戚を頼って母親とリスボンを経て大西洋を渡った。アメリカで教育を受け、女子大のスミス・カレッジに入学したものの、「同級生と親密過ぎる関係にある」と咎められ、とっとと自分から中退してパリへ戻った。アメリカは亡命した当時から大嫌いだったらしい。本名はポルトガル式の長ったらしいもので、ファースト・ネームとセカンド・ネームのあとに父親と母親の姓がついていたが、アメリカで暮らすようになった時、セカンド・ネームと父親の姓を取り去って「ジーン・デ・メディロス」に改名した。ポルトガルの「デ」はフランスの「ド」とは違い、必ずしも貴族の出自を意味しない。事実、ジーンの母は中流階級出身だ。しかし、「『デ』がついてると、アメリカ人は貴族だと勘違いしてちやほやするのにうんざりして」、「デ」も除去し、今の「ジーン・メディロス」になった。それからはその名前を筆名にしている。
ジュリアンと私は、ジーンがパリでオリンピア・プレスのためにレズビアン小説を書いていた時に出会った。ジーンはジュリアンと同じくポルノ作家として経歴を始めたが、すぐにミステリに転向し、男に恋する度に事件に巻き込まれる青年シリル・リアリーを主人公とした三部作で「サスペンスの皇女」と呼ばれていた。しかし、十年もしないうちにミステリに飽きてしまい、実験的な幻想小説に手を出した後、一九八〇年代からは文学的なスタイルに手を染めた。本人同様、作風も落ち着きがない。今でも時々思い出したようにミステリや幻想小説を書く。
「それで回想録は仕上がった?」ジーンは不満話を打ち切り、ホテルの禁煙を無視してゴロワーズに火をつけた。アルコールはシャンパンしか飲まないのと同じように、煙草はゴロワーズしか吸わない。喫煙はジュリアンと同じくジーンの悪癖の一つだ。
「まだだ。ようやく書き始めたところだ。自分で作り上げた虚像を破壊するのは気が引ける。やめた方がいいかもしれない」
「あなたは」ジーンは私の顔を横目で見遣りながら言った。「臆病な癖にいつもジュリアンの陰に隠れてやりたい放題だった。あなたはジュリアンで、ジュリアンはあなただったじゃない」
「その言い方は歓迎できないな。私が偽善者みたいだ」
「あなたは陰険な偽善者で嘘つきそのもの」ジーンは突き放すように言って、私の顔に紫煙を吹きかけた。「ジュリアンとの関係がばれるのが嫌なんでしょう。回想録を書かなかったら、あなたは自分を偽ったまま自分が作った虚構のなかで生を終える」
「今日はいつにも増して辛辣だ。作家が自分の虚構のなかで死ぬのはむしろ幸福なことだ」私は煙にむせながら言った。
「私がいつでも言わなくちゃいけないことを言うのは、あなたも知っているでしょう。もっと言ってあげようか? あなたはジュリアンを犠牲にして生き残った。確かに作品にとっては作家の人生はどうでもいい。でも、それだとあなた自身の現実の人生はどうなるわけ?」
「まるで私がジュリアンを殺したような言い草だ。私は自分の人生に満足している」頬がわずかに引きつるのが自分にもわかった。
「あなたは」ジーンは溜息をついてまた煙を吐き出した。「ずっと書くことにしか興味がなかった。ジュリアンはそれほどでもなかった。あなたはジュリアンを利用していた。回想録を書きなさい。ジュリアンとあなたの間に何が起きたかを。今更ジュリアンのことをあなたが書いても、誰も非難しない。トラブルに巻き込まれるのが嫌だったら死後出版でもいい。私を遺言執行人にでもして全部任せればいい」
「まるで私がもうすぐ死ぬような言い方はやめてくれ」
「あなたはアメリカ人の平均寿命をとっくに過ぎていて、イタリア人の平均寿命も超えた。自分が永遠に生きるとでも思ってる? 過去の自分と向き合いなさい。そうすれば満ち足りた死を迎えられる」
そう言うとジーンはおどけた顔をして私の目を覗き込んだ。私は「考えておく」と言うほかなかった。ジーンと話すといつもこうだ。高速で回転する頭脳から導き出した結論を放り出すように言う。そのアドバイスが間違いだったことは一度もない。自分の言葉に反して私の心は決まった。迷いは潮が引くように消え、緊張が去ったと同時に空腹を覚えた。夕食は家で摂ることにしている。陽は既に地平線の向こうに没し去っていた。プールサイドの照明が灯り始めている。
「バーニー、帰ろう」
「シ、シニョーレ。今晩のメインは鴨のコンフィですよ」まだガールフレンドといちゃついていたバーニーはこちらに顔も向けずに言った。
私は二本目のクリスタルを注文したジーンに暇を告げた。彼女は家に帰りたくないそうだ。エイミーが毎晩眠る時刻までここにいると言う。「老人は早寝だから大丈夫」と自分も老人のジーンは茶目っ気たっぷりに笑った。
続きは文庫『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』でお楽しみください。