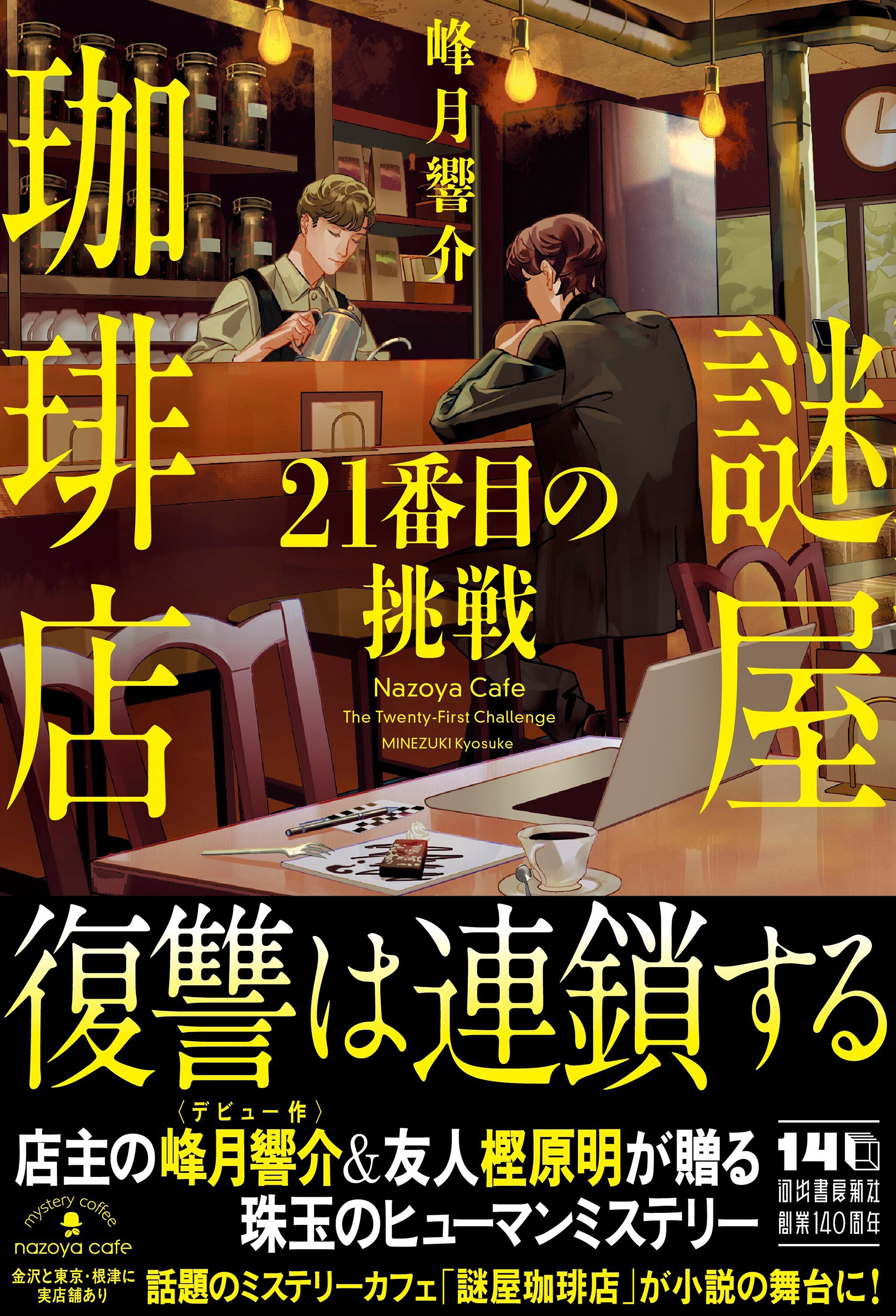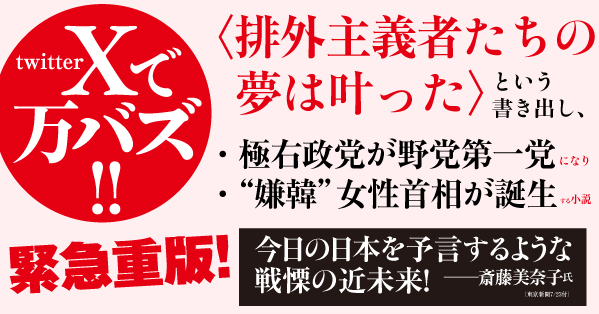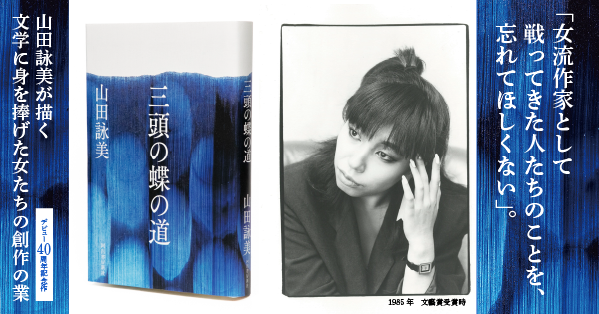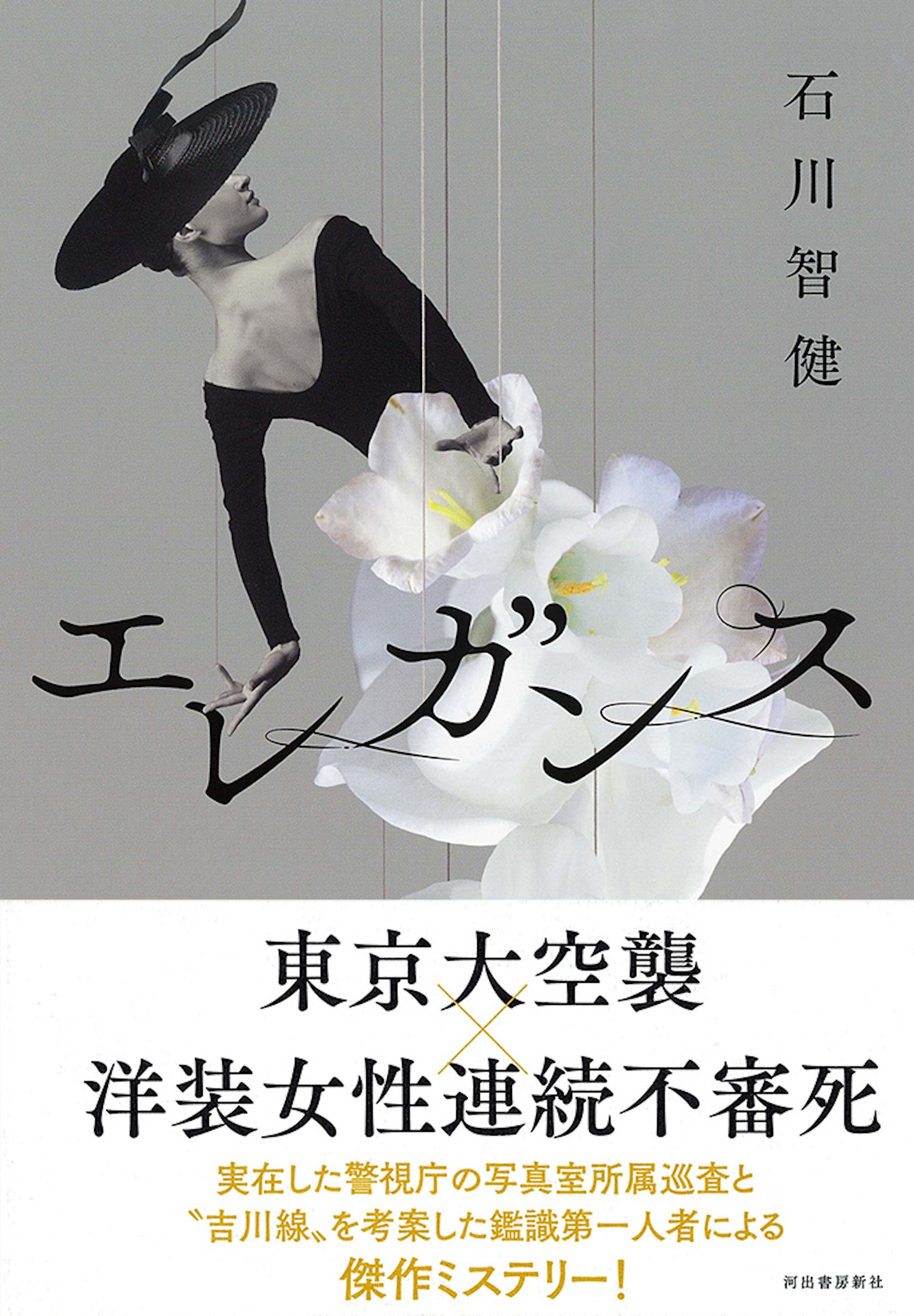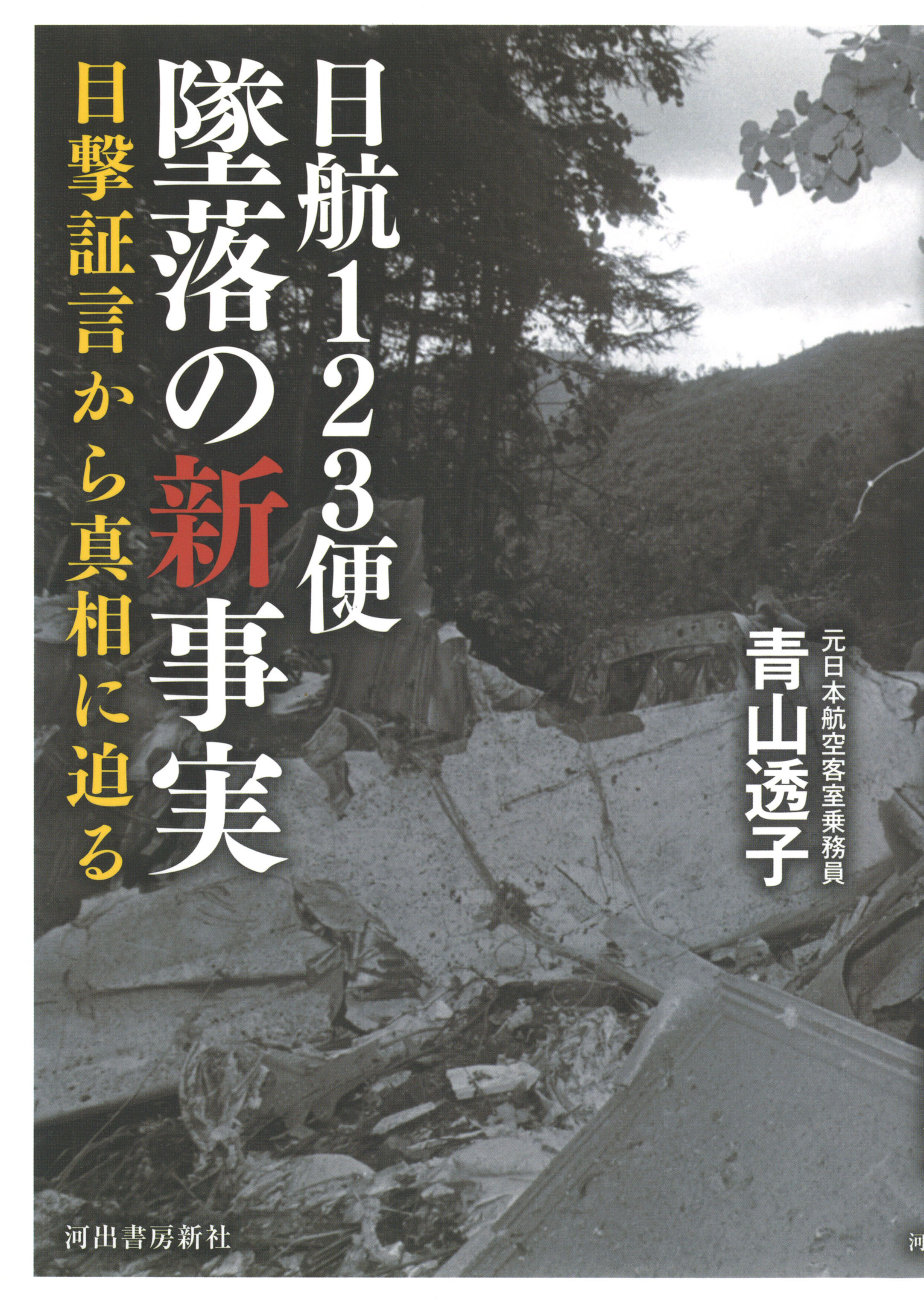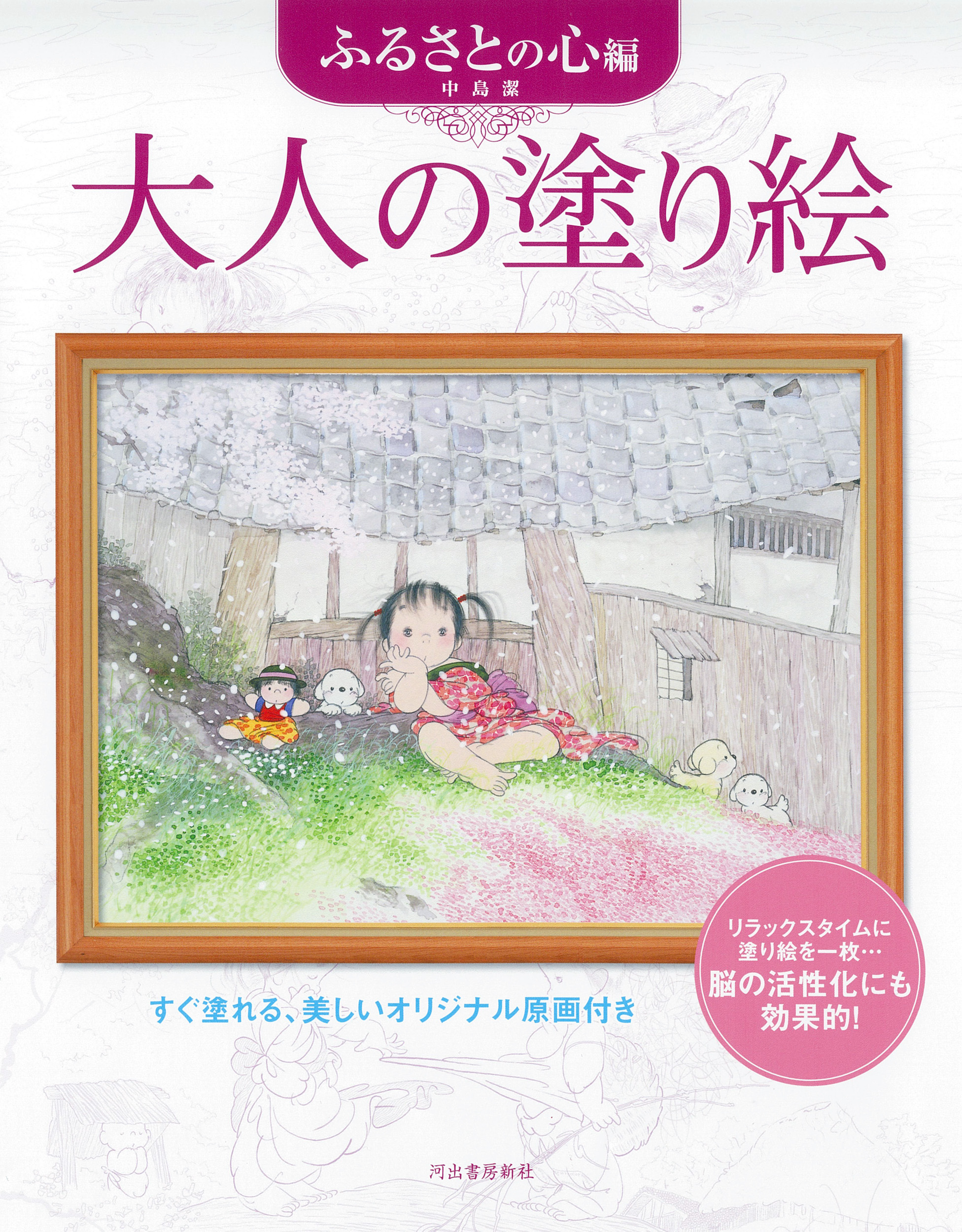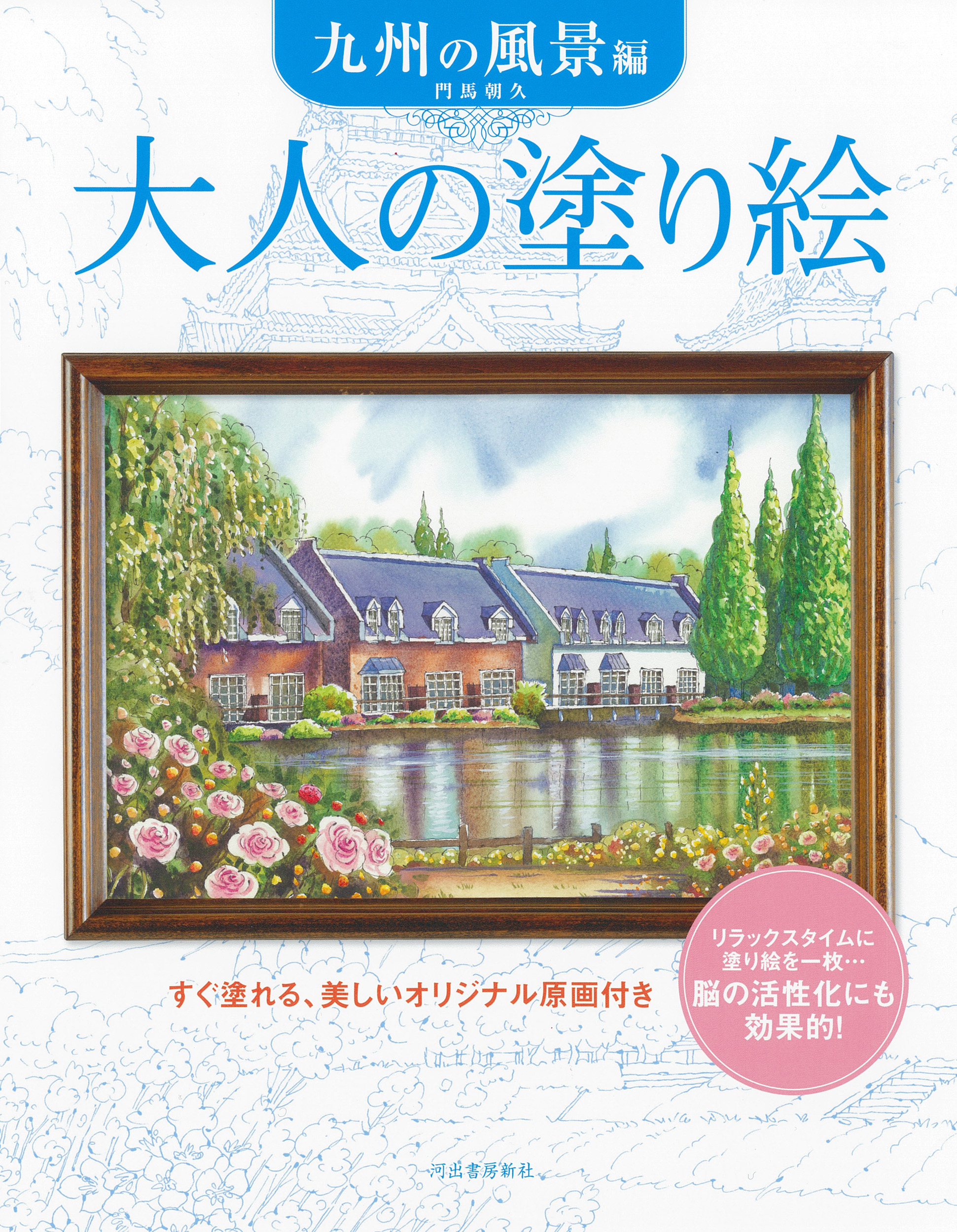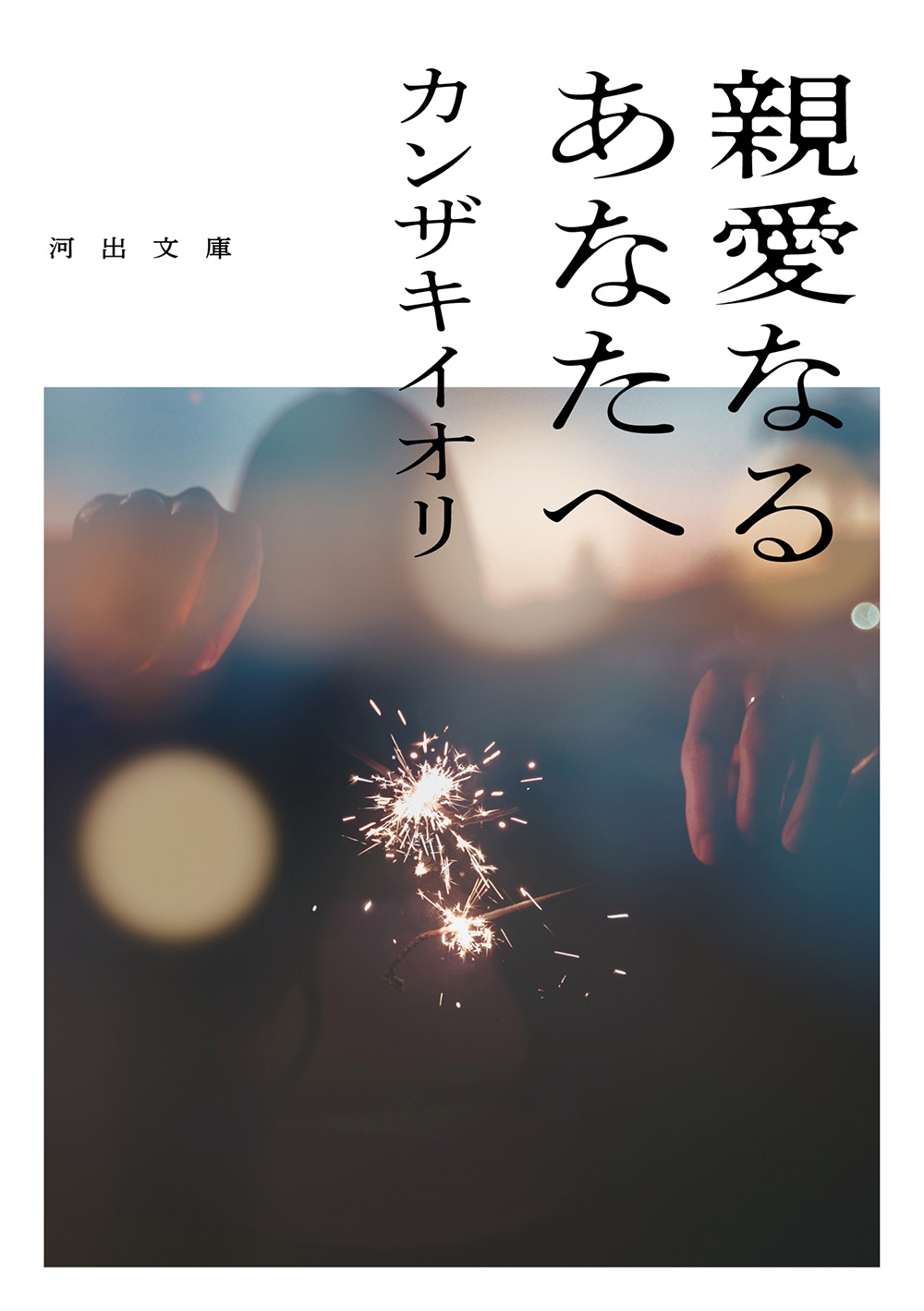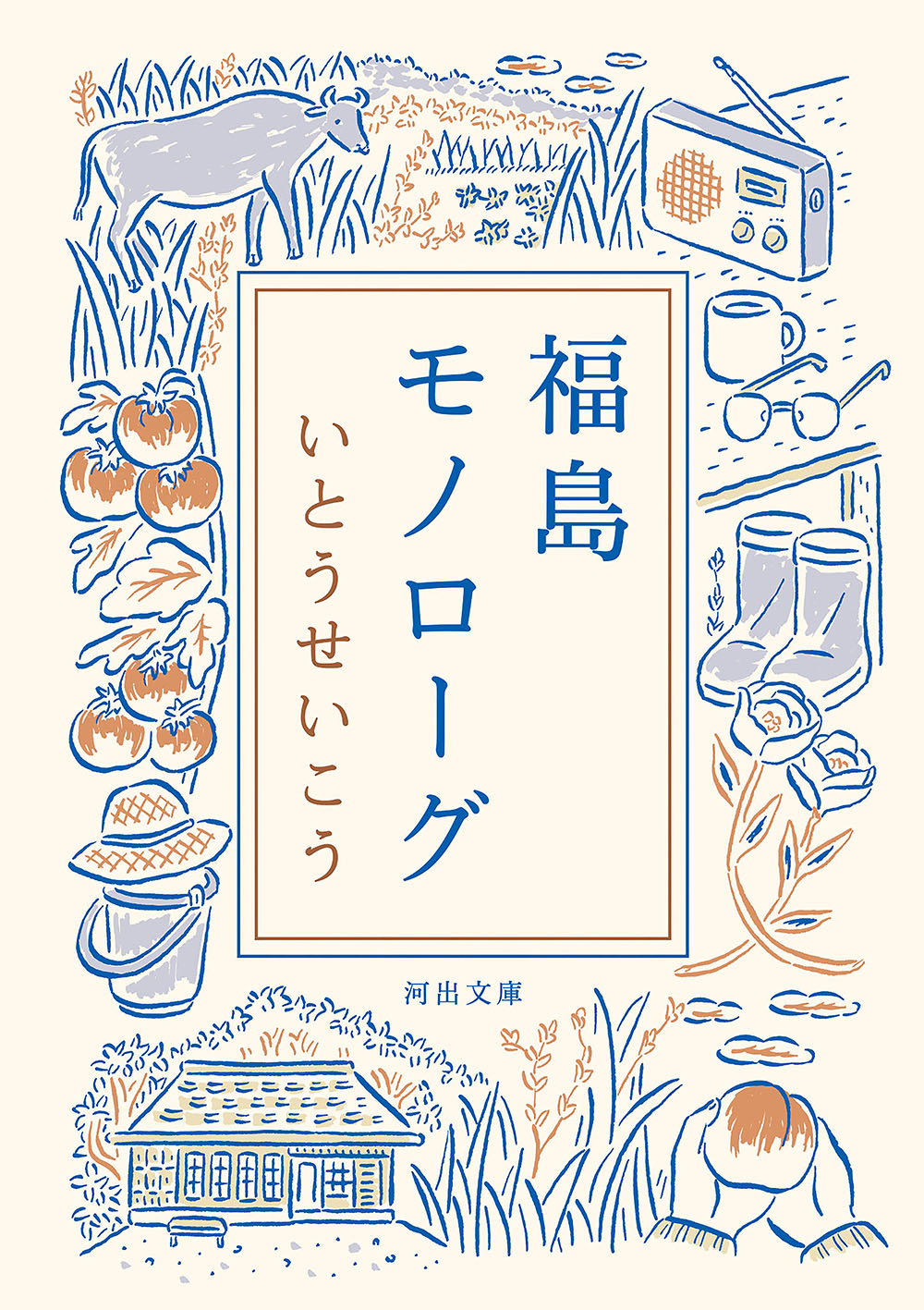ためし読み - 日本文学
〈批評がマッチョだというのは嘘である。〉瀬戸夏子「我々は既にエミリー・ディキンソンではない」(『クリスマス・イヴの聖徳太子』収録)全文試し読み
瀬戸夏子
2025.09.29

歌人・批評家の瀬戸夏子さんの新刊『クリスマス・イヴの聖徳太子』を9月18日に刊行しました。刊行を記念して、本書収録エッセイ「我々は既にエミリー・ディキンソンではない」を全文公開いたします。
このエッセイは、アメリカの詩人エミリー・ディキンソンをめぐり、著者自身が「無名で幸福なワナビ」であった二十代を思いおこし、「批評」と呼ばれる言葉の本質を照らし出します。
ぜひお読みください。
==ためし読みはこちらから↓==
「我々は既にエミリー・ディキンソンではない」
わたしは大学で創作活動をメインとする専攻にすすんだ自己顕示欲のつよい人間だった。そこはわたしのようになみなみならぬ自己顕示欲とそれに対する羞恥心をない交ぜにしたワナビが集う薄暗い場所で、わたしたちは過剰すぎるハリネズミ状の自意識で互いを刺激しすぎないように牽制しあいながら不思議にしずかに授業を受けていた。様々な授業で様々な教授や講師の言葉をきいたが、彼/女らはいつも息苦しそうだった。なぜならわたしたちが求めていた言葉は誰に対してもたったひとつ、――「あなたには才能がありますよ」。それ以外の言葉を求めていないわたしたちにとって彼/女らのそれ以外の言葉は、来るべき――「あなたには才能がありますよ」――の前座にすぎなかったので、わたしたちの焦る呼吸、そしていつまでもやってこない――「あなたには才能がありますよ」の手前で喋りつづけなければならない彼/女らはねばねばとした熱視線を受け、わたしたちは既に一段上の成功者であるところの彼/女らを妬みつつ、彼/女らよりも才能がある「かもしれない」ワナビ特有の傲慢さを隠しきれずに存在していたに違いない。
そこできいた言葉でもっとも印象的なものが「我々は既にエミリー・ディキンソンではない」、であった。周知のとおり、十九世紀アメリカを代表する詩人、エミリー・ディキンソンはアマーストの家に終生引きこもり、いくつかの例外を除いてその詩は生前に発表されることはなかった。生きているあいだにその肉体が名声を纏うことはなかった。
彼は、「我々は」と言った。彼はすでに多数の本を出版し、数々の賞をうけていた。けれど、彼はわたしたちワナビをも巻き込んで「我々は」と言ったのだ。おそらくいくつかの例外はあれど、わたしたちはまだ書いたものを世に問うていたわけではなかった。けれど彼は「我々は」と言った。わたしたちのいまにも破裂しそうな自己顕示欲によって教室は溢れていたから、彼はまぼろしの名声をあらかじめわたしたちに冠して、その冷たさ、突き放し、一突きで風船を割るような針がなければ、わたしたちの耳はまともに機能しない。わたしたちは一瞬だけ冷静になった。しかしそれも一瞬でしかなかった。なぜならわたしたちはエミリー・ディキンソンではなかったからだ。
結局わたしは二十代を無名で幸福なワナビとして過ごした。そのあいだ、わたしがもっとも熱中していた表現形式は短歌だった。あまり知られていないようだが、短歌という形式はしばしばそれのみでは完結せず、相互評を伴う。わたしの短歌はほとんど評価されなかったが、評だけは好かれ、褒められ、需要が伸びつづけた。ワナビという甘い地獄からわたしを引きずりだしたのはそんなつもりではじめたわけではなかった批評だった。そのままに、わたしは短歌以外を対象とする批評も書くようになった。これまでの苦労はなんだったのかと思うくらいたやすく成功してしまったような気がした。
短歌、詩、エッセイ、小説、日記、川柳。俳句以外のほとんどのジャンルにわたしは手を染めたが、そのなかで批評は断然人恋しい書きものだと知っている。批評はつねに寄生先を探している。ひとりでは自立できない。対象がなければ批評はない。不安定で断然甘ったれている。なぜ批評の文章というのは大概(たいがい)、過度に偉そうなのか? その依存症的恋愛体質を隠蔽するためである。批評がマッチョだというのは噓である。
わたしが批評が得意なのは思考の枠組みの体質もあるだろうが、ワナビとしての才能に恵まれていたからだとも思う。妬み、嫉(そね)み、粗探し、ゴシップが大好きで、自分のことを棚にあげ、特権的に振舞い、傲慢な自我を恥じようとしない。
出版は
人間のこころの競売
貧乏ならしかたがないかもしれない
そんな卑しい事をしても
けれどわたしたちの雪を投資するより
むしろ屋根裏べやから
白いまま 白い造り主のもとへ
ゆくほうがいい
思考は それを恵まれた神のもの
だから その肉体を与えられた
神にこそ気高い調べを
売るべきだ ひとまとめに
天国の恵みの
商人となっても
決して人間の魂を
価格の恥辱におとしめてはいけない
(エミリー・ディキンソン)
わたしは大学院でエミリー・ディキンソンの研究をしていたことがある。けれど止めた。貧しかったからである。金持ちの子どもに薄給で勉強を教えて学費と生活費を稼ぎながら、ディキンソンを読む。心底その詩を素晴らしいと思いながら、引きこもって労働せずともひたすら詩のために生を捧げることができたディキンソンを少しずつ憎むようにもなっていた。「貧乏ならしかたがないかもしれない」と言われて腹が立った。研究は大学院でなくたってできる。大学院で研究したのはエミリー・ディキンソンを商品にして生きていこうと考えたからだ。けれどそれは失敗した。そしてわたしはいま「人間の魂を」「価格の恥辱におとしめ」ながらなんとか生きていくための日銭を稼いでいる。ものを書いてお金を貰っている。ディキンソンは詩人だからいい。死後に名声を得ることもできる。果たして、生前ほとんど書いたものを発表せずに死後名声を得ることができる批評家はいるのだろうか?
批評は人恋しく、そしてなまぐさい生者の文学である。批評がもっとも力を持つのは同時代である。いちばん滅びやすい文学である。けれど、わたしはどこか諦めながら、そのことを安らかに受け止めてもいる。
そもそもエミリー・ディキンソンのような世紀の天才がそういるわけもない。けれど貧しい才であろうとものを書いたっていい。既にエミリー・ディキンソンではないだろうが、もともとエミリー・ディキンソンである必要だってないのだ。それにエミリー・ディキンソンだって死ぬ前にみずからの手でみずからの詩を破棄したりはしなかった。
これは一度も手紙をくれたことのない
世間のひとびとに送るわたしの手紙です
優しくおごそかに
自然が語った素朴な便りです
わたしが見ることのできない手に
自然の言葉を委ねます
なつかしい国の皆さん――自然のために
わたしをやさしく裁いてください
(エミリー・ディキンソン)
確信している未来の名声に語りかけている。どこかに存在していたかもしれない、生前にみずからの原稿を破棄したエミリー・ディキンソンに、わたしは心からの敬意を捧げたいが、死後アメリカ最大の詩人のひとりになった臆病(おくびょう)で尊大なエミリー・ディキンソンにもわたしは平然と心からの賛辞をおくることができる。並々ならぬ図々しさで、二十一世紀においてさえ批評を書く者特有の傲慢さをもって。
(初出:「群像」2022年7月号)
******
■『クリスマス・イヴの聖徳太子』
内容紹介:
わたしの言葉を奪いにくるならわたしはお前の命を奪う──。三島由紀夫、穂村弘、BL、タワマン文学、木嶋佳苗etc. 稀代の歌人にして天性の批評家による言葉のレジスタンス。
■著者紹介:
瀬戸夏子(セトナツコ)
1985年生まれ。歌人・批評家。著書に、『そのなかに心臓をつくって住みなさい』『かわいい海とかわいくない海 end.』、『現実のクリストファー・ロビン』『白手紙紀行』『はつなつみずうみ分光器』がある。