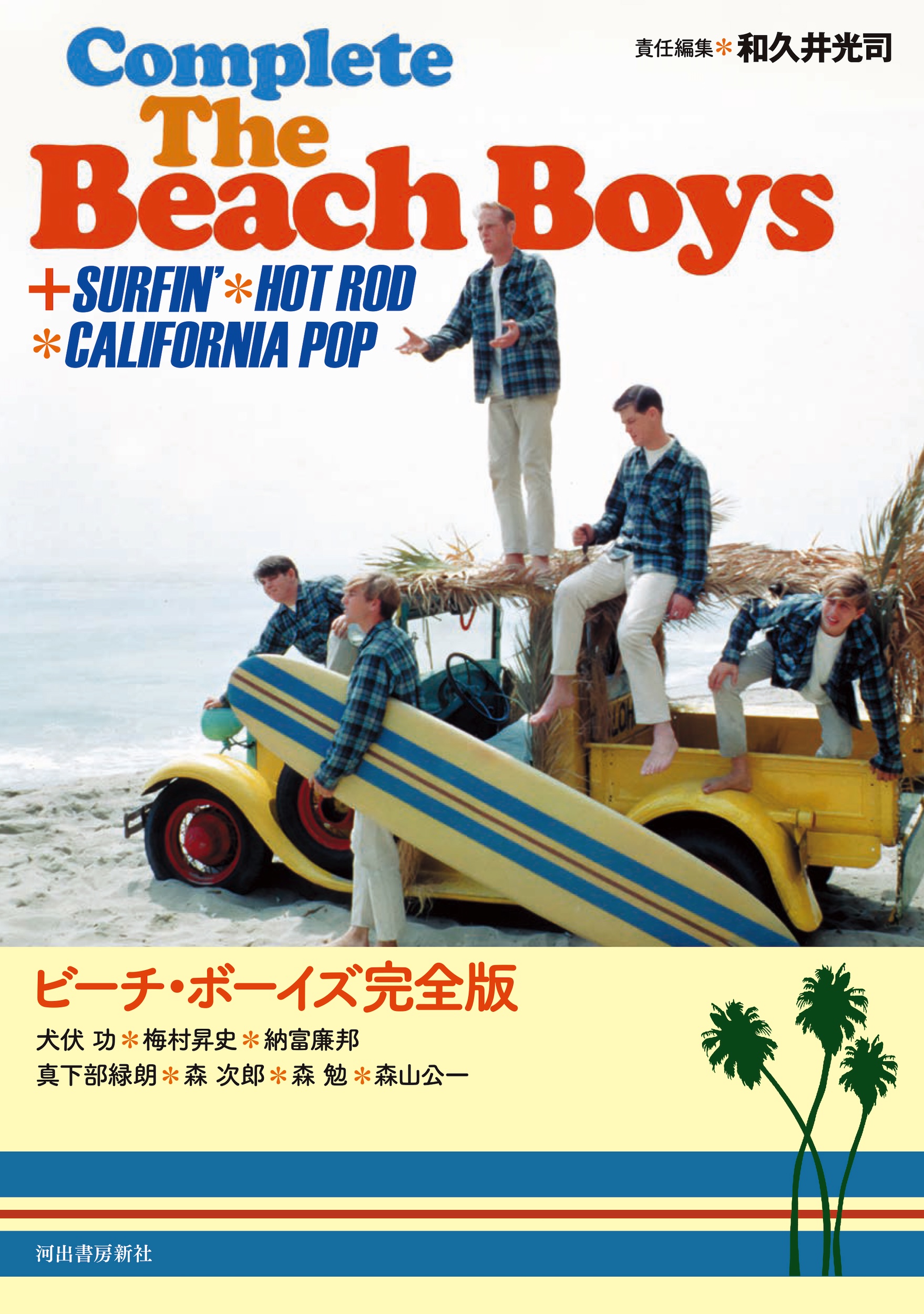ためし読み - 日本文学
女性作家が「女流」と呼ばれた時代──山田詠美デビュー40周年記念作『三頭の蝶の道』特別無料公開!
山田詠美
2025.11.10

1985年に『ベッドタイムアイズ』で文藝賞を受賞、衝撃的なデビューを果たした山田詠美。作家生活40年となる今年、満を持して長編小説『三頭の蝶の道』が発表されました。
その刊行を記念して、冒頭17ページを、特別無料公開します!
三人の女性作家の、創作をめぐる情熱と愛憎を描く長編小説。
ぜひお楽しみください。
山田詠美 長編小説『三頭の蝶の道』
女性作家が「女流」と呼ばれていた時代。
現代では問題視されるその呼び名をものともせず、
ひたすら自身の文学に身を捧げた大先輩たちの姿を
四十年間末席で見詰め続けた私だからこそ書けた作品と自負しています。
――山田詠美
それはそれは質素な葬儀でした。女の書く小説が女流文学と呼ばれ、男のものするそれらより一段低い位にあると見なされた時代から、声高に女としての自分を主張するでもなく、対抗心あらわな反論を書き殴るでもなく、ただひたすら自分の文学世界を追求した人。そして、女性で初めて日本文学の登竜門と呼ばれる夏目賞の選考委員に就き、晩年まで優れた若い才能を見つけ出すことに尽力した人。そんな歴史に名を刻むべき、偉大なる女性作家、河合理智子の、今日は告別式なのでした。
通夜も初七日も兼ねているというその式には、親族以外には、数人の編集者と作家しか出席していませんでした。しかも、作家は、女性三名だけ。河合理智子と若い頃から付かず離れず交流を続けて来た鈴木しょう子と、デビュー以来、理智子を慕って来た親子ほどの年の差の玉川桜子と山下路美の二人。河合理智子は、生前、この三人の作家以外を自分の葬式には招んでくれるな、と言い遺していたそうです。
「河合先生と、玉川さん山下さんの間の世代の女性作家の方たちも、もうほとんど亡くなってしまってるものね」
そう林田咲の耳許で囁いたのは、のんちゃんと呼ばれて河合理智子にたいそう可愛がられていた咲の先輩編集者である間宮乃里子でした。定年間近だというのに、生涯一編集者でありたいと公言している通り、まだまだ現役感たっぷりの彼女は、咲よりひとまわり以上も年上ですが、会うたびに生命力が増しているよう。葬儀の場だというのに、それは変わらず、いえ、だからこそ、いっそう、そのエネルギーの放出が目に付くのでした。作家関連の冠婚葬祭という場は、編集者の腕の見せ所でもあるのです。とりわけ、間宮乃里子のような人間の場合には。ほら、語りかけられた咲が横を向いた時には、彼女は、もう鈴木しょう子の肩を抱きに棺の方に歩いてる。
長年励まし合って来たであろう女性作家たちの別れの場に居合わせて、咲も涙をこらえることが出来ませんでした。鈴木しょう子は、棺に覆い被さるようにして号泣していました。ちょっとお、なんで先に逝っちゃうのよお! そう叫んで遺体の頬を撫でる様子は、それが、鈴木しょう子であるが故に、本当に、その死を悼んでいるのが伝わって来るのでした。
ええ、咲は、さまざまなタイプの作家を知っています。観客がいれば、俳優顔負けの演技をして見せる人たちが存在することも。
作家とは、嘘八百を文字にして生きる糧を得ている人種です。その嘘八百が根も葉もないものなのか、あるいは、真実を育てた故の根も葉もある嘘八百なのかは、その人の素質によるでしょう。どちらが良いとも悪いとも言えない。嘘つきにも、上品と下品があるとしか。
鈴木しょう子は前者でした。自分を貶しめてユーモアを醸し出す、その作風が咲は大好きです。河合理智子より二歳年下と聞いたことがあるから、今、八十六歳か。はあ、と咲は溜息をついてしまいます。この世代の女性の作家の元気な様子ったら、ない。頭も明晰で、創作意欲も全然衰えていないのですから。その下の世代は、次々とこの世を去っているというのに。戦争をくぐり抜けた強さなのか。手書きのスタイルが、末梢神経から中枢神経にかけてのトレーニングの役目を果たしているのか。河合先生も亡くなる寸前まで、次に書きたいものについて語っていたっけ。
「先生、じゃ、それ書くまでに御体なおさなくちゃ」
最後の見舞いに行った時、間宮乃里子が河合理智子の手を握って、そう言ったので、咲は、内心驚いていたのでした。どう見たって、死の床にいる人なのに、調子良過ぎやしないか、と。
しかし、河合理智子は、こう答えたのでした。
「いいのよ。この体は、もうじき駄目になるから、焼かれた煙の行き着いた先で書く。次作は死後の楽しみに取っておくわ」
そして、もっと驚いたことに、乃里子は、少しも動じずに、それどころか笑みを浮かべたのです。
「解りました、先生。やがて、私も、そちらに参りますので、それまでに仕上げておいてくださいよ」
「ま、のんちゃんたら。また他社を出し抜くのね?」
病室を出た後も咲は感服したままでした。長年、作家の苦楽に付き合って来た編集者とは、ここまで肝が据わっているのか、と思ったのです。なんか、いい。この仕事、恰好良い。
「ね、のん先輩、私……」
先輩を目指します、と伝えようと横を向くと、乃里子は、表情を変えることなく泣いているのでした。
咲は、言葉を失ってしまい、それから二人は、ただ無言のまま歩き続けたのでした。
「これで何人の作家を送ることになるのかしらね」
乃里子は言って、深い溜息をつきました。
「のん先輩ったら……河合先生、まだ大丈夫ですよ」
そお? と咲の慰めの言葉など何の意味もない、というように乃里子は続けたのです。
「あれは、もうじき死ぬわよ」
「……そんな」
「人は誰でも死ぬのよ。遅かれ早かれ、その時はやって来る。長生きして良かったかどうかは、人それぞれね。河合先生は、どうかな。それは、御本人の心の中を覗いてみないことには解らないわね」
長寿がめでたい、という紋切り型は使えない、というのを、それなりのキャリアを積む中で、咲も学んで来たつもりです。出版業界に身を置いていると、常識が意味を持たない瞬間に少なからず遭遇します。
「河合先生は、もうじき死ぬ。でも、もしかしたら、私か咲ちゃんの方があの方より早く死んでしまうかもしれない」
「ええ⁉」
「だって大地震が襲うかもしれないし、車がコントロール不能になって、こちらに突っ込んで来るかもしれないし、これが倒れて来るかもしれないよ?」
そう言って、乃里子は、工事現場を囲う板に手を伸ばして触れました。
「なんか、のん先輩、怖いこと言いますね」
咲の咎めるような口調を聞いて、乃里子は、ははは、と乾いた笑い声をたてるのでした。
「怖くないよ、別に。いつ死ぬか解らない、と思ってると、この瞬間がかけがえのないものに感じられるでしょ? 作家でも、そういう諦観を常に持っている人が、私は好き。品格があるでしょ? その上で、明るい心持ちでいる人がいいわね」
「なーるほど。河合先生はそうだったんですね。それは、私にも解ります」
でしょ? とにこやかに問い返す乃里子の表情が、その直後、かすかにくもりました。
「あー、でも、たぶん確実に、河合先生の最後の願いは叶わないままかもしれないね」
「それは?」
と、咲は首を傾げます。
「ほら、咲ちゃんも聞いてたじゃない。私、一日でも多く森羅さんより長生きしたいって、河合先生がおっしゃったの」
ああ、そうだった、と咲は思い出しました。まだ河合先生がお元気でいらした頃だった、と。
河合理智子は言ったのです。森羅さんより先に死んだら、後で何を書かれるか解らないもの、と。
森羅万里は、河合理智子と同い年の大正十五年生まれでした。二人は小説家志望の若い頃からの親しい付き合いで、互いに切磋琢磨して文学修業に励んで来た、とは森羅万里の言い分でした。河合理智子に言わせると、切磋琢磨なんて、誰ともしたことないわ、とのことでしたが。
「でも、森羅さんと仲が良かったのは確かねって、河合先生は御自分でおっしゃってましたよね」
「そう。そして、仲たがいしたこともいっぱいあった、ともおっしゃった」
「ああ、そうでした。それで、御自分は森羅先生より一日でも長く生きないとって……あれ、マジだったんですか? 冗談かと思った。笑っていらしたし」
「咲ちゃん、編集者なら、もっと観察眼を養わなくっちゃ。あの時、河合先生の目は笑ってなかったよ」
はあ、と肩をすくめる咲でした。
森羅万里は、出版界では特別な地位にある作家でした。そのスピリチュアルな言動と、華やかでありながら威厳に満ちた容姿、そして、それを裏切るようなチャーミングな語り口で、熱狂的なファンを獲得していました。TV出演も積極的にこなしていましたから、多くの人々に顔を知られて、どこに行くにも握手やサインを求められる有様。困ったように笑みを浮かべながらも、彼女自身まんざらでもないようでした。
「これで、もう少し小説の方も売れれば、ばんばんざいなんだけどねえ」
追っかけファンの多さを内心喜びながらも、森羅万里は、そう愚痴るのが常で、そして、それもまた本当なのでした。彼女の人生論を説いたものや悩み相談は人気があって、たいそう売れましたが、小説の方は、なかなかそこに届かないのでした。
「頭来ちゃうわ。私、小説家なのにさ」
新人作家のように口を尖らせる女流の大家を周囲は、微笑ましい気持で見詰めたものです。
咲が初めて大阪にある森羅万里の屋敷を訪れたのは、大手である太陽出版に入社してまもない頃でした。当時、大衆小説と呼ばれた読み物を集めた雑誌の編集長と、そこでも名を成していた森羅万里の担当だった先輩男性編集者、岡安に同行したのでした。
「あら、岡安さんの後は、この方が担当に? ずい分とお若いけれど?」
咲は、女性たちのカリスマと呼ばれる高名な作家を前にして身の縮む思いでしたが、岡安は、まるで年の離れた弟のように親し気に口を利くのでした。
「いや、まだ担当見習いといったところですが、これから少しずつ仕事を覚えて行くでしょう。この世界の流儀をこの林田に叩き込んで鍛えてやってくださいよ」
何、これ、まるで運動部みたい、と咲が呆気に取られていると、森羅万里は言ったのでした。
「やーだ、私、親でも先生でもないもん。なんで私がこの女の子の教育係にならなきゃなんないの?」
はっ、と岡安は一瞬、恐縮したかのように背を伸ばして見せましたが、顔には柔和な笑みを浮かべたまま動じることもありません。二人だけのお約束めいたやり取りなのかもしれません。
編集長がにやにやしながら、間に割って入りました。
「まあまあ、森羅さん、この岡安もずい分と年を取って、やがてガタも来るでしょう。その前に、しっかりと引き継ぎをして、最強の森羅万里担当を育てたいんですよ」
「えー? それなら、私、若い男が良かったかなー」
と、言いつつ咲の顔をちらりとうかがって、森羅万里は、ぺろりと舌を出しました。その、悪戯好きな少女のような振る舞い。
「なーんてね。私は、若い女も大好きよ。女性相手なら、セックスが絡むこともないから気楽だしね」
思わず口の中の玉露を吹き出しそうになった咲でしたが、側にいる男二人は動じる素振りもありません。この種の物言いには慣れているのでしょう。
しばらくの間、刊行予定の単行本についての打ち合わせが続きましたが、やがて一段落すると、森羅万里は、佳代ちゃーん、と秘書を呼びました。すると、その佳代さんは、待ちかまえていたかのように、すっと襖を開けて、二人の手伝いの人を従えて中に入って来ました。そして、あれよあれよ、と言う間に酒宴の支度を整えたのでした。
おお、これはこれは、と編集長は年代物らしいワインのボトルを手に取りしげしげとながめています。
「谷原編集長は白ワインよね。いただきものだけど、このムルソーを開けて。岡安さんは、何でもいけるんでしょ? 私と一緒にシャンパンを飲んでもらえる?」
「御相伴に与ります」
で? と森羅万里は、咲に問いかけました。あなたは、どうするの? と。
どぎまぎしました。咲の飲酒歴は、大学のサークルのコンパ以来、全然進化していなかったのです。
「何でもお好きなもの言ってちょうだい」
「え……と、あの、じゃ、私、ハイサワーで」
お、おいおい、居酒屋じゃないんだから……と、上司二人は、この屋敷に来て初めて慌てたようでした。
しかし、森羅万里は、呆れた様子も見せずに、もう一度、佳代さんを呼ぶと、この方にはハイサワーを、と申し付けたのです。そして、また佳代さんも一向に動じることなく、すみやかに盆にハイサワーセットとも言える一式をのせて運んで来たのです。
「御自分で飲みたいように作ってちょうだい」
はい、と言って、アイスペール代わりの九谷の器を移動させた咲でしたが、男たちの困惑した視線を感じて、ようやく自分が場違いなことをしていると気付きました。そう言えば、この氷の容れ物、豪華過ぎる! ここでハイサワーなんて飲む人、いないんだわ。
「ねえ、咲ちゃん。咲ちゃんて呼んで良いかしら」
はい、という返事も、マドラーを持つ手も震えてしまう咲でした。
「咲ちゃん、ハイサワーのハイって、どういうところから来ているか知ってる?」
「……高みに登るとかですか? それとも、ウイスキーのハイボールの真似……とか?」
それがね! と言って、森羅万里は嬉し気に手を叩いたのです。
「ハイサワーのハイは、実は『我輩』の『輩』なのよ!」
「え? あの、ヤカラって書く『輩』……ですか?」
「そう! 知らなかったでしょ。私、創業者のお友達に聞いたんだもん! 本当よ」
そう言って、森羅万里は得意気に鼻を蠢かすのでした。
「ハイサワー飲むお客さんなんて、なかなか来ないから、このこと教えてやる機会もなかったの。今日は、最高!」
森羅万里は、手にしているシャンパンフルートを咲のごついグラスに控え目に当てて乾杯しました。
その後の数時間の楽しさと言ったら! 咲は初対面の作家の家にいるのも忘れて、飲んで食べて笑って、至福の時を過ごしたのでした。
あの時の森羅万里は、既に六十なかばを超えていたでしょうか。金色に染めて巻いた長い髪は若作りというより、まるで彼女を王妃か何かのように威厳たっぷりに見せていましたが、気さくな口調は、女友達に対するそれのようでもあり、日本文学の歴史をつぶさに見て来た生き字引のようでもありました。そして、それらを下世話におもしろく、しかし、それなりの深味を込めて語る。
「日本文学は、ゴシップの歴史なのよ」
続きは単行本でお楽しみください!
山田詠美 長編小説『三頭の蝶の道』