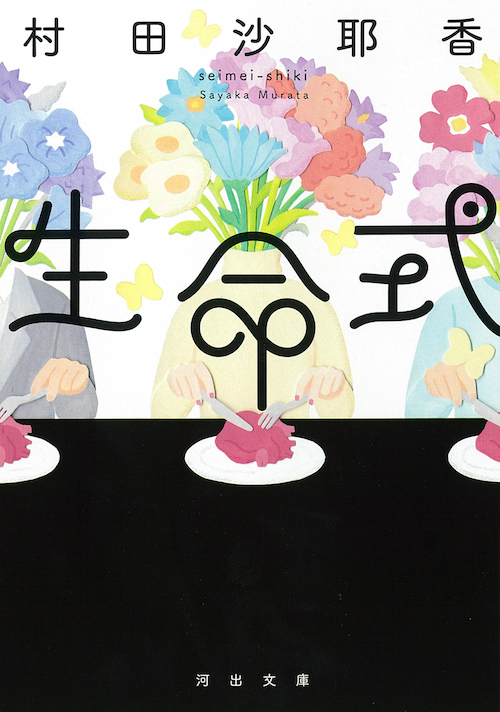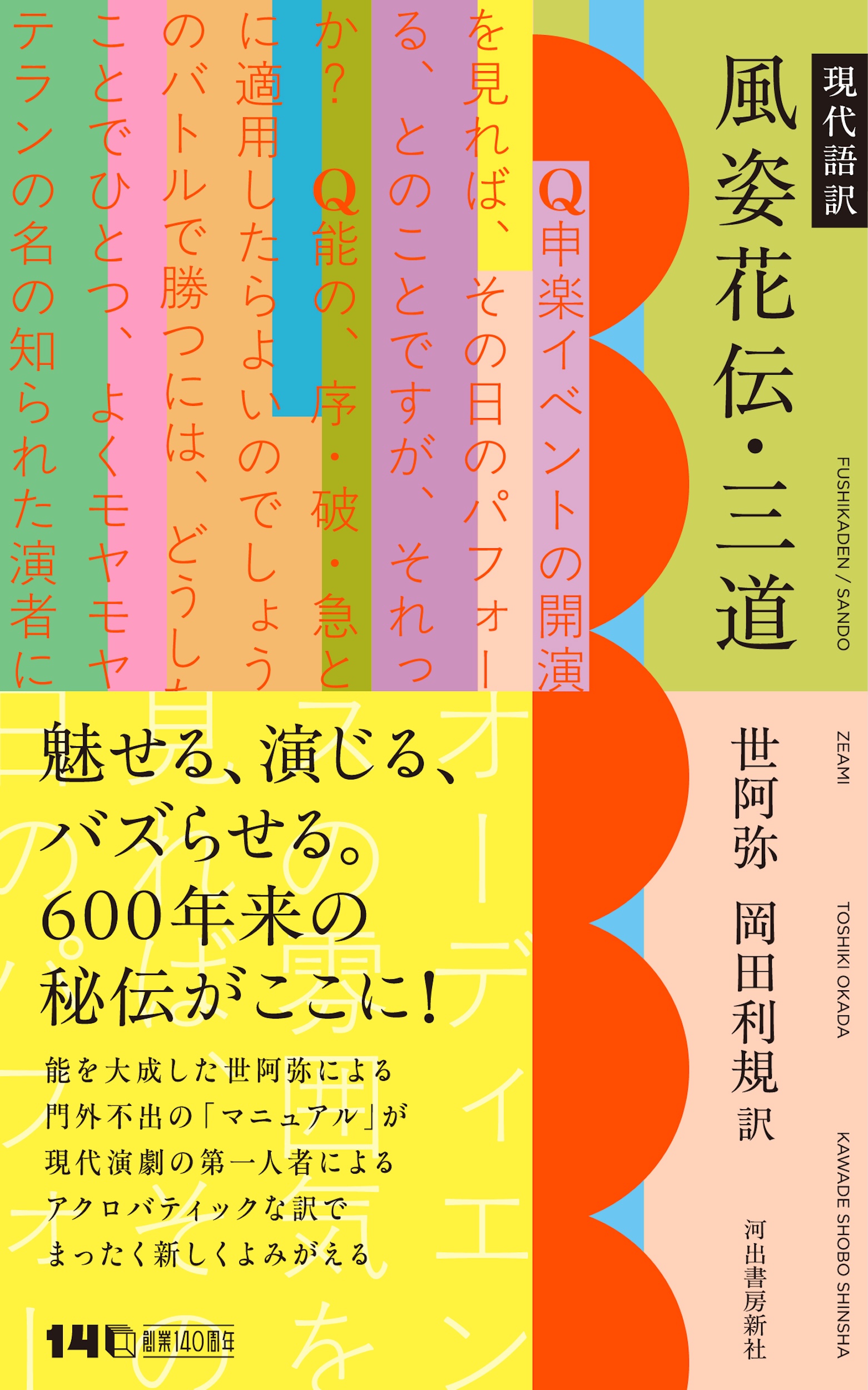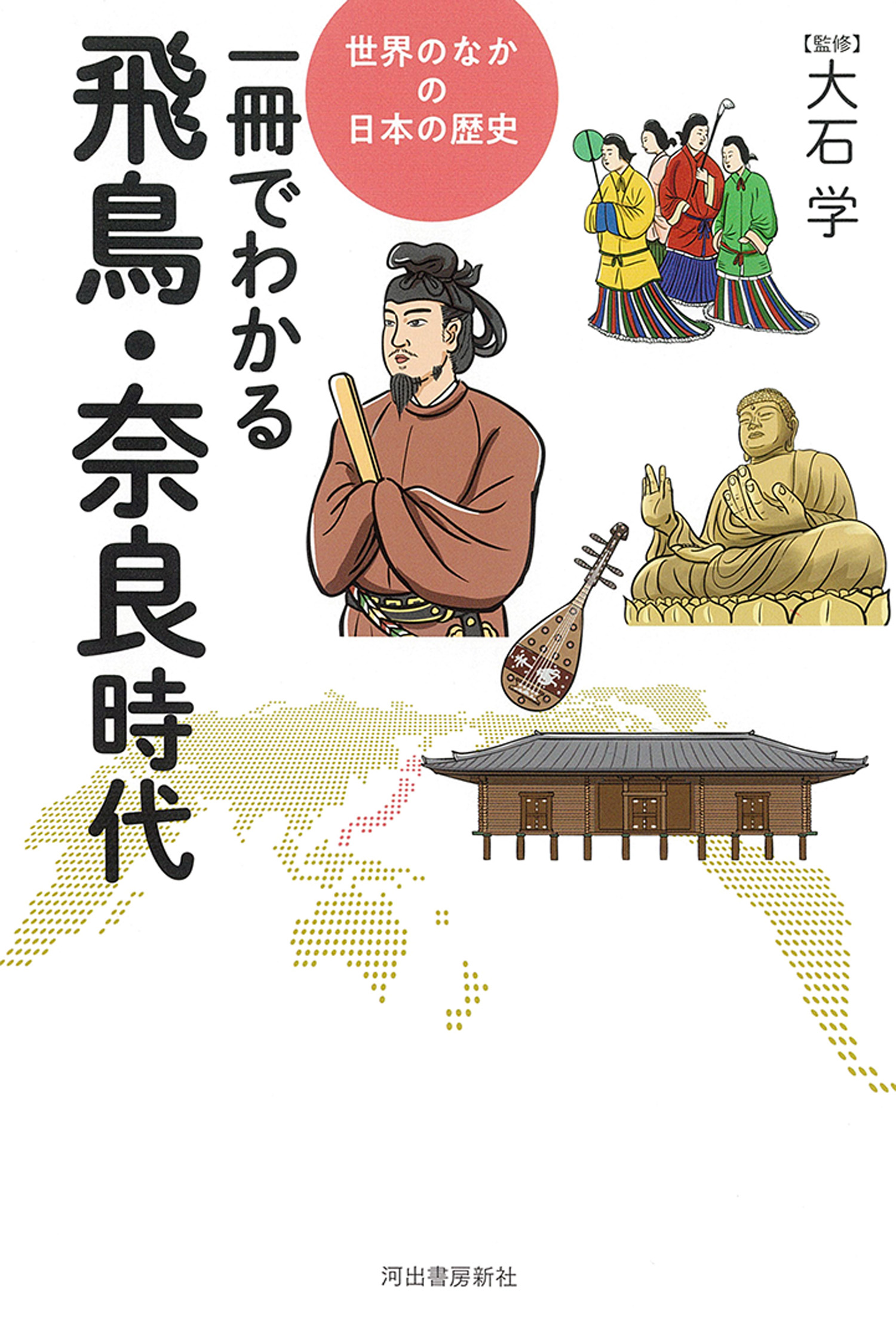ためし読み - 日本文学
「セックス」も「家族」も消えた未来──世界的ベストセラー作家 村田沙耶香作品『消滅世界』冒頭21ページ大量無料公開
村田沙耶香
2025.11.28

世界で熱狂的に愛される村田沙耶香作品。
『消滅世界』は人工授精で子供を産むことが常識となった近未来を舞台にした作品。「日本の未来を予言している」「見たこともない恐ろしい『楽園』」と話題を呼び、15万部突破のロングセラーとして愛されています。

『消滅世界』(河出文庫)
『消滅世界』あらすじ
人工授精で、子どもを産むことが定着した世界。そこでは、夫婦間の性行為はタブーとされ恋や性愛の対象は「家庭の外」の恋人か、二次元キャラというのが常識に。そんな世界で「両親が愛し合った末」に生まれた主人公・雨音は、母親に嫌悪を抱いていた。家庭に性愛を持ち込まない清潔な結婚生活を望み、夫以外のヒトやキャラクターと恋愛を重ねる雨音。だがその“正常”な日々は、夫と移住した実験都市・楽園で一変し──。
「アダムとイヴの逆って、どう思う?」
昔、恋人にそう聞かれたことがある。
二十歳のころ、誰もいない家へ恋人を連れ込んだときのことだ。
二人の体温が溶け込んだシーツの中でうとうとしていた私は、外の雨の音と混じるように自分にむけて舞い落ちてきた不可解な質問に、薄く目を開けた。
「逆って、どういう意味?」
「アダムとイヴはさ、ほら、禁断の果実を食べて、楽園から追放されただろ? 人類で最初にセックスをした男女なんじゃなかったっけ? だから、逆に人類がどんどん楽園に帰っていくようになって、最後にセックスをする男女がいるとしたらさ、それってアダムとイヴの逆だろ?」
まどろみながら、私は恋人に返事をした。
「そんな話だったっけ……? アダムは善悪の実を食べたあと、労働をしないと食べ物を得ることができなくなって、イヴは出産の苦しみがすさまじくなったとか、そういう話じゃなかったっけ」
「あれ、そうだっけ」
恋人は吞気に言って煙草を吸い始めた。
「でもほら、快楽とか恥じらいを知ったのは、果実を食べたせいじゃなかった? 俺の中で、雨音って、最後のイヴっていうイメージなんだよな。皆が楽園に帰っていく中で、最後の人間としてのセックスをしている存在っていうかさ」
「何、それ。怖い。呪いみたい」
「何となく、そんな気がするんだ」
恋人は私の髪を撫でた。
「まさか」
私は笑ったが、その呪いのような言葉は身体の中に入り込み、肌の裏側にこびりついてはがれなかった。
私が生まれた日のような、強い雨の音がする夜明けのことだった。
Ⅰ
小学校にあがるまで、私は母の作った世界の中で暮らしていた。
保育園には通っていたが、その記憶はあまりない。当時の自分を思い返して浮かび上がるのは、母と二人きりで過ごした木造の小さな一軒家の光景ばかりだ。
そのころには、離婚した父はもう家を出て行ってしまっていた。けれど、テレビ台の上や母の化粧台など、家の随所に父が写った写真が飾られていた。私を抱く父の写真がびっしりと貼られたアルバムを開きながら、母は、「お父さんはね、本当に雨音ちゃんを愛していたのよ」と何度も私に言い聞かせた。
私たちが住んでいたのは亡くなった祖母が遺した古い一軒家だった。外観は和風なのに、部屋の中には少し黒ずんだ赤い絨毯が敷かれ、洋館のようになっていた。
赤は母が好きな色だった。部屋には小さな赤いソファがあり、カーテンにも赤い花が散らばっていた。夜になると光るガラスの小さなランプも仄かな赤い光を発していた。
赤いソファの背後に古い障子があるような、ちぐはぐで悪趣味なインテリアだったが、母は、「愛の色だから、お母さんはこの色が大好きなの」といつも言っていた。
母は二階の小さな和室にベッドを置き、母はベッドで、私は横に敷いた布団で眠った。母はいつも、古いお伽噺を読み聞かせるような口調で、自分と父のなれ初めを話して聞かせた。
「お父さんとお母さんはね、とっても好き合ってたの。恋に落ちて結婚して、愛し合ったから雨音が生まれたのよ」
「うん」
私は素直に頷いた。母が絵本をめくるように私に見せるアルバムには、背が高くて気が弱そうな青年が生真面目な顔で写っていた。それが自分の父だと言われても、ぴんとこなかったが、この二人きりの家では、母の言うことが絶対だった。
「駆け落ち同然だったの。本当に本当に、愛し合っていたのよ」
「うん」
「雨音ちゃんも、大きくなったら、好きな人と結婚するのよ。そして、恋をした相手の子供を産むの。とっても可愛い子供よ」
そのアルバムの他に家にあるのは、大量のボロボロの絵本で、お姫様と王子様が愛し合って結婚する物語ばかりだった。保育園にあるような、新しい綺麗な絵本が欲しかったし、ねだったこともあったが、いつもすげなく却下されていた。
「雨音ちゃんも、いつか好きな人と愛し合って、結婚して、子供を産むのよ。お父さんとお母さんみたいに。そして愛する二人で、大切に子供を育てるのよ。わかった?」
「うん」
私が大人しく話を聞いていると、母は機嫌がよかった。保育園はあまり好きではなかったので、母の与える世界が、私のすべてだった。
だから私は、母の与える「正しい世界」を全身で吸収しながら育った。
うとうとと眠くなると、母の体温と頰に押しつけられた柔らかい乳房の感触や、抑揚をつけてしゃべる囁き声はゆっくりと遠ざかっていった。閉じた瞼の向こうに、母が床に置いた赤いランプの光を感じた。いつも、その赤い光に吸い込まれるように、私は眠りについていた。
初めて恋に落ちたのは、まだ保育園に通っていたころだ。
男の子はテレビの中の男の子だった。
どんな恋にも、恋に落ちる瞬間というものが必ずある。その時が訪れるまでは、私は単にそのアニメーションが面白く、保育園でも観ている子が多かったので毎週テレビを点けていただけだった。
それは子供の中で流行っていたアニメーションで、私も木曜日の夕方になるといつもかじりついてそれを観ていた。
その物語は、七〇〇〇歳の不老不死の少年が、色彩を奪われた世界に少しずつ色を取り戻していく物語だった。
最初にテレビを点けたときは、変なアニメだなと思った。画面は真っ暗で、声しかしなかった。
やがて主人公の少年ラピスは「白」を取り戻し、画面は白黒になった。そのとき、初めてラピスの顔がわかった。少し猫のようなきつい目をした、十四歳ほどの姿の少年だった。
物語が進むにつれて、ラピスは一つずつ色を世界に取り戻していった。黄色、紫色、緑色。赤を取り戻したときは、ラピスの身体から出てくる血液にはっとした。
そして物語の中盤、青が世界に取り戻され、空と海が一気に青く染まった。ラピスがやっと青い瞳を取り戻したその場面を見たあとは、涙が止まらなかった。
不老不死の男の子が、腕を切られ、足を切られ、それでもヒロインの女の子のために闘い続け、顔も切られて指一本になっても闘い続けたとき、画面いっぱいに広がる男の子の血と、繰り返されるヒロインの悲鳴を聞きながら、私はその男の子に心を奪われてしまったのだった。
今までに経験したことのない、熱を持った針が心臓に埋まっているような、不可解な疼きと痛みが私を襲った。
眠ろうとしても痛みは消えず、男の子の姿ばかりが浮かんだ。
世界に色を取り戻したあと、ラピスの身体はバラバラになり、研究所へ連れていかれ、歳をとった博士が再生手術を行った。男の子は不老不死だとわかっているのに、彼が本当に戻ってくるのか気が気ではなくて、眠れない日々が続いた。
そして、やっと手術に成功した男の子が再び画面に現れたとき、私はもう、その青い目を真っ直ぐに見ることができなくなっていた。
身体が火照って、体中の皮膚が裏側からくすぐられているような、不思議な、こそばゆい気持ちになった。心臓は病気ではないかと思うほど痛んだ。テレビを観ているだけなのに、こんなふうに身体がおかしくなることが、不思議でしょうがなかった。けれど全身が、彼にもっと会いたいと訴えているのだった。
「ねえお母さん、私、この子に会いたい」
私は母に訴えた。
「この子には会えないのよ。どこにもいないんだから」
洗濯物を畳んでいた母はふっと笑ってぞんざいに答えた。
母は、私を小馬鹿にし、失望させようとしているようだった。けれど、「会えない」という言葉が私の内臓の奥からさらに熱い熱の塊を引きずり出した。
私にはすぐにわかった。会えないことも含めて、その人はその人なのだということが。そのこと自体も含めて自分がその男の子を好きになっているのだということが。
全身の不可解な痛みと、強烈に循環する血液の感触は続いていた。恋とはこういう疼きと痛みを身体に宿すことなのだと知った。
私はこのとき、物語の中に住んでいる人に、初めて自分が恋をしているのだと悟ったのだった。
自分がちょっと変わった方法で受精された子供だと知ったのは、小学校四年生の性教育の授業のときだ。
明日が性教育だという日、母は茶色く変色した古い本を私に見せ、挿絵を指差しながら私がどのように父との間にできたかを説明した。その話はどこか薄気味悪かったが、私は大人しく聞いていた。勉強だと母が言ったからだ。
しかし翌日の性教育の授業では、昨日とはまったく違うことを教えられた。人工授精のしくみと、それによって子供が生まれる生命の神秘についてのDVDを延々と見せられたのだ。
母は噓をついたのだろうか、と最初思った。先生が間違っていることを言うはずはない。不思議に思って、放課後、担任の女の先生にこっそり聞いてみた。何かわからないことがあったらいらっしゃいと、授業の最後に優しく言ってくれていたからだ。
私の話を聞いた担任の先生は困惑した様子だった。
「……ええと……昔はそういう方法で妊娠する人が多かったのよ。お母さんは、きっと科学の発達の歴史を、雨音ちゃんに勉強して欲しかったんじゃないかしら」
「いえ、私はそうやって生まれたんだって、母が言ってたんです」
「まあ……ええと……」
「母はおかしいんでしょうか? 噓をついているんでしょうか?」
「……そうね、こんど家庭訪問があるから、少し先生もお母さんとお話ししてみるわね。きっと、お母さんは勉強熱心なだけなのよ」
だが家庭訪問に来た先生にも母はあけすけに、自分が性行為で私を妊娠したことを話し、仰天した先生がつい同僚に漏らして、職員室で話題になってしまった。
話はいつの間にか、PTAまで広がった。男子からは学校で下品な言葉でからかわれた。
「お前んちって、父さんと母さんがヤッて生まれたんだろ? そういうのキンシンソウカンっていうんだぜ、うげー、気持ちわりー!」
吐く真似をする男子に、私は反論できなかった。吐き気を誰よりも堪えているのは自分だったからだ。
私が顔を真っ赤にして俯いていると、担任の先生が慌ててやってきて、
「そんなこと言うんじゃありません! 昔はみんなそうだったのよ」
と男の子をった。けれど、先生こそがそれを不気味に思って言いふらした張本人なので、説得力はなかった。
「昔」がいつのことなのか、そのときの私にはさっぱりわからなかった。けれど、私はそのとき、自分が住んでいるあの赤い部屋は、冷凍保存された過去に囲まれた密室だったのだと知ったのだ。
それからは毎日図書館に通って、「正しい」性について調べた。
「ヒトは科学的な交尾によって繁殖する唯一の動物である。
第二次世界大戦中、男性が戦地に赴き、子供が極端に減った危機的状況に陥ったのをきっかけに、人工授精の研究が飛躍的に進化した。男性が戦場にいても精子を残していけばそれで妊娠が可能になり、残された多くの女性が人工授精で子供を作った。
戦後になると人工授精の研究はさらに進んだ。人工授精による受精の確率は交尾よりも圧倒的に高く、安全であり、先進国から、今では全世界に広まり、交尾で繁殖する人種はほとんどいなくなった。
繁殖に交尾はまったく必要なくなったが、今でも人間は年頃になると、昔の交尾の名残で恋愛状態になる。アニメーションや漫画、本の中のキャラクターに対して恋愛状態になる場合もあれば、ヒトに対して恋愛状態になる場合もあるが、根本的には同じである。
恋愛状態が進み、発情状態になると、それをマスターベーションで処理する。性器を結合させ、昔の交尾に似た行動をとって処理する場合もある(これをセックスと呼ぶ)。
ヒトの妊娠・出産は科学的交尾によって発生するので、恋愛状態とは切り離されている。子供が欲しくなると、パートナーを見つけ、女性が病院で人工授精を受けて出産する。男性は今の科学の力では妊娠ができないので、女性が出産するしか現代では方法がない。最近は、人工子宮の研究が進んでおり、男性や、自分の子宮では妊娠ができなくなった高齢の女性なども、妊娠・出産ができるようになるのではないかと、期待が高まっている。」
たくさんの本で調べて、正しい知識が増えていくにつれ、疑問は強まるばかりだった。なぜ母は、父の精子を人工授精するのではなく、わざわざ避妊器具を外して交尾をしてまで自分を妊娠したのだろう。考えるだけでいつも気分が悪くなった。
私は母とあまり口をきかなくなった。母も何かを察したのか、私にしつこく原始的な交尾について話すことはなくなった。
三学期になった冬のある日、私の髪の毛を三つ編みにしている母に、思わず聞いてしまったことがある。
「ねえ、何で?」
「なに? 雨音、どうしたの?」
「お母さんは、何で、『普通じゃない方法』で私を妊娠したの?」
母は息を吞み、三つ編みをする手が一瞬止まったが、ふっと息を吐くと、再び手を動かし始めた。
呟くように母が言った。
「そんな予感がしていたわ」
それが返事なのか、独り言なのか、私にはわからなかった。
「見て、雨音。今日も雨が降っている。あなたが生まれた日も、こんな風な夏の匂いのする雨が降り注いでいたのよ」
飄々とした顔でそう言い、母は急に、私の三つ編みから手を離した。
「うまくできないわ。右と左の太さがばらばら。もう大きいんだから、自分でやりなさい」
私は、自分が頼んだわけではないのにとむっとして、髪をひっつめにして学校へ行った。学校へ行くと、友達が、
「何か今日、雨音ちゃん大人っぽいね」
と褒めてくれた。いつもは母の趣味で編み込みや三つ編みを駆使した女の子っぽい髪形にされていたので、新鮮だったのだろう。
「うん。これからはもう、前みたいな子供っぽい髪はやらないの」
私はつんと顔をあげて、友達にそう答えた。自分は、母が作り上げた箱庭の外に出るのだ。漠然とだが、そのとき私は自分が新しい世界へ踏み出せたのだと感じていた。

続きは『消滅世界』(河出文庫)でお楽しみください。