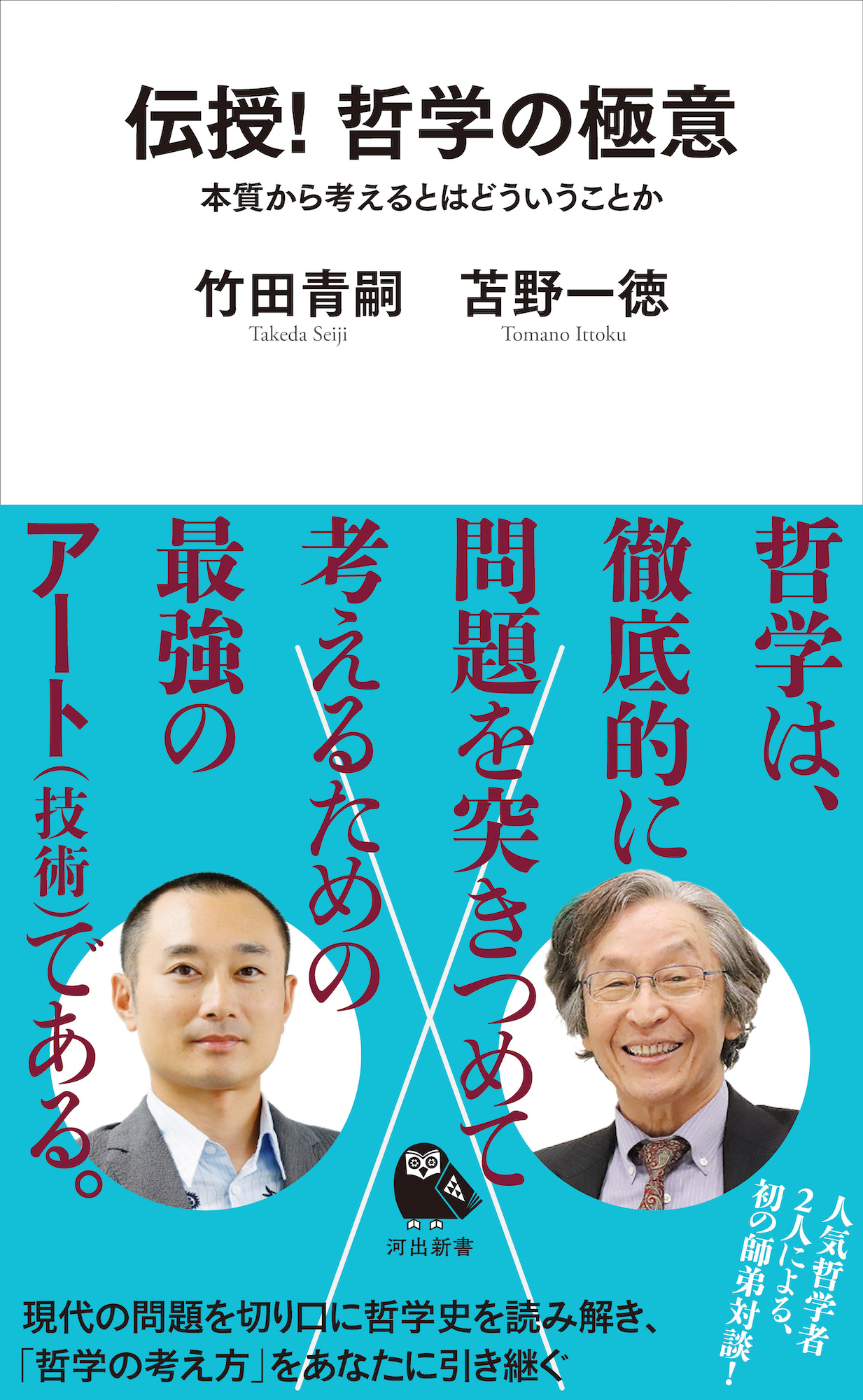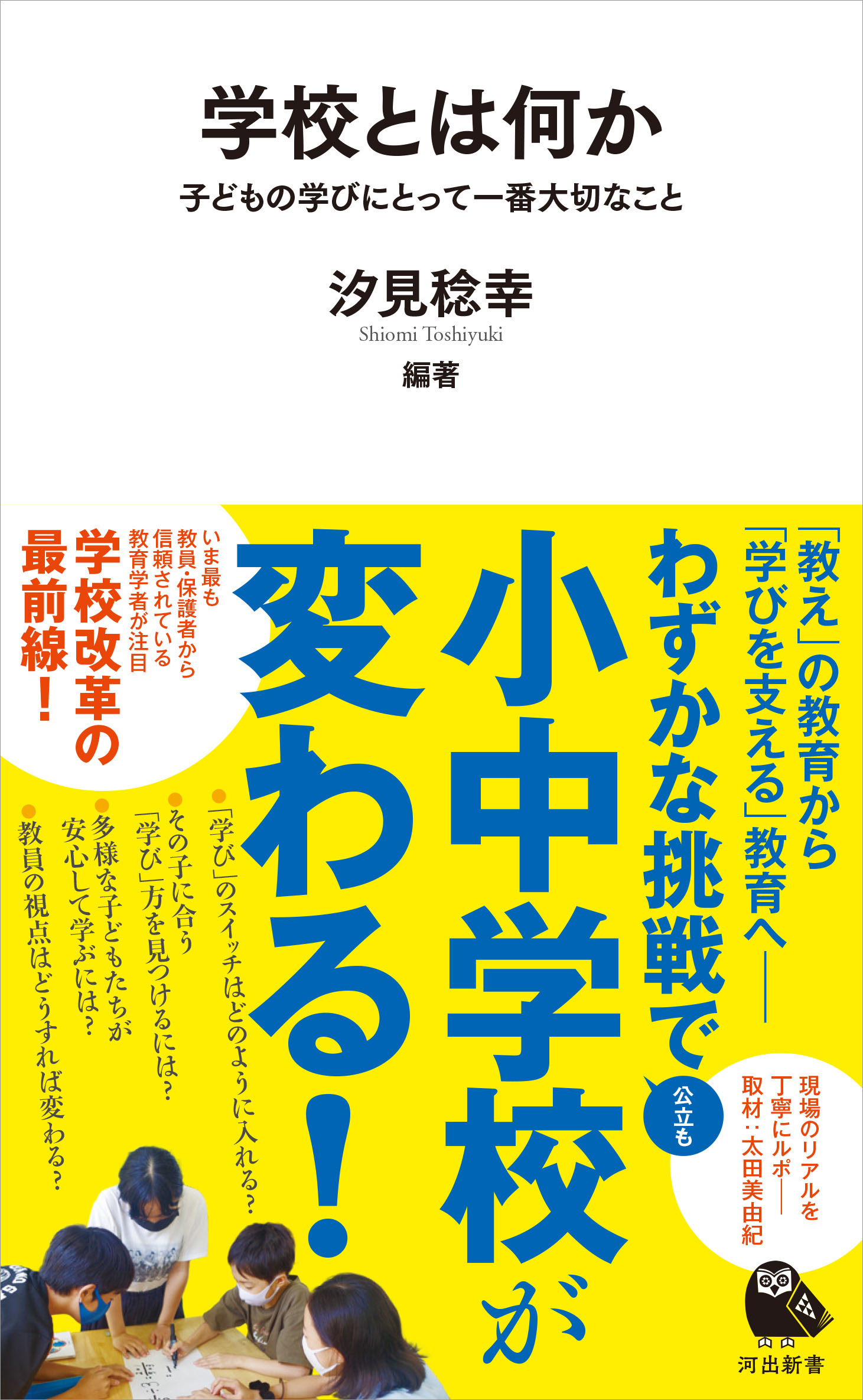ためし読み - 新書
幽霊や霊魂が存在するか、死後の世界があるのか、仏教では、お釈迦様の時代から公式見解が決まっている。それは──恐山の住職代理が説く「生きる」とは
南 直哉
2026.02.19

死とは何かという根本的な問いに正面から向き合おうとする試みで書かれた『「死」を考える』。
恐山の禅僧 南直哉が、小児喘息で死と隣り合わせだった幼少期の原体験や、僧侶として多くの人の死に寄り添ってきた経験を踏まえ、死とは何か、自分とは何か、そしてどう生きるかを問う一冊から、一部を無料公開します。死と向き合い続けることで、苦しくてもどうにか生きていくための手がかりが見えてきます。
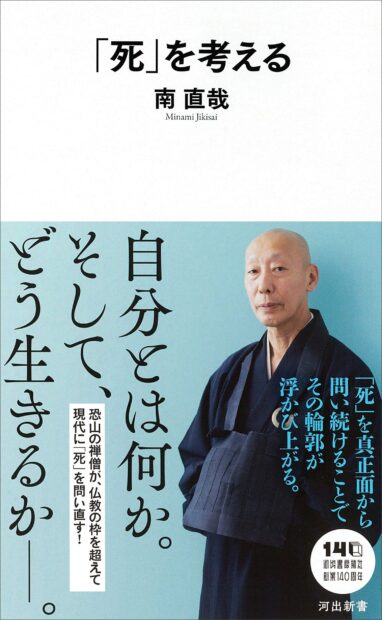
南 直哉『「死」を考える』
死について語れる人間はいない
世の中にあふれる死についての語りは、死を語っているのではない。彼らが語っているのは、ほとんどの場合、死ぬまでの話か、死んだ後の話にすぎない。死そのものは語れるはずがないのである。
死ぬまでの話は、要するに、老いと病と我が身の始末についての話であろう。どうそれらに対処するかという、生きている間の案件にすぎない。
死んだ後の話は、古今東西、人類の社会と文化のあるところ必ず語られるが、その物語が本当かどうか確かめる術は原理的に存在しない。
だいたい私の知る限り、「死後」の話をしている人物は、全員生きている。その話のすべては、生きている人間が、生きている間に、生きている限りの経験として、なされているにすぎない。死人が出てきて死後の話をしているわけではないのだ。
この「前」「後」の話以外によく出てくるのは、いわゆる「臨死体験」と「脳死判定」にからむものである。
まず、そもそも「臨死体験」は死の経験ではない。当人は要するに生きているのだからこそ、「臨死体験」を語れるのである。
また、「脳死判定」は死を検出して判定しているのではない。検出しているのは、脳の生理的過程と反応である。そこに特定の不可逆的現象を検出したとき、それを「死」と考えようというだけのことなのだ。人工呼吸装置の発明が「脳死」のアイデアを制作したのである。
つまり、「脳死判定」は、死が絶対的に「わからない」純粋な観念であることを、最も端的に示している例である。誰にもわからないから、ご時世の都合で適当に決めて、法律で強制できるのである。
死は、いかにしても語ることはできない。というよりも、語られた死は死ではない。いわば、死はわれわれに対して「絶対答えられない問い」として以外に現前しないのだ。
「死後の話」を欲望させるものとは
死は語り得ないが、死後についての話は世に尽きない。
たとえば、私がいま住職代理(院代)を務めている恐山(恐山菩提寺)は、古くから「霊場恐山」と呼ばれていて、これを聞けば大概の人は、「幽霊の出る恐いところ」、と思うだろう。
あの火山岩がゴロゴロしたところに風車が林立する現実離れした風景と、いわゆる「イタコ」さんの存在からすれば、そう思われるのも無理はない。
それが証拠に、数年に一度、恐山には東京のテレビ局から、「スピリチュアル」系のバラエティ番組の取材依頼がある(ちなみに、恐山はこの種の番組の撮影とイタコさんに対する境内での取材は一切受け付けない)。
ここ最近で一番笑ったのは、某局のアシスタント・ディレクターらしき若者が恐る恐る申し出てきた、「幽霊の実況中継」なる企画である。
「ご存じかどうか知りませんが、この種の番組はほとんど、写真か再現フィルムしか出てきません。しかし、私たちは違います! 夜中に恐山の岩場にテントを張って、出るまで待ちます!!」
これを正気で言っているなら、番組のレベルが知れるところだろうが、問題は幽霊が出るかどうかではない。そうではなくて、この種の番組が繰り返し放送されていること、つまり、一定の視聴率がコンスタントに取れるほどの需要が、いつまでも尽きないということだ。
ちなみに、ご承知のように、幽霊や霊魂が存在するかどうか、死後の世界があるのかないのかなど、これらの疑問について、仏教では、ゴータマ・ブッダ(お釈迦様)の時代から、公式見解が決まっている。それは「答えない」という答えである(この態度を称して「無記」と言う)。その意味を私流に言わせてもらえれば、あると言ってもないと言っても、その断定はナンセンスになるということだ。
「ある」と言うなら、すでに述べたとおり、この話はすべて生きている人がしているのだから、それは断然「死後」の話ではない。
では、「ない」と言い切れるか? 古今東西、社会と文化のあるところ、こういう話のない社会と文化は、ただの一つも存在しない。これだけ人類が熱心にし続けている話が、最初から根も葉もないでっち上げと言う根拠もないだろう。
かくのごとく根拠不明にもかかわらず、世に「死後」の話の需要は厳然と、しかも大規模に存在する。この需要はどこから来るのだろうか。
それは不安からだろう。死の不安が、「死後」の話を欲望させるのだ。
死と同じように「生」も絶対にわからない
不安は恐怖とは違う。不安は正体不明のものに脅威を感じることである。恐怖はその対象がわかっている。
「幽霊の 正体見たり 枯れ尾花」という諺があるが、「幽霊」と「枯れ尾花」の区別がつかないから、人は不安になるのであって、それがまさに「幽霊」だとわかって初めて、恐怖するのである。
死が絶対にわからないなら、恐怖することはできない。では、人が「死ぬのが怖い」と言うとき、何を言っているのか。「怖い」対象は何なのだろうか。
一つは、死ぬまでの身体的苦痛だろう。「死がイヤなんじゃない、死ぬのがイヤなんだ」という誰かのセリフは、それを言っているのだろう。
もう一つは、「死んだらどうなるか」という問題だ。結局、それらは、「死そのもの」ではなく、「死ぬ前」と「死んだ後」の話にすぎない。
このとき、「前」は主に医療の問題であり、「後」は宗教の領域にある。その「後」の問題で肝心なところは、それがあくまでも「自分の死後」の話だということである。
だが、この「自分の」という意味について、よく考えておかなければならない。
「死の不安」は、実は「自分が存在していることの不安」に直結している。それゆえに人々は、「死後の世界」を強く求めるようになるのである。
死が絶対にわからないことだとすれば、それは言うなれば、「生きていく」ということが、行先のわからないまま歩いているのと同じで、要は「彷徨っている」のである。これは不安だろう。
目的地がわからず彷徨っている不安をかろうじて抑えているものがあるとすれば、出発地点はまだ覚えている、ということだ。いざとなったら帰ろう、出発地点に引き返して出直そう——そう思えばこそ、現在の彷徨に耐えられもしよう。
とすると、死が何かわからないという不安がどうにも解消できないとなると、思考は反転し、では生まれるほうはどうだ、となる。出発地点を確認したくなるわけだ。つまり、なぜ生まれてきたのかがわかれば、死の意味もわかるかもしれない、と考えるのである。無理もないところではある。
ところが、死と同様、自分がなぜ生まれたかも、絶対にわからない。死と同様、誕生するとき、それを経験できる「自分」はいないからである。
生まれた後に、その「理由」の話をする人間は大勢いる。ある者は「神が命令した」と言い、別の誰かは「仏が送り出した」と言うかもしれない。しかし、何を言おうと、それらはすべて後知恵で、本当かどうかは確かめようがない。本当か噓かわからないことは、普通「理由」や「根拠」にならない。
生まれてくる前、母親のお腹の中にいる間に、どこからか何かの声が聞こえてきて、「君は○○年△△月××日に、日本の某県に、こういう人を両親として生まれ、およそこういう人生を送ることになりますけど、よろしいですか?」と問われて、「ハイ!」と返事して生まれてきたなら、これを「理由」だの「根拠」だのと言うのも道理だが、それ以外はお伽噺と変わらない。
われわれは事実として、何の理由も根拠もなく生まれる。ということはすなわち、自分の生の意味も価値も知らぬまま、問答無用、ただ生まれてくる。これは死の絶対的なわからなさと同様の「原理的なわからなさ」なのである。
==全編は『「死」を考える』でお楽しみください。==

南 直哉『「死」を考える』