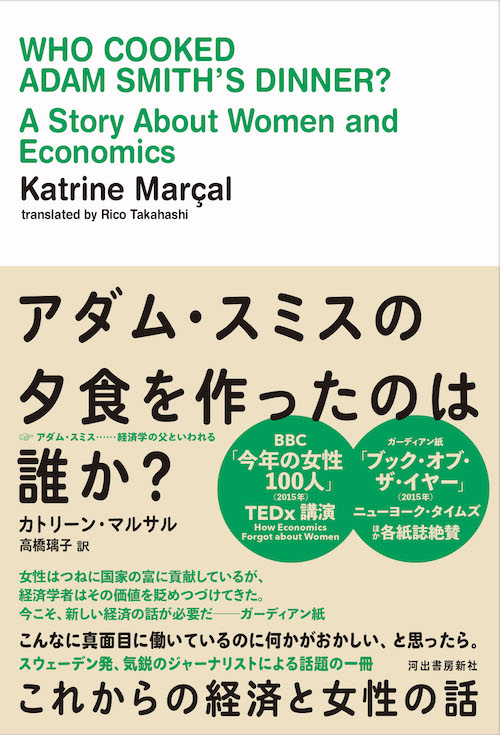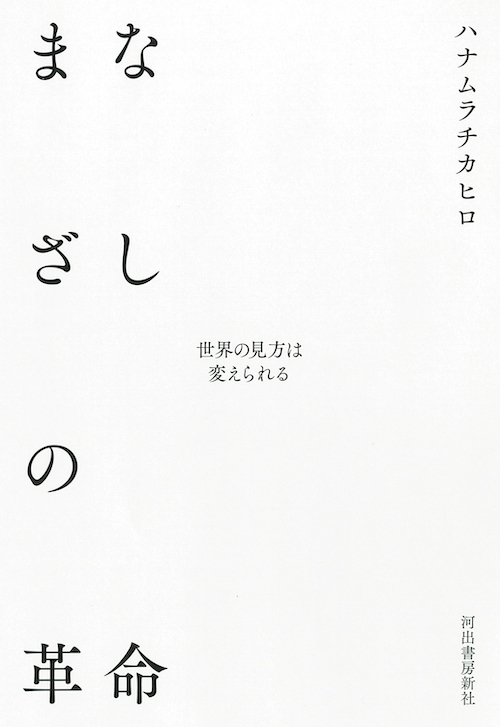単行本 - 政治・経済・社会
『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?』プロローグ無料公開 経済と女性の話をしよう
カトリーン・マルサル著 高橋璃子訳
2021.11.18
とびきり刺激的な経済学の本が届きました。『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?』。本書を刊行後、著者はBBCの選ぶ「今年の女性100人」に選出。本書自体もガーディアン紙のブックオブ・ザ・イヤーに選出され、今や世界20カ国で翻訳されています。
ついに今月、邦訳が刊行されましたが、従来の経済学の不備をするどく指摘し、パラダイムシフトを起こす内容に、早くも大きな反響の声が届いています。
女性不在で欠陥だらけの経済神話を終わらせ、新たな社会を志向するスウェーデン発21世紀の経済本から、著者によるイントロダクションを公開します。
フェミニズムはつねに、経済を語ってきた。ヴァージニア・ウルフは女性に「自分ひとりの部屋」が必要だと説いたが、そのためにはお金がかかる。
19世紀後半から20世紀初頭にかけて、女性たちはさまざまな権利を手に入れるために立ち上がった。相続権、財産の所有権、起業する権利、お金を借りる権利、就職する権利、同一労働同一賃金。お金のためではなく愛のために結婚できる経済力。
フェミニズムは今も、お金をめぐって進行している。
ここ数十年のフェミニズムの動きは、男性の持っているお金や特権を女性が手に入れ、そのかわり男性に「人前で泣く」などのソフトな権利を与えましょうということだった。少なくとも一部ではそう言われる。
ただし、話はそんなに簡単ではない。
2008年9月15日、米国の投資銀行リーマン・ブラザーズが経営破綻したことはまだ記憶に新しい。
それをきっかけに、世界中の銀行や保険会社が立てつづけに倒産した。数百万人が職を失い、貯蓄を失った。人々は家から追いだされ、国々は破綻の危機に追いこまれ、市場は混乱を極めた。ショックは市場から市場へ、国から国へと波及し、世界経済のシステム全体が足場を失って崩れ落ちるかに思われた。
信じられない光景だった。
私たちがまじめに働いていれば、黙って税金を納めていれば、すべてうまくいくはずではなかったのか。
みんなそう言っていたじゃないか。
でも、それは嘘だった。
金融危機を受けて、各地で数々の国際会議が開かれた。数えきれないほどの書籍が金融危機を分析し、従来のしくみの欠点を指摘した。保守派の政治家からローマ教皇まで、あらゆる人がいっぺんに資本主義を批判しはじめたかのようだった。今回のできごとはパラダイムシフトをもたらす、と誰もが言った。もはや世界の枠組み自体が大きく変わらざるをえない、と。国際金融システムの改革が必要だ。経済は新たな価値に率いられねばならない。貪欲さ、所得格差、グローバルな経済格差といった話題がメディアを賑わせ、中国語で危機を表す単語は「危険」と「チャンス」の組み合わせなのだ、という豆知識が何かの合言葉のように繰り返された(ちなみにそれは正しくない)。
危機はやがて過ぎ去った。金融セクターは回復し、企業の利益や人々の給料、配当やボーナスも以前の水準に戻った。
もはや消え去るしかないと思われた経済のしくみとストーリーは、金融危機を経てもなお、踏みとどまった。奇跡的な図太さだった。なぜ災害級の危機でさえそれを変えられなかったのか?
さまざまな答えが考えられる。本書ではそのうちの、ひとつの視点を紹介したい。
ジェンダーだ。それを本気で掘り下げてみたい。
もしもリーマン・ブラザーズがリーマン・シスターズだったなら、あのような形での金融危機は起こらなかったはずだ、と当時フランスの財務大臣を務めていたクリスティーヌ・ラガルド[もと国際通貨基金(IMF)専務理事。2021年現在、欧州中央銀行総裁]は言った。*1 もちろん(半分は)冗談だろう。
経済危機をほぼ無傷で乗りきった数少ない投資銀行のひとつ、アイスランドのオイズル・キャピタルは女性だけで経営されている、とラガルドは指摘する。テストステロン値の高い男性ほどリスクを取りたがる傾向が強いという研究結果もある。*2 金融セクターの過剰なリスク志向が危機を招いたのだとすれば、男性はホルモンの影響が強すぎて、経済を動かすのに向いていないんじゃないだろうか?
別の研究によると、女性も男性と同じくらいリスク志向になることはあるが、それは排卵が起こる時期だけだという。*3 つまり男性はいつでも排卵期の女性と同じような状態だから、あんな金融危機を起こしてしまったのだろうか。月経周期と景気サイクルの謎めいた関係とはいったい?
また別の研究によると、女子校に通う女子は男子と同じくらいリスク志向であるらしい。一方、共学校の女子はリスクを避ける傾向がある。「男対女」の社会規範がどうやら肝になっているようだ。*4 少なくとも、異性の見ている前では。
こうした話を冗談と笑ってもいいし真に受けてもいいが、ひとつ、確かなことがある。
リーマン・ブラザーズは、けっしてリーマン・シスターズではありえなかったという事実だ。
女性がウォール街を支配する世界がもしあったとしても、それは私たちの生きる現実とはあまりにもかけ離れているため、比較してもまったく意味がない。リーマン・シスターズという名の投資銀行が米国の住宅バブルに直面する瞬間をつくりだすためには、それに先立つ数千年の歴史を書き換えることから始めなくてはならない。
男を女に入れ替えればいいというような、単純な話ではないのだ。
*
経済と女性の話はそれよりもずっとスケールが大きい。
フェミニズムの歴史は、二百年以上前にさかのぼる。賛否はどうあれ、フェミニズムが私たちの時代の非常に大きな民主的・政治的ムーブメントであることは事実だ。またフェミニズムは、前世紀でおそらく最大の経済的変化に寄与してきた。
その変化は一般に、こんなふうに語られる。
「60年代に女性が働きだした」
だが、その言い方は正しくない。女性は1960年代になって急に働きだしたのではないし、第二次世界大戦のときでもない。
女性はいつだって働いていた。変わったのは仕事の種類だ。
家の仕事をするかわりに、女性は労働市場に出ていって労働の対価を受けとりはじめた。看護や介護や教師や秘書の仕事をするかわりに、医師や弁護士や海洋生物学者になって男性と張り合いはじめた。
社会と経済にとって、これほど大きな変化もなかった。人口の半数が、おもな仕事の場を家庭から市場へと移したのだ。
私たちはそれと知らずに、ひとつの経済システムから別のシステムへと移行していた。
と同時に、家庭のあり方も変化した。
1950年頃まで、アメリカ人女性は平均で4人の子どもを産んでいた。ところが現在では、2人にまで減少している。
英国と米国では、女性の出生パターンと教育水準とのあいだに明らかな相関がある。高学歴の女性は子どもの数が少なく、出産年齢が高い。低学歴の女性は子どもの数が多く、出産年齢が低い。*5
世間はその両者に悪いイメージをつけたがる。
泣き叫ぶ子どもをブリーフケースに入れたキャリア・ウーマン。40歳になってようやく出産したものの、世話をする時間もない。利己的で無責任な、悪い母親。
公営住宅に住み、生活保護を受けている若いシングルマザー。こちらも利己的で無責任な、悪い母親。
大規模な変化が現在進行形で起こっているというのに、世の中の議論はたいていそこに行き着いてしまう。女性に対して、あるいはそのカリカチュアに対して、ああすべきこうすべきという外野の意見。
子育て支援に巨額の予算を注ぎ込んでいる北欧では、学歴による女性の出生パターンの変化は見られない。一般に、北欧の女性は英米よりも多くの子どもを産む。ところが誉れ高い北欧の国々でさえ、女性の賃金は男性より低く、*6 上級管理職のポジションにいる女性の数も他国にくらべて多いとは言えない実情がある。*7
なぜそうなるのだろう。どこかに解けない数式が隠れているのではないか。
正体が何であれ、それが経済学の方程式であることはまちがいない。
経済学は人を怖気づかせる。
難解な用語、あふれる威厳、立派な儀式、どこまでも深い謎。金融危機にいたる時期、経済学は専門家にしか扱えない領域だった。素人の手に負える話じゃない、すべて専門家にまかせておけばいいんだと言われてきた。中央銀行の総裁がセレブ扱いされ、我々の文明を救った英雄としてタイム誌の表紙を飾る時代だった[第14代FRB議長ベン・バーナンキが2009年にタイム誌の「今年の人」に選ばれている]。
そんな時代は過ぎ去った。
本書が描きたいのは、誘惑の話だ。ある経済学の見方が私たちを狡猾に言いくるめた話だ。それはどうやって私たちの皮膚にもぐりこみ、ほかの価値観を制圧し、世界経済にとどまらず私たちの日常をも支配するようになったのだろうか。それは男と女についての話だ。おもちゃに現実の力を与えると支配されてしまうという話だ。
きちんと筋が通るように、そもそもの最初から話を始めたい。
つづきは『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?』でお楽しみください。
*1 Lagarde, 2010.
*2 Croson and Gneezy, 2009.
*3 Pearson and Schipper, 2013.
*4 Booth, Cardona-Sosa and Nolen, 2014.
*5 Wolf, 2013, chapter 2.
*6 Statistics Sweden, 2004.
*7 上級管理職に就く女性の割合のランキングにおいてスウェーデンは25位、フィンランドは13位、デンマークは37位。Grant Thornton International Business Report 2012 による。