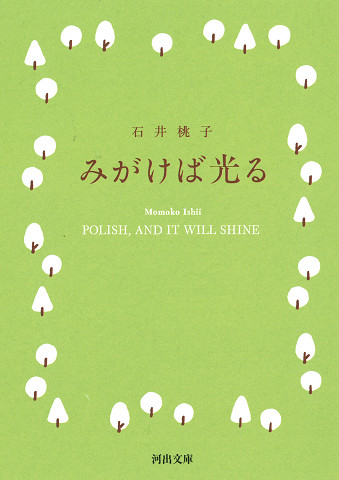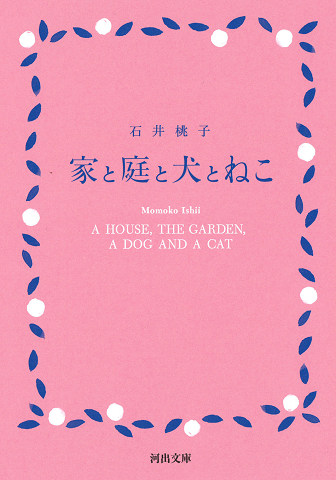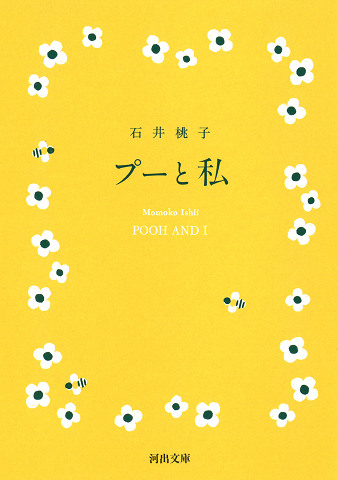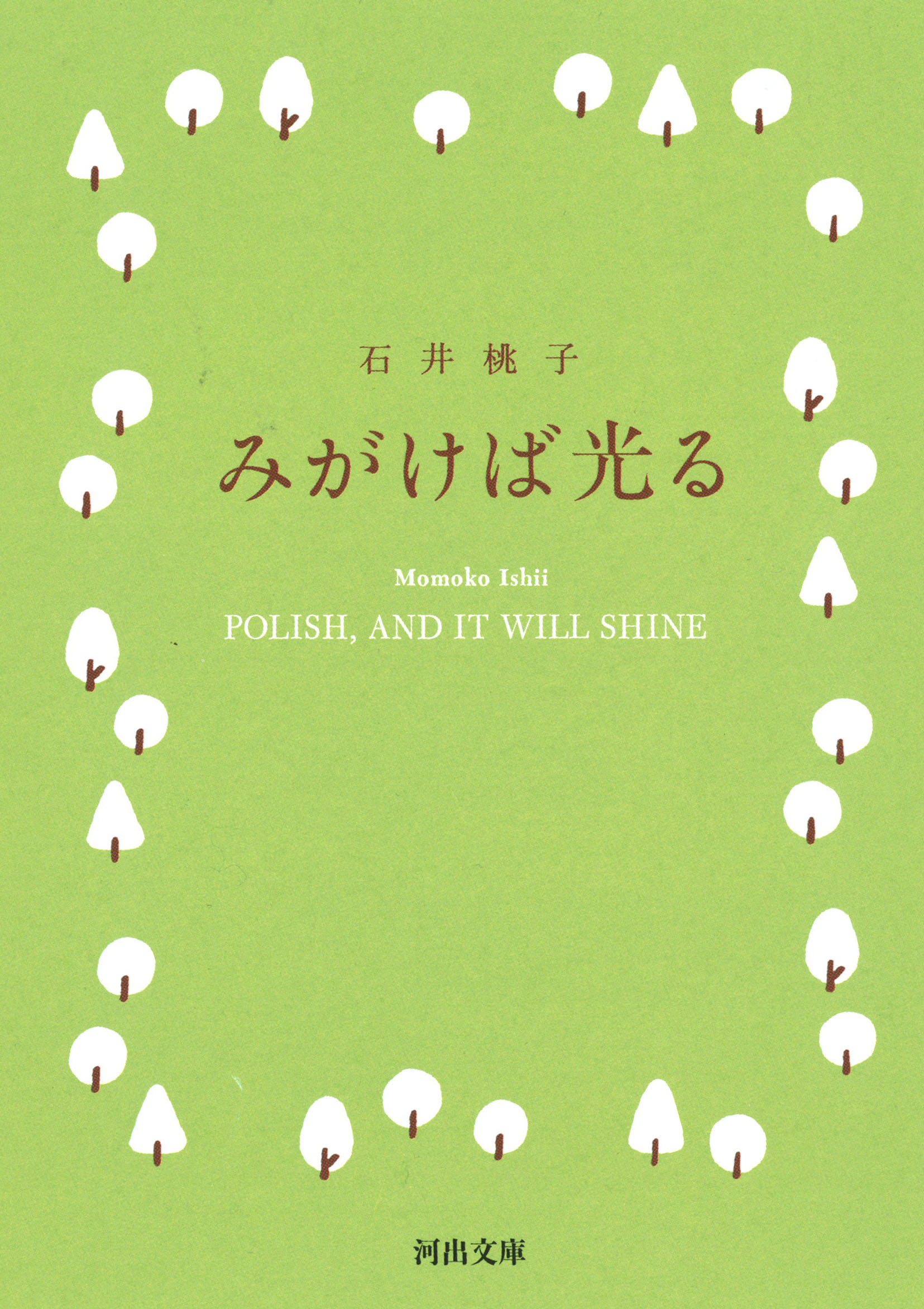
文庫 - 随筆・エッセイ
「没後10年 石井桃子展 ―本を読むよろこび―」開催中──石井桃子『みがけば光る』解説公開
東直子
2018.08.15
『みがけば光る』
石井桃子
文庫解説公開中
****************
ことばを「みがく」
東直子[著]
子どものときに読んだ本の記憶は、詳細は忘れてしまっていたとしても、私たちの心のいちばん深いところで、その礎を支える大事な要素となっている気がする。『クマのプーさん』や『ちいさなうさこちゃん』のやさしくて明るい日本語の響きは、育っていく子どもの心にじっくりとしみて、その心の一部になっていったに違いない。日本の児童書文化の礎を築いてくれた石井桃子さんの培った言葉は、多くの人の大切な心の財産となっている。
その石井さんのエッセイ集。日々の生活の中の細々とした思いや回想、仕事の思い出等を綴った小文たちが、それぞれ確かな光を灯しながら寄り添うように集っている。表題となった「みがけば光る」というタイトルのエッセイは、タイトルだけ見ると才能のことを書かれているのかと思ったが、書かれていたのは、話し言葉に関してのことだった。
石井さんより二十歳ほど年上の先生の「このごろの若い人は、わたしたちが『かしこまりました』とか、『承知いたしました』というところを、『承知しました』とか、『わかりました』っていうんですね。ときどきびっくりしますよ」というつぶやきが発端である。明治四十年生まれの石井さんの二十歳年上といえば、明治半ば生まれということになる。その世代の話し言葉の意識はさすがによく分からないとはいえ、「承知しました」「わかりました」が「びっくりします」ということに、びっくりしてしまった。今や普通の丁寧な言葉として定着していて、目上の人にもこの言い方で通してしまっているからだ。「戦前に育って、そういう固定観念ができてしまっている」という石井さんも「若い人にものをたのんで、『わかりました』と答えられると、『ブー』と鳴ることを期待していた汽笛が、『キー』と鳴ったようなびっくりさは感じる」と書いている。その上で、こう続けるのだ。「でも、まだ私は、『わかりました』をわるいとは断じない。わるいか、いいか、まだ答えがでないのだと思っている。『わかりました』は、わけのわかったことばだし、これから先、日本人が、しんぼうづよくこれにみがきをかければ、いい返事になるかもしれないではないか。」と。
「わかりました」ということばを「みがく」。考えてもみなかったことで、はっとした。「わかりました」ということばは、明治生まれの方にとっては乱暴だったのだ。今後口にするときは、心して使わねば、と思う。
「ことばを『みがく』」といえば、表現の創意工夫をする、というニュアンスで今は使われている気がするが、石井さんが書かれた「みがく」は、そのことばをなげかける相手に、誠実に、気持ちをこめて、ていねいに伝えること、という意味が込められているように思う。つまり、自分の表現のためではなく、相手のための「みがく」なのだ。なんてすてきなことだろう、と思う。
思えば、石井さんが子どもの本のために残されたことばは、自己表現のためではなく、子どもがその内容をよりよく受け取れるためのことばだった。言葉に対する意識を知った上で、石井さんの関わった児童書を読み直すと、ますます味わいが深まる。
さらに、このエッセイ集の読みどころは、石井さんの人としての思いや経験が率直に描かれているところである。「知識人としてすてきな生活」を誇示するところは一切なく、ユーモアも交えながら、一人の人間の淡々とした生き方を率直に綴っている。菊池寛や太宰治と話をしたことも(あの『走れメロス』の誕生秘話も!)、戦後に山の中で農業を始めたことも、旅行先で忘れ物をしたことも、講演依頼をうっかり受けてしまったことも、すべて気負うことなくひょうひょうと描かれていて、不思議な親しさと共に気持ちよく読める。石井さんの肉体はこの世にもうないけれど、文章を読むと、すぐそばで生き生きと話しかけてくれているような気になる。
「あともどりがいいというのではない。けれども、[ファッションが・筆者注]生活とむすびつかないところにとんでいってしまうことは、美しさもなくしてしまうことだろう。」
「わからないことはわからないということ、そういうことをいっても、人に笑われはしまいかと考えて自分を傷つけるということをしないですむ精神的な安定感」
「私は、恋愛や結婚の当事者の見つめるべき、この『はるかなもの』が、一つの星でなければ、ならないとは考えません。それこそ、世の中には、数えきれないほどの星があるのです。」
やわらかな箴言のようなこれらの文言に、しばし立ち止まる。柔軟かつ真摯に生きることのすがすがしさに、胸がすく。
こうした短い文章に込められた鋭さに感じ入る一方、懐かしい時間を描いた文章が、実に美しい。「わが青春記」と題されたエッセイで、三十分以上かけて徒歩で高校に通学する様子を描いた場面を抜き出しておきたい。
「道は古い中仙道で、姉や私が途中で友だちをさそって、だんだん人数をましながら、つれだって、この古い街道を北からのぼっていくと、やがて、向こうから、道を一ぱいにうずめて、まっ黒い波が押しよせてきます。町のやや南よりにある駅から、逆に北へくだる高等学校、中学校の生徒の群です」
大正の終わり頃の、埼玉県の通学風景が、一枚の美しい絵として動き出したようで、とても好きな場面である。
高校卒業後、東京の女子大に進み、他の同級の女性たちと違って女に生まれたことを悔やまないと感じるその理由として「もし自分が男に生まれていたら、そのころの日本では、じぶんもそこらに見る男と同様、やがて結婚するだろう女を、きっとふみにじることになるのだという、少女らしい一てつな正義観をもっていたこと」をあげていることが、とても象徴的である。「まっ黒い波」から飛び立った鳥が、「少女らしい一てつな正義観」をもって、女性が働く場を切り開いていったのだ。戦後の職業婦人としてしなやかに生きてきた「一てつ」が、数々のエッセイを貫いている。
(歌人・作家)
*******
石井桃子随筆集の解説を公開中。
*******
〈没後10年 石井桃子展 ─本を読むよろこび─〉
7月21日(土)~9月24日(月・振休)
【会場】神奈川近代文学館
http://www.kanabun.or.jp/exhibition/7991/
*******