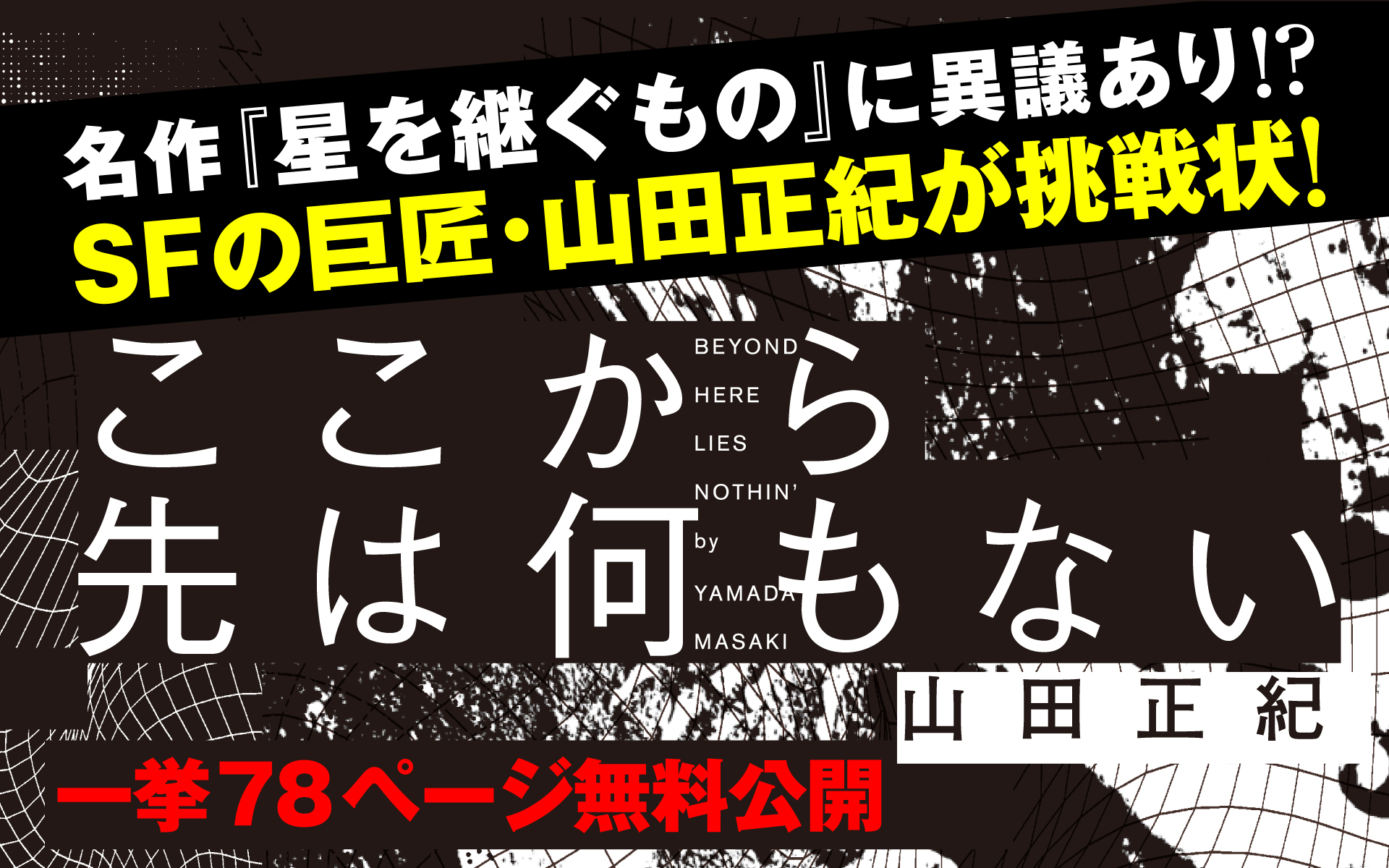文庫 - 日本文学
平野啓一郎さんによる、遠野遥『改良』の文庫解説を一挙公開!
平野啓一郎
2022.02.09
芥川賞作家・遠野遥のデビュー作『改良』の文庫版が発売されました!
発売を記念して、平野啓一郎さんによる文庫解説の原稿を一挙公開します。
遠野遥『破局』が芥川賞を受賞した際の選考委員でもあり、「新しい才能に目を瞠らされた」と評した平野さん。
『改良』の魅力と新しさをロジカルに解き明かす解説、必読です!
(できれば本編をお読みいただいた上ですと、より楽しめます)
”納得”することの他者性
平野啓一郎
遠野遥氏は、デビュー作『改良』に於いて、既に確乎たる個性的な文体を獲得しており、読者はその着実な発展を、芥川賞を受賞した『破局』に見ることが出来る。
一見、特に技巧を凝らした風にも見えない、平易と言って良い文体だが、絶えず、ユーモアのかたちを採った、何とも知れない落ち着かなさが感じられ、それが巧みな構成力と相俟って、物語の進展と共に増幅されてゆく。
この文体は、確かに新鮮だが、しかしどこかで心当たりもあり、人によっては、カミュの『異邦人』を思い出すかも知れず、また私は、横光利一の『機械』を連想した。
時間芸術である小説では、基本的に起点があり、終点があり、その間で、事象の連なりが描かれるのであるが、まさにその事象が連なっているように見えるためには、物語の禍中の主人公が、自ら経験するところに〝納得〟していること/していないことを、読者が納得することが肝要である。
遠野氏は、この〝納得〟の構造に着目し、それをテコにして、言語的に形成されている社会秩序そのものを問おうとしている。
物語は、主人公が小学生の頃にスイミングスクールに通っていた記憶から語り起こされている。それは、親の勧めであり、彼自身は通うことに憂鬱を感じていた。
水泳自体は「好きでも嫌いでもな」かったが、「人前で下着同然の格好」になるところ、また、「プールの中でこっそりとおしっこをする子がいる」ことが、その憂鬱の理由だった。
この冒頭から、プロットとしてはそれ故に、親に反発して通うのをやめた、という方向にも進み得るのだが、主人公は「喘息持ち」であり、水泳が、心肺機能の向上に役立つという親の考えに従ってスイミングスクールに通い続ける。これは、医学的にも認められている、一種の常識である。
つまり、彼は自らに課された不快な「強制」を、そのように〝納得〟して受け容れるのである。読者もまた、この成行には〝納得〟するはずだが、著者が問うているのは、こうした読書の了解的な関係である。
水泳をやめる頃になると、実際に彼は、喘息がよくなっているが、しかし振り返って、それは、「水泳をやっていたからではなく、成長とともに自然と治った」のだと解釈さ れている。つまり結局は、〝納得〟したはずのことを、〝納得〟していないのであり、強 制は強制のままということになる。そうすると、主人公が〝納得〟したはずの理屈と、 読者の〝納得〟とは乖離してしまうのだが、作者はそれを、物語のこの後の展開に委ねて放置するのである。
スイミングスクール通いを巡る、このありきたりな経験の記述は、小説全体を通して執拗に反復される抵抗と〝納得〟の構造の原型である。
主人公は、スイミングスクールの友人で、「バヤシコ」という渾名の少年に、屋外セックスの覗き見に誘われるのだが、この時も、「別にカップルを見たいとは思っていなかった」が、「ゲームのようで楽しかった」と、その強制を〝納得〟し、受け容れる。──しかし、この〝納得〟も、後に撤回されるのかもしれない。
やがて、覗き見をしながら、バヤシコに性器を触られ始めた時も、主人公は、激しい怒りを覚えつつ、やめてほしいなら、逆に彼の性器を触るように命じられ、「そんなことはしたくなかったが、私に拒否権はなかった」と、その条件に従う。更に、手で上手く出来なかったことの「罰」として、オーラル・セックスまで強いられ、これもまた受け容れるのである。
彼の〝納得〟は、言語的に形成された秩序観に基づいており、その理屈は、常識や通念といった他者的なものである場合(水泳は喘息に良い効果がある)もあれば、自身の判断(覗き見もゲームのようで楽しい)ということもある。
私は嘗て、「『機械』には、ただ心理だけがあり、感情がない。」(「独白の不穏」『モノローグ』収録)と書いたことがあるが、『改良』に読者が感じる違和感も、これと似ている。主人公の〝納得〟する理屈は、その一文だけ取り出してみれば、瑕疵なく意味をなしているが、しかし、普通なら、状況に対してそれを適用しようとした時、何かもっと感情的な抵抗があるはずなのではないか、と感じられる。この小説に、どことなく人間の思考を学習したAIが書いたかのような雰囲気があるのは、そのためである。
主人公の強制に対する態度は、しばしば過剰適応的に見える。一概にヘンだとも言えないが、全体として共感出来るというわけでもない。しかし、本作が最終的に突こうとしているのは、まさにその微妙な一点なのである。
主人公は、この秩序観故に、企業のクレーム対応のバイトを黙々とこなし、面倒な相手でも、上司に回すことなく「自分で頑張る」。感情的になりそうな現実に対しては、乖離的に「別の世界の人間」、「別の世界の出来事」と感じ取り、結果、残されるのは、仕事である以上、役割を務めるべきだ、という一種の職業倫理だけである。
この当為は、他方で、自己のみならず、他者にも適用される。本作のみならず、作者は『破局』でも、トイレの便座が上がっている、という状態をしきりに問題とし、便座とは、「下がった状態が便器本来の姿」だと主人公に立腹させている。このネットの世間話のような逸話が、主人公の人物造型に効果を発揮している。
主人公が従属するのは、常に、他者というよりも、この内面化された規範群の方である。従って、他者がそれから逸脱していると感じられている時もまた、強い反発が芽生える。バヤシコへの怒りがそうで、但し、彼から「やめてほしいなら」という条件を与えられ、「罰」を科されると、忽ち、それが新たな規範として状況に上書きされ、〝納得〟してしまうのである。彼が好意を寄せていたのは、デリヘル嬢のカオリだったが、彼女が肝心な時に職業的に的確に対応出来ず、「不安定」さを露呈すると、「絶対に許せない。あってはならないことだ」と激怒し、その関係を破綻させてしまうのである。
そして、こうした強制の象徴として、自己と他者との双方に跨がり、作品全体を支配しているのが、ルッキズムである。
女装は、主人公の情熱であるが、それは彼の性自認とも性的指向とも無関係の性表現であり、その根底にあるのは、「どうして、私は美しくないのだろう。」というコンプレックスである。美しくなりたいというのは、まさに彼自身の願望だが、しかし、その願望を強制しているのは、その実、今日では大いに批判されている、この差別的な価値観である。主人公は、人間の価値は多様だと知っているものの、それらは「どれも美しさの前では霞む」と感じ、ルッキズムに〝納得〟している。彼が「美しくない」が故に劣等感を抱かずに済み、蔑みつつも好感を抱いているのが「つくね」という幼馴染みであり、その関係は、読者に、主人公としては例外的に人間的なものを感じさせる描き方となっている。
主人公は、カオリに激怒し、女装のままつくねの家を訪ねる途中、男に声をかけられ、公衆トイレに連れ込まれて、性的暴行を受ける。その描写は生々しく凄惨であり、主人公が冒頭で、人前で裸体になりたくなく、また排泄の不潔さに嫌悪感を抱いていると語っていた素朴な呟きが、痛ましく谺している。
しかし、その暴力の禍中でも、彼は、自分で無理だと判断して逃げることをしない。また、汚い手で性器に触ることを咎められると、トイレの床に触れ、男の靴でも踏まれていたので、「確かに汚かった」と〝納得〟してしまう。
主人公の服従に対する読者の違和感が、最も批評的に検討されるのは、この場面であり、何故なら、性暴力被害者に対して向けられる世間の「普通なら」という二次加害的な偏見は、常に、なぜ抵抗しなかったのか、なぜ言われるがままに従ったのか、……といった懐疑の言説を採るからである。
言うまでもなく、無抵抗であるのは、多くの場合、殺されるかもしれない、という恐怖心の故である。決して心から相手を受け容れているわけではない。つまり、ここに至って批評されているのは、主人公の〝納得〟というより、寧ろそれに何となく違和感を抱いてきた読者の方なのである。
主人公は、性行為を強いられながら、この暴力を招いたのは、自分の女装なのだと内省する。しかしそれは、ただ、「自分をきれいに見せることができるようになっていくのが嬉しかった」からであり、決して「男の気を惹く」ためではなかった。この思考の場面は、「わからない時にはなってみる」という、美術作品に対する森村泰昌氏の試みを想起させる。性暴力を誘発するのは、女性の挑発的な格好なのだというのもまた、被害者を傷つける二次加害の典型だが、それに対して、作者は主人公を通じ、女性になってみることで、身を以てその不当さを告発しているようにも見える。その自らの服従を「私を守るための一時的な反応でしかない」と考える件は、バヤシコからの性的暴力以降続く、彼の抵抗と〝納得〟とのメカニズムに対する総括的な自己批評と言えよう。それは、彼の乖離的な現実の受け容れからも看て取れる。
この状況に至った主人公を、自業自得だと突き放す読者は、多くはないだろう。彼はただ、美しくなりたかっただけなのである。ところが、彼がそもそも捕らわれていたルッキズム自体は、社会的に否定されていた考えのはずである。つまり、読者に突きつけられているのは、結末から遡行されたはずの原因追及を、決して結末に短絡させてはならないという苦い倫理的教訓なのである。
ここから主人公は、自らの被った暴力を拒絶するために、相手の性器を嚙みちぎろうとし、ヒールで足を踏みつけて、その場から逃走する。その「ひどい格好」のまま、向かう先は、つくねの家である。
この結末は、主人公が遂に、自らの好悪に正直な主体性を恢復して、その受け止め先として「つくね」への愛を確認するという未来を予感させる。しかし、暴行現場から逃げ出した主人公がしきりに憤っているのが、相手には、自分の鼻を「どうこうしていい権利などないはずだ」という点であることに注目したい。つまりは、彼が許せないのは、相手が規範に背いていることであり、その意味では、便座が上がったままのトイレへの 怒りと、本質的には変わらないのである。
作者は、この『改良』の主題を、次作『破局』では一層先鋭化させている。ルッキズムに相当するものとして焦点化されるのは、スポーツとセックスという肉体的欲望であり、それ以外は、「正気」、「常識」、「礼儀」、「マナー」、父の言いつけ、……といった、片々たる正しさの規範──それはシニカルに笑われつつ、決して全否定することも出来ない──に、徹底して”自律的に他律的”な主人公を造型している。しかも、そのような規範群と同化した彼に対し、最も他者的に振る舞うのは、実のところ、その自らの欲望であり、やがてスポーツが、規範群と結託しながら他者をも吞み込んでゆき、また、同時にセックスが他者と結託して彼を吞み込み、双方向から「破局」をもたらす様は鮮烈である。
重要なのは、作者が、社会の全般に張り巡らされている権力構造を、個人が何気なく胸に思い浮かべ、”納得”する通念に言語的にアプローチしようとしている点である。
作者、登場人物、読者を巻き込んだこの大掛かりな実験の行方を、私たちは今後も、 試みられつつ、見守ってゆくこととなるだろう。(小説家)
*遠野遥『改良』について、単行本発売時の過去記事はこちら!
https://web.kawade.co.jp/bungei/3055/