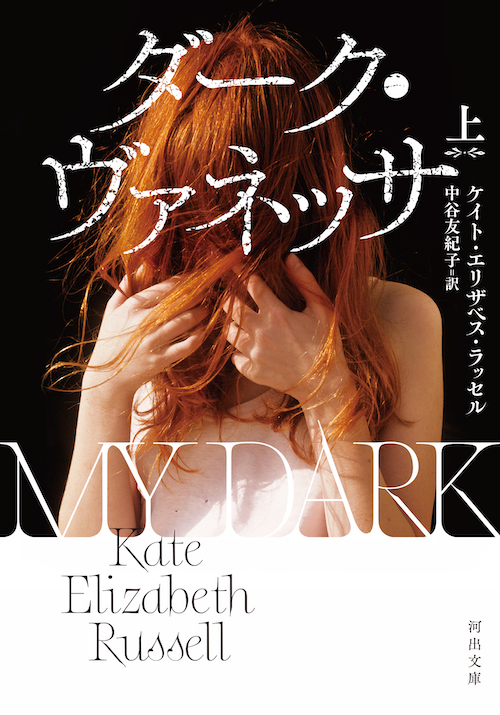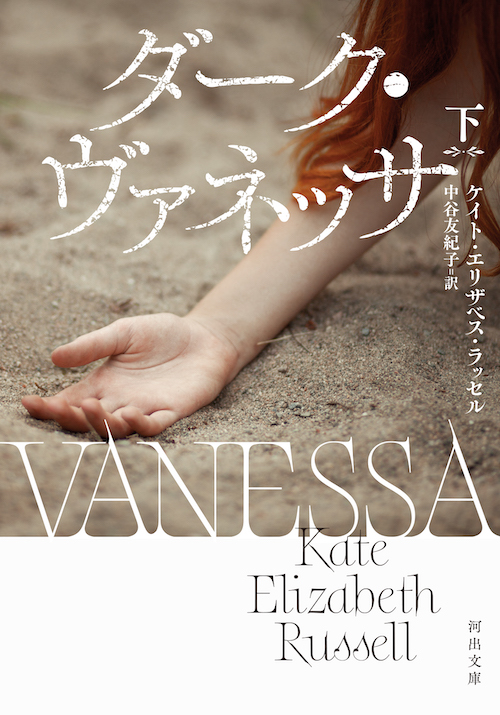文庫 - 外国文学
世界32か国で刊行!支配と虐待をめぐるサスペンス『ダーク・ヴァネッサ』試し読み
ケイト・エリザベス・ラッセル
2022.05.09
《ニューヨーク・タイムズ》《サンデー・タイムズ》ベストセラー!
世界32か国で刊行、各紙誌騒然の衝撃作がついに邦訳。15歳、寄宿学校に通うヴァネッサは42歳の教師・ストレインの“恋人”だった。しかしその17年後、思い出を胸に秘めた彼女の前に、彼を未成年者への性的虐待で告発するというひとりの女性が現れる。「私は彼女とは違う」と自分に言い聞かせるヴァネッサだったが、混乱する記憶の底からはやがておぞましい過去が浮き上がり……。
「少女との禁断の愛」の欺瞞を粉々に打ち砕く衝撃作、冒頭試し読みを公開!
────────────────────────────────
二〇一七年
出勤の準備をはじめたとき、投稿から八時間が過ぎていた。髪を巻きながらわたしはページを更新する。現時点で”シェア”が二百二十四件、”いいね!”が八百七十五件。黒いウールのスーツを着てからまた更新する。ソファの下をあさって黒のフラットシューズを引っぱりだし、更新。襟に金色の名札をつけ、更新。そのたびに件数は伸び、コメントも増えていく。
あなたはとても強い。
すごい勇気ね。
子供にあんなことをするなんて、とんでもない変態野郎!
四時間前にストレインに送ったメッセージを呼びだす──”ねえ、大丈夫?”。返信はなく、既読にさえなっていない。”話したければどうぞ”と新たにメッセージを入力したものの、思いなおして削除し、疑問符だけを並べた一行を送る。数分待って電話してみたが、留守電に切り替わったので、携帯電話をポケットに突っこみ、荒っぽくドアを閉じてアパートメントを出る。躍起になる必要なんてない。騒動の種をまいたのは彼なんだから。これは彼の問題で、わたしのじゃない。
ホテルに出勤し、ロビーの隅のコンシェルジュデスクについて、宿泊客に見どころや名物料理を紹介する。いまはオンシーズンも終わりかけ、残り少ない観光客が紅葉を目当てに訪れている。それが過ぎればメイン州は冬に閉ざされる。口もとだけに笑みを貼りつけたわたしは、結婚一周年のお祝いに来た夫婦のためにディナーを予約し、食後の部屋に用意しておくシャンパンの瓶も手配する。そういったとっておきの心遣いを示すとチップも期待できる。それから家族連れを空港へ送るためのハイヤーを呼ぶ。隔週月曜日に泊まるビジネス客が汚れたシャツ三枚を手に現れ、翌朝までにクリーニングできるかと尋ねる。
「おまかせください」
相手はにっと笑い、ウィンクをよこす。「きみは最高だ、ヴァネッサ」
休憩時間、バックヤードの空いた仕切り席にすわり、昨日のイベントで残ったサンドイッチを食べながら、携帯を覗きこむ。フェイスブックの投稿をチェックするのがやめられない。指を動かし、画面に目を走らせ、増えていく”いいね!”と”シェア”の数や、”あなたは勇敢な人、真実を語るのをやめないで、わたしは信じる”といった何十件ものコメントを確認せずにはいられない。それを読むあいだも三点リーダーが表示される。この瞬間にも誰かがコメントを入力中なのだ。やがて、魔法のように新しいコメントが現れる。励ましと支持のメッセージが。それを見てわたしは携帯を机の奥に押しやり、ぱさぱさのサンドイッチの残りをゴミ箱に放りこむ。
ロビーに戻ろうとしたとき、携帯が振動する──”着信中 ジェイコブ・ストレイン”。無事に電話してきたことに安堵して、笑いながら応答する。「大丈夫?」
少しのあいだ間があり、わたしは息を詰めて窓の外のモニュメント・スクエアを眺めやる。ファーマーズ・マーケットが開催され、フードトラックが並んでいる。十月初旬、秋たけなわのポートランドは、なにもかもがL・L・ビーンのカタログから飛びだしてきたかのようだ。丸形やひょうたん形のカボチャ、アップルサイダーの瓶。チェックのフランネルシャツとダックブーツの女性が、抱っこ紐で胸に抱えた赤ん坊に笑いかけながら広場を横切っていく。
「ストレイン?」
重々しいため息が聞こえる。「見ただろう?」
「ええ、見た」
なにも訊かないうちから、ストレインが説明をはじめる。学校側の調査が開始され、最悪の事態になりそうだという。おそらくは辞職を強いられる。学年末はおろか、クリスマス休暇までいられるかもあやしいそうだ。声を聞いているだけで心が乱れ、話についていくのに苦労する。最後に言葉を交わしたのは何カ月もまえ、父を心臓発作で亡くしたショックで、もうやりとりはしないとストレインに告げたときだ。失業や失恋、ノイローゼ。長年のあいだ、なにか起きるたびに、わたしはそうやって唐突にモラルを持ちだしてきたのだった。行いをあらためれば、過去の過ちも帳消しにできるかのように。
「でも、彼女が生徒だったときに、調査はすんでるんでしょ」
「再調査になったんだ。全員があらためて事情を訊かれるらしい」
「当時は問題なしと判断されたのに、なぜいまになって方針が変わるの?」
「ここ最近のニュースを知らないのかい。昔とは時代が違うんだ」
大げさすぎる、やましいことがなければ平気でしょと返したいが、ストレインの言うとおりだ。ここ一カ月、男性からのセクハラや性暴力を告発する女性が相次ぎ、そのムーブメントが勢いを増している。名指しされるのは大半がミュージシャンや政治家、映画スターといった著名人だが、それほど有名でない人たちの名前も挙げられている。どのような立場であれ、告発された者は同じ末路をたどる。まずはすべてを否定する。やがて非難がやみそうにないと悟り、不名誉な形で職を去って、非を認めているとは言いがたいあいまいな謝罪文を発表する。そして最後に──沈黙し、消える。連日のようにあっけなく破滅していく男たちを目の当たりにするのは、信じがたいような思いだった。
「問題ないはず。彼女が書いたことなんてみんな噓っぱちなんだから」
電話の向こうでストレインが息を吸い、歯のあいだを空気が通る摩擦音が聞こえる。
「噓と呼べるかどうかはわからない、少なくとも、厳密には」
「でも、ほとんど触ってもいないんでしょ。あの投稿には、あなたに暴行されたって書かれてるけど」
「暴行か」皮肉な笑いが混じる。「なんだって暴行になりうる。手首をつかむのも、肩を小突くのも。意味のない法律用語だ」
わたしは窓の外のファーマーズ・マーケットをまた見やる。のんびりとぶらつく人々、群がるカモメ。屋台の女性が金属の蒸し器をあけ、立ちのぼる湯気のなかからトウモロコシ粉を練ったタマルをふたつ取りだす。「じつは先週、彼女からメッセージが来たの」
一拍の間。「それで?」
「いっしょに声をあげるつもりはないかって。わたしを巻きこめば、訴えの信憑性が高まると思ったのね」
返事はない。
「返信はしてない。もちろん」
「ああ、だと思ったよ」
「鎌をかけてきたんだと思う。そんな度胸があるなんてね」前かがみになり、窓ガラスに額を押しつける。「大丈夫。どっちの味方か、わかってるでしょ」
それを聞いて、彼が息を吐きだす。安堵の笑みを浮かべ、目尻に皺が寄ったのが見えるようだ。「その言葉が聞きたかったんだ」
コンシェルジュデスクに戻り、フェイスブックを開いて、検索バーに”テイラー・バーチ”と入力し、プロフィールを画面に表示させる。何年も前からチェックを続けている数少ない公開コンテンツの写真や近況アップデートをスクロールして眺めてから、トップにあるストレインに関する投稿をまた確認する。件数はまだ増えつづけている。”シェア”が四百三十八件、”いいね!”が千八百件、さらに似たようなコメントが新たに加わっている。
すごく勇気づけられました。
あなたの強さに感服しています。
真実を語りつづけて、テイラー。
*
出会ったときのわたしは十五歳、ストレインは四十二歳だった。ほぼ完璧な三十歳差。当時は年の差をそう考えていた──完璧だと。わたしの年齢の三倍にあたることも気に入っていた。彼のなかには三人分のわたしがいる、そんなふうに想像せずにはいられなかった。ひとり目は脳に、ふたり目は心臓にまとわりつき、三人目は液体になって血管を流れるところを。
ブロウィック校では教師と生徒の恋愛がたまに噂になるものの、自分には縁がなかったとストレインは言っていた。わたしに会うまでは、そんなことをしたいとも思わなかったという。わたしが彼の頭にそういった考えを植えつけた初めての生徒だった。わたしには危険を冒す価値のあるなにかがあった。引き寄せられずにはいられない魅力が。
ストレインにとってそれは、わたしの若さではなかった。なによりも愛したのはわたしの中身だった。きみは感情知能指数が天才級に高く、神童のような文才があり、なんでも話せて信頼できると彼は言っていた。わたしの心の奥には、彼と同じ暗いロマンティシズムがひそんでいるという。わたしが現れるまで、彼のなかにある黒い翳の部分を理解した人はいなかった。
「これが運命というやつなんだろうね。ようやく見つけたソウルメートが、十五歳だったとは」
「運命って言うなら」とわたしは言い返した。「十五歳なのに、ソウルメートがおじさんだったらどう?」
それを聞いた彼は、冗談だとたしかめるようにこちらの顔を窺った。もちろん冗談に決まっている。わたしは同年代の男の子たちになんの興味もなかった。フケやにきびにも、女の子を見た目でより分け、胸のサイズを十段階にランクづけするような残酷な振る舞いにもうんざりだった。こっちからお断りだ。ストレインの中年らしい慎重さと、性急でない求愛のほうがわたしには好みだった。彼はわたしの髪色をカエデの葉に喩え、詩集を贈ってくれた。エミリー、エドナ、シルヴィアの。そして彼の目にわたしがどう映るかを教えてくれた。赤い髪で立ちあがり、空気のように彼を食らう力を持った少女なのだと。恋しさのあまり、彼は授業のあとでわたしの席にすわってテーブルに顔を伏せ、残り香を嗅ごうとさえした。キスもしないうちから。彼は慎重だった。いい人間であろうと努力していた。
はじまりの瞬間がいつだったかは迷わず言える。日の光が降りそそぐ教室に足を踏み入れたわたしに、彼が初めて目を奪われたあのときだ。でも、終わりははっきりしないし、そもそも終わったのかどうかもあやしい。二十二歳のころ、自分を取りもどしたい、きみがそばにいるとまともな人生を歩めないと彼に告げられたときに区切りはついたものの、その後の十年も深夜の電話は続き、そのたびにふたりして過去を振り返り、癒えるのを拒むように傷をつつきあってきた。
十年か十五年後、身体がいうことを聞かなくなったころ、彼が頼るのはわたしだと思っている。それがこのラブストーリーの結末になりそうだ。わたしはすべてをなげうち、なんでもやり、犬のように身を捧げ、彼はただ奪って、奪って、奪う。
夜の十一時に仕事が終わる。人けのない街なかの通りを歩きながら、テイラーの投稿をチェックするのを我慢できたら勝ちだと自分に言い聞かせ、通りすぎるブロックをひとつずつ数える。アパートメントに戻っても、まだ携帯電話は見ない。スーツをハンガーにかけ、メイクを落として、ベッドでマリファナを吸い、明かりを消す。自制心で。
ところが、暗がりでシーツに脚をこすりつけているうち、心のなかでなにかが切り替わる。とたんに我慢できなくなる。安心させてほしい、テイラーの言うようなことはもちろんやっていないと、はっきり彼の口から聞かせてほしい。彼女は噓をついているのだともう一度断言してほしい。十年前から変わらず噓つきで、おまけにいまは被害者意識に酔っているのだと。
待ちかまえていたように、一回目の呼出音の途中でストレインが出る。「ヴァネッサ」
「ごめんなさい。こんな遅くに」そこでためらう。してほしいことをどう伝えれば? 最後にあれをしたのはずいぶんまえだ。暗い室内に視線を漂わせる。あけっぱなしのクロゼットの扉の輪郭、天井にのびた街灯の影。キッチンでは冷蔵庫が低くうなり、蛇口から水が滴っている。彼にはそのくらいの貸しはあるはずだ。沈黙と忠誠を守っているのだから。
「すぐにすむから。ほんの数分だけ」
ストレインが毛布を剝いでベッドに起きあがり、反対側の耳に携帯を押しあてる音がする。ノーと言われるだろうか。一瞬そう思ったが、やがて骨をミルクのように溶かす囁き声で彼が語りはじめる。かつてのわたしがどんなだったかを。ヴァネッサ、きみは若くて美しさに満ちていた。十代のきみはエロティックで、生気にあふれていて、それがたまらなく怖かったんだ。
わたしは腹這いになって枕を股にはさみ、せがむ。思い出を聞かせて、昔に戻れるように。彼の静かな声がぽつぽつと情景を語りはじめる。
「教室の奥の、私の教員室でのことだ、冬のさなかの。きみはソファに寝そべって、全身に鳥肌を立てていた」
目を閉じるとわたしは教員室にいる。白い壁、黒光りする床板、未採点のレポートが積まれた机、ちくちくするソファ、シューッと音を立てるラジエーター、海のような緑がかったガラスの八角窓。彼に触れられながらその窓を見ていると、水のなかにいて、木の葉のように波に揉まれているみたいな気がしたものだった。
「私はキスしているところだった、あそこに。きみを沸騰させようと」小さな笑い声。
「そう言ってただろ、”わたしを沸騰させて”って。おかしな言いまわしばかり思いついたものだったね。ひどく恥ずかしがって、はっきり言おうとしないまま、私がはじめるのを待っていた。覚えてるかい」
本当のところ、あまり覚えていない。あのころの記憶の多くはおぼろげであいまいなものになっている。彼の言葉でその隙間を埋めるしかないが、話のなかの少女が知らない人間のように思えることもある。
「声を殺すのに苦労していたね。いつもぎゅっと口を閉じていた。一度など、嚙みしめた下唇から血がにじんでいるのに、それでもやめようとしなかった」
マットレスに顔を押しつけ、枕に身をこすりつける。彼の言葉が脳を満たし、わたしをベッドから過去へと運び去る。わたしは十五歳、腰から下は裸で、熱を帯びて震える身体を教員室のソファに横たえ、両脚のあいだにひざまずいた彼に見つめられている。
ああ、ヴァネッサ、唇が。血が出てるじゃないか。
わたしは首を振り、クッションに指を食いこませる。いいの、続けて。最後まで。
「きみはとても欲しがり屋だった。きみの引き締まった小さな身体は」
どんなふうに感じたか覚えているかと尋ねられた瞬間、鼻から強く息を吸って絶頂に達する。ええ、ええ、ええ。覚えてる。そのときの感じだけはいまも残っている。彼がわたしにどんなことをしたか、わたしがどんなふうに身もだえし、続きをせがんだかは忘れていない。
父が亡くなってから、ルビーのところへ通いはじめて八カ月になる。グリーフセラピーとしてはじめたものだが、いまでは母のことや元彼のことや、仕事に行き詰まりを感じていることや、そもそもすべてに行き詰まりを感じていることまで話すようになっている。収入に応じた割引料金だとはいえ、話を聞いてもらうだけで週に五十ドルは分不相応の贅沢だ。
クリニックはホテルから二ブロックのところにあり、やわらかい照明の室内には肘掛椅子が二脚とソファ、ティッシュ箱が積まれたサイドテーブルが置かれている。窓からはカスコ湾が見渡せる。釣り桟橋の上空に群がるカモメたち、ゆっくりと進む石油タンカー、ガアガアと賑やかに水へ入り、バスから船へと変身するダックツアーの水陸両用車。ルビーはわたしより年上で、年の差は母娘というより姉妹に近い。髪は茶色がかったブロンド、ファッションは自然派ヒッピー風。室内を歩くとコン、コン、コンと音を立てるウッドヒールのサボサンダルはわたしのお気に入りだ。
「ヴァネッサ!」
ドアをあけてわたしの名前を呼ぶときの声も気に入っている。そこにいるのがほかの誰でもなくわたしなのを見てほっとしたように聞こえる。
今週は、父が亡くなって初めてのクリスマス休暇に帰省するときのことを相談する。母がふさぎこんではいないかと心配で、父のことにどう触れたらいいかわからない。それで、ルビーとふたりで対策を練ることにする。助けが必要か訊いたときに母がどんな反応を見せるか、何通りもシナリオを考える。
「気持ちに寄り添ってあげれば、きっと大丈夫。仲がいいんだから。つらいこともちゃんと話せるはず」とルビーが言う。
母と仲がいい? あえて否定はしないけれど、実際は違う。自分が苦もなく人を欺けることに、われながらときどき感心してしまう。
セッションがすみ、ルビーが次の予約をカレンダーに入力しようと携帯電話を出すのをどうにか待って、わたしもフェイスブックのチェックをはじめる。顔を上げたルビーが、猛然とスクロールするわたしに気づいて大ニュースでもあるのかと訊く。
「あててみましょうか、またセクハラ野郎が告発されたんでしょ」
手足がすっと冷たくなるのを感じながら、画面から目を上げる。
「まったく、次から次へと」ルビーが笑顔を曇らせる。「逃げようったって無駄ね」
それから、話題沸騰中のスキャンダルの話をはじめる。女性に対する暴力を描いた映画でキャリアを築いた監督が、その制作現場で若い女優たちに性器をさらし、フェラチオをさせていたというのだ。
「あいつが加害者だったなんて、誰が想像できた?」ルビーが皮肉っぽく続ける。
「映画のなかに証拠はすべてあったのに。あまりに堂々としてて、かえって見過ごされてきたってことね」
「黙認されてきたから。みんな見て見ぬふりで」
うなずきが返される。「ほんと、そうね」
こんなふうに、じりじりと核心に近づいていくスリルがたまらない。
「何度もあの人と仕事をしてきた女優たちのこともよくわからない。自尊心はどこ?」とわたしは言う。
「いや、彼女たちは責められないでしょ」ルビーの言葉には反論せず、わたしは黙って小切手を渡す。
帰宅してマリファナをやり、家じゅうの明かりを点けたままソファで眠りこむ。朝の七時、床板の上で携帯がうなりだす。メッセージの着信表示が見え、よろよろと取りに向かう。母だ。”おはよう。どうしてるかなと思って”
母はなにか知っているのだろうか、そう考えながら画面を見つめる。テイラーのフェイスブックの投稿から三日もたっているし、母はブロウィック校の関係者とつながっていないとはいえ、記事は大々的に拡散されている。それに最近の母はネット漬けで、四六時中”いいね!”をつけたり、シェアしたり、ネトウヨたちとバトルを繰り広げたりしている。テイラーの投稿を目にしていてもおかしくはない。
メッセージを閉じ、フェイスブックを開く。”シェア”が二千三百件、”いいね!”が七千九百件。ゆうべ、テイラーは新たに全体公開記事を投稿した。
女性を信じよ。
二〇〇〇年
ノルンベガへ向かう片側一車線の幹線道路に入りながら、母が言った。「今年こそは外に出るようにしてね」
高校二年目の新学期、入寮日のその日は、母にとってわたしと約束を取りつける最後のチャンスだった。ブロウィック校に吞みこまれてしまえば、わたしと話ができるのは電話と休暇のあいだだけになる。一年前、母は全寮制の寄宿学校に入ることでわたしが自堕落になるのを心配し、お酒とセックスは我慢すると約束させた。今年は新しい友達を作ると約束させたがっている。そっちのほうがはるかに屈辱的で、残酷ですらある。ジェニーとの絶交から五カ月、傷はまだ癒えていない。”新しい友達”というフレーズだけで胃がきゅっとなり、そんなことを考えるのが裏切りに思えた。
「昼も夜も部屋に引きこもっているなんてだめ。そんなにつらいの?」
「家にいたら、部屋から一歩も出ないくらい」
「でも、もう家にはいないでしょ。そもそも、友達作りのためだったんじゃないの? この学校に入りたいってせがんだとき、”人脈”がどうとか言ってなかった?」
わたしは助手席のシートに背中を押しつけた。そこにすっぽりうずまり、わたしの言葉を盾に母がうるさく言うのを聞かずにすませたかった。一年半前、八年生のクラスにやってきたブロウィック校の入試担当者から、まばゆい日差しが降りそそぐぴかぴかのキャンパスが映った生徒募集用ビデオを見せられたとき、わたしはすぐさま両親に受験を認めてもらうための準備にかかり、”ブロウィック校が公立校より優れている理由”と題した二十カ条からなるリストを作成した。そのひとつがブロウィック校で得られる”人脈”だった。ほかにも、卒業生の大学進学率とか特進コースの数といった、パンフレットから拾った情報をずらりと並べた。結果的に、両親にうんと言わせるのに必要だったのは二点だけだった。学費免除を受けられるのでお金の心配はいらないこと、そしてコロンバイン高校の銃乱射事件が起きたことだ。生徒たちが逃げまどう映像がCNNで繰り返し流れ、わたしたちも連日ニュースに釘づけだった。
「コロンバイン高校みたいなことはブロウィック校では起きないから」とわたしが訴えると、両親は目と目を見交わした。すでに同じことが頭にあったらしい。
「夏じゅうふてくされてたじゃない」と母が言った。「そろそろ切り替えて、前へ進まなきゃ」
「ふてくされてなんかない」ぼそっとそう答えたものの、母の言うとおりだった。テレビの前でぼんやりしているか、でなければヘッドフォンを着けてハンモックに寝そべり、泣ける歌を聴いているかのどちらかだった。いつまでもくよくよするのはいい生き方じゃないと母は言った。いつだってつらいことはあるんだから、幸せになる秘訣はマイナス思考に引きずられないことよと。悲しみにひたるのがどんなに快感か、母はわかっていない。フィオナ・アップルを聴きながら何時間もハンモックに揺られているのは、幸せでいるより快適なのだ。
助手席でわたしは目を閉じた。「父さんに送ってもらえばよかった、そしたらこんなこと言われずにすんだのに」
「お父さんも同じことを言ったはずよ」
「うん、でももっとやさしく言ってくれたはず」
目を閉じていても、車窓を流れる景色は残らず思い浮かべることができる。ブロウィック校生活二年目にして、すでに十回以上はこの道を走っている。メイン州西部のなだらかな丘陵と酪農場、冷えたビールと生き餌の看板を掲げた商店、屋根がたわんだ田舎家、緑の草やセイタカアワダチソウが腰の高さまで茂った庭と、そこに並ぶ錆びた廃車。ノルンベガに入ったとたん、風景は美しくなる。絵に描いたような町の中心部にはパン屋に本屋、イタリア料理店、麻薬用品販売店、公共図書館が建ち並び、丘の上にはブロウィック校の白い下見板張りの校舎が燦然と輝いている。
母が正門に車を乗り入れた。入寮日なので”ブロウィック校”の銘板には臙脂と白の風船が飾られ、キャンパス内の狭い通路は車で埋まっている。荷物をぎっしり積んだSUVが雑にとめられ、新入生や保護者たちがあたりをうろつきながら校舎を見上げている。母がハンドルに覆いかぶさるように身を乗りだし、徐行と停止を繰り返すうち、ふたりのあいだの空気が張りつめはじめた。
「あなたは頭のいい、面白い子よ。友達なんて大勢できるはずなのに。ひとりくらい失っただけで、自分の時間を台無しにしちゃだめ」
悪気はないのかもしれないが、言い返さずにはいられなかった。「ジェニーはただの友達じゃない。ルームメートだったんだから!」特別な関係なのは当然でしょ、ほかのことが目に入らなくなるくらい、相部屋の外の世界が色褪せて見えるくらい親密な間柄なんだから。そんな気持ちをその言葉にこめたものの、母には通じなかった。大学にも、もちろん寄宿学校にも行っていないから、寮生活の経験がないのだ。
「ルームメートがいたって、ほかにも友達は作れたはずでしょ。ひとりの相手にこだわるのはあまり健全じゃないって言ってるの」
芝生の庭に近づくと、前方で車の列がふたつに分かれているのが見えた。母は左折のウィンカーを出し、それから右に切り替えた。「どっち?」
わたしはため息をついて左を指差した。
グールド寮は民家と変わらないほど小ぢんまりした建物で、八つの居室と、寮監の教師用の居住スペースがあるだけだった。学年末にあった部屋決めのくじ引きで若い番号を引いたので、十年生にしてはめずらしく個室に入ることができた。母とふたりで四往復して、ようやくすべての荷物を部屋に運びこんだ。衣類のスーツケースがふたつ、本の箱がひとつ、予備の枕やシーツ、わたしの古着で母がこしらえたキルト、部屋の中央には首振り扇風機。
荷解きをしていると、開いたドアの外を人が通りすぎた。保護者たちに生徒たち。廊下を走りまわっていた誰かの弟が転んで泣きだした。そのうちトイレに立った母が取りすました声でこんにちはというのが聞こえ、相手の返事が続いた。棚に本を並べていたわたしは手を止めて耳を澄ました。眉根を寄せ、声の主を思いだそうとする──ミセス・マーフィー、ジェニーのお母さんだ。
部屋に戻ってきた母が「ちょっと騒がしくなってきたから」とドアを閉じた。
本を棚に押しこみながら、わたしは訊いた。「さっきの、ジェニーのお母さん?」
「ええ、まあ」
「ジェニーはいた?」
母はうなずいただけでなにも言わなかった。しばらくのあいだふたりで黙って荷解きを続けた。ベッドメイキングにかかり、ストライプ柄のマットレスにボックスシーツをかけながら、わたしは言った。「正直、気の毒なのはジェニーのほうだと思う」
格好をつけてそう言ったものの、もちろん噓だ。つい昨日の夜も、ジェニーの目に自分がどう映るだろうかと、寝室の鏡を一時間も覗きこんでいたのだから。ミストブリーチで明るくした髪に気づいてもらえるだろうか、新しいフープピアスは?
母はなにも答えずにビニールのトートバッグからキルトを取りだした。わたしが未練たらたらで、また傷つくのではと心配しているのだ。
「仲直りしようって言われても、時間の無駄だし断る」
母はうっすらと笑い、ベッドのキルトを平らにした。「ジェニーはまだあの子と付きあってるの?」ジェニーの恋人で、絶交のきっかけを作ったトム・ハドソンのことだ。さあねと肩をすくめたものの、知っている。もちろん知っている。夏じゅうずっと、ジェニーのAOLのプロフィールをチェックするたび、交際ステータスは”相手がいる”のままだった。まだ付きあっているのだ。
母は帰るまえに二十ドル札を四枚くれ、毎週日曜日には家に電話すると約束させた。
「忘れないでね。それと、お父さんの誕生日には帰ってくること」そう言って、骨が痛むほどきつくわたしを抱きしめた。
「息ができないってば」
「ごめん、ごめん」母は潤んだ目を隠そうとサングラスをかけ、部屋を出ていこうとしてこちらに指を突きつけた。「自分を大事にしてね。人付き合いも」
わたしは手を振って応えた。「わかった、わかった」ドアのところに立って、廊下を歩きだした母が階段を下りて見えなくなるまで見送った。やがて、賑やかに響く母娘の声が近づいてきた。ジェニーとお母さんだ。姿が見えたとたん、わたしは部屋に逃げこんだ。ちらりとしか見えなかったが、ジェニーが髪を切り、去年はクロゼットにしまいっぱなしだったワンピースを着ているのがわかった。
ベッドに寝転がってぼんやり部屋を眺めながら、しばらく廊下のざわめきを聞いていた。別れの挨拶、洟をすする音、くぐもった泣き声。ふと、一年前に九年生の寮に入り、初めてジェニーと夜更かしした日のことを思いだした。ジェニーのCDプレーヤーからザ・スミスやビキニ・キルが流れていて、どちらも聴いたことのないバンドだったのに、わたしは知ったかぶりをした。ダサい田舎者だとばれるのが怖かったからだ。そうなったら、きっと仲良くしてもらえない。ブロウィック校で数日を過ごしたころ、わたしは日記にこう書いた。”ここに来てなによりよかったのは、ジェニーみたいな子たちと知りあえることだ。彼女、めちゃめちゃイケてて、そばにいるだけで自分も同じになれそう!”。そのページは破りとって捨てた。目に入っただけで、屈辱で頰が熱くなるから。
グールド寮の寮監のトンプスン先生は、大学を出たての新任のスペイン語教師だった。談話室で開かれた初めての夜のミーティングでは色とりどりのマーカーペンと紙皿が用意されていて、各自のドアに張る名札をこしらえた。寮生は上級生ばかりで、十年生はジェニーとわたしだけだった。わたしたちはできるだけ離れてテーブルの両端の席についた。ジェニーは茶色のボブヘアが頰に垂れかかるほど深くうつむいて名札をこしらえていた。ひと息入れてペンを替えに近づいてきたときも、わたしなどいないかのように視線を素通りさせた。
「部屋に戻るまえに、これをひとつずつ取ってください」トンプスン先生が言って、ビニール袋をあけた。最初はキャンディかと思ったけれど、中身は銀色のホイッスルだった。
「使うことはまずないでしょうけど、念のために持っておいたほうがいいですからね」
「なんでホイッスルなんて必要なんですか」ジェニーが訊いた。
「それは、ほら、校内の安全対策よ」トンプスン先生が大げさににっこりしたので、気まずいのだとわかった。
「でも、去年はもらわなかったのに」
「レイプされそうになったときのためでしょ」ディアナ・パーキンズが言った。「それを吹いて、相手にやめさせるの」そしてホイッスルを口にくわえ、勢いよく吹いた。小気味いいほど大きな音が廊下に響きわたり、誰もが真似してみずにはいられなかった。
トンプスン先生が騒音に負けじと声を張りあげた。「はい、そこまで」そして笑って続けた。「ちゃんと鳴るのがわかってよかった」
「こんなもので、レイプしようとする相手をほんとに止められるんですか」ジェニーが尋ねた。
「レイプ魔を止めるなんて無理」ルーシー・サマーズが言った。
「そんなことありませんよ」トンプスン先生が答えた。「それに、これは”レイプ”防止用のホイッスルじゃないの。幅広く使える防犯グッズよ。校内で不安を感じたら、いつでも吹いていいの」
「男子もホイッスルをもらうんですか」わたしは訊いた。
ルーシーとディアナがあきれたように目を剝いた。「なんで男子にホイッスルが必要なわけ」ディアナが言った。「考えてものを言えば」
それを聞いてジェニーが大笑いした。自分はルーシーとディアナにあきれ顔をされてはいないかのように。
授業開始日、キャンパスは人であふれ、下見板張りの校舎は窓があけ放たれて、職員駐車場は満車だった。朝食のとき、シェーカースタイルの長テーブルの端の席についたわたしは、胃が締めつけられてなにも食べられなかった。ストレートティーを飲みながら、カテドラル型天井の食堂内に目を走らせ、新顔はいないか、見慣れた顔になにか変化はないかとたしかめた。誰のことでも、どんなことでも、わたしは気づかずにはいられない。マーゴ・アサートンが瞼の垂れた右目を隠すために髪を左分けにしていることも、ジェレミー・ライスが毎朝かならず食堂のバナナをくすねることも。トム・ハドソンがジェニーと付きあいはじめるまえ、目を留める理由などないうちから、彼がボタンダウンシャツの下に着るバンドTシャツのローテーションを完璧に覚えていた。わたしのことなど誰も気にしていないのに、わたしは人のことにあれこれ気づいてしまう。それが自分でも不愉快で、なのにどうしようもなかった。
朝食のあと、一時限がはじまるまえに集会があった。ぞろぞろと講堂に入ると、内部は温かみのある板張りで、赤いビロードのカーテンの隙間から差しこんだ日の光が、弧の形に並んだ椅子の列を照らしていた。白髪交じりのボブヘアを耳の後ろにかけたジャイルズ校長が、震えがちな声を張りあげて校則や教育方針について話し、その数分のあいだは誰もが潑溂とした顔で聞いていた。けれども、校長が演台を離れるころには講堂内の蒸し暑さが増し、誰の額にも汗の粒が浮かびはじめた。二列後ろで誰かが文句を言った。「いつまで続くんだ?」アントノヴァ先生が振り返ってにらんだ。わたしの隣の席のアナ・シャピロが両手で顔をあおいだ。開いた窓からかすかな風が吹きこみ、閉じたカーテンの裾を揺らした。
そのとき、英語科主任のストレイン先生が壇の中央に進みでた。顔は知っているけれど、授業を受けたことも、話をしたこともない先生だ。癖の強い黒髪、黒い顎ひげ、レンズの反射のせいで眼鏡の奥は見えないが、なによりもわたしの目を──たぶん誰の目も──引いたのは体格だった。太っちょではないけれど大柄で肩幅が広く、ひどく長身なせいか、自分のかさ高さに恐縮しているみたいに背を丸めていた。
演台に立ったストレイン先生はマイクの角度を限界まで上に向けた。眼鏡を日の光できらめかせながら先生が話をはじめると、わたしはバックパックを探って時間割をたしかめた。あった、今日の最終時限だ──アメリカ文学上級クラス、担当教師ストレイン。
「今朝ここにいるきみたちは、若さと大いなる可能性に満ちている」スピーカーから声が轟いた。あまりに明瞭な発音のせいで、耳障りなほどだった。長く伸ばされた母音、硬い子音。うとうとしたかと思うとはっと目を覚ますようなリズムだ。「遠くの星を目指そう、届かなくても、月には着けるかもしれない」内容はありきたりなのに、話し方が上手なせいでなんとなく深みのある言葉に聞こえた。
「これから一年、最高の自分を目指す努力を怠らないように。きみたちの力でブロウィック校をよりよい場所にしてほしい。足跡を残すんだ」ストレイン先生が後ろポケットから赤いバンダナを引っぱりだして額を拭ったとき、腋に黒っぽい汗じみが見えた。
「私はブロウィック校の教師を務めて十三年になる。その十三年間に、本校の生徒たちの勇気ある行いを数えきれないほど目にしてきた」
気づけば自分の膝の裏と肘の内側も汗ばんでいて、わたしは椅子の上で身じろぎしながら、勇気ある行いとはどういうものだろうと考えた。
秋学期の受講科目はフランス語上級クラス、生物上級クラス、世界史特進クラス、幾何学クラス(数学が苦手な生徒向きのクラスで、アントノヴァ先生も”落ちこぼれの幾何学クラス”と呼んでいた)、選択科目のアメリカ政治とメディア論クラス(CNNを見て、じきにはじまる大統領選挙について議論する)、そしてアメリカ文学上級クラスだった。初日は、重たい教科書を抱えて教室から教室へと右往左往する羽目になった。学年が上がって勉強量が増えたことをひしひしと実感した。どの先生からも、今後は加速度的に宿題や試験が大変になると脅された。ここは並みの学校ではなく、わたしたちも並みの生徒ではないのだから、選ばれし者として困難を受け入れ、立ちむかわなければならないのだそうだ。そうこうするうち、くたびれてきた。一日が半分終わるころには頭もまともに上げていられなくなったので、昼食は飛ばしてグールド寮にこっそり戻り、ベッドに丸くなって泣いた。そこまでして、なんで頑張らないといけないの? そんな態度を、それも初日からとるなんてどうかしている。そう思うとあれこれ考えずにはいられなかった。そもそもなぜブロウィック校なんかに来たんだろう? なぜ学費を免除されたりしたのか、なぜわたしがここにふさわしいほど優秀だと見なされたりしたのか。そんな負のスパイラルに陥るのは何度目かで、行きつく答えはいつも同じだった。わたしにはなにか欠陥が、生まれつきの弱点があって、それが怠け癖や努力嫌いとして表れているのだ。おまけに、こんなふうに四苦八苦している生徒はわたしひとりのようだった。みんな自信に満ち、余裕をもって教室を移動していた。いともやすやすと。
最終時限のアメリカ文学の教室に入り、まっさきに気づいたのは、ストレイン先生が集会のあとシャツを着替えたことだった。教室の前に立って黒板にもたれ、腕組みをしたその身体は、講堂の壇上にいたときよりいっそう大きく見えた。生徒は十名、ジェニーとトムもいて、めいめいが教室に入ってくるたびに先生は値踏みするようにその動きを目で追った。ジェニーが入ってきたとき、わたしはすでに大きなミーティングテーブルについていて、ふたつ離れた席にトムがいた。トムはジェニーを見て顔を輝かせ、自分とわたしのあいだの空いた席を手で示した。それが大問題だとわからないほど鈍いのだ。ジェニーはバックパックの肩紐をつかんだまま、冷ややかな笑みを浮かべた。
そして「こっちにすわらない?」と言った。テーブルの反対側、つまりわたしから遠い方ということだ。「そのほうがいい」
ジェニーの目が、寮のミーティングのときと同じようにわたしを素通りした。なんだかばかばかしく思えた。そこまでして、友情などなかったかのように振る舞うなんて。
始業のベルが鳴っても、ストレイン先生は動こうとしなかった。教室が静かになるのを待って初めて口を開いた。「きみたちは知った顔同士だろうが、私はそうでもなさそうだ」
そしてテーブルの正面の席にすわり、生徒たちをランダムに指して名前と出身を訊いた。ときどき別の質問も加わった。兄弟姉妹はいるか、これまで行ったいちばん遠い場所はどこか、自分で選べるとしたらどんな名前をつけるか。初恋の年を訊かれたジェニーは頰を染めた。隣のトムも真っ赤になった。
自分の番がまわってきたとき、わたしはこう自己紹介した。「ヴァネッサ・ワイです、出身はどこでもありません」
ストレイン先生が椅子の背にもたれた。「ヴァネッサ・ワイ、出身はどこでもない、か」
オウム返しされた自分の言葉がひどく間抜けに聞こえ、気まずさに笑ってしまった。
「その、町とも呼べないようなところなんです。名前もついてなくて。”二十九番郡区”としか」
「メイン州のかい? 東部の幹線道路沿いの? あそこならよく知ってるよ。近くにすてきな名前の湖があるね、ホエールなんとかっていう」
わたしは驚いて目をぱちくりさせた。「ホエールズ・バック湖。うちはその湖岸です。定住しているのはうちの家族だけなんです」そう話しながら、奇妙な胸の痛みを覚えた。ブロウィック校に来てからホームシックを覚えることはなかったけれど、それは誰にも故郷の話をしなかったせいかもしれない。
「驚いたな」ストレイン先生は少し考えて続けた。「あそこに住んでいて寂しくはないかい」
一瞬、言葉に詰まった。その問いに心がすっと切れた。痛みもなく、驚くほど鮮やかに。森の奥での生活を”寂しい”と表現したことはなかったものの、ストレイン先生にそう言われると、そのとおりだ、ずっとそうだったにちがいないと思えて、急に恥ずかしさを覚えた。まさか、顔じゅうに寂しさがべたべた貼りついているんだろうか、先生がひと目で見抜けるくらい、寂しい人間なのが丸わかりなんだろうか。やっとのことで「まあ、ときどきは」と返事をしたものの、先生はすでにわたしから注意を移し、平地のシカゴからメイン州西部の丘陵地帯に引っ越してきた感想をグレッグ・エイカーズに尋ねていた。
全員の自己紹介がすむと、ストレイン先生は、今年度の授業のなかでこのクラスに最も苦労するはずだと告げた。「教え子のほとんどは、ブロウィック校でいちばん厳しい教師は私だと言うだろうね。大学の教授より厳しいと言う卒業生もいるほどだ」そう言って指先でテーブルをこつこつと叩き、これは大事だと生徒たちが悟るのを待った。それから黒板の前へ行ってチョークで板書をはじめ、振り返って言った。「ほら、ノートはどうした」
あわててノートを開くわたしたちを前に、先生はヘンリー・ワズワース・ロングフェローの詩﹁ハイアワサの歌﹂の解説をはじめた。聞いたこともなかったのはわたしだけではないはずだが、知っているかと先生に訊かれると、全員がうなずいた。誰も間抜けに見られたくはない。
授業を聞きながら、わたしはこっそり教室を見まわした。人文学科棟にあるほかの教室と造りは同じだ。板張りの床、本棚が造りつけられた壁、緑色の黒板、ミーティングテーブル。でも、ここには息遣いや温もりが感じられる。中央に足跡の筋がついたラグ、緑色のシェードのバンカーズランプに照らされたオーク材の大きな机、ファイルキャビネットの上にはコーヒーメーカーとハーヴァード大学の紋章入りのマグカップ。刈りたての芝のにおいと車のエンジン音が開いた窓から流れこんでいる。ストレイン先生はチョークが砕けるほどの力をこめてロングフェローの詩の一節を板書しはじめた。途中でふと手を止めてこちらを振り返ると言った。「このクラスでなにかひとつ学ぶとするなら、この世は互いに交差する無数の物語で成り立っていて、そのすべてが真実で意味のあるものだということだ」わたしはひとことも漏らすまいと、必死にその言葉をノートに書きとった。
終了時間まで残り五分のところで、解説がいきなり止まった。ストレイン先生は両手をだらんと垂らし、肩を落とした。黒板を離れてテーブルの席にすわりこむと、顔をこすり、ため息を漏らした。それから疲れた声で言った。「初日はいつも長いな」
テーブルを囲んだわたしたちはとまどい、ノートを取っていたペンを宙に浮かせたまま待った。
先生は顔をこすっていた手を下ろした。「みんなには正直に言おう。もうへとへとだ、くそったれ」
テーブルの向かいでジェニーが驚いたように笑った。授業中にふざけたことを言う先生はときどきいるけれど、”くそったれ”は初めて聞いた。教師はそんなことを言わないものだと思っていた。
「悪態をついてもかまわないだろうか。いや、先に許可を取るべきだったな」先生はわざとらしいほど真面目な調子で両手を組んだ。「私の下品な物言いに重大な異議がある者はいますぐ申しでよ、さもなくば永遠に沈黙せよ」
もちろん、誰もなにも言わなかった。
*
新学期の最初の数週間は足早に過ぎた。いくつもの授業にストレートティーの朝食、ピーナッツバターサンドの昼食、図書館での自習、グールド寮の談話室で見るWB局のドラマ。その繰り返しだった。わたしは寮のミーティングをさぼって罰を受けることになったが、トンプスン先生に頼みこんで飼い犬の散歩で許してもらった。寮の自習室で一時間も向きあってすわっているなんて、お互いに苦痛でしかない。ほぼ毎朝、わたしは授業の直前までかかってどうにか宿題を仕上げた。どんなに頑張ってもつねに余裕がなく、落ちこぼれる寸前だった。先生たちには、もっとやれるはずだとしきりに言われた。頭はいいのに、集中力とやる気が足りないのだと。怠惰という言葉をいくらか婉曲にしただけだ。
入寮してほんの数日で、わたしの部屋は散らかり放題になった。脱ぎ捨てた服に、ばらばらの紙、飲みかけの紅茶のカップがいくつも。スケジュールを管理するためのシステム手帳もなくしてしまったが、なんでもかんでもなくすので、やっぱりねと思っただけだった。週に一度は部屋の外のドアノブに鍵がぶらさがっていた。バスルームか教室か食堂で誰かが拾って届けてくれたのだ。本当に、なにひとつきちんとしまっておけなかった。教科書がベッドと壁の隙間から見つかったり、宿題はバックパックの底に突っこまれていたり。先生たちはくしゃくしゃの提出物に毎回目を剝き、その分は減点しますよと警告した。
「整理整頓を身につけなさい!」前日に書いたメモを見つけようと必死に教科書をめくっていると、世界史特進クラスの先生にりつけられた。「まだ二週目だぞ。いまからそんな調子でどうする」最終的にメモは見つかったものの、先生の評価は変わらなかった。わたしのだらしなさは弱さの表れで、深刻な欠点なのだ。
ブロウィック校では、指導教員と受け持ちの生徒たちが月に一度夕食をともにする。教師の自宅を訪ねるのが伝統だが、わたしの担当のアントノヴァ先生は生徒を家に招かなかった。「線引きは必要ですからね。意見の違う先生方もいますが、それはかまいません。生徒たちと四六時中いっしょにいるのもいいでしょう。でも、わたしは違う。どこかへ食事に行き、少し話して、解散とします。線引きを大事にね」
学年最初のミーティングが開かれたのは、町なかのイタリア料理店だった。リングイーネをフォークで巻きとるのに気を取られていると、各教師の評価によれば、わたしの最優先課題はだらしなさの克服だとアントノヴァ先生に告げられた。露骨にいやな顔をしないようにつとめながら、気をつけますとわたしは答えた。続いて、テーブルの並び順に生徒全員に問題点が告げられた。ほかには誰もだらしなさを指摘されなかったが、それでもわたしの評価が最低というわけではなかった。カイル・グインはふたつのクラスで宿題を提出していなかった。重大な問題だ。アントノヴァ先生がカイルの評価を告げるあいだ、残りのわたしたちはパスタの皿に目を落としたまま、自分はまだましだと胸を撫でおろしていた。食事がすんで皿が下げられると、先生はチェリーの砂糖漬けが入った手作りのドーナツの容器を一同にまわした。
「パンプーシュカといって、ウクライナの食べ物なの。母の故郷の」
レストランを出て丘の上のキャンパスへ戻るとき、アントノヴァ先生がわたしの隣に並んだ。「そうそう、ヴァネッサ、今年は部活動に参加しなさい。できれば複数の。大学の入試対策にね。いまのままでは心もとないから」あれこれ助言がはじまり、わたしはうなずきながら聞いていた。もっと積極的になるべきなのはわかっていて、努力もしてみた。まえの週にはフランス語部に顔を出してみたものの、部員は会合のたびに小さな黒いベレー帽をかぶると知ってあっさりやめた。
「文芸部はどう? あなたは詩を書くでしょ」
文芸部のことも頭にはあった。そこでは部誌を発行していて、去年はそれを隅から隅まで読み、自分の詩と掲載作のどちらが上手いかを客観的に見きわめようとした。
「ですね、いいかも」
先生がわたしの肩に手を置いた。「考えてみて。今年の顧問はストレイン先生で、指導も上手だから」
そして振り返って手を叩き、だらだらと遅れて歩く生徒にロシア語で注意した。なぜだか英語よりも、生徒を急がせるには効果的だった。
文芸部の部員はほかにひとりきりだった。ジェス・リーという十一年生で、ブロウィック校にはめずらしくゴスっぽい服装をしていて、ゲイだと噂されていた。わたしが教室に入っていったとき、ジェスはミーティングテーブルに置かれた書類の山の前にすわり、コンバットブーツを椅子にのせて、耳の後ろにペンをはさんでいた。ちらっとこちらを見ただけで、なにも言わない。わたしの名前さえ知らないかもしれない。
でも、机の奥にすわっていたストレイン先生のほうはぱっと立ちあがり、つかつかと近づいてきた。「入部希望かい」
わたしは口を開いたものの、答えに迷った。部員がひとりだけだと知っていたら来なかったのに。その場で帰りたくなったが、ストレイン先生に喜々として手を握られ、「おかげで部員が百パーセント増しだ」と言われたので、いまさら逃げられなかった。
先生はわたしをテーブルの席に案内して自分も隣にすわり、書類の山は部誌への応募作だと説明した。「選考も生徒がやるんだ。なるべく応募者の名前は見ないように。ひとつずつ丁寧に、最後まで目を通して決めてほしい」それから用紙の余白にコメントを残し、各応募作を五段階で評価するようにと続けた。一は問題外、五は文句なしだ。
ジェスが目も上げずに言った。「ぼくはチェックマークで分けてます。去年もそうだったので」そしてすでに目を通した応募作を手で示した。右上の隅に、それぞれチェック、チェック・マイナス、チェック・プラスのしるしが記入されている。先生は眉をひそめたが、ジェスは気づく様子もなく、読んでいる詩から目を離さなかった。「どんな方法でもいい、ふたりで決めてくれ」先生はそう言ってわたしに笑いかけ、ウィンクした。そして腰を上げながら肩をぽんと叩いた。
先生が机に戻ると、わたしは応募作の山からひとつを手に取った。「彼女の人生最悪の日」と題した短篇だ。応募者はゾーイ・グリーン。ゾーイとは去年代数のクラスでいっしょだった。席がわたしの後ろで、セス・マクロイドがわたしを赤毛のデブと呼ぶたびに、そんなにおかしな言葉は初めて聞いたというようにげらげら笑った。わたしは首を振って頭から先入観を締めだそうとした。だから先生は名前を見ないようにと言ったのだ。
作品は病院の待合室にいる少女が祖母を亡くす話で、第一段落を読んだだけで退屈だとわかった。何枚あるのかとページをめくっているわたしに気づいて、ジェスが小声で言った。「つまらなければ、最後まで読まなくたっていい。去年も部誌の編集はやったけど、顧問のブルーム先生はなにも言わなかった」
自分の席にいるストレイン先生にさっと目をやると、背中を丸めて書類の山に目を通しているところだった。わたしは肩をすくめた。「とりあえず読んでみる。大丈夫」
ジェスがわたしの手にしたページを読もうと眉根を寄せた。「ゾーイ・グリーン? 去年のディベート大会で大泣きした子だっけ」そう、ゾーイは死刑肯定側に割りあてられ、決勝の対戦相手のジャクソン・ケリーに主張が人種差別的で非人道的だと指摘されて、わっと泣きだした。ジャクソンが黒人でなければ、ケリーもそこまで動揺はしなかっただろう。ジャクソンの優勝が宣言されると、ゾーイは相手の反論が個人攻撃にあたり、ディベートの規則に違反していると訴え、結局はふたりが優勝を分けあう形になった。とんだ言いがかりで、誰もがそう気づいていた。
ジェスが身を乗りだしてゾーイの作品をわたしの手から取り、右上にチェック・マイナスのしるしを書きこんで、”不採用”の山にぽんとのせた。「一丁あがり」
それから一時間、ジェスとわたしが作品に目を通すあいだ、ストレイン先生は机で採点をしながら、ときどきコピーを取ったり、コーヒーメーカーに水を足しに行ったりした。途中でオレンジの皮を剝いたときには、いい香りが教室を満たした。活動時間が終わってわたしが椅子から立つと、先生が次の会合にも来るかと訊いた。
「まだわかりません。ほかの部も試してみようかと思って」
先生は笑みを浮かべ、ジェスが教室を出ていくのを待ってから言った。「友達作りの役にはあまり立ちそうにないね」
「いえ、それはいいんです。もともと、超社交的っていうわけじゃないし」
「なぜだい」
「さあ。なぜか大勢友達ができるほうじゃなくて」
深いうなずきが返ってくる。「わかるよ。私もひとりが好きなほうでね」
とっさに、違います、わたしはひとりが好きなわけじゃないんですと答えそうになったが、たしかに言われたとおりかもしれない。わたしはひとりを好み、孤独を選んでいるのかもしれない。
「でも、まえはジェニー・マーフィーが親友だったんです。アメリカ文学のクラスでいっしょの」言葉が口をついて出て、わたしははっとした。教師に、それも男の人に、そんなことまで話したことはなかった。でも、頰杖をついた先生に、にこやかなやさしい目で見られていると、打ち明けたい、自分を知ってほしいと思った。
「ああ、あのかわいらしいナイルの女王か」わたしがとまどって眉をひそめると、ボブカットがクレオパトラみたいだからだと先生は説明した。それを聞いたとき、身体の奥でなにかが疼いた。嫉妬のような、いや、もっと意地の悪いものが。
「あの子の髪はそんなにきれいじゃないと思いますけど」
ストレイン先生がにやりとした。「そうか、友情は終わったんだね。なにが原因で?」
「ジェニーがトム・ハドソンと付きあいだしたから」
しばらく間があった。「もみあげの彼か」
わたしはうなずき、教師はそんなふうに生徒を見分け、頭のなかで分類するのかと考えた。誰かがヴァネッサ・ワイの名前を出したら、先生はどんなふうにわたしを思いだすんだろう。赤毛の女の子。いつもひとりぼっちの女の子。
「つまり、裏切られたというわけだね」ジェニーに、という意味だ。
そんなふうには考えていなかったが、とたんに胸が熱いもので満たされるのを感じた。わたしは裏切られたのだ。わたしの思いが重たすぎ、依存しすぎたせいで、ジェニーに逃げられたわけじゃない。そう、わたしは被害者だ。
先生が立ちあがって黒板の前へ行き、授業の板書を消しはじめた。「入部の理由は? 履歴書の中身がお粗末なせいかな」
わたしはうなずいた。先生には正直になれる気がした。「アントノヴァ先生に勧められて。でも、書くのは好きです」
「どんなものを書くんだい」
「たいていは、詩を。上手いわけじゃないですけど」
振りむいたストレイン先生は、微笑ましいものを見るようなやさしい表情を浮かべた。「きみの作品を読ませてほしいな」
わたしの頭は”作品”という響きに反応した。わたしの書くものに、まともに読む価値があると言われた気がした。「いいですけど。本当に読みたいなら」
「読みたいとも。でなきゃ、頼んだりしない」
それを聞いて、顔が赤らむのがわかった。母に言わせれば、わたしのいちばん悪い癖は、うれしい言葉をかけられたときに、自分を卑下して受け流してしまうことなのだそうだ。褒め言葉の受けとり方がわたしにはよくわからない。要するに自信の問題なのよと母は言っていた。というより、自信のなさの。
ストレイン先生が黒板消しを受皿に置き、離れて立っているわたしを見た。両手をポケットに突っこんで、上から下までしげしげと眺める。
「すてきなワンピースだね。趣味がいい」
どうも、とわたしはぼそりと答えた。そういう反応がしみついていて、反射的に出てしまう。そう思いながら自分の服を見下ろした。深緑色のジャージーワンピースで、しいて言えばAラインだが、全体的にだぼっとしていて、丈は膝上までしかない。流行りのスタイルではなく、色合いが自分の髪に映えるから着ているだけだ。中年の男の人が女の子の服に目を留めるのが不思議な気がした。父はワンピースとスカートの区別さえつかないだろうに。
ストレイン先生が黒板に向きなおり、すでにきれいになった板面をまた拭きはじめた。なんだか気まずそうに見えて、もう一度心をこめてお礼を言いたい気持ちが頭をもたげた。すごくうれしいです。そんなことを言ってもらったのは初めて。振り返るのを待ってみたけれど、先生は緑色の板面に白っぽい筋をつけながら、黒板消しを左右に動かしつづけた。
少しして出口に向かいかけたとき、声をかけられた。「次の木曜日も来てくれるとうれしいよ」
「じゃあ、そうします」
そんなわけで、次の木曜日も、その次の木曜日も、そのまた次の木曜日もわたしは文芸部に顔を出した。そして正式な部員になった。ジェスとふたりで部誌の掲載作を選ぶのは、思ったよりも時間がかかった。おもにわたしが優柔不断で、何度も考えなおしては評価を変えるせいだった。一方のジェスはページに勢いよくペンを走らせながら、容赦なくさっさと決断を下した。どうすればそんなにすぐ決められるのかとわたしが尋ねると、出来の良し悪しなんて最初の一行でわかるだろと答えた。ある木曜日、ストレイン先生が教室の奥の教員室に引っこみ、部誌のバックナンバーの束を手に戻ってきた。実物がどんなものかを見せるためだ。といっても、ジェスは去年も編集作業をしたのでもちろん知っていた。そのうちの一冊をぱらぱらとめくると、ジェスの名前が目次の”小説”の欄に見つかった。
「ねえ、あなたのもある」
それを見て、ジェスはうめいた。「目の前で読まないでくれ、頼むから」
「なんで?」わたしは一ページ目にさっと目を通した。
「読まれたくないから」
わたしはそれをバックパックにすべりこませたまま、夕食後まで忘れていた。ちんぷんかんぷんな幾何学の宿題に悪戦苦闘していて気分転換がしたくなり、部誌を手に取ってジェスの作品のページを開き、二度読んだ。よかった。わたしがこれまで書いたものも、今年の応募作も到底かなわないほど、本当にいい作品だった。次の会合でそれを伝えようとすると、ジェスはさえぎった。「書くほうはもう興味ないんだ」
別の日の午後、部誌編集に使う新しいDTPソフトの操作法をストレイン先生に教わった。ジェスとわたしがコンピューターの前に並んですわり、後ろに立った先生が操作を見守り、間違いを正した。途中でわたしがミスをしたとき、先生は身をかがめて大きな手でわたしの手をすっぽり覆い、マウスを正しい場所へ動かした。触れられたせいで全身がかっと熱くなった。もう一度ミスをしたときも同じようにされ、今度は軽く手に力がこめられた。じきにこつがわかるさと励ますような感じだったけれど、ジェスには同じことをしなかった。ジェスがうっかり保存せずにソフトを終了してしまい、手順を一から説明しなおす羽目になったときも。
九月の下旬、秋晴れの完璧な天気が一週間続いた。朝が来るたびに木々の葉は鮮やかさを増し、ノルンベガ周辺の山並みを錦に染めた。キャンパスはブロウィック校の受験を決めたときにしきりに眺めたパンフレットそっくりになった。セーター姿の生徒たち、青々とした芝生、白い下見板張りの壁が黄金色に染まる夕暮れ。それを満喫できるはずなのに、天気のせいでわたしは落ち着かず、平静を失っていた。放課後もじっとしているのが苦痛で、図書館からグールド寮の談話室へ移っては、また図書館に戻った。どこにいてもくつろげず、すぐに移動したくなった。
ある日の午後、キャンパスを三周しても、落ち着ける場所がどこにも見つからなかった。図書館は暗すぎるし、散らかった寮の部屋は気が滅入りそうで、ほかはどこも仲間同士で勉強する生徒たちだらけなので、ひとりの自分が、いつでもひとりぼっちの自分が目立ってしまう。しかたなく、人文学科棟裏の草の斜面で足を止めた。落ち着いて、深呼吸しよう。
アメリカ文学の授業中によく眺めている一本きりのカエデの木に寄りかかり、火照った頰を手の甲で押さえた。気温は十度しかないのに、気持ちがたかぶって汗ばんでいる。
大丈夫。ここで勉強して、ちょっと落ち着こう。
木にもたれてすわり、バックパックに手を入れて、幾何学の教科書を押しやってリングノートを取りだした。先に詩に取り組めば気分もよくなるかと思ったのに、書きかけのページを開いて、孤島に囚われた少女が沖の水夫たちに手招きするさまを描いた二連にあらためて目を通すと、そのへたくそさに驚いた。ぎこちなく、まとまりに欠け、ほとんど意味不明だ。なのに、それをいいと思って書いたのだ。いいって、どこが? どう見てもだめなのに。わたしの詩なんてみんなだめなんだ。ぎゅっと身を丸め、てのひらの付け根で瞼をこすっていると、落ち葉や小枝を踏んで近づいてくる足音が聞こえた。目を上げると山のようにそびえるシルエットが日差しをさえぎった。
「やあ」
わたしは目の上に手をかざした。ストレイン先生だ。わたしの顔を見て赤い目に気づいたのか、表情が変わった。「泣いていたんだね」
わたしは見上げたままうなずいた。噓をついても無駄だ。
「ひとりにしてほしいかい」
少し迷ってから、首を横に振った。
先生は数十センチの距離をとって地面に腰を下ろした。長い両脚が投げだされ、ズボンの下の膝の形があらわになる。そして涙を拭うわたしをじっと見守った。
「邪魔する気はなかったんだ。あそこの窓から姿が見えたから、声でもかけようかと思ってね」そう言って、背後の人文学科棟を示した。「泣いていたわけを訊いてもいいかな」
わたしは大きく息を吸い、言葉を探したが、少しして首を振った。「ひとことじゃ説明できません」悲しいのは自分の詩がへたくそなせいでも、自習の場所探しに疲れてしまったせいでもない。もっと暗い感情、自分には直しようのない欠陥があるのではという恐れのせいだった。
それで話は終わると思った。けれども、先生は授業中に生徒たちに向けて難しい質問をしたときのように、答えを待った。ひとことで説明できないのは当然さ、ヴァネッサ。難しい質問をするのは、その感じを味わわせるためなんだから。
もう一度息を吸いこんでから、わたしは言った。「季節のせいか、落ち着かないんです。時間切れに近づいてるような気がするというか。人生を無駄にしてるみたいな」
ストレイン先生は面食らった顔をした。そんな言葉は予想外だったにちがいない。
「人生を無駄に、か」
「意味不明でしょ」
「いや、そんなことはない。よくわかるよ」先生は頭の後ろで手を組んで首をかしげた。「そうだな、きみが私の年頃なら、中年の危機のはじまりじゃないかと言うだろうね」
笑いかけられ、つられてわたしも笑顔になった。ふたりしてにっこりする。
「創作の最中だったようだね。いい作品になりそうかい」
わたしは肩をすくめた。自分の書いたものをよく言っていいのかわからない。自慢するようで気が引けた。
「書いたものを見せてもらえるかな」
「だめ」手に持ったノートをぎゅっとつかんで胸に押しつけると、その急な動きにぎょっとしたように、先生の目に緊張が走った。わたしは気を落ち着けてから続けた。
「まだ完成してないので」
「作品が本当の意味で完成することなどあるのかな」
どう答えるか、試されているような気がした。少し考えてからこう言った。「より完成に近いものはあると思います」
笑みが返された。答えが気に入ったようだ。「より完成に近いものなら見せてもらえるかい」
わたしはノートを胸から離して表紙を開いた。中身は大半が書きかけの詩で、走り書きしては直しを繰り返したものだ。後ろのほうのページをぱらぱらとめくって、ここ二週間かけて書いた一篇を見つけた。未完成だけれど、ひどくはない。ノートを先生に渡しながら、綴じ目に沿って余白に落書きした花の蔓に気づかれませんようにと思った。
先生はノートを大事そうに両手で持ち、そんなふうに自分のノートを人が手にするのを見ただけで身体に震えが走った。それまでは誰にも触らせず、もちろん中身を見せたこともなかった。詩を読み終えると先生は「うーん」と言った。もっとはっきりした反応が欲しかった。気に入ったかどうかわかるような。でも、続きは「もう一度読んでみよう」だった。
ようやく先生が目を上げて「ヴァネッサ、すばらしいよ」と言ったとき、思わず大きなため息をついて、笑ってしまった。「長い時間をかけて書いたのかい」
ふと閃いたことにしたほうが感心してもらえるかと思い、肩をすくめて噓を言った。
「そんなには」
「日頃からよく書いているそうだね」ノートが返される。
「たいてい毎日」
「だろうね。とても上手いから。読み手としての意見だよ、教師としてじゃなく」
あまりのうれしさにまた笑うと、ストレイン先生は微笑ましそうなやさしい目になった。「なにかおかしかったかい」
「そうじゃなくて、書いたものをこんなに褒めてもらったのは初めてで」
「冗談だろ。いまのじゃ到底足りない。もっともっと褒めたいくらいだよ」
「じつは、いままで誰にもちゃんと見せたことがなくて、自分が書いた……」ものをと言おうとして、思いきって先生の言葉に倣った。「作品を」
ふたりのあいだに沈黙が落ちた。先生は頭の後ろで手を組んで景色を眺めていた。絵のように美しい町並み、遠くを流れる川、緩やかに起伏する丘。わたしはノートに目を落としてページを眺めたが、なにひとつ頭に入らなかった。隣にいる先生の身体が気になってしかたがない。斜めに木にもたれた胸、シャツをつっぱらせているお腹、足首のところで組んだ長い脚。ズボンの片裾がめくれ、ハイキングブーツとのあいだの皮膚が一センチほど覗いている。先生が立ちあがって行ってしまわないように、引きとめられそうな言葉を探したが、なにか思いつくまえに、先生は赤いカエデの落ち葉を拾い、葉柄を持ってくるりとまわしてから、少し考えたあと、それをわたしの顔のそばにかざした。
「ほら、きみの髪の色とそっくりだ」
わたしは身をこわばらせた。口があいたのがわかった。カエデの葉はもうしばらくそこにあり、葉先がわたしの髪をくすぐった。やがて、小さく首を振ると先生は手を下ろし、葉を地面に落とした。そして腰を上げ──また日差しをさえぎって──太腿で両手を拭うと、なにも言わずに人文学科棟へ戻っていった。
その姿が見えなくなったとたん、パニックが押し寄せ、逃げだしたくなった。急いでノートを閉じ、バックパックをひっつかむと寮へと歩きだしたが、思いなおして引き返し、先生がわたしの髪にかざした葉がどれだったかと地面を探した。それを大事にノートにはさんでから、宙に浮かぶようなふわふわした足取りでキャンパスを横切った。部屋に戻ったあと、ようやく自分の姿が窓から見えたと言われたことを思いだし、教室に戻った先生に葉を探すところを見られたかもしれないと気づいて、ぎゅっと目をつぶった。
(続く)
*ルビの省略など、試し読みのために一部を変更しています。