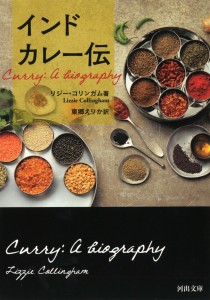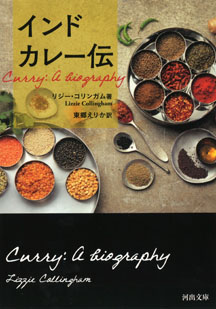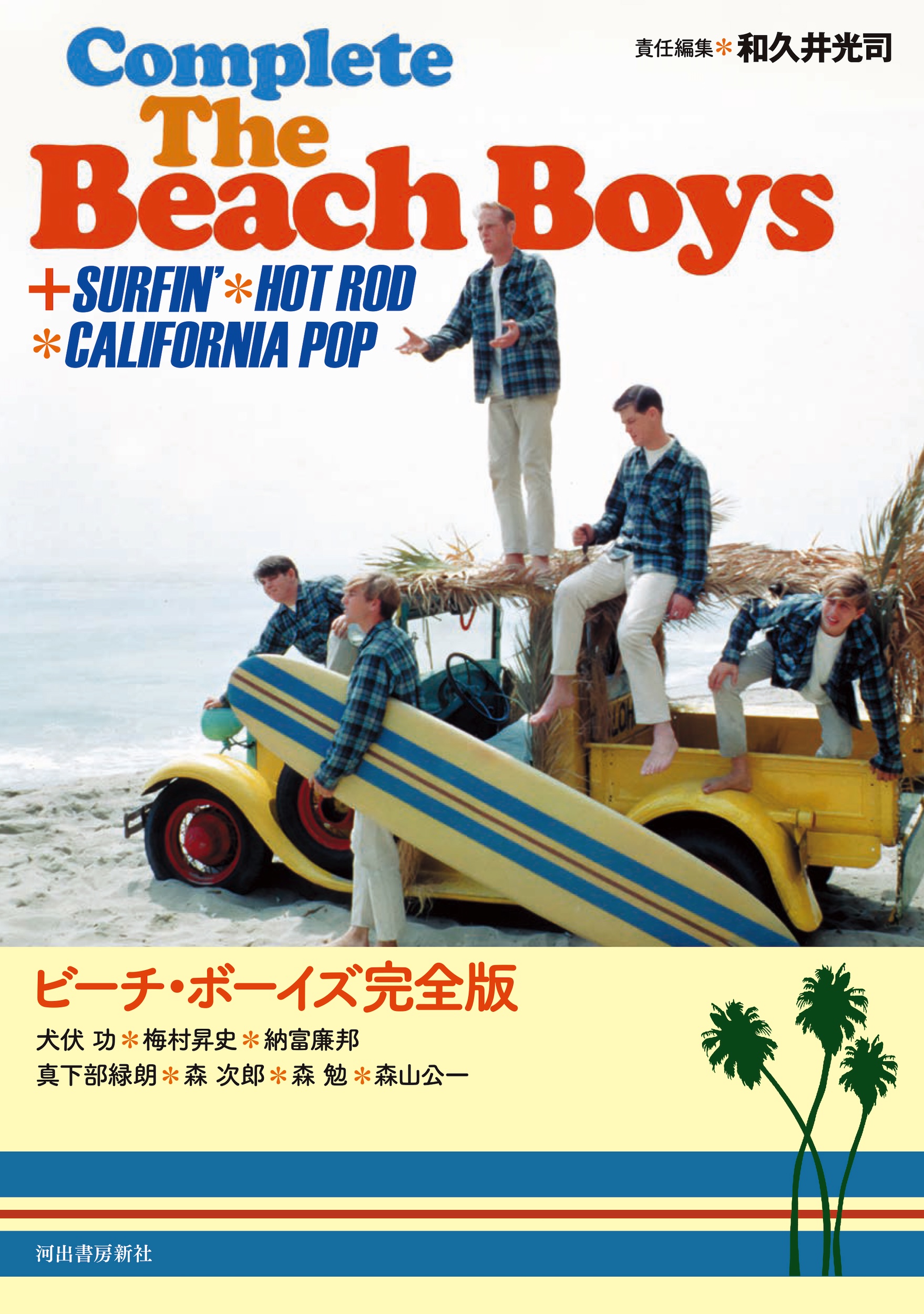文庫 - 随筆・エッセイ
カレーを味わい尽くす!カレーの成り立ちから現代まで400年にわたる華麗なるインド食文化史
【訳者】東郷えりか
2016.04.08
『インドカレー伝』
リジー・コリンガム
【訳者】東郷えりか
日本人はカレーが大好きだ。各種統計によれば、一人当たり週に一回以上は食べている計算になるという。その多くは、肉と野菜をざっと炒めて煮込み、固形ルーを割り入れるだけの、いわばお手軽料理だ。朝からレトルトカレーを食べる人も結構いるらしい。人はなぜこれほどカレーに惹かれるのだろう? 単にそれが手間のかからない料理だからなのか。
カレーがイギリス人を介して日本に入ってきた経緯はよく知られている。「大正時代には、軍は新兵を募集する際に、入隊すればカレーが食べられることを宣伝に使いさえした。当時、カレーにはまだ西洋のオーラが取り巻いており、その魅力で惹きつけたのである」と、本書『インドカレー伝』(原題 Curry a biography)の著者リジー・コリンガム Lizzie Collingham は書いている。当初、カレーがインド料理として伝わっていたら、しかもそれが豆のカレーだったりしたら、これほど国民的な料理になったかどうかは疑わしい。
もちろん、最近は玉ねぎをよく炒め、マンゴー・チャツネやガラム・マサラを加えて、豆のカレーをはじめとしたさまざまなインド風カレーを目指す人も多くなった。ホールスパイスを挽いて本格的なインド料理に挑戦する人だっているだろう。身体によい香辛料をたっぷり使った、菜食中心のインド古来の食文化が注目されはじめたのは、実は近年、インドが発展途上国のイメージを払拭しだし、経済的・政治的な存在感を高めていることと決して無縁ではない。いまやレストランも加工食品業界も、本場インドの味であることを競って「売り」にしはじめている。
しかし、そもそも本場のカレーとは、本物のインド料理とは、いったい何を指すのだろう、と著者コリンガムは疑問を投げかける。唐辛子ですら南米からポルトガル人がもちこんだ食材だし、全インドを代表するような料理も、イギリス統治時代に初めて生まれたものなのだ。
食は生命を維持するための根幹であり、人は食べるものによって無意識のうちに大きな影響を受けている。食材の歴史や料理法が伝播する経緯に、何よりも端的に時代の趨勢が現われていると考えたコリンガムは、ケンブリッジ大学ジーザス・カレッジの特別研究員としてインドの歴史を研究するなかでカレーの本を書こうと思い立った。そして、カレー、およびそれに関連したさまざまな飲食物を切り口に、インド亜大陸の、あまりにも広大で、あまりにも複雑な社会を描こうと試みたものが、本書なのである。インドに関する文献は、耳慣れないカタカナ語が多すぎて、つい読む気が失せてしまうが、インド各地の料理をつくりながら味で覚えていく本書のやり方は画期的だ。
食べ物の違いは、民族・共同体間の対立を生むもとにもなる。インドには浄・不浄の概念が深く根づいており、「紅茶はよく小さい素焼きのカップでだされ、これは使用後、地面で割られてしまう。こうすることで、ほかの人の唾液で汚された器から飲んで、汚される心配がなくなるのだ」という。こうした飲食物をめぐる身体に染み込んだ感覚が、豚肉以外の肉は食べるイスラム教徒と菜食主義のヒンドゥー教徒のあいだの溝を越えがたいものにし、憲法で廃止されても、いまなおカースト制度が社会に残る原因にもなる。
独立後の貧しいインドしか知らないわたしたちの世代にとっては、大航海時代に始まり、イエズス会や東インド会社の時代、大英帝国の植民地時代にいたるまで、何世紀ものあいだ西洋と東洋の接点となったインドを知ることも、大きな発見になるだろう。また、その後の移民社会の変遷への言及は、今日、欧米社会がかかえている移民問題やテロ問題を理解するうえで大いに役立つ。
発見といえば、イギリス統治時代、大英帝国の威信を保とうと、イギリス人が暑いインドで夜会服を着て、「イギリスの料理らしく聞え、そう見える」金属味の缶詰食品を食べていたと知ると、日本人が崇拝してきたイギリス人も、実はこんな人びとだったのだろうかと驚きとともに疑問がわいてくる。
植民地史の研究は、とかく支配者側の負い目や自己弁護、あるいは被支配者側の被害者意識が前面にでやすいが、コリンガムは飽くまで公平な視点で、控えめなユーモアを交えながら双方の立場を描く。何百年も昔にインドを訪れた人が書いた私信や、当時の新聞、雑誌、料理の本等の資料が膨大に残されていること、そしてカレーの研究のために太平洋の島々まで訪ね歩く女性研究者を輩出するところに、イギリスの底力を見た気もした。
考えてみれば、キプリング以外にも、イギリスの児童書にはよくインドが登場した。バーネットの『秘密の花園』の「つむじ曲がりのメアリーさん」はインド生まれだし、ネズビットの『宝さがしの子供たち』には、子供たちがアメリカ原住民の「貧しいインデアン」と勘違いするネイボッブがでてくる。インドの贅沢品を次々に取りだす場面は印象的だった。一時期、黒人差別で問題になった『ちびくろサンボ』も、本当はインドの話だ。著者のヘレン・バナマンは、軍医の夫とともに三〇年間マドラスに住んだ人で、挿絵の壺には確かにギーと書いてあった。本書で紹介されているベビンカと言う菓子は、ゴアのポルトガル人が伝えたレイヤーケーキで、ギーを流し込みながら重ねて焼いていく。虎のバターでつくるホットケーキの原型はこれにちがいないと、わたしは勝手に想像している。
白状すると、わたしはそもそもカレー好きではないし、インドにいったこともない。そんなわたしが、この仕事を通じてすっかりインド料理の魅力にとりつかれ、いまでは弁当に自己流チキンティッカを入れるほどになった。夜のうちに、一口大に切った鶏肉をクミンやコリアンダー入りのヨーグルトに浸けておき、朝、それを竹串に刺して魚用のグリルで焼くのだ。弁当箱は、インド製の二段重ねダッバーだ。疲れているときは、玉ねぎやニンニクをたっぷり入れたカレーをつくる。アーユルヴェーダ医学では、これらの食材が攻撃性を高める〝ラジャシック〟な食べ物に分類されていると知ると、妙に元気がでてくる。イギリスの労働者が好む辛いカレーとビールとフライドポテトという、胸の悪くなりそうな組み合わせが、意外においしいことも知った。自己流のマサラ・チャイも愛飲している。
この仕事のおかげで、うちの食卓だけでなく、わたしの人生も随分豊かになった気がする。これほど奥深く、かつ楽しい本を訳す機会を与えてくださり、料理上手とは言いがたい訳者のいたらぬ点を補ってくださった河出書房新社編集部の新井学さんに、心から感謝したい。(2006年8月)