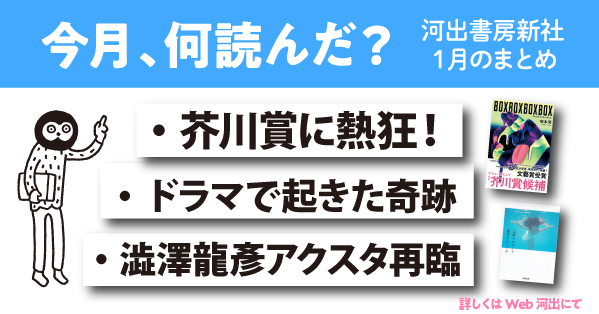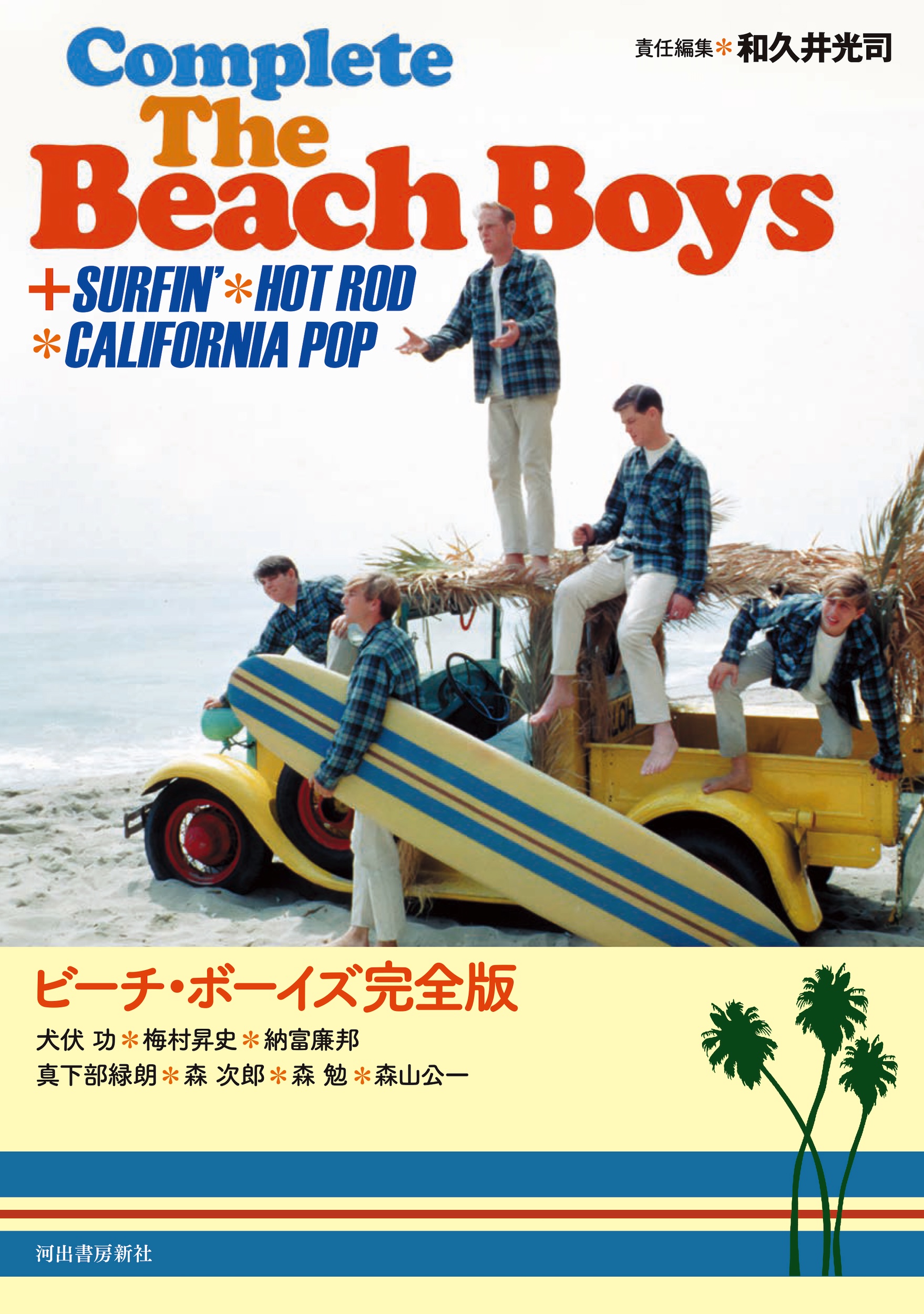特集・コラム他 - 記事
座談会「12年経った今だからこそ、消化できたものがある」 坂元裕二『それでも、生きてゆく』刊行記念 巻末座談会公開!(抜粋・前編)
坂元裕二
2023.12.28
2023年5月、映画「怪物」(監督・是枝裕和)で第76回カンヌ国際映画祭脚本賞を受賞、11月に配信開始となったNetflix映画「クレイジークルーズ」も話題の脚本家・坂元裕二さん。
かつて坂元さんが「特別」なキャスト、スタッフと作り上げ、「愛着がある」作品と振り返る「それでも、生きてゆく」(2011年、フジテレビ)は、永山瑛太さん演じる7歳の妹を殺された兄・深見洋貴と、満島ひかりさん演じるその少女を殺害した文哉の妹・遠山(三崎)双葉が、事件から15年後に出会い、次第に惹かれあっていく姿を中心に展開する連続ドラマ。放送から12年経った今も視聴者の記憶に残り続ける傑作です。
本作のシナリオブック『それでも、生きてゆく』の発売を記念して、坂元裕二さん、プロデューサー・石井浩二さん、演出・永山耕三さん、主演の永山瑛太さん、満島ひかりさんが12年ぶりに集結し、特別座談会が実現しました(司会・上田智子さん)。
被害者遺族と加害者家族というテーマの難しさに加え、東日本大震災直後の制作という緊張感の中で真摯に制作され、放送されたこのドラマを振り返った座談会より、脚本執筆時の苦悩や、撮影時は「ドキュメンタリー」のようだった、と語る主演お二人の話などを一部抜粋、再編集してお届けします。
3時間を超える第1話の脚本の初稿
上田智子(以降、上田):完パケ(編集が完了し、ドラマを放送できる状態にしたもの)を初めて見た時のことを坂元さんにお聞きしたいんですが。
坂元裕二(以降、坂元):今まで書いたドラマの中で、第1話の初稿が一番長かったのが「それでも、生きてゆく」(以降、「それでも」)です。そのまま撮影すると3時間近くあったと思います。
なぜかというと、亜季(※7歳で殺された洋貴の妹)の事件の日の状況がわからないから、あの日起きただろう出来事──それこそ朝、響子(亜季の母・大竹しのぶ)が家を出て美容室に出勤するシーンとか、達彦(亜季の父・柄本明)が朝から何をしていたのか、亜季がどこに行ってどのように事件に遭ったのか、そして空に凧が見えて……と、最初から全部順番に書いていたからなんです。
「Mother」(2010年、日本テレビ)の頃までは、シーンが始まったらお話がちゃんと始まってたんですよ。
でも「それでも」は物語の状況が僕にもまったく分からないからとにかく手探りで。何も起きていない状態から書いていかないと本筋にたどり着けないので、例えばファミレスに入って注文して、少し雑談して、そして本題に入って、その後また店から出ていくとか、本来なら必要ない部分も含めて一連の動きをどのシーンでも全部書いた。そうして出来上がった3時間くらいの脚本を1時間ちょっとに縮めていきました。
最初は、落とすことになったシーンがない状態でちゃんと伝わるのかどうか心配だったんですけど、完パケを見て、演者とスタッフの皆さんのお力で物語がちゃんと生きている、伝わるものになっているってわかりました。
第1話以降も、たしか最終話まで、その日起きたことを全部書くっていうシステムは続けたと思うんですけど、決定稿では落としたシーンが、出来上がってきた映像にちゃんと残っているのをすごく感じて、それが面白かった。
洋貴と双葉が初めて出会うシーンも、どうすればいいのかわからなかったから、「……あ」「え?」「や……」というやり取りをわからないままに書いてたんですね。
でもお二人が演じているのを見て、わかったんです。書いていても見えなかったものが、お芝居によって見えてくるんだということにこの第1話で気づけた。
ちなみに、「それでも」を書くに当たって最初に決めていたのは、後半はラブストーリーをやろうということだけだったんですが、第5話の完パケで洋貴と双葉が話している姿を見て、「あ、これは最終回で二人がハグするまでのお話だ、そこまで行くことが素晴らしいんだ」と思い当たったんですよね。
第1話のラストで瑛太さんがどんな顔をしているかがわからないと、あの役が何を背負っているのか僕にも見えてこなかったし、そうやって、上がってきた映像から僕自身に返ってくるものがたくさんあったんですよ。
上田:以前坂元さんにインタビューさせていただいた時、「それでも」は自分の文体が見つかったドラマだとおっしゃっていました。お話しに出た「……あ」「え?」「や……」のやり取りのように、ふつうの会話はつっかえたりするものですが、脚本にもその通りに書かれていて、お二人もとても自然に演じられていました。それを坂元さんがまたご覧になって、次の脚本に生かされて、と、まるで手紙のやり取りのように共同作業で作っていかれたんですね。
坂元:本当にそうですね。脚本が上がって映像が上がって、というキャッチボールにそんなにタイムラグがなかったんです。当時は映像の上がりを待って書いても問題なく間に合うくらい速く書けたということもあります。今はそんなに速く書けないから、映像を待っちゃうと返せなくなっちゃうんですけど(笑)。
役を演じるというより、ドキュメンタリーだった
上田:満島さんは、話題に上がった「……あ」「え?」「や……」みたいなセリフを脚本でご覧になってどう思われましたか?
満島ひかり(以降、満島):今思うと、たぶんあの頃は必死に「書いてあることを生きられるか」不安だったし夢中だったんだと思います。読んでるうちにのめり込んで、自分の体が双葉になっているから、脚本がどうとかじゃなくてドキュメンタリーをやっている感覚になるというか。
支度したり思考したりもするけれど、脚本を読んで覚えるよりも、双葉のドキュメントが描かれているように体が反応していました。
だから、第7話で文哉(双葉の兄・風間俊介)が再犯した時に双葉として怒ってしまって、「なんで再犯する話を書くのか、本当に嫌だ、もう信じられない」って、フジテレビの廊下のベンチで、文哉に当たるかのようにプロデューサーの石井さんに当たったこと、よく覚えています(笑)。
一同:(笑)
石井浩二(以降、石井):そうでした、「双葉はこれ以上背負えない!」っておっしゃってましたね。
永山耕三(以降、永山):こういう話を、ドラマ放送直後の12年前にするのと、12年経った今するのとでは相当違うと思うんだよね。
満島:そうですね。
永山:今だからやっと消化できたこともあるし、まだ消化しきれていないものもあるんですよね。撮影していた僕自身、第1話と第2話はどうだったんだろう、よかったんだろうかと今でも思う。
でもきっと12年前に話していたら、終わったばかりの勢いで「これで良かったんですよ」って言い切れちゃうんだろうな。時間が経てば経つほど、これでよかったんだろうかって考えるようになってきますね。
上田:先ほど満島さんがドキュメンタリーだったとおっしゃってましたけど、瑛太さんはいかがでしたか?
永山瑛太(以降、瑛太):僕も、同じようなことが起きていたと思います。響子の第5話の長台詞(※娘を亡くして15年経ち、初めて母としての本当の思いを吐露するシーン)も、それを聞いて洋貴が涙するなんて脚本にはどこにも書かれてないんですけど、僕はあの長台詞を聞くたびに何度でも涙が出てきてしまったんですよね。芝居じゃなくなっちゃってたんですよ、もう。
ドラマが終わってしばらくたった頃、たまたまあのシーンがYoutubeから流れてきたことがあって。
一同:(笑)
瑛太:「そうだ、こんなことあったな」って思い出しながら流れてきちゃったシーンを見てたら、気づいたらやっぱり泣いていて。
このシーンを撮影した時の感覚は覚えているんですけど、芝居じゃなくて音というか、響子を演じた大竹しのぶさんが発しているものによって生まれてくるイメージがあったんです。
それまでまったく知らなかった響子の本心に、洋貴もあのシーンで初めて直面したんですよね。あれは何度聞いても新鮮というか、お芝居じゃなくて常に初めて聞いた話のように感じる。
嘘のないエンターテインメント
永山:特に意識はしてないけれど放送できるものを作りたいっていう感覚はありましたよね。
例えば、痛い題材を扱ってる瞬間は、それがセリフとしては出てきても映像には映すまいとかね、テレビ的と言われると全くその通りですね。
そういえば、さっき話に出ていた第5話の響子の長台詞、本当はもっととんでもなく長かったんですよね。
坂元:たしか、あの倍はありましたね。
一同:(笑)
坂元:あの長台詞は「よし書くぞ」って決めて、ファイルも別に作って、物語から一旦離れてそのことだけに集中したんですよ。亜季が殺害された場所に響子が行くじゃないですか。その日の気持ちを全部書いてたんですよ、やっぱり時系列で。
その日あった出来事を一から順にという書き方は、それまでの作品ではしてなかったんです。人が、しかも子供が死ぬところから始まる物語だからということもあるし、第3話以降ですけど、やっぱり東日本大震災があったこともすごく大きくて。自分の中に緊張感があったんでしょうね。
僕の中にもポップさというかエンターテインメント性があって、放っておくと面白い方に流れていくことがある。そのエンターテインメント性をなくそうとは思わないけど、できるだけ噓はつかないようにしようとは思いました。
満島さんがドキュメンタリーだったって言ってたけど、まさに僕もキャラクターのその時その時を自分の中で再現しながら書いてたんですよね。現実世界では震災をきっかけにさまざまなことが起こっていて、気を緩めることができなかった。
ドキュメンタリーとポップさの境目を意識していたわけではないけれど、どちらかに行きすぎないように無意識下で気をつけていたんだと思います。