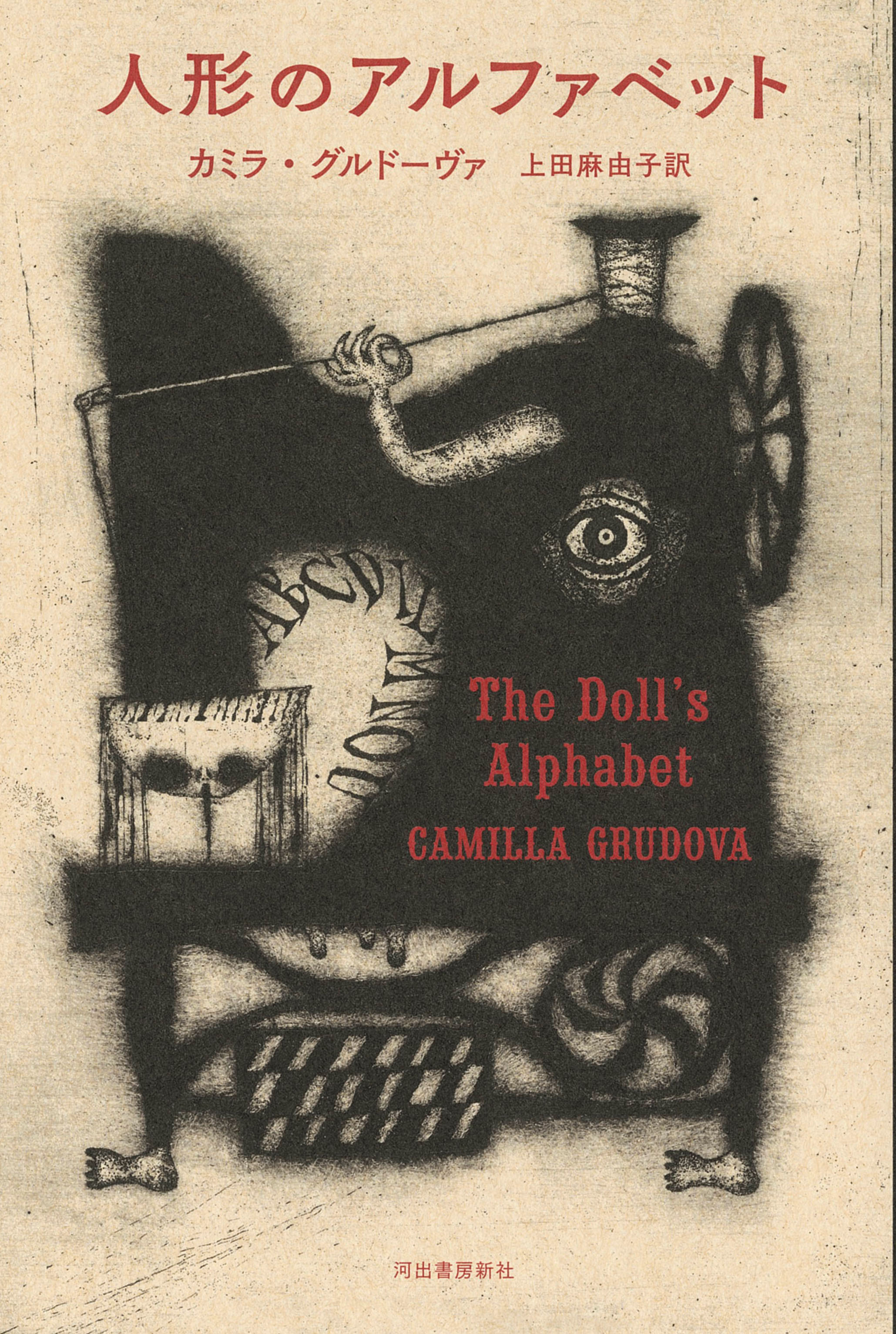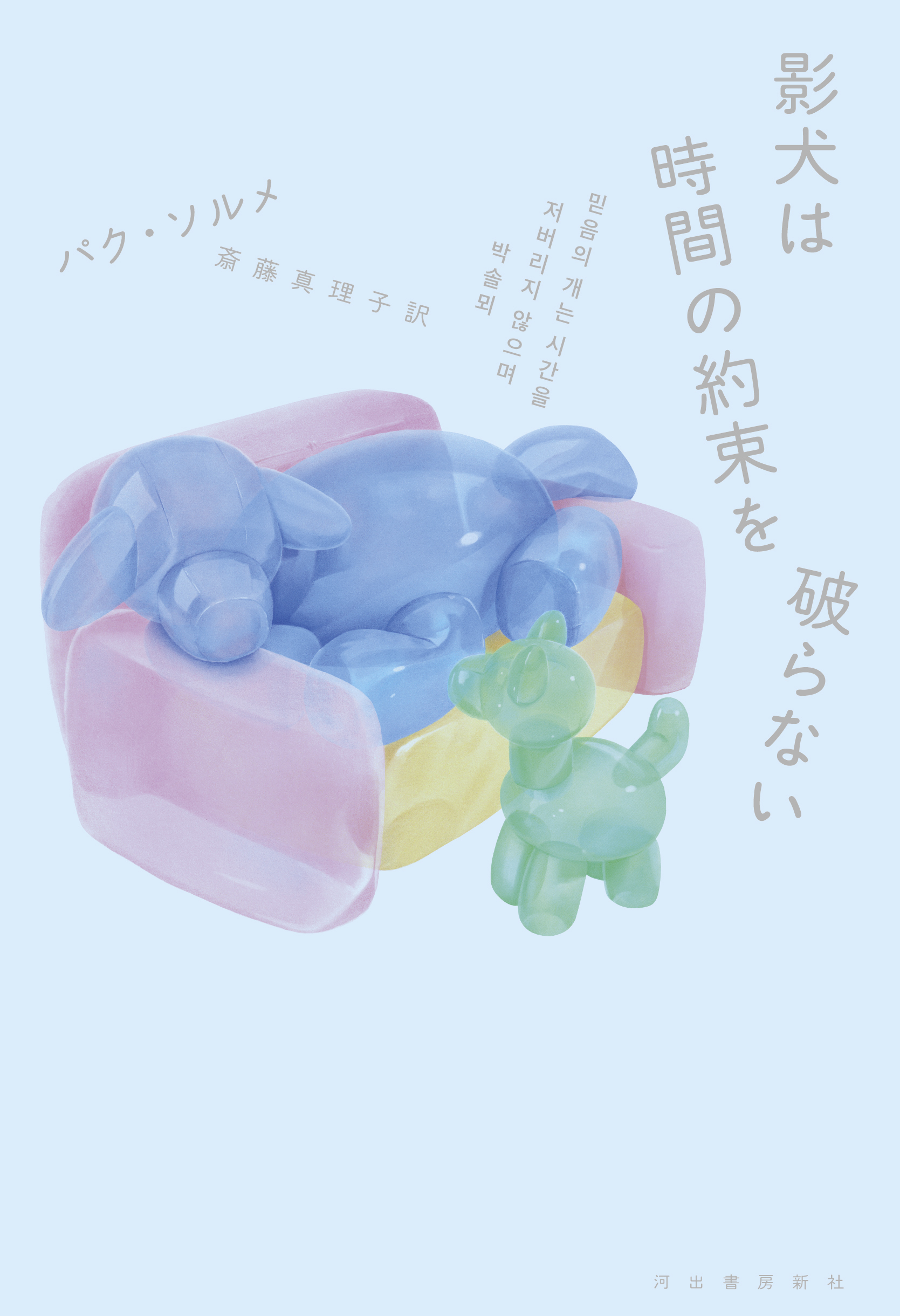書評 - 文藝
話の通じない「おじさん」との結婚生活でボロボロに…会社と家の往復でいいと思っている45歳バツイチ女性を描いた金原ひとみのエンタメ小説
評者:高瀬隼子(作家)
2024.11.19
金原ひとみ 著
評: 高瀬隼子(作家)
平木直理(ひらきなおり)がヒーローだった。登場した時は正直警戒した。スケボーで通勤し、転んで捻挫したことを理由に在宅勤務を希望する入社五年目の編集者ってやばいやつでしょと思った。平木は確かに破天荒だが、読み進めて行くうち魅力にぞっこんになる。対して、浜野文乃(はまのあやの)にはシンパシーを感じやすい。四十五歳、ルーティンで簡潔な生活を良しとし、昼休み終わりに数分遅れるだけで怯んでしまう。うんうん分かる。そんな浜野が本作の主人公だ。
浜野は、離婚した元夫に〈結婚生活の中で、数限りある希望を、私の心に咲く数少ない花を、ケンケンパみたいに遊び感覚で全部踏み潰されていった〉過去があるのだが、この元夫の人物造形がすごい。デフォルトマンとして生きてきた男の、表面的には現代的な価値観を持っているふうでありながら、他者を踏みつける権利が自分にはあるという確信が内面化された様態に唸った。作中では不妊治療の経験が語られるのだが、それがなくとも(妊娠出産できていた場合の子育てを想像するとぞっとする)、ケンケンパで遊ぶように人の心を散らしていく在り様はいつか発現しただろう。
心の花を根こそぎ踏み潰された浜野は、平穏なルーティン生活を守っていたが、第一イレギュラーである平木直理を通じて、第二イレギュラーのかさましまさかに出会い、〈お付き合いしていませんという体の、お付き合い〉を始め、〈誰かと生きていくという方向にシフトし直す〉。まさかとパートナーシップを築く中で、浜野は自身の過去、定期的に起こる不安の発作、他者に付けられた傷がまだありありと残っていることに向き合い、人間として再生していく。
わたしもしばしば考える。一人でもいいじゃん、波風立てずに、自分の人生においてさえモブだとしても、平穏に勝る幸せなんてないんだから、と。それは誰にも責められ得ない自己防衛だ。話の通じない「おじさん」との結婚生活でぼろぼろになった浜野が、他者の声に耳を傾けられるかさましまさかと関わり、自分の言葉を差し出す勇気を持つ時、人間として生き直し始める。この紛れもない希望の物語を、よかったね、浜野さん……と祝福の気持ちで読んだ。自分にはないかもしれないけれど、同じ世界に生きる誰かにはこんな幸福が起きてほしいと思った。わたしが自分ごととして羨んだのは、平木直理との出会いの方だ。
雑草すら生えない一面の土っ原を想像する。花はないが、別にこのままでもいいと思う。見晴らしがいいから安全だし、雨が降ってもすぐに乾く。悪くない。けれどふいに耳を澄ませて待つ。スケボーのローラー音を響かせて、この土っ原にまっすぐ、突っ込んで来てくれる誰かを。〈私は唯一無二の平木直理だし、それはもう誰よりも素敵なんですけど〉と言い切る彼女に、どうしたって憧れる。この本を手にしたわたしたちは、物語を通して平木直理と出会った。スケボーの細い轍で、花の種が芽吹く。開いた花を恐る恐る守ろうとする時、勇気を持って、ルーティンから半歩踏み出せる。