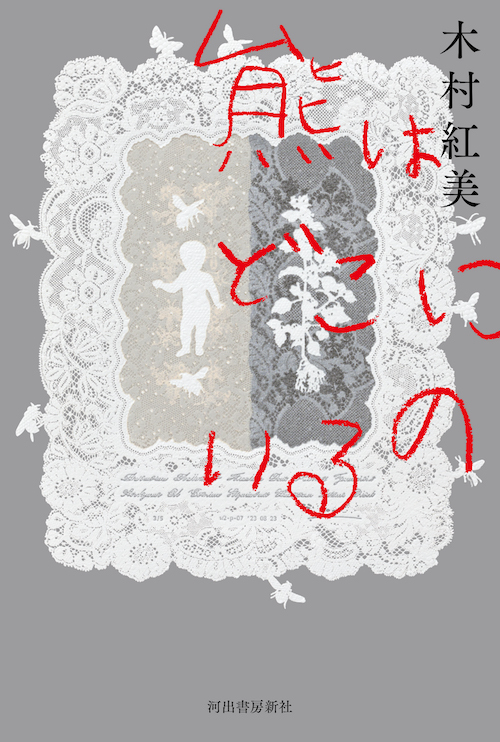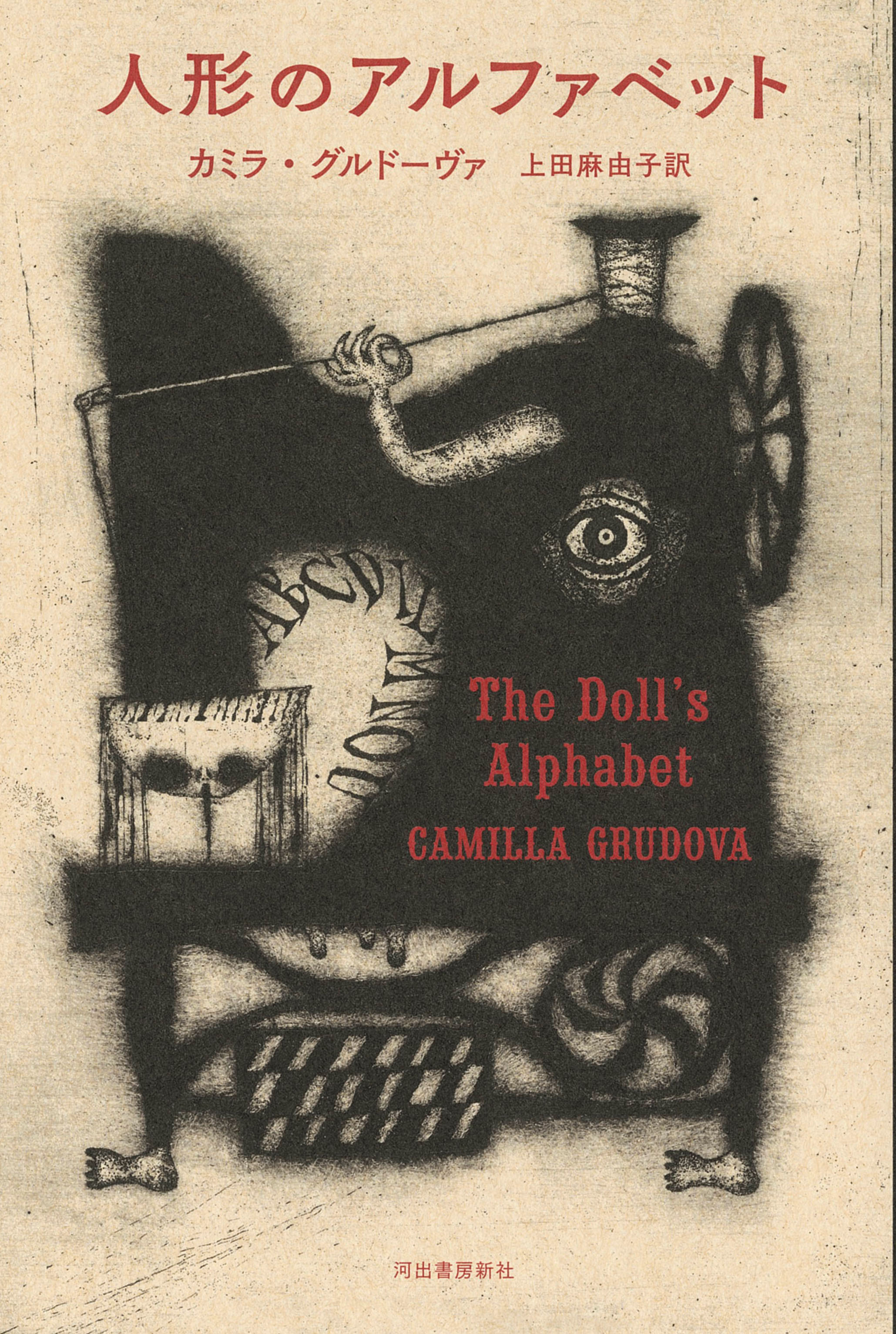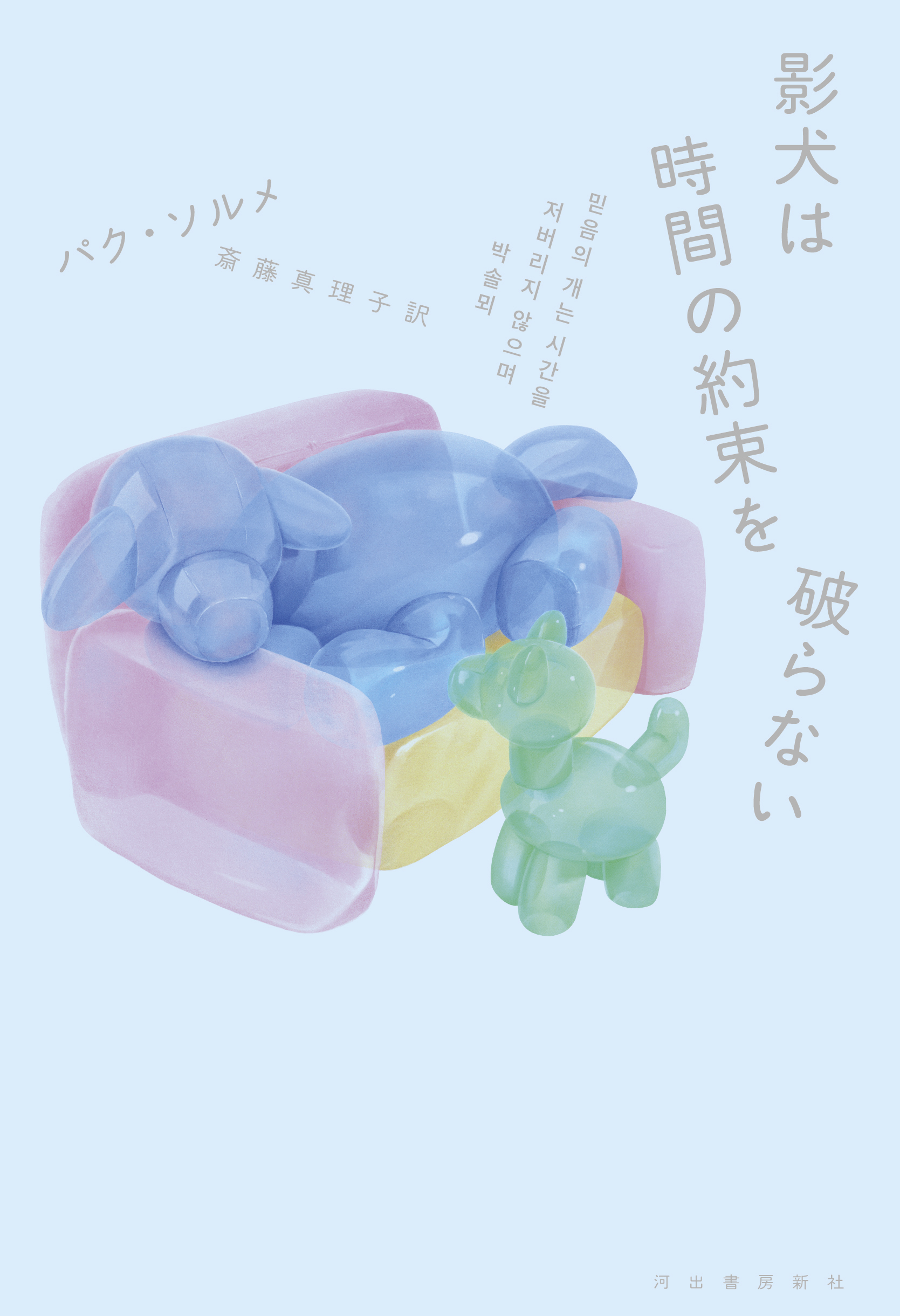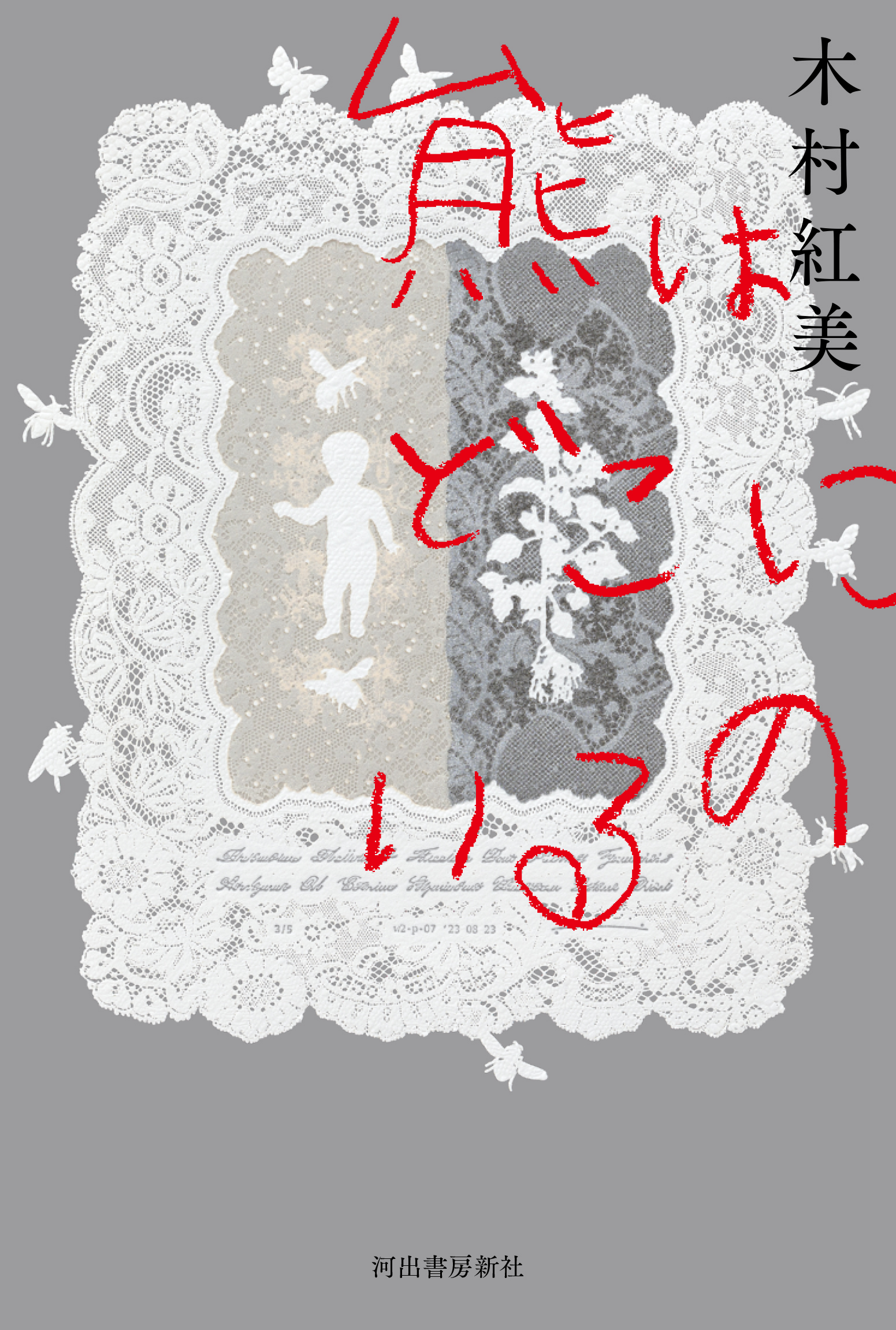
書評 - 文藝
暴力から逃れ、山奥の家で暮らす女性たちが身元不明の幼子を育てる…作家・木村紅美の小説『熊はどこにいるの』の読みどころ
評者:はらだ有彩(テキストレーター)
2025.02.20
『熊はどこにいるの』
木村紅美 著
評:はらだ有彩(テキストレーター)
独創的な小説世界で注目される作家・木村紅美による最新作『熊はどこにいるの』が刊行。
本作の魅力をテキストレーターのはらだ有彩さんが語る。
***
先日、薬局で順番を待っていると怒鳴り声が聞こえた。高齢の二人連れが会計を済ませて出て行こうとしているところで、片方がもう片方を詰っていた。「しょうもないこと聞かんでええねん。お前は阿呆なんやから黙っとけ。」はい、すみません、という謝罪の途中で自動ドアは素早く閉じた。あまりにも一瞬の出来事で、その場にいた誰もが何もできなかった。
本作に登場するリツは、「あらゆる暴力から逃げてきた女たちを匿」う丘のうえの家で暮らしている。幼い頃のトラウマから男性全般に嫌悪感を抱くリツをはじめ、入居者たちによって、家には「男性」は入れないルールが敷かれている。家の創設者フミ先生と、離婚して困窮に陥り丘へ身を寄せた妹分のアイ。それから、アイがある夜に拾ってきた「男の」赤ちゃん。一方で、丘から少し離れた町で赤ちゃんくらいの大きさの荷物を抱えたサキと、サキに車を出すように頼まれるよそもののヒロ。リツとアイは折り合いが悪く、女だけの生活は決して楽園ではない。
「女たち」は、自分たちが押し付けられ苦しんだはずの固定観念を少なからず内面化している。ユキと名付けた赤ちゃんを「男の子らしく」育てないために、「ワンピース」を着せる。フランス人形のようにしておきたいと考える。ユキにあなたは男の子なのだと繰り返す。この子がどう育ってもいいように、と言いながら、お前は男の子なのだというまなざしを向け続ける。
外には熊がいるから危ないと「女たち」はユキに教える。熊の危険性を説くのは「女たち」だけだ。テレビの中では、熊は憎めないキャラクターとして描かれる。丘のうえの家は、加害され、加害され、ようやく逃げてきた「女たち」にとって唯一生きられる場所でもある。そして同時に、加害の温床ともなりうる。新たに丘にたどり着いた「女たち」に、リツは家父長制の代表格のような態度を取ったりもする。
リツ、アイ、フミ、サキ、ヒロ、ユキ、と情報を削ぎ落された名前はいっそ匿名のようでもある。物語は「女たち」それぞれの視点で、会話も事実も想像も地続きに、断続的に語られる。誰かが少し話しては、また別の誰かが話す。誰もが自分の考えを話す。だから誰も客観的ではいられない。彼女たちのしたことを、客観的に裁く人物は登場しない。罪を暴き、加害を証明し、罰する人はいない。彼女たちに対して犯された罪を暴き、加害を証明し、罰する人が誰もいないように。
では誰がいるのだろう。熊はどこにいるのだろう。「どこにいるの」という日本語は、一般的には小さな子供や女性のキャラクターの話し言葉としてしばしば使われる。熊がどこにいるのか分からないまま、それでも確実にいるのだということに怯え、探し続ける人。熊がこの世にいることさえ知らず、あるいはそんなもののいない遠い町へ行くことができ、自分がなぜ熊と呼ばれるのか理解しないまま生きて死んでいく人。どんな人が、どんな人に問いかけるべき言葉なのだろう。もう既に私たちに向かって放たれ、聞かなかったことにする術がこの世の誰にも与えられていない、この質問は。