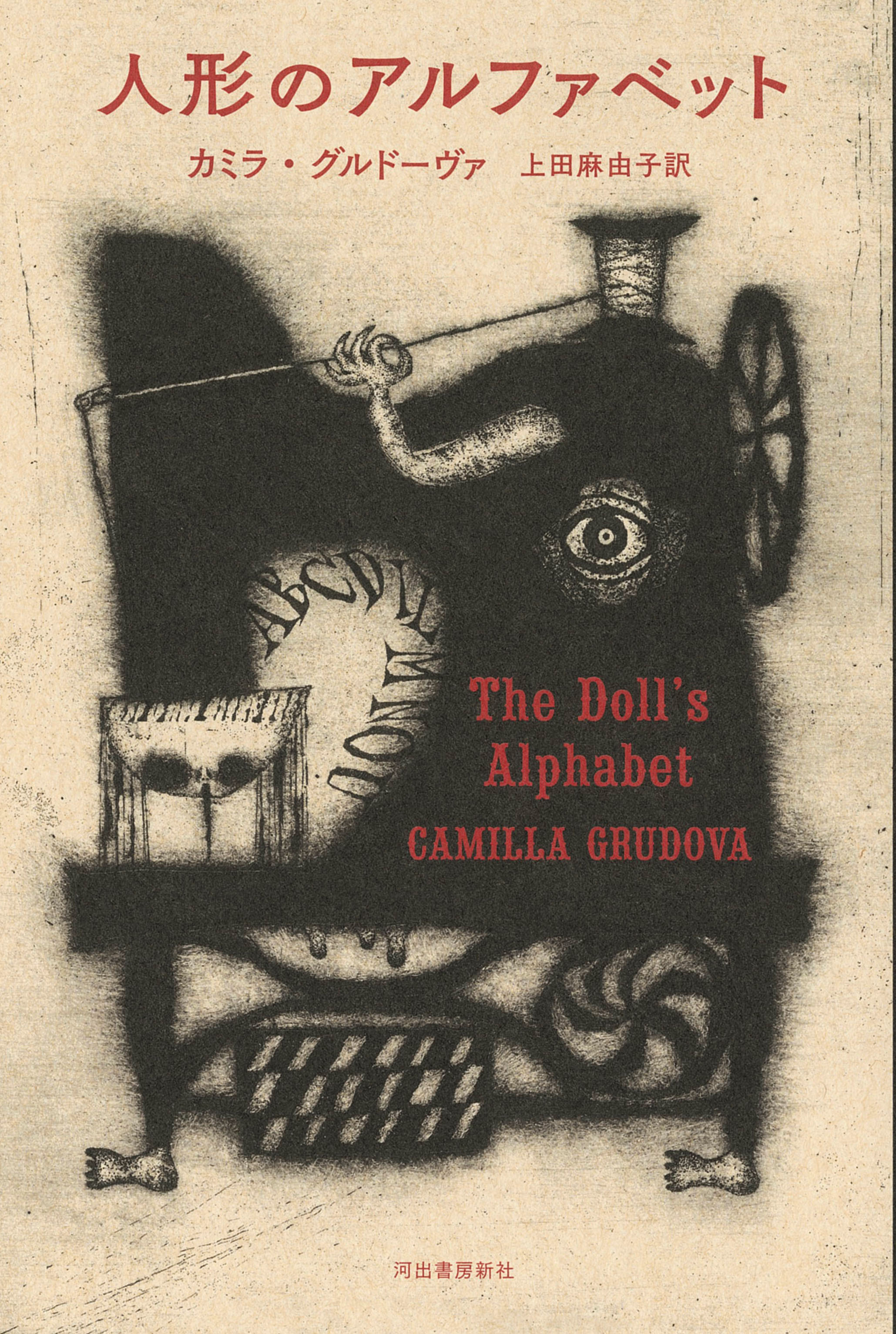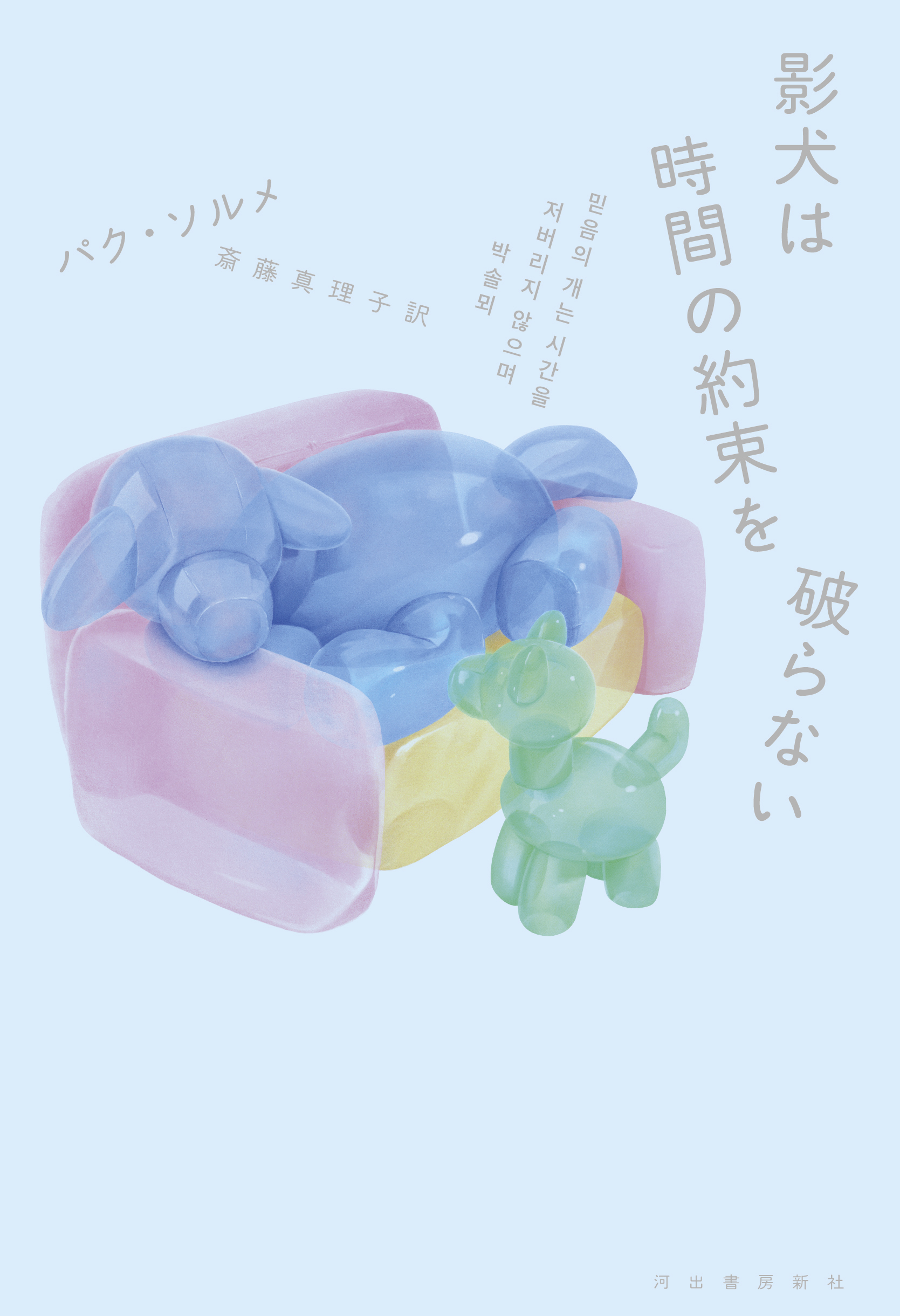書評 - 文藝
新時代の「父」小説!滝口悠生の新刊『たのしい保育園』忘れてしまう「育児」の一瞬一瞬をとんでもない解像度で描く短篇集(評者:東直子)
評者:東直子(歌人・作家)
2025.05.16
『たのしい保育園』
滝口悠生 著
評:東直子(歌人・作家)
芥川賞作家・滝口悠生、初めての「父」小説となる最新刊『たのしい保育園』が刊行。
本作の魅力を歌人で作家の東直子さんが語る。
***
こんなに不穏な世の中だけど、子どもはそんなことはなんにも知らずに生まれてくる。両親をはじめ周囲の大人たちは不穏な気配を感じつつ、無力な子どもたちを懸命に守り、社会生活を送りながら育てていく。当たり前のようで、とても特別なことでもある、ということを、じっくりゆっくり新しく感じさせてくれる連作短編集である。
収載されている六編はいずれも「ももちゃん」という子どもを育てている父親の目線を中心に描かれている。冒頭の「緑色」は、徒歩十分ほどの保育園に二歳児を預けにいくその行程だけで一本の短編となったものである。「お母さんがよかった」と、抱っこしている父親から逃れようと体をつっぱねて拒否する子と、それをなんとかなだめながら保育園へ向かおうとする父親。その様子を「遠目には組体操というよりはフィギュアスケートのペアみたいな格好に見えなくもない」といった具合に、その都度の状況を絶妙な言語表現で味わいつつ、彼らに流れる時間を細密に追体験していくことができる。
子どもの時間の体感は、大人よりもずっと長いということはよく言われることだが、それを解像度高く再現している。子どもを見つめる主体が、母親だったり、通りすがりの近所の人だったりと、ゆるやかに変化しつつ、芯となる一人の赤ん坊の安堵へと収斂していくなめらかな筆致に、胸をやわらかく耕されたような感慨を覚えた。
私もかつて、子どもを産み、育てたことがある。核家族で専業主婦をしていたので、夫が仕事に出ていったあとは、ゼロ歳児と一歳児の二人を一人でふらふらになりながら面倒を見ていた。あの時間の長かったことの本質を今改めて知ったようだった。長く感じた時間の中で、気持ちは激しく揺れ、思考も巡らした。私はそれをいくつかの短歌として書き残していたが、ほとんどの感情も考えも消えてしまった。しかし作者の滝口さんは、一人の親として現実に子育てをしている経験を色濃く反映し、「ももちゃん」という子どもの成長を通じて人々の変化を繊細に書き留め、豊かな示唆を与えてくれる。
時期的にコロナ禍での育児が描かれているが、どんな状況でも子どもたちへの純粋な敬意が込められ、見守る人々の自然な思いやりが端々に感じられて気持ちがいい。
《小さな子どもと一緒にいると、いつもどこか遠くからその日その日を眺めているひとがいて、そのひとに何事かを語りかけられながらその日々を過ごしているような感じがももちゃんのお父さんにはあった》
これは紛れもなく小説家の視点だと思う。目の前の子どもと向き合いつつ、その二人の姿を俯瞰し、客観的に捉えて言語化する視点が「そのひとに何事かを語りかけ」ていることだといえる。同時に、大人の計り知れない所へ想像を広げる子どもたちの遠い視点に寄り添える人の感覚でもある。それをこんなにも濃密に描いた小説は、他にないだろう。