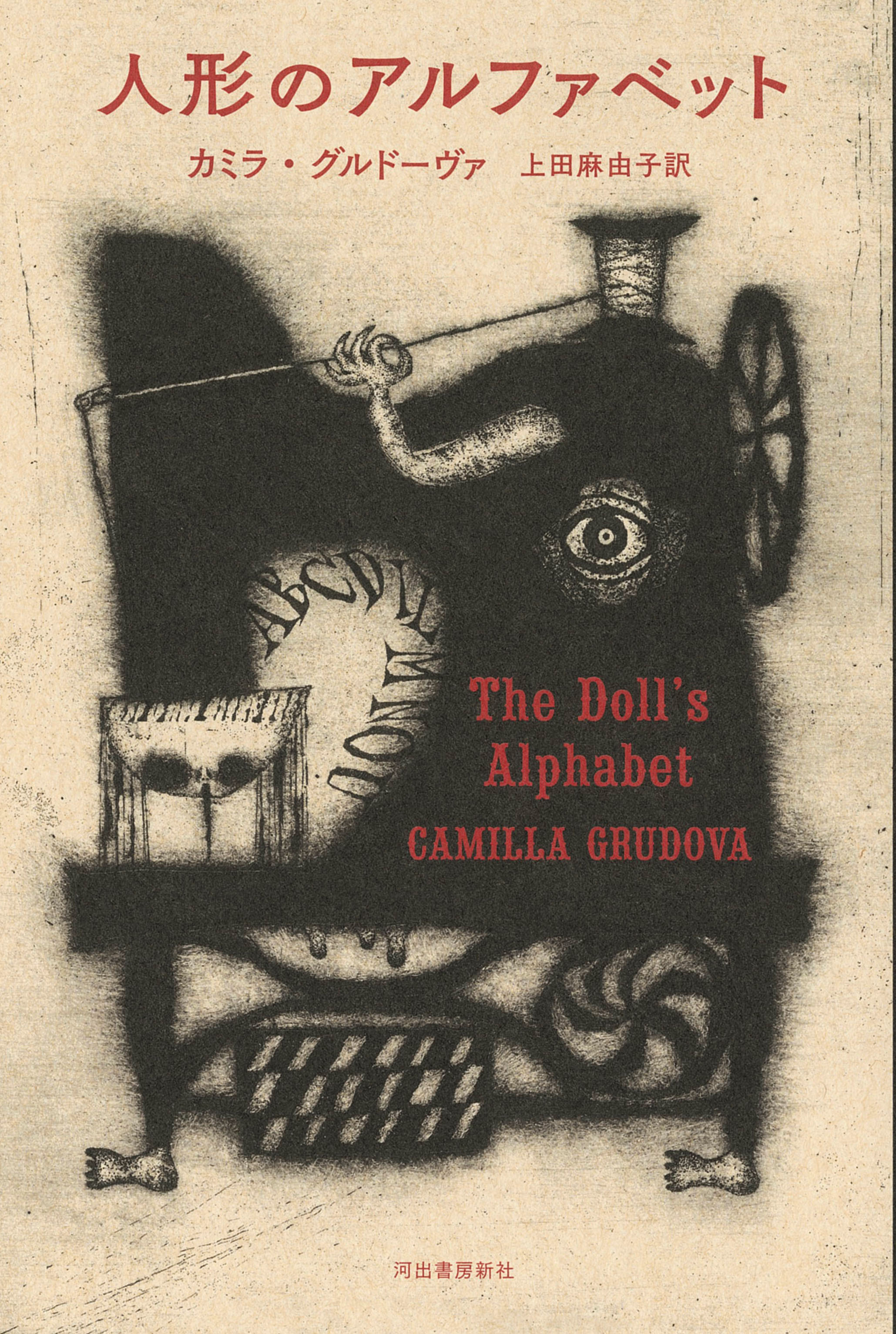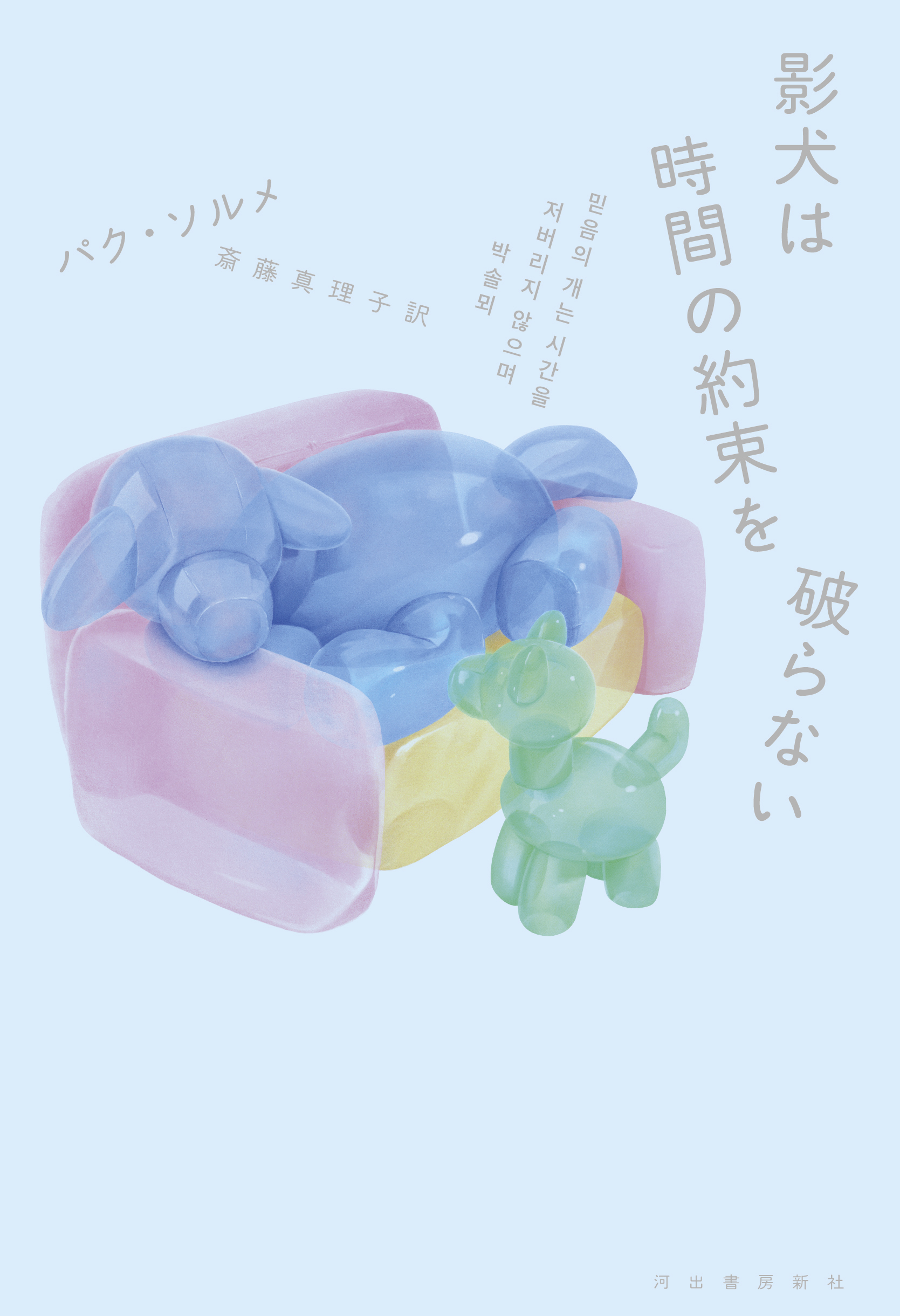書評 - 文藝
芥川賞作家・山下澄人の新たな到達点、異次元の冒険譚『わたしハ強ク・歌ウ』書評(評者:小森はるか)
評者:小森はるか(映像作家)
2025.05.19
山下澄人 著
評:小森はるか(映像作家)
執筆開始から4年をかけた山下澄人の最新小説『わたしハ強ク・歌ウ』が刊行。
本作の魅力を映像作家の小森はるかさんが語る。
***
日々は、生きている限り過ぎていく。その日、その瞬間の忘れたくない出来事や感情。すべてを覚えていることはできないが、できる限り覚えていたいという欲望や、忘れてはならないという切実さに動かされ、私は記録することがほとんどだ。しかし日々が過ぎていくうちに、ひたすら溜まって、膨大になって。人生が終わりを迎える時には、必然と、手放さなければいけなくなるものたちでもある。見返されることのないまま行き場のなくなった、記録物たちの運命について、この物語はノートと呼ばれる日記を書き写しながら書く、主人公ネルを頼りに思い馳せることになる。
ネルは、書き綴られた他者の日々を読むことが好きな人であった。『アンネの日記』と、母の日記と、母の父の日記が書き写されながら、ネル自身の旅の記録が編まれていく。日記を書く理由は人それぞれにあるが、どんな日記にも、紙に残された秘密の話は、誰かに読まれる日が来ることを待っている、という性格を持ってしまうものであると思う。アンネ・フランクがそうしたように、この物語の登場人物たちはカタカナの仮名(かめい)になっていて、仮名にする必要があるということは、やはり誰かに読まれるのをどこかで望んでいる日記たちだったのだろう。その書き方をネルも引き継いで書いているので、誰がいて、今はどこなのか、目線や時空が複雑に入り組んだ日記となっている。ネルによって何が記録されたのかを掴みたい気持ちで読んでいたが、「読めるより理解の方が大きな顔をしている」という一文に出会い、読み方を間違えていたのかもしれないとハッとした。
何が書かれているのかという理解よりも、「読める」あるいは「残されている」という事実の方へ目を向けたいと思えて、気づいたことがある。ネルの母は、溜まり続ける日記を間引くように捨てていた。古いものから処分するのではなく、また大事なものを残すのでもなく、ランダムに行うようにしていた。だから、母の旅の日記が残されていたのは偶然で、しかしネルにとっては、旅という身体の移動を重ねなければ、繋がることのできない家族とのコミュニケーションがあったように感じる。アンネは日記をキティーと名付け、友達のキティーへの手紙として日記を綴ったそうだ。日記自体が、人生の隣を歩き続けてくれる他者になりえるのだと、ネルは『アンネの日記』から学んでいて、アンネとキティーのような関係を母に対して欲していたのかもしれない。書き写したり、旅をしたりすることで。
どんな旅をしたのか、読み手によって胸に残るものは一致しないだろう。旅の断片に秘密にしていた過去があった。母の故郷には海があった。ガソリンスタンドがあり、回転寿司があった。そこは地震と原発事故がありコロナ禍を経験した日本であった。猫のごえもんだけはひらがなの仮名であった。現れる読み手によって、写され、消され、翻訳され、上書きされ、日記はまた別の誰かの人生の隣で生き続けている。