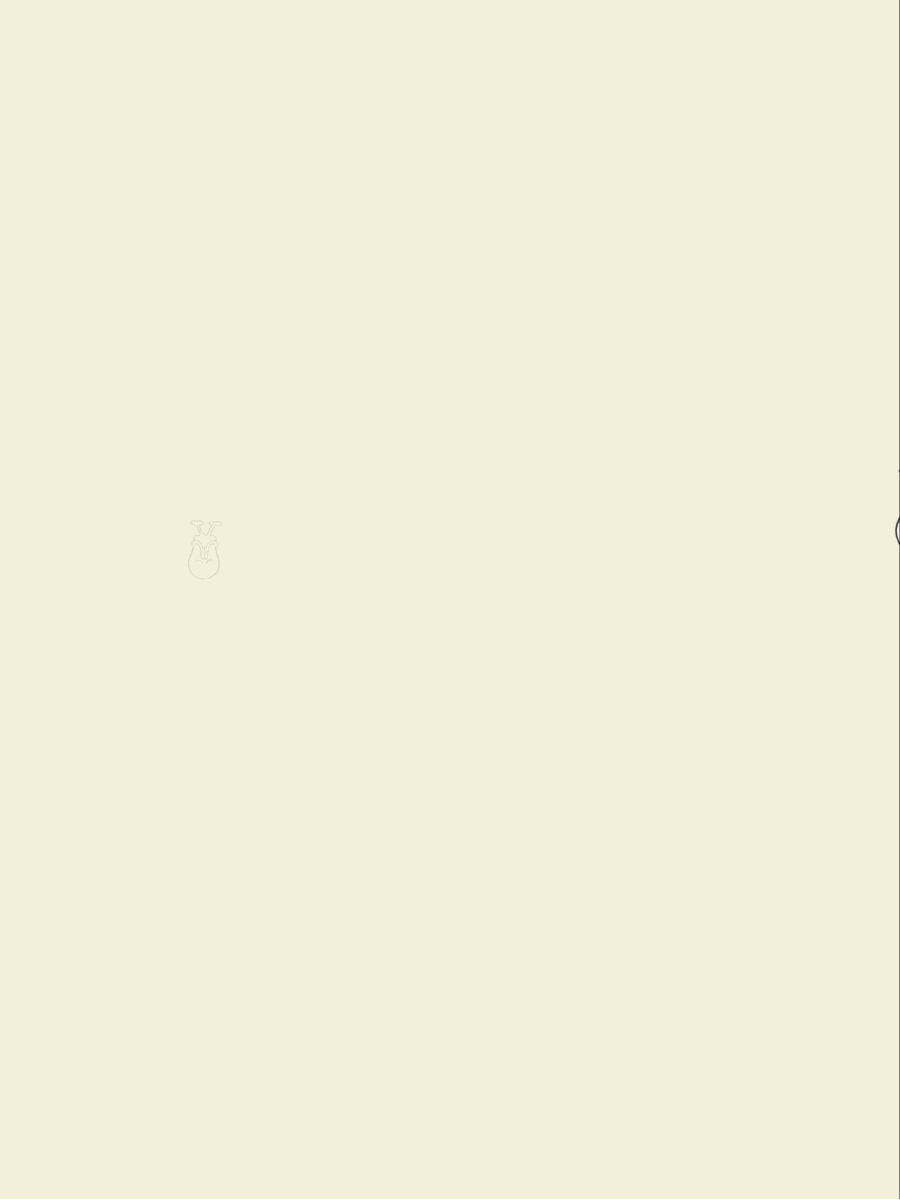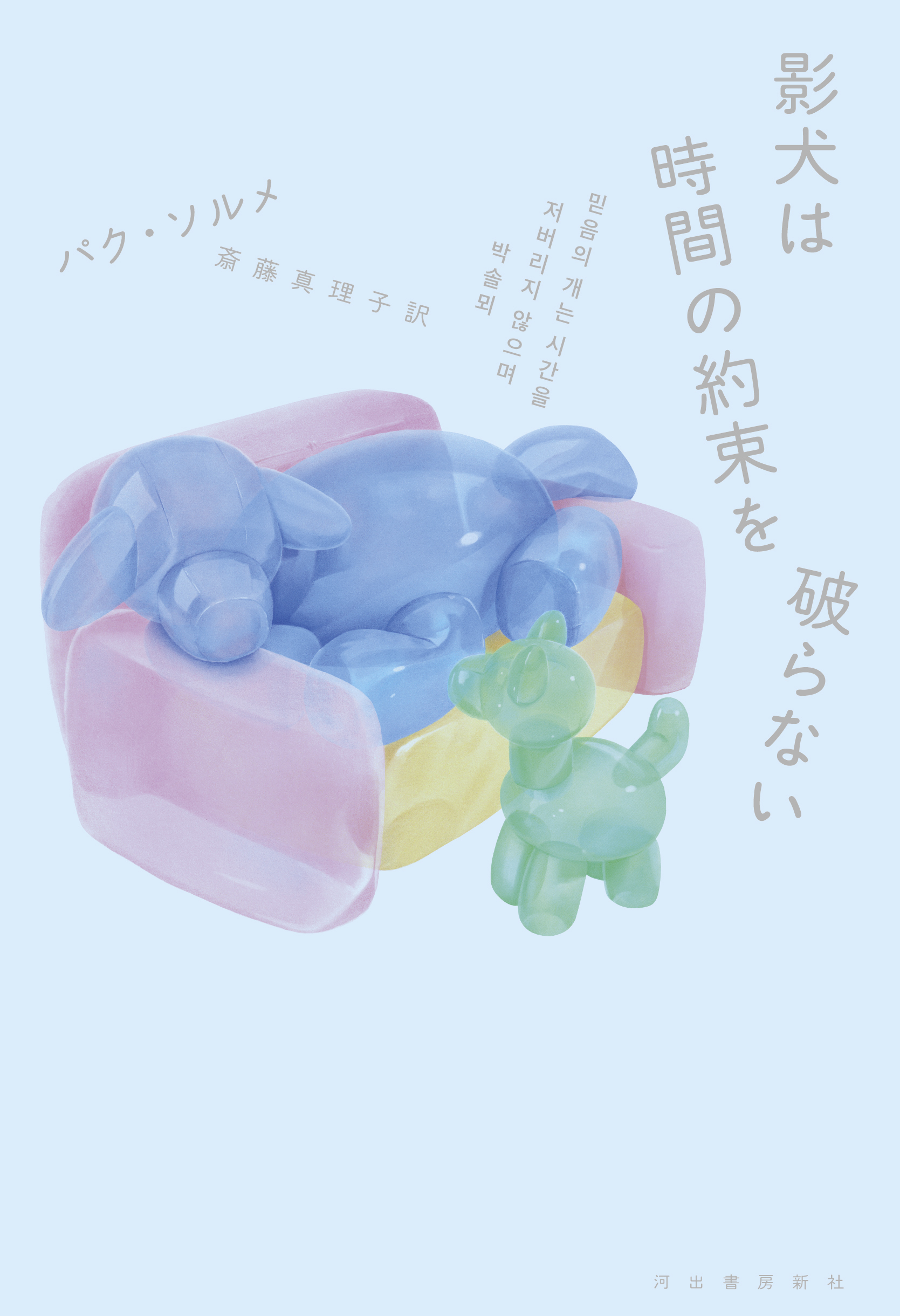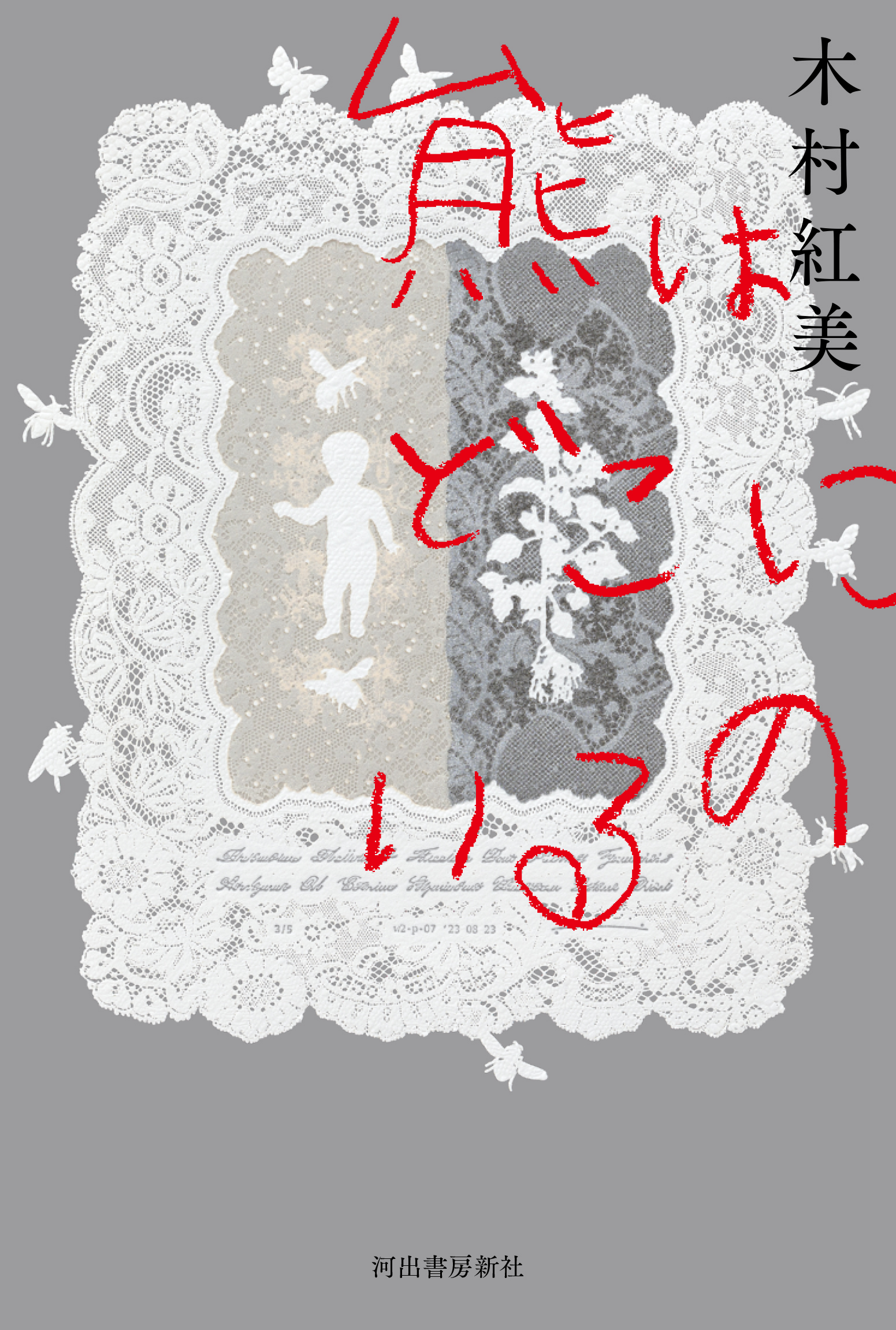書評 - 文藝
「向き合わずにいられて、安全圏で生きられて、いいな」 “差別”に向き合う作家・桜庭一樹が五度、六度と読み返した作品
桜庭一樹(作家)
2023.02.28
自分はずっとずっと差別してきたと思う。
多くの場合、「心を痛めてはいるが、よく知らない事柄だから口を挟み辛い」として沈黙を選んできた。そもそもよく知らないんだから私は差別をしていない、という言い訳もしてきた。でも、知らないままでいる、知ろうとしないことも差別への加担だったんじゃないか。酷い時は、自分が知らないということさえ知らずにいたが、それでも支障なくこうして暮らせるのが私の持つ特権なのだ。
語り手の一人、伏見もまさにそういう人間だ。関東の障害者施設で起きた無差別殺傷事件の報道を見ても、「どこか別の世界の出来事のよう」とぼんやりし、体温も変わらない。高校のクラスメートの大石のほうは、正義感と思いやりからまっすぐ差別に反対し、「許せない事ばっかでさ」と呟いてみせるが、その実、問題の本質までは理解できていない。どちらの人物の罪にも非常に身に覚えがあり、悄然として私は読み進めた。
一方で、私自身が差別される側に身を置かされることもある。だから、分教室に通う知的障害者の坪井勝夫の幼馴染の明石が、伏見に勝夫との仲を説明しようとして、「関係ない話してごめんね」と諦めたときの虚しさも、勝夫の妹の坪井敦子が大石に「向き合わずにいられて、安全圏で生きられて、いいな」とぶつける苛立ちも、身につまされて迫った。
分断による偽りの静寂は、クラスで浮いている古川のある行動で唐突に破られる。それは勝夫へのいじめと解釈され、大石は古川を「お前自身がここでボッチだから、ギリギリの立場だから、弱い者いじめがしたくなるんだろ」と責め立てるが、異質な存在である古川を疎外してきたクラスメートたち、つまり自分の罪は不問にしてしまっている。勝夫を遠巻きにせず、かわいそうで終わらせず、踏みこみ、近づいた古川のやり方に正しさはおそらくないのだが、コミュニケーション上の乱暴な正解があったように私は思う。伏見の呟く「普通の人が、またごく普通に酷い事してる。なんとなく自分はひとりぼっちだ」というディスコミュニケーションの不安を私も日々感じて生きているが、それは知らないことを知らないままにし、異質な他者とは関わらず、向き合わないという、何食わぬ顔で身につけてきた間違った良識のせいではなかったか。
ラスト近く、伏見と大石と敦子がついに向き合い、三者三様に異なる正しさと苦しみをぶつけあうシーンは圧巻だ。ここは五度、六度と読み返し、そのたび発見があった。
また、中盤で展開する敦子と古川の恋愛模様が私はとても好きだった。自傷的なもの、ままならぬ辛さから距離を縮めていく関係のように読めたのだが、この〝痛みと悲嘆を伴ういわく言いがたい愛しさ〟は、敦子が家族との生活から傷だらけになって年月をかけて学んだ尊い愛の形であって、人は時に、生育環境から培った自分だけの愛を追求して幸福な一生を送ることができるからだ。