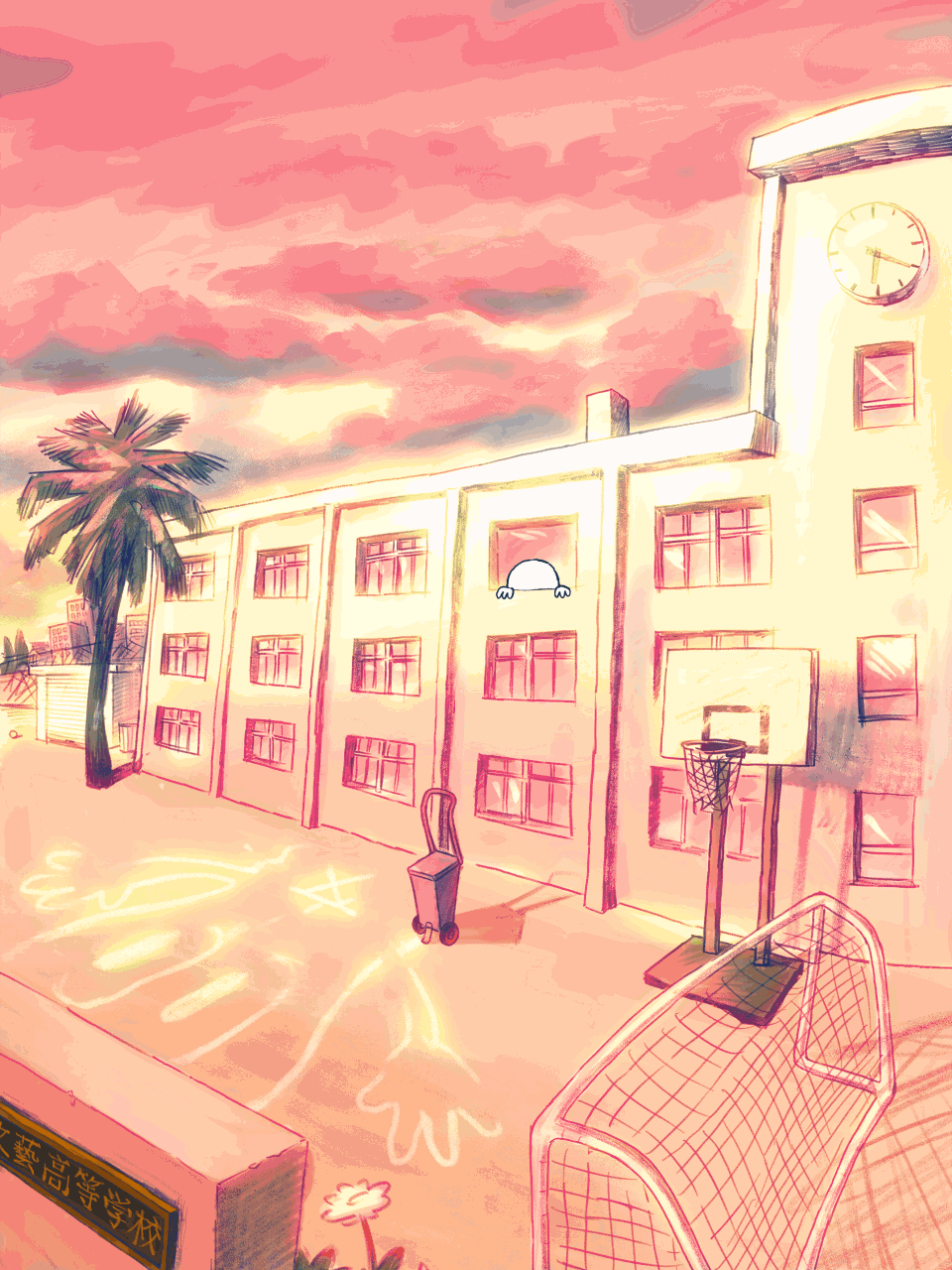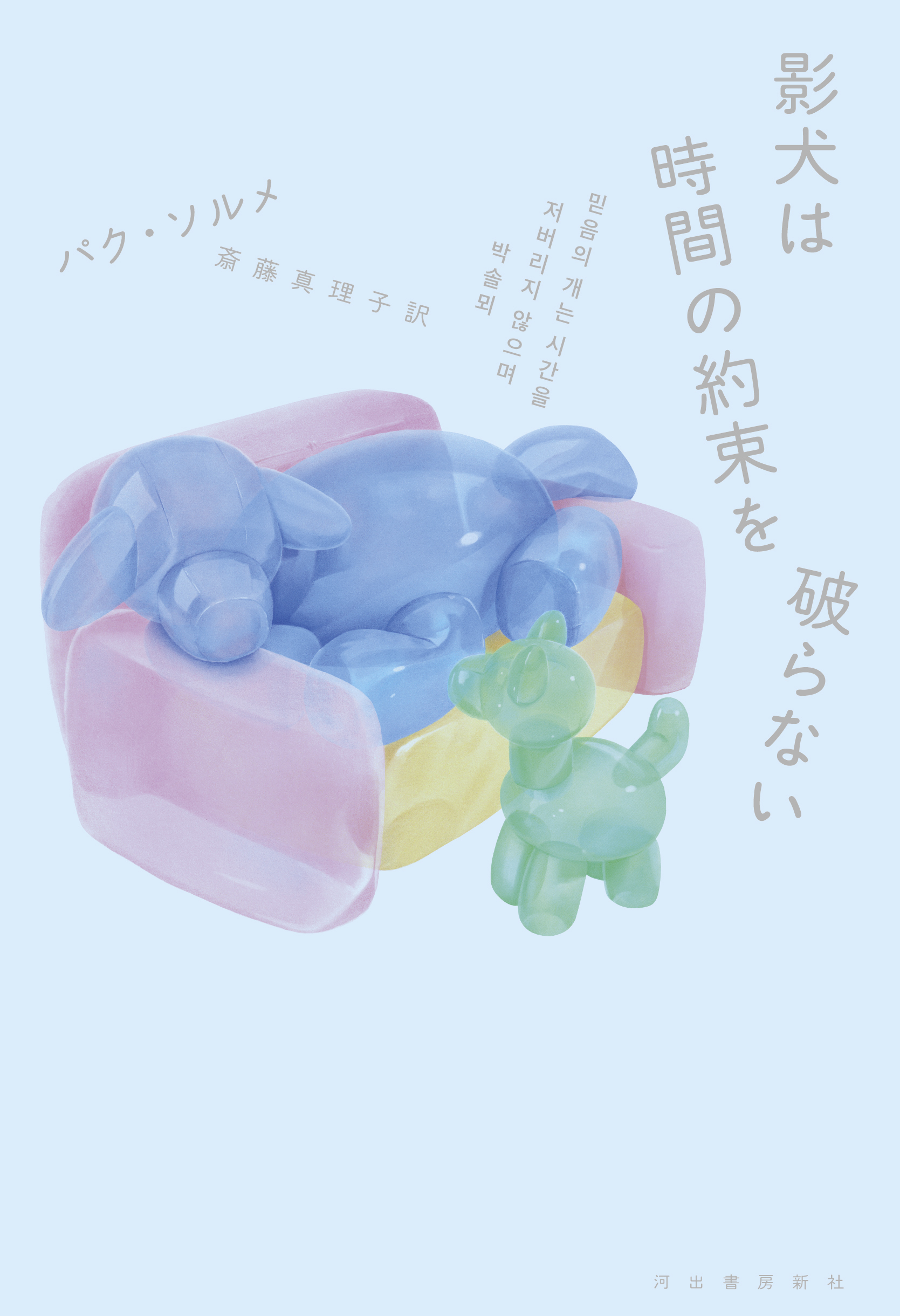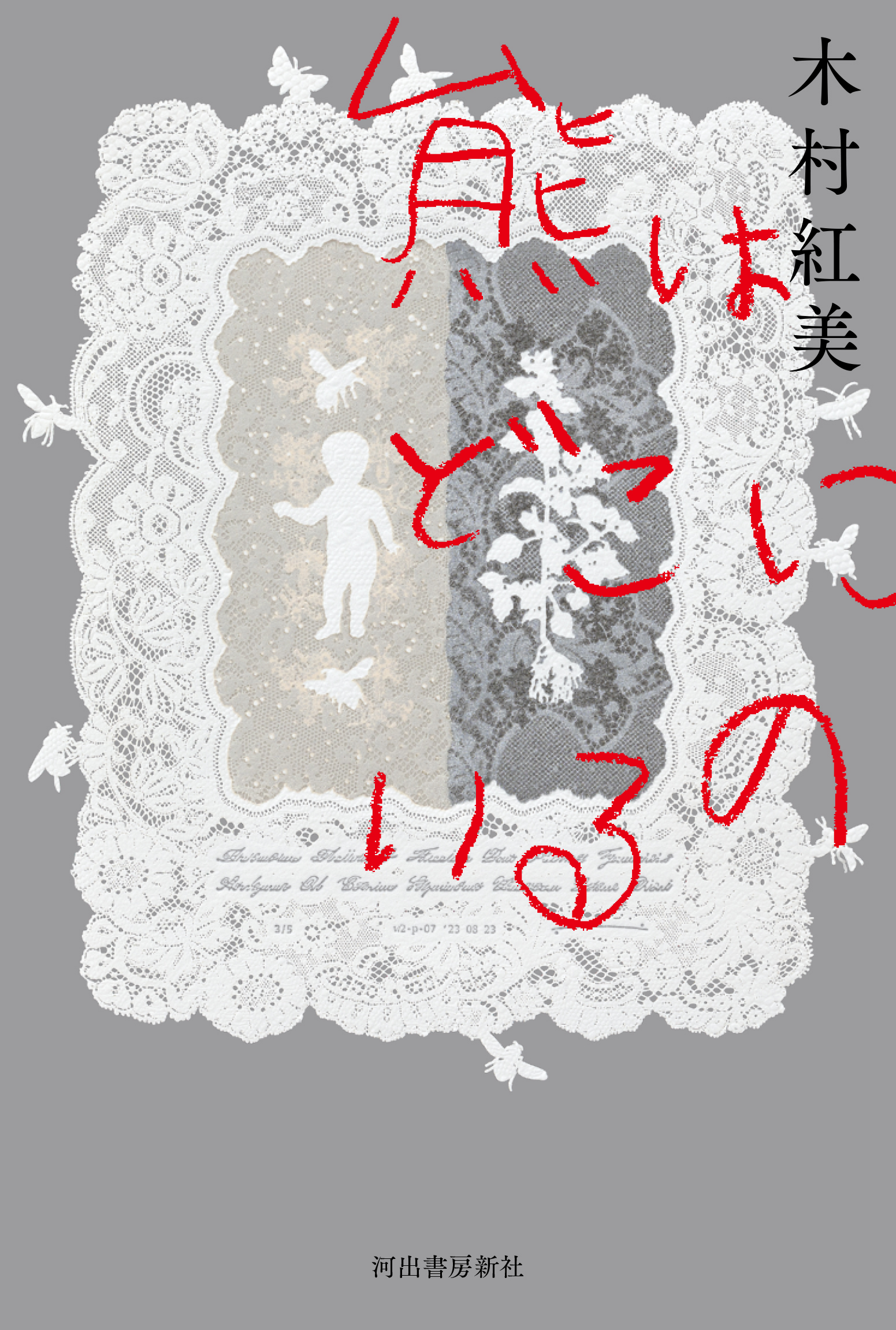書評 - 文藝
「弱い人間」がただ生きる物語――闘病中の 32 歳女性の視点で描いたマイノリティに対する社会の束縛
評者:竹田ダニエル(ライター)
2023.10.02

桜庭一樹著
評:竹田ダニエル(ライター)
我々が今生きている時代は、想像力が問われている。
主人公の小林波間は、病気の治療をしているということ以外は「普通の三十二歳」。ある日、幸せそうな若い女性を狙った通り魔事件の現場で旧友の中川君と再開するが、LINEでは繋がれて会う約束をしても、それぞれの見えている世界は少しだけずれている。パラレルワールドに住む二人は、お互いに見えている景色をシェアしあう。SF的な設定でありながらも、そのパラレルワールドのズレを通して差別問題、新型コロナウイルス、ウクライナ侵攻など、現代社会を生きる人としての当事者性が浮き彫りにされるような作品だ。
「普通」の社会でも、例えばささやかな価値観の違いだったり、捉えている社会の解像度の違いだったりと、私もあなたもパラレルワールドに住んでいる。隣にいる人のことも一生わからないし、なんなら自分のこともわからない。「違い」の中から「理解」を見つけ出すためには、想像力が必要となる。そして当事者性が欠けたままでの社会生活は、必然的にマイノリティを抑圧する「優しい傍観者」を生きることになる。
現代の日本の社会問題の中心は、「無関心」にあるのではないだろうか。みんなが自分のことで精一杯だから、政治にも興味を持てないし、小さな半径の生活にしか目を向けられなくなってしまっている。主人公波間の場合は、病を持つことでさらにその「余裕」が失われていく。女性に対するヘイトクライムについて考える時、波間は「〝戦争〟が始まる」と言う。そうとはいえ、自分のことでいっぱいで当事者意識が持てないと、まるでパラレルワールドで起きていることのように感じる。それがたとえ本当に自分の身で起きていても。
病気を持つ人は、日本では透明化されてしまう存在だ。様々な理由で社会問題に目を向ける余裕のない主人公の、当事者としての目線で変化しながら描かれていく。この作品は、主人公は「強い女」でなければならないというジブリ的な世界観ではなく、「弱い人間」がただ生きる物語でもある。なぜ日本社会では、「強い女」でなければいけないのか? なぜ病人は「弱く」なければならないのか? マイノリティに対する社会の束縛を、気持ち良いほどに解していく。
この文章を読んでいるあなたも、パラレルワールドにいるのかもしれない。永遠に通じ合わない人も、もちろんいる。だが、想像力を持って、「他の人」の存在を可視化しなければならない。同じパンデミックを経験したはずなのに、世界をどう生きていくか、それぞれの正義がいくつも存在している。そんな事実を肯定するような、「優しくなれる」物語だ。どんな人であれ、ここにいるだけで、生きているだけでいい。そう、何度も言い聞かせてくれる。ただ、想像力と当事者性を持って、「優しい傍観者」にさえならなければ。