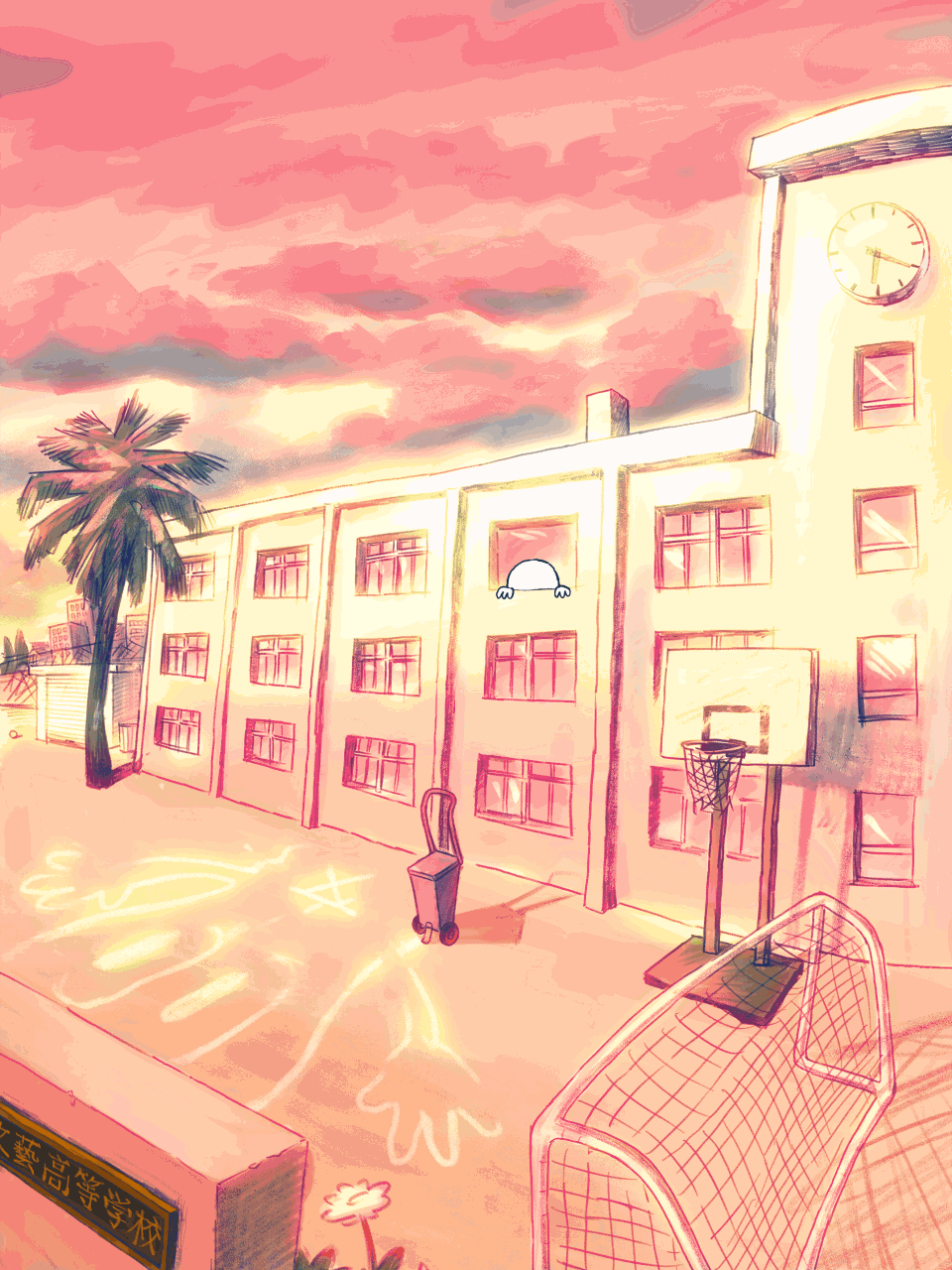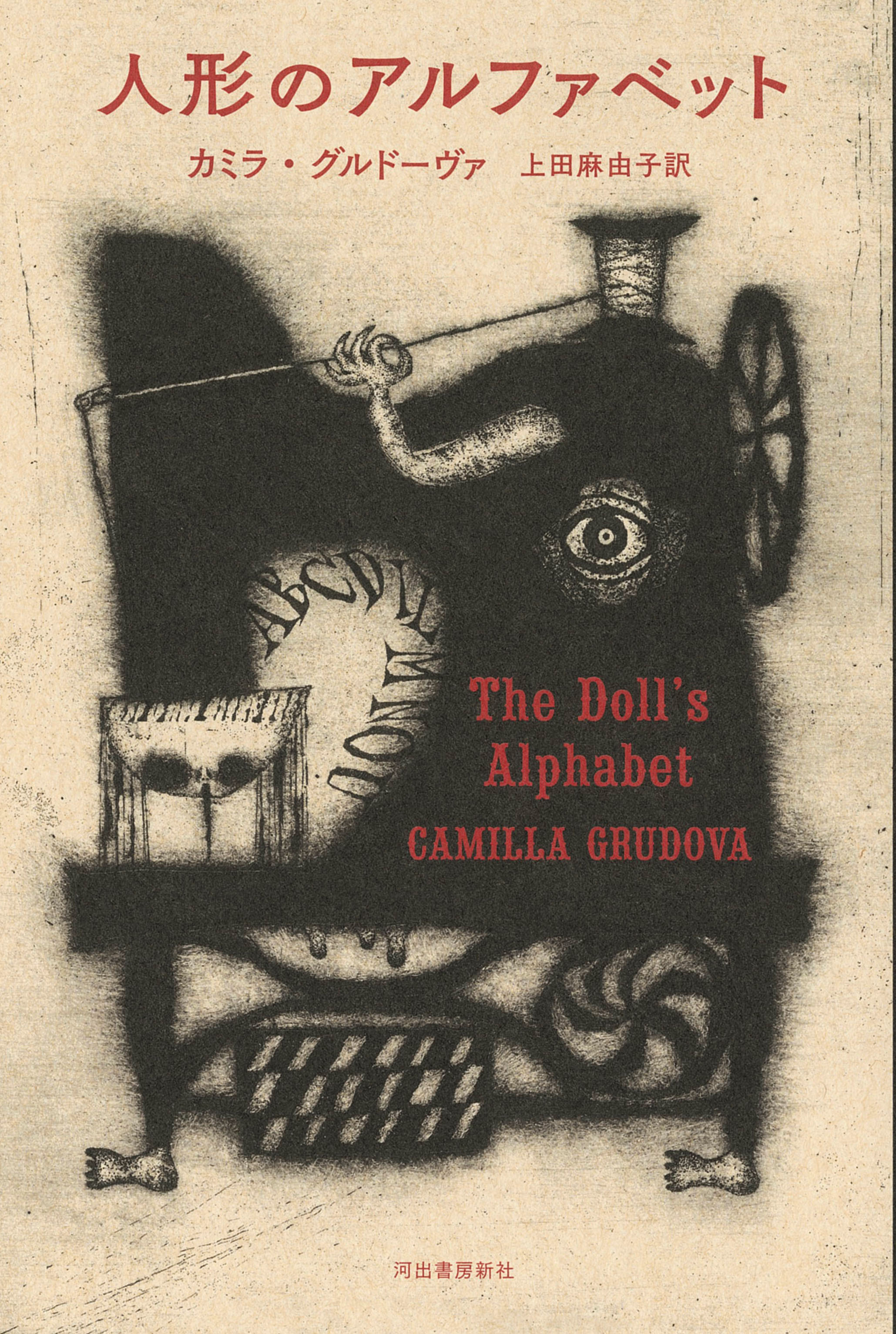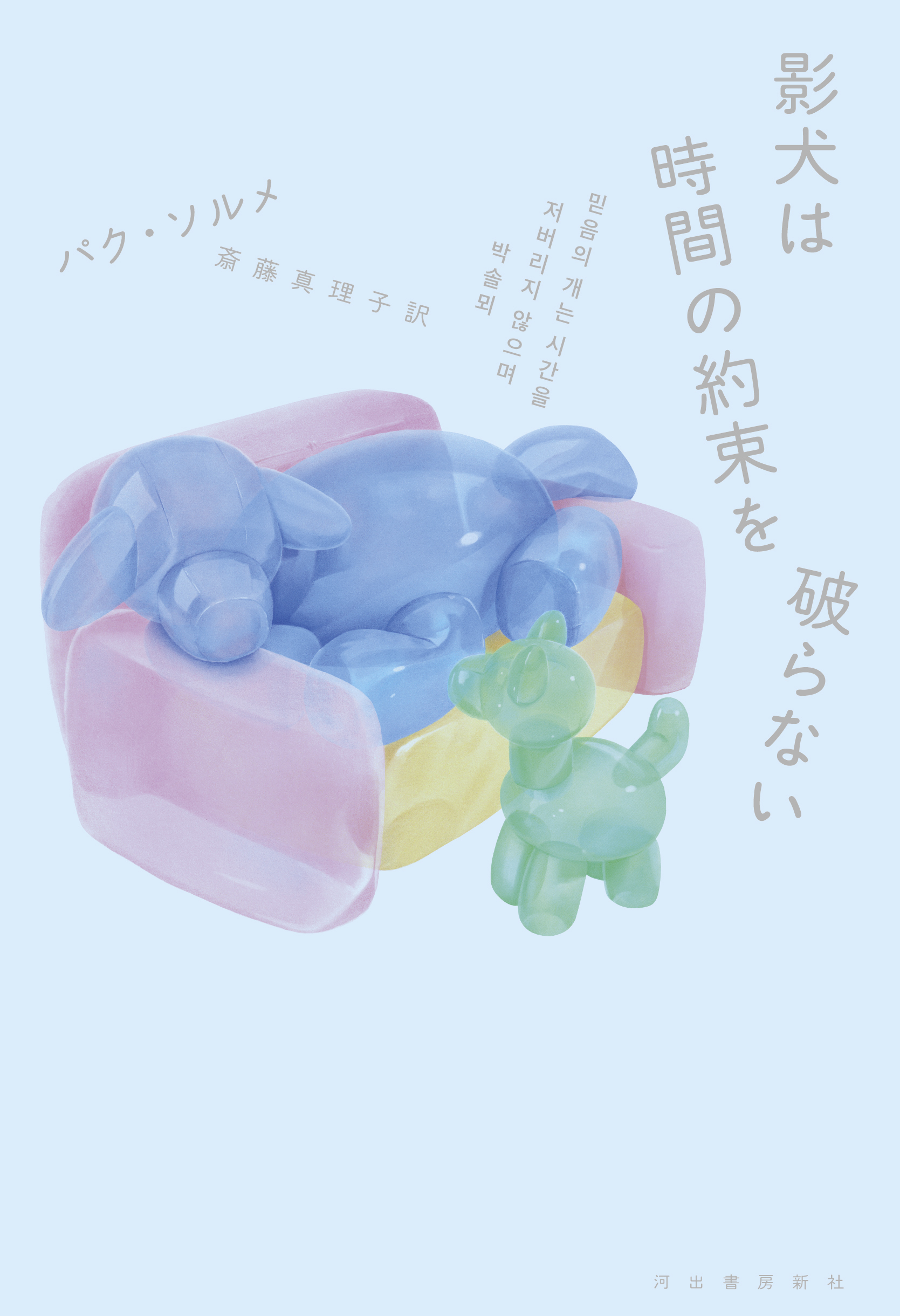書評 - 文藝
「人間をこんなふうに詰め込んではいけない 」東京の満員電車に異常さを感じたときの記憶が蘇った小説 作家・八木詠美が紹介
評者:八木詠美(作家)
2023.10.03

若竹千佐子著
評:八木詠美(作家)
はじめて東京の満員電車を見たとき、嘘だと思った。人間をこんなふうに詰め込んではいけない、きっと今の電車はどこかの学校が遠足のためにJRと約束をし、全校生徒を詰め込んだのだろう、と他県から来た小学生のわたしは考える。しかし次の電車も混んでいた。仕方なく乗るが、お腹が押されて息ができないし、誰かのビジネスバッグの角が腕に食い込んでずっと痛い。
わたしは黙って呼び掛ける。あの、まず目の前のあなた。こういうのって毎日乗れば慣れるんでしょうか。次、顔が見えないけど隣のあなた。決して怒っているわけでないのですが、鞄刺さってるの気づいてます? というか冷静に考えたらあなたすごく斜めってますよね。え、大丈夫? いや、無理でしょその体勢。脱臼するよ、あるいは骨折。というか変だよね。みんなこんなに無理して電車乗るなんて。ねえ、本当に誰も苦しくないの? おかしいと思うわたしがおかしいの? 誰も何も言わない車内で、わたしは彼らの声が聞きたかった。
若竹千佐子さんの『かっかどるどるどぅ』を読んでいる間、これはあのとき聞けなかった「声」だと思った。
主な登場人物は夢を捨てられず、倹しく暮らす60代の悦子。介護に明け暮れ、自分の気持ちを置き去りにしたまま68歳になっていた芳江。大学院を出たものの就職氷河期に重なり、非正規雇用の職を転々とする30代の理恵。不器用で、自死を考える20代の保。何かを諦めたように、あるいは自分を責めるように、それぞれ不安を抱えて毎日を過ごしている。理恵は日記に綴る。「すべて自己責任なのだろうか(中略)大きな流れの中で逆らえないことなのだろうか」
そして4人は古いアパートの一室を訪れる。そこでは片倉吉野というアフロヘアの女性が、訪れる人たちに食事を振舞っていた。彼女は来る者を拒まない。名前のない料理を囲み、箸がこすれあう音や咀嚼する音が、そして彼らの内側にあった言葉が声となって響き出す。「自分だけ応援団」から「みんな応援団」へと変わり、立ち上がろうとする。
あったかいなあ、と読みながら思う。と書きながら同時に考える。この書評を読んでいる人の中には「それってよくある物語じゃない?」と思う人もいるのかもしれない。確かに食事を通じて人が交わる物語は珍しいものではないし、この小説を「人と人が出会い、人生を肯定する感動作」とまとめてしまうこともできるのかもしれない。それでもこの小説が輝いているのは、語りの巧みさに加え、つらいときにつらいと口にすること、手を取り合おうと声を上げることすらためらうような冷笑的な言説が横行する今、この物語自体が若竹さんの声だと感じるからだ。『おらおらでひとりいぐも』で一人で生きていくことを描いた若竹さんが、数年の時間をかけてこの小説を生み、孤独を抱えながらも「みんなで生きる」ことをここまで力強く宣言している。その人間らしく、誇りに満ちた声に胸を打たれ、満員電車にはじめて乗った日の自分にも届けたいと思う。