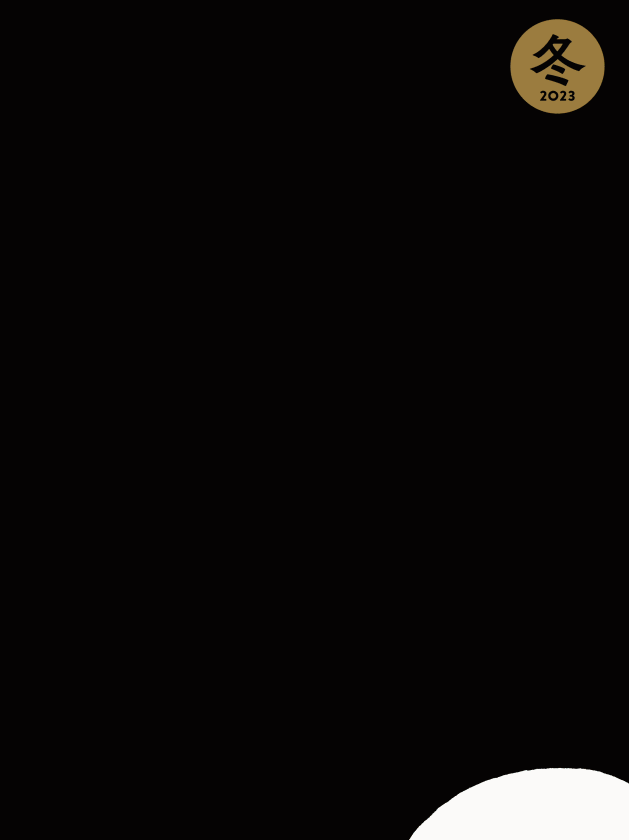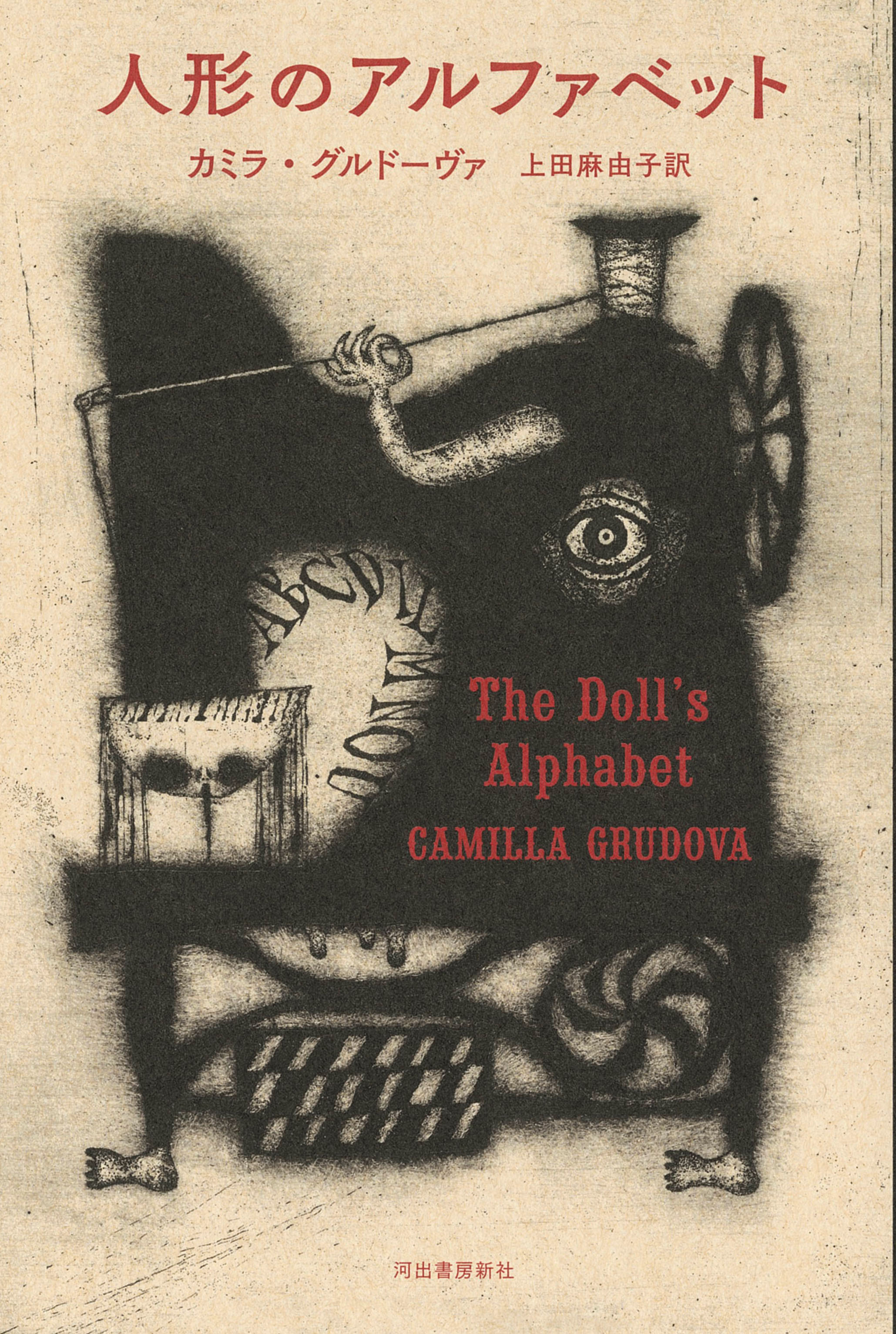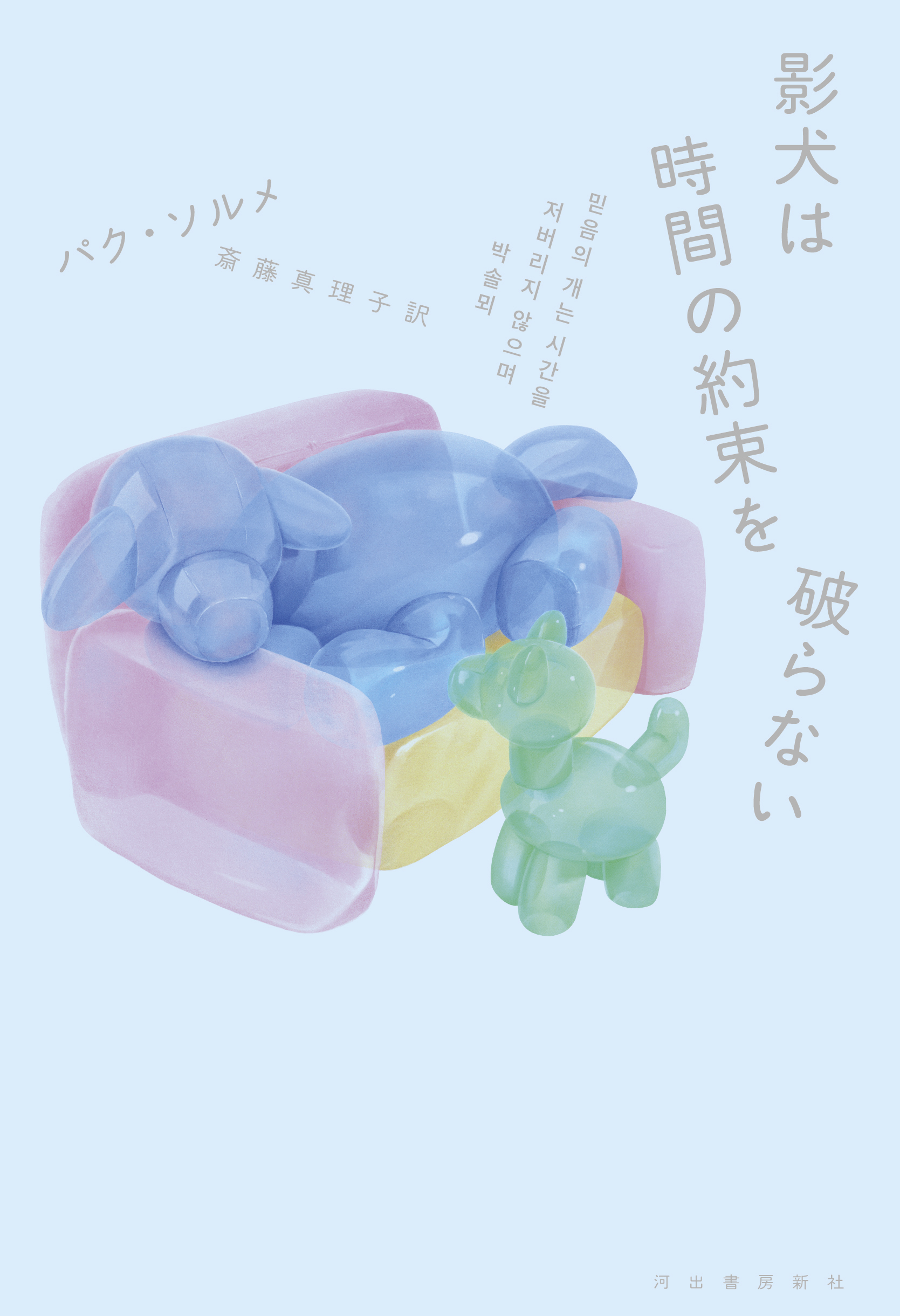書評 - 文藝
あの娘との時間を「闇」と呼べない、でも――芸能界で過ごした少女たちの物語を俳優が読む
評者:小川紗良(俳優・映像作家・文筆家)
2023.12.04
作詞家としても活躍する作家・児玉雨子による第169回芥川賞候補作『##NAME##』が刊行。本作の魅力を俳優・映像作家・文筆家の小川紗良さんが語る。
『##NAME##』
児玉雨子 著
評:小川紗良(俳優・映像作家・文筆家)
自分の手で、ゆっくり解いていくしかないのだ。他人が名付けた「闇」の物語は、どこか夢見心地な二次創作でしかない。向こう側から見た闇は、さぞきれいな黒をしているのだろう。しかし渦中から見たそれは、時にまばゆいコバルトブルーをしていたり、甘やかな香りを放っていたり、人肌のあたたかさを持っていたりする。闇は一見闇らしくないからこそ、時間をかけてじわじわと人を追い詰め、自覚したころにはぼんやりと霞んでしまうこともある。行き場のない怒り、落胆、諦観。それらを包みこむ、剥がしにくいオブラートのようなノスタルジー。まるごと口に放り込めば、闇と哀愁がぬちゃぬちゃと融け合っていく。
ジュニアアイドルをやっていたわけではないけれど、10代から芸能活動をしていた身としては、感覚的にわかってしまうことがあまりにも多い一冊だった。オーディション会場に張り詰める「そこにない視線」、その視線に向けて天真爛漫に振る舞うこと、芸能活動と実生活の隔たり、コンビニスイーツの誘惑と罪悪感。歳を重ね、少し芸能と距離を置いた今になって「何だったんだろう」と思うようなことが多々ある。声を上げるまでもないけれど、どこか煮え切らないモヤっとした感覚がいくつも沈んでいて、度々発酵するようにぷくりと気泡が弾ける。そのほとんど聴き取れないくらいの小さな音に、じっと耳を澄ませるようにして読み進めた。
主人公・雪那は過去と未来、現実と非現実を行き来するなかで、様々な名前を持つ。親からもらった「雪那」、あの娘に呼ばれた「ゆき」、SNS上の「ゆきじ」、名付けそびれた「##NAME##」。祈りのこもった名前でも、特に意味がなくても、授かったものでも、自ら名乗ったものでも、名前は自ずと人格を持ち、その数だけ主人公が存在する。そしてそれらはゆるやかに地続きで、「私」の所在を曖昧にしていく。私が思う私、誰かが思う私、社会のなかでの私、ネット上の私。どれもが紛れもない「私」なのだけど、どれも「私」ではない気もして、菓子パンやカップ春雨のような「それらしいもの」の渦に飲み込まれていく。
そのなかでぎこちなく「ゆき」「みさ」と呼び合ったあの娘との時間を、私は勝手に「闇」と呼べないのと同時に、「光」とも言い難いむず痒さを覚えた。「ゆき」は一般人として、「みさ」はグラビアの世界で、別の道を歩みながら、一緒に過ごした時間だけがぽっかりと浮かんでいく。時代が変わり、世間の声も変わり、彼女たちが受けていた被害の形が見えてくる。しかし世間がつくった形と、彼女たちの過去の形がぴったりとハマるわけではない。被害を訴え戦う力を出すほどの、心の救済も間に合っていない。児童ポルノが罪に問われ滅ぶべき害であることは間違いないけれど、どこまで葬られても、被害を受けた人々は一生それを抱えて歩んでいく。そのやるせなさに頭を抱えながら、すがるように読んだ最後の一文に、かけがえのない「私」の所在を見た。