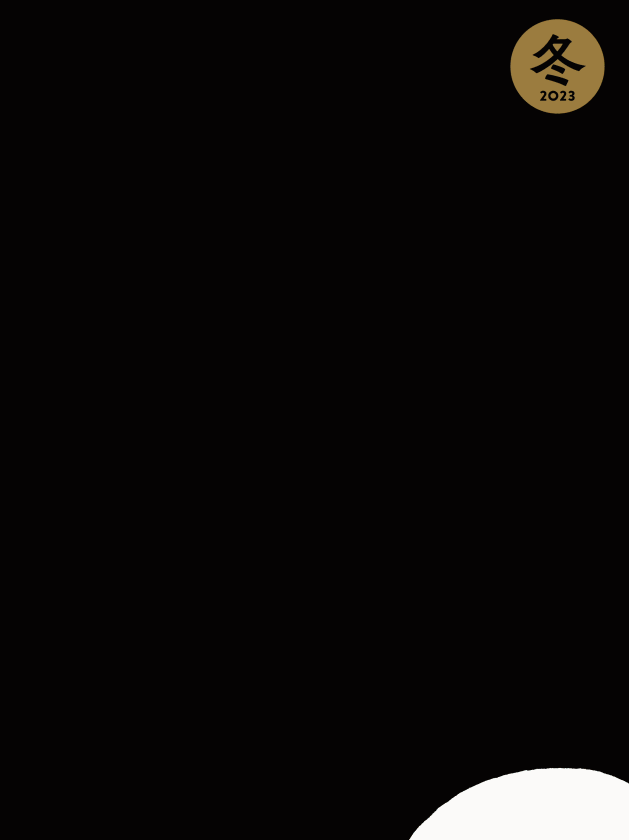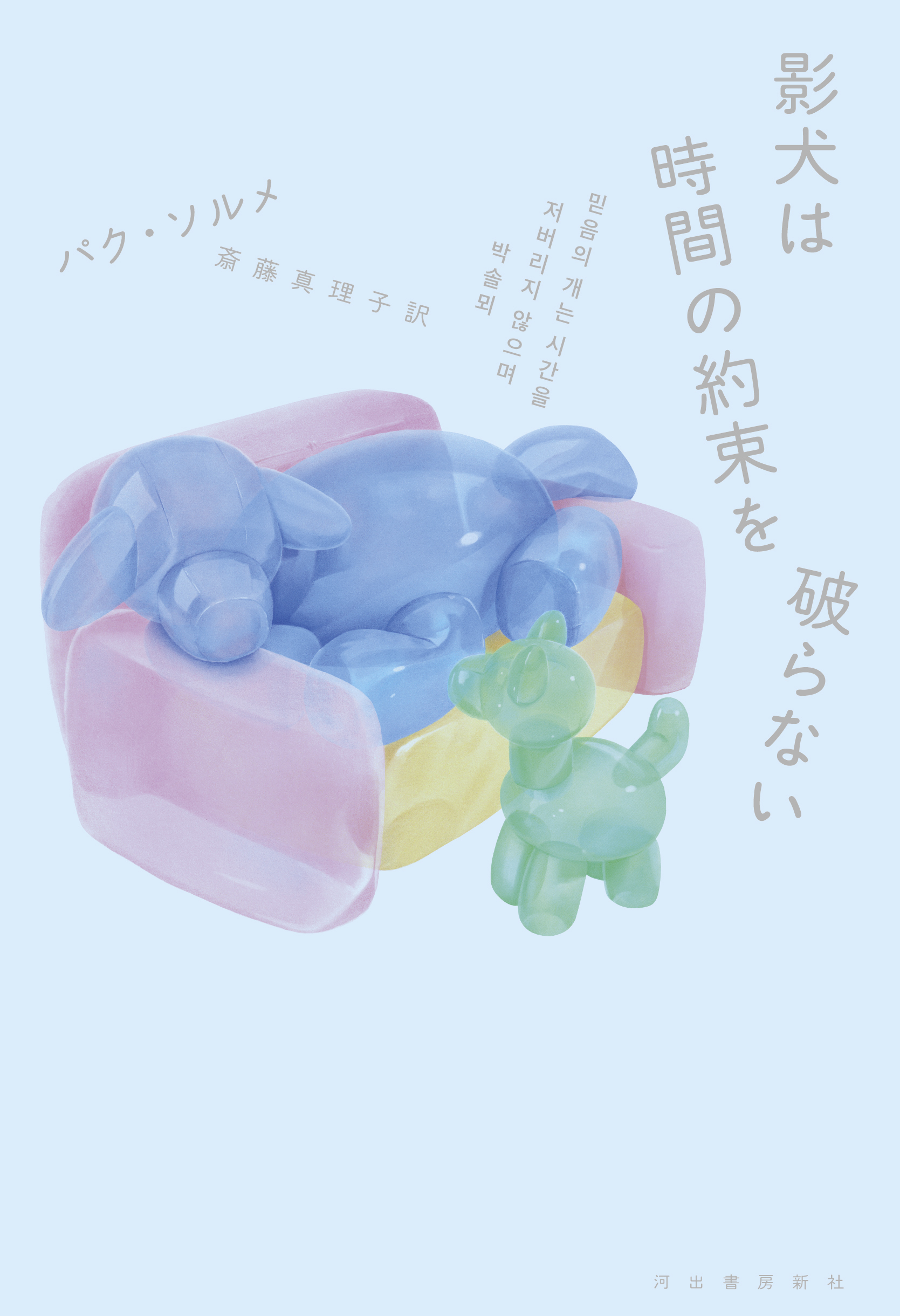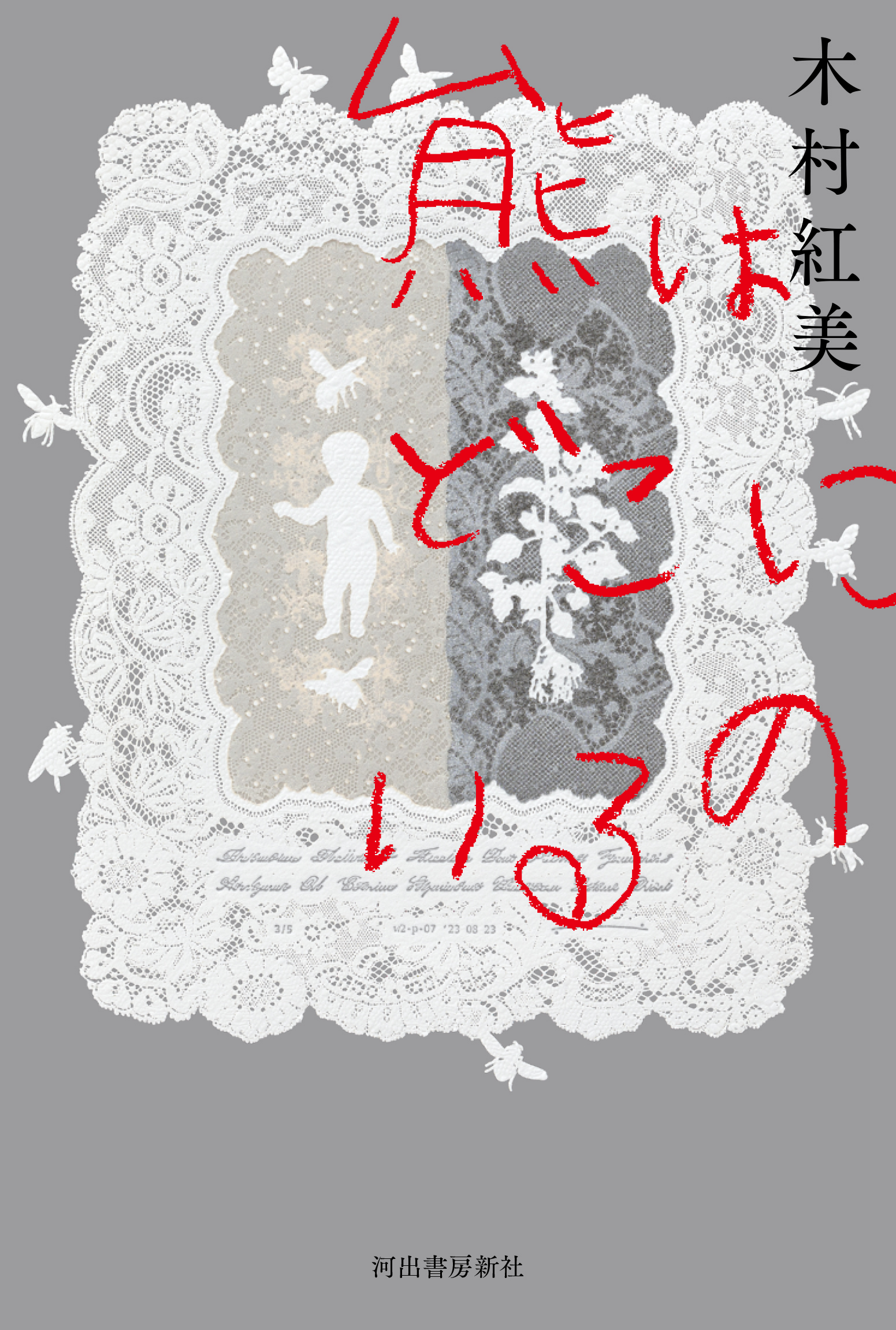書評 - 文藝
謎の国際テロも大統領選もあらゆる重要な仕事も、全てが無に帰る フランス発大ベストセラー
評者:樋口恭介(作家)
2023.12.11
ヨーロッパを代表する作家・ウエルベックによる最新作『滅ぼす』が刊行。本作の魅力をSF作家の樋口恭介さんが語る。
「滅ぼす(上・下)」
ミシェル・ウエルベック 著
野崎歓/齋藤可津子/木内尭訳
評:樋口恭介(作家)
宇宙が誕生したとき、巨大な爆発音が無の中で鳴り、我々は今なおその残響の中で生きている。その音が鳴り止むとき、全ては再び無の中へと帰っていく。そしてあとには何も残らない。静寂だけがあり、あるいは静寂すらもどこにもない。始めからそこには何もなかったかのように。
ミシェル・ウエルベック『滅ぼす』は人類文明の喧騒を緻密に描写し、同時にその緻密さをもって、それらのできごとの全てを無化するように描写する。舞台は二〇二六年のフランス。翌年に大統領選を控えた慌ただしい官僚組織の中で、夫婦生活に問題を抱えた主人公、ポール・レゾンは人生から逃れるように仕事をし続ける。大統領選に出馬予定の上司のための文書作成、対抗馬の動向確認、そして国際テロ組織から幾度も届けられる犯行声明への対応。小説はあたかも、連日の深夜労働によって分泌されるアドレナリンとドーパミンによってハイになったワーカホリックな官僚たちの心境を映し出すようにして進行していく。ポールは自分の仕事を愛している。けれども一方で、そんな仕事を生み出している社会を「滅ぼす」ことを試みるテロリストにも共感を寄せている。
物語は基本的に、テロ組織への謎解きを軸にしてサスペンスフルに推進される。けれどもその流れは唐突に断ち切られる。以降の展開に関する詳細は作品の核心に触れるため割愛するが、サスペンス=宙吊りは、ポールが自分自身の、代わりのきかない、私的な、動かしがたい、生活上の、あるいは人生そのものの、絶対的な問題の発生を前にして、永遠に宙吊りのまま捨て置かれる。ここで物語は、それまで展開してきた「滅ぼす」というテーマ自体を自ら「滅ぼす」のだ。
ポールが生きる、あるいは我々が今ここに生きている近代社会は、死を遠ざけることを目的として発展してきた。傷を治し、病いを治し、死を待つ人々は病棟の中へと隔離され、その結果、健康的で清潔で、道徳的な秩序ある生活空間の中で日常を過ごす人々は、自分がいつか死ぬことを、現実感をもって迎え入れることが困難になった。けれどももちろん、言うまでもないことなのだが、人は死ぬ。例外なく、いつかは誰もが必ず、死という抗うことのできないできごとによって滅ぼされる。死という確定的な真実の前では、大統領選に向けた準備も、テロの謎解きも、その他のあらゆる重要とされる仕事も、結局のところ、近代社会が用意した、ひとときのかりそめの喧騒に過ぎない。絶対的かつ私的な問題を前にして、ポールの妻は魔女信仰に傾倒し、ポールはニューエイジに共感を寄せ、ミステリ小説を読み耽ることで、ささやかながら静かな生活を取り戻す。
物語の最後でポールの妻は「私たちには素敵な嘘が必要だった」とささやく。そこで言われる嘘とは何か。答えはどこにもなく、文が尽きるとともに、あらかじめ約束された無が、そこに生きた全ての人々の全ての絶望と希望とを消し去っていく。