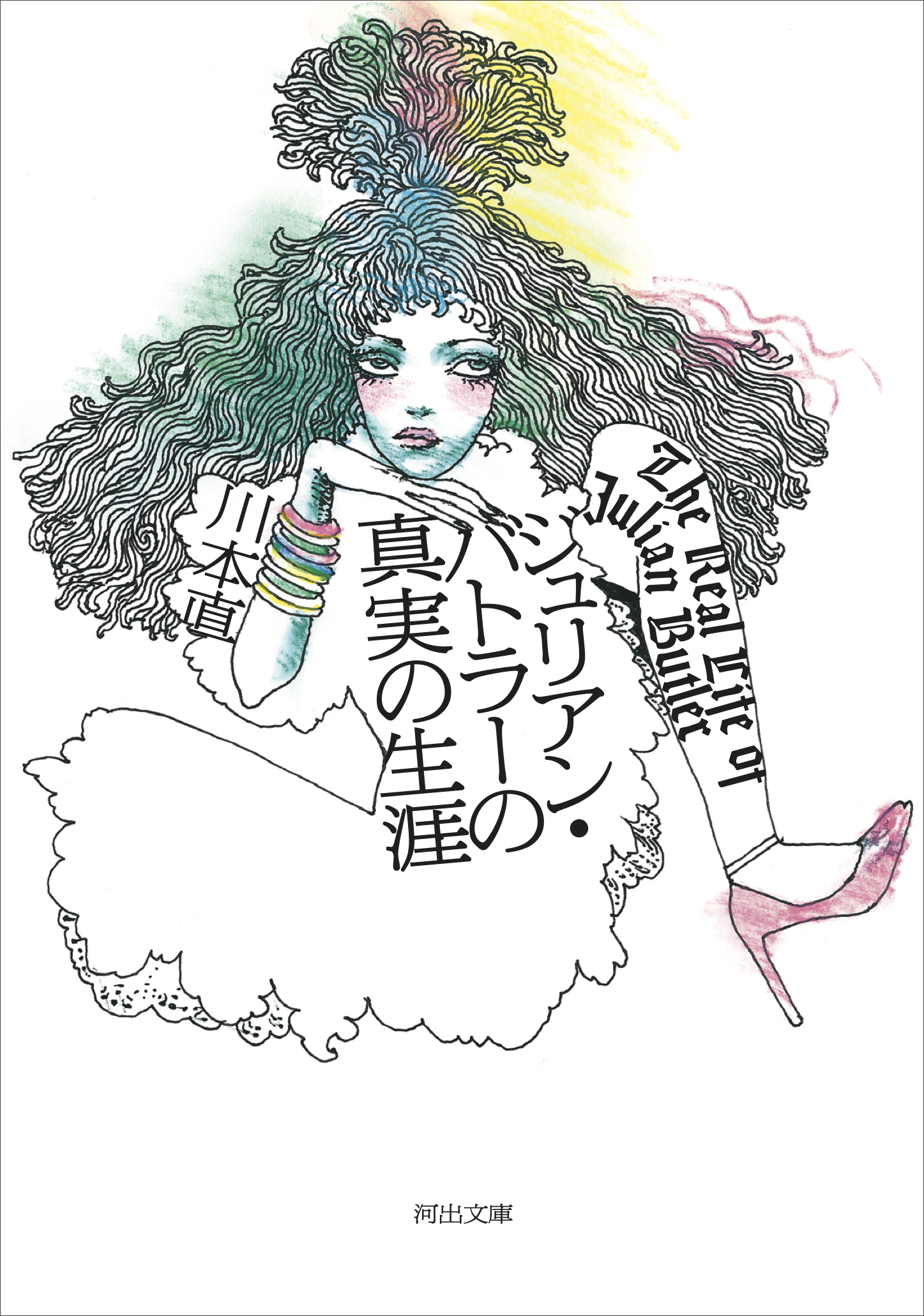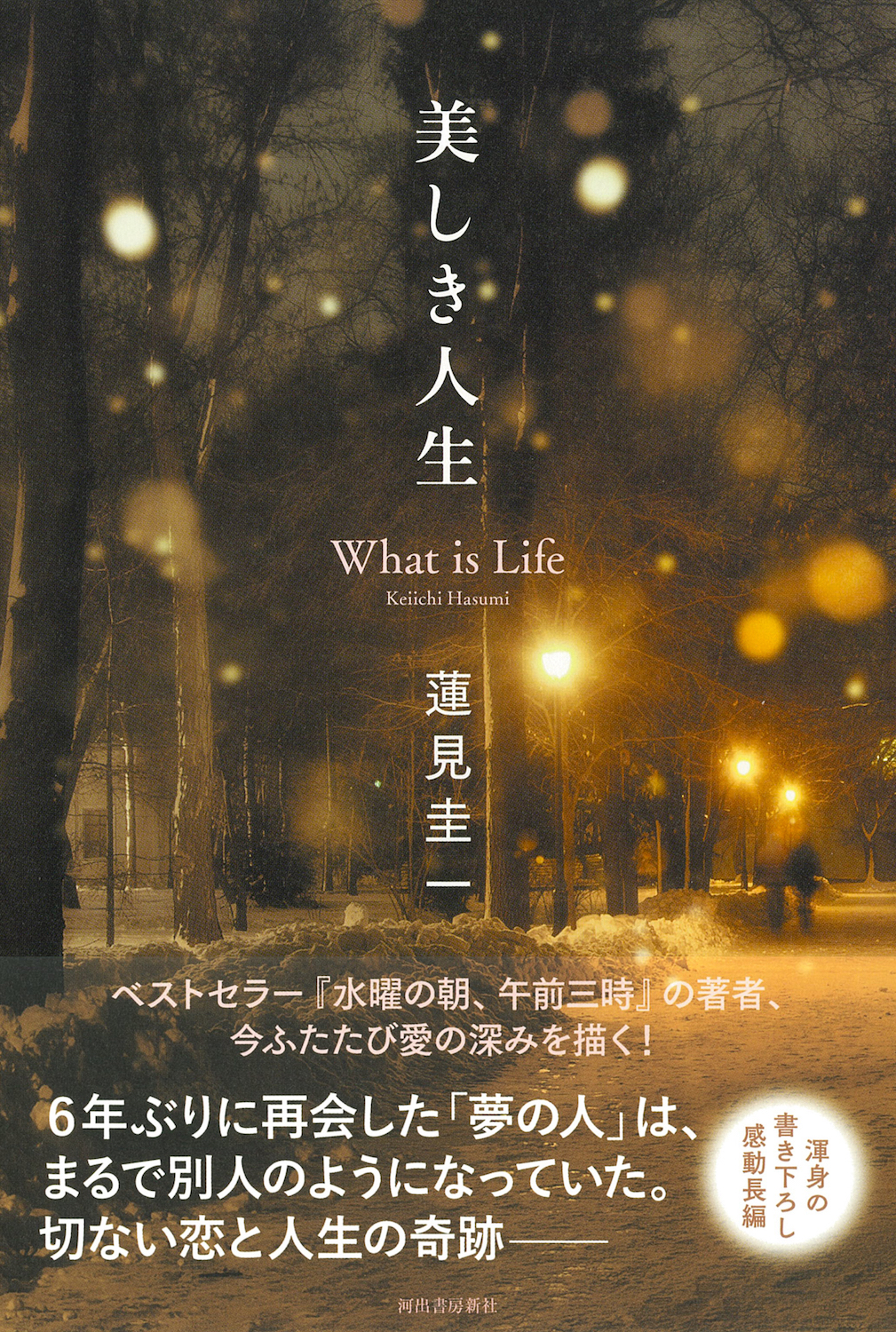書評 - 日本文学
恩田陸『灰の劇場』文庫化記念! 斉藤壮馬さん書評掲載。──「救済を感じた」ラストシーン
評者・斉藤壮馬
2024.02.02
記憶と記録――恩田陸著『灰の劇場』
斉藤壮馬
灰色の羽根が降り積もり、やがてすべてを掻き消してしまう。あとに残るものは、いったいなんなのだろう。記憶する、記録するとは、いったいどういうことなのだろう。恩田陸さんの『灰の劇場』は、そんなことをしみじみと考えさせられる、不思議な味わいの作品だった。
文章は大きく三つのセクションにわかれている。作家である「私」は以前読んだ記事がずっと心に棘のように引っかかっていて、それを元に小説を書くことを決心する。その小説が作中作として展開され、TとM、二人の半生が綴られる。そして作品の舞台化を持ちかけられた「私」は、戸惑いながらもそれに応じていく。
非常にジャンルレスな印象で、そもそもそういった区分が無意味に感じられるような、様々な要素の詰まった作品である。虚構を扱っているのでかなりメタ的な部分もあるし、ホラー要素もものすごく感じる。個人的には、自分には知識がないけれど、能の観点から読み解いてみたいと思った。
作中では、記憶と記録についてのイメージが無数に描かれる。そもそものアイディアの核となっている、いつか読んだはずの新聞記事。夏の終わりに初めて歩く、でもどこか既視感のある海沿いの町。新宿で見た、顔のない奇妙な男……そうしたイメージの連鎖が、読み手を物語の迷宮にどんどんいざなってゆく。
〈0〉の語り手である「私」は恩田さんご本人を思わせるが、本当にそうであるかどうかはいち読み手には重要ではないだろう。大事なのは、もしそれが本当のことでも─本当だと記録されていることでも、記憶していることでも─その真偽は誰にも、下手をすると本人にすら確かめられないということだ。この現実の日々を生きるぼくたち、この無数の「かもしれない」と共に歩くぼくたちもまた、物語を生み出し、触れ合い、咀嚼しているのだろう。そんな気づきに、はたと立ち止まり、考えさせられた。
物語が進むにつれ、それぞれのセクションは変質し、融和していく。「私」は次第に、今自分がどこにいて、何をしているのかわからなくなる。「私」は幻視する。時間も空間も超え、そこにあるはずがないものを見る。聞こえるはずのない声を聞く。現実と虚構が入り混じり、物語は終幕へと向かう。そのあとに続く〈1〉の最後の場面は、様様な味わい方ができるだろう。ぼくは穏やかなる救済を感じたが、ぜひ皆さんにも、それぞれのラストシーンを感じてみていただきたいと思う。
刊行された書物は、記録と呼んでも差し支えないだろう。そして、この『灰の劇場』を読んだぼくには、間違いなく記憶の羽根が降り積もっている。この先どこかでふと思い出したときに、今感じたことと違う記憶を抱いていたとしても、それはそれでいいのだ。そのときはまた、記録に残したこの書評と本を読み返して、再び味わえばいいだけなのだから。
初出=「文藝」2021年夏季号