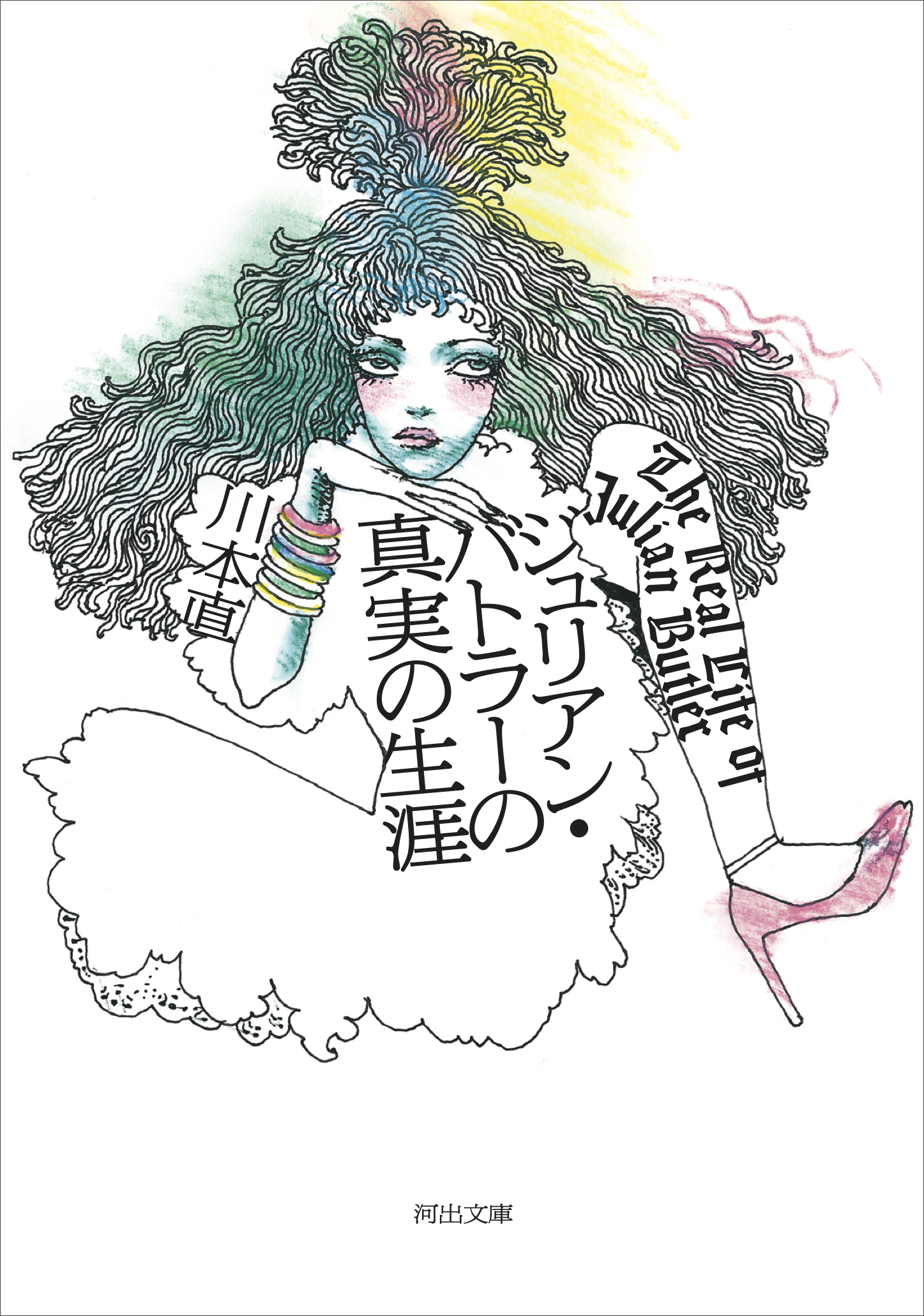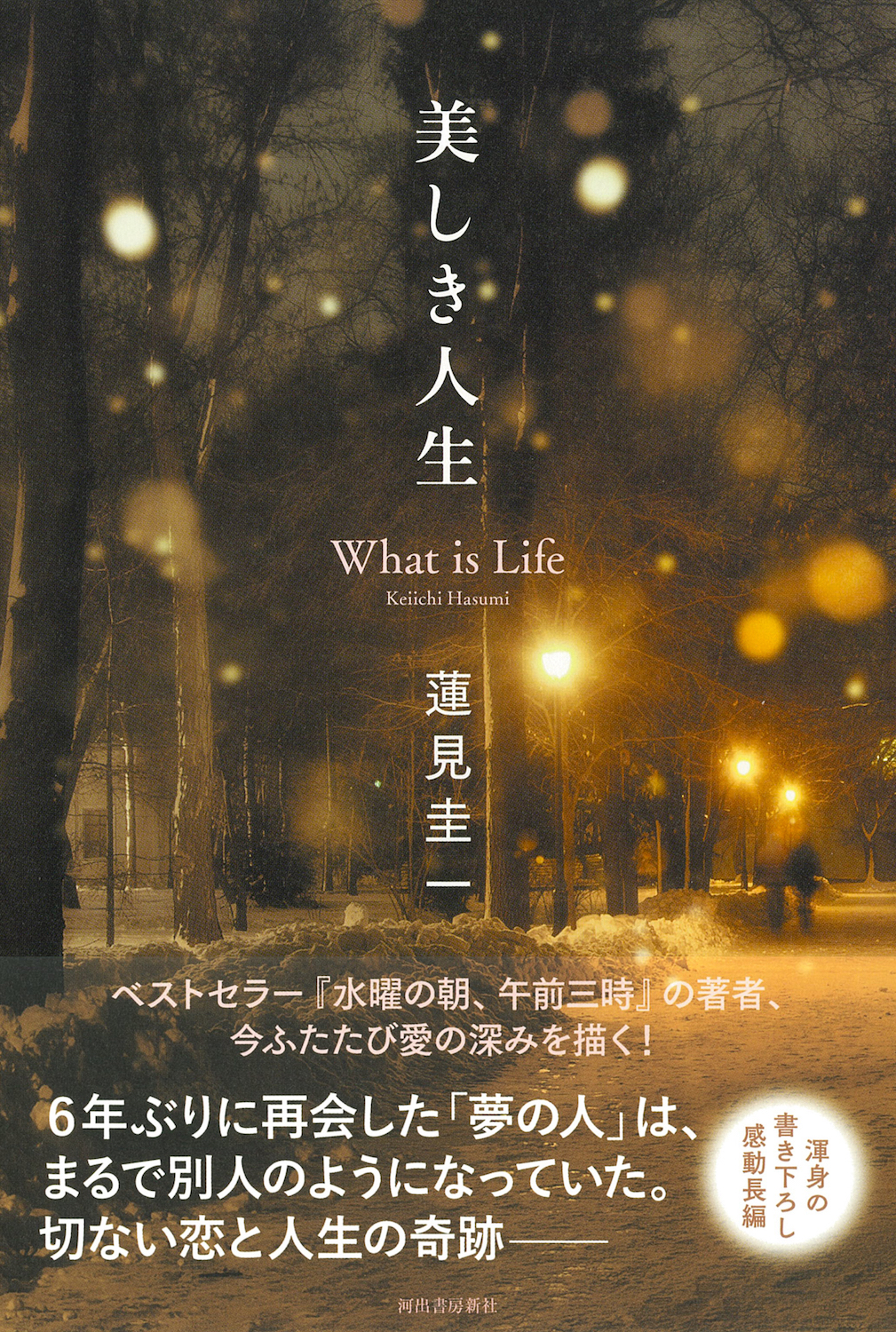書評 - 日本文学
恩田陸『灰の劇場』文庫化記念! 武田砂鉄さん書評掲載。──日常と絶望は近い
評者・武田砂鉄(ライター)
2024.02.02
今、生きている人間が全員漏れなく死ぬことになっているというのは、なかなか恐ろしい事実である。いや、でもですね、自分に限ってはそんなことなくって、もうずっと生きているんです、かれこれ540年くらいになりますかね、という人は見当たらない。みんな死ぬのだ。「死」を漠然と怖がっていた幼少期、自分以外の家族全員が車に乗ってスーパーマーケットに出かけ、帰ってくるはずの予定時間を15分くらい過ぎると、ああもう、みんな、死んでしまったのかもしれない、と考えた。なぜか、妙に冷静になった。これからどうやって暮らしていこう。まずはおばあちゃんの家に電話をしよう、おばあちゃんと一緒に暮らすことになるんだろうか、どっちの家に住むんだろう、この家なのか、それとも、おばあちゃんの家なのか。自分の家のほうがいいな。今後のプランを練っていると、聞き覚えのあるエンジン音が聞こえてくる。胸をなでおろす。その後で、妙に冷静になっていた自分が恐ろしくなる。なぜ、悲しくならなかったのだろうか。寝る前に、死とは何か、と考える。どうやら多くの人が、幼少期に同じような命題を自分にぶつけて悩むらしい。
先ほど、「死」を漠然と怖がっていた幼少期、と書いた。で、どうだろう、大人になって、死のイメージは、漠然を通り抜けて、明確になったのだろうか。死にゆく人を見た。不慮の死を知った。なんとか取り戻した生に喜んだ。わずかながら、そんな経験を持つ。これだけ共感や共有をやたらと好む社会なのに、死生観については議論する場が用意されず、誰かの劇的な死をテーブルに並べて、マジ泣ける、ホント泣ける、と賑わっている。衝撃映像を扱うテレビ番組が定期的に放送され、その多くの場合で、九死に一生、なんて言葉が使われている。ほとんどの確率で死ぬはずだったのに、なんとか助かった、という映像を見ると、私は必ず、確率通りに死んでしまった人を思う。あと1秒遅れていたらダンプカーに轢かれていた映像を見て、1秒遅れてダンプカーに轢かれた人のことを思うのだ。むしろそうやって、1秒遅れた人ばかりなのではないか。
生きるのって、選択の連続である。進路、就職、結婚といった、大ごとだけではない。9時37分の電車を諦めて、45分のでも間に合うだろうか。25時閉店なのに24時すぎから新規入店を煙たがってくるファミレスに今から行ってもいいものだろうか。そんなに仲良くない同僚が向こうから歩いてきたけど、イヤホンを外してまで挨拶するべきだろうか。こういう細かな選択肢の連鎖によって、私たちの毎日は構築されていく。毎回、ひとつを選択する。選択されなかったほうを選んだら、自分がどうなっていたか、誰にもわからない。猛ダッシュして9時37分の電車に間に合っていたら、自分はもう、この世界にはいなかったかもしれない。『灰の劇場』では、「絶望」と「日常」が交錯する。あるいは、隣接する。その双方の距離は誰にもわからない。急に縮まったり、ゆっくり遠ざかったりする。
日常とは何か。「日常。なんという不可思議なものだろう」「誰しも、日常は連続しているし、どこにも隙間や欠落はない。時間は続いていて、逆戻りしたりはしない。波瀾万丈の人生を送っている人でも、ご飯を食べ、トイレに行き、風呂に入り、布団に入っている時間が人生の大部分を占める」
絶望とは何か。「絶望。/人はどんな時に絶望するのだろう。/大きな絶望でなくとも、小さな絶望は日々、体験している。/引越てきた時から使っていたスーパーマーケットが無くなる。/馴染みにしていた書店が無くなる。/それは、生活に直結する、ささいなようでいて、じわじわとダメージが効いてくる絶望である」
日常と絶望は、絶望的なほどに日常生活に混じり合っている。天ぷら油の凝固剤「固めるテンプル」がなかったことが、「死」への入り口になる。「人は、意外に『気分』で死ぬ」らしい。死んだ人に、死んだ理由を聞けない死んだ人に、まだ生きたかったかと聞けない。
年を重ねていくと、どうしたって喪失が増えていく。喪失にどれだけ慣れたとしても、自分がいなくなる実感を得る、ということにはならない。朝起きて夜寝る毎日をどれだけ繰り返しても、得られない実感。自ら命を絶った人の存在を知ると、人はどうしてそんな判断を下したのだろうかと詮索する。遺した言葉はなかったか、ほのめかす行動はなかったか、その日常はどうだったのか、その日常に絶望が混じっていなかったか。がむしゃらに理由を探す。理由らしきものを見つけると、それを軸にして、物語を練りあげる。涙を流したり、逆に怒ってみたり、静かに抱き留めたりする。でも、そこで作られた理由は、ただただ簡易的に用意された理由でしかない。
生きるとは何か。死ぬとは何か。そういう煩悶は、時に幼稚な悩みだとされる。青臭いと言われる。その煩悶に答えを出すのではなく、そのまま放置され、日常に切り刻まれ、まぶされ、なかったことにされる。だから、身近に死が浮上する度に、私たちは、その死を受け止められなくなる。日常が絶望に染まる。やがて薄まる。この繰り返しだ。『灰の劇場』からは、ずっと死の臭いがする。でも、本来、死というのは、こうやって永続的に臭っているものなのだと思う。私たちが消しているだけなのだ。
幼少期、自分以外の家族全員が乗った車のエンジン音が聞こえてくると、ひとまず死を遠ざけた。でも、その日の夜は、死ぬって何だと考え込んだ。今、さっきまでにぎやかに話していた誰かと、これが最後になるかもしれない、とは考えない。どうして考えないのだろう。最後になるかもしれないのに。日常と絶望は近い。残念だけど近い。怖いほど近い。遠ざけたところで、実際に遠ざかっていくわけではない。この作品を読むと、死が怖くなる。でも、死が怖くなるのって、健全なのではないか。すぐそこにあるかもしれないものとして視界に入ってくる。こんなに視界に入ってきたのは、とても久々だ。そういうものだったはずなのだ。
『文藝別冊 恩田陸 白の劇場』収録