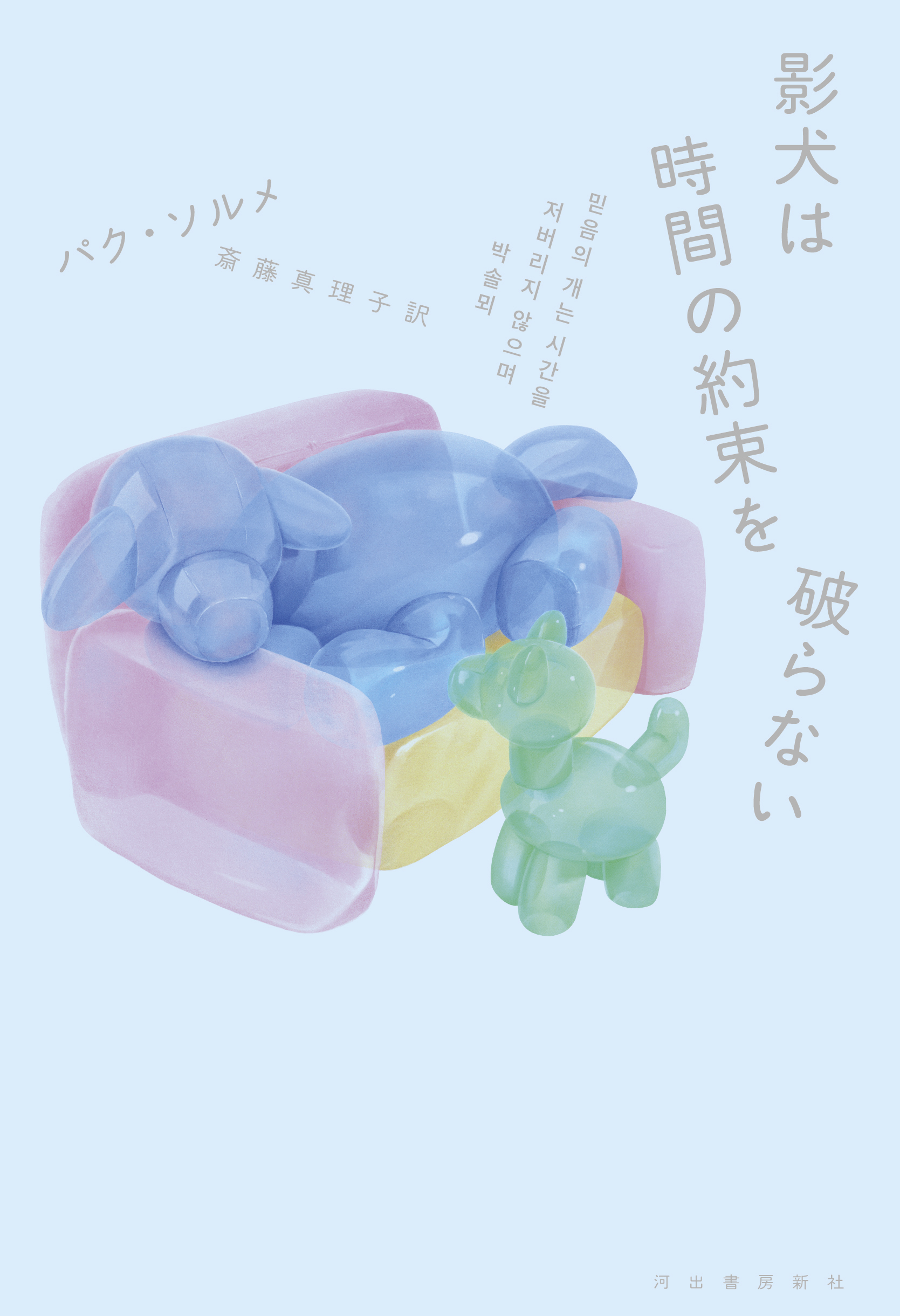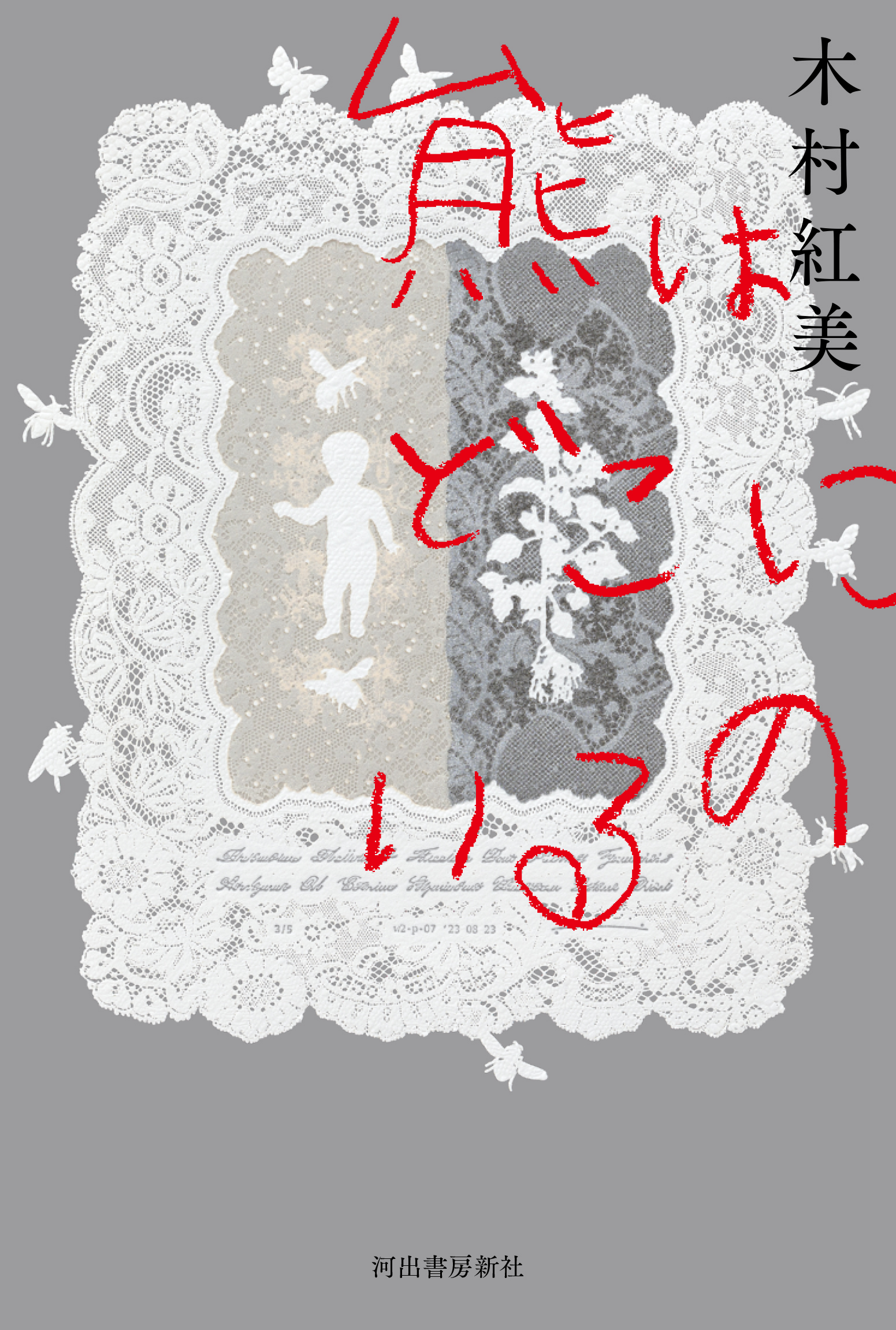書評 - 文藝
マリリン・モンローを通して女性の差別問題を描いた小説『マリリン・トールド・ミー』とは? 花束書房の代表・伊藤春奈が紹介
評者:伊藤春奈(花束書房/文筆家・出版業)
2024.08.21
山内マリコ 著
評:伊藤春奈(花束書房/文筆家・出版業)
マリリン・モンローをフェミニズムの視点で見直す動きがあるとどこかで読み、調べてみようと思いつつ数年が経ち、気づくと「誰か書いてくれないかな」になっていた。Netflixのドキュメンタリーにがっかりしていたところ、まさに読みたかった本が登場した。フェミニズムの古さと新しさに敬意を払い、この先に受け渡すような小説だ。
主人公・瀬戸杏奈の大学生活はコロナ禍のステイホームで幕を開け、ひたひたと迫りくる死のリアルを逃れようとSNSを眺める日々。そんなある晩、あのマリリン・モンローから電話がかかってくる。映画会社の男たちに搾取されていること。頭の悪いブロンド女というステレオタイプばかり演じさせられること。女が稼げる仕事の少なさ。誰も私の話を聞いてくれないし、世界中が私を軽く扱う――。ありえない電話に驚きつつも、軽妙で知的な愚痴に杏奈は魅了される。
いつしか着信は途絶え、3年生になった杏奈はジェンダー論のゼミで「目覚めて」いく。だがじつは、Twitterやゼミ生の会話から「正解」を把握しているだけの、いわばAIフェミニズムだ。それはマリリンの素顔を垣間見た杏奈が、彼女を消費する現代人に怒るのとは矛盾したふるまいでもある。先生からは、過去の女性を知るには時代背景も詳しく知る必要があると、文献の読みの荒さを指摘された。杏奈はその言葉を胸に、卒論でマリリンを書くため本格的に調べ始める。読んでは考え、ふと現実に戻ると社会がいつもと違って見えたりもした。
杏奈の卒論を通して明かされるマリリンの素顔は、従来のイメージを大きく塗り替える。じつは内気で読書家。演じることに真摯で、業界の搾取構造を変えるために独立プロを作るなどして闘った。全米にヌード写真が出回ると、恥じてなどいないと断言して社会を揺さぶった姿は、60年代の性革命を先取りしていた。性被害を告発した――。時代も国籍も超え、実在した女性たちの声とともに浮かび上がる実像はとても身近で、親しみがわく。それを消費してはゆがめ、虚像を再生産してきたのが、映画会社やメディア、そして私たち大衆だった。
4年生になった杏奈は、「アップデート」されて見える下級生にひるんだりもするが、じつは杏奈が少し成長している。マリリンの心の底に降りていき、傷を知ったことで、性被害を告白した下級生と対話するようになるのもその一例だ。マリリンとしたようにフェミニズムの言葉を交わし、今度は「話の合う友達に考えをぶちまけるみたいに」、卒論を書き上げたのだ。
過去と現在を行き来しながらフェミニズムを知ると、変わらぬ差別構造に絶望することもある。ただ、それ以上に大きな宝をもたらしてもくれる。例えば、目の前の人間の痛みを想像できること。世代を超えて強化されているように見える「分断」が、まやかしだと気づくこと。埋もれてきた声に耳を澄ますと、差別構造にわずかなヒビを入れることができるということも。入ったヒビは、後世の誰かが、いつか見つけてくれる。