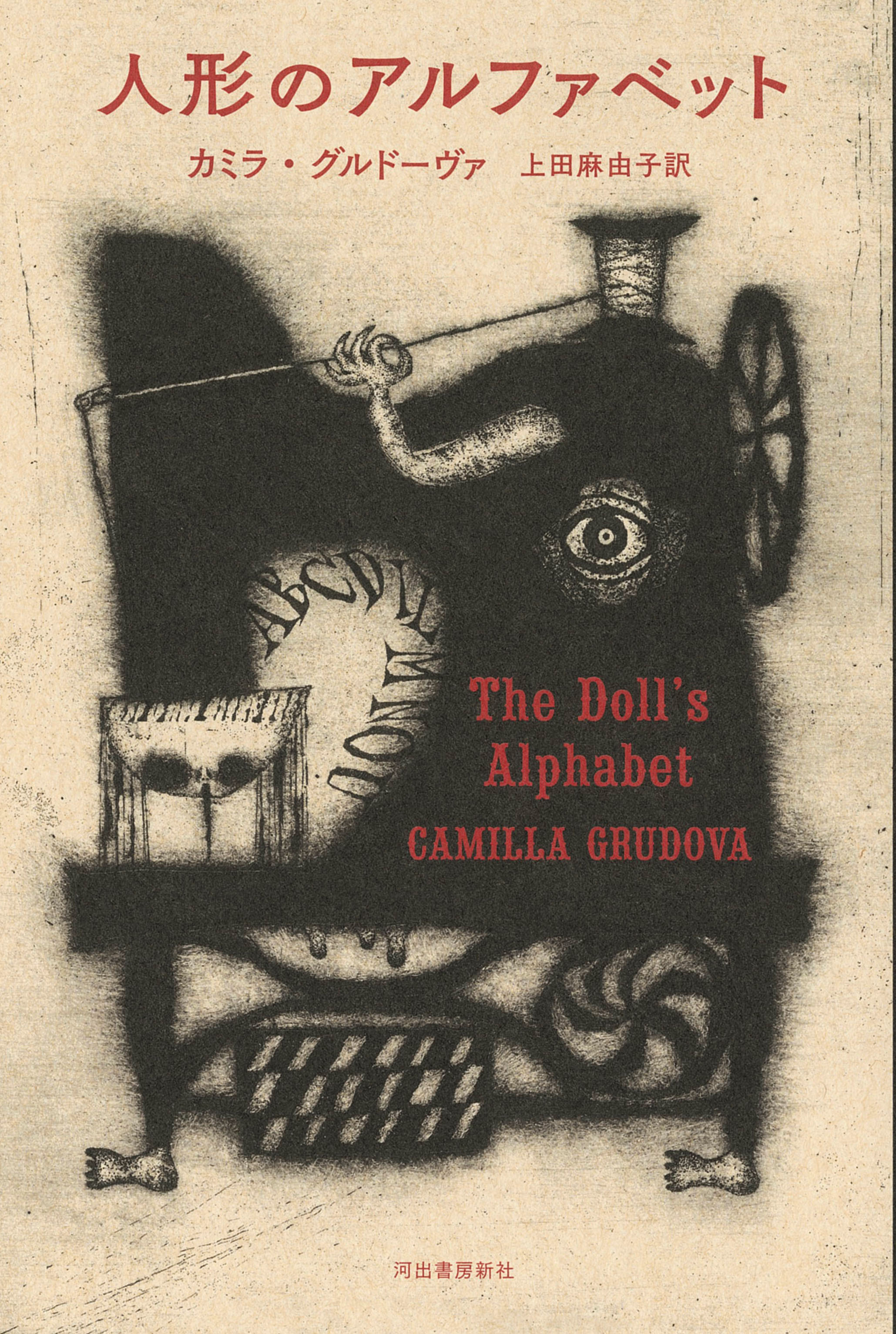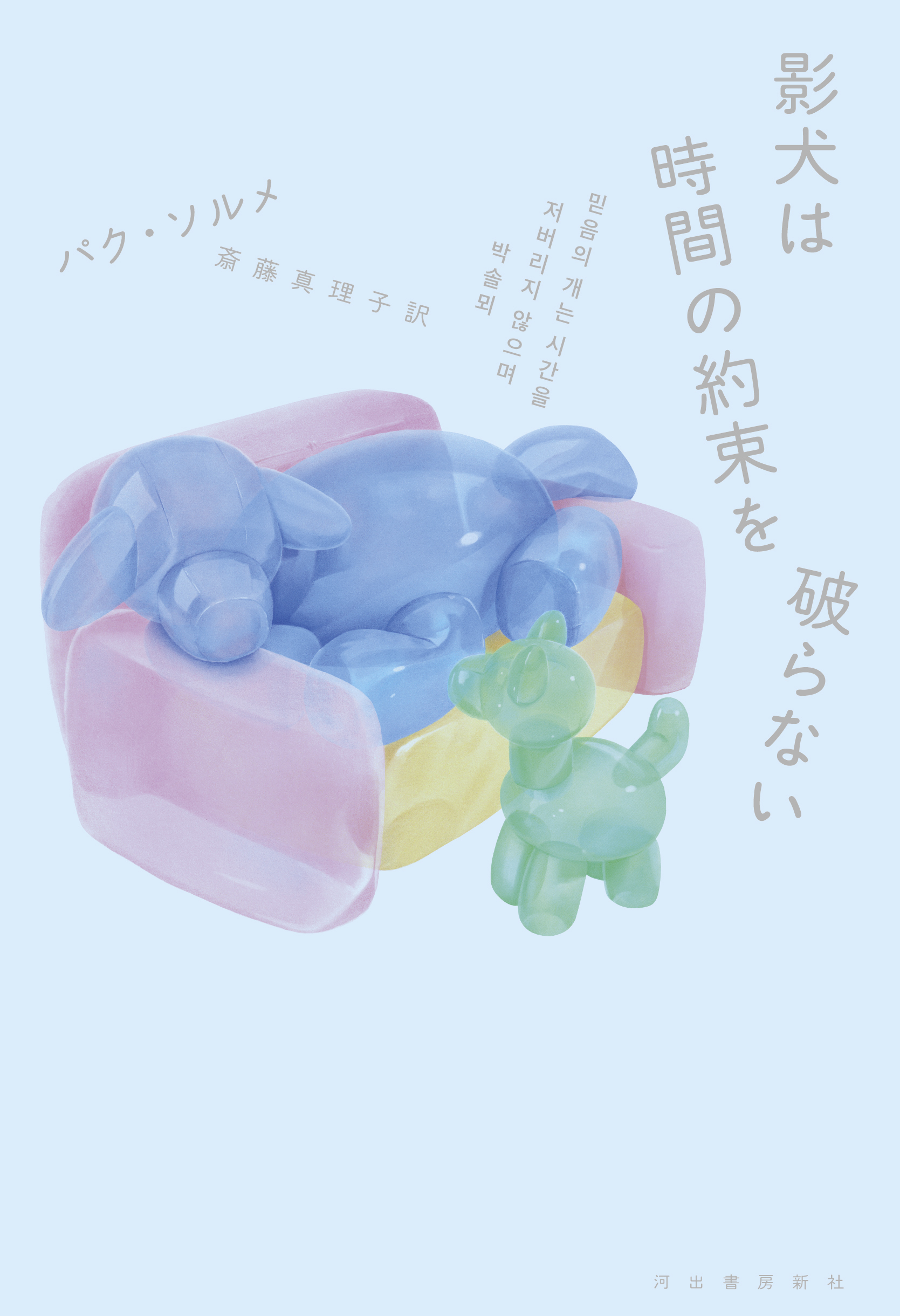書評 - 文藝
紫式部、現代京都でオペラをかます!? 直木賞作家・河﨑秋子が語る、古川日出男のワンアンドオンリーな快作の魅力
評者:河﨑秋子(作家)
2024.08.22
古川日出男 著
評:河﨑秋子(作家)
パンデミック。一瞬、その意味を正確に思い出せず、そんな自分に驚いた。たった三、四年前の新型コロナ騒ぎに伴う制約や息苦しさを、進んで記憶に留めておきたいと思えなかったせいか。それとも、人は過去の厄災を忘却したがる傾向にあり、ゆえに逐次受傷を繰り返してきたのか。筆者個人の忘れっぽさを棚に上げ、視点を広角にした上で考察したくなるのは、間違いなく本書の影響だ。
オペラと題されただけあって、本書は登場人物が歌と共に語る物語部分と、その創作にまつわる作者の雑記によって構成されている。そう書くと単純なネタばらし付きの戯曲と思われてしまうかもしれない。しかし、実際にはその二つのパートを隔てる壁は薄く、互いの鼓動が響きあって紙を波打たせている。その強い拍動は希少かつ繊細なバランスに基づいて本書から響く。まさにセッションだ。
物語部分の登場人物がまず魅力的だ。デニムとGショックで身を整えた偉丈夫・小野篁。時に鶏の頭部を具え、人間最初の火を通じて金閣寺に火を放つ幻想を手放さない(三島ではなく)二島由紀夫。みどりの黒髪をばっさり切ってヘアドネーションに奉じたうえ、ヨガと英会話を新たな武器とした紫式部。パンデミックの京都で彼らは出会い、そして喉と精神を震わせて唄う。
更にそこに、京都に、また人類における歴史が斜めの糸として絡まり、それは複雑なモザイク状の背景と化して、三人の歩みを立体視のように浮かび上がらせていく。例えばネアンデルタール人。例えばオオサンショウウオ。そして応仁の乱。
三人には共通点がある。三つの啓示をそれぞれ宿していること。そして黒い牛革の長財布をなぜか所持していること。その財布の中に入っている金は消費してもいつの間にかもとに戻って(繁殖している、とも表現される)いる。これによって突然京都市中に生身の肉体を具えて降臨した彼らは、貨幣の力をもって生存と活動の推進力を得る。
ただし、紫式部の財布にある紙幣は、無数の二千円札だけなのだ。そこには沖縄の首里城守礼門と紫式部の肖像、そして源氏物語絵巻の一部が描かれている。この紙幣を詳細に思い出せる人は多くはないだろう。様々な事情でレアな存在になったその紙幣を、紫式部は令和で存分に使う。自分が描かれた二千円札でヘッドスパに通い、タクシーに乗り、やがて自分の墓とすぐ隣に建てられた小野篁の墓を見に行くのだ。
紫式部が虚構の語りによって人心を惑わせたかどで死後は地獄に堕とされた、という説はかなり昔から存在するらしい。仮に昔の言説が正しいとして、フィクション・ライターがおしなべて地獄に堕とされる運命ならば、全ての先陣を切った紫式部が斯くのごとく強靭であることは、後の世の全ての物語作家たちにとって頼もしいことこの上ない。彼女と二人の同胞が吠えるセッションがページを繰る指先に心地よく伝わる。まさにワンアンドオンリーな読書体験だった。