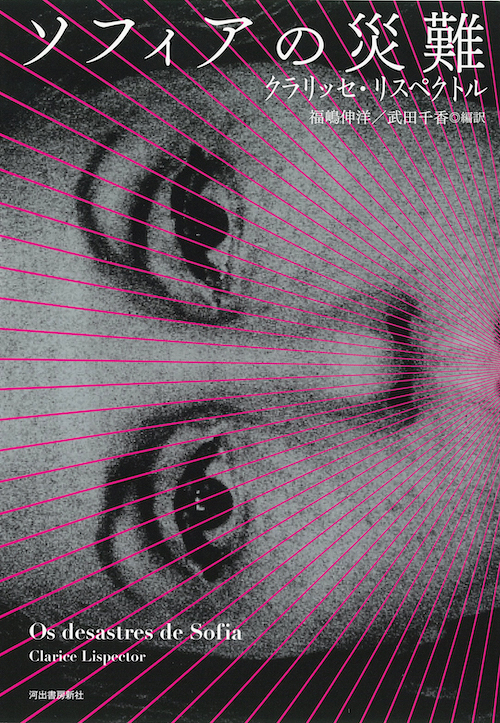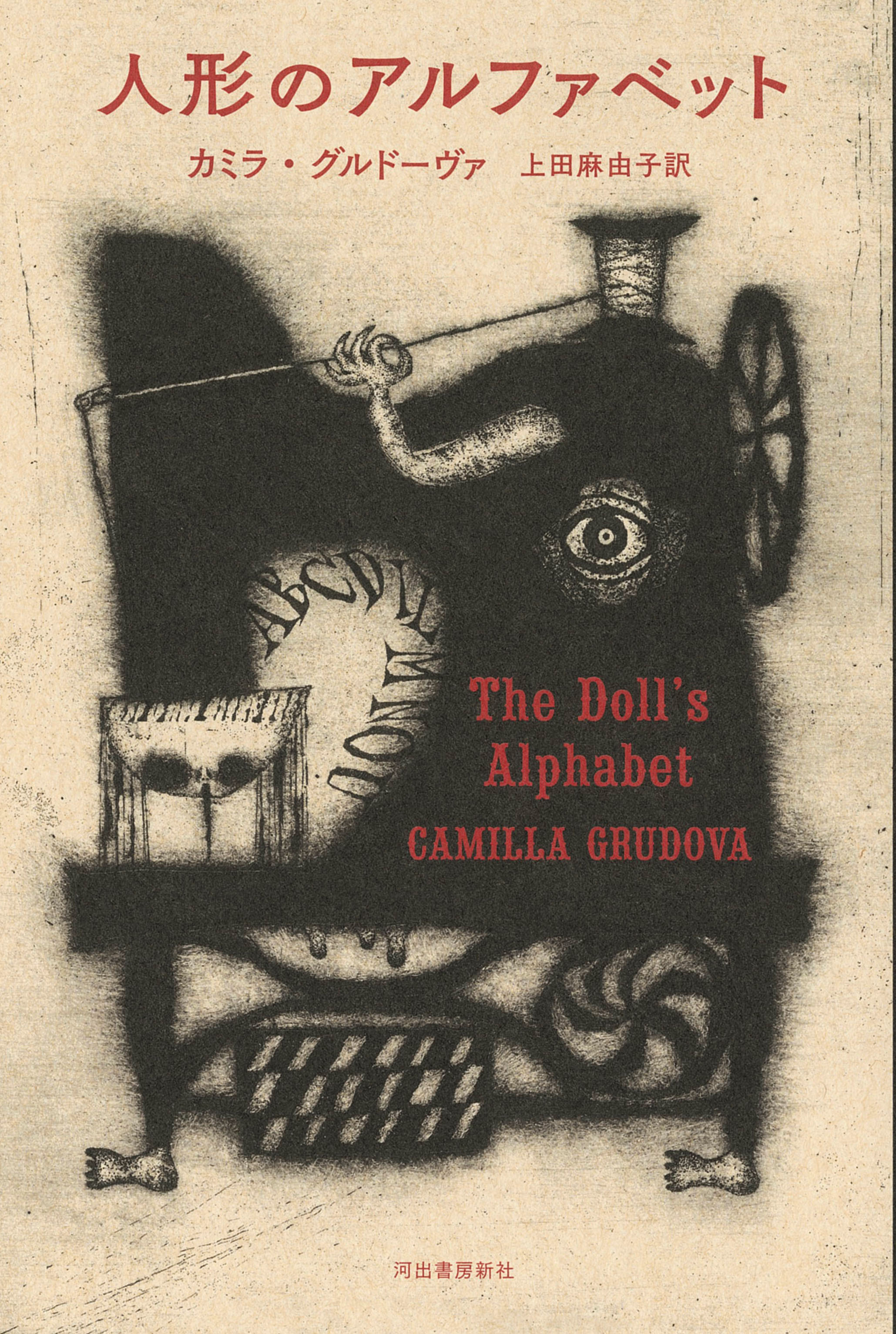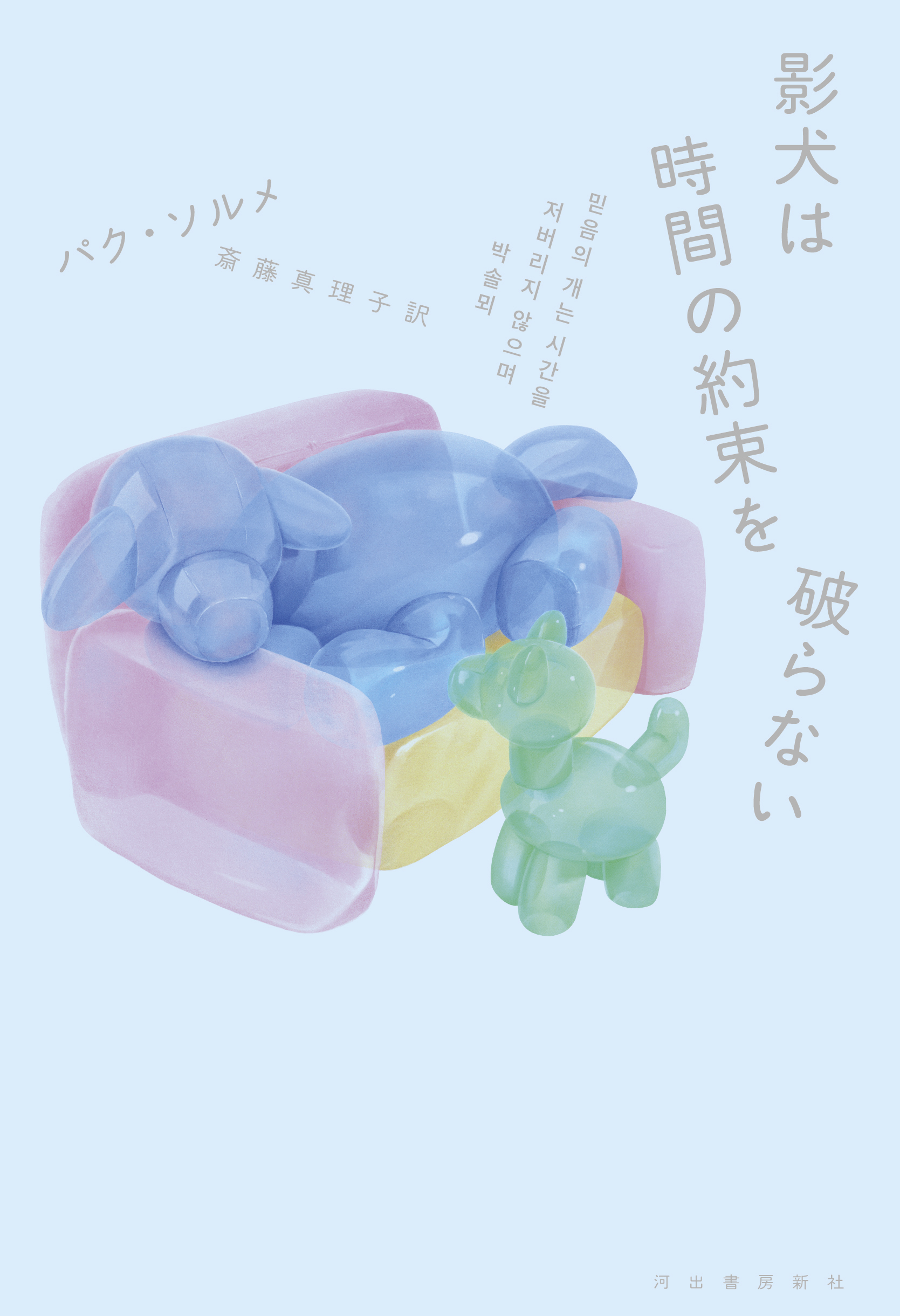書評 - 文藝
小学校の先生に恋した少女の動揺と混乱の日々 極限の理性を書いた作家・リスペクトル作品の読みどころとは?
評者:島本理生(作家)
2024.08.23
『ソフィアの災難』
クラリッセ・リスペクトル 著
福嶋伸洋/武田千香編 訳
評:島本理生(作家)
クラリッセ・リスペクトルの小説を途中まで読んだという友人が言った。
「難解だけど、自分の中でピースが一つ合ったら、その瞬間にすべて理解できるような気もする」
それはリスペクトルの小説の手強さと正確さを両方言い表しているようで、なるほど、たしかに言い得て妙だな、と納得した。
私自身、リスペクトルの小説を理解するためには感覚と理論のどちらを用いても、足りないように思う。このたび刊行された短編集『ソフィアの災難』の翻訳家の武田千香氏は、巻末の解説で「感性」で読むことを提案している。感性とは言うなれば感覚と理論の間の、純粋な咀嚼段階である。それを踏まえると、小説自体が難解というよりも、難解なものを忠実に描写しているというほうがしっくりくるかもしれない。
表題作「ソフィアの災難」は小学校の先生に恋した少女の話だが、その心理は単純ではない。「私」は「軽蔑するような素振り」をし、「背が高く不細工」な彼を「私の人生を捧げるべき男性である」と受け止める。しかし、その愛は思いもよらなかった展開によって「私」に動揺と混乱をもたらし、聖なる深層へと導いていく。誰もが想像しえなかった成長の苦痛が鮮やかに激しく描き出されている。
「美女と野獣、または大きすぎる傷」では、物乞いとの会話を通して「私がしているのは人生ごっこ」だと気付いてしまったカルラが、裕福な夫との結婚は「社会面のコラムに身売りした」ようなものだと実感し、「自分があまりに、あまりに金持ちだと感じ、気分が悪く」なる。リスペクトルの精細な描写は、他者との比較によって自己と向き合わざるをえなくなった内面の解剖図のようだ。
印象的なのは、いくつかの短編で、登場人物の「顔」が失われる瞬間である。修飾をはぎ取られたとき、人は自己認識よりも遥かに空虚で曖昧な存在と化す。一方で、リスペクトルの描写はそれを否定してはいない。なぜなら誰にとっても「人生はきれいごとではない」ことをおそらくは書き手自身が実感しているからだ。
ものすごく不幸に囚われているわけではないが眠剤で無理やり終わらせなければならない一日や、眠りと死が肉薄する夜の深淵もまた、私たちはなんとか見過ごすことで生きている。「脱走」や「今のところ」はその無音の隙間をくみ上げる。優れた観察眼や感性と、巧みさが混在している。「P語」は英語教師のシジーニャが汽車に乗ると、男たちの会話が「おぽまぱえぺ」といったP語で聞こえ始めるという、ブラックユーモア溢れる短編だ。女性が暴力的な理不尽に晒される世界を少ない字数で見事に書き上げている。
物事を正確に捉えすぎた人というのはしばしば、おかしくなったという扱いを受ける。が、実際は「私」以外の世界が間違っている場合もままあることは見過ごされてはならない。リスペクトルはその極限の理性を書いた作家だ。