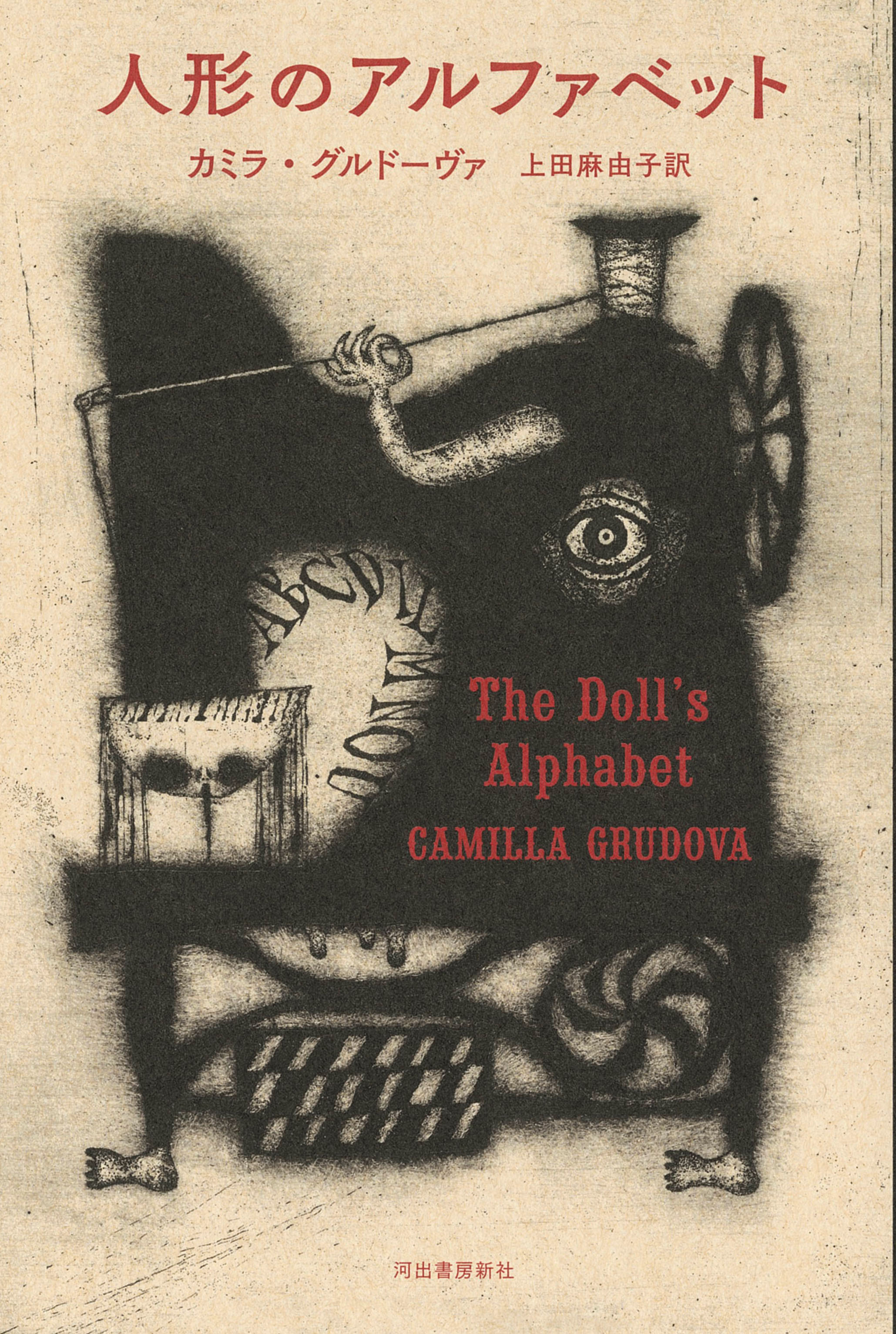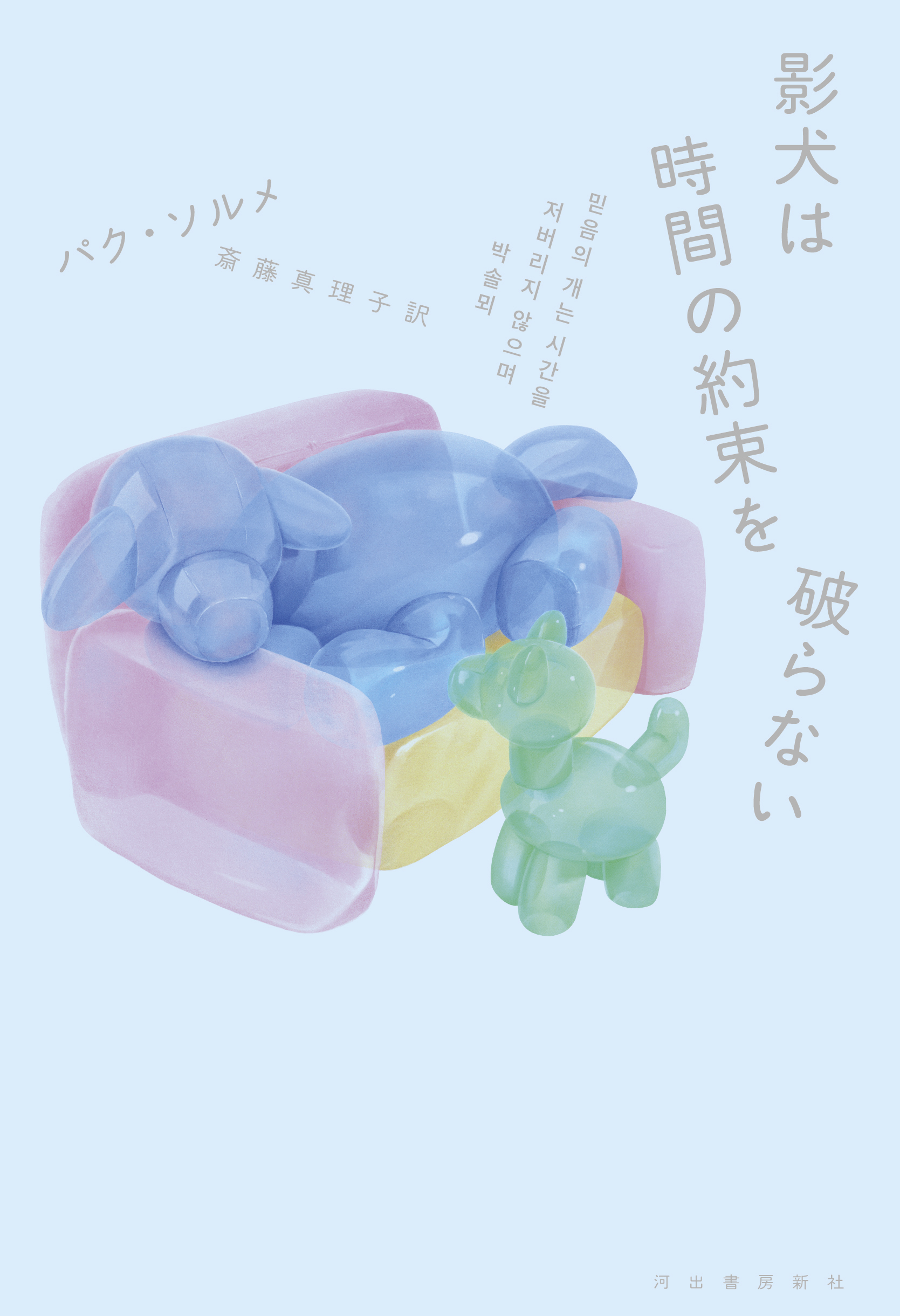書評 - 文藝
わかりやすくない有害な男性らしさが生む混乱を描く 俳優・長井短の小説『ほどける骨折り球子』を児玉雨子が読む
評者:児玉雨子(作家、作詞家)
2024.08.27
長井短 著
評:児玉雨子(作家、作詞家)
「きっと何者にもなれないお前らに告ぐ」という名台詞がアニメファンの間で話題になったのは何年前のことだろう。顧みれば、当時の社会は「何者かになるべきである」という課題に頭のてっぺんまで浸されていたように思う。現在ではあらゆる差別を改めて問い直すムードがあるが、これは分解してゆけば「なぜ、何者でもないまま私と君でいられないのだろうか」という苦悩がその核にあるのではないだろうか。かといって、私たちの社会は、今までを洗い流しすべてを忘れて清算できる大きな栓があるわけでも、そもそも簡単な構造で出来上がったわけでもない。
本書の表題作は主人公:勇の配偶者球子との慈愛とジェンダー勾配が主題である。相思相愛の夫妻が互いを守りたいと想い合うやさしさがやがて「守りバトル」という戦いへ変容してゆくようすは、ごく自然な流れで、しかし不穏な予感を匂わせながら進んでゆく。球子はいとしい天使から不気味な魔女へ、そして切実な叫びを抱えた人間へと、痛みを伴いながら勇に再認識されてゆく。
同僚の遠山と比較されるように、勇は決してマスキュリンな存在としては描かれない。男性社会の中では強者ではない、しかし女性より確実に有利なジェンダーであるという事実と彼が対峙したとき、物語に混乱が生まれる。絡まった糸の玉を解くように勇と球子は言葉を交わし、互いを開陳するラストは固唾を飲む。わかりやすくない有害な男性らしさとの対峙に、本作はひとつの未来を示唆している。
ホラー映画撮影で出会った俳優キヌと幽霊の「私」のシスターフッドが語られる「存在よ!」では、すでに私であってきたのに、他者や構造によって透明化されてきた存在たちが示唆されている。売れない俳優としてキヌは主役の吹き替え(本作では音声アフレコではなく、主演俳優の代わりに危険なシーンを演じるスタントダブルのことを指す)を演じ、ここにモチーフ化された「私」――作品内に作られた役――主演俳優――吹き替え俳優と、幾重もの存在のレイヤーが生まれるのが特徴的である。「私」はのちに椅子と名を改めるが、この名前にもひとつの椅子を何人もの人間が奪い合い、時に重なって座り、その座られた椅子は存在を覆われ見えなくなってゆくという演劇・芸能の構造が巧みに組み込まれている。
キヌや周囲の人間たちがひとつずつ椅子の存在を認識してゆくたびに、恐ろしい「うらめしや」という音でしかなかった椅子の声は言葉として立ち現れる。というより、ずっとそこにあったのだが、やっと私たちが言葉として聞き取ることができるようになった。そしてこれは椅子とキヌの間で完結せず、読者の私たちにも物語が開かれている。
こうして読み返すと、二篇とも不可視化されてきた存在との関係の再構築だけでなく、やわらかな希望がそれぞれひとつずつ光りながら、現在へ開放された物語であるという構成も共通している。私たちは、針でついたような小さな穴から少しずつ現在を押し広げてゆく。