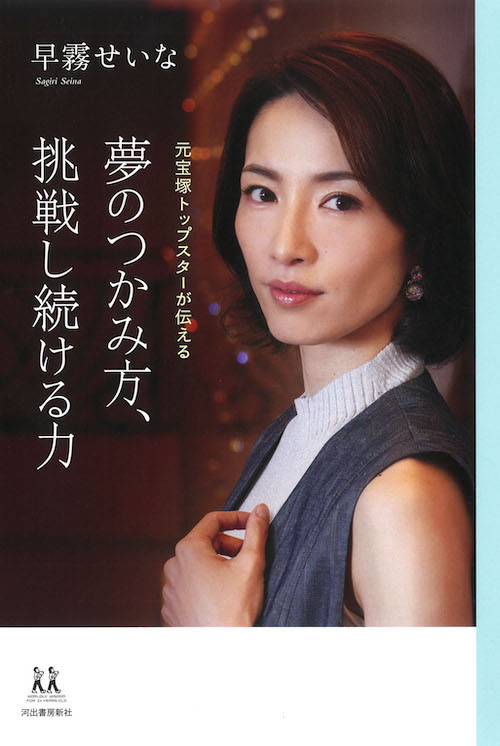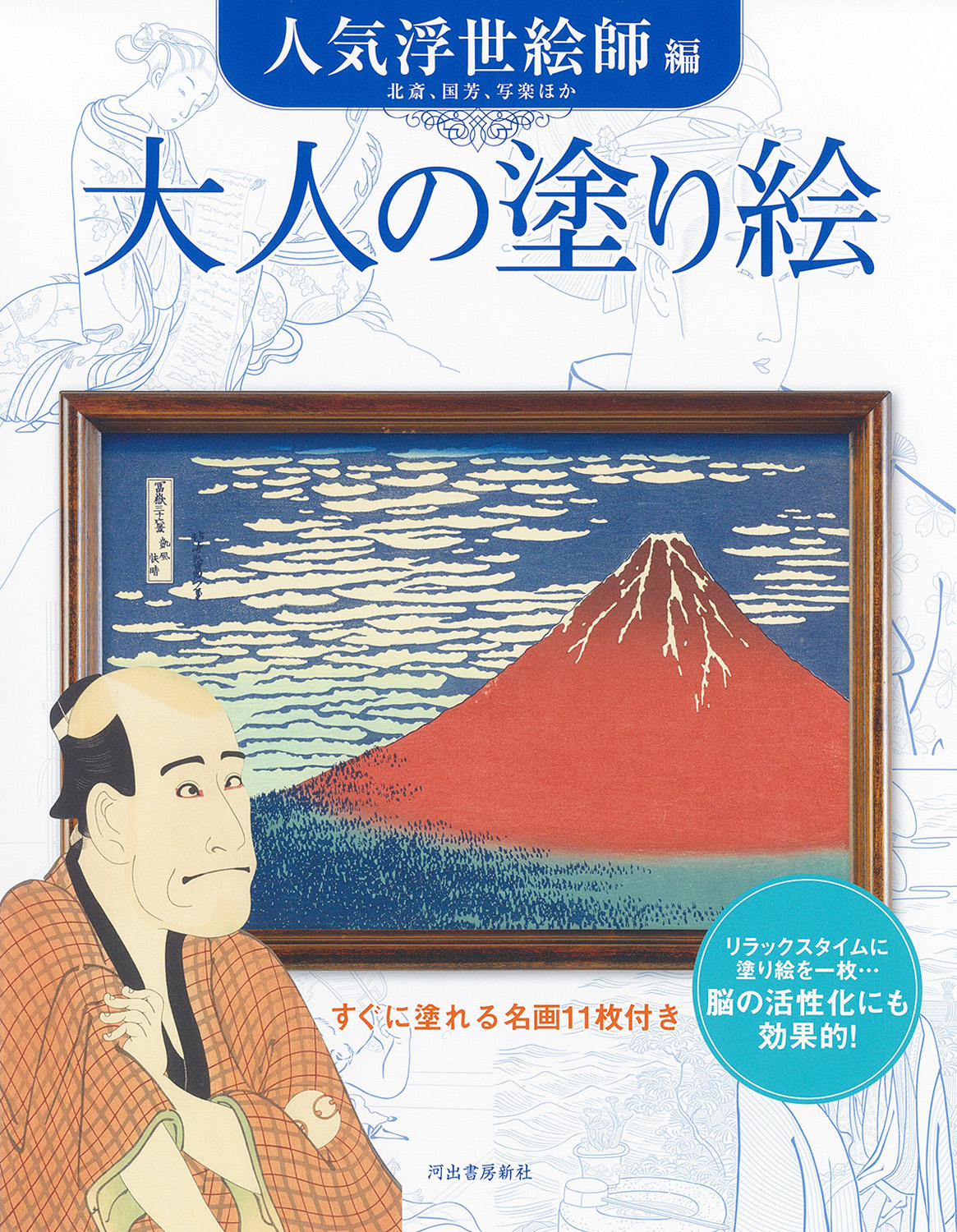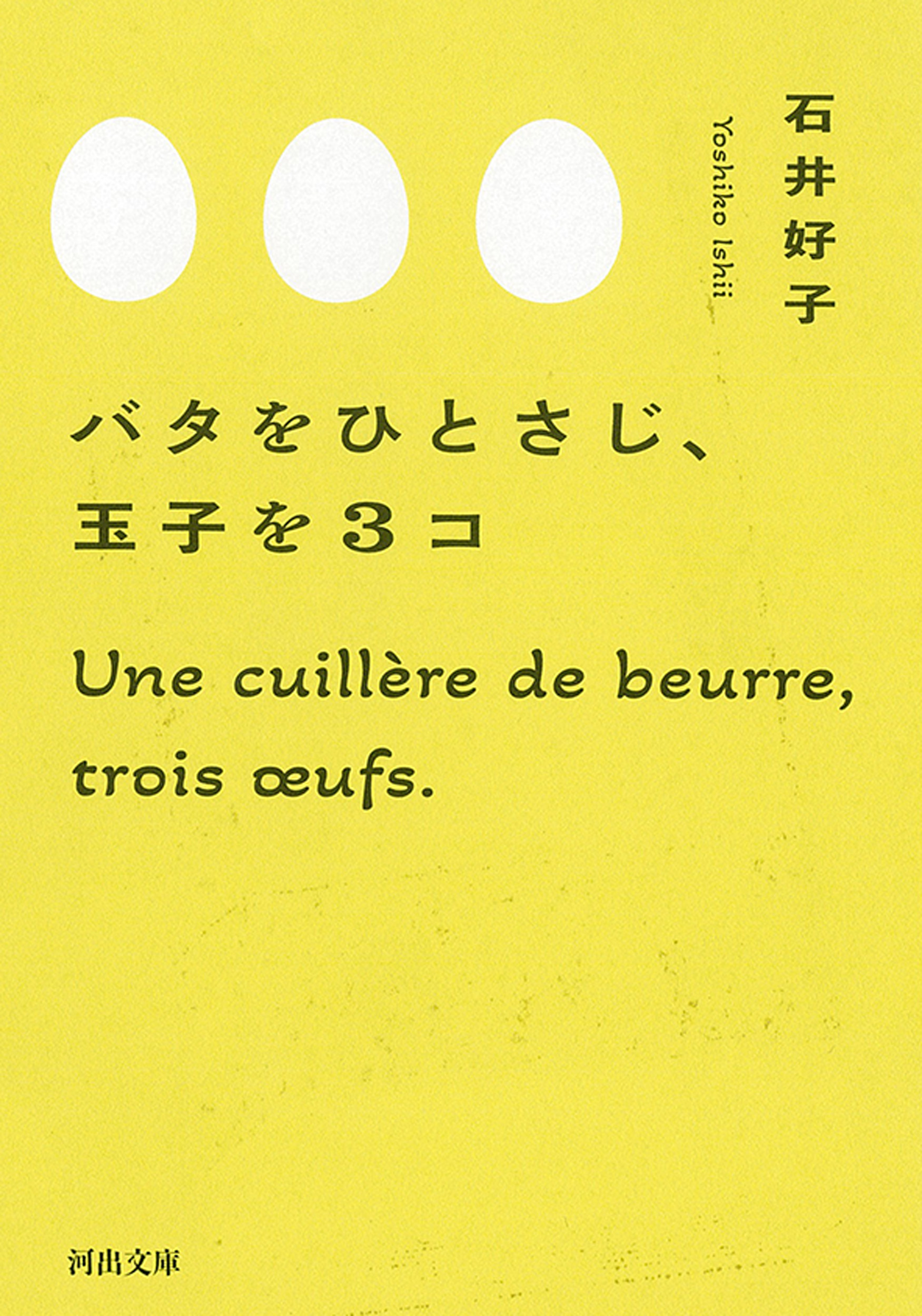ためし読み - 日本文学
岩谷時子の自伝的名エッセイ『愛と哀しみのルフラン』刊行記念!冒頭3篇ためし読み無料公開!!
岩谷 時子
2024.10.29

伝説の歌姫・越路吹雪を生涯にわたり支え、「愛の讃歌」訳詞や歴史に残る名曲の作詞も多数の岩谷時子。
越路吹雪生誕100年の年に、すべての宝塚ファンにとって感動の記録である『愛と哀しみのルフラン』を記念復刊。
単行本に収録している「誰もいない誕生日」「越路さんがいて私がいた」「毛皮そして越路吹雪さん」愛情あふれる冒頭の3篇を、ためし読みとして無料公開いたします。
誰もいない誕生日
花散多風雨 人生足別離
花に嵐のたとえもあるぞ、さよならだけが人生だ、と井伏鱒二先生が訳された唐詩がある。七年前に母を亡くしたあと、心の支えとしてただひとり残された友人越路吹雪さんまで失った私は、もう失うものは自分の生命だけになってしまった。
百ヵ日から四日後の二月十八日は彼女の誕生日だった。毎年誕生日には、親しい友人達が越路さんの家に集まった。顔が揃うとハッピーバースディを合唱し、鯛の尾頭つき、煮物、中華料理の前菜などをおいしくいただき、やがてお寿司屋さんがネタとおひつを担いで威勢よく現れる。
「待ってました」と、お酒も入って一層賑わうのが近年の習慣になっていた。
いくつになっても童女の心を持っていた越路さんは、パーティのさなかに私をベッドルームへ引っ張って行き、小さな声で、「私いくつになったの? 本当にいくつ?」と耳もとでささやくこともあった。
他に誰もいないのだから、大きな声でいってもいいのだが、私も同じようにできるだけ小さい声を出して年齢を教えたものである。
これからは、残された者たちが一年に一つずつ年をとっても、彼女だけは、もう決して年をとらないと思うと、彼女が天国で、老いて行く私たちを見て、いたずらっぽく笑っているような気がする。
こんなに早く別れが来るなら、もっと二人で話すことがあったのではないかと、悔やまれてならない。私が年上なのに、彼女は、姉のようにしばしば慰めてくれたものである。
「きょうだいなんて、いてもしようがないよ。親族とかかわりあう煩わしさをとるか、一人の淋しさをとるか、人生は二つに一つの道しかないんだからね。一人の孤独より多勢のなかの孤独のほうが怖いよ」
越路さんの舞台姿は一見豪放にみえるが、舞台に出る前は、いつも初舞台を踏む人のようにおののき、それは千秋楽までつづいた。
舞台を、それほど恐れていながら「スポット・ライトのなかにいるときだけが、本当の自分のような気がして、ホッとする」ともいう人だった。
私はリサイタルやミュージカルに出演しているときの彼女の、あの重苦しい、責任感にさいなまれている姿や、連日の苛酷な緊張を目の当たりにしながら、ここ数年「こんな仕事をつづけていたら寿命がちぢまる。いつ、やめさせればいいのだろうか」と、深刻に思いつめていた。
「もう仕事は、いやだよ」と、本人も近年しばしば口にした。
「それ本当のこと? ぜったいに本当?」
「うん、本当の本当」
こんな会話が私たちの間で交わされるときもあったが、他人にいわせれば「そうはいっても彼女は舞台に立つことが生甲斐なのだ」という意見が多かった。私も、彼女が自分の生甲斐である舞台にうちこみ、疲れ果て、「やめたい」という言葉が出るのかもしれないとも思い、また一方では、本当にやめたいと思っているのではないかと悩みつづけた。
そんな彼女が心から解放されストレスを解消させることができるのは、最愛の夫内藤法美さんとの外国旅行だった。大好きな外国で彼女は内藤美保子と呼ばれる一人の女になり、ホテルの夜は、次ぎの目的地への荷作りと洗濯に追われる良き妻であったようだ。演劇やミュージカルも精力的に観て歩き、帰国したあとの仕事の糧にすることも忘れなかった。
私のために夫妻で選んでくれたお土産を、「自分が欲しくなったから、少し使ってからあげる」と、後ろ手にかくす様子も、宝塚時代と変わらぬ愛らしさに見えたものである。
数日後の死を前にしたある日、彼女は弱々しい声で、突然ひとり言のようにいった。
「ねえ、私を、もういらないの?」
病気になった自分を、もう誰も舞台で必要としなくなったのかという、この質問に、私は胸を衝かれ、けんめいに涙をこらえた。
「なにをいうの、クリスマス・ショウも来年の三月も六月も九月も舞台がきまっているのに」
彼女は黙っていたが、私が初めて吐いたそのしらじらしい言葉を、どんな思いで聞いていたかと考えると、女優というものの業が限りなく哀れでならない。
主のいない誕生日がことしもまた訪れる。
越路さんがいて私がいた
越路吹雪さんが、まだ元気なころ、私は、ふと彼女にいったことがある。
「もう両親もいないし、やっぱり私、熱海辺りに老人マンションを買っておこうと思うの。医者も看護婦もいて、面倒をみて貰えるのですって」
なに気なくいった言葉だったが、越路吹雪さんは突然、
「なんて情けないことをいうの! 私たち夫婦がいるじゃないの。どうして、そんなこと考えるのよ」と、怒ったような口調で私を責めた。
越路さんと私とは、四十年近く、互いに深い友情で結ばれていた。女同士の友情は続かないと、よくいわれるが、私たちは宝塚歌劇団の屋根の下で出逢い、以来、文字どおり喜びも悲しみも共にして来た仲であった。
越路さんには、結婚という大きな転機があったが、私たちの場合、かえってそれが友情を深める絆になり、大人の女同士の友情は年と共に成長し深くなっていったとさえ思われる。
私は、心の中では、いつも保護者のつもりでいたが、人生経験は越路さんのほうが豊かで、教えられることが多かった。
長い年月の間、互いに裏切ることも裏切られることもなかったのは、ひたすら信じあっていたからではなかっただろうか。この信頼感は、やはり長い歳月の土壌の上に培われ積み上げられてきたものだったと思う。
そんな私が、老人マンションを買おうといい出したのは、舞台という大事業を抱え、最愛の夫を持つ人に、迷惑をかけてはならないと、かねがね思っていたからだった。
私は長年、老母と暮らしている間に、人間の老いというものを、この目で、まざまざと見てきた。母を、この上もなく愛していた私は、子としてできるだけのことをして、それを苦痛とも思わなかったが、それでも「真実の子にしか、この世話はさせられない」と思うことが、いくつかあった。
越路さんの両親は六十歳前後で亡くなり、彼女は人間が老いさらばえていくさまを、身辺には見ていない。
「あなたは、どんなに大変なものか知らないからよ。あの思いは、あなたにはさせられない」
と、口まで出かかった言葉を呑みこんだあと、私は彼女の好意をありがたいと思い、
「そうね、ありがとう」
話は、それきりで終ったが、越路さんは、まごころのある、やさしい人だった。
とくに、私が母を亡くしたあとは、なにかと、いたわってくれたものだった。
「今日は、なにを食べた?」
「ライスカレーと野菜サラダ」
「ひとりで?」
「…………」
「そんな侘しいことしないで毎晩家へ来て食べればいい。夫婦二人で食べるのも、あんたと三人で食べるのも一緒なんだから」
頑固な私は、それでもできるだけ一人で食べるように心掛けていた。
それが私の生き方だったし「どんなに親しくても、その人の生活に土足で踏み込んではいけない」というルールを、私は自分で作って、貫き通してきた。そして今、それだからこそ、私たちは友情を全うすることができたのだと思っている。
特定の人と親しくしていると、当然のことながら周囲からの嫉妬や中傷がある。私たちにも、それがなかったとはいえない。しかし、それさえも難なく乗りこえてこられたのは、二人とも女くさくない、さっぱりした人間で、どんな話が耳に入っても、確かめあうことさえしなかったからではなかったか。
そんな私たちの性格を見ぬいて、バカバカしくなったのか、いつか中傷する人さえ、いなくなった。
「私たち、今になってケンカ別れなんかしたら、みっともないから、気をつけようね」
などと、ときどき越路さんがいっていたところをみると、彼女の耳にも、いろいろな中傷が入った時代があったのだろう。
越路さんが結婚すると決まったとき、私は二つの条件をつけた。
「離婚と、お葬式の世話だけは、させないでね」
それなのに彼女は、約束を忘れて、一昨年の十一月、名実ともに花のさかりのまま、忽然と逝ってしまった。
今年の秋は、早くも三回忌を迎えるが、私にはまだ、病中のことを詳しく書く余裕はない。
月日と共に、心の空白は拡がり、かけがえのない友を失った哀しみは、深くなるばかりである。
別れなければならない運命がそうさせたのか、晩年の越路さんは、それまで以上に優しかった。
大好きだった海外旅行で買ってくる衣類も、あとで私が着られるようにと、地味なスタイルのものを、えらんで買っていた。
エレガントで、すてきな大人の女性でありながら、子供のようなところがあった。
私が持っている新しいハンドバッグが気に入ると、台所から紙の手さげを探してきて、バッグの中身を全部、手さげの中にあけてしまい、私のバッグを嬉しそうに抱えて自分の部屋へ運んで行ったりした。
私は消えたハンドバッグの代わりに紙の手さげを持って帰る始末になるのだが、今では、その可愛らしい、わがままさえも、なつかしい。
越路さんに逝かれたあと、私は三十五キロという、前代未聞の体重になった。
常日ごろ、仕事に追われて、最高に人づきあいの悪い私であったのに、暗闇のなかから、たくさんの古い友人たちが現れ、今、私は、あたたかい多くの友情に支えられながら、辛うじて、その日その日を送っている。
「おっ母さんも死んだし、越路さんもいなくなって、もう張り合いがない。余分の人生を送っているようなものだわ」
といえば、たちまち友人の一人が叱ってくれる。
「なにいってんの。まだしなければならないことが、あなたの人生に残っているはずよ。しっかりしなさい」
人生のなにものかを、すでに知っている友人たちの激励は、ありがたい。
私は今まで「友だち」という歌の歌詞を、いくつか作ってきたが、そのなかに、
友だちは いいもんだ
目と目で ものが言えるんだ
という一節があった。
越路さんとはもう、目と目でものが言えなくなってしまったが、生涯で、これほど充実した友情を持たせてもらったことを、私は感謝している。
毛皮そして越路吹雪さん
毛皮は昔から、女ごころをくすぐるものとされているが、女の子ごころをもくすぐるものらしく、私が小学校低学年のころ、白い兎の衿まきが流行したことがあった。
猫も杓子も子供たちは同じパターンの白兎を首に巻き、どこの商店街も洋品店の店先きには、ずらりと白兎が並んでいた。
年の暮だったような気がするが、私の両親も一人娘に、この可愛らしい衿まきを買ってやろうと、私を大阪心斎橋筋へ連れて行った。
「いらっしゃい、いらっしゃい」
店員さんは愛想よく私を取り巻いて、当然のことのように何本か白兎を持ってきたが、私は一向に興味を示さず、一人であちらこちらを物色したあげく、緑いろの繻子地に桜の花を刺繍した真綿入りの薄い衿まきを抱えてきた。
「これがいい」
繻子地だから肌ざわりも冷たく、それは新派の舞台にでも出て来そうな古風なものだった。
「嬢さん、毛皮のほうがぬくいでっせ。さわってみなはれ、ふわふわしてまっしゃろ」
「あたたかくない、こっちのほうが、あったかい」
あたたかくないといわれて、店員も両親も顔を見合わせて笑いだし、とうとう繻子の衿まきを買ってもらった記憶がある。
毛皮を「あたたかくない」といった話は、ながいあいだ、我が家の笑い話の一つになっていたが、話題の繻子の衿まきも、よれよれになるまで、たんすのどこかにいつまでも残っていて、私に幼いころの冬を思い出させてくれたものである。
たぶん子供ごころにも、みんなと同じ白兎より、自分の気に入ったもののほうがよいと思ったのだろう。
私には昔も今も、そういうところがあって、好みに合ったものなら、それが流行のものでなくても平気で身につけるくせがある。
毛皮との縁は小学生のころに、こうしてはぐれてしまい、その後は戦争があったりして、毛皮どころではない生活ばかりがつづいた。
戦後、東京に住みつき、平和になった街で毛皮を見かけるようになったが、あれは私が身につけるものではないと思い込んでいた。毛皮は「私はお金持ちです」と宣伝しているようなもので、うとましいとさえ思っていた。
それが、ひょっとしたことから毛皮店へ行かねばならないことになった。
越路吹雪さんが「毛皮のコートが欲しい」と、いい出したのである。
宝塚をやめて、東宝の女優さんになった越路吹雪さんは、当時二十六、七歳になっていただろうか。共に困苦欠乏の戦時をのり越えたあとである。
「いいじゃないの、買いましょう、買っちゃいましょう、ミンクがいいわ」
ミンクがよいといったものの私は兎と狐とミンクしか毛皮の名前を知らなかった。
彼女も、もう大人の女優である。常日ごろ、心身ともに豊かな暮らしをして、舞台でどんな豪華なものを着せられても負けない女優になってほしいと思っていたので、私も毛皮を買うのは大賛成だった。
幸い放送局のKさんが毛皮店を紹介して下さって、とうとう越路さんも初めて毛皮を着ることになった。
ミンクを買うつもりだったが、ブロード・テールのコートに変わり、それがとても上品でシックだった。
昭和二十八、九年ごろのことだから、まだ毛皮を着ている人は少なかったが、年と共に毛皮も大衆化されてきたようである。
近年パンタロンにセーターで楽屋入りをすることが多かった越路さんは、いつもその上に毛皮の七分コートを無造作に着ていた。
ジーパンに毛あしの長いクロス・フォックスを、ジャンパーでも着ているように気がるに羽織っていたこともある。
ほんもののおしゃれだったのだろう。
レオパード、豹、スワカラ、ブラック・ミンク、シルバー・フォックス、セーブル、チンチラなど、舞台で着たものを含めて、ほとんどの毛皮に手を通していたのではないだろうか。
こうして毛皮を身近に見るようになっても、私はまだ長いあいだ「越路さんは毛皮を着る人、私はそばで見ている人」と、思っていた。
それが五、六年前から、とつぜん着る人になってしまった。
「もう毛皮を着てもいい年齢よ。軽いし、あたたかいし、こんなよいものないんだから。ちょっと、これを着てみたら?」
と、越路さんが着ていたコートが廻ってきたのが、毛皮との縁の始まりになった。
着てみると、いわれたとおりに軽くて、あたたかい。
「似合う似合う、もう年齢なんだから。似合う年齢になったんだから」
おだてられているのか、ひやかされているのか、年齢だ年齢だといわれるうちに、いつのまにか毛皮が好きになり、あろうことか今では、毛皮のショウにまでノコノコと見に出かける始末である。
越路さんは、新しい毛皮が欲しくなると私を呼び寄せた。そして長いあいだ愛用していたコートを出してくるのであった。
「ちょっと、これ、きっと似合うと思うよ。パーティのときに着られるんだから。ぜったいに持っているほうがいい、ああよく似合うわア」
と、笑いながら私に持って帰らせた。
「ちょっと可哀そうだから、オマケをつけてあげる」
つまり、私は、彼女の新しい毛皮のためにセーターかスカーフのオマケつきで愛用のコートをゆずり受けることになる。これは、越路さんがいなくなるまで毎年つづいた、二人の冬の楽しい遊びであった。
私が自分で毛皮店から買うものは、ほとんどがライニング・コートである。黒い絹のコートのなかに、レオパード・キャットを付けて貰ったりするが、軽くて、雨の日も着られるし、おおげさでなくていい。
仕事で出歩くことが多いから、短い丈の衿なしを、気楽に、表の絹が、すりきれるまで着てしまう。
フォーマルなものは、一年に一、二回しか着ることがないが、ないと不自由なもので、これも越路さんのおすすめ品?があるから、一生大事に着ようと思っている。
二年前、思いがけず越路さんと別れるときがきて、私のコートのいくつかが形見になってしまったのは何よりも哀しいことだ。
今年も夏がすぎてまた、越路さんのいない秋が訪れた。
やさしく肌にふれる毛皮は、心のなかを風が吹く、淋しい女が着るものかもしれない。
※WEB転載にあたり、単行本に記載のルビを省略いたしましたのでご了承ください。
『愛と哀しみのルフラン』
著者:岩谷時子
仕様:46判/上製/312ページ
発売⽇:2024年10⽉29⽇
税込定価:2,750円(本体価格2,500円)
ISBN:978-4-309-03920-6