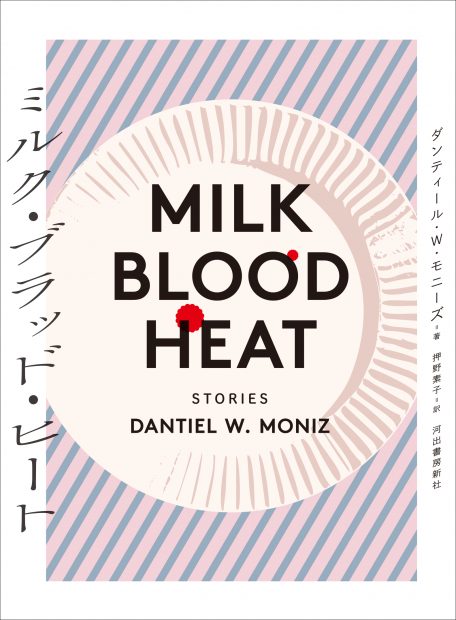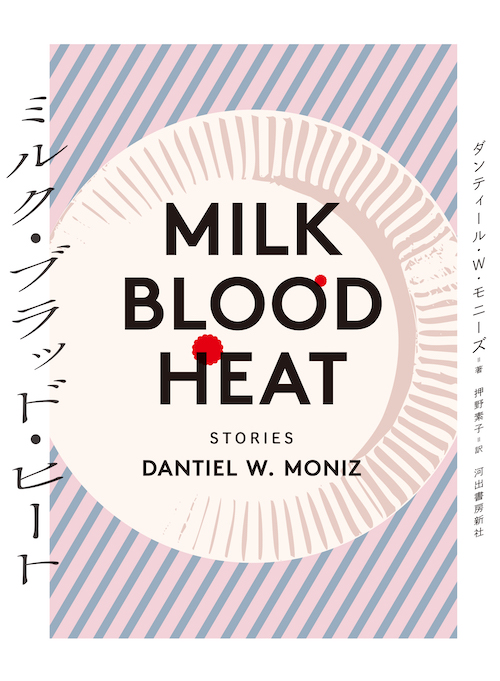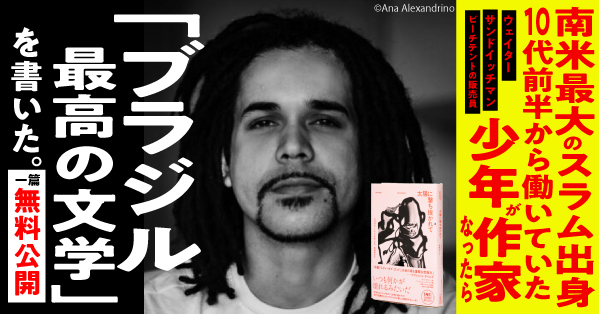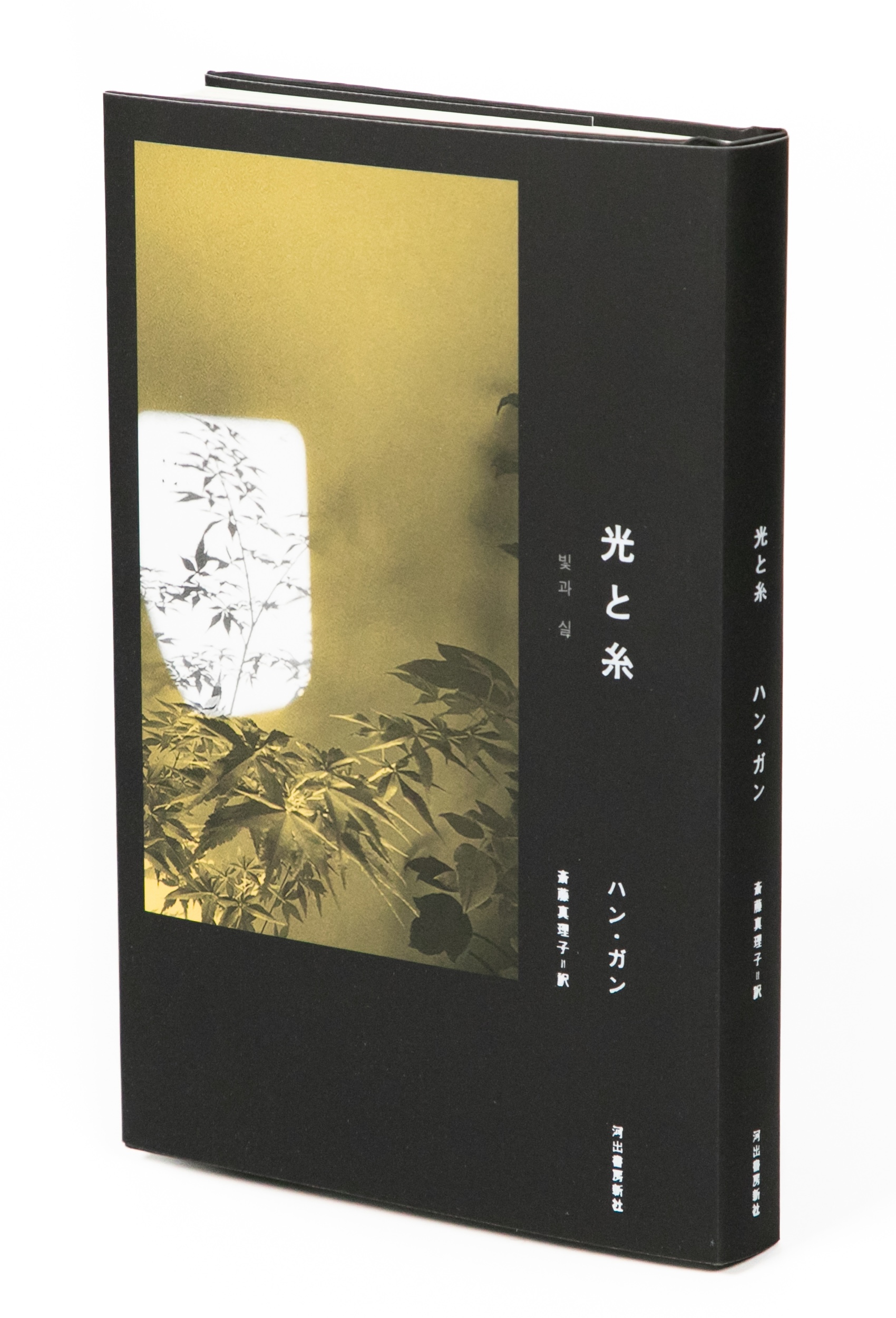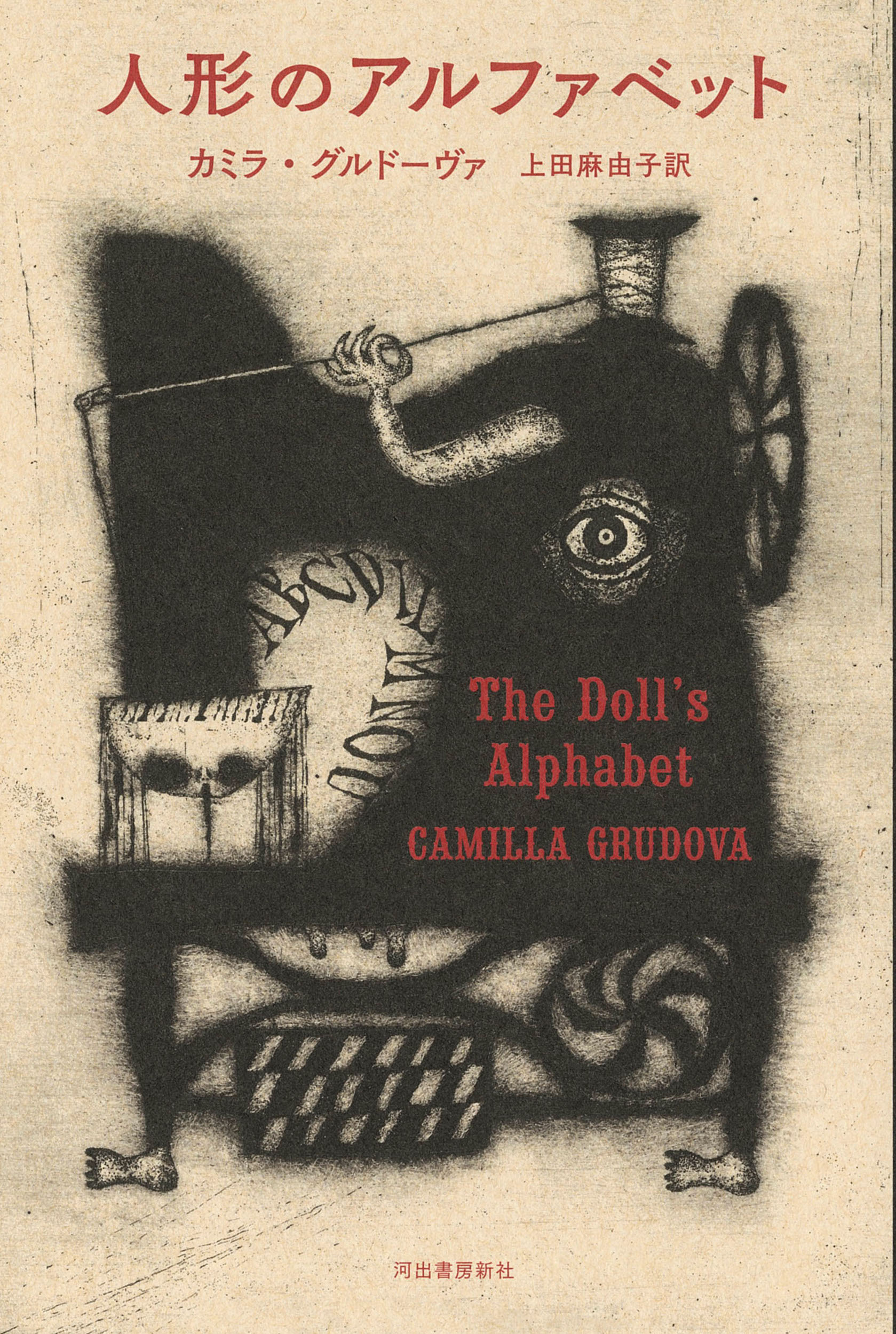ためし読み - 海外文学
ミレニアル世代による、アフリカン・アメリカン文学の新潮流――ダンティール・W・モニーズ『ミルク・ブラッド・ヒート』訳者あとがき公開
ダンティール・W・モニーズ著 押野素子訳
2023.04.11
@Marissa Pilolli
デビュー作『ミルク・ブラッド・ヒート』が刊行されると、アメリカの有力誌が次々と絶賛し、一躍アメリカ文学の最前線に立つひとりとなったダンティール・W・モニーズ。待望の日本語版発売がいよいよ近づいてきました。死に取り憑かれた少女たちの誓約を描いた表題作を含め、過激でダークな11篇を押野素子さんの翻訳でお届けします。
刊行にあたり、訳者あとがきの一部を掲載いたします。
なお、現在発売中の「文藝」2023年夏号では、『フライデー・ブラック』で注目を集めたナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤーとダンティール・W・モニーズのふたりによる、日本語オリジナル対談を掲載中。そちらもぜひお手にとってご一読ください。
=====試し読みはこちら=====
「訳者あとがき」
ダンティール・W・モニーズ著 押野素子訳
本書は、ダンティール・W・モニーズ著『Milk Blood Heat』(グローヴ・プレス、2021年2月刊)の全訳である。
モニーズのデビュー作となる本短編集は、さまざまな世代の人々(主に女性たち)が日常で経験する苦しみや悲しみ、怒りや不安、喜びや気づきを独特の暗さと温かさで描いた情緒豊かな作品だ。刊行当初から大きな話題を呼び、2021年度のPEN/ジーン・スタイン賞とPEN/ロバート・W・ビンガム・デビュー短編集賞の最終候補作、2022年度のニューヨーク公共図書館ヤング・ライオンズ・フィクション賞の最終候補作品となるなど、全米で高い評価を得た。全米図書財団による「5 Under 35(35歳未満の5人)」にも選出された彼女は、同じく短編集(『フライデー・ブラック』)で鮮烈なデビューを飾った同年代のナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤーと並んで、若手作家として将来を嘱望されている。
1989年に生まれたモニーズは、本書収録の物語ほぼすべての舞台となるフロリダ州ジャクソンヴィルで育った。読書家の母親の影響で幼い頃から本に親しむと同時に、詩や文章を自ら認めていたという。「手当たり次第に読んでいたから、年齢に相応しくないものもあったけれど、家族は何でも読ませてくれた」ことが、読者としての自身を育て、母親のすすめでV・C・アンドリュースの『屋根裏部屋の花たち』を読んだことが、「人間の暗い部分や、口には出しにくいことを探求する傾向を持つ」作家としての資質を助けたと語っている。現在は、MFA(芸術修士)を取得した母校ウィスコンシン大学マディソン校で創作を教える傍ら、執筆活動を行っている。
モニーズの筆致は、「読むだけでなく、感じるもの」(ボストン・グローブ紙)、「ニュアンスと味わい深さを兼ね備えている」(ションダランド)など、各方面で絶賛されている。「物語がイメージの形で浮かぶことも多いので、私の脳は絶えずイメージを言葉に、言葉をイメージに変換している」と語る彼女が、瑞々しく詩的な文章を紡ぐうえでこだわっているのは、「音とリズム」だ。声を出して文章を読み、正しい音やリズムが生まれていないと感じた時には、音やリズム優先で別の単語に変えてしまうほどの徹底ぶりだが、「その単語の定義を調べてみると、どういうわけか言いたかったことや意味にもっとも近くなっている」という。また、大学院在学中に初めて観客の前で作品を読んだ際には、「君の作品の音と静寂がとても良かった」と詩人のビリー・コリンズに賞賛されている。音、リズム、間が、彼女の直感的かつ身体的な文章の大きな要素であることが分かるエピソードだ。
もちろん、絶賛されているのは文体だけではない。一見関係なさそうな複数の出来事(本人曰く「種」)をひとつに結びつけて物語へと昇華させ、ひとつの出来事を複数の視点から見ることに長けたモニーズは、「フロリダ・ゴシック」(アヴェニュー誌)とも称された美しくダークな物語のなかで、人間の儚さと逞しさ、脆さと強さ、汚さと美しさ、冷たさと温かさなど、万人に内在する数々の要素をあぶり出す。彼女が描く登場人物も、不完全だからこそ誰もが人間らしく、どこか共感できるところを持っている。作家/大学教授/編集者/社会評論家として大きな影響力を誇るロクサーヌ・ゲイが主宰するブッククラブでは、本書で描かれる母親像が特に注目された。幼い娘を置いて旅に出かけ、気が向いた時にだけ帰ってくるフーテンの母親ヘレン、妊娠しながらも不安に駆られ、母親になるか否かを決められないビリー、罪の意識に苛まれた卑屈な態度で、娘の神経を逆撫でするフランキー……「モニーズの描く母親は、パーフェクトであることよりも、オーセンティックであることを優先している」、「善悪を決めつけずに複数の母親を描くことで、モニーズは母親になるための正しい方法はひとつではないことを示しており、母親の経験をありのままにさらけ出している」といった意見のほか、子どものいない読者からは、「母性というテーマが出てくると歯がゆい思いをしがちだが、モニーズが描く母親の二面性は新鮮だった」という声も上がっていた。母親だって、この世で生きるのは初めてで、母親という属性の前にひとりの人間として存在している、という思想が、彼女の物語の根底には流れているのだ。「悪い人って、どういうこと? 良い人って、どういうこと? それを定義するのは誰? 私が善人か悪人かを決定する力を持つのは誰?」登場人物とモニーズは、読者にそう問いかけている。
さらに本書には、女性であること、黒人であることで登場人物が直面するアメリカの日常が、さりげなく挿入されている。「エイヴァの方が美しいけれど、肌の色が遥かに濃いせいで、引き立て役になりがちだ」(「ミルク・ブラッド・ヒート」)、「修士号や高いクレジットスコアと同様に、この赤ちゃんは私の価値を認めてくれた」、「普通の倍努力しても、得られるものは半分」(「宴」)といった記述は、アメリカの黒人女性に共通の認識だろう。「スノウ」の主人公トリニティの「他人に仕える以外は自分に取柄なんてないのでは」という懸念もリアルに響く。ジェンダー・ギャップ指数が146か国中で116位(2022年)と、先進国、アジア諸国のなかでも最低レヴェルの日本に住む読者ならば、こうした黒人女性の状況や心の機微を一部は理解できるのではないだろうか。また、バーテンダーのトリニティ(モニーズ自身も18歳から大学院入学までバーテンダーとして働いていた)は、自身の顧客について、「大半が暮らし向きの良い中年の白人で、リベラルを自称しながらも、おそらく定期的に話している黒人は私だけだろう」と考察し、「私の立ち居ふるまいや、知的で上品な話しかたに、心底驚いていた」と、悪気のないリベラルな白人によるマイクロアグレッション(無意識の偏見/差別に基づく行動)を表現している。なお、「speak well/well-spoken(知的で上品に話す)」という誉め言葉は、インテリで知られる元大統領バラク・オバマにも多用されていたが、「黒人は知的で上品な英語を話さない」という根強いステレオタイプに基づくため、これは立派なマイクロアグレッションだ。さらには、「欠かせない体」に登場する「どこに行っても、どんなふるまいをしても、彼女たちの行動や外見、その存在は、どういうわけか常に監視の対象になっていた」という言葉も、多くの黒人女性の共感を呼んだ一文である。そのほかにも人種関連の描写はあるものの、作品を通じてモニーズは、弱さや欠点を含めてありのままに人物を描くことで、「人種」を超えた「人間」としての輪郭を際立たせている。「自分の作品に人種を書き込むことは重要だと思う。でも、黒人の作家や周縁化された作家には、それだけを期待されてしまうことがある。私は黒人とその世界を描写するけれど、それが中心点ではない。私はまだこの人を愛してる? 壊れつつある世界に子どもを誕生させるって、どんな感じ? とか、人間が経験することを経験している人々について記しているのだから」。
前述のとおり、本書収録の物語はフロリダ州を舞台にしており、彼女はその理由をこう語っている。「南部は、その歴史を理由にいろいろな意味で見下されている。フロリダを含む南部は抑圧された州。でも、南部の差別はこの国の根幹を作った。これが建国の経緯。文字通り民族を盗み、既にここに住んでいた人々を殺害して国を建てたのだから、この国から闇を消し去ることはできない。フロリダは書く価値のない場所だと思われているからこそ、私はこの場所について書きたかった。フロリダは私を作り上げた場所だから。でも、具体的な通りの名前とか、そういうことを書きたかったわけじゃない。あの雰囲気や感覚、熱気を書きたかった。気候って大きな要因になると思う。暑くて、湿気がすごくて、息もできないように感じる時、それが人間にも影響を与える。まとわりつくような暑さがずっと続いたら、思考や行動は、どんな影響を受ける?」
日本の過酷な夏を生き抜いている読者ならば、フロリダの熱気や湿気に囲まれて暮らす登場人物の心情や行動に、自分を重ね合わせることもできるだろう。「これらの物語が、あなたに語りかけ、あなたの魂のなかで根を張り、成長することを願って」──これが著者から日本の読者に向けたメッセージ。この本がみなさんの魂のなかだけでなく、家庭の本棚、書店、図書館でもしっかりと根を張り、成長しますように。