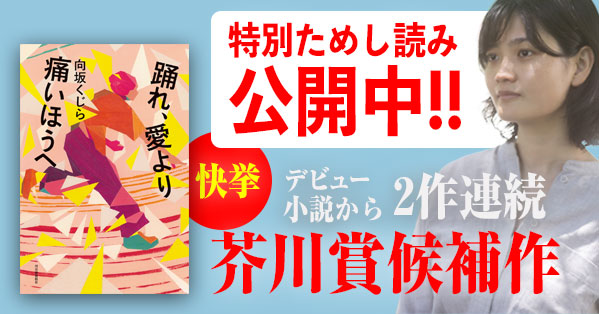ためし読み - 日本文学
娘が人を殺した。父親は警察官だったーー発売直後より話題! 連続ドラマ『パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜』の原作者・中村啓が贈る最高の警察小説!
中村啓
2024.01.22
池袋で連続殺人事件が発生。厳しく箝口令が敷かれていたが、殺害された被害者の額には刃物で「×」印が刻まれていた。反社ばかりを狙った犯行から、マスコミは犯人を、街をきれいにする清掃車にかけて“聖掃者”と命名。池袋署には特別捜査本部が設置され、刑事課強行犯係の警部補・薬師丸遼一をはじめとした捜査員は、日夜、犯人探しに奔走していた。そんな中、遼一のもとへ、娘の佳奈から電話が入る。彼女は電話越しに、信じられない言葉を発した。「……私、人を殺しちゃったかもしれない」 ―― 娘のもとへ急行する遼一。そこで目にしたのは、目から光を失った男の姿だった。娘の人生をここで終わらせていいのか ―― 「おまえを助ける」遼一は娘に告げると、男の額に「×」印を刻印した。いま、後戻りのできないミッションがスタートした。
「無限の正義」
中村啓
序章
老人介護施設〈ひまわり〉にあるテニスコート一面ほどの広さの庭で、薬師丸遼一は古びたベンチに腰を掛け、車椅子に収まった父の和夫を静かに見つめた。
三月中旬のこの日は比較的穏やかな陽気で、カーキ色のチェック柄のネルシャツに栗色のカーディガンを羽織り、下は黒のコーデュロイのズボンといった格好でも、父は寒そうではなかった。遼一は仕事着であるチャコールグレーのスーツの上に、薄手のベージュのスプリングコートを着ていた。ネクタイはネイビーのブランドものである。妻が誕生日にプレゼントしてくれた。服装にはさして気を遣わないが、ネクタイにだけはこだわっている。
庭に植えられた桜の蕾は膨らみ、花壇にはフリージアやヒヤシンスといった早春の花々が色鮮やかに咲いている。
七十五歳の父が認知症と診断されてから三年が経つ。レビー小体型認知症といって、記憶障害を中心とした認知機能の低下や幻視、手足の震えといったパーキンソン症状を呈する認知症である。アルツハイマー型認知症に次いで多いと言われている。認知機能に変動が生ずるのが特徴で、和夫は一過性の意識障害も見られるため、意識がはっきりしているときとぼんやりしているときの差が大きかった。
母はすでに十二年前に他界しており、浦和にいる父を一人にさせることはできなくなったので、昨年から石神井公園駅の近くにある老人介護施設に入居させることにした。遼一の住む練馬区桜台からも近く通いやすい。
週に一度、父のもとを訪ねることにしていた。今年に入ってからとみに父はやせ細り、そう長くはないと感じたからだ。少しでも多くの時間を父と一緒に過ごしたかった。
施設に来ると、一緒に庭まで散歩する。庭は常に清掃が行き届き、手入れがされていて、いつも四季折々の花が咲いているが、なぜかきれいだと感じたことがなかった。
和夫は陽溜まりの中でおとなしくしていた。視線は花壇のほうを向いているが、花を愛でているようには見えない。話しかけているのだが、先ほどから反応はない。
遼一はネクタイの結び目の位置を正した。いつも曲がっていないか気になって、結び目をいじるのが癖になっている。 「今度、昇任試験があるんだよ。いまちょうど厄介な帳場が立っていて、忙しいんだけどさ。一昨年から勉強してきたから、たぶん合格すると思うよ。そうしたら、おれも晴れて警部だ」
薬師丸遼一は池袋署の刑事課強行犯係に所属する捜査員だ。今年で四十五歳、階級は警部補。強行犯係は殺人や強盗など凶悪犯を摘発する部署である。
目下、池袋署管内では連続殺人事件が発生し、特別捜査本部(帳場)が立っているため、目が回るほど忙しい。本来なら父に会っている暇などないのだが、上司に断って今日は特別に半日だけ時間をもらったのだ。
四月の下旬に昇任試験の一次試験がある。いまが一番勉強をしなければいけない時期だが仕方がない。警部昇進の試験の受験は今年で二度目であり、十分な準備をしてきたので、試験をパスする自信があった。
警部に昇進してからは、警視庁(本庁)捜査一課の配属になれば、と考えていた。警視庁刑事部の捜査一課は言わずと知れた花形の部署である。捜査本部が立っているいま、本庁の幹部たちが捜査員たちの働きに目を光らせている。彼らの目に留まれば、本部に引っ張り上げられることも十分ありうる。
警察は上意下達がモットーの軍隊式の組織である。上に立たなければ顎で使われるだけだ。遼一はなんとしてものし上がりたかった。三流の大学卒ではあるが、理屈の上では警視正までなら出世可能である。警視正になれば国家公務員扱いになり、県警本部長や警察署長を任せられることもある。そんな未来を夢見ていた。父の意識がはっきりしていたとしても、出世とは無縁の元中学校教師であり、のんびりとした性格の父には、遼一の野心はわかるまい。
「警部になれば収入も少し上がるから、月々の家のローンの返済額も増やせるよ。恵理子に世話になってばかりもいられないしな。夫として肩身が狭いし。あと、これからは佳奈の留学費用も捻出しなくちゃならない」
大手総合商社に勤務する妻の恵理子は、公務員の遼一よりはるかに収入がよい。父の老人介護施設の入居費も馬鹿にならないため、月々の自宅のローンは妻が多めに払っていた。また、十八歳になって高校を卒業したばかりの娘の佳奈が今年の秋にロンドンにバレエ留学することになっている。小学校一年生のころ、バレエ好きの妻に無理やり習わされて以来、いつしか佳奈はバレリーナになる夢を抱き、今冬、念願だったイギリスの名誉あるバレエ学校のオーディションに合格した。警察官の給料ではとてもではないが、バレエ教室に通わせたり、留学させてやったりなどできない。費用は妻の恵理子が全額出すというが、遼一がまったく出さないわけにもいくまい。
「おれの娘がバレリーナだってさ。何だかぴんと来ないよ。これで世界的に有名なバレリーナになったらどうする? そのときは娘に食わせてもらうかな」
遼一は自嘲気味に笑った。ふと、和夫の様子がおかしいことに気づく。どこか一点をにらみつけている。
「親父、聞いてるか?」
「あいつだ。あいつがいる……」
和夫はがたがたと震え出すと、立ち上がろうと車椅子の肘掛けを握りしめた。
父がにらみつけるほうを向くまでもない。いつものことだ。幻を見ているのだ。レビー小体型認知症を患う患者の幻視にはさまざまなタイプがあるが、父が見る幻はたいがい黒っぽい服装をした中年の男だった。自分を監視していると思い込んでいる。
「あいつが来た。何を見てるんだ! あっちへ行け!」
そんな者はいないと言っても聞かない。本人には見えているのだから。
和夫は車椅子の中で手足をばたつかせて暴れ出した。こうなってしまうともう手のつけようがない。
「あっちへ行け!」
「親父、部屋に戻ろう。な?」
遼一は父をなだめながら、車椅子を押して庭をあとにした。
今日は特に意識がはっきりしていなかった。残念だが、これからよくなることはなく、悪化の一途をたどるだけだろう。
遼一は悲しみとともに暗澹たる気持ちになった。そして、次の昇任試験こそは絶対にパスし、のし上がってやるのだと決意を新たにした。
第一章
1
男たちは一日の労をねぎらって缶ビールで乾杯した。 夜の十一時、薬師丸遼一は自宅のリビングに集まった男たちの顔を見渡した。みな疲れているはずだし、晴れやかな気分ではないはずだが、このときばかりは顔をほころばせていた。
遼一の自宅に泊まることになったのは、同じ池袋署刑事課強行犯係の同僚、谷川栄吉巡査部長、相馬誠一郎巡査部長、そして、遼一がいまバディを組んでいる本庁捜査一課の小田切護巡査部長の三人である。男たちはスーツ姿のままリビングにあるソファに座っていた。遼一の所属する強行犯係にはほかに、吉野聡巡査と紅一点の深田有美巡査がいるが、二人は捜査本部の設置された所轄の道場に宿泊している。
池袋署管内では、反社会的勢力の構成員ばかりを狙った連続殺人事件が発生していた。三週間前の二月二十一日、須藤組の組員が刃物でめった刺しにされて殺されたのを皮切りに、三月二日に宮本組の元組員、三月十日に半グレ集団〈ブラックチェリー〉のメンバーと、だいたい一週間おきに、いずれも刃物で刺し殺されたのだ。凶器は刃渡り十五センチくらいのサバイバルナイフのようなものと考えられる。殺害された三人の額には刃物で×印が刻まれていた。これに関しては厳しく箝口令が敷かれており、マスコミには公表されていない。反社ばかりを狙った犯行から、マスコミは犯人を、街をきれいにする清掃車にかけて〝聖掃者〟と名付けた。警察内部でもその渾名が通名となっている。
これまでのところ捜査にはさほど進展が見られていない。唯一、最初に殺害された須藤組組員、伊藤裕也の爪の間から、犯人のものと思われる皮膚片が見つかったが、警察が保有する被疑者DNA型記録や遺留DNA型記録のデータベースと照合してもヒットしなかった。今回が初犯なのかもしれない。目撃情報もなし。怨恨による犯行か、通り魔的な犯行なのかもわからない。捜査は長期化の様相を呈していた。
重大な事件が発生し捜査本部が立つと、所轄の道場で寝泊まりする者も出てくる。遼一の家は池袋署から近いので、この日は特別ということで、三人の男たちを薬師丸宅に招待することにした。昔は署内で酒を飲んだりもしたそうだが、昨今はそうもいかない。久しぶりに酒を飲みたかったし、飲んだら風呂に入り、そのまま眠りたかった。 遼一は夜食にと簡単にペペロンチーノと冷やしトマトを振舞った。共働きで、家事は分担しているので、料理は当然できる。男たちは「旨い旨い」と食べ、小田切は遼一が料理ができることに感心していた。ペペロンチーノをつくるのは簡単だし、冷やしトマトは切ってドレッシングをかけるだけなのだが。
妻の恵理子と娘の佳奈はすでに就寝しているようだ。息子の将太は不規則な生活をしているので起きているだろうか。二階の自室に引きこもっているためわからない。男たちは声をひそめて話をする。
谷川は大きな目をぎょろりと動かして、リビングの四方を見回した。谷川は五十七歳のバツイチの独身者で、三鷹にある公務員住宅に一人で住んでいる。いつも型崩れした身体に合っていないスーツを着ている。おしゃれとは無縁のオヤジである。
「それにしても、立派な家だな。おれもこんな家に住んでみたいもんだ」
薬師丸家を訪れる者はたいがい同じせりふを口にする。相馬と小田切も感嘆した様子で、部屋のあちこちに視線を走らせている。
「建て売りじゃなく自分好みに自由にデザインして家を建てるってのは夢だよなぁ。今世じゃもう叶わないけど……」
薬師丸家の一階のLDKは二十畳の広さがあり、二階まで吹き抜けの天井は高く、開放的なつくりになっている。フローリングの床から壁、家具の色まで、オフホワイトで統一され、北欧スタイルの内装だ。これは恵理子の趣味である。
相馬が物めずらしそうに目の前の檜のテーブルをなでている。
「これって一枚板っすよね? いったいいくらするんすか?」
三十八歳の相馬は、高校時代はヤンキーだったという。どういう心境の変化か警察官になった男だ。いまどきのソフトリーゼントという髪型がやけに似合うイケメンである。結婚しており、一男一女がいる。
「さあ、いくらだったかな……」
家の話題になると、遼一はいつも居心地が悪くなった。公務員の給料ではけして購入することはできない物件である。いや、妻の給料を足しても、とうてい無理だ。実のところ、隣に住んでいる妻の父親が所有していた土地の上に十年前に建てたもので、購入価格の半額相当を義父が払ってくれている。そして、残りのローンも現在は妻が多めに払っているのだ。夫としては非常に肩身が狭いと言わざるを得ない。
檜の一枚板のテーブルもいくらなのか、妻が手配したため知らなかった。
谷川がまた口を開く。
「檜のテーブルぐらいで驚いてたらいかん。娘さんなんてバレリーナを夢見て、今度ロンドンの名門校に留学するっていうんだから」
「バレエ留学ですか。絵に描いたようなセレブじゃないですか?」
小田切が驚嘆している。小田切とは今回帳場が立って初めて知り合った。明るく愛嬌があり、谷川たちからも好かれているので、今日は自宅に誘ったのだ。年齢は三十歳。温厚そうな顔つきながら、体格は意外にがっちりとしている。話を聞くと柔道高段者で、左の耳がカリフラワー状になっている。柔道やレスリングなどで激しい練習をすると、摩擦により耳がつぶれてしまうのだ。
遼一は無意識にネクタイの大剣をいじっていたが、それが高級品だと思い出して手を引っ込めた。
「いやいや、セレブでも何でもないよ。実は、妻の父にずいぶん助けてもらっている。それにうちは共働きだからな」
言い訳をするように言った。
独身だという小田切がうなずく。
「いまの時分はどこも共働きですよね。女性だって仕事に生きたい人もいるし、そっちのほうが家庭に経済的なゆとりも生まれますからね。奥さん、どんなお仕事をされてるんですか?」
「商社に勤めている」
遼一が商社の社名を口に出すと、小田切は驚いて仰け反った。
「えっ、奥さん、すごいエリートじゃないですか。いったいどうやって刑事が商社勤務の女性と知り合うんですか?」
谷川が頬を弛める。
「小田切はなかなかの引き出し上手だな」
「大学時代の後輩だ。きみもさっさと結婚したらいい」
「いや、婚活中なんですけどね。これがなかなか出会いがなくて……」
「アプリなんてどうだ? いまいろいろあるだろう?」
流行りものに疎そうな谷川がそんなことを言う。
「出会い系のアプリですか? いやぁ、友達が言うには、詐欺まがいやパパ活目的が多いっていうんですよ。警察官はどっちもまずいじゃないですか」
「そりゃ、そうだ」
「で、奥さん、美人なんですか?」
なおも小田切が聞いてくる。尻のあたりがむずがゆくなる。
「いやいや、そんなたいしたもんじゃない……なんて言ったら怒られるが、どうだろう。おれは好きになって結婚したよ」
「でしょうね。好きにならなかったら結婚しませんからね」
咳払いが聞こえたので振り返ると、リビングの入り口に、妻の恵理子が部屋着姿で立っていた。恵理子は遼一より三歳年下の四十二歳だ。吊り目がちな上、鼻ぺちゃながら、愛嬌のある顔立ちをしており、歳よりずっと若く見える。まだ寝ていなかったようで、挨拶だけでもと思って顔を出したのだろう。
「起きてたのか……。自慢の妻の恵理子です」
機嫌を取ろうとしたが、恵理子は遼一に目もくれなかった。
一番年配の谷川が立ち上がって頭を下げた。
「奥さん、お邪魔させてもらっています」
相馬と小田切もあとに続いて立ち上がって、「お邪魔しております」と挨拶をした。
「いえいえ、連日お疲れ様です」
恵理子もあらたまって頭を下げて返す。
「ごゆっくりしてください。わたしは先に失礼させていただきますので」
恵理子が廊下に出ていくと、遼一はあとを追った。リビングのドアを閉めて妻と向き合う。
「悪いな。みんな風呂に入りたいって言うから」
「いいよ、一日ぐらい」
二日目はない、ということだ。それは遼一もわかっていた。たまにある一日なら許容してもらえる。
「洗い物はしておいてね」
「もちろん」
恵理子は手を伸ばすと、ネクタイの結び目の位置を直した。
「おやすみ。美人じゃなくてごめんね」
「いやいや、おまえはきれいだよ。おやすみ」
密かにため息を吐くと、笑顔をつくってリビングに戻った。息苦しさを感じてネクタイを緩める。
明日も朝は早い。遼一たちは日をまたぐ前に就寝することにした。
浅い眠りの中で同じ夢を繰り返し見ていた。夢を見るのはめずらしい。恵理子と外食をしているシーンだ。二人で初めて行ったイタリアンの店で、妻が真剣な表情で話している。怒っているようにも見える。何かを必死に訴えているが、無声映画のように言葉がまるで聞こえない。ナプキンを投げ捨て、妻が席を立ち、去っていく。漠然とした不安が胸の中に湧き起こる。
電話が鳴っていた。仕事用の携帯電話だ。薄目を開ける。カーテンの向こう側が白み始めている。隣で谷川たちが寝息を立てていた。昨夜はリビングに布団を敷き、同僚たちと雑魚寝したのだ。
枕元に置いていたスマホに手を伸ばす。電話の相手は課長の竹野内義則だった。階級は警視だ。直属の上司である警部の男がうつ病にかかり長期休暇中なので、いまは竹野内が遼一の上司である。
あわてて上体を起こすと、「お疲れ様です」と応答した。同僚たちも着信音で起きたようで、もぞもぞと身体を動かしている。
低く、響く声が聞こえた。
「朝早くに悪いが、また殺しだ。聖掃者だ」
竹野内は被疑者の発見された現場の住所を告げると通話を切った。
目を覚ました谷川が横で胡坐になり身体を掻いている。
「殺しか?」
「聖掃者だそうです。現場は南池袋二丁目──」
「いま何時だ……?」
スマホの画面で確認する。
「五時三十五分ですね」
リビングの電気を点けると、相馬と小田切も次々に起き上がった。男たちは部屋着からスーツに着替えた。遼一はワードローブから臙脂色のネクタイを出してきて締めた。忙しいときも、毎日ネクタイを取り替えることにしている。
家の中は静まり返っていた。恵理子と佳奈はまだ寝ているだろう。将太はいま時分から寝るのだろうか。
顔を洗うために、洗面所へ向かった。途中、二階に続く階段の上方をうかがう。真っ暗でしんとしている。
将太のことを心配した。高校二年に上がってから、すっかり学校へは行かなくなってしまった。最近は特に生活のリズムが乱れており、昼ごろに起き出して、自分でカップ麺などをつくって食べているらしい。それもなるべく家族に顔を見られないようにして。学校へ行くよう何度も説得してきたが、自宅で受験勉強をして、大学へはちゃんと行くからと言い張る。学校にも塾にも行っていないものだから、学力がどの程度なのかもさっぱりわからない。真剣に話し合わなければと思いながら、まだ高二だからいいかとずるずると先延ばしにしてきている。
洗面所で顔を洗い、急いで用を足す。始発はとっくに動いているが、タクシーを使うつもりだった。四人いるので、割り勘にすればいい。
玄関で革靴を履く。ドアノブに手をかけたそのとき、突然ドアが開き、佳奈が帰ってきた。遼一の顔を見て、驚いた顔をしている。
佳奈は黒のダウンジャケットを羽織り、淡いパープルのチュニックという出で立ちで、初めて目にする服装をしていた。ずいぶんと大人びて見える。
昨夜は遅く帰宅したため、佳奈が在宅しているかどうか気づかなかったが、まさか朝帰りしてくるとは。
「いままでどこに行ってたんだ?」
思わず厳しい口調で問い詰める。
「友達と遊んでた」
佳奈はそれだけ言うと、遼一たちをすり抜けるようにして、靴を脱いで階段を駆け上がっていった。
気まずい空気が流れる。
谷川が気を遣って言った。
「まあ、年頃ってやつだな」
「困ったもんですよ。挨拶もしないで……。あとで厳しく言い聞かせます」
遼一の胸にいろいろな思いが込み上げてきた。佳奈がバレリーナで大成することは夫婦の夢でもある。いまが大事な時期なのだから、遊びにうつつを抜かしている場合ではないはずだ。
「行きましょう、薬師丸さん」
小田切に急かされて、遼一は頭を仕事に切り替えた。
2
現場は閑静な住宅街だった。大小の住宅が建ち並ぶ中にところどころ背の高いマンションが建っている。あたりはずいぶん明るくなっていた。小さな墓地に隣接した十数階建てのマンションの前に、警察車両が複数台と救急車が駐まっている。
捜査員らが取り囲む一角に、人が仰向けに倒れていた。一目見て、死んでいるとわかるほど顔が青白い。死体は五十代の男で、黒のトレーニングウェア姿。見るからにガラの悪そうな人相をしている。額に×の印の切創があり、腹部を刺されたようで、アスファルトに血溜まりができていた。
吉野聡巡査と深田有美巡査がすでに到着していた。
「お疲れ様です!」
二人の若い声が飛ぶ。
吉野聡は七三にきちんと分けた髪に生真面目そうな顔立ちをしている。自称、HSP(Highly Sensitive Person)とのことで、非常に感受性が高く敏感な気質のため、人付き合いが苦手だと言う。そのためか、彼女がいたという話を聞いたことがない。三十二歳の独り者である。
深田有美はボブヘアの似合う童顔の持ち主で、どう見ても学生にしか見えない。見た目のわりに気が強くしっかりしており、頼もしい部下である。アイドルを目指していた時期があるそうで、カラオケが抜群に上手い。二十八歳の同じく独り者だ。
「お疲れさん」
今度は野太い声がした。池袋署組織犯罪対策課(通称、組対)の浜田雄馬警部補だ。相棒の警視庁捜査一課所属の藤井俊介巡査部長の姿もある。本事案は被害者が反社ということもあり、所轄からは組対の面々も加わっていた。
浜田は遼一より二つ年上の四十七歳で、暴力団関連の事案を担当する組対に所属している。組対の刑事たちはみな暴力団に見間違われそうな人相をしているが、浜田もその例に漏れない強面である。上背がある上、恰幅もよく、髪が短く、目付きが鋭い。たいがいの人は浜田を避けて通る。一方の藤井は対照的な男だ。年齢は三十代前半。センター分けにしたさらさらの髪型に、色白で中性的な顔立ちをしている。非常に無口で、黙ったままじっとこちらをうかがう癖がある。本庁の捜査一課にいるのだから優秀なのだろうが、何を考えているのかわからないタイプだ。
挨拶を交わすと、遼一は遺体の検分を始めた。
「ヤクザか。身元は?」
浜田が遺体を顎でしゃくる。
「こいつは、天宮興業の者だ。名前は岸谷彰吾。何度か会って話したことがある。北口にある風俗店の店長を任されていたかな。天宮興業は元は天宮組という極天会系の三次団体だったが、ずいぶん昔に組を解散している。ただ、フロント企業だという噂がある」
暴力団関連事件の捜査に当たるのは組織犯罪対策課であり、刑事課とは畑が違うため、遼一はあまり暴力団に詳しくはない。
そばにいた谷川が茶化すように言う。
「会ったことがあるというのは、その店に行ったことがあるってことだな」
浜田は下卑た笑い声を上げると、これまでに得た情報を話した。
「今朝五時十五分ごろ、散歩中の男性が遺体を発見した。検視はまだだが、死後硬直の具合から見て、死後五時間以上は経ってるんじゃないか。遺留品は財布のみ。本人の運転免許証が入っていた。住居はここのマンションの二階。こいつもスマホがない。犯人に持っていかれたな」
最初に殺された伊藤裕也を別にすると、これまでに聖掃者に殺された二人はスマホを所持していなかった。犯人が持ち去ったものと考えられる。そのため、スマホの解析が進まず、三人の交友関係に共通項があるかどうかつかめずにいる。
遼一はしゃがみ込んで、遺体の手の爪を見た。少し伸びた爪の間には挟まっているものはないようだ。最初の被害者以来、現場に容疑者のものと思われる遺留品は見つかっていない。
「抵抗した様子がない」
通常、刃物を持った相手に抵抗すると、手や腕に防御創ができる。
浜田がうなずいた。
「ああ、すれ違いざまに腹を一刺しって感じだろう。聖掃者は殺しの腕を上げているよ」
「今度も防犯カメラ、なさそうですね」
深田が残念そうな口調でこぼす。
「事前に下見をしているのかもしれないな。最初の犯行以来、へまをやっていない」
遼一は立ち上がると、周囲をぐるりと見回した。マンションのほかには一戸建てが建ち並んでおり、一見したところ防犯カメラの存在は認められない。聖掃者は殺す相手を尾行し、その行動パターンをつかみ、殺す場所を計算しているようだ。
相馬が悔しそうに顔をしかめた。
「もう四人目っすよ。聖掃者は調子に乗ってるんじゃないっすか? SNSでみんなが〝正義の使者〟だとかはやし立てるから」
SNS上では、犯人に対する賞賛の声が続々と投稿されている。遼一も覗いてみたことがあるが、見識を疑うようなものが多かった。やれ、〝反社みたいなクズは殺されて当然だ〟とか、やれ、〝聖掃者は捕まえても死刑を免除するべき〟とか。そんな状況に鑑みて、マスコミが犯人を聖掃者と皮肉った渾名をつけたという経緯がある。そして、容疑者一人挙げられていない警察をこき下ろしている。被害者が反社だから警察は真面目に捜査をしていないのではないか、とも……。警察も報道にはほとほと困り果てていた。
谷川が同調するように応じる。
「マスコミも〝聖掃者〟なんて渾名をつけるからなぁ。被害者の反社はゴミクズってか。反社にだって人権はあるんだ。それはあんまりだろう。なあ?」
「それはどうでしょう」
深田は納得できないとばかりに口を尖らす。
「反社に人権はないとまでは言いませんけど、実際、暴対法や暴排条例などで法律的な制限は受けてますよね。それでいいんだと思います。だって、ろくでなしの反社なんですから」
「意外に深ちんは厳しいな。反社の中には好き好んで反社になったわけじゃないやつもいる。そういう連中の受け皿だって必要なんじゃないか?」
小田切が深田に加勢する。
「だからって犯罪に手を染めちゃダメですよ。反社になった段階で人としてアウトです」
深田がうなずく。
「わたしもそう思います。SNSの意見ってバカにならないと思うんですよ。あれが民意ですから。国民は反社に怒っているんです」
こういうとき、吉野は会話に入ってこない。黙ったままみんなの意見を聞いている。けして興味がないわけではないのは、聞く姿勢でわかる。単純に会話が苦手なのだ。
「いやぁ、最近の若い警察官は正義感が強いんだな。おれたちにもそんなころがあったっけ?」
谷川が助け船を求めて遼一に顔を向けた。
「〝おれたち〟ってやめてください。谷やんとおれは同世代じゃないですから」
「薬丸さん、四十を過ぎたらみんな一緒だ。辞書で調べてみるといい。〝初老〟とは四十過ぎのことを言うんだから」
谷川は遼一を〝薬丸〟と呼ぶ。
相馬が驚いた声を上げる。
「えっ、それだと、おれもあと二年で初老ですか? 嫌だなぁ」
他人事だと思って、小田切がけらけらと笑っている。
「笑っていられないぞ。三十代なんてあっという間だ」
浜田が話に入ってきた。
「いずれにせよ、聖掃者が調子に乗ってるんなら、まだまだ殺しは続くかもしれないな」
嫌なことを言うなと思ったが、遼一は反論しなかった。その場に居合わせた捜査員らの顔色をうかがう。みんな疲れの色がこびりついている。聖掃者は相当に手強い。この三週間、捜査員はほとんど休みもなく働きづめである。聖掃者を捕まえない限り、安息の日はやってこないのだ。
「よう、お疲れさん」
池袋署刑事課の竹野内義則課長がやってきた。コートはよれよれな上に、その下のスーツも型が崩れ、ネクタイは曲がっており、数日は剃っていない無精髭を生やし、一歩間違えばホームレスに見えなくもない。しかし、刑事としての矜持を持った優秀な男である。
「お疲れ様です」
一同は一斉に礼をした。
竹野内は片手を上げて応じた。
「ついに四人目か。状況はかなりマズい。目撃者なし。容疑者一人挙げられてないんだから、マスコミからの突き上げが一層厳しくなる。警察の威信が地に落ちるぞ」
遼一はため息交じりに応じた。
「でしょうね」
「〝でしょうね〟じゃない。おれたちは全員無能ってことになる。被害者はみな反社とはいえ、殺される最期というのはむごい。その無念を晴らしてやれるのはおれたち以外にはいない。そうだろう?」
捜査員たちはみな力強くうなずいた。
竹野内はその反応に満足すると続けた。
「それじゃ、周辺の聞き込みに行ってくれ。捜査会議はいつもどおり八時半から始める」
捜査員たちは「はい」と返し、目撃情報を求め、夜明けを迎えたばかりの住宅街に散った。
午前八時半に捜査会議が始まった。池袋署の講堂に本庁と所轄を合わせた百人近い捜査員たちが集まっている。前方に設置された雛壇には、中央に警視庁捜査一課長の柳沢登志夫警視正、管理官、池袋署署長、そして、竹野内刑事課長ら幹部らがずらりと並ぶ。
遼一は柳沢捜査一課長の顔を目に焼き付けようとした。本庁に配置換えになった暁には、自分の上司になる人物である。柳沢捜査一課長は中肉中背の目付きの鋭い五十代半ばの男で、日に焼けた浅黒い精悍な顔立ちをしている。切れ者で通ってはいるが、今回の事件では苦戦を強いられており、打開策を見出せずにいる。その表情にわずかに困憊の色がうかがえた。
遼一は前方に立てかけられたホワイトボードに視線を転じた。ホワイトボードには、これまでに殺された四人の被害者の写真と殺害された日にち、名前、年齢、所属する組織名が記されている。
2/21 伊藤裕也(56) 須藤組
3/2 戸田慎介(57) 宮本組 元組員
3/10 小倉 漣(28) ブラックチェリー
3/14 岸谷彰吾(53) 天宮興業
会議の司会進行役の竹野内課長が講堂内をぐるりと見渡す。
「それでは、会議を始めます。今朝方、南池袋二丁目の住宅街の路上にて、天宮興業の組員、岸谷彰吾、五十三歳の遺体が発見された。詳しい死亡原因などは司法解剖の結果を待ち、追って報告するが、腹部を鋭利な刃物のようなもので一刺しされていること、額に×印が刻まれていることから、反社連続殺人事件の容疑者、通称、聖掃者の犯行であるとの見方が濃厚である。知ってのとおり、額に刻まれた×印の件はマスコミに公表していない。よって、この四件の事案は同一犯によるものと考えられる」
雛壇の柳沢捜査一課長は、虚空をにらみつけたまま、口を真一文字に結び、腕組みをした状態で動かずにいる。
竹野内課長は続けた。
「被害者の四人は反社あるいは元反社という以外に共通項はいまのところわかっていない。犯人にとって殺す相手は反社か元反社であれば誰でもよかった可能性も考えられる。通常、無差別殺人は社会的弱者が狙われる傾向があるから、本事案は極めてめずらしいケースかもしれない。それでは、昨夜の捜査会議に出席できなかった者は報告をお願いします」
夕方に営業が始まる店舗に聞き込みに行っていて、捜査会議に顔を出せなかった捜査員たちの報告が始まった。
最初に殺害された須藤組組員の伊藤裕也は、池袋一丁目にある組事務所の近くで、後ろから刃物で背中を刺されている。一撃目は傷が浅かったため、犯人ともみ合いになったようだ。伊藤が犯人を取り押さえようとしたのか、爪の間に犯人の皮膚片が入り込んだ、と推測される。犯人は何度か伊藤を刺したが、それでも伊藤は抵抗を続けたことが、遺体の両腕に残された防御創によりうかがえる。犯人は十回以上も刺し続け、ついに伊藤は失血性ショックで死亡した。聖掃者は伊藤の死後、その額に骨にまで達するほど深々と×印を刻んだ。聖掃者が殺人に手間取ったのは、最初のこのときだけであり、二人目以降はみな一刺しで殺している。
暴力団関係者からの聞き込みから、伊藤裕也は生前、裏カジノを商売にしていたことがわかっている。担当になった捜査員らは、伊藤の鑑取り(人間関係や交友関係の捜査)を行ったが、目ぼしい成果は上げられなかったと報告した。また、現場周辺の地取り(聞き込みの捜査)を行った捜査員らも同様に特筆すべき情報はないとのことだった。伊藤だけは発見時にスマホを所持していたため、解析が行われた。通信記録やSNSの利用履歴などから交友関係が洗われているが、こちらもいまのところ成果が出ていない。
二番目に殺害された宮本組元組員の戸田慎介は、北口の繁華街から付き合っている女のいるマンションへと歩いているところを、脇腹を刺され殺された。聖掃者はすれ違いざまに脇腹を迷うことなく一突きすることを学んだようだ。
戸田は宮本組の元組員であり、素行の悪さから組を破門された男だった。たいしたシノギも上げられないため、最近はカネに困っていたらしく、風俗嬢をしている女に食わせてもらっていたとは、かつての宮本組の組員の証言である。戸田の鑑取りと地取りを担当した捜査員らもまた、目新しい情報を得られなかった。
「次、薬師丸」
三番目に殺害されたブラックチェリーの小倉漣は、遼一と小田切の担当であり、鑑取りを任されていた。ブラックチェリーは末端まで入れると百人以上のメンバーがいる半グレ集団である。シノギは、投資詐欺、風俗、闇金融など多岐にわたるようだが、メンバーたちは秘密主義な上に結束が固いために、組織の実態がよくわかっていない。
小倉の鑑取りの成果もまた、芳しくない。生前何をシノギにしていたのかさえわかっていない。この四日間、遼一と小田切のコンビは、ブラックチェリーのメンバーたちに聞き込みを行ったが、彼らは頑として口を開こうとしなかった。ブラックチェリーの主要なアジトがどこにあるかは、所轄の組対からの情報、主に浜田から話を聞いて知っていた。池袋の隣にある要町駅近くのタワーマンションの最上階がブラックチェリーのリーダー、春日凌の自宅兼本拠地だという。いまどきの半グレというのはヤクザとは感覚がだいぶ違う。タワマンを訪ねてみたが、警察の聴取には応じないと、インターフォンの前で門前払いされてしまった。
小倉が組織においてどういう役割を担っていたのかわからないまま時間だけが過ぎた。昨夜、アジトの一つだというメンバーが経営する池袋駅北口にあるバーを訪ねたとき、酔っぱらったメンバーの一人が、「聖掃者はおれたちが見つけ出す。懸賞金が懸かってるからな」と口を滑らせた。懸賞金について聞くと、一千万円だという。やつらは警察には頼らず自分たちの力で聖掃者を見つけ出し、制裁を加えようとしているのだ。
遼一は椅子から立ち上がると、ブラックチェリーが聖掃者に懸賞金を懸けている旨を話した。一千万円という金額に、講堂のあちこちから驚きの声が漏れる。「おれも聖掃者を捕まえたら、一千万もらえるんだろうか?」と、誰かが冗談を飛ばし、一部から笑い声が上がった。
「おまえたちは引き続き、ブラックチェリーの聞き込みを行ってくれ」
「了解です」
竹野内課長の命令を聞いて、遼一は椅子に腰を下ろした。内心ほっと息を吐いて、思わずネクタイの結び目に手をやる。
隣に座っている谷川がつぶやく。
「あの被害者たちの中で、ブラックチェリーのメンバーだけが異質なんだよな」
遼一はあらためてホワイトボードに書かれた被害者を見た。確かに、谷川の言うとおり、殺された暴力団組員・元組員がみな五十代なのに対し、ブラックチェリーの小倉だけが、二十代と若い。
「ブラックチェリーのメンバーだけが若いってことですね。何か意味があるんですかね?」
「ブラックチェリーのほうは敵対する半グレ集団の仕業かもしれないぞ」
「でも、凶器は全員同一のものらしいし、額の×印だってあるんですよ」
「そういう可能性もある、ということだよ。とはいえまあ、おそらく通り魔だろうな」
「……通り魔ですかね?」
「被害者に共通項がないからな。知ってるか? マスコミ曰く、犯人は正義感の異常に強いサイコパスだそうだぞ」
「マスコミの言うこと信じてるんですか?」
遼一の呆れた声に、谷川は小さく肩をすくめた。
竹野内課長が会議の締めの言葉を口にした。
「マスコミが大騒ぎしているし、世間の注目度は高まるばかりだ。一刻も早い被疑者の確保が望まれる。諸君らもいっそう気を引き締めて任務に当たってもらいたい。以上だ」
捜査員たちがぞろぞろと立ち上がり、講堂の外へ向かう。先の見えないことも相まって、みんなの背中には疲れがこびりついていた。
3
遼一は途方に暮れた。これまでどおりブラックチェリーのメンバーから事情を聞こうとしても、彼らは口を割らないだろう。どうしたものか。夜になるまで待って、またメンバーが経営する池袋駅北口にあるバーを訪ね、酔っぱらった輩が口を滑らせるのを期待するか……。
遼一と小田切は池袋駅北口の繁華街を当てもなく歩いていた。午前中ということもあって、まだどこも店は開いておらず、空気は清涼で、人気がなく閑散としている。
今日も比較的暖かい日だった。小田切は小腹が空いたからと、近くのコンビニでホイップクリームたっぷりのデニッシュを買ってくると、歩きながらかぶりついた。
「うまいのか?」
「ええ、うまいですね。おれ、スイーツ大好きなんです」
遼一には自分でスイーツを買って食べるという習慣がない。
「高校時代、家が貧しくて、お小遣いを貯めてたまに買うコンビニのスイーツが最高の贅沢品だったもので。以来、コンビニのスイーツの大ファンなんですよ」
「人にはいろいろな過去があるものだな。なあ、この事件をどう思う?」
「どう思うといいますと?」
「マスコミの言うように、過剰な正義感を持ったサイコパスによる通り魔的な犯行なんだろうか、それとも、怨恨だろうか?」
小田切の細い目が遼一を見た。その表情が真剣なものに変わる。
「怨恨だとすると、被害者に共通する人物がいるはずですよね」
「だよな。そして、そいつが犯人だよな」
遼一は嘆息した。
「いまのところ殺された四人の被害者に共通点はない。組織もばらばらだし、現役と元暴力団の三人に半グレも一人交じっている。マスコミが言うように、池袋を根城にしている悪どもなら誰彼かまわず殺して回っている可能性だって捨てきれない」
「サイコパスの連続殺人鬼ですか。どんなやつだと思いますか?」
「案外、そこらへんにいそうな兄ちゃんだったりするかもな」
世間で怖い事件が起こると、犯人はどんな人間だろうと誰もが思うが、実際、犯人はどこにでもいそうなやつだったりするから厄介である。
「しくじったのは最初の犯行の一度だけ。それ以降は現場に何の痕跡も残していない。防犯カメラにも注意している。これじゃ手の打ちようがない」
小田切はデニッシュを平らげ、口のまわりを拭った。
「暗礁に乗り上げましたね……」
「そうだな……。ちょっとやり方を変えてみよう」
「ええ、どうします?」
「ブラックチェリーのメンバーに当たっても口は割らない。だから、カタギから話を聞くんだ。ブラックチェリーの周辺にいるカタギに。できれば、メンバーだったやつが理想的なんだが」
「探しましょう。きっといるはずです。でも、夜までどうしますかね」
小田切の言うとおりで、カタギに聞くと言っても、ブラックチェリーの周辺にいるような輩なら夜に街に繰り出してくる。それまでどうするべきかと考えていると、遼一の私用のスマホが鳴った。画面を見て思わず顔をしかめたが、出ないという道理もない。
「よう、久しぶり」
「久しぶりだな。いまから少し会えないか? ちょうど池袋にいるんだ」
「こっちはこれから捜査だ」
「例の聖掃者だろ。今朝も一人犠牲者が出たそうじゃないか」
「四人目だ」
「捜査も行き詰まっているそうだな」
「頭の痛い話だよ」
「気分転換にどうだ? そんなに時間は取らせん」
隣で小田切がうなずいている。自分は問題ないというように。
「じゃあ、会うか」
遼一は待ち合わせ場所を聞いて通話を切った。
「ちょっと人と会ってくるから、どこかで時間をつぶしててくれ」
「別にいいですよ。女ですか?」
「馬鹿言え。本庁人事一課の監察係長だ」
小田切は血相を変えた。
「ええっ⁉ 監察って……、薬師丸さん、何かやらかしたんですか?」
「いやいや、ただの同期の桜だよ」
遼一は笑った。通常、監察から連絡が来たとは、警察官人生の死を意味するからだ。
警視庁警務部は警視庁本部および都下百二の警察署すべての警察官の人事を司るエリート集団である。管理部門であるため犯罪捜査に当たることはないが、警務部人事一課の監察係は〝警察の警察〟ともいうべき存在であり、警察官の違法・触法行為(非違事案)を調査する任務を負っている。監察官に接触されたら警察官としての人生が終わると言われるほど恐れられており、遼一が監察から電話を受けたと知った小田切が驚いたのも無理はない。
片瀬勝成は遼一の高校時代からの友人だった。片瀬は当時から学業優秀で、大学も一流の私大を卒業している。二ランクも三ランクも落ちる大学を出ている遼一とは頭の出来が違う。そして、警察組織においては当然のように、出世にも違いが生まれてくる。片瀬は警部だ。警部補の遼一とは一つしか階級が違わないが、警部と警部補の間には大きな溝が横たわっている。しかも監察係長ともなれば、ノンキャリアの中では出世コースにいると言って過言ではない。父親もまた警察官で巡査から警視にまで上り詰めたというから、正真正銘のサラブレッドである。
池袋駅北口近くにある喫茶店に入った。レトロな雰囲気のある落ち着いた照明の店で、流行りのコーヒーショップよりも、遼一はこの手の昔ながらの喫茶店のほうが好きだった。
窓際の二人掛けの席に片瀬を見つけた。片瀬は遼一と同じ四十五歳だが、なかなかのイケオジである。最近あちこちに肉が付き始め、髪も薄くなってきた遼一とは大違いだ。スーツの上からも引き締まった身体がうかがえる。鍛えているのかもしれない。おまけに出世コースにいる警部殿ときている。嫉妬を覚えずにはいられなかった。
そんな感情を包み隠して、遼一はネクタイの結び目の位置を正すと、向かいの席に腰を下ろした。
「よう。元気そうだな」
「そっちはちょっと疲れてるみたいだな。髭ぐらい剃れよ、みっともない」
自分の見た目を馬鹿にされたような気がして、一気に気分が悪くなった。
「無理もないだろ。連日歩き回っていて、髭を剃る時間もないんだ。で、話って何だ?」
通りかかった店員にコーヒーを注文する。
片瀬は周囲に首をめぐらせた。店のテーブル席は互いの会話が聞こえない程度には離れている。
遼一に視線を戻す。一秒にも満たないほんのわずかの間、遼一の表情から何かを読み取ろうとする時間があったような気がした。
「知ってのとおり、おれの耳には東京中の警察官のいろんな情報が入ってくる。おまえのことも含めて」
「おれの?」
遼一はひやりとさせられた。とはいえ、監察に目をつけられるような非違行為を犯した覚えはない。
「おれ、何かやらかしたか?」
片瀬は顔の前で手を振った。
「いやいや、そうじゃない。今年、また昇任試験を受けるつもりでいるだろう?」
思わず顔をしかめた。一度落ちているからだ。片瀬のほうはとっくにそれに合格している。
「ああ。おかげで二年間も勉強してきたからな。今度は絶対パスするつもりだ」
「おまえなら受かると信じるが、警部に昇進できれば、本庁に配置換えになるかもしれない」
思わぬ話の展開に驚かされた。本庁への転属は遼一の願いである。
「本当か?」
「本当だ。本部勤務の候補者名簿におまえの名前が載っている。真面目な努力家だと評価されているようだ」
見る者は見ているものだ。真面目な努力家とは、遼一自身そう思っている。年末に勤務評定という人事評価があるが、上司が高い点数をつけてくれたのだろう。
「おまえに面と向かって言われると恥ずかしいがな。ありがたい話だ。今回の事件で手柄を立てられたら、本庁の心証はもっとよくなるだろうな」
「そりゃ、そうだろう。功績によっては表彰を受けるかもしれない」
警務部人事一課に属する表彰係は警視総監賞などの表彰を行っている。捜査本部が立つと、その所属長が表彰係に対して表彰の上申を行う。表彰が決定すると、捜査本部員の人事記録が人事情報管理システムに登録され、在籍中ずっとついてまわるという。功績を挙げた者は上層部の覚えが目出たくもなるだろう。出世にも大きく影響してくるはずだ。
警察組織内部で可能な限り出世すること、それこそが遼一の願いである。
俄然やる気が湧いてきた。
片瀬は内密な話をするように顔を近づけてきた。
「実際のところ捜査のほうはどうなんだ? おれもこの事案には興味がある」
この三週間、何人の同期から連絡を受けたことか。十年以上音沙汰のなかった知人からも電話がかかってきた。みんな捜査の状況を知りたいのだ。
コーヒーが運ばれてきて、遼一は店員が去るまで待った。
「どうもこうもない。最初の被害者の遺体からは犯人のものと思われる組織片が見つかってはいるが、警察のデータベースにヒットしなかった。以降、聖掃者は何一つ証拠を残していない。目撃情報もなし。犯人像がまるで浮かび上がってこない」
「これでもう四件目だろう。それで成果がまるでないんじゃ、世間の警察に対する風当たりが強くなるな」
「そう言われてもな。こっちだって頑張ってるんだ……」
じろりと遼一の顔を見た。何かを探っているような目だった。
「で、おまえはどう考えているんだ?」
何も考えていないと言えば無能だと思われる。遼一は誰にも話していない胸の内を吐露した。
「復讐じゃないかと考えている」
「ほう。どうして?」
「最初に殺された須藤組組員の伊藤裕也はめった刺しにされて殺された。最初の一撃で殺せず、もみ合いになったからだと幹部連中は考えているようだが……。おれは伊藤に対する犯人の憎悪を感じる」
「復讐ねぇ。刑事の勘か」
剃られたばかりのような顎をなでながらにやりと笑った。
遼一はふんと鼻を鳴らす。
「本当は伊藤の鑑取りをしたいところなんだが、おれはブラックチェリーの捜査を命じられている。こいつらがまた口が堅くてね。手柄を立てたいところなんだがなかなか難しいよ」
「そうか……」
そこで、会話が途切れた。片瀬はカップに口をつけると、「話は変わるが」と言った。
「その後、娘さんのほうはどうだ? 確かバレエ留学したんだったろ?」
今朝方の娘の行動を思い出して気分が悪くなったが、そのことには触れないことにした。
「いや、留学は今年の秋からだ。カネはかかるが、将来への投資だと思うことにしてる。本人もバレエダンサーでの成功を夢見てるしな。親としてできる限りのことはしたいと思ってる」
「そうか。いいな、子供っていうのは」
しみじみとそんなことを言う。片瀬に子供はいない。子供を欲しがっているのだろうか。
「息子さんのほうはどうだ?」
「え?」
また気分が悪くなる。息子は引きこもりだ。大学に進学できるかどうかも怪しい。
遼一はコーヒーを啜った。ブラックのコーヒーがことさら苦く感じる。
「ああ……。困ったもので、部屋に引きこもって何をしているのかさっぱりわからない。大学に進学できるかどうかも……」
「大学には行ったほうがいいだろう。話し合ってみたらどうだ?」
余計なアドバイスにむっとする。
「散々話し合いなんてしてきたよ。それでこの結果なんだ……。娘には息子の分まで頑張ってもらいたいよ」
「ふうん、そういうもんか……」
片瀬は腑に落ちない表情をしていた。子供のいない男に子供で悩む遼一の心境などわかるまい。
コーヒーを飲み干すと、店の前で片瀬と別れた。去り際、片瀬は「変な噂が耳に入ったら教えてくれ」と言ってきた。監察という仕事柄、所轄内の悪い噂を気にしているのかと思ったが、数歩歩き出して、遼一はふと立ち止まった。何のためにおれに会いたいと言ってきたのか。片瀬の探るような眼差しを思い出していた。
=======
続きは単行本「無限の正義」にて
お楽しみください。
=======