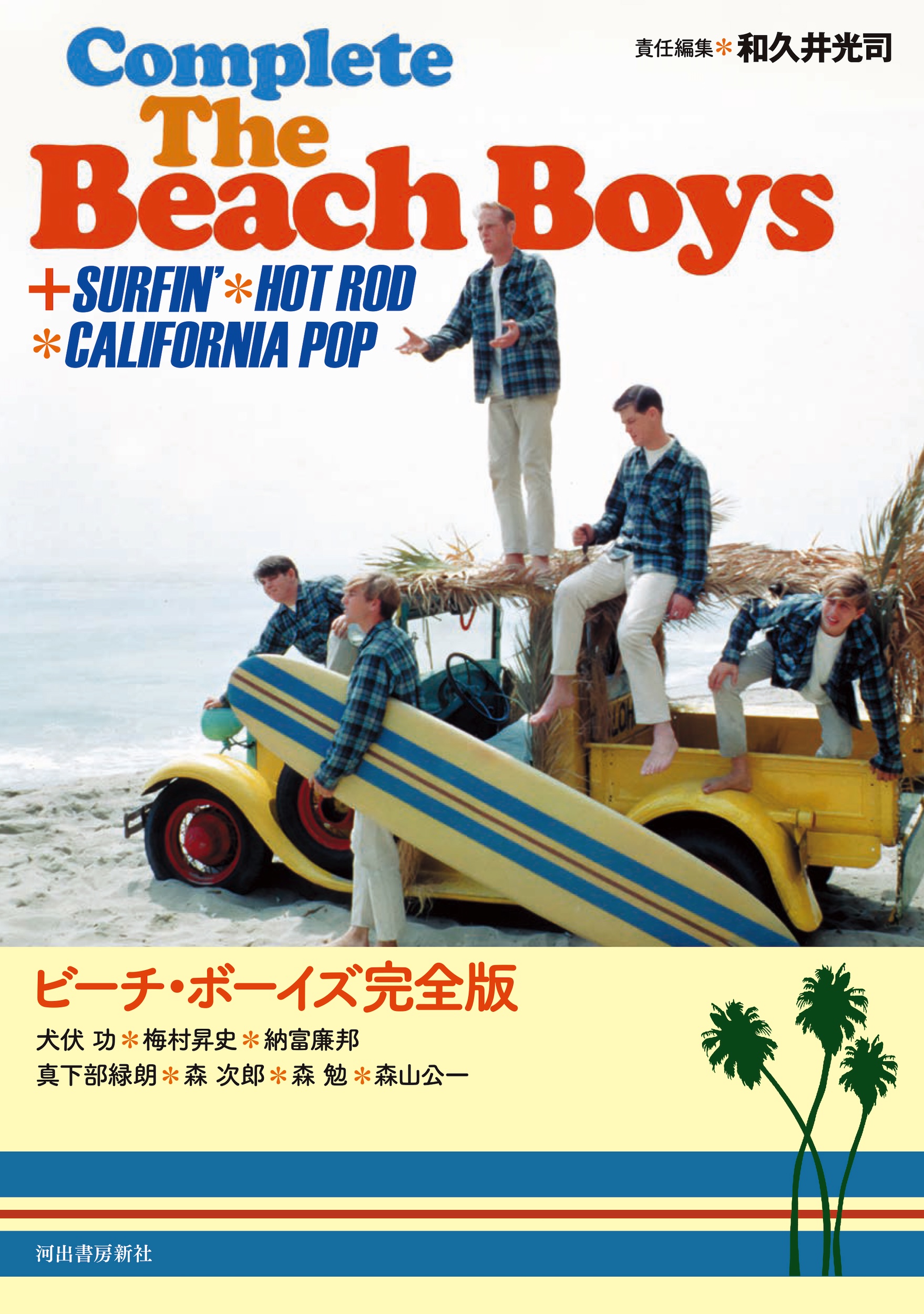ためし読み - ノンフィクション
特別対談「梯久美子×角野栄子 ここではないどこかへ―出かけて戻って書いて読んで」──「文藝別冊 総特集 角野栄子 水平線の向こう」より一部公開!
角野栄子
2024.02.16
この度刊行したKAWADEムック「文藝別冊 総特集 角野栄子 水平線の向こう」では、「フィクションVSノンフィクション」と題して、角野栄子さんと二人のノンフィクション作家との豪華な対談を収録しております。
第二弾では、ノンフィクション作家・梯久美子さんとの特別対談を一部公開いたします。
『狂うひと―「死の棘」の妻・島尾ミホ―』(新潮社)や『この父ありて―娘たちの歳月』(文藝春秋)など、綿密な調査に基づき、数々の作家たちの生涯を辿ってきた梯さん。そんな梯さんから見た角野栄子さんとは……?
「ここではないどこか」の文学
梯 今、住まいに対する感覚を伺いましたが、角野さんはもう一つ、「移動する文学」の人だと思っているんです。ここ数年、サハリン(旧樺太)に興味があって、三度ほど行きました。きっかけは宮沢賢治が百年前の一九二三年八月に樺太を旅をしていたことです。その年の五月にサハリンまでの鉄道が開通して、北海道との間の宗谷海峡も鉄道省の連絡船が運航するようになって、上野から樺太の栄浜という駅まで、鉄道切符を一枚買えば行けるようになった。当時学校の先生だった宮沢賢治は鉄道が好きで、教え子の就職を頼みにいくという口実で樺太に行くんですが、その汽車の中で、前年に亡くなった妹のトシの死についてずっと書いているんです、日付もつけて。それを読んで、宮沢の文学は移動する文学だと気がついたんですよね。語りに速度が感じられる。移り変わる風景に呼応するようにして心情が変化していく様子がすごく魅力的に描かれているんです。汽車や船だけではなくて、馬車に乗って書いてる部分もあるんですが、それを読むと馬車のスピードを感じます。
角野さんの作品も改めて読んでみると、移動する際の風景の描写がすごく面白い。『魔女の宅急便』で空から移動していく視点はもちろん、『イコ トラベリング 1948─』の冒頭、船が進んでいく時の水平線が見えたり波が下がっていく様子を描いた一ページ分ぐらいの描写も素晴らしくて。林芙美子も移動する文学の人だと最近思っているんですけど、やっぱり角野さんも移動の描写がものすごく素敵だと思います。
角野 私、ここではないどこかに行きたい人なのよ、常に。やっぱり、母がいなかったことが理由としてあると思います。父と新しい母が作った家庭は、たしかに私の居場所には違いないんだけれども、それでもなんかちょっと居心地が悪い。それは姉も感じていたと思いますし、弟もゆくゆく感じるようになったと思う。そういう環境だったから、そこに居続けるよりもっと他のところに行きたいという感覚は、大人になってからではなくて子どもの頃から持っていたんです。小学生の頃かな、江戸川の岸辺で水の流れをじーっと眺めながら、「ああ、あっちの方へ行ってみたいな」と思ったり、そんな記憶がありますね。
梯 『角野栄子さんと子どもの本の話をしよう』(講談社 二〇一五年)という本の中で、「ブラジルに行くなんてすごいね」と言われるけれど、それは今までが寂しい環境だったからで、自分の家の玄関の扉を開けて違う世界に行きたいといつも思っていたとおっしゃっていますよね。だから『魔女の宅急便』のキキも、旅立って新しい環境で生きていくことになった時、本当は寂しい気持ちもあったと思いますけれど、すごく前向きに描かれていますよね。
角野 そうね、出口はそこしかなかったっていう感じがするわね。居続けることもできるんだけど、そこに不満があるんだったら自ら出ていくしかない。姉もなるべく早く結婚しようと思ってたって言ってましたから。
梯 家を出て自分の新しい居場所を作ろうということですか。でも、結局「居場所」にならなくて、どんどん進んでいろんなところに行っちゃう(笑)。
角野 そうそう、落ち着きないのよ(笑)。
梯 今いるところが辛くて別のところに行く時、半分は辛さから逃げることなんだけど、もう半分は希望だったり、もっと面白い良いことがあるんじゃないかというような前向きな気持ちなんですね。
角野 自分で動いたら「良かった」と思えることはたしかにありますね。けれど、自分から動くエネルギーすらないっていう子もいるんじゃないかなとは思うんだけどね。私は転校は意外といいと思ってるんですよ。
梯 角野さんは疎開してみたかったっておっしゃっていましたよね。それまでの泣き虫で弱い自分のことを誰も知らないところに行きたいと思っていたって。私、いろんな人に疎開の話を聞いたんですけど、みんな嫌だったとおっしゃるんですよ。行ってみたかったという方は角野さんが初めてでした。
角野 自分を変えるチャンスだと思ったのよ。疎開先で出会う人は誰も私のことを知らない。それまでの私は文句ばっかり言ってぶーぶー泣いてた子だったから、変わらないといけないなって。その時少し変わったような気がしましたね。
梯 『トンネルの森 1945』に出てきましたね。変わろうと思って方言を覚えるんですよね。自分のことも「俺」って言って。
角野 「俺」って言わないとみんな笑うのよ。
梯 「四年何組、角野栄子」って自分の名前を叫んでからトンネルを通ったという話も、元気でかわいいんですが、よく考えるとかなり辛い境遇なんですよね。
角野 そうそう。実の母も亡くなっていて、唯一頼れる父もいないものですから。継母はひどい人ではなかったけれども、私たちにどう接していいかわからなかったみたいでしたしね。それはしょうがないと思う。
梯 結婚したばかり、赤ちゃんも産んだばかりですものね。この、トンネルの前で何年何組って言って歌を歌うエピソードは本当の話なんですよね?
角野 そうです。「みかんの花咲く丘」とか「お山の杉の子」とかね。
梯 それがすごくいいなと思いました。「私はここにいます」という世界に対する宣言みたいなものでしょう。
角野 トンネルってラッパみたいじゃない?
梯 ああ、声が響いて。
角野 そうそう。それで毎日通るから、私はこういう子だっていうのをトンネルに知ってもらいたいなっていう気持ちでね。
梯 「トンネルに知ってもらいたい」というのが、ファンタジー作家っぽいですね。そういう怖い気持ちと折り合おう、人間ではなくて“モノ”であるトンネルと仲良くなろう、知ってもらおうというのがすごいです。これは創作かもしれませんが、兵隊さんがそこで死んだんじゃないかっていう話も出てきますよね。
角野 実際に噂があったんです。事実かどうかはわからないんだけど、私が疎開した家に昔、逃げ込んだらしいって友だちに言われて、ちょっと怖くなりました。脱走というのは極刑になるくらい悪いことなんだけど、その兵隊さんが一人で逃げたっていう決意、極刑になってもいいという覚悟はすごいって思ったわけ。誰にも言えない、家族にも言えない、そうしてたった一人で逃げ続けて。
梯 勇気を出して、ここではないどこかに行ったわけですからね。終わり方もいいですよね、兵隊さんを見たような気がしてふと気づくと、光の中からお父さんが帰ってくる。お母さんが亡くなった話から始まって、もしかするともう死んでおばけになっているかもしれない脱走兵の話で終わる。死というものをファンタジックに、でもリアルにお書きになっているなと思いました。
角野 死ということでよく覚えているのは、一つは我が家のお墓の納骨棺です。うちのお墓は清澄庭園の反対側にあって、関東大震災で全部焼けちゃったのでコンクリートでできてるの。墓石の下を開けて、地面の下の穴に紐で吊るして骨壺を入れるようになっているんだけど、中を覗いたら真っ暗で、死んでからあんな暗いところに行くのかと考えたらとても嫌だったの。まだ五歳でしたから。それで、向こうの世界というのがあって、そこに母が行っていたらいいなと思って、その世界がどんなところなのかをよく想像した。もう一つ覚えているのは、お盆の時に焚くお迎え火。父はご先祖様が帰ってくると言うんだけど、私たち姉弟にとって帰ってくるのは母なんです。母を家の中に案内するつもりで、父は「入り口が高くなってるからつまずかないようにお入りください、簞笥の角にぶつからないようにお仏壇まで行ってください」って言うのよ。すると、実際には見えないんだけど母が見えるような気がして、お盆の間だけは必ず母がいると感じられるの。怖い半分、嬉しい半分。そういうことを言った父はすごいと思っています。
梯 早くにご家族を亡くされたこともあって、死は怖いけど、死者は近しい存在で、亡くなった人が帰ってくるのは怖いけどそれがお母様だからちょっと嬉しい、という感覚なんですね。死者の世界と生きている世界が、だんだん緩く繫がっていく感じが良いなと思うようになったのは、歳をとってからですか? それとも昔からですか?
角野 小さい時からです。家の玄関の隣に小さな部屋があったんだけど、子どもの頃、嫌なことがあるとその部屋で泣きながら、「玄関のドアを開けて出ていく」という家出話を妄想していたの。家出して優しいおばさんに会うとか、カステラをお土産でもらうとかね。そうやっていろいろ妄想するうちにだんだん元気になって、泣きやんでいたんです。私たちは違う世界に出かけていくと、そこでいろんなものに出会って、見て、また帰ってきますよね。それこそが物語の原型だと思うんです。トールキンが「行ゆきて帰りし物語」と言っているけれど、本当にその通りだと思う。
梯 先ほど角野さんが、辛い状況にある子どもは物理的にどこかへ逃げるエネルギーすらない場合もあるかもしれないとおっしゃっていましたが、そういう子でも、どこかへ出ていくという想像をするだけで慰められて、力をもらえるのかもしれませんね。
角野 そうね。それって、まさに本と同じだと思う。本も、扉を開いて違う世界に行くじゃないですか。
梯 本の表紙を開いた一ページ目を、まさに「扉」と言いますしね。本は絶対に終わりがあるし、元の場所に戻って来られるから、子どもにとっても安心感があると思います。行ったきりだとちょっと不安ですけど。
角野 だから子どもの本はハッピーエンドにしたいですよね。もしくはこれから何が起きるかなっていうワクワクで終わるのもいいかもしれない。
*****
続きはぜひKAWADEムック「文藝別冊 総特集 角野栄子 水平線の向こう」でお楽しみください!