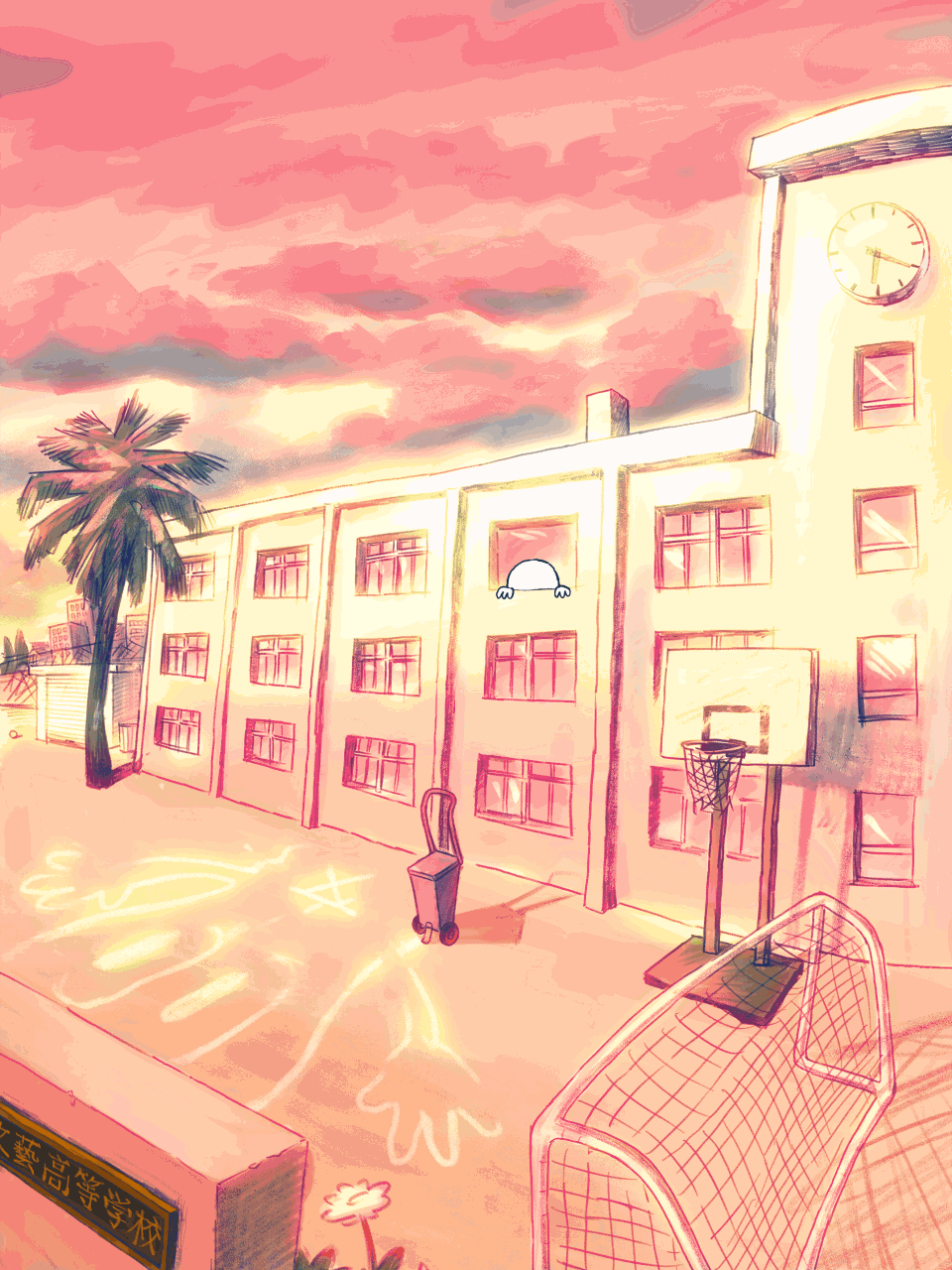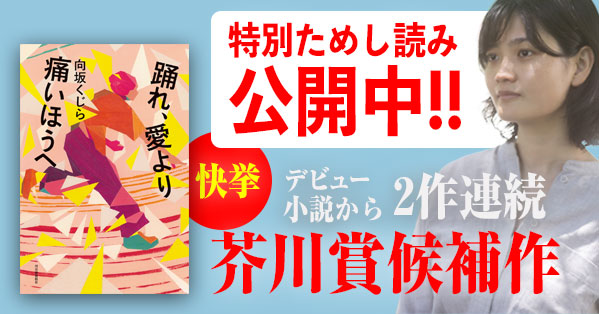ためし読み - 日本文学
町屋良平『生きる演技』刊行記念 冒頭無料公開
町屋良平
2024.03.12
芥川賞作家・町屋良平さんが「デビューから7年のすべてを投じました」という新作長篇、『生きる演技』の刊行を記念して、作品冒頭の一部を公開します。
元「天才」子役の生崎と、「炎上系」俳優の笹岡。高校1年生男子ふたりは、性格は真逆だが、同じように親を憎み、家族を呪う。そしてふたりが文化祭で演じた本気の舞台は、戦争の惨劇――。
朝日新聞文芸時評で古川日出男さんが「最高に読み応えがあり、かつ唯一無二の印象がある。時代のフロンティアに刺さっている」と評してくださった、著者最高到達点となる本作。
ぜひご一読ください。
===ためし読みはこちら===
『生きる演技』
町屋良平
1
暗闇の解像度を上げると光った。かれは午前四時の公園にいる。あたりは暗く、視覚だけでは捉えきれない場を感じる。景色が五感に混ざっていく。土の匂いや風の音で風景をかきわけ、さわる樹皮の感覚で補う視界はまるく、重々しい塊のような世界が迫ってくる。それでようやくあらわれる枝葉の様子をその身で捉えると、視力が増していくかのように暗さに慣れる五感が下方へと繋がっていき、ふくらみを帯びた幹に裂ける皮のさかいから新芽がこぼれるのを光が満ちる前にたしかに見た。
それからスツールに座って明け方の公園に休む、かれの輪郭を溶かすようにじょじょに朝の光が広がると、さっき夜闇にまぎれ公園を歩き見ていたものとは違う木々の姿が現れ、公園の全景が現れ、かれは丁寧に五感を修正し、風景を身体に混ぜた。朝になっていく移ろいとともに吹く風が、寝起きの肌の上がっていく体温を深部へと戻すように、かれの半袖からのびる腕の産毛にとどこおる。枝葉の隙間から空の、晴れているがどこか青オレンジのようなあいまいな色が目に映る。スタッフの集まる酸い臭いが点々と空気に混ざり、翻って自分の身体を思い出す。自らの身体が持つ社会性を、役割を思い出す。いつかこの身体もこうした臭いを発するようになるのだろうか。
ドラマの現場はやたらとスタッフが多く、演者を緊張させないための笑顔はみんな同じで、かれは人間の表情をできるだけ見ないようにする。その代わりのように公園の表情をうかがうと、ようやく集中できる身体だった。五時を待っている。割本に「青オレンジ、加齢臭、明けていく朝に間違っていた風景、合っていた風景」と汚い字でメモしていった。公園全体のイメージを描き起こすような抽象的なイラストも加えた。この場の昨日や明日にこもる記憶や、長い時間をかけ風景が経験した恋愛や団欒や蹂躙や殺人のことを思い出し、公園自体が演じるみたいにここにいる。これから主演と抱き合い、主演に愛を囁かれる。まだかれは十五歳で、ギリギリ子役と区分される年齢だから五時までは〝労働〟を禁止されている。だれかと抱き合うことも愛することも現実ではまったく経験のないことだった。監督から指示を聞いて何回かリハをやり、動きの機微と動線を確認する。それで余計な思考や仕草を切っていくように削ぎ動くと、やがて監督は「もう生崎くんはそれでいい」と言った。かれの相手役となる主演の気分を丁寧に上げていく、言葉に動きと表情の指示をこまかく混ぜる。
五時きっかりに撮りは始まった。
「よーいスタート」
いつも思う。本番を告げる声はなんと間抜けなものだが、現実はつねに間抜けなのだからリアリティとしては正しい。助監督が伸ばした人差し指をくるくる回す、撮影中であることを場にしめす動作を視界のはしで捉えた次の瞬間に、フッとかれは意識を身体と場の中間に預けるように滲む。そして主演に抱きついた。
泣く。
主演がなにか言っている。なにを言うかは知っていたけど初めて聞いた。
「愛してる」
そう主演は言った。
「カット」
監督がモニターを覗き込む。棒読みというより一言一句はっきり発音しすぎている、もう少し長くカットがかからなければ演じている身体がさっと醒めていくような「愛してる」だった。
「うん。はい、オッケー」
われわれにはあまり時間がない。
早くしないと完全に朝になってしまう。このシーンはまだ薄暗いうちに撮らなければならない。主演はかれと別れて早朝に旅立つ。かれは役の上で主演と今生の別れだからどこへ行くか知らない。モニターを囲む監督らが、なにか話し合う。ここでの撮りはこのワンカットのみだ。すぐにスタッフが主演に駆け寄り演技を讃えた。迫真の演技だったよ。役の昌子が、まさに乗り移ってた。狂気を感じたよ! いやー、こっちまで泣きそうだったな。
「いいねいいね、よくやったよ」
監督が主演に言って、ニッコリ笑った。すごくよく見るタイプの笑顔。タイプ1の笑顔。かれのマネージャーも寄ってきて、「陽くんおつかれ。いい涙だったよ」と言った。
「ありがとうございます」
「だいじょぶそ? もろもろ」
「はい。だいじょぶそです。もろもろ」
マネージャーの口癖をさりげなく真似て和ませた。その実、普段はモデルをしているという主演以上にぎこちなかった自らの演技を頭のなかで反芻し、うんざりしている。つまらないフィクションのなかでまた人を愛してしまった。かれがフィクションで人を愛するのはこれで十三度目で、この作品がかれの最後のドラマ仕事になる。
「このあとは、入学式?」
マネージャーが今日何度目かの台詞を言う。
「そですよ」
「ほんとに、陽くんお仕事セーブする? オーディションとか、もうLINEしないほうがいいよね」
「あ、はい。すいません。しばらく真面目に高校生やります」
「おけおけ。何度もごめんね」
そのころには完全に朝になった。かれの身体から出ていく、公園がザワザワ立ち上がる。人体はシャツ一枚でも充分暖かい、季節をよろこんでいた。
一年A組の札がついた教室は、初めてそこに身を置く高校生約三十人を迎えて騒々しく、机が、椅子が、教卓が、ホワイトボードがそれぞれの情緒で落ち着かず、その昂揚が高校生たちの身体を浮き立たせていた。われわれはうれしい。あらたな春が、そもそもうれしいのだった。いっぱいの高校生の、これからを思う。始まるドラマが場をアッパーにさせ、現実がそれを鎮めんとする。春にしては幾分つめたい風が窓から廊下へ抜けゆき身体らが醒める。
担任との初対面を待つかれ、生崎陽はボンヤリその時間を過ごしている。場の騒々しさに浮ついて、すこし頬が緩みそうになっていた。そうだよね、うれしいよね、春。かれよりもつよく場がそう思っていることを、クラスの中でかれだけがすこしわかる。うしろの席に座っている男子がこちらに身を乗り出してきて椅子をコンコンと叩き、「初めまして、前後の席だね~」と言った。
話しかけてくれている?
かれはうれしい。ややマスクを下げて唇の上のほうまでを見せ、「うん、よろしくお願いします」と言った。相手も同じようにした。
「生崎くん? オレ甲本。これ、五十音順なんですね。しばらくこの順なのかなあ」
「あ、そういうことなんですね。どうなんだろ、あー、すぐに席替え、やるのかもですね」
「ね、あ、入学式どうだった?」
入学式どうだった?
かれがスッと言葉が出ずに、「えー、入学式、だったよねえ。なんか。あー、すごく」というようなことをゴニョゴニョと喋っていると甲本の横に座っていた生徒が、「ねえ、おなじ中学のヒト?」と聞いてきた。
「え、違います。なんか、ただ話してた」
「ウン。甲本くんが話しかけてくれたの」
「そうなんだ。私、慶具っていいます」
「よろしくお願いします」
「よろしくお願いします。おなじ中学の子、みんな別クラになっちゃって、ちょー緊張……」
「わかる。おれも、知り合いいないから」
「オレもオレも。ね、入学式どうだった?」
「え、入学式? あー、なんか、豪華すぎず、質素すぎず。あ、でもあの区民会館、小学校のとき合唱でなんか来た気がする」
「そうなんだ。え、なんか選抜みたいなの? 地区の」
「たぶんそうだったと思います。そんときの担任がなんか音楽の先生だったからかも」
「あー。わかるかもその感じ」
「オレはねえ、入学式でスニーカー履いてきちゃって、恥ずい。ねえ、なんでみんなローファーっていうの? そういうの知ったんすか?」
「え、なんか親に言われて。ホントだ。甲本くんスニーカー。でもかっこいいっすよ」
「えー、ありがとうございます。なんかすごい、誰かに言いたくて恥ずかしって」
そこに担任教師が来た。
福生幸と名乗った若い先生の話を聞き、自己紹介に緊張しながら先ほど初めて話した甲本の、「入学式どうだった?」っておもしろい質問だったな、とかれは思った。しかも、二回聞いていた。慶具とかれに。ひとりだけスニーカーを履いてきたことがよっぽど恥ずかしかったのだ。
朝の撮影時から感じていたことだが、今日はすごく天気がいい。窓から差し込む陽光が教室の三分の二を斜めに切って、隣に座る慶具の腰のあたりから膝下までを照らしている。全開にされた窓から強風が吹き込んで、壇上で話している福生の声がよく聞こえない。早起きがたたり半分眠りかけていた。私服もオーケーの校則のゆるい公立校だが、入学式の今日はみなブレザーを着ていて、たしかに足元は大体ローファーで統一されているけれど、思い返せばたった一ヶ月前までスニーカーで中学校に通っていたのだから、甲本からするとわれわれがグルになって自分ひとりを騙しているのだとビックリしていた。
ホームルームが終わり、今日はもう帰ってよいということになった。男子十五人、女子十九人のクラスで中学よりゆるやかに配置された机、いまはまだ用途のわからない部屋がたくさんありそうな校舎とまだ足を踏み入れていないたくさんの建物。
「甲本くん、徒歩? チャリ?」
「オレは徒歩でモノすよ。電車ですか? 一緒に出ます?」
「いや立川なんで家。でも、途中まで一緒に出ないすか? もともとだれか帰るひといる?」
「あ、D組の友達誘っていい?」
「いいっすよ、あ、なんかすいません邪魔だったら」
「ぜんぜん。一緒に出よ」
「ねえ、生崎くん。生崎陽くん」
話していると突然、背後から大きめの声がした。振り向くと、ちょうどかれと同程度の体格の男子がかれを見下ろして笑顔になっている。
「ねえ、生崎陽くんでしょ? おれ、笹岡樹っていいます。ねえ、生崎陽くんってあの生崎陽くん? 昔ドラマの、あの『母』っていう名前の作品に出てたよね」
「あ、いや。はい、一応」
「やっぱり。あのドラマでしてたキスシーン、あれめっちゃエロかったよね!」
笹岡はあきらかに興奮している。われわれがかれらを見ている。かれは自分の感情に集中する。それでかれはこの笹岡樹という名前を持つ初対面の同級生のことをめちゃくちゃ嫌いになった。
*
「ね、笹岡くん高一ってほんとう?」
リハの合間に仲田を演じる立野にそう聞かれ、かれは一瞬にして役の上では仲いい、だけどそれ以外では初会話であるという設定をなんとなく頭に思い浮かべるが、それはドラマというより現実の設定である。
「あーうん。そう。です。あは。フレッシュな」
「マジフレッシュ!」
「マジフレッシュ! そう。ありがとうございます」
わざわざ新一年生であることを聞かれたということは、たぶん年上なのだろう。
木材にこもった湿気が教室中にたちこめていた。内側にいる二十名ほどの同級生たちから匂うヘアケア商品やメイクの香り。そうしたキラキラはフィクションで演じられる偽の友情、偽の人格を覆い隠し、つくられたセットをより現実の教室らしくしていた。ここは演者がいないと明確にセットだとわかる、しかし演者がいる状態でカメラに撮られると現実より本物の教室らしくなる。そのようにつくられている、なにかしら「引かれている」場なのだった。
撮影が始まる。教室で教師役と主演が言い争うシーンが予定されている、声は出していないのに各々のグループが雑談をしているような表情をつくる。セットについた偽りの汚れや疲れが同じメンバーで撮影してきたフィクションのクラス時間を表し、これは高校三年生の設定だからもう二年この学校に通っているような顔をして違う制服を着ているけれど現実のかれ、笹岡樹は高校に入学してまだ一ヶ月しかたっていない。
たった一ヶ月の経験を、二年やり尽くしたかのような顔をする、セットと一緒に場に疲れていく、かれはシーンとシーンの間に生崎陽に言われた台詞を思い出す。
「キス……ありがとうございます」
しかし、顔は醒めきっていた。というより、現実に醒めているときの顔ではなく、醒めている演技をしているときの生崎の顔だとかれにはわかった。演じている者だからこそわかる両者の差分は、それを感じ分ける者にだけ伝わる強いメッセージになる。ようするにありがとうございますの発音で、余計なことを言うなと言われている。やはり生崎陽はいい俳優だとかれは思う。
シーンが再開され、そんなことはすぐに忘れる。生崎陽の心根に直接さわってしまったような感触を得たかれはしかし謎のモチベーションで、自分も生崎陽のように演じたい、もっともっと演技について考えたい、と昂った。教室で乱闘、そんなベタなシーンのさなかに人格がありすぎるようでもなさすぎるようでもダメ、そんなモブのクラスメイトに相応しい身振りでそこに存在し、そのように現実のかれと役のかれが分かたれて、目立った台詞のない役をこなすことに途方もないよろこびを感じていた。
「おい、だいじょうぶなのかよあんなこといっちゃって!」
「失敗したら、今度こそほんとに退学だぞ!」
「あーあ、先が思いやられるなあ」
「まったく」
「まったく」がかれに割り振られた台詞だった。実際にはまだ一ヶ月しか高校生してない自分がもう二年もこの教室に通っている実感が「まったく」という台詞を言うだけで積み上がっていくようで、とたんに幸せになる。偽の友情が、偽の青春が、偽の人格が、心からうれしい。カットがかかると、すこし役のままの友情を引きずって演者たちは、それぞれの社会に戻る。
かれの演じるクラスメイトらが映り込むシーンはそれほど必要とされておらず、全十一話の放送シーンを二日に分けてすべて撮ってしまう予定だった。今日は二週間空いたその二回目の日で、名字しかないクラスメイトを演じる者たちはこれでオールアップなのだけどただ制服を返して日常に戻るだけで演じた人格もすぐに忘れる。全員がこのドラマをぜんぜん面白くないと思っている。どうやら役の上で親友らしい仲田を演じる立野とかれは今後の人生で二度と会わなかった。
終了予定の八時ギリギリまでかかった撮影が終わり、スマホをさわっていると事務所から、
…… 不幸トーク系のアンケートきてたから、ファイル送ります
というLINEとWordの添付ファイルが送られてきた。
…… ありがとうございます!
かれは深夜バラエティのトークコーナーに、半年に一、二回ほど出る。話すテーマはいつも両親の逮捕について。最近はオーディションの合格率もよくなってきた。知名度が有利に働いているというより、若くして自分を偽りなく喋る様子が受けているのだと思う。エチュードや作品に応じた迫真がうまく演じられるわけではないのに、カメラの前で自然でいるのは好きで得意だった。元々は中学時代に趣味でしていたYouTubeでの暴露系トークがテレビプロデューサーの目に止まり、そうした露悪を深夜バラエティの数分で披露しているうちにスタッフの一人がドラマ制作に移り、エキストラに起用してもらえることがたびたびあった。もともと零細だったYouTubeはモチベーションがなくなり閉じてしまったが、人伝に紹介された事務所に所属してからは子役出身の本格派に交ざって積極的にオーディションを受けに行っている。いま露出量に比べて知名度が多少あるのはかれが両親の前科を売って活動している、つまり犯罪自慢といわれてアンチが多いせいだったがアンチがつけばファンも同じようについた。
「笹岡樹くんは、え、両親が両方逮捕って、いったいなにをして? 大丈夫? 言えるやつ?」
「ぜんぜん大丈夫です! 両親が家で麻薬を栽培していて、夜中にドラッグパーティーしていて、それがバレて懲役二年っすね!」
それから麻薬を通年収穫している家あるあるを言う。家に立ち込めるうす甘い匂いだの、襖の隙間から漏れでるLEDライトの明るみだの、めちゃくちゃうれしそうに喋るので、君もなんかヤってない?と言われて毎回受ける。そういう機会が忘れたころにまたやってくる。高校に通いはじめて一ヶ月、そろそろ噂は広まってこうした動画が出回り、中身の薄い自己紹介などでは伝わりきらない醜聞が現実のクラスメイトにもおおむね知れ渡っていた。同級生の都築に一昨日、「笹岡くんち、両親が大麻で逮捕ってマジ?」と直接言われた。
「マジマジ。やらせなし」
「うおー。事情抱えてるなあ」
都築はなぜか羨ましそうだった。直接聞かれるということはきっともうクラスの八割は知っている。けれどダメ押しでまたTVで喋れたらかれはうれしい。
「笹岡くんはそんで、将来の夢とかはあるの?」
「やー、ないっすね。なくないっすか? 中坊で夢とか」
「いやあるでしょー。いずれドラマで主演やるぞ!とか、有名になりたい!とか普通」
「いやー、いやいやいや。そういうのは無理なんで、ぜんぜん、演技得意じゃないんで。あ、好きなんすけどね! 演技。夢っすか。うーん、強いていうならやっぱ……おれも一回逮捕されてみたいっすね」
「あーダメだ。やっぱこの子もなんかヤってるわ」
過去に出演した自分の動画を眺めていると、笹岡樹という人格がどんどん傷ついていく、いいぞいいぞと思う。この現実でこの身体がどうなったってかまわない。
家に帰ると、児玉司がかれの部屋で待っていた。
「おつかれーい」
中間試験にむけ勉強しようと約束していたのだった。黒い楕円の形をしたテーブルに参考書、ノート、タブレットを広げ、数式解説動画を聞いていたイヤフォンを外して児玉が「おかえりー」と言った。
「飯くってきた?」
「食べたー。樹のご飯はある?」
「コンビニで買ってきた」
両親が二年の服役を終えたのが中二の冬のことで、さらに半年を空けてふたたび同居している。その間は叔父夫婦の家に預けられていた。
入所前は元気だった母は戻ってくると寝たきりになっていた。薬物依存の果てに若くして発症した認知症状による自傷癖があり暴れるので、家を空けるとき父親の風呂のときなどにはベッドに身体拘束していることを、ケアマネには黙っていた。腰を悪くして歩くこともままならず、一家は生活保護を受けながら父とヘルパーとで介護を行い生きている。笹岡樹の稼ぐギャラも生活保護の減額対象として役所に申請しなければならず、かれはいちいち収入をケースワーカーに報告していたが、いまのところ大学進学の資金を貯めているものと認定され減額はされていない。出所した両親とまともに口を利いたのはケースワーカーの同席する数十分だけで、あとは定期的に両親に「死ね」と言う。
児玉と勉強していても、ときどき母の呻くような、悲鳴のような声が聞こえる。
レンジで温めたコンビニ弁当を食べながら、教科書を開いて勉強した。高校初めのテストが肝腎だと先生たちは言っていた。中学で培った学力の保険はすぐになくなるから、早いうちに勉強する習慣をつけないとすぐに落ちこぼれる。中学のようにテスト前の勉強だけではなんともならない。かれと児玉は小学生の頃から一緒なので、しっかり時間を区切って勉強するリズムに持っていきやすかった。思考を問題に向けながらそれでも会話ができる、互いに集中の妨げにならない存在感を長い時間で培った。小中では友達というものが一切できなかったから児玉はかれのゆいいつだ。
一ヶ月の高校生活。入学式の日に、児玉とはクラスが分かれて落ち込んだけど、生崎陽ってまさかあの生崎陽?と思って顔を見たらまんま生崎陽で驚いた。スポーツテストで倒れた花倉はそのままクラスに来なくなり、ときどき保健室登校をしているらしかった。新一年生歓迎会で謎の踊りを披露していたイケてる先輩のTikTok投稿がバズって問題になり、校舎内の撮影がすべて禁止となった。その「ひまわり祭」という由縁のよくわからない歓迎会で、90年代にヒットしたダンスナンバーを踊るのがクラスで流行って放課後に動画を撮影しに行くメンバーと、そういうのが無理なメンバーとでざっくりクラスは分かれて、動画に映れる踊れる派閥と無理な派閥、無理かOKか決めかねてさぐりさぐりで折衝している派閥とゆるやかな輪郭がつくられていった。かれは生崎陽と友達になりたかった。
「けど、なんかダメみたい。くそ避けられてる」
「エロいキス発言がダメだったんだろ」
「あれ、ダメ?」
「ダメに決まってるだろ。どんなセクハラ野郎でも初対面でエロいとか言わないでしょ普通」
かれには知るべくもないことだが、このときすでに大抵のわれわれはかれのことを嫌っていた。
=======
続きは単行本「生きる演技」にて
お楽しみください。
=======