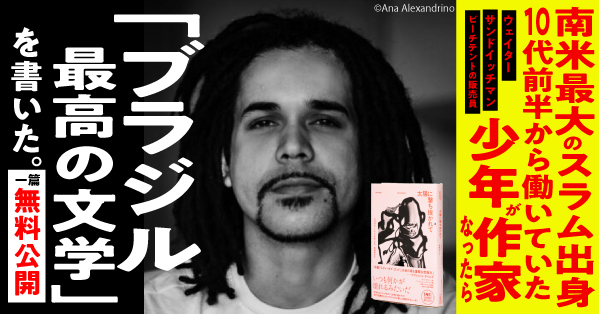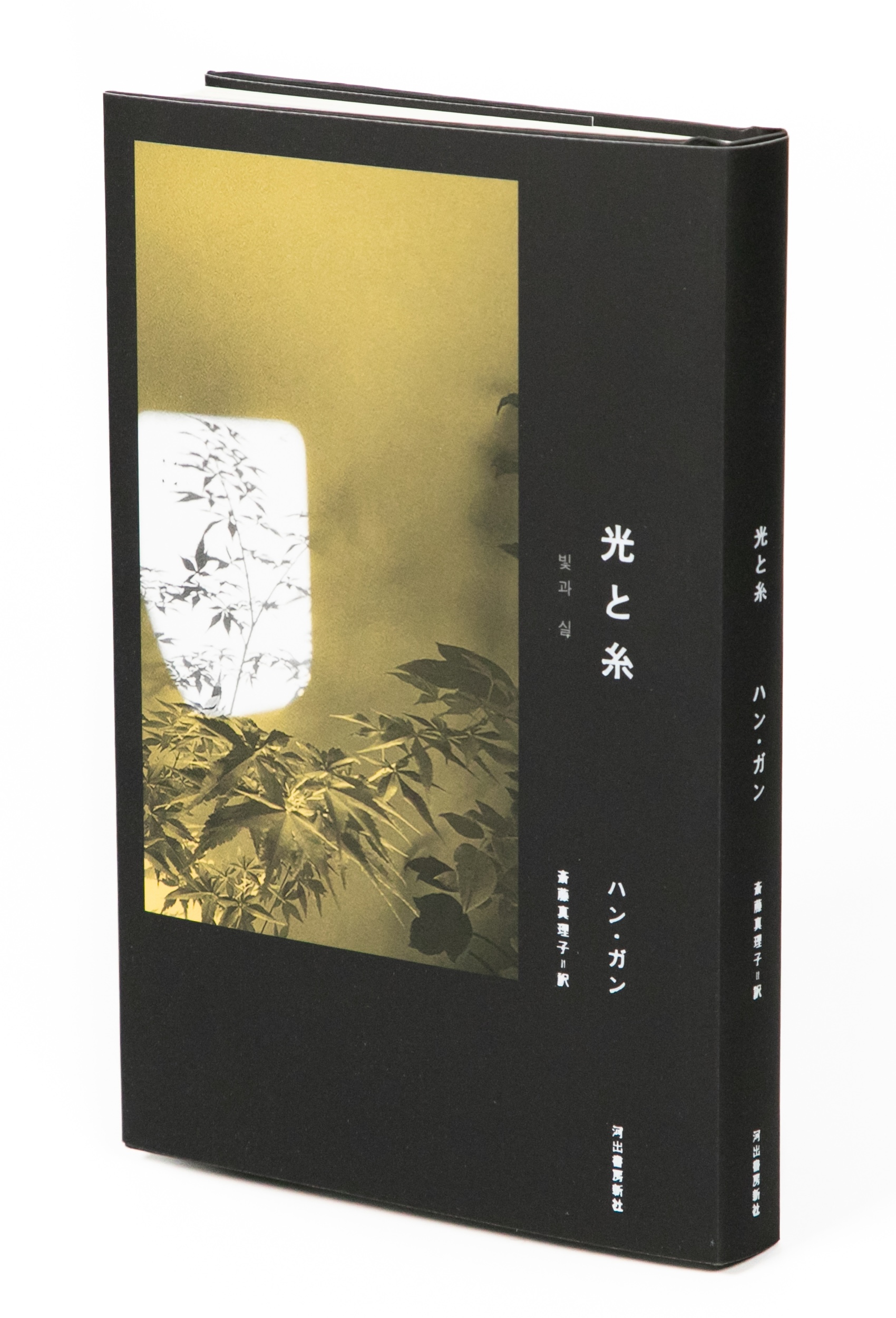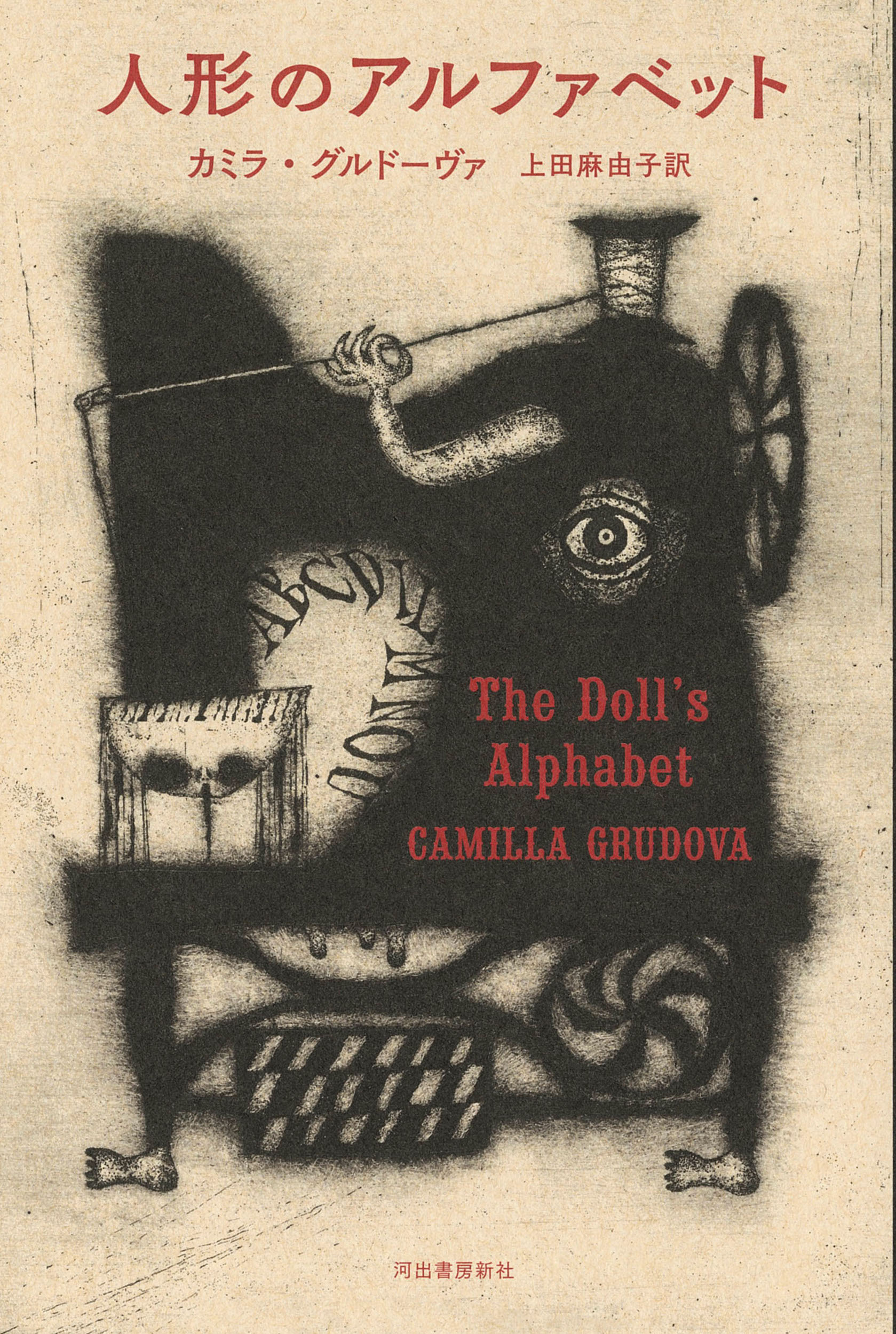ためし読み - 海外文学
ナボコフが才能を絶賛した《新世代の代弁者》デルモア・シュワルツとは誰か?――『夢のなかで責任がはじまる』訳者・小澤身和子さんによる「あとがき」を全文公開!
デルモア・シュワルツ ルー・リード序文 小澤身和子訳
2024.07.29
「夢のなかで責任がはじまる」という、たった一本の短編小説で、一夜にして二十世紀アメリカ文学史上に伝説を残した作家、デルモア・シュワルツ。
ウラジーミル・ナボコフが、サリンジャーの「バナナフィッシュ日和」と並べて高く評価したその作品は、T・S・エリオット、エズラ・パウンド、ソール・ベロー、ハンナ・アーレントら錚々たる作家たちも絶賛しました。
日本では、柴田元幸さん、坪内祐三さん、畑中佳樹さんらの紹介により、あるいは世界的ミュージシャンのルー・リードに文学を教えた人物として、ひそかに一部で知られていましたが、このたび、初めて邦訳作品集が刊行となりました。
「たった一発の狙いすました弾丸でたった一つの的を射抜き、あとは一切余計なことをせずに死んでいった作家」(畑中佳樹)
「自分たちの世代のボイス」(アーヴィング・ハウ)
「無謀なまでに突き抜けた心理学」(ハンナ・アーレント)
「あんたは史上最高の短編を書いたんだよ。夢のなかで」(ルー・リード)
デルモア・シュワルツとは誰か?
どのような作品を書いたのか?
その生涯と作品について、訳者・小澤身和子さんによる、充実した解説をお届けします。
デルモア・シュワルツ
『夢のなかで責任がはじまる』
訳者あとがき
デルモア・シュワルツ(Delmore Schwartz、一九一三~六六)は、アメリカ文学の“伝説”のように語られてきた作家だ。というのも、本書の表題作の短編「夢のなかで責任がはじまる」で鮮烈な登場を果たすも、その後は酒と薬に取り憑かれスキャンダラスな生活を送り、最後にはなんともやりきれない死に方をしているからだ。そうした破天荒な生き方や、名声からの転落のほうが注目され、アメリカ文学史のなかでも異彩を放った存在として扱われてきた。生涯にわたり数多くの詩や短編、評論を残したが、とりわけ「夢のなかで責任がはじまる」だけに高い評価が集まり、今でもアメリカ文学における傑作として、数々のアンソロジーに収録されている。
本書はデルモア・シュワルツによる短編集『In Dreams Begin Responsibilities and Other Stories』(ニュー・ディレクションズ、二〇一二年)の全訳である。デルモア・シュワルツの本邦初の単独作品集となる。
日本では数編の作品が翻訳されただけで、十分には紹介されてこなかった。それでも「夢のなかで責任がはじまる」にはやはり熱狂的なファンが多く、これまでも畑中佳樹、柴田元幸といった名翻訳家たちが、それぞれ『and Other Stories とっておきのアメリカ小説12篇』や『アメリカン・マスターピース 準古典篇』といったアンソロジーに収録してきた。畑中は「たった一発の狙いすました弾丸でたった一つの的を射抜き、あとは一切余計なことをせずに死んでいった作家」と評している。
近年は、編み直された短編集や詩集、さらには伝記までもが本国で刊行され、「夢のなかで責任がはじまる」以外の作品を含め、シュワルツの再評価が進んでいる。
◆デルモア・シュワルツの生涯と作品
「夢のなかで責任がはじまる」は、シュワルツが二一歳のときに書いた作品で、二年後に左翼雑誌『パルチザン・レビュー』の一九三七年再創刊号の巻頭を飾った。当時まったくの無名だったシュワルツの名前は、哲学者のシドニー・フックや文芸批評家のエドマンド・ウィルソンといった著名人と並んだ。読者の多くは、反スターリン主義のオピニオン記事を目的に購読していたため、珍しく巻頭に掲載された短編小説を読み、新しい時代を生きる若者たちの代弁者のボイスや詩的な描写に衝撃を受けたという。「夢のなかで責任がはじまる」はこれまでにない方法で自伝的素材にモダニズムを取り入れた驚くべき作品として、批評家たちに高く評価され、W・H・オーデンやハート・クレインと比較されるなど、瞬く間にシュワルツを注目の作家に仕立て上げた。そして翌一九三八年、ニュー・ディレクションズより、数編の詩とこの短編を収録した『In Dreams Begin Responsibilities』が刊行された。
『In Dreams Begin Responsibilities』はすぐに大きな反響を呼び、エズラ・パウンド、T・S・エリオット、ウィリアム・カーロス・ウィリアムズ、ロバート・ローウェル、ウラジーミル・ナボコフなど、多くの作家から絶賛された。そればかりでなく詩も高く評価され、詩人で批評家のアレン・テイトは「エリオットとパウンド以来の、真の斬新さ」とそのスタイルを称している。
文学的にも、政治的にも新旧交代が求められたとき、シュワルツはまさに新時代の寵児となった。評論家の坪内祐三は、二〇世紀のアメリカ作家のなかでも、日本であまり知られていない変死した人物をとりあげ、当時の時代精神や彼らの反逆や渇望を描いた『変死するアメリカ作家たち』の一章をシュワルツの生涯と作品紹介に割いている。そしてシュワルツには、生涯「アメリカに留まりながらヨーロッパ的伝統もとりこんだ新たな文学世界を創り上げる世代の代表たらんという気負い」がつきまとっていた、と記している。
また、詩人の鮎川信夫の『宿恋行』(一九七八)に収録された「必敗者」という詩はシュワルツの「スクリーノ」を読んだときのことが書かれている。鮎川がシュワルツのペシミズムや根強いルサンチマンに共鳴していることがうかがえる。
少しややこしいのだが、本書は一九七八年にニュー・ディレクションズが『In Dreams Begin Responsibilities & Other Stories』として、表題作と『The World Is a Wedding』(一九四八)に収録された全短編と、『Successful Love and Other Stories』(一九六一)を再編するかたちで刊行したものを底本としている(この本はしばらく絶版になっていたが、二〇一二年に復刊された)。
『The World Is a Wedding』が刊行された当時、批評家や文学者は高く評価し、『タイム』誌はスタンダールやアントン・チェーホフと比較して絶賛したが、部数は伸びなかった。だが、文芸批評家ロバート・フリントは『コメンタリー・マガジン』で一九六二年、「大恐慌の時代を生きるニューヨークの中流階級のユダヤ人を描きとった」作品であり、アメリカ文学史に残る短編集と高く評価し、ハンナ・アーレントは「無謀なまでに突き抜けた心理学」と述べ、「近代社会によってあらゆる真の共同体から切り離された個人の内面と社会生活」を明らかにしたと称賛している。
『Successful Love and Other Stories』も、刊行後すぐに「ニューヨーク・タイムズ」に書評が掲載され、世代ごとのさまざまなイノセンスを描いた良作と評されている。
本書の底本となった短編集『In Dreams Begin Responsibilities & Other Stories』のあとがきで、文芸批評家のアーヴィング・ハウは、一七歳ではじめてシュワルツの作品を読んだときに、「自分たちの世代のボイス」――親しみある声だが、英語の語りにはそこまで馴染んでいない人たちの声――を聞いたと書いている。それには、一九三〇年代のアメリカという社会背景が大きく関係している。
一九一三年にニューヨーク、ブルックリンにて、ルーマニア系のユダヤ人の両親のもとに生まれたシュワルツは、いわゆるユダヤ系アメリカ人の子孫だ。祖父母の世代は一般的に、アメリカに移民としてやってきて、英語を身につけることで、新しい人生を夢見ることに終わり、親の世代は富を手に入れようとがむしゃらに働いた。その子どもの世代となると、高い教養を身につけながらも、大恐慌という時代の波に飲み込まれ、さらにアメリカ国民としてのアイデンティティと、東欧からの移民のユダヤ人というアイデンティティとの間で、どちらにもなりきれない疎外感を抱く者が多かった。
シュワルツの短編に登場する人たちは、抜け出せない停滞感のなかで生きている。不安定な社会に翻弄されて、思い描いたとおりの人生を歩めずにいる。概してみな他者に対して辛辣だが、それは同時に自分への批判でもある。そうした彼らのやり場のないいきどおりを、シュワルツは一切の甘さを持たずにリアルに、ときに現実世界で覚える当惑や焦燥感、恐怖や絶望を「映画的に」あるいは不条理な夢のように描きだした。それが当時の多くの若者たちに、代弁者として受け入れられたのだろう。
「夢のなかで責任がはじまる」で一躍、時の人となったシュワルツは、その後も詩作や評論を書き続けたが、一九四三年、二九歳のときに、十年の構想を経て書かれた二〇〇ページを超える半自伝的な長篇詩『創世記』(第一部)を発表する。しかしこの作品はことごとく酷評され、第二部が刊行されることはなかった。ここからシュワルツの人生は坂道を転げ落ちていくかのごとく低迷する。
期待されていた『創世記』の売上は散々で、収入に頼っていた妻とも離婚したシュワルツは、ハーバード大学で講師の仕事をしながら、長編『アメリカの夢』を書き上げて、ゆくゆくはハリウッドに買い上げてもらい大金持ちになることを夢見ていた。しかし現実の生活に追われてなかなか思うように執筆時間は取れず、実現しなかった。
ハーバードという閉鎖的でお堅い空間に馴染みきれず、作品の評価も振るわず、にっちもさっちもいかなくなったこの頃から、アルコールや睡眠薬を乱用するようになる。「ユダヤ人は酒を飲まない」と言って若い頃はほとんど酒に手をつけなかったシュワルツだが、伝記を書くことになったフィッツジェラルドに影響されて(その伝記は未完に終わったが)酒を飲みはじめると、怒りやすく偏執的になり、過剰な妄想に陥ったり、不条理なことで執拗に攻撃に出たりすることも多々あったという。
一九四九年、作家エリザベス・ポレットと結婚するが、妄想にとらわれるようになり、耐えかねたポレットは一九五五年秋にシュワルツのもとを去る。シュワルツは怒りっぽくますますひどい妄想にとらわれ、最終的に精神科病院に送り込まれた。退院後は、親しくしていた作家ソール・ベローらが自分に対する陰謀を企てていると告発したこともあった。
一九六〇年代初頭、シュワルツの最後の職場となったシラキュース大学では、身なりは不潔で、重度のアルコール依存症だったが、学生からの支持は熱かった。しかし、一九六六年七月一一日、シュワルツはグリニッジ・ヴィレッジの安ホテルで、きちんとゴミを捨てるようにと注意してきた隣人と口論になり、ゴミ袋を抱えて廊下に出たところで心臓発作を起こし、ゴミまみれのまま五三歳で亡くなった。遺体は引き取り手が見つからず、二日間死体安置所に置かれていたという。
死後数年して、シュワルツ作品への関心は再び高まり、ジョン・ベリーマンやソール・ベロー、そしてロバート・ローウェルは、シュワルツに影響を受けたと公言しているし、ローウェルはまた、シュワルツを今世紀最も過小評価された詩人だとも述べている。生前親しくしていたベローにおいては、シュワルツについての半フィクション的回顧録『フンボルトの贈り物』(一九七五)で、ピュリッツァー賞を受賞している。他にも一九七二年、ウラジーミル・ナボコフは『サタデー・レビュー』誌に「インスピレーション」というエッセイを寄稿し、アメリカ文学のお気に入りの短編六作のひとつとして、「夢のなかで責任がはじまる」を挙げている。
シラキュース大学で教えた学生のなかにはミュージシャンのルー・リードがおり、シュワルツは詩人、ミュージシャンとしてのリードに大きな影響を与えた。リードは、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド&ニコのファーストアルバムに収録されている曲「ヨーロピアン・サン」をシュワルツに捧げている(リードによれば、シュワルツは歌詞を好まなかったそうだ)。酒と薬物にまみれた狂気の日々を送っていたシュワルツを知りながらも深く感化されたリードは、一九八二年のアルバム『Blue Mask』に収録された「My House」でシュワルツの亡霊が訪ねてくるという曲を書いてもいる。またリードの伝記『ワイルド・サイドの歩き方 ルー・リード伝』には、ユダヤ人と思われることを嫌ったユダヤ人、ニューヨークの郊外から逃げ出すために文学を指向したブルックリンっ子、アルコールと錠剤でその才能をあたら無駄にしてしまった詩の天才、哲学的な飛躍を街のストリートの声と結びつけた作家――デルモア・シュワルツは青年ルー・リードにとっての完璧なロールモデルとなったと書かれている。
他にもシュワルツが影響を与えたミュージシャンには、U2のボノがおり、「Acrobat」という曲をシュワルツに捧げ、歌詞に「夢のなかで責任がはじまる」が引用されている。
シュワルツの生前のその他の出版作品には、詩劇『Shenandoah』(一九四一)や、詩集の『Vaudeville for a Princess and Other Poems』(一九五〇)や『Summer Knowledge』(一九五九)がある。
◆収録作品紹介
注:作品の結末についても紹介されています。
「夢のなかで責任がはじまる」
語り手の僕が映画館で、結婚する前の両親がブルックリンからコニーアイランドへ出かけ、プロポーズするまでの午後のひとときがスクリーンに映し出されるのを観ているという設定だ。突然僕は泣きはじめ、スクリーンに向かって結婚するのはやめてくれと叫びだす。「ふたりとも、今ならまだやめられる。そんなことしたって何もいいことなんか起きないんだ。ただ後悔や憎しみや恥辱、それからぞっとするような性格のふたりの子どもが生まれるだけなんだから」と。印象深いタイトルはイエーツの詩「Responsibilities」のエピグラフから取ったもので、村上春樹が『海辺のカフカ』でこの言葉を引用したことでも知られる。映画と現実、夢と現実の境界があやうい物語世界のなかで、僕が現実を生きる責任について考え学ぶという、強烈な読後感を残す一作だ。
「アメリカ! アメリカ!」
本作でシュワルツは、いわゆるアメリカン・ドリームをおそらく最も直接的に分析し、アメリカにおける成功と失敗の意味を検証している。シュワルツが描く不幸な家庭は、どれもよく似ていて、父親が金儲けに奮闘する一方で、母親は子どもを甘やかすが、その結果誰も得をしない。この話は、シュワルツが母親と住んでいたワシントン・ハイツの隣人ソロモン一家の話が題材になっている。主人公のシェナンドー・フィッシュ(「大晦日」をはじめシュワルツの短編に繰り返し登場する芸術家/詩人で、シュワルツのペルソナと言われている)の母親が語る、バウマン家の物語は、東欧からの移民でありユダヤ人のバウマン氏が保険事業で成功を収めるものの、時代の流れとともに衰退し、大金持ちか権威ある人間になるだろうと期待された子どもたちが成功せずに終わる。この物語がシュワルツの親の世代を描いたものだとすれば、「生きる意味は子どもにあり」でシュワルツは再び世代を超えた一家の物語に立ち戻り、そこでは自分の幼少期を描き出したと言えるだろう。
「この世界は結婚式」
二〇代後半から三〇代前半のユダヤ系知識人たちの物語。彼らは大恐慌によって精神的にも経済的にも行き詰まり、毎週土曜日の夕方に集まって傷をなめ合う。このサークルのメンバー一人ひとりの精神が、別の登場人物の心のなかで分析されるにつれ、世俗的な失敗が彼らの強烈な個性と結びついていることが、次第にわかっていく。ほとんど自分たちのなかだけで生きている彼らは、より大きな世界の冷静な仲介がなく、文学的才能と哲学的知性への崇拝がサークルのメンバーを支配している。いわゆるアウトサイダーである自分たちが作り上げたバブルに閉じ込められ、孤立していく青年たちと、そのバブルのなかでさえも、他人と自分とを結び付けられず、自分に似ている人たちを恨み、軽蔑するという超現実的な世界が見事に描かれている。彼らは自分たちの人生の無意味さに意味を持たせようとし続け、その結果、正当性を見出そうとしている。物語の最後にジェイコブは人生を結婚パーティーに見立てて言う。「このパーティーでは、みんなのための十分な場所と役割があり、何の役割も果たせなくても誰もがパーティーに参加できて、ごちそうにありつける。自分が披露宴にいるとわからない人は、目の前にあるものを見ていないだけだ。この世界が結婚式であるとわからないのは、死んでいるのと同じかもしれない」
「大晦日」
第二次世界大戦の影がちらつく一九三七年最後の夜にパーティーを開くことにした、ニューヨークの若い作家と編集者のグループによる群像劇。特定の主人公はおらず、新年を迎えるパーティーに人々が招待されてやってきて、仲良くなろうと色々と会話を試すが、どれもうまくいかずバラバラのまま、ともに祝うべき新年に変わる瞬間を逃して帰路につくまでを、大勢の視点と意識を通して描いた作品だ。一九八五年の「ニューヨーク・タイムズ」の記事で、ジェームズ・アトラスは、これは『パルチザン・レビュー』のスタッフたちを描いたものであるとも記している。何よりも目を引くのは、夫から今でいうオープン・リレーションシップ(既婚・交際中でも、互いに合意の上で他の人とも関係を結ぶこと)を一方的に宣言されて、必死で相手を探そうとするデリアだ。彼女は相手が見つからないことを自分のせいにして、どんどん酒に溺れていく。最後に酔っ払った彼女が連呼する「なぜ?」と「あなたはどなた?」は、彼らを取り巻く世界と自分たちに対する痛烈な批判でもあり、読後もその言葉が異様に心に残る。
「卒業式のスピーチ」
一九三七年に書かれた作品で、ニューヨークという大都市のなかで、正気を失っているのか、失っていないのか、正論を言っているのか、たわごとを言っているのかわからない演説を、年老いたダスペンサー博士が行う様子を長回しの映画のように延々と綴ったもの。いわゆる知識人が、大勢の学生を前に頭のなかをさらけだし、狂気をのぞかせる。最後に描かれる都市の描写が、あたかも滑稽な人間たちを作者(あるいは読者)とニューヨークが傍観しているような雰囲気を醸し出し、何とも言えない読後感を残す。
「陸上競技会」
早朝、まだ寝ているフランク・ローレンス(僕)のもとをイギリスからよく知らない男が訪ねてくる場面からはじまる。男に誘われて陸上競技会に繰り出すと、自分の五人の兄弟がレースに参加していて、しかも母親がそれを観覧しているのを目にして僕はショックを受ける。いくら呼びかけても自分のことがわからない兄弟に不安をつのらせながら、僕はイギリス人にキルケゴールの三つの存在様式について語りだす。それに対してイギリス人は、新聞に掲載された殺人事件や自殺の記事を読み上げ、しまいには『祈祷書』を読みはじめる始末。そうこうしているうちに目の前で兄弟らが乱闘騒ぎをはじめ、女の子たちが登場して銃を向ける。現実と幻想が入り交じる支離滅裂な展開に、イギリス人が口にする「目覚めるだけでは、悪夢からは逃げられない」という言葉が突き刺さる。
「生きる意味は子どもにあり」
シュワルツの自伝的要素が色濃く表れている作品。夫と長男を亡くしたルース・ハートという母親を中心に、ハート家の人々を三世代にわたって描きながら、成功や幸せという夢にとらわれた大恐慌時代を生きるある家族の姿をあぶりだしている。作中、ルースはとにかく末息子のサミュエル(のちのシーモアと改称)を甘やかし、二人の姉たちはそれぞれ夫の甲斐性のなさに問題を抱えながらも、働かないシーモアを経済的に支える。何をやっても続かないシーモアだったが、兵役を経て少しまともになり、退役後は戦時経済で潤うようになった賭け屋の仕事で成功する。ルースがすべてを懸けて育てあげた三人の子どもたちは、「最高の子ども」なのか、あるいは「最悪の子ども」なのか? ルースと、娘のサラとレベッカ、という、血はつながれどまったく異なる女性三人を母親として描くことから、母親の無償の愛は美しいという“幻想”を浮き彫りにしている。シュワルツ自身、早くに両親が離婚し、不動産業を営んでいた父親がウォール街大暴落によって資金を失い、その翌年に亡くなってからは、母親が女手ひとつでシュワルツと弟のケネスを育てた。母親は偏執狂だったと言われている。
「スクリーノ」
一九三七年に原稿を書き終えたものの、タイプされることも出版されることもなかった短編で、他の短編にも名前を代えて何度か登場する、シュワルツを彷彿とさせる男コーネリアス・シュミットが主人公だ。コーネリアスは鬱然とした考えを払拭するために映画館に向かうが、そこで賞金を賭けた「スクリーノ」というビンゴのようなゲームをすることになる。運良く賞金を当てるが、自分も当選したと言い張る音楽家の男が現れ、受け取る賞金をめぐって悪夢とも美しい夢とも言える展開に陥っていく。坪内祐三が二〇〇一年『鳩よ!』に、日本語訳を掲載している。
*
シュワルツが描く語り手たちはみな一筋縄ではいかない人たちで、彼らの葛藤には共感できる部分もあるが、できない部分も多い。シュワルツは人と人との心が通い合う瞬間だったり、わかりやすく希望を抱かせたりするような場面を描かない。描いたとしても必ず自虐的あるいは皮肉が込められた一言が入る。経験と意識の相容れなさ、つまり日常生活の陳腐さと醜さ、そして知的存在こそが真実であり美しいという考え方の間の矛盾に苛まれながら、なんとか折り合いをつけて自分を納得させようとしている彼らは、誰も決して幸せそうではない。だが、もしかするとこの人たちはみな、自分の頭のなかだけで生きている分、ある意味で幸せなのかもしれないと思わずにはいられない。
それに対してと言ってはなんだが、作品に登場する若い女性たちの“しっかり”していること! 彼女たちの多くは男たちの才能に魅せられていたり、精神的に依存していたりはするが、生活のために働いて金を稼ぎ、なかには男たちを養っている者もいる(金がなければこの短編集に描かれている男たちの生活はほとんど成り立たない)。彼女たちが幸せでないのは男たちに甲斐性がないからではないのか、とつい思ってしまう。酔った勢いで辛辣な本音を吐き、自己陶酔しがちな男たちをどきりとさせる、デリアやローラといった女性たちは、訳していて一番しっくりきた。シュワルツ作品における女性についての考察があれば読んでみたい。
最後に、担当してくださった編集者の伊藤昂大さんに、心から感謝を申し上げたい。適切なコメントやご指摘をいただいたおかげで、訳稿がみちがえるように良くなったことは間違いない。シュワルツ作品への情熱を感じられる編集者と仕事ができたことは、私にとってとても励みとなった。また、素晴らしい装幀・デザインを手掛けてくださった、クラフト・エヴィング商會さんも、本当にありがとうございました。そして最後に、シュワルツの短編を訳してみませんかと声をかけてくださり、『波』(二〇二〇年六月号)で「夢のなかで責任がはじまる」を訳す機会を与えてくださった、新潮社の楠瀬啓之さんに心からの感謝を。
私のシュワルツに対する責任と長い道のりは、そこからはじまったのかもしれない。難解な原文を日本語にするのには苦労したが、シュワルツの分身のような登場人物たちとこれでしばらくお別れだと思うと、少し淋しくもある。
二〇二四年五月
小澤身和子