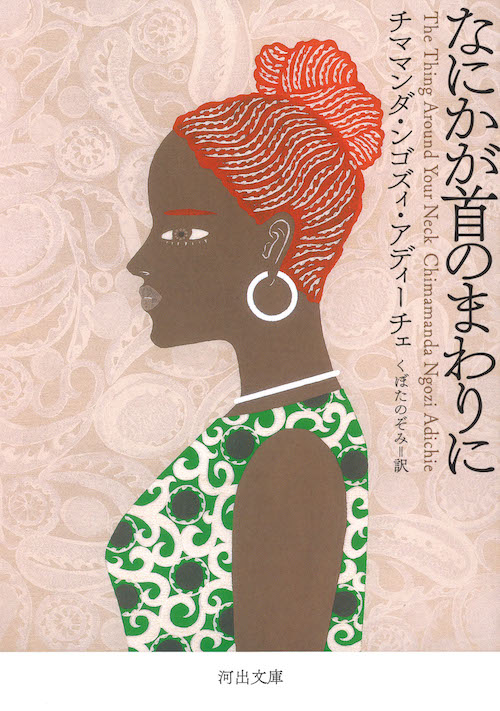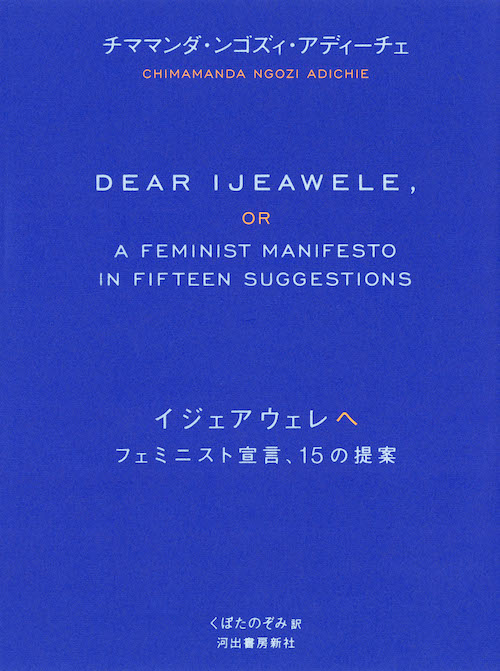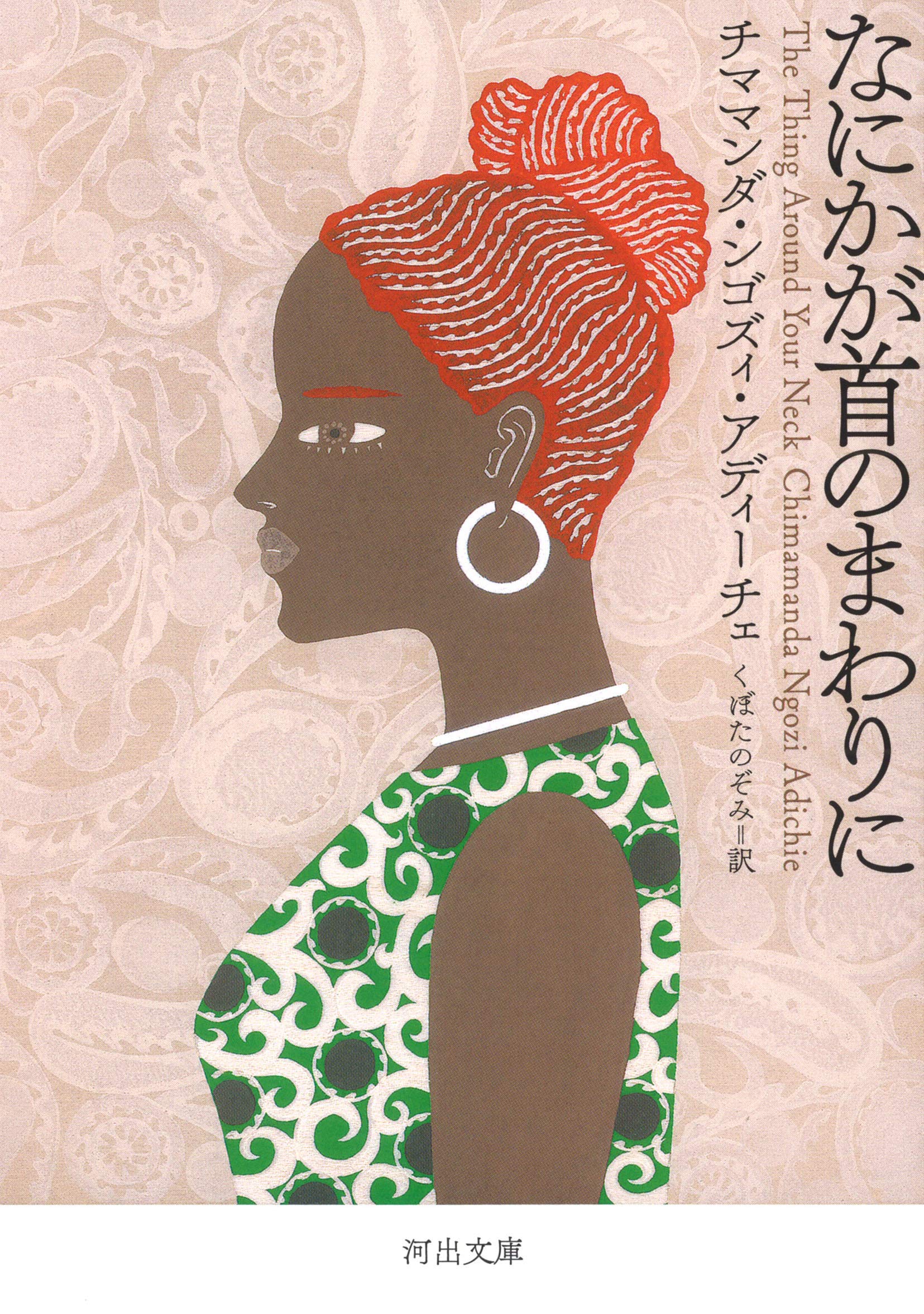
文庫 - 外国文学
【全文公開】チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ『なにかが首のまわりに』より表題作「なにかが首のまわりに」
チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ くぼたのぞみ訳
2019.09.03
アメリカではみんな車や銃をもってる、ときみは思っていた。おじさんやおばさん、いとこたちもそう思っていた。きみが運良くアメリカのヴィザを取得したとたん、みんなそろって、ひと月もすれば大きな車をもって、すぐに広い家に住むようになるだろうけど、アメリカ人みたいに銃だけは買わないで、といった。
ぞろぞろと、きみが父親、母親、それに3人の弟や妹と暮らしているラゴスの部屋までやってきて、みんなに行き渡る椅子がないのでペンキの塗っていない壁にもたれて、大きな声でさよならをいい、小さな声で送ってほしいものをあげた。彼らの望み──ハンドバッグ、靴、香水、衣服──なんて、大きな車や家(それにひょっとすると、銃)とくらべたら、ささやかなものだ。いいよ、わかった、ときみは答えた。
きみの家族全員の名前をアメリカのヴィザ抽選の申し込み用紙に書き込んだのはアメリカに住むおじさんで、おじさんは、自分でなんとかやれるようになるまでいっしょに住んでいいといってくれた。空港まで迎えにきたおじさんが買ってくれたのは大きなホットドッグで、黄色いマスタードにきみは胸がむかついた。アメリカ・デビューの第一歩だな、といっておじさんは大きな声で笑った。おじさんはメイン州の、白人ばかり住むちいさな町に住んでいた。湖畔にたつ築30年の古い家だ。勤めている会社が、給料に平均額よりさらに2、3千上乗せして、ストックオプションもつけよう、といってくれたという。会社が自分たちの多様性を必死でアピールしようとしているからだそうだ。あらゆるパンフレット類に、おじさんが働く部署とは無関係のパンフレットにまで、おじさんの写真を載せていた。おじさんは笑っていった。仕事はわるくない、住人は白人ばかりだがこの町に住む価値はある、女房が黒人の髪をあつかえるヘアサロンに行くのに1時間も車を飛ばさなければならないとしてもだ。アメリカを理解すること、アメリカはギブ・アンド・テイクだと知ること、それがこつだ。諦めることもたくさんあったが、得るものも多かった、と。
大通りのガソリンスタンドでレジ係の仕事に就くにはどうすればいいか教えてくれたおじさんは、公立のコミュニティカレッジの入学手続きもしてくれた。カレッジでは太い腿をした女の子たちが爪を真っ赤に塗っていて、セルフタンニングのせいでオレンジ色に見えた。女の子たちがきみに質問してきた。どこで英語おぼえたの? アフリカにはちゃんとした家があるの? アメリカに来るまでに、車を見たことはあった? みんなきみの髪にはあっけに取られた。ブレーズをほどくとぴんと立つの? それとも垂れるの? と知りたがった。全部ぴんと立つの? どんなふうに? なぜ? 櫛は使うの? その手の質問がきたとき、きみはしっかり微笑んだ。そう質問されるぞ、とおじさんからいわれていたから。無知と傲慢の混ぜ合わせだ、とおじさんはいった。さらに、おじさんたちがここに引っ越してきて数カ月後、近所の人たちがなんといったかも教えてくれた。リスが姿を消しはじめた、といったのだ。アフリカ人は野生の動物ならなんでも食べてしまうと聞きかじっていたせいだ。
おじさんといっしょに大笑いするきみは、おじさんの家で、とてもくつろいだ気分になった。奥さんはきみを「ンワンネ(妹)」と呼び、学校へ通っているふたりの子どももきみのことを「おばちゃん」と呼んだ。彼らはイボ語を話すし、お昼にはガリを食べるし、まるで故郷みたいだった。でもそれは、古いダンボール箱なんかといっしょにきみが寝泊まりしている、狭苦しい半地下の部屋におじさんがやってきて、きみをぐいっと引き寄せ、きみのお尻をもみしだき、うめき声をあげるまでのことだった。彼は本当のおじさんではなくて、きみの父親の妹が結婚した相手の兄弟だったから、血のつながりはなかったのだ。きみがおじさんを押しのけると、おじさんはきみのベッドに腰かけて──結局そこは彼の家だったから──にやにや笑いながら、23歳にもなって、もう子どもじゃあるまいし、といった。やらせてくれたらいろいろ面倒みてやるのに、頭のいい女はいつだってそうしてきたんだ、といった。故郷のラゴスで高給取ってる女はみんなそうやって職を手に入れてると思わないか? ニューヨークの女だってそうだろうが?
きみがバスルームに閉じこもって鍵をかけると、おじさんは上の階にもどっていった。きみは翌朝、家を出た。風の強い長い道を歩いていくと、湖の近くで稚魚の臭いがした。おじさんが車できみの横を通りすぎるのがわかった。いつも大通りできみを降ろしてくれたのに、おじさんは警笛さえ鳴らさなかった。奥さんに、きみが家を出ていったことをどう説明するんだろう。そのとき、きみはおじさんがいったことを思い出した。アメリカはギブ・アンド・テイクだ。
コネティカット州の小さな町にたどりついた。そこが、きみの乗ったグレイハウンドバスの終点だったから。鮮やかな、きれいな日除けの出ているレストランに入っていって、ほかのウェイトレスより2ドル安く働く、といってみた。インクのように黒い髪をしたマネージャーのフアンは、ニッと笑うと金歯が見えた。ナイジェリア人はこれまで雇ったことはないが、移民はみんなよく働く。自分もそうだったからわかる。1ドル安く、だが内緒で、きみのために税金を払わされるのはこまる、といった。
学校へ通う余裕はなかった。部屋代を払うことになったからだ。染みだらけのカーペットが敷いてある狭い部屋だった。おまけにコネティカット州のその小さな町にはコミュニティカレッジがなくて、州立大学の入学金はとても手が出なかった。そこできみは公立図書館へ行って、大学のウェブサイトで講義要綱を調べて本を何冊か読んだ。ときどき、ツインベッドのごつごつしたマットレスに腰をおろして、故郷のことを考えた──干し魚やプランテーンを売りあるき、うまいこといって客をのせたり、買わない客には悪態をついたりするおばさんたち、地酒ばかり飲んで家族をたった一部屋に押し込んで生活させているおじさんたち、きみが出発する前にさよならをいいにやってきて、きみがアメリカのヴィザに当たったことを喜び、本当はうらやましいと打ち明けた友人たち、日曜の朝、教会まで歩いていくとき、よく手をつないでくれた両親、それを見て隣室から笑ってひやかした人たち、仕事先のボスが読んだ古い新聞を持ち帰って弟たちに読ませた父親、弟たちを中等学校へ通わせるための学費にしかならなかった母親の給料、それも、茶封筒を手に滑り込ませると子どもにAをつけるような教師のいる中等学校へ。
きみはAをとるため金銭を使う必要はなかったし、中等学校で教師に茶封筒をこっそり渡したこともない。でも、きみはいま横長の茶封筒を使って、月々の稼ぎの半分を両親へ送っていた。母親が掃除婦をしている半官半民組織の住所宛に、いつもフアンがきみに渡す紙幣を送った。客がくれるチップと違って、ピン札だったから。毎月。お金は白い紙に丁寧に包んで送ったけれど、手紙は書かなかった。書くことがなかったのだ。
それでも数週間もすると書きたくなった。伝えたい話ができたからだ。アメリカの人たちはびっくりするほど開けっぴろげなことを書きたかった。自分の母親がガンと果敢に闘うようすや、義理の姉が早産したことを──故郷では絶対に表沙汰にしてはいけないし、回復を願う身内にだけこっそり打ち明けるようなことを──熱心に話すようすを伝えたかった。人が皿にたくさん食べ物を残し、しわくちゃのドル札を数枚、まるでお供えみたいに、無駄にした食べ物への罪滅ぼしみたいに置いていくことも書きたかった。子どもが泣き出して自分の金髪をかきむしり、テーブルからメニューを払い落としたりすると、両親が有無をいわさずその子を黙らせる代わりに、五歳ほどの子どもに懇願して、それから全員立ちあがって出て行ってしまうことも伝えたかった。お金持ちなのにみすぼらしい服を着て、ぼろぼろのスニーカーをはいている人たちのことも書きたかった。彼らはラゴスの大きな邸宅の正面に立つ夜警みたいに見えた。お金持ちのアメリカ人は痩せていて、貧しいアメリカ人は太っていること、大きな家や車をもっていない人も大勢いることを書きたかった。でも銃については、まだよくわからなかった。もっているとしてもポケットにいれていたから。
きみが手紙を書きたいと思った相手は両親だけではなかった。友だちにも、いとこにも、おばさんやおじさんにも書きたかった。でもウェイトレスをして稼いだお金では、みんなに行き渡るだけの香水や衣服やハンドバッグや靴を買って、さらに部屋代を払う余裕はなかったから、手紙はだれにも書かなかった。
だれもきみの居場所を知らなかった。きみが教えなかったからだ。ときどき自分を見えない存在のように感じて、部屋の壁を通り抜けて廊下に出ていけそうな気がしたけど、やってみると壁にぶちあたって腕に打ち身のあとが残った。フアンが、きみを殴るやつがいるのか、いるなら俺がそいつの面倒みてやるぞ、というので、そんなときは曖昧な笑いを返しておいた。
夜になるといつも、なにかが首のまわりに巻きついてきた。ほとんど窒息しそうになって眠りに落ちた。
レストランでは、いつジャマイカからやってきたの? と質問する人が大勢いた。聞き慣れないアクセントでしゃべる黒人はみんなジャマイカ人だと思っているのだ。きみのことをアフリカ人だと察した人のなかには、象は大好きだ、サファリに行ってみたい、という人もいた。
だからきみがその客に、薄暗いレストランのなかでその日のおすすめ料理を読みあげたあと、アフリカのどの国から来たの? と質問されたので、きみはナイジェリアと答え、次はきっとこの人、ボツワナのエイズ撲滅のために寄付をしたというな、と身構えた。ところが彼のした質問は、ヨルバ人? それともイボ人? きみはフラニ人の顔つきじゃないもんな(*1)。それを聞いて、きみはびっくり──この人ぜったい州立大学の人類学の教授だ、20代後半にしては、ちょっと幼いけど、でもほかに考えられる? と思いながら、イボ人よ、と告げた。彼はきみの名前をたずねて、アクナって名はきれいだ、といった。名前の意味をたずねなかったのでほっとした。「『父の富』だって? つまり、きみの父親はきみを夫に売るってことかい?」とだれもがたたみかけてくるのにうんざりしていたのだ。
彼はガーナとウガンダとタンザニアにいたことがあって、オコト・ビテックの詩やエイモス・チュツオーラの小説が大好きで、サブサハラ・アフリカの国々について、その歴史や複雑さについて、たくさん本を読んだという。注文された料理を運んでいくきみは、自分が感じている侮蔑感を示してやりたいと思った。というのは、アフリカを過度に好きな白人とアフリカを全然好きじゃない白人はおなじ──腰は低いが人を見下す態度をとるからだ。ところが彼は、メイン州のコミュニティカレッジでアフリカでの脱植民地化についてクラス討論したとき、コブルディック教授がやったように、えらそうに首を横に振ったりしなかった。自分が知ってる民族について、当の民族よりずっとよく知ってると思い込んでいる人の表情をしなかったのだ。彼は次の日もやってきて、おなじテーブルにつき、きみがチキンでいいかときくと、ラゴスで育ったの? ときいた。3日目もやってきて、注文するまえに、ボンベイへ行ったときのことや、次はラゴスに行ってそこで人が、実際に、スラムみたいなところに、どんなふうに住んでいるか見てみたい、と話しはじめた。だって海外に行ったとき自分は、愚かしい観光客がやるようなことは絶対にやらないからと。彼は夢中になってしゃべりつづけ、ついにきみは、これはレストランのポリシーに反すると告げねばならなかった。水の入ったグラスをテーブルに置くきみの手を彼はさっと撫でた。4日目、彼がやってくるのを見たきみは、フアンに、あのテーブルの係はもうしたくないと告げた。その夜、勤務が終わると、彼が店の外で耳にイヤホンを突っ込んだまま待っていて、つきあってくれないかな、ときみにいった。きみの名前はハクナ・マタタと韻を踏んでる、「ライオン・キング」は感傷的映画のなかで例外的に好きな映画だし、といった。きみは「ライオン・キング」がどんな映画か知らなかった。明るい光のなかで見ると、彼の目がエクストラ・ヴァージン・オイルの色をしていることに気づいた。緑色がかった金色。エクストラ・ヴァージンのオリーブオイルはきみがアメリカにきて、たったひとつ、心の底から気に入ったものだった。
彼は州立大学の最終学年に在籍していた。年齢を教えられて、なぜまだ卒業していないのかときみはたずねた。そして、そうか、これがアメリカなんだ、自分が育ったところとは違うんだ、と思った。大学があんまりしょっちゅう閉鎖になるので通常コースに3年も追加しなければならなかったり、講師陣がいくらストライキをやっても給料がいまだに払われない、そんなところとは違うんだ。彼は2、3年休学して、自分を発見するためにおもにアフリカとアジアを旅したとか。それで、どこで自分をみつけたわけ? ときくと、彼は声をあげて笑った。きみは笑わなかった。人が学校へ行かない道を選択できるなんて、人生の方向を自分で決定できるなんて、思ってもみなかったから。きみは、人生があたえてくれるものをただ受け取ることに、人生が声に出して命じることを黙って書き留めることに馴染んできたから。
それから4日間、きみは彼とつきあうことに、ノーといいつづけた。じっと顔を見つめられるのは気詰まりだった。きみの顔をひたすら、穴があくほど見つめるのでさよならしてしまったけど、一方では離れがたい気持ちもあった。そして5日目の夜、勤務が終わったあと、彼が戸口に立っていないのを知ってパニックになった。祈るような気持ちになったのはずいぶん久しぶりだったので、後ろから彼があらわれ、やあ、と声をかけてきたとき、誘われないうちから、つきあってもいいよ、ときみはいってしまった。ひょっとしてもう誘ってくれないかも、と不安になってしまったのだ。
次の日、彼は晩ご飯を食べにきみをチャンの店へ連れていった。きみのフォーチュンクッキーには紙が2枚入っていたけど、2枚とも白紙だった。
きみがレストランのテレビで「ジェパディ」を観ること、有色の女性、黒人男性、白人女性、そして最後に白人男性、の順序でファンになって応援してる、と彼にいってしまうと、すごく気持ちが楽になったのが自分でもわかった。その順序では、ようするに白人男性は応援しないことになる。彼は笑って、自分は応援されないことに慣れてる、母親が女性学について教えてるから、といった。
そして、ラゴスの父親はじつは教師ではなくて、建設会社の運転手助手だと打ち明けたとき、彼と親密になれた。きみは父親が運転するおんぼろプジョー504のなかで、ラゴスの交通状態を体験した日のことを話した。雨が降って、錆びて穴のあいた屋根のせいでシートがぬれていたこと。すごい渋滞のこと、ラゴスの道路はいつも、ものすごい渋滞で、雨が降るともうメチャクチャになること。道路が泥沼になって、車が抜け出せなくなると、いとこが車の後ろを押してお金をもらったりすること。あの日、父親がブレーキを踏み遅れたのは、雨が降って、沼みたいになっていたせいだ、ときみは思っていた。身体で感じる前に音でわかった。父親が突っ込んでしまった車は大型のダークグリーンの外車で、ヒョウの目のような金色のヘッドライトがついていた。父親は大声で許しを乞いはじめて、車を降りるや平身低頭、身を投げ出して、まわりからさんざん警笛をあびることになった。すみません、サー、すみません、サー、とひたすら謝りつづけた。わたしと家族を売り渡しても、あなたさまの車のタイヤ一個ほどにもなりませんので、といいつづけたのだ。ごかんべんを。
バックシートの「ビッグマン」は車から出てこなかったが、運転手が降りてきて、車の被害を調べ、きみの父親がひれ伏すように謝るようすを横目でちらりと見た。まるで懇願することがポルノグラフィーの演技かなにかみたいで、本当は見て楽しんでいるくせに、それを認めるのは恥だといわんばかりに。ついに、運転手が父親に、行っていい、さっさと立ち去れ、と手をふって合図した。ほかの車は警笛を鳴らしっぱなし、運転手は悪態をつきっぱなしだった。父親が車にもどってきたとき、きみは断固、父親を見ないことにした。市場のそばの湿地をよたよたと歩きまわる豚みたいだったから。きみの父親は「ンシ」のようにみえた。糞。
きみがこのことを話すと、彼は口をきゅっと結んで、きみの手を握り、わかるよ、きみの気持ち、といった。きみは急にむかっときて、その手をふりほどいた。彼は、世界が自分のような人たちでいっぱい、いや、いっぱいであるべきだと思っていた。きみは、わかるなんてことはない、ただそうだってことで、それだけ、といった。
彼はハートフォードのイエローページでアフリカンストアを見つけ出し、きみを車で連れていった。いかにも慣れた調子で歩きまわり、ヤシ酒の瓶を傾けて、どれくらい沈殿物があるか調べたりするので、ガーナ人のオーナーが彼に、ケニアや南アフリカの白人かという意味で、アフリカ人かい、とたずねた。彼は、そう、でもアメリカにきてからずいぶんになるな、と答えた。店のオーナーが彼のことばを真に受けたので、彼は嬉しそうだった。その晩、きみは買い入れたものを使って料理をした。ガリのオヌグブスープ添えを食べたあと、彼はきみの部屋のシンクに吐いた。でも、きみは全然気にならなかった。だって、いまでは肉の入ったオヌグブスープを料理できるようになったんだから。
彼は肉を食べなかった。動物を殺す方法が正しくないと考えていたからだ。動物のなかに「恐怖の毒」を放出させ、その毒が人びとを偏執症にするのだといって。故郷できみが食べた肉片は、肉があればの話だが、指半分ほどの大きさだった。でもきみはそのことはいわなかった。カレー粉やタイムが高すぎるので、きみの母親が料理という料理に使う「ダワダワ」のキューブがMSG(グルタミン酸ソーダ)入りだと、いや、MS Gそのものであることもいわなかった。彼はMSGには発ガン性がある、チャンの店が好きな理由はMSGを使わないからだ、ともいった。
一度、チャンの店で彼はウェイターに向かって、上海に行ってきたばかりだ、中国語が少し話せるんだ、と話しかけたことがあった。ウェイターが話にのってきて「どのスープがいちばん美味しかった?」とたずね、さらに「それで上海にガールフレンドができたの?」ときいた。彼はニッと笑って、なにもいわなかった。
きみは食べる気がしなくなった。みぞおちのあたりがきゅっと詰まったように感じた。その夜、彼がきみのなかに入ってきても、きみは唸り声をあげなかった。唇を噛んで、行きそうもないふりをした。そうすれば彼が気にするのを知っていたから。あとになってきみは、なぜ自分がうろたえたか、その理由を話した。こんなにしょっちゅうきみがチャンの店にいっしょに行っているのに、メニューを持ってくる直前にきみがキスしてるのに、あの中国人の男はきみが彼のガールフレンドであるはずがないと決めつけたから、それにあのとき彼がニッと笑うだけでなにもいわなかったから。彼は謝るまえに、ポカンときみを見た。だからきみは、彼が全然わかっていないことを知った。
彼がきみにプレゼントを買ってきたとき、そんな高いものダメよ、といってきみは反対した。すると彼は、ボストンの祖父は金持ちだったからといい、それからあわてて、その老人が多額の寄付をしたから彼の信託資金はたいしたことないんだ、と言い足した。きみは彼のプレゼントに惑わされた。振ると内部でピンクの衣装を着たスリムな人形がスピンする、拳大のガラス球。触れるとその表面が触れたものの色に変わる、きらきらした石。メキシコで手描きされた高価なスカーフ。ついにきみは彼にむかって、皮肉っぽく長く引き延ばした声で、これまでのきみの人生では、プレゼントはいつだってなにかの役に立つものだった、といってしまった。たとえば大きな石、それなら穀物を挽ける。彼は大きな強い声で長いこと笑ったけど、きみは笑わなかった。彼の人生では、プレゼントというのはプレゼントするために買うものであって、それ以上のものではなく、役に立つものでもないことにきみは気づいた。彼がきみのために靴や服や本を買いはじめたとき、そんなことしないで、ときみはいった。もうプレゼントなんてほしくなかった。それでも彼は買ってきたので、きみはそれをいとこやおじさんやおばさんのために、そのうち故郷に帰れるようになったら、と思って取っておいた。といっても、きみはどうしたら航空券を買って、さらに、部屋代まで払えるようになるか、まったく見当がつかなかった。彼は、本気でナイジェリアを見たいと思ってるんだ、二人分の航空券を払ってもいいよ、といった。故郷に帰るために、彼にチケット代を払ってもらうのは嫌だった。彼がナイジェリアへ行って、ナイジェリアを、貧しい人たちの生活をぼんやりながめてきた国のリストに加えるのも嫌だった。そこの人たちは「彼の」生活をぼんやりながめることなどできはしないのだから。ある晴れた日に、きみはそのことを彼にいった。彼がきみをロングアイランド湾に連れていった日だ。口論になって、静かな水辺を歩いているうちに、きみの声がどんどん大きくなった。彼は、きみが彼のことを独りよがりだなんていうのは間違ってる、といった。きみは、ボンベイの貧しいインド人だけが本当のインド人だという彼は間違ってる、といった。それじゃ、ハートフォードで見かけた太った貧しい人みたいじゃない彼は、本当のアメリカ人ではないってこと? 彼がきみを追い抜いてぐんぐん先に歩いていく、裸の、青白い上半身を見せて、ビーチサンダルで砂をちょっと跳ねあげて。でも彼はもどってきて、片手をきみにむかって差し出した。きみたちは仲直りして、セックスをして、たがいに相手のヘアのなかに指を走らせた。成長するトウモロコシの穂軸に揺れる房みたいに柔らかくて黄色い彼の毛、そして枕の詰め物のような弾力のある黒っぽいきみの毛。彼の肌は太陽にあたりすぎて熟れた西瓜のようになり、その背中にきみがキスしてローションをすり込んだ。
きみの首に巻きついていたもの、眠りに落ちる直前にきみを窒息させそうになっていたものが、だんだん緩んでいって、消えはじめた。
きみはまわりの人たちの反応から、きみたち二人がふつうではないことを知った──いやな人たちはものすごくいやな感じで、すてきな人たちはものすごくいい感じなのだ。年をとった白人の男女は小声でなにかつぶやいて、彼をじろりと見た。黒人の男たちはきみにむかって首をふった。黒人の女たちの哀れむ視線が、きみの自負心のなさと自己嫌悪を嘆いていた。それでも黒人の女たちのなかには一瞬、ひそかな連帯の微笑みを見せる人もいた。黒人の男たちのなかには、きみを許そうと努力するあまり、彼にあからさますぎる「ハーイ」をよこす人もいた。白人の男女のなかには「すてきなペアだこと」と、いかにも明るく、大声でいう人もいた。まるで自分の偏見のなさを自分自身に納得させようとしてるみたいに。
でも彼の両親は違った。それがごくふつうのことだと思わせてくれたのだ。彼の母親は、これまで息子はハイスクールの卒業ダンスパーティのとき以外、女の子を親のところに連れてくることはなかった、といった。彼は強ばった表情でニッと笑って、きみの手を握った。テーブルクロスがきみたちの握った手を隠していた。彼の手がぎゅっと握りしめてきたので、きみもぎゅっと握り返しながら、なぜ彼はこんなに強ばった顔をしてるのかしら、なぜ彼のエクストラ・ヴァージン・オイル色の目が、両親と話をするとき暗くなるのかしら、と不思議に思った。彼の母親は、ナワール・エル=サーダウィ(*2)は読んだ? ときみにきいて、きみが、ええ、と答えると嬉しそうだった。彼の父親はインド料理とナイジェリア料理がとても似ているといい、勘定書がきたとき支払いのことできみたちをからかった。彼らを見ていて、きみは感謝の気持ちでいっぱいになった。きみを製品のように、エキゾチックな戦利品みたいに品定めしなかったからだ。
あとから、彼が両親とのあいだに抱えている問題をきみに話してくれた。両親がその愛をバースデイケーキのように分けあたえるやり方を、彼がロースクールへ入学することに同意すれば、どれほど大きなスライスをあたえるつもりかを。きみは共感を感じたいと思った。でもその代わりにきみは怒った。
彼が、両親といっしょにカナダに行くのを断った、ケベック州の田舎にある夏のコテージで一、二週すごさないかといってたけど、といったとき、きみはさらに怒った。きみも連れておいでといってくれたという。彼はきみにそのコテージの写真を見せた。なぜそれがコテージと呼ばれるのか、きみにはわからなかった。きみの住んでいた土地では、銀行や教会ほどもある大きな建物だったからだ。きみはグラスを落とし、グラスは彼のアパートの堅い木の床で粉々に砕けた。いったいなにがうまくいかないの、と彼はきいた。きみは、うまくいかないことなんて山のようにあると思ったけど、なにもいわなかった。そのあと、シャワーをあびながらきみは泣きはじめた。水が涙を薄めていくのをじっと見ながら、なぜ、自分が泣いているのかわからなかった。
ついにきみは家に手紙を書いた。両親にあてた短い手紙をパリパリのドル札のあいだに滑り込ませた。自分の住所も書いておいた。ほんの数日後、宅配業者が返事を持ってきた。手紙は母親の自筆だということが、よれよれの字体と誤字からわかった。
お父さんが死んだ。会社の車のハンドルに被いかぶさるようにして。もう5カ月になる、と母親は書いていた。送ってくれたお金でちゃんとしたお葬式を出せた。客のために山羊を屠り、ちゃんとした棺で父親を埋葬したと。きみはベッドのうえで身をまるめ、両膝をしっかり胸に引き寄せて、父親が死んだとき自分はなにをしていたのか、父親が死んだあとのこの数カ月ずっとなにをしていたのか、思い出そうとした。ひょっとすると父親が死んだのは、きみの全身に、火を通さない米粒のようにぶつぶつと鳥肌が立ったあの日だったかもしれない。うまく説明できずにいると、シェフと交替したらどうだい、キッチンの火で暖まれるぞ、とフアンにからかわれたあの日だったかもしれない。ひょっとすると、父親が死んだのはきみがミスティックまでドライブした日、あるいはマンチェスターで劇を観た日、それともチャンの店で晩ご飯を食べた日だったかもしれない。
きみが泣いているあいだ、彼はきみを抱いていてくれた。髪を撫で、きみのチケットを買うよ、いっしょに行って家族に会うよ、と彼はいった。きみは、いいの、ひとりで帰らなければ、といった。もどってくるんだろ、ときくので、きみは自分のグリーンカードが一年以内にもどってこなければ失効することを彼に思い出させた。いってる意味はわかってるんだろ? もどってくるよな? くるよな?
きみは顔をそむけてなにもいわなかった。彼がきみを車で空港まで送ってくれたとき、きみは彼を長く、長く、しっかりと抱きしめて、それから手を放した。
*1 多民族国家ナイジェリアにはヨルバ、ハウサ、イボ、フラニなど二百五十を超える民族が住んでいる。
*2 エジプトの著名なフェミニスト作家、医師。
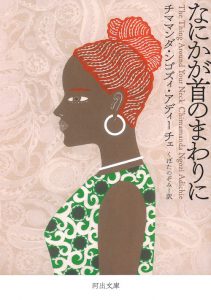 アディーチェ短編集『なにかが首のまわりに』は「ひそかな経験」「明日は遠すぎて」など、全12編を収録した短編集。河出文庫より好評発売中。
アディーチェ短編集『なにかが首のまわりに』は「ひそかな経験」「明日は遠すぎて」など、全12編を収録した短編集。河出文庫より好評発売中。
「なにかが首のまわりに」──まず「アメリカにいる、きみ」として2001年に発表され、何度も書き直されて進化してきた作品で、本書のタイトルになっている。最初の「アメリカにいる、きみ」が日本での第一短篇集のタイトルになった。ラゴスからコネティカットへ移民した若い主人公がエクストラ・ヴァージン・オイル色の目をした白人の男の子と親しくなる。異なる環境で育ってきた二人のあいだの大きなギャップが、しなやかなタッチで描き出される。2010年9月に国際ペン東京大会のゲストとして来日したとき、早稲田大学大隈講堂で俳優、松たか子によって朗読された。
Chimamanda Ngozi ADICHIE:
THE THING AROUND YOUR NECK
Copyright ©2009, Chimamanda Ngozi Adichie
All rights reserved
Japanese translation rights arranged with Chimamanda Ngozi Adichie
c/o The Wylie Agency (UK) LTD.