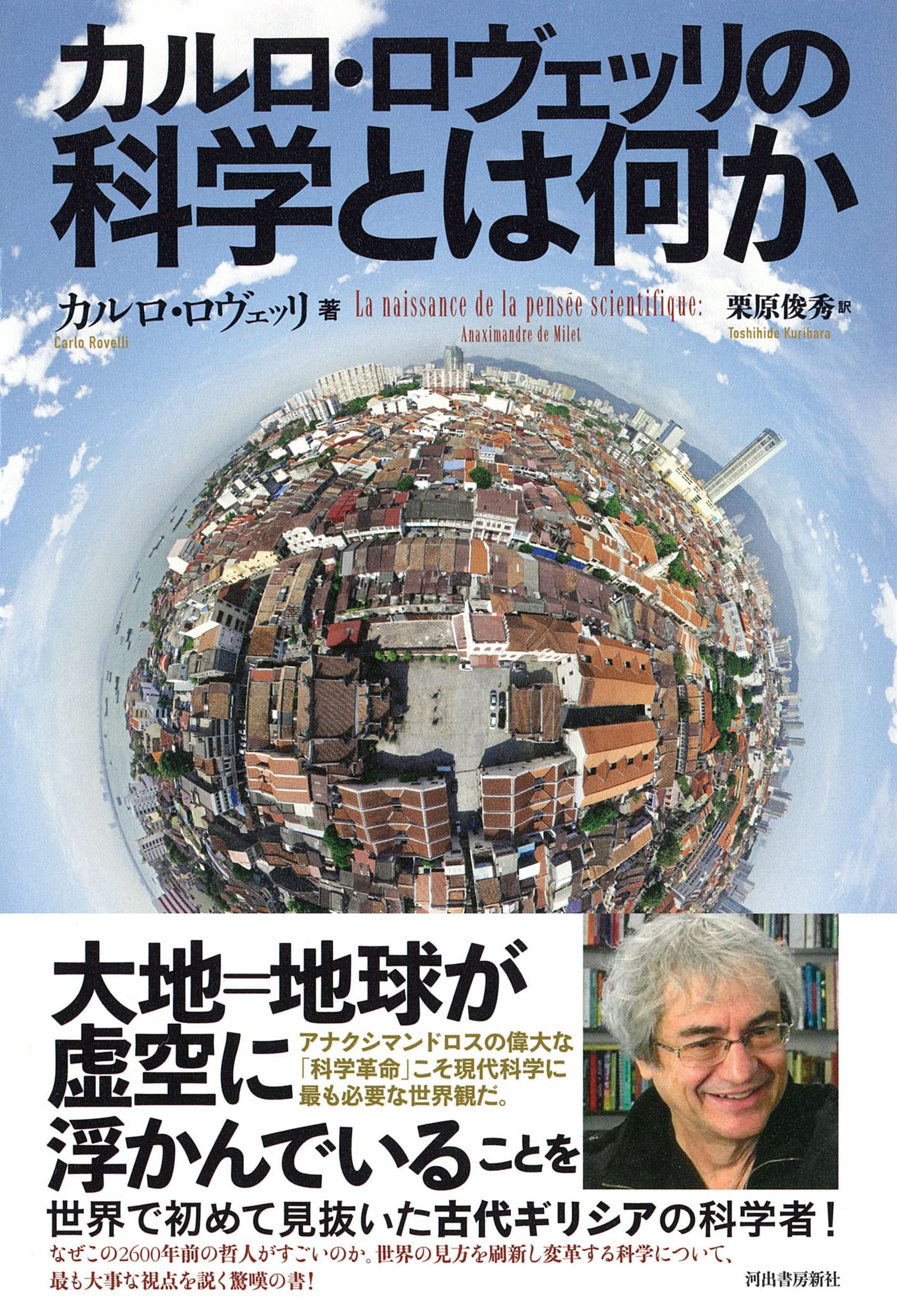単行本 - 自然科学
『科学を語るとはどういうことか 科学者、哲学者にモノ申す 増補版』への提題
松王政浩/谷村省吾
2021.05.28
2013年刊行の『科学を語るとはどういうことか』新版のため、須藤靖氏と伊勢田哲治氏に新たに対談していただくにあたり、松王政浩氏(科学哲学者)と谷村省吾氏(理論物理学者)に、提題をお願いしました。書籍には対談の体裁上、一部のみしか掲載できなかったため、全文を、こちらでお読みいただけるようにしています。これらの提題をもとに繰り広げられた議論については、ぜひ『科学を語るとはどういうことか 増補版』にてお楽しみください。
■松王政浩氏からの提題
1(書籍p.311)
本書が「科学」対「科学哲学」という構図でありながら、科学側の視点としては、概ね須藤さんの「物理学者」の視点でしか語られていない。この本の副題は本来「物理学者、哲学者にモノ申す」とすべきところ。伊勢田さんが何カ所か、脳科学など他の科学にちらっと言及しているが、須藤さんの議論に押されて、この本で扱われている「科学」観が一般的なものとはとても考えにくい。哲学者との対談以前に、異分野の科学者間の対談でいかに科学観が異なるかという確認があって、その上で科学哲学をぶつけないと、(物理学の常識だけで判定されては)科学哲学のフェアな評価はできないと思われる(かつて科学哲学が物理学を科学のモデルとしていたことはあるにせよ)。可能であれば、もう一人、別分野の科学者を入れて三者の会談にするのが最もよいように思うが、それが難しければ伊勢田さんがもっと他の科学の例を積極的に持ち出して、今回の須藤さんの物理の常識が科学の非常識かもしれない部分(少なくとも科学の常識とは言えないこと)をあぶり出してほしい。
2(書籍p.321)
実在論の問題と関わるが、本書全体で一貫した須藤さんの態度は、「そんな昔の話と違って、現代の物理学は確固たる基盤の上に成立している」(科学史の中で現代科学は特別な地位にある)ということだろう。これはまさに科学的実在論の核となる主張の一つであり、反実在論から批判を受けている点である。須藤さんは今の物理学で(量子力学の解釈問題を除き)実在を疑うなど論外としつつ、最後の方では実在を「信じる」ことで十分だとして少し論を弱めているが、「現代科学が特別である」ことの根拠はそれほど明確に語っていない。須藤さんにその論拠を挙げてもらうことは、科学哲学の実在論論争との接点をさぐる上で有効に思われる(たとえばそれが、実在論者シロースの挙げているようなナイーブな論拠にとどまるのかどうかが、一つの見所となる)。
3(書籍p.329)
科学哲学への期待の一つとして、いまのパンデミックについて状況や問題を整理して、有効な施策に結びつけられないか、ということがある(私の周辺ではそういう話を耳にする)。物理学者が感染者数シミュレーションについて、クラスター対策班(理論疫学者)の分析に異論を唱えるということがあったが、科学哲学者は今のところ目立った動きをしていない。たとえばこうした問題に、科学哲学者が何らかの関わりを持てるのかどうかについて伊勢田さんに論じてもらえば、科学哲学の射程を理解してもらうよいきっかけになるのではないか。
4(書籍p.337)
最後にもう一つ。本書の終わりの方で教育に関する話題が出て、須藤さんも条件付きで、少なくとも理学部の学生に対しては科学哲学を「教えるべきだ」と述べている。伊勢田さんは「そうした議論に積極的に関わるべき」だとしているが、すでに伊勢田さんをはじめ、専門教育ではなく一般教育で科学哲学は教えられている。そこで何が教えられ、どのような教育効果を狙っているかについて説明がほしい。それをもとに、須藤さんの考える科学哲学教育とのギャップ(もしそれがあれば)について論じてもらいたい。そもそも教育の観点と研究の観点は異なる。須藤さんは本書ではもっぱら「研究に役立つか」という視点で述べられているが、研究には直接役立たなくても、将来研究者となる(あるいは専門の知識をもった社会人となる)学生への教育として、科学哲学が十分よい刺激となることが考えられる。既存の科学者ではなく、「新しい科学者像」について考える中で、科学哲学が(クリティカル・シンキング以外の部分でも)「役立つ」可能性はあると思う。
松王政浩(まつおう・まさひろ)
北海道大学大学院理学研究院教授。著書に『科学哲学からのメッセージ』、訳書にソーバー『科学と証拠』など。
■谷村省吾氏からの提題(谷村氏からは、箇条書きの提題に加えて、その意図の背景や説明もいただきました)
提題箇条書き:
1(書籍p.316)
マルチバースというアイデア(宇宙は複数個あるという考え)の信憑性についてどうお考えでしょうか? マルチバースは科学的に反証可能だと思われるでしょうか? また、超弦理論やマルチバースのような実験・観察・反証の難しそうなアイデアを科学の中にどのように位置づけるべきだと思われますか?
2(書籍p.323)
科学哲学における因果(因果性)の定義をお尋ねしたいと思います。また、谷村が後述するような因果観(人間の認識様式としての原因結果観)は科学哲学の中では正当な考え方として扱われているでしょうか? もしも、私が申し上げるような因果の定義ではもの足りない点があると思われるのであれば、不足点を指摘していただきたいです。
3(書籍p.326)
科学的実在論vs反実在論論争はどうなりましたか?
4(書籍p.331)
哲学界には「寛容(チャリティ)の原則」というのがあるそうですが、それはどういう内容でしょうか? それについて須藤先生はどう思われるでしょうか? 伊勢田先生は、哲学界において寛容の原則は好ましい形で実現していると思っておられるでしょうか?
5(書籍p.336)
研究成果の発表媒体として書籍や論文がありますが、研究者にとっては、あるいは、市民にとっては、どういう形態が望ましいと考えられるでしょうか?
提題の詳細:
1.マルチバースや超弦理論など反証の難しいアイデアの位置づけ
これは『科学を語るとはどういうことか』に書かれていた論点というよりは、須藤先生が他書で書かれていたことに関する質問ですが、マルチバースというアイデア(複数の宇宙があるとする説。我々の宇宙と空間的につながっている他宇宙があるとする説もあるし、我々の宇宙とはつながりがなく物理法則すら我々の知っているものとは異なる宇宙があるとする説もある)の信憑性について須藤先生はどうお考えでしょうか? マルチバースは科学的に反証可能だと思われるでしょうか? また、須藤先生と伊勢田先生の両方にお訊きしたいですが、超弦理論やマルチバースのような実験・観察・反証の難しそうなアイデアを科学の中にどのように位置づけるべきだと思われますか?
2.因果は科学的概念か
『科学を語るとはどういうことか』(増補版pp.11-14, pp.121-184)の、哲学者の考える「因果論」と物理学における「因果律」、因果論とビリヤードなどの議論に関連して質問・コメントします。
須藤先生は、法学部の先生に因果論について尋ねられて、物理学における因果律の意味で答えて、何か的を外したような印象を持たれたとのことですが、「因果」という言葉に込められている意味が分野ごとに異なっていて、若干の混乱があることを指摘されているようでした。
私なりに「因果」概念を分類するなら、以下のように言いたいです:
(1) 哲学における因果:すべての出来事には何らかの原因があるとする考え。これが人間側の信念や方法論にすぎないのか、それとも世界の側に備わった性質なのか、因果とはそもそも何ものなのか、などという疑問が哲学的テーマになる。哲学では「因果性」と言うらしい。
(2) 理論物理における因果律:物理的影響は超光速では伝わらないという法則。とくに相対論的場の理論では因果律は明確に定式化されるが、互いに影響しうる二つの事象のうちどちらが原因でどちらが結果なのかという定義は難しい。
(3) 広く科学で使われている因果概念:原因つきとめ型の思考。何によってこれは起きたのか、これを起こしたければあるいは避けたければ、何をすべきなのかなどを考える思考の型。
(4) 日常語としての原因と結果という概念:科学的根拠までは追究せず、「これのせいであれが起きたのだ」的な直観的思考パターン。しばしば短絡的誤解であることもある。「犯人捜し」に似た思考のパターンであり、損得に関わる重大な事象に直面したときに原因を追究せずにはいられないという衝動を伴うことがある。
これらの「因果の用法」は少しずつずれていると思います。たぶん(2)の理論物理的な因果律概念が、最も明確に定義されていて、最も日常感覚から離れているだろうと思います。(3)と(4)は、追究の程度や根拠の強度が異なるだけであり、明確な違いはないと思います。
私流の原因・結果の定義はこんなふうです。原因は、人が変えられそうな・選べそうな・起きたり起きなかったりしていることが察知可能な条件・事象である。結果は、人にとって目立つ事象、とくに人の価値観に照らして良し悪しの判断対象になる事象である。そして、原因事象から結果事象への間をつなぐ(確率的であってもよいが)物理的過程の連鎖がある。因果関係と呼ぶためには、物理的過程の連鎖の詳細をつきとめられなくても、原因と結果を結ぶ何らかの機序があることがある程度の確度で期待できていなくてはならない。
例えば、「火事」は人間の生活を脅かす重大な事象であり、できれば防ぎたい事柄なので、原因を知りたくなります。「火の不始末」や「漏電」は原因かもしれません。しかし、「空気中に酸素があったことが火事の原因だ」とはあまり言われません。空気中の酸素分子を見分けたり除去したりすることは困難なので、地上で起きてしまった火事については酸素の存在は自明なこととして扱われます。しかし、宇宙船の中で火事が起こったら、酸素は原因の一つに挙げられるでしょう。また地上においても消火活動という局面で、ふたをする、消火剤を撒くなどするのは、酸素との接触を遮断する策があるからでしょう。
肺の存在は肺炎の必要条件ですが、「肺炎の原因は肺があることだ」とは言わないでしょう。肺の存在は選べないからです。全人類があきらめるしかない所与の条件は「原因」として槍玉に上げられません。
地殻プレートの運動や断層の破壊が地震の原因だという言い方はすると思います。人間はプレートの動きを止めることはできませんが、プレートがぶつかり合って地震の起きやすい場所と、厚いプレートの真ん中に位置していて地震の起きにくい場所との差異なら人間は検出できるし、ローカルには地滑りの可能性が高い場所も特定できます。地震の原因になりそうな条件を探索し、重要な施設を建設する場所を選ぶなどして危険を避けることは現実的な用をなします。100パーセント地震が起こると言えなくても、あるいは正確な確率の値を言えなくても、定性的な評価だけでも、予測がないよりはましであり、判断の材料になります。これが科学的に正当な原因・結果概念の使い方だと私は思います。
私は、数学的に定式化された物理理論は原因と結果という事象を特定するようにはできていないと思っています。過去光円錐の中にある事象は「多少なりとも原因と言える事象」であるし、未来光円錐の中にある事象は「多少なりとも結果と言える事象」です。しかも過去と未来という時間の方向を純粋理論物理的方法で定めるのはかなりの難問です。
原因も結果も、人間の認識様式であり、注目の様式であり、何らかの基準を人間が設定しないことには定まらない概念だと私は思っています。ただし人間だけが因果の判定をできるというわけではなく、動物も身の回りに生起する事象群に何らかの因果的関係を見出していてもおかしくないし、機械も人間が判定基準を教えれば、あるいは大まかな基準を教えられただけで学習することによって、何が原因、何が結果という判定をできるようになるでしょう。実際、統計的因果探索は人工知能の一つのテクニックになっています。
私は以上のような考え方をしていますので、「因果は客観的実在だ」とは言わないけれども、世界を認識・把握する上で有用な方法であると思っており、それが有用であるのは人間が一度に多くのことを把握しきれない生物であることが関係していると思っています。そして因果概念の適用の仕方は状況次第にならざるを得ないと思っています。おそらく私が抱いているような因果観は、須藤先生はじめ大概の物理学者に共有されている理解の仕方だと思います。
伊勢田先生には、科学哲学の文脈における因果(因果性)の定義をお尋ねします。また、私(谷村)が抱いているような因果観は科学哲学の文脈では正当な考え方として扱われているでしょうかとお尋ねしたいです。もしも、私が申し上げたような因果の定義ではもの足りない点があると思われるのであれば、不足点を指摘していただきたいです。
須藤先生は、谷村の因果観にご同意されるでしょうか? 私としては、上に示したような因果の説明で日常的には用をなすと思っています。科学的因果関係の定義とするには、私が与えた定義ではちょっと雑すぎると思います。正式な使用に堪える概念にするためには、実験状況のコントロールや、統計的な意味などをもっと丁寧に織り込むべきだとは私も思っています。そういう「科学的使用に堪えるように概念を正確に整える作業」に哲学者が知恵を出してくださるならなおよいと思います。
3.科学的実在論vs反実在論論争は、なぜ科学者に不評か
『科学を語るとはどういうことか』(増補版pp.185-234229)の、実在論と反実在論に関する部分について質問・コメントします。
おそらく大部分の科学者は、「科学的実在論vs反実在論論争」というものを知らないだろうと思います。そして科学的実在論vs反実在論論争は、それを聞きかじった物理学者からの評判が最も悪い科学哲学の一面だろうと思います。
結局、この論争は形而上学的論争(人間の知覚を超えたところで世界の真の姿はどうなっているのか、本当は世界には何があるのか、を問うのが形而上学)であって、物理学者からすればあさっての方向を向いている論争だから、というのが、評判が悪い理由の一つだと思います。「世界の真の姿を問う」というところは物理学者の気持ちに近いのですが、物理的装置を駆使した観測をあてにせず言葉と五感だけを頼りに何かを論じようという態度において形而上学者の方が物理学から積極的に離れて行っているのです。
悪評のもう一つの理由は、これが形而上学論争だということがわからない物理学者が聞くと、反実在論者が「物理学の主要な概念の多くは錯覚であるから放棄せよ」と言っているように聞こえるからだと思います。「放棄せよ」とまでは言っていないかもしれませんが、「物理学者たちはナイーブに過信している」と言われている気はします。
さらに反実在論者がバカにされる(すみません、私はバカにしています)理由として、人間の感覚で知覚できるものにしか実在性を認めないという態度があります。これは捉えようによっては非常に謙虚で慎重な態度だとも言えるのですが、慎重すぎてバカバカしいことになっています。古代ギリシャの時代や中世ならいざ知らず、エレクトロニクスや合成化学や分子生物学を頼りにしている現代にあって、目に見えるものしか信じないという態度は、恐ろしく時代錯誤的に見えます。さらに、GPSやスマホやWiFiや赤外線感知自動ドアや気象レーダーなど、電子や電磁波などの性質に依拠したテクノロジーの恩恵を享受する生活を送っていながら、「それらの背後にあるとされているメタフィジカルな存在の実在性にはコミットしない」という態度は、文明の利器のほとんどすべてをブラックボックスとみなすということなのか?それで何の不思議も感じずに生きていられるのか?コミットしない方が心安らかでいられるということなのか?その方が認識論的リスクを抑えられるらしいからそうかもしれないな、ひょっとすると反実在論的態度を貫ける人はある種のサイコパスなのだろうか?彼らにしてみれば実在論者の方が幻想に騙されている人間なのだろうか?などの疑問を科学的実在論者(私)の心に呼び起こします。
例えば、可視光の実在性を認めるが赤外線や紫外線の実在性を認めないとしたら、現代において一通りの理科教育を受けたはずの大人であれば変人扱いされてもしかたのない態度だと思います。紫外線の実在性を信じない立場からは、日焼け止めクリームのUVカット指数を何ものと考えるのでしょうか?チョウやハチは紫外線が見えているらしいという話をどう受け止めるのでしょうか?光の実在性は認めるとして、では、電磁波の実在性は認めないのでしょうか?光が横波だということは偏光サングラスでも見てとれるけども反実在論者は何を見ていると思うのでしょうか?X線の実在性は?光子の実在性は認めないのか?音の実在性は認めて超音波や低周波の実在性は認めないのか?ウイルスの実在性は認めるのか? DNA分子やATCGの塩基配列の実在性は認めるのか?ワクチンとは何だと思っているのか?遺伝子診断を何だと思っているのか?といった質問に反実在論者はどう答えるか聞いてみたいものです。反実在論者は反実在論者であることにコミットメントを有しているのか?それとも哲学的論争ゲームの場でのみ反実在論者を演じているのか?という問いに言い換えてもいいです。
量子力学の出現によって、光や電子や原子は、ある局面では粒子のように振る舞い、別の局面では波動のように見えるということが、いちおう説明できるようになりました。そんな光や電子や原子は実在と言ってよいのか?そのような原子で自分の体や脳はできているという説明を反実在論者は受け入れられるか?という問いも訊いてみたいです。
黒体輻射のスペクトルの公式は、光を粒子だと思っても導けず、波動と思っても導けないです。量子的としか言いようがないです。量子力学のベルの不等式の破れは、物理量の値の客観的実在性を否定しているように見えます。物理学者は、電子や光子などのありようを不思議に思っているし、これらに対して何らかの具体的なイメージを持とうともしています。しかし、少なくとも古典物理学的なイメージを描こうとすると、理論とうまく噛み合わず、実験結果も説明できません。
「実在」という言葉で哲学者が何を指しているのか、私にはわからないです。EPR(アインシュタイン・ポドルスキー・ローゼンのこと。量子力学は実在の記述理論としては不完全だと主張した)は、実在の数学的条件をちゃんと与えています。それを定量的に実測できる問題設定にしたのがベルです。数学的に明晰で物理実験可能であるような問題の定式化をしたので科学の問題になり得ます。感覚に訴えるようなやり方で実在概念を定めて(ちっとも定めていない)、何か確かなことが言えるのか?と私は思うので、実在論論争を見ていて虚しくなります。
じつは、「光の量子効果と思われている現象を、光子の概念を使わずにどこまで説明できるか」という試みが昔ありました。1970年代に Neo-classical theoryというムーブメントがあって、参加者は少なかったですが、ラムシフトを実測したラムなど著名な物理学者も参加していました。光電効果やコンプトン散乱は、光子の概念を使わずに古典的な電磁波の概念だけを用いて説明できる、という理論的デモンストレーションを彼らはやっていました。ラムシフトも電磁場の量子論を使わずに説明できるという議論もありましたが、私にはかなり苦し紛れな説明に思えました。黒体輻射の公式はNeo-classical theoryでは導けないと結論されていました。
Neo-classical theoryは首尾一貫した物理理論ではなく、あくまで特定の各現象についてアドホックな説明を与えるにすぎません。Neo-classical theoryは物理理論の作り直しというよりは、「これこれの現象は古典物理では説明できず量子論によって初めて説明された」という言い方が安直すぎることを指摘する教育的な注意だったと捉えた方がよいと思います。
しかし、Neo-classical theoryまで行かなくても、また、アインシュタインに限らずとも、多くの物理学者たちも心の底では光子や電子の「本当の姿」は何だろうということを気にしています。場の量子論ではすべての素粒子は場の励起状態にすぎないことになっているけれど、そんなものを実在と言ってよいのか?という気持ちは皆さん大なり小なり持っていると思います。とくにディラック場の励起状態としてのフェルミオンは、実在と言うには奇妙な気がしますし、ゲージ場の励起状態としての光子やゲージボソンも不思議な概念です。
私は、物理学は世界の実像に肉薄していると思います。私が理論物理の観点から思い浮かべている描像は、自然界の真の姿ではないかもしれないけど、錯覚でもなく、自然界のありように近いものは捉えていて、自然物はこういう理論で記述するしかないような姿をしているんだなという考え方を私はしています。
また、同じ物理現象を説明する理論は一つとは限らないという点もよく言われます。複数の理論がある場合にどのような「実在像」を採用したらよいのかという問題はあるでしょう。例えば、前期量子論は電子を粒子として扱っていると言ってよいと思います。粒子であるかのように積分作用量という数量を計算して、最後に量子条件を課すのがボーア・ゾンマーフェルトの前期量子論でした。シュレーディンガーの波動力学では電子を波動のようなものだと思って波動関数を計算します。ハイゼンベルク・ボルン・ヨルダンの行列力学は物理量を行列で表して計算します。行列力学は電子のありようを記述していないように見えます。ファインマンの経路積分は、1個の電子を無数の軌跡をたどる粒子であるかのように扱います。こうしてみると、電子の古典物理的・一意的な描像は諦めた方がよい、というのが現代の物理学者の理解だと思います。所詮、粒子や波動などの古典物理的描像はアナロジーの用しかなさないということで、ほぼ全物理学者の見解は一致していると思います。そんなふうなので、形而上学的実相というものを語りたかったら、量子論の言葉をそのまま使うしかないだろうと思います。
結局、形而上学的議論によって自然物の実在性や真の姿がわかるとは私は思いません。また、「科学はメタフィジカルなコミットメントを負わない」という反実在論的態度にとくに褒めるべきところはなく、反実在論者がもしいれば、赤外線や紫外線やX線は実在するとかしないとか君はどう思っているの?空気の実在性は認めて二酸化炭素分子の実在性は認めないの?炭酸ガス排出規制についてどう思う?などといじってやりたくなるだけです。
反実在論を非科学的態度であるかのように評してさんざんコケにしてしまいましたが、科学的実在論論争は、科学者間の論争に起源があり、しかも反実在論(論理実証主義)は現代的な科学(原子論や相対論や量子論)を擁護するために始まったということも言及してもらえると物理学者の同情をいくらかは得られると思います。詳しくは戸田山和久氏の『科学的実在論を擁護する』の序章(pp.1-17)と第1章4節(pp.51-54)で論じられています。もちろん伊勢田先生は、戸田山先生の本に書かれているような内容はよくご存知だと思います。そこに示されているのは科学者にわかりやすいように戸田山氏が組み立てた歴史観かもしれませんが、なるほどそう考えれば、反実在論的な論理実証主義は、素朴実在論的信念を持つ古参の物理学者による批判から抽象的かつ非感覚的な(原子論に代表される)現代物理理論を守るための運動だったということはよくわかります。
一方で、量子論などを創った物理学者たちが、反実在論的論理実証主義者たちによる擁護運動を歓迎していたかという点は疑問です。相対論や量子論の立て役者であり、まさに抽象的・数学的な物理理論を創る名人とも言えるアインシュタインは、量子力学の波動関数の確率解釈をすんなりとは受け入れなかったし、確率解釈を受け入れた(と言うか、抵抗を示さなくなった)のちも、量子論が実在論的でない点は受け入れられないという態度を生涯貫いていたようです(日経サイエンス2019年2月号の記事『アインシュタインの夢 ついえる―測っていない値は実在しない』で私もこの点を論じました)。言い換えると、形而上学的な実在のありようにアインシュタインは終生こだわっていたと言えそうです。
歴史的に語るなら、このようなすれ違いの経緯まで語り伝えた方が、哲学者にとっても物理学者にとっても、よい反省材料になるような気がします。20世紀後半の科学的実在論争は、当初の問題提起者の思惑から遠く隔たり、物理学を題材にした形而上学的論争になっていったように見えます。そのような論争は物理学者にとってまったく参考にならないとは私は思いません。実在という観念にとことんこだわるとそういうことになるのか、という視点を得ることはできます。でもそのような議論をいくらやっても物理学の進歩を1ミリメートルたりとも後押していないと思います。
そのような議論に価値はあるのか?は難しい問いだと思いますが、「物理学の進歩の足を引っ張っているわけじゃないから哲学的議論をしたっていいじゃないか」みたいな言葉に触れると、それって学問的存在価値と言えるでしょうか?と思うし、「反実在論は科学のメタフィジカルなコミットメントを軽減している」などと言われると(私はツイッターで言われたことがあります)、メタフィジカルなコミットメントを科学に負わせたり免除したりしてもらっても個人としての科学者は苦しくも嬉しくもないし、科学という営みの総体は負担を感じるような主体じゃないし・・・と思います。
結局、私は形而上学の存在意義を理解していないんでしょうね。私が思うに、形而上学は、ココロのスキマを埋めるおとぎ話なんですよね。二千年くらい前なら形而上学の存在意義はあったと思いますが、いまや形而上学はみじめな存在でしかないと思います。
須藤先生は形而上学の存在意義を理解されているでしょうか? 伊勢田先生は須藤先生に形而上学の存在意義を伝えることができるでしょうか?
あと一言、なぜ私がこうも形而上学を信用しないのかというと、それが言葉と論理と乏しい経験と直観だけに依拠しているように見えるからです。人間の言葉は、地球という環境で進化してきた人類がここ数万年に獲得した能力です。論理も絶対的な真理かどうかわかりません。古典論理も経験則の一種でしょう(私がそう言うのは、直観論理や量子論理やトポス論理など数理論理には数学的法則性の異なるバリエーションがあり、とくに素粒子レベルの物理的基本構成要素は古典論理ではなく量子論理に従うとすると、古典論理はマクロスケールで成立する近似的規則にすぎないと考えられるからです)。形而上学者が加速器にも電子顕微鏡にも頼らないのは言うまでもありません。それでいて形而上学者はけっこう自分の直観に頼ります。そんな言葉で、宇宙や素粒子について真相を言い当てることができると思う方が無謀だと私は思います。
デイビッド・ドイッチュは、量子論の多世界解釈の支持者であり、量子コンピュータの原理の発案者の一人でもあり、科学哲学にも傾倒しているようですが、彼は『無限の始まり』という本の中で、我々人類は宇宙の辺境に生まれ育ち、このあたりの、ここ最近のことしか知らない、という旨を述べていました。彼のような態度こそ科学的に謙虚な態度であり、そういう態度からは、「時間の始まりはあるかないか形而上学的方法で検討しよう」といった議論をする気は起きないだろうと思います。
【Neo-classical theory についての参考文献】
[1] W. E. Lamb, Jr. and M. O. Scully, “The Photoelectric Effect without Photons”, in Polarization, Matter and Radiation. Jubilee volume in honor of Alfred Kastler (1969) pp.363-369.
[2] P. W. Milonni, “Semiclassical and Quantum-electrodynamical Approaches in Nonrelativistic Radiation Theory”, Physics Reports 25, No. 1 (1976) pp.1-81.
[3] 日本物理学会編『量子力学と新技術』培風館, 1987年. 第9章(著者 矢島達夫氏)pp. 184-185.「…これらについても、光の古典論を用いて現象の出現のみならず、量的な性質についても驚くべき程度にまで説明できることを指摘する理論がいろいろ現れてきた。これらの理論は Neo-Classical Theory (NCT) と呼ばれ、1965~1978年頃の時期にこれを主張する研究者と批判する研究者との間に活発な論争が繰り広げられてひところの話題となった。」
[4] 霜田光一「光の粒子性の証拠」パリティ,Vol. 8,No. 8 (1993) pp.75-77. 「内外のたいていの物理の教科書には、光の干渉・回折・偏光などは光が波動性を示す現象であり、光電効果・コンプトン効果などは光が粒子性を表す現象である、と書かれている。そして、大部分の物理学者も量子力学を学ぶ学生も、光電効果とコンプトン効果を説明するためには、電磁場を量子化して光量子すなわち光子を考えなければならないと信じている。光電効果もコンプトン効果も光を波と考えたのでは理解出来ないので、これらの効果は光が粒子性を持つことの証拠とされている。しかし、これは物理教育における”迷信”のようなものである。光電効果やコンプトン効果は、光が古典的な電磁波であると考えたのでは説明できないと思い込むのは正しくない。自然科学においては99%の人々に信じられているからといって、それが真理とは言えない。」
[5] W. E. Lamb, Jr., “Anti-photon”, Applied Physics B 60 (1995) pp. 77-84.
[6] 霜田光一「光の粒子性と波動性III : 光電効果とコンプトン効果の波動論」レーザー研究,1997年 25巻 6号 pp. 442-446.
4.「寛容の原則」はいいことか
『科学を語るとはどういうことか』(増補版pp.35-42)の、荒唐無稽な主張がなぜ哲学界でまかり通るのかという議論に関連して、質問・コメントします。
哲学界では一見荒唐無稽に思える発言・論説であっても、よいところをすくってやろう、思考を触発してくれる点があれば評価しようという雰囲気があるとのことです。そういう態度を、哲学界ではcharity, charitable interpretation というという話を聞いたことがあります。テキストを読む態度としてcritical reading(批判的読解)に比してcharitable reading(寛容な読解)というのがあるらしいです。
私自身、複数の哲学者から「我々はどんなに破綻しそうな論でも最後まで聞いてしまう癖がついてしまっている」、「ある程度フォローして理解を試みてみたけれども、どうにも空疎としか判断できないという境界線というものはあって、それを超えた議論を哲学の中で目にすることは正直あります」などといった意見を聞いたことがあります。 私自身は、現役の物理学者同士の間にチャリティという概念はほとんどないと思っています。論文の中や講演の中で誰かが変なことを書いたり言ったりしていたら、他に多少は正しそうなことを言っていても、かなり減点し信用度を差し引くのが当然だと思っています。荒唐無稽なレベルに達していたら、まったく相手にしないのが普通だと思います。私は物理学の雑誌のeditorも務めていますが、投稿された論文にいいことも書いてあるけれど、余計な変なことも書いてあったり、舌足らずなところがあったりするようであれば、変なところは削除して説明を補って整理して書き直すようにと著者に指示することはあります。同業者に対する学問的チャリティとはその程度のものでよいと思います。 チャリティ・寛容という態度は、異分野の人が交流するときには表立って意識すべきことであって、同類分野の研究者は基本的には切磋琢磨すべきライバルであり、チャリティを前面にもってくることはないと思います。 あるいは、文献を書いたのが遠い昔の人であれば、当時の知識や常識の範囲内でしかものを考えられなかった、表現方法も限られていたでしょうから、現代的観点から揚げ足を取りの批判をしてもしょうがないと考えて、書物から意味を汲み取ろうとするという態度なら私にも理解できるし、誠実な態度であるように思えます。そういうチャリティなら奨励してしかるべきだと思います。数学・物理系の人たちは、自分の見解が正しく相手の見解が間違っていると思うときに、容赦なく相手を批判してしまう傾向があると言われることがあります。おそらく数物系の研究者はふだんから白黒の決着がつきやすい問題を扱っており、間違いを指摘されて多少は悔しい思いはするかもしれませんが、あくまでも批判の矛先はピンポイントで当該の問題を指していることはわかっており、人格を否定されたことにはならないと心得ているから、他人に対しても強く当たってしまうのかなと思います。また、理系の研究者は、研究の価値ということに関しても互いの評価の目が厳しいと思います。軽くパワハラ気味な気もしますが、私も大学院生時代に研究テーマに関して「そんな小さなことをやっても意味がない」というような言葉をしばしば指導教官に言われました。言われた方はヘコみもしますが、それ以上に追いつめられることはなく、たんに思ったとおりのことを言われているのだなと思いましたし、結果的には言われてよかったと思っています。要するに、我々は、悪気はないけど、粗野なのです。あと、私の先生たちは学生のやっていることをたんに否定するだけではなく、では何をやったらいいのかというアドバイスをくれました。さらに言えば、そのアドバイスに学生が従わなくても、咎めませんでした。私はそういう種類の学生でしたが、頼めば先生は推薦書も書いてくれました。つまり、思ったことをお互い直截に言うけれども、人格を攻撃しているわけではないし恭順を求めているわけでもないということは大前提としてありました。それに比べると哲学系の方は研究に関することについて「くだらない」とか「意味がない」とか価値判断に触れることを言われると、ものすごく傷つくようです。批判が人格攻撃にあたるかあたらないかをものすごく気にされます。私だったら傷つくよりも「こんなに意味があることをやっているんだ。それに、価値があるかどうかは措いても、数学的な正しさは保証する」と反論しますが、哲学者からはなかなかそういう反論は聞こえて来ません。どうも哲学界では異分野の者から批判を受けて自分野を守ろうとするときに身内に向けて最強のチャリティ精神を発揮なさっているように見えて、私にはチャリティをいただけないようです。哲学界では身内の見解には「けちをつけない」ことが優先されており、ややもすると荒唐無稽な論者にとって居心地の良い環境になり、結果的にはチャリティ精神が真に建設的な方向には機能していないような気がします。
5.研究発表の形態と質保証
『科学を語るとはどういうことか』(増補版pp.30-31)で議論されている、文系分野では研究成果を書籍として発表することが多いという点について、問題提起します。
まず私の個人的な見聞を述べます。私が哲学者の皆さんと分担執筆した書籍『〈現在〉という謎』は、紙上討論という形を取っていたので、ピアレビューになっていると言えるのかもしれませんが、私が哲学者の草稿に質問・コメントを大量に付けたら、哲学側の方から、そんな論文査読みたいなことをされるとは思っていなかったと言われ、哲学者の草稿を見せていただいたのち1週間ほどで、これで最終稿にしますと言われ、紙上討論は噛み合わず、私の疑問は晴れない形になりました。あの書物の内容に私が納得・同意していると思われてはたまらないと思い、私は補足ノート(『一物理学者が観た哲学』、いわゆる『谷村ノート』)を書いてネットに公開しました。この一件をもってしても、商品としての書籍を発表媒体として内容の品質保証ができるのか?という強い疑問を持ちます。
また、私は、外国の学術誌に投稿された哲学的主題を扱った英文論文の査読を2回依頼されたことがあります。物理の哲学的側面を議論している論文でしたが、どう見ても著者は主題としている物理学的部分をよく理解していないようであり、内容がいいかげんだとしか思えなかったので、私は掲載却下を勧めました。私の個人的な見聞のエピソードは以上です。
理系の研究者が論文を載せたいと思うようなブランド力の高い学術誌は、高額な論文掲載料を取るところもあります。なので、「自費出版」に近い状況は理系にもあると思います。ただ、その場合でも査読があるのは当たり前です。
理系では論文掲載料が無料の学術誌も、そこそこありますが、文系の方たちには発表媒体の選択肢があまりないとすれば気の毒に思える面もあります。それでも査読の有無の差は大きいと思います。
あるいは、人文系の研究テーマについて語り出すと、自分の研究成果だけを述べるだけでは済まず、先行研究の整理から話をしなくてはならず、まとまりのある論を展開しようとすると、数ページから数十ページの論文では収まらず、どうしても書籍という形が選ばれるのかもしれません。たぶん理系は、特化された専門分野に多くの研究者が集まっていて、昔の研究成果は常識として同種研究者たちに共有されているので古い問題を蒸し返す必要がない、理系研究者は概念的な問題をしつこく問いただしたりしないという事情・性格もあって、短い論文で研究情報を交換できるという面もあると思います。ですので、文系・理系を同じ土俵で比較することはフェアではないと私は思っています。ただ、質保証という点に関しては、哲学系研究者は、もうちょっと相互に、また、自己に対しても、厳しくしてもいいんじゃないかと思います。
私自身は、論文はうるさく査読されるべきだと思いますが、他方、書籍は自由に書かせてほしいと思います。しかし、何を書いてもよいという自由ではなく、他の物理学者や数学者に読まれても恥ずかしくない内容を書かなければならないという緊張感はあります。それは、私自身も他の物理学者が書いたものを相当批判的に読んでいるからです。数学書は、定義・定理・証明が書かれているのが通例で、疑ってかかるような読み方はしなくてよいのが普通ですが、それでも意味の取れないようなことが書かれていたら用心して読みます。
文系・理系にどちらにしても、厳しい査読を経て質保証されている知識の蓄積・流通形態と、査読されていなくて玉石混交であり内容の価値判断は読み手に任せる形態とを、はっきりと棲み分けて使い分けた方がよいのではないか、と私自身は考えています。やがては、研究の知見を玉石混交にしておいてもAI(人工知能)がふるいにかける時代が来ると思います。
以上は質問というよりも私の意見ですが、文系・理系どちらもこういった状況をこのまま放置しておいてよいと思われるでしょうか?改善するとしたら、どのような方策があるとお考えでしょうか?
谷村省吾(たにむら・しょうご)
名古屋大学大学院情報学研究科教授。共著書に『<現在>という謎』があり、その補足ノートは谷村氏のホームページにて読むことができる。