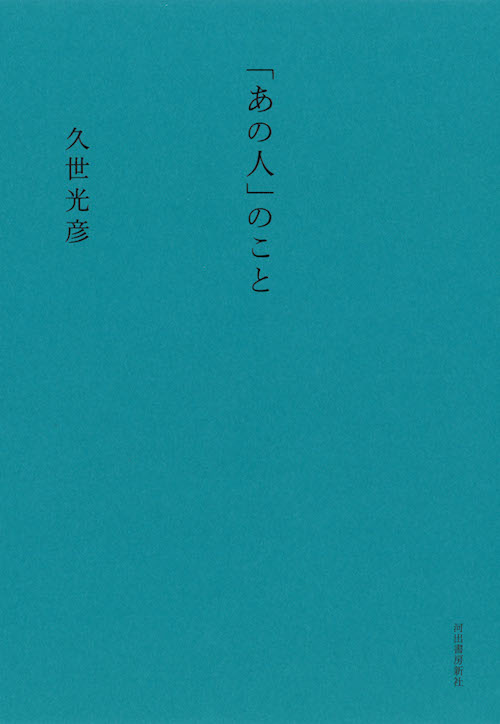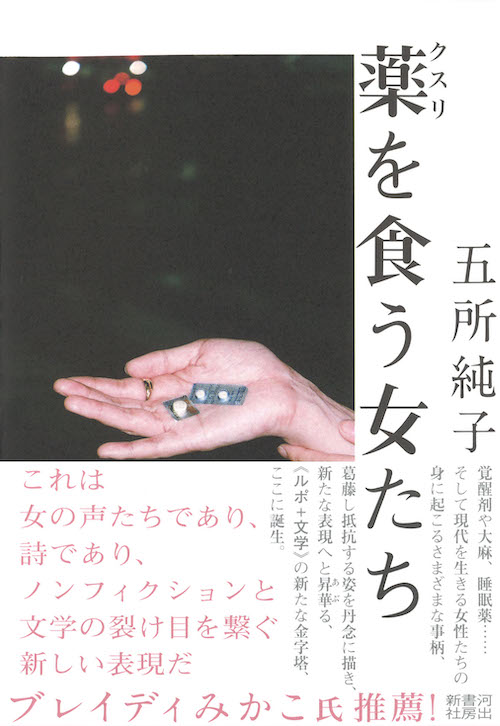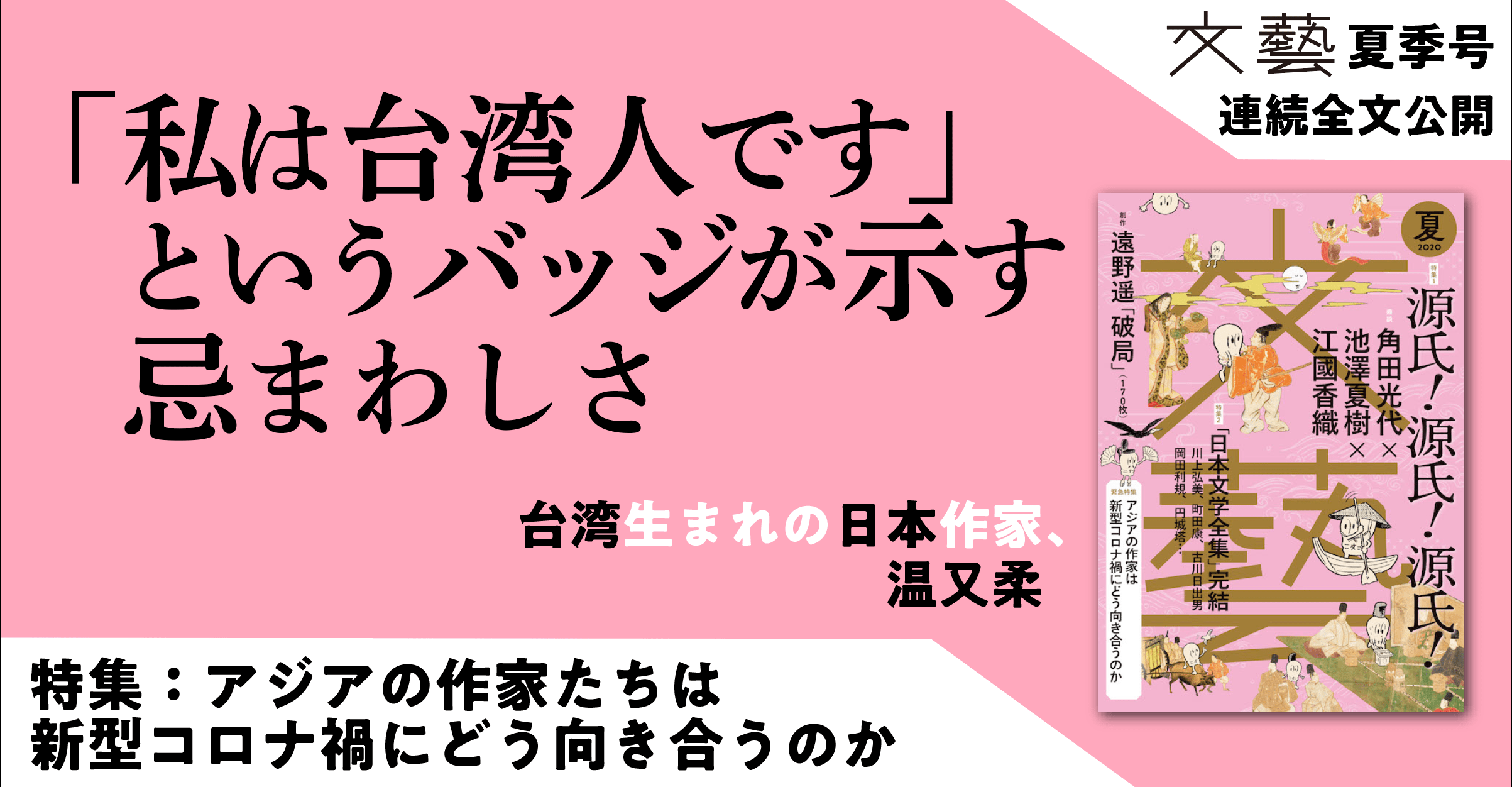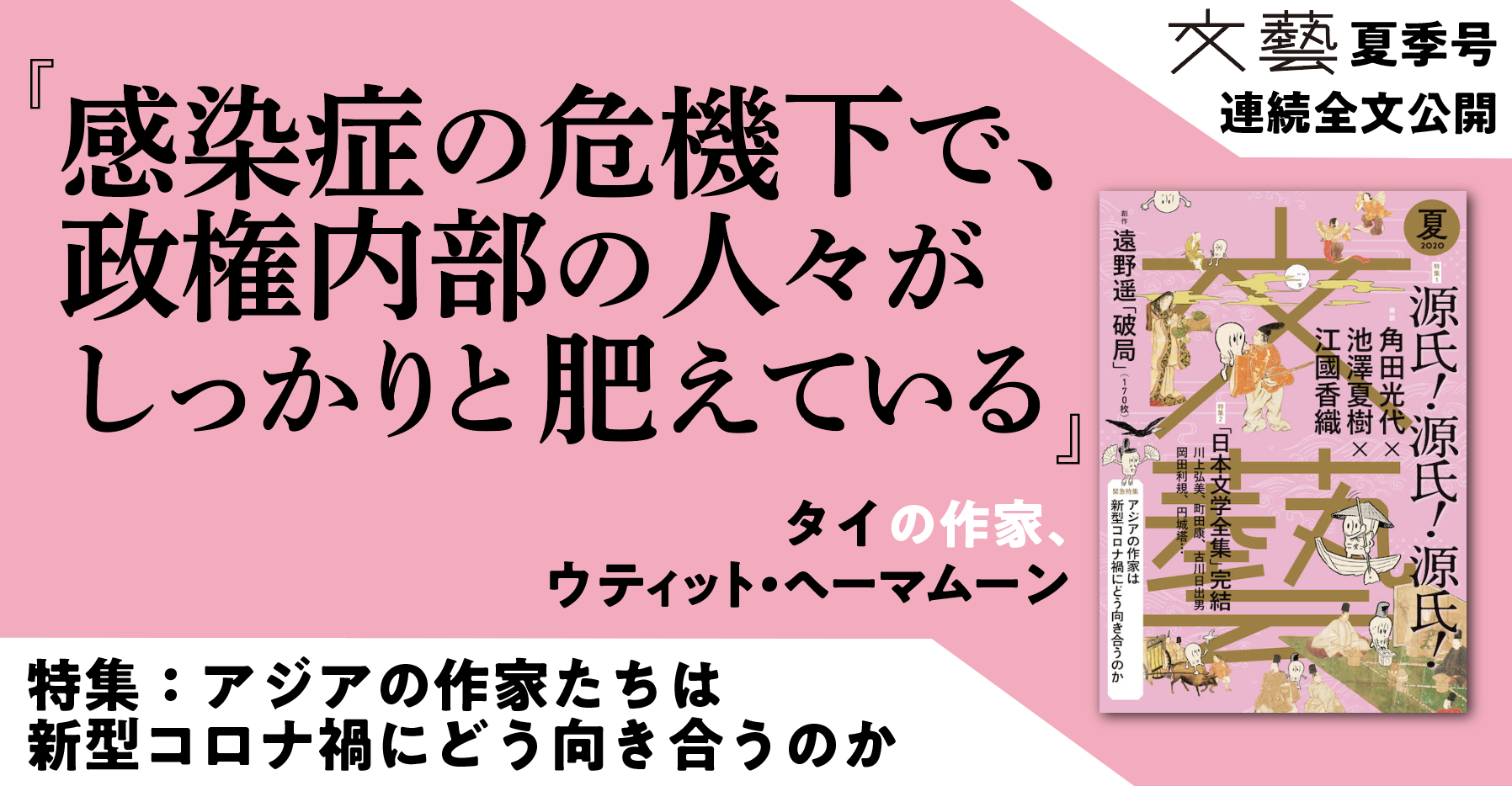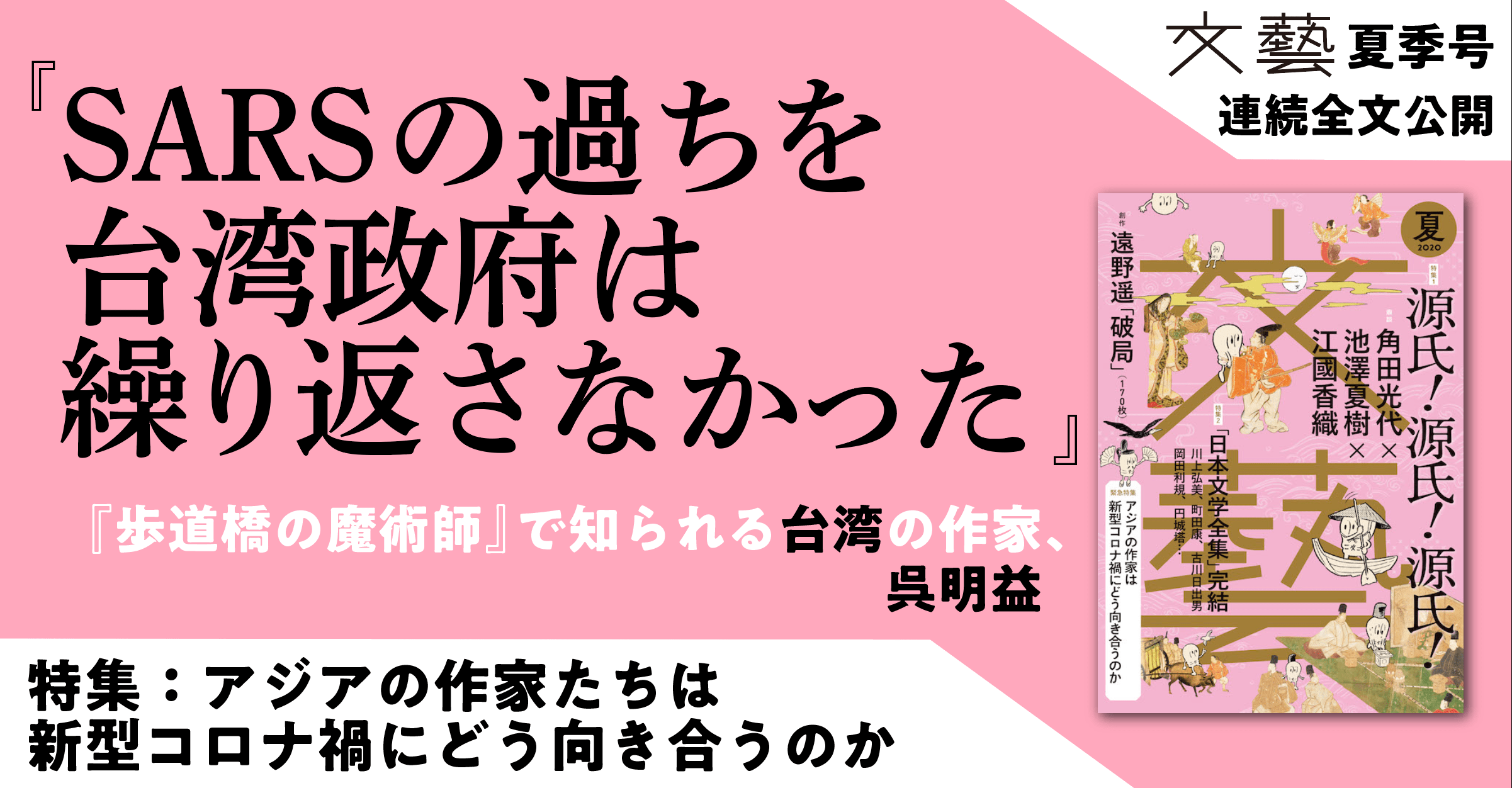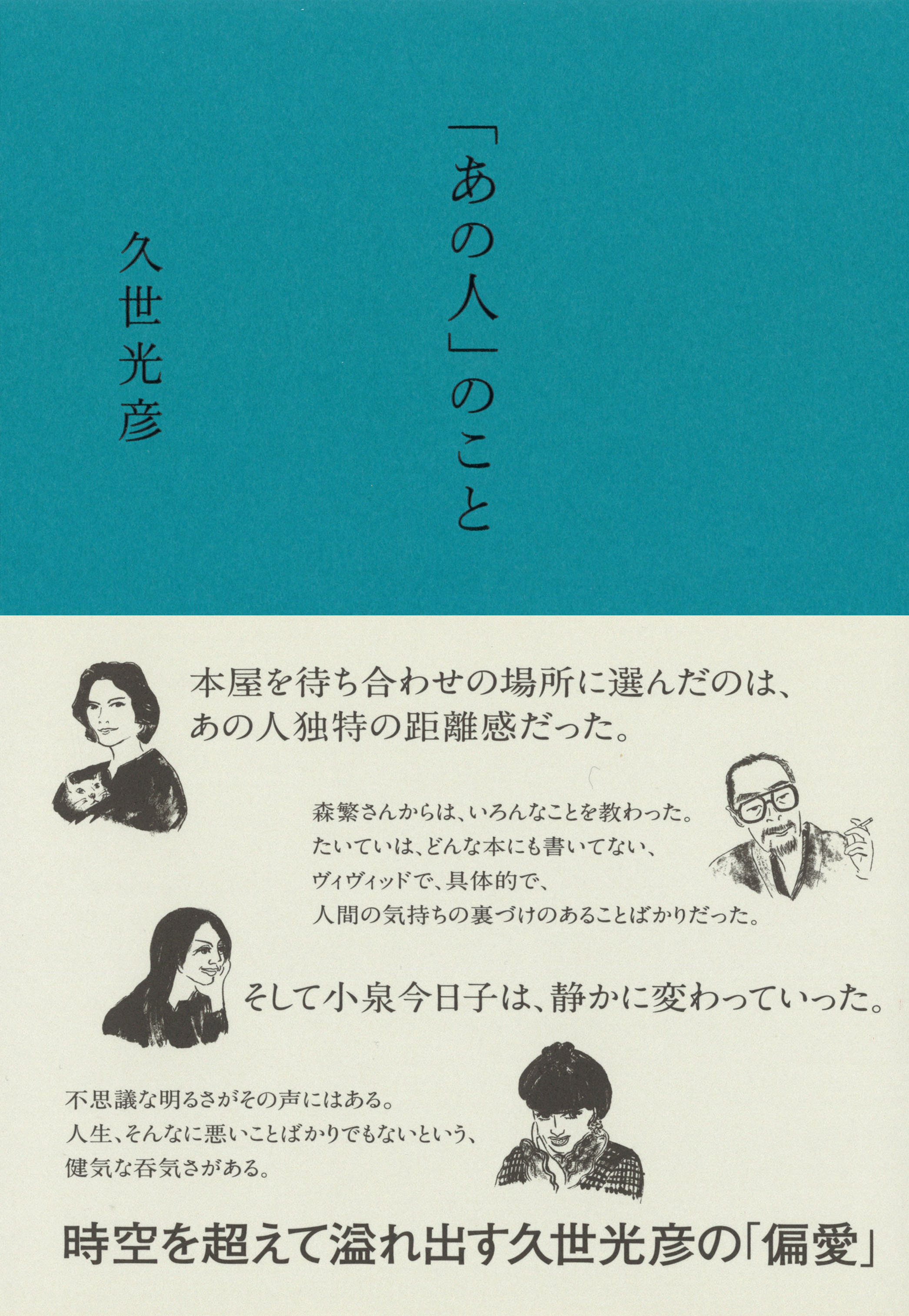
単行本 - エッセイ
可憐なテロリスト、内田裕也の<友情>|久世光彦エッセイ集『「あの人」のこと』から
久世光彦
2020.07.01
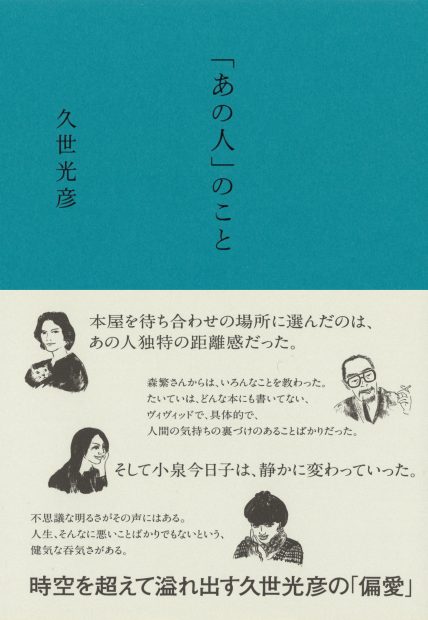
演出家、テレビプロデューサー、小説家として幅広く活躍された久世光彦さん。卓抜した審美眼は知られるところですが、その琴線にふれた人々について愛情あふれるエッセイを多く遺されたことはご存じでしょうか。
このたび、その人物エッセイから精選したアンソロジー『「あの人」のこと』を刊行しました。向田邦子、森繁久彌、黒柳徹子、小林亜星、ちあきなおみ、高倉健、阿久悠、江戸川乱歩、太宰治……人々の息吹と時代がよみがえる名文揃いの一冊です。
本書刊行を記念して、収録作品から、内田裕也さんについて書かれた名品「十階のモスキート」を公開します。久世光彦さんと内田裕也さんの濃厚で不可思議な交流を是非ご堪能ください。
十階のモスキート
内田裕也について書いたり喋ったりするには、度胸と細心の注意と、その上に相当の覚悟が要る。小さな雑誌の片隅に、ほんの五十字ほどの字数でこっそり書いても、あるいは口の固い身内だけの席でふと一言彼について洩らしても、三日も経たないうちに、当人の耳に入っているからである。そのことについてクレームが来るわけではない。ただ、読んだとか、聞いたとかいうことだけが、それとなく人を通じて当方に伝わってくるのだ。怒っているとも、笑っていたとも、その辺のところは解らない。解らないから尚のこと、無言の圧迫感にギクッとする。何か気に障ることを書いただろうか。口にしただろうか。――そんな謂れのない不思議な圧力に怯えることが、もう三十数年もつづいている。
内田裕也とは一年に一度だけ会う。というよりは、一年に一度しか会わないことにしている。触らぬ神に祟りはないからである。どこがどう面倒なのかは上手く言えないが、どちらかと言えば顔を合わせない方が無難なのだ。だいたい世間の人は、私と同じように思っているらしいが、そう考えるのも、あまり根拠のあることではなく、気配に過ぎない。私は毎年大晦日になると、お酒を三本下げて彼の主宰するロックコンサートへ出かける。この何年かは浅草の〈ロック座〉に落ち着いているが、その前は晴海の埠頭だったり、浅草国際劇場だったり、もっと昔の昭和四十年代は、渋谷の〈西武劇場〉なんかを転々としていた。当時のロックンロール族は、醇風美俗に相応しくないとのことで、大抵の劇場から不当に締め出されていたのである。
〈ロック座〉の楽屋は大変な混雑だ。みんな革のコートや黒装束で髪が長く、老若もいろいろで誰が誰だか解らない。そうした黒い人間たちの渦の真ん中に〈総帥〉がソファに埋もれている。背後にも足元にも一升壜が林立して、彼は白髪白髥の酒仙のように決まっているが、周囲は飲んでいても〈ロックの神様〉だけは素面なのが不思議である。恒例の年越しのカウントダウンが終わるまで、つまり新しい年が明けるまで、彼は律儀に酒を口にしない。それが彼の信条であり、矜持であり、ロックンロールの魂なのである。
雛段に例えれば、内田裕也の両脇には、〈右近の橘〉と〈左近の桜〉よろしく、ジョー山中と安岡力也が控えて壮観である。ヤクザ一家に例えれば、代貸と若頭といったところだろうか。このアナーキーで美学的な構図は、過去二十年来変わっていない。このごろ滅多に見かけない〈男たちの世界〉の匂いがプンプン立ち籠めている。もしジョーや力也が危難に遭っていると聞いたら、内田裕也は深紅の扱帯を風に翻して、高田馬場へ走るだろうし、裕也が襲われていると知れば、この二人は何の躊躇いもなく現場に駆けつけて、あっさり命を捨てるに違いない。これは物の譬えではなく、正気の話である。
内田裕也の交遊関係は非常識に広く、また深いから、年に一度の〈ニューイヤーロックフェスティバル〉の楽屋周辺は、無数の彼の〈友だち〉で芋の子を洗うような混雑なのだが、彼は律儀にその全ての人たちを私に紹介しようとする。一人一人、氏名に身分、経歴から係累まで詳細に説明してくれる。それが彼の考える気遣いであり、礼節なのだ。とてもではないが、憶えきれない。その都度の握手で掌が痛くなる。相手は音楽関係、映画テレビ関係、服飾、美術業界から文筆出版関連、大道芸人から木遣り社中、錺職人がいるかと思えば、頰に疵のあるヤバい男もいる。浅草署の刑事にフーテン娘もいて、ゴッタ煮の一夜だった。〈御大〉は知らない同士が親しくなっていくのが、いかにも嬉しそうに目を細めている。この一夜、〈ロックンロール〉というキイワードでみんなが結ばれているのに満悦しているのである。内田裕也はそんな風に単純で、解り易い男なのだ。
何にしても人間関係に臆病なくらい神経質だ。あちら立てれば、こちらは立たない場合にも、彼は何とか両方立てようと死に物狂いになる。無理だと言っても聞かない。だから可愛い娘の也哉子と、本木雅弘との結婚披露を明治記念館でやったときは、招待客の顔触れとその席順で、女房の樹木希林さんと二人で血みどろの騒ぎになった。会場の都合で人数に制限がある。女房の方は亭主を立てて遠慮して、ごく控え目な招待客だったが、裕也側は非常識な〈友だち〉の数である。二日二晩モメて、当日の朝になってまだ結論が出なかった。草臥れ果てて、新婦の両親はその日一日、腑抜けのようになっていた。
披露宴の引出物は、菊の御紋の入った金色の文鎮と、赤い唐傘だった。意味はよく解らなかったが、小粋なものだった。宴がお開きになった午後三時ごろ、折りよく杉木立を縫って、パラパラと夕立がやってきた。玄関口から出た客たちは、一斉に引出物の傘を開いた。新緑の中に、唐傘の赤がきれいだった。――一度〈也哉子〉のことを〈哉也子〉と書き間違えて、希林さんに厳しくられたことがある 。裕也が知ったら大変なことになるという。裕也の〈也〉の方が先なのである。
ジョーと力也だけは〈アンちゃん〉と言うが、大方の連中は彼のことを〈裕也さん〉と呼ぶ。沢田研二もビートたけしも、死んだ松田優作も〈裕也さん〉だった。娘の也哉子も婿の本木も〈裕也さん〉だから面白い。〈裕也ちゃん〉と懐かしげに呼びかけるのは、渡辺プロ会長の美佐さんで、「ジイジ!」と怒鳴りつけるのは、〈雅樂〉と〈伽羅〉という風雅な名の孫たちである。〈裕也〉と呼び捨てにするのは、渡辺プロ時代に〈ダブル・ビーツ〉というペアを組んで歌っていた田川ジョージぐらいのもので、偶に若いロッカーなどが、阿って〈御大〉とか〈大将〉とか呼ぶと、当人に三白眼で睨まれて黙る。だから男も女も〈裕也さん〉である。
私は何と呼ぶかと言うと、いろいろ考えた末、名前を呼ばないことにしている。何と呼んでも角が立ちそうに思われるのだ。蔭では年長の特権で〈内田裕也〉と言っている。まあ、一種の呼び捨てである。すると時々、尊敬される。あんな凄い人を呼び捨てにするのだから、もっと偉い人かと思われるのだろう。それなら裕也の方はどうかというと、全人類なべて〈さん〉である。この平等主義は気持ちがよかった。相手がフジテレビの日枝会長でも、〈会長〉ではなく〈日枝さん〉なのだ。時に年若の人にも〈さん〉を付けて気味悪がられる。
三十年ほど前に、内田裕也が「週刊プレイボーイ」に、交友録を書いたことがある。見開き四ページに、無慮数十人に及ぶ人物が登場して壮観だったが、それぞれの人に付ける敬称が、いかにも裕也らしくユニークで、ほとんど感動した。例えば〈キョードー東京〉のプロモーターの永島達司さんなら〈永島氏〉だった。勝新太郎さんは〈勝さん〉、オノ・ヨーコさんは〈オノ・ヨーコ女史〉で、旧友の田辺昭知は〈昭ちゃん〉、たけしは〈タケチャンマン〉で、沢田研二は〈沢田選手〉と、その気配りの利いた使い分けが見事だった。いまでも忘れられない、友情に溢れた名文だった。
長幼の序を重んじると共に、体育会系の上下関係にも厳しいものがあった。数十組が出演する〈ニューイヤーロックフェスティバル〉の演奏順にしても、デビュー年も、参加回数も心得た上での差配だから、一切苦情は出ない。ただ、彼の上下感覚には、多分に山下清の〈兵隊の位〉的なところがあって、面食らうことが屢々ある。あるとき、こんなことがあった。――六本木に〈パブ・カーディナル〉というスコットランド風のパブがあって、私は内田裕也とある日その店にいた。私よりも、裕也よりも年若のある男が、偶々入ってきた。そのころ、私がやっていた「悪魔のようなあいつ」というドラマで、私はその男にちょっとした不義理をしていたので、私は立って彼の席へいって頭を下げて挨拶した。その途端、裕也から猛烈なクレームがついた。「自分はかねてから、あなた(私のこと)に敬意を払って接している。そのあなたがあの男に頭を下げるということは、自分もそうした態度をとらなければならないことになる。自分はあの男に何の借りも義理もない。むしろ見下ろしている。したがって、あの男に頭を下げられては困る」――これが裕也の筋道だった。私は言った。「あなた(裕也のこと)と私の関係と、私とあの男の関係は別物である。二者の関係の中に、突然第三者が入ってきて、上下関係を統一しろと言われても、できないこともある」――これが裕也には納得できない。顔色が変わっていた。
こんなこともあった。裕也が新宿のゴールデン街で飲んでいた。隣りのテーブルで盛り上がっていたテレビ関係の男が、何かのついでに私の悪口を言ったらしい。それが裕也の耳に聞こえた。逆上した裕也がいきなりその男に摑みかかった。二人は縺れて、裕也はガラス戸に腕を突っ込んで血塗れになった。翌日その話を聞いて、私は涙ぐみながら迷惑だと思った。――それが内田裕也の〈友情〉なのである。
「時間ですよ」という番組をやっていたころ、裕也から電話があってリハーサルを見学したいと言う。その晩、彼と悠木千帆(いまの樹木希林)さんは初めて会った。その日のうちにそうなったらしい。そんな縁で、七三年十月、築地本願寺で行なわれた彼らの仏前結婚式に、私は〈立会人〉として列席することになった。〈媒酌人〉は立てず、〈総括立会人〉がかまやつひろし、新郎側が沢田研二、新婦側が私という〈三人立会人制〉であった。意味はよく解らなかったが、三人とも厳粛な気持ちで、仏前に新郎新婦を挟んで並んだ。取材のカメラのフラッシュが眩しかった。次の朝のスポーツ紙に、軒並み写真が載った。左から順に、沢田、裕也、かまやつ、悠木千帆――右端にいたはずの私は、タキシードの肩しか写っていなかった。
その夜、中野公会堂で開かれた〈沢田研二リサイタル〉に、新夫妻と私はいった。リサイタルの中ごろ、沢田に呼ばれて裕也が舞台に上がった。掛け合いの《If You’re Looking For Trouble》が始まった。潤んだ目と目を見交わして、男と男の何とも色っぽいステージだった。あの夜の内田裕也は、ほんとうに嬉しそうだった。
何でモメるのかは知らないが、夫妻は結婚当初からモメにモメて、爾来三十数年、二人で〈The Troublers〉というデュオをやっている。――あのころは夜中によく電話がかかってきたものだ。午前三時ごろ電話を取ると、裕也が殺気立った声で「すぐ来てください」と言う。遥か遠くで、私の名を呼ぶ千帆の泣き声が聞こえる。私は兎に角、着替えてタクシーに乗る。〈立会人〉の義理である。代々木上原のアパートの四階でエレベーターを降りると、降りた目の前のフロアに、そのころ流行っていたロンドンブーツの、折れたヒールが一つ転がっている。〈trouble〉の痕跡である。開けっ放しのドアを入ると、髪振り乱した両人が、肩で大きな息をつき、蒼ざめて対峙 している。「まあまあまあ」と中に入って三人でミーティングが始まる。これが毎度、朝の九時ごろまでつづく。
私はいつも思った。どうして私だけが呼ばれるのだろう。公平に、新郎側立会人の沢田も呼んで欲しいものだ。――亭主はひたすら怒鳴り、女房は泣きながら、その合間に寸鉄人を刺すような、痛烈な一矢 を放つ。怒髪天を衝くとはよく言ったもので、本当に二人の髪は逆立って、まるで連獅子を踊っているようだ。九時になると、テーブルを挟んだ二人の間の電話が鳴る。一般社会の始業時である。雌獅子が受話器を取る。いままで泣き叫んでいたのが噓のように、女房は愛想よく、「あ、例の物件ね、あれ、もう少しキープさせてくれません?」――相手は不動産業者である。女房の実益を兼ねた趣味は、不動産の売買だったのである。折しも、部屋に燦々と朝日が射す。三人はガックリ白ける。
内田裕也は可憐なテロリストである。いつだって、あの炯々とした危険な目で、標的を狙っている。ウカウカ眺めているわけにはいかない。いつ銃口がこっちを向くか知れないからだ。私が大晦日しか彼に会いにいかないのは、いくら何でもニューイヤー前夜ぐらいは私を撃たないだろうと思うからなのだ。それでも私は、背中で怯えながら、〈ロック座〉の階段を小走りに駈け降りる。
縦縞の紺のスーツの胸に紅い花を一輪飾ったテロリストがいる。「エロティックな関係」だったか「十階のモスキート」だったか忘れたが、バーバリーのレインコートのポケットに両手を無造作に突っ込み、廊下をほんの少し揺れながら、真っすぐにこっちへ歩いてきた内田裕也を、私は忘れない。彼はタイトに束ねられた赤い花束を小脇に、まるで機関銃みたいに手挟んでいた。
ついでに言うと、この国で〈私立探偵〉という役を完璧にやってのけるだろう俳優は、内田裕也一人である。レイモンド・チャンドラーは、てっきり裕也をモデルにしてフィリップ・マーロウを創ったのかと思ったことがあるが、調べてみたら、まるで年代が違っていた。チャンドラーが、〈The Big Sleep〉で、初めてマーロウを世に送り出したのは、一九三九年だったが、裕也はちょうどその年に西宮で生れている。あの有名な《If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. If I couldn’t ever be gentle, I wouldn’t deserve to be alive》(hard でなければ生きていけない。gentle でなければ生きていく資格がない)という名台詞は、裕也のために用意された台詞としか思えない。映画「三つ数えろ」は、チャンドラーの〈The Big Sleep〉をハワード・ホークスが第二次大戦後すぐに、ハンフリー・ボガートとローレン・バコールで作ったものだが、私が見た映画の裕也はボギーよりもずっと、よれよれの探偵のコートが似合っていた。――因みに内田裕也の映画のベストスリーをここに挙げるなら、私が選ぶのは「嗚呼!おんなたち 猥歌」「十階のモスキート」「コミック雑誌なんかいらない!」の三作に、次点が「水のないプール」である。
裕也が主演した「十階のモスキート」はセンスがあって、なかなか面白い映画だった。この洒落たタイトルは裕也自身がつけたものだが、彼はそのころ、青山の九階建ての痩せたビルの屋上に乗っかった、物置小屋風のプレハブに一人で棲んでいた。一度訪ねたことがあるが、台風でもくれば簡単に吹っ飛びそうな、建て付けの悪い情けない小屋だった。その中に、顔色の悪い一匹のモスキート(蚊)が、息を潜めている。ドアを開けると、入り口から奥のベッドまで、床いっぱいに広がった衣裳の海で、そこを渡ると足が膝まで沈む。シャツにジャンパーにコートにネッカチーフ――他にこの部屋には、家具什器の類いは一切ない。その日私は、衣裳の山の底から掘り出した革ジャンを彼に貰った。アメリカ西海岸の古着屋で見つけてきた、背中から胸にかけて、星条旗が翻るド派手なデザインだった。折角だったが、恥ずかしくて一度も着なかった。
裕也の私立探偵には、沢田研二が歌う「探偵〜哀しきチェイサー」という歌がよく似合う。ヤクザ紛いのモスキートみたいな、街の探偵の歌である。《何げないしあわせの裏に/ひそんでいる罪の色を/得意げにあばきたてたあと/この胸は重くなる》《夜の闇の中を/犬のようにはいずり/むくわれないよ/ひんやりと重いコルト/抱きしめ酔いつぶれ/哀しきチェイサー》《探偵が見る夢は/ドクターが見捨てたひとの/強がりやすすり泣き/俺もまた捨てられたひとりか》――まるで裕也の独白のようではないか。そして沢田は、〈裕也さん〉の背中に囁きかけるように「哀しきチェイサー」を歌う。沢田研二は裕也が五十年来、誰よりも愛する男なのである。思い出してみれば、結成当初の〈タイガース〉は、〈内田裕也とザ・タイガース〉であった。――そう言えば、沢田の古いアルバムに「湯屋さん」という可愛らしい歌がある。
九階建てのビルの〈十階〉に棲んでいたころからこっち、彼がどこで、どうやって生きているかも知らない。噂にも聞かないし、女の匂いも匂ってこない。東京のどこか片隅で「ロッキンロール!」と呟きながら、油の沁みた布切れで銀色の狙撃銃を磨いているのだろう。彼は〈ロックンロール〉のことを〈ロッキンロール〉と発音する。彼が以前講談社から出した本は『俺はロッキンローラー』だった。けれど私には、それが〈ロッケンロール〉に聞こえる。彼の〈rock’n〉は、〈rock’in〉よりは寧ろ〈rock’en〉なのである。彼が出演した映画の録音技師に聞いた話だが、裕也は監督の「ヨーイ」の声が掛かると、圧し殺した声で激しく「ロッケンロール!」と吐き出して演技に入るという。それが全部録音されている。通俗に言えば〈気合い〉なのだろうが、彼はそうやって自分を高揚させ、魂を鼓舞して〈本番〉という〈敵〉に挑むのだ。彼の〈結婚〉もそうだった。裕也は悠木千帆という、神がかりの〈不思議〉に挑んだのだと思う。お互い、その高揚は愛と名付けるに相応しいものだったが、勝負の決着はまだついていないようだ。――東京都知事選もそうだった。得体の知れないモヤモヤしたものを見ると、彼の魂が「ロッケンロール!」と叫び、体が白熱して闇雲に飛んでいってしまうのだ。
人はそれを〈狂気〉と言う。裕也の場合、〈狂気〉は〈凶器〉でもあり〈俠気〉でもある。いずれにしてもヤバいフレーズの数々を、彼は見境なくその身につけている。半世紀の間、私の知っている裕也は、いつだってそうだった。そして年月は過ぎ、内田裕也の〈狂気〉は精神の意匠ではなく、一つの〈ファッション〉にまでなってしまった。それが裕也の、余人には真似のできない〈凄さ〉なのだ。
夕暮れ、渋谷の街が夕焼けると、裕也のことを想うことがある。北原白秋は病気みたいに日暮れの歌ばかり書いたが、なぜかそれらの歌は、どれをとっても裕也に似合い過ぎるくらいよく似合う。《コロガセ、コロガセ、ビール樽、/赤イ落日ノナダラ坂、/トメテモトマラヌモノナラバ/コロガセ、コロガセ、ビール樽。》――《にくいあん畜生は紺屋のおろく、/猫を擁へて夕日の浜を/知らぬ顔して、しやなしやなと。》――《金の入日に繻子の黒――/黒い喪服を身につけて、/いとつつましうひとはゆく。/海のあなたの故郷は今日も入日のさみしかろ。》――夕焼けは〈ユウヤケ〉である。
裕也が死んだという噂だけは、聞きたくない。私にもし、彼への友情の欠片があるとすれば――それだけである。