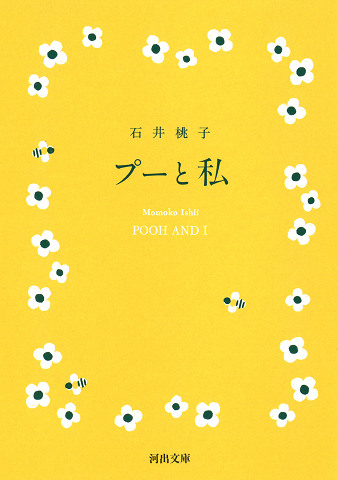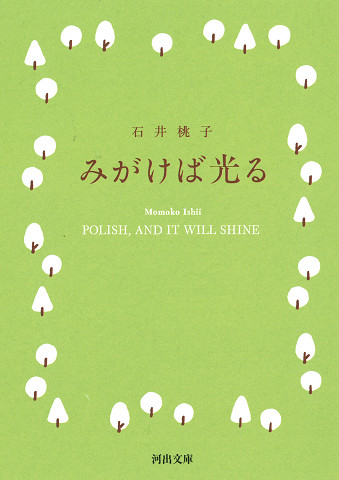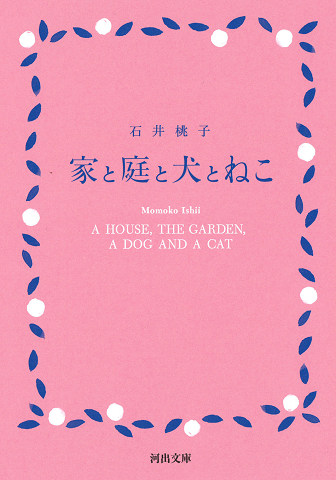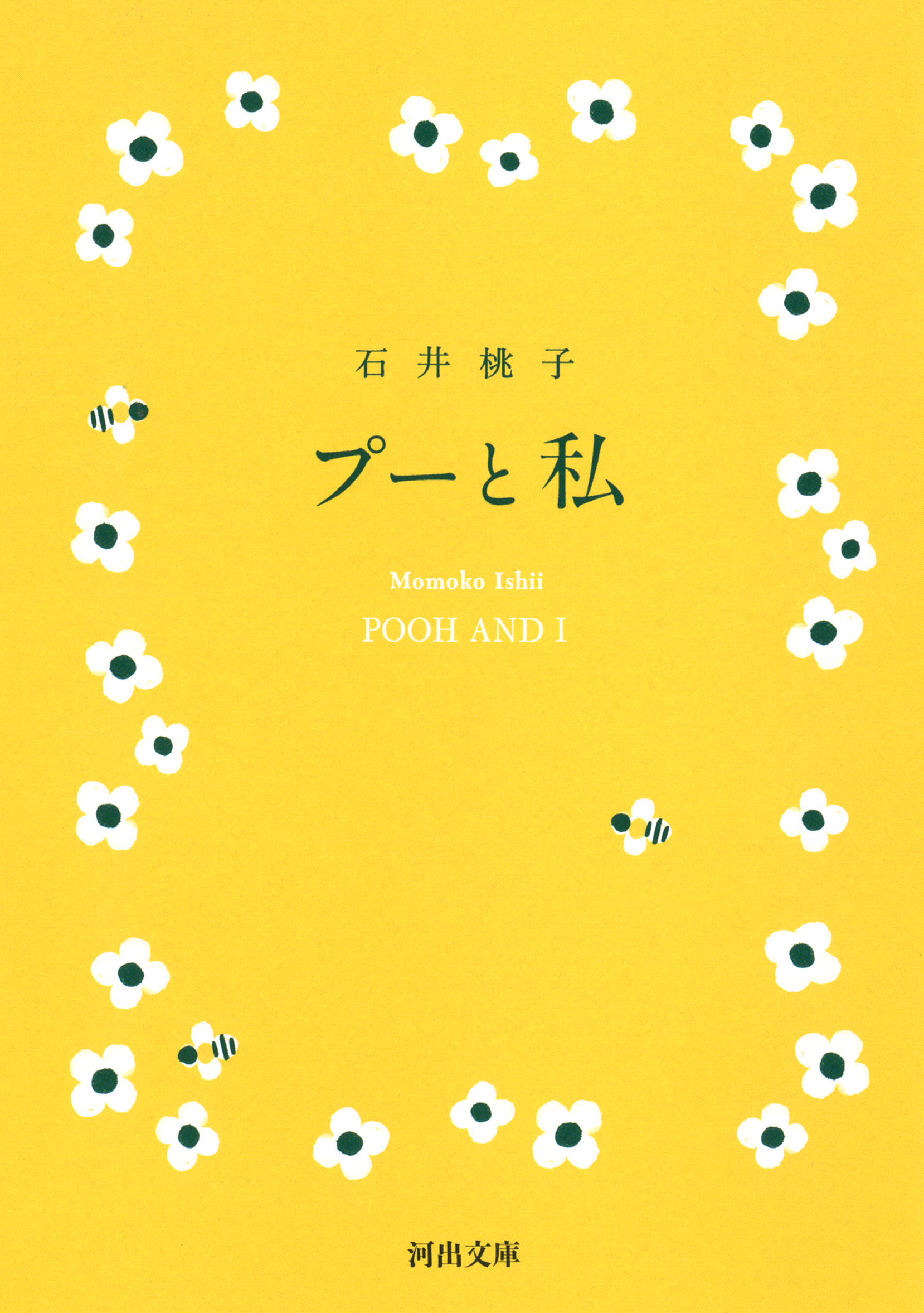
文庫 - 随筆・エッセイ
「没後10年 石井桃子展 ―本を読むよろこび―」開催中──石井桃子『プーと私』解説公開中
梨木香歩
2018.08.20
『プーと私』
石井桃子
文庫解説公開中
****************
「深く関わっていける」資質
梨木香歩[著]
本書は石井桃子の独白とも言えるエッセイ群を編んだものだが、読後改めて、「クマのプーさん」と「ピーター・ラビットの絵本」が、彼女にとって特別の作品であったことを、ひしひしと感じている。
「プーさん」との出会いが最初からいかに運命的であったかは後半で取り上げるが、それに比べて一筋縄ではいかなかったらしいポター作品とその著者との「付き合い」が印象深い。「ピーター・ラビット」に出会った当初、彼女は「さらっとしたお話」だと思ってほとんど気にも留めなかった。だがそれはやがて「気がかりな、こわい本」になる。ビアトリクス・ポター本人にも複雑な惹かれ方をしていく。所収の「ニア・ソーリーまいり」では、ポター作品やポター本人を「訳すのに苦手」だと言っている。「きらいとか、すきとかいうこととは、全然関係がな」くそうだというのだから、向き合うのが苦手だったのだろう。それはつまり、本当は似た資質の持ち主だったからではないか。
ビアトリクス・ポターは晩年農場経営に手腕を発揮し、湖水地方の土地を次々と買い入れてナショナル・トラストに寄付する(その甲斐あって、今の湖水地方の景観が守られた)。石井桃子も戦中から戦後にかけて宮城県の山奥に移住し、自ら鍬を持って開拓、翻訳などで得た印税をその農場経営や協同組合につぎ込んでいる。土や家畜相手の労働、ということに掛け値なしの価値を認める人は珍しくないが、主体としてその労働のなかに身を投じていける人間はそう多くはない。そしてその「深く関わっていける」資質が、創作の際、選ぶ言葉にも反映されていく。石井桃子が苦手としながらもどんどんポターに傾倒していったのは、ミルンに対してと同様、運命的なものだったのではないだろうか。
さて、本書後半に、続きの章で収められている「ビリー」と「ビル」は同一人物、読めば同じ思い出について書いてあるのだということがわかる。前者はその思い出の元になった出来事から一年目、後者は二十年目に執筆されている。だが同じ思い出で、書いている本人も同じでありながら、細部は大きく違う。
紅葉の季節、ニューイングランドの小さな町で、知人の甥夫婦の家に宿泊させてもらうことになった石井桃子は、そこの家の末の男の子と親しくなる。迎える初めての朝、朝食をとる予定の七時近くになると、石井の部屋の前の廊下を小さな足音が行ったり来たりし始める。果たして七時になると、「ビリー」(一年目)の方では、石井が「おはいり」と声をかけるとすぐに入ってきてぶっきらぼうに「おきる時間」と言ったことになっているのだが、「ビル」(二十年目)では、ドアノブがかちゃかちゃいって、小さい声で「おきる時間、おきる時間」とささやく(なんとも可愛らしい)。もっと大きな違いは、「ビリー」での石井はそれから、自分の身支度をすませ、彼といろんな話をしながら折り紙のツルを折ってあげる。一方、「ビル」の方では、石井はベッドのなかから「おはいりなさい」と言い、入ってきたビルの体が(寒い廊下をうろついていたせいで)すっかり冷え切っているのを不憫に思って、「私は、彼を自分のわきに寝かせ、あたためてやりながら、この小さい子を相手に会話の勉強をした」。まるで、母親か祖母が、生まれたときから知っている愛し子に接するそれのように、冷たくなった彼の体を自分の体温で温めた、というのだ。これが石井桃子だ、と思う。一年目では、まだそこを書くのにためらいがあったのだろう。しかし二十年目では、なんだかもう確信犯のように、さらりとそのことを書いている。この二十年間に何があったのだろう。
そもそも、石井桃子が児童文学に大きく開かれることになったきっかけは、本書のタイトルにもなっているエッセイに、詳しく述べられている、犬養邸での、The House at Pooh Cornerとの出会いである。その出会いで彼女は、「その時、私の上に、あとにも先にも、味わったことのない、ふしぎなことがおこった。私は、プーという、さし絵で見ると、クマとブタの合の子のようにも見える生きものといっしょに、一種、不可思議な世界にはいりこんでいった。それは、ほんとうに、肉体的に感じられたもので、体温とおなじか、それよりちょっとあたたかいもやをかきわけるような、やわらかいとばりをおしひらくような気もちであった。」
母子間に色濃くあるような一体感、性的な意味合いを超えた、ある種のエロスの向こうに広がる世界──とばりの向こうはそういう世界であったのだろうか。
さらさらした金髪の五歳の男の子、「おきる時間、おきる時間」と小さくささやく男の子は、まさしくプーの世界の住人、クリストファー・ロビンのように思われたのではないか。そのクリストファー・ロビンを、自分の寝床に思わず引き入れて、母鳥が雛を温めるように温めた、その比類なき幸福感を、石井は最初、世間に向けてうまく説明することができずにいたのではないだろうか。それでありのままに描くことをためらったのかもしれない。しかしこの理屈なきエロスを通してやってくる圧倒的な生命力、これこそが児童文学の持つ力だと、かつら文庫での活動を通すうち、彼女は確信するに至ったのだろう。それがその後の「ビル」となったのではなかろうか。翻って、たとえ「ビリー」の方が現実に起こったことなのだとしても、この間の年月で、石井のなかで思い出が「ビル」に変わっていくほど、その「エロス」への肯定感が強まっていったということだろう。(かつら文庫の開設は一九五八年。その四年後には雑誌『母の友』で「わが友ビル」という、これもまた同じ題材のエッセイを書いているが、このときにはもう、「…おとなしく私のベッドにはいって、しばらく一しょに寝て」という表現になっている)
石井桃子も人間である限り完璧ではない。試行錯誤も迷いもあっただろう。にもかかわらず、その名前は──ずいぶん早くから──批判や反論を寄せ付けない「児童文学の神様」のように扱われてきた(この手のエロスの前には、日本人の批判精神は全面降伏するのだ)。その「扱われ方」の良し悪しは別として、そういう土壌が、空気が、作られてきたことは事実である。それは結局のところ、「あたたかいもやをかきわけ」、「やわらかいとばりをおしひら」いた向こうの世界への番人として、また守り手として、彼女ほどたくましく雄々しく、頼り甲斐のある人物はもう二度と出ないであろうことを、私たちが心のどこかで悟っていたからであろう。
(作家)
*******
石井桃子随筆集の解説を公開中。
*******
〈没後10年 石井桃子展 ─本を読むよろこび─〉
7月21日(土)~9月24日(月・振休)
【会場】神奈川近代文学館
http://www.kanabun.or.jp/exhibition/7991/
*******