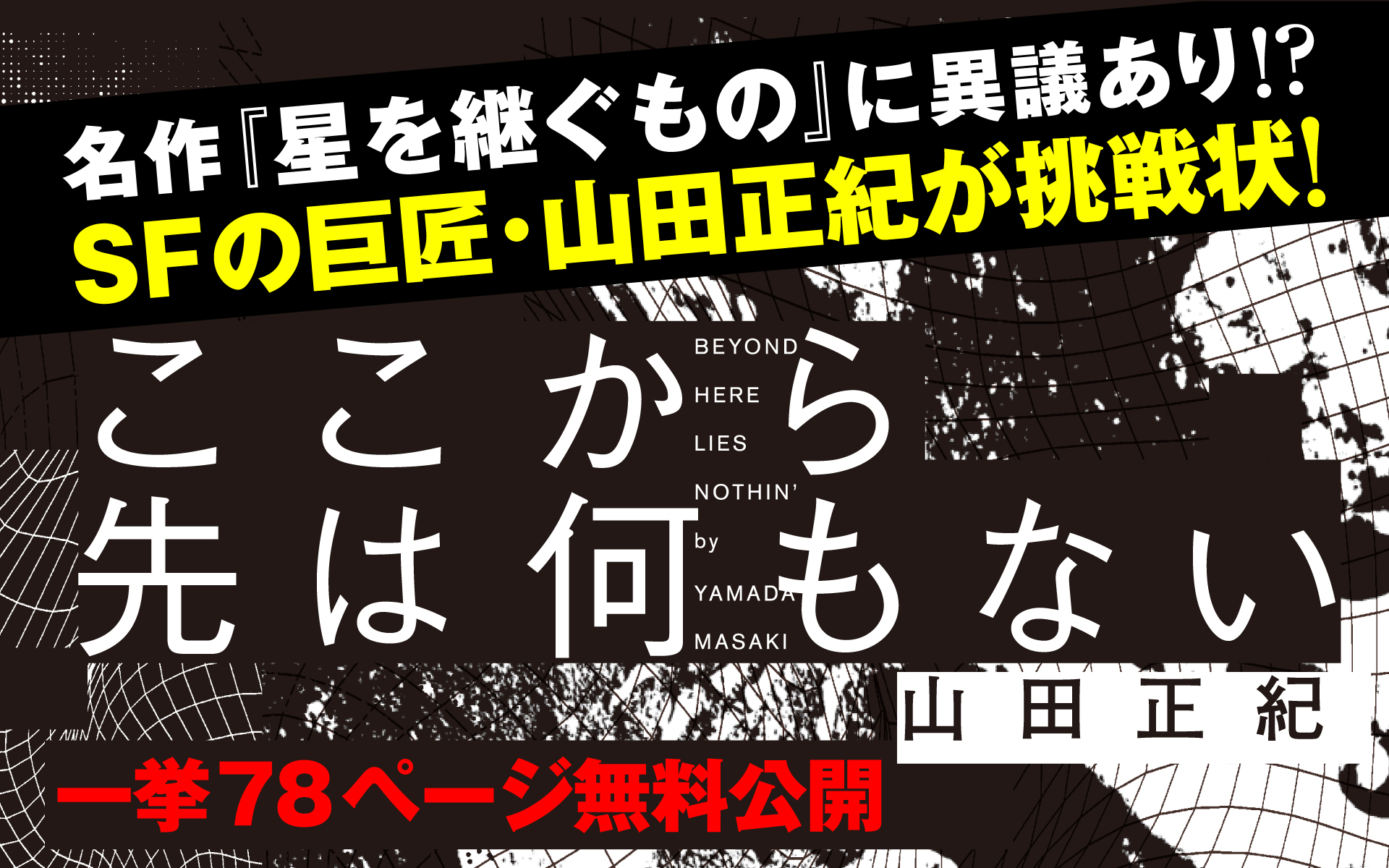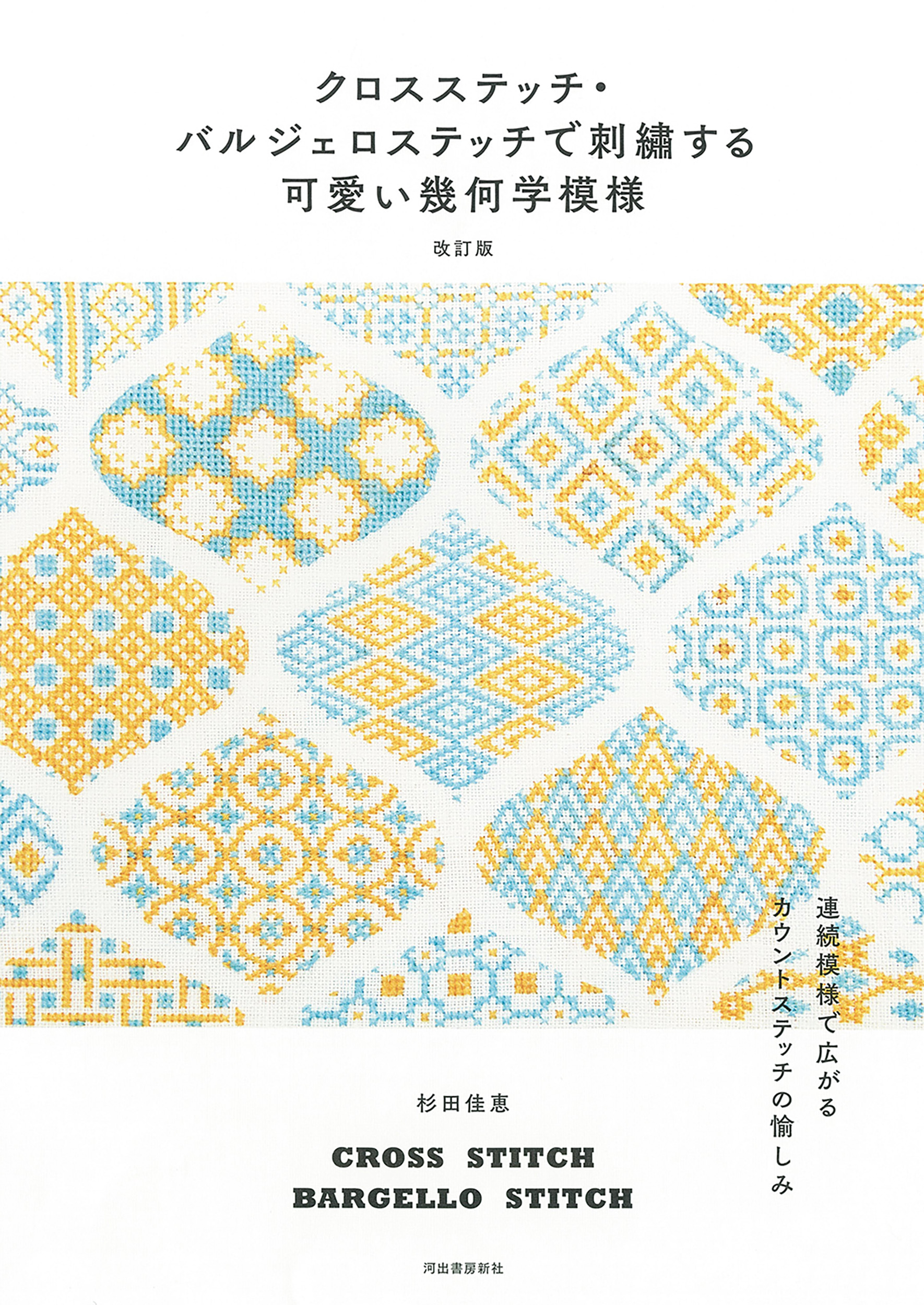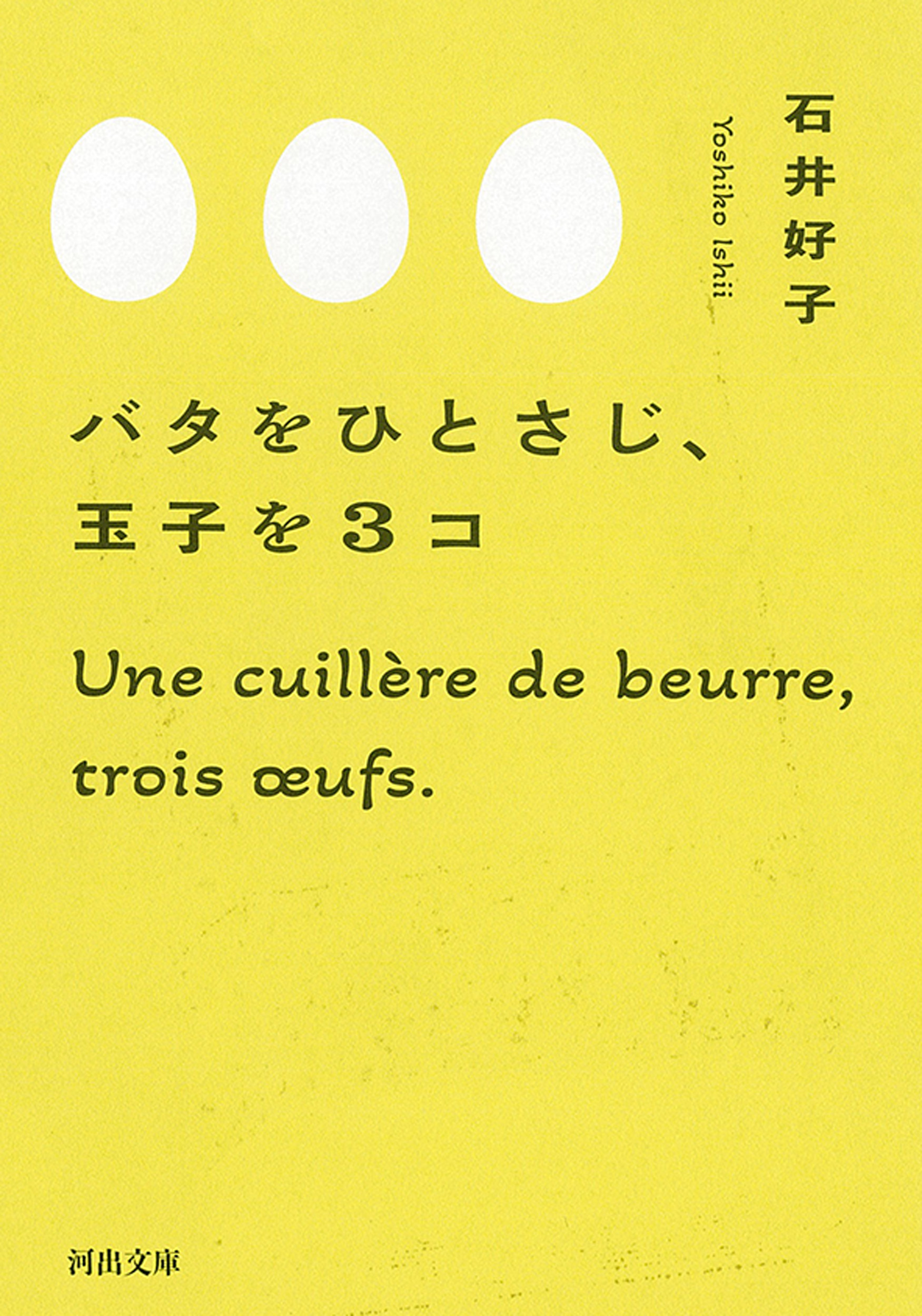文庫 - 日本文学
小説家・津原泰水さんの代表作「五色の舟」(河出文庫『11 -eleven-』収録)全文無料公開!
津原泰水
2020.04.28
小説家・津原泰水さんの代表作「五色の舟」(河出文庫『11 -eleven-』収録)を無料公開いたします。本作は2010年『NOVA 2 書き下ろし日本SFコレクション』のために書かれ、2014年に発表された『SFマガジン』700号記念「オールタイムベストSF」では国内短篇部門1位となった作品です。
<あるべきだった世界の姿と実際に訪れた世界の姿が、凄まじい速度で乖離していく今、僕はその空想を、改めてたくさんの方に読んでいただきたくなりました。>
——津原泰水氏<「五色の舟」全文公開に際して>より
百年に一度生まれ、未来を予言するといわれる生き物「くだん」。鬼の面をした怪物が「異形の家族」に見せた世界の真実とは――。
津原泰水が贈るめくるめく幻想の世界を是非、皆様の「舟」に揺られつつご堪能下さい。
2020年4月28日
株式会社 河出書房新社
***************************************
【「五色の舟」全文公開に際して】
すこしのあいだ、ほんの暫くのあいだだけ、SARS-CoV-2が誕生しなかった世界を想像してみてください、「新型コロナウイルス」という不穏な響きに無縁で生きていられた世界を、反対派にぶつくさ云われながらも東京オリンピック・パラリンピックの準備が荒々しく進み、テレビは選手たちに意気込みを語らせて彼らの及第点を引き上げ、子供達は新しい教室に慣れを感じはじめる一方で連休の予定に胸を躍らせ、お洒落な人々は初夏を先取りした装いでコンサートや芝居に出掛けて風邪をひいている世界を。
そちら側のあなたにとって、治療法が確立されていない疫病が蔓延して連日数多くの人命が奪われ、悲嘆と閉塞感、対策を巡っての口論や罵倒に充ち満ちているこちら側は、失笑が洩れてしまうほど空想的で、野蛮で、もどかしく、でもすこしのあいだ、ほんの暫くのあいだだけなら覗いてみたい世界かもしれません。元の世界に戻れるあてもなく、だらだらと身を置きたいとは思わないでしょうけれど。
もし朝、目覚めたとき、自分がそういう世界の住人だったら――と「むこう側」のあなたはもうひとりの自分を想像し、しかし程なくしてみずからにこう宣言するでしょう――出来ることは限られるかもしれないが、少なくとも、人々への無償の愛と凛々たる勇気を胸に、世界の残酷さに挑み返してやる、断じて負けるものか、後退るものか、と。
誰しもがSARS-CoV-2なき世界に暮らしていた頃、僕はひとつの小説を書きました。その頃から見ても遥かに昔の出来事を、空想して描いた作品です。あるべきだった世界の姿と実際に訪れた世界の姿が、凄まじい速度で乖離していく今、僕はその空想を、改めてたくさんの方に読んでいただきたくなりました。自分の希望というよりも、果たさねばならない義理を思い出したような感覚でした。矢も楯もたまらずその日のうちに出版権を委ねている河出書房新社に相談を持ちかけましたところ、幸いにして無償公開へのご快諾を賜ることが出来ました。
残酷で退屈な「こちら側」でのご退屈しのぎが、いまそこに居られるはずだった「むこう側」のあなた、そしてその思い描くところの凛々しい「こちら側」のあなたへと、輝かしい反射を重ねてくれますならば、かつての僕はこの小説をものした甲斐がありました。
2020年4月28日
津原泰水
五色の舟
下駄屋に生まれたというくだんのために、僕らは一家総出で岩国に出向いた。もちろん買い取るためだ。官憲からの申渡しで派手な興行ができなくなって久しかったが、秘かな催しに僕らを呼びつける旦那の数は、むしろ増えていた。国じゅうが惨憺たる状態にあって、生半可な涙や笑いが受けようはずもない。人々のまなざしを爛々とさせられるのは、もはや僕らのような、圧倒的に惨めな存在だけだった。
一夜の興行としては充分すぎる報酬をもらえたから、いつまで続くともつかない戦時にあって、僕らは未だ飢えていなかった。空襲への恐怖も薄かった。河に舫った舟で暮らしている僕らは、なにか起きたらすぐさま別の街へと逃げられるような心地でいた。
かりに飢えていたとしても、僕らのお父さんはなんとしてもくだんを買うべく算段したことだろう。そんな凄まじい怪物を一座に迎えられたなら、生きている間だけでも購入金の何倍、何十倍を稼ぎ出してくれるか知れない。死んだら死んだで骨だけの見世物にも、標本として商品にもなる。砕いて粉にすれば薬になるだろう。
もっとも、くだんは長くは生きないという噂に対して、それは(面倒見が悪いのだ)というのがお父さんの見解だった。(私は昭助も桜も死なせはしなかった)
一寸法師で怪力の昭助兄さんは、顔に濡れ紙を貼られた赤ん坊の死体としてお父さんの前に現れて、拾われた。当時のお父さんは、先を失った脚に義足を縛りつけ、杖に縋って歩きながら、よく身投げの場所を探していた。ある晩、杖が折れて河原に転げ落ちて、大切な顔に怪我をした。捨て鉢になったお父さんは、すぐさまこの世におさらばするべく、水際に向かって躄っていった。その途中、草陰に兄さんを見つけた。
乾きかけている紙を剝がしてやったが、赤ん坊は身じろぎひとつしなかった。木彫りの仏さんのようだった。愛らしさに思わず抱き上げ、そのずっしりした重みに驚いた。これは特別な子だと分かった。その身はすっかり冷たくなっていたけれど、ふたたび地べたに返す気がしなくなった。
お父さんは思った。このまま朝まで暖め続けても息を吹き返さなければ、ともに水に入ろう。さきはこの子に導いてもらおう。もし息をしたなら、一緒にこちらに留まろう。
河原に朝の光が届いた瞬間、兄さんの身がびんと反り返った。
それからもお父さんの脱疽は進み、すでに切っていた脚の残りも、また反対の脚もほとんど失ってしまったけれど、自分から死ぬことは考えなくなった。僕らのよく知る、今のお父さんになっていった。
桜は、旧家の座敷牢で死にかけていた。噂を聞きつけたお父さんは、十三になっていた兄さんに背負われて、屋敷に通いつめた。そんな娘などいるか、とけんもほろろにされるほど、ここには必ずいると確信したそうだ。
塩をまかれながら半年も通って、今日はなにか家の気配がおかしいと感じていた晩、とつぜん対面をゆるされた。噂どおりの娘たちだった。しかし腰から下を分け合っていたもうひとりの桜は、すでに息をひきとっていた。
(切り離さないと、もう片方も死ぬ)脱疽の経験から、そうお父さんは桜の両親に教えた。(この子を買わせてください。私が医者に診せます)
両親は首を縦にふらない。旧家の意地で血迷っている。子を売るくらいなら、いま目の前で死なせたいと思っている。
(では、もう死んだでいいではないですか。私が弔います。それとも、存在しなかった娘の葬式を出しますか。貴方がたに出せますか)
お父さんは自動車を呼ばせて、死んだ上半身がくっついたままの桜を蒲団袋に詰め、犬飼先生の許に運んだ。せめて遺体としての体裁がととのえばいいとの条件で、先生は施術を引き受けた。死んだ側の上半身を切り離し、はみ出した内臓を縫い、たっぷりと膏薬を詰めて皮膚も縫った。
桜は生き延びた。骨の形がもうひとりが付いていた頃のままなので、前から見ると体がくの字に曲がっている。お父さんは桜の腰に、作りもののもうひとりを縛り付けてお客に覧せようとしたが、彼女の芝居が下手で話にならなかった。
仕方なく体じゅうに鱗を描いて蛇女ということにして、蛙のまる吞みを覚えさせた。もちろんあとで吐き出すのだ。大抵、蛙はすでに死んでいるが、たまに生きたまま出てきて、跳ねて逃げていくのもいる。
こちらはうまくいった。今では桜の鱗は立派な彫り物で、お父さんや僕が毎度描きなおしてやる手間はない。
姿を現したあとは蛙を吞む以外にやることがなかった桜の、最近のもうひとつの大仕事は、別料金を払ったお客にまぐわいを見せることだ。お父さんは最初、昭助兄さんに抱かせようとした。ところが兄さんの一物が並外れて大きいものだから、ほとが裂けてしまった。そこで僕の仕事になった。
眺めるだけではなく自分で桜を抱きたがって、より大金をちらつかせるお客も少なくない。でもお父さんは決して頷かない。あとで桜が相手に似た子を産みでもしたら、具合が悪い。桜か僕か、それとも両方に似た子がいつか生まれるのを望んでいる。それなら一生、食べるに困らないから。
物心がついたときには押入れの闇にいた僕の、最初の外の記憶は、河原を吹く風と、満天の星空と、生い茂った草の向こうで息をしているようにゆったりと沈んでは浮かぶ、大きな舟の影だ。そのときは、とても大きく見えた。
そこが新しい僕の世界だということはすぐに理解できたし、そう考えたとおり、朝になって僕を見つけたお父さんは、快く舟の上に導いてくれた。
お父さんは脚無しだが、僕は生まれつきの腕無しで、指は肩から生えている。でも自分と人との差異を意識しはじめたのは、お父さんの期待どおり見世物としてお客を喜ばせられるようになってからだ。なにしろ犬飼先生が気付くまで、家族も僕自身も、僕の耳が聞えないのを知らなかったほどだ。ちゃんと命令が伝わるものだから、ただ極度に無口な子と思われていた。 僕は僕で、なんで桜は家族と喋らないのか、なぜ僕にだけはときたま、人とは違った調子で喋りかけてくるのか、不思議でならなかった。生まれてから長らく誰にも話しかけられなかった桜は、死んでしまったもうひとりとの間にしか通じない、特別な言葉を持っていた。それが分かるのは、音に関係なく生きている僕だけだった。
僕らのいちばん新しい家族は、牛女の清子さんだ。みずから望んで舟に乗り込んできた。兄さんよりも年上で、世間をよく知っている。人と違うところをすこしは隠しておけたお蔭で、学校に通った経験さえあるのだ。
くだんのこともよく知っていて、それを一座に迎えるのを、ひどく嫌がっていた。本物の人と牛とのあいのこが来てしまった日には、本当は牛になんか似てやしない自分は、居場所を失うと思っている。
くだんは滅多に生まれないのだと、清子さんは教えてくれた。百年に一度だという。 牛だが人の顔をしていて、生まれつきよく喋るのだそうだ。
そして昔のことであれ未来のことであれ、本当のことしか言わないそうだ。
リヤカーを牽いているのは、力持ちの昭助兄さんだ。荷台に敷かれた藁蒲団の上に、日除けの傘を差したお父さんと清子さんがいる。清子さんは膝の関節が後ろ前なので、長くは歩けない。
彼女が元から牛に近いのはそこだけで、あとは犬飼先生に髪のなかに埋め込んでもらった角や、内をつなげた鼻の穴に通した縄や、啼き声や、ぶらぶらさせた大きな乳で、牛から生まれた人間のようなふりをするのだ。今は縄がなく、角も乳も膝も隠しているから、良家の奥さんが疲れて両脚を投げ出しているようにしか見えない。
かたわらを桜と僕が歩いている。僕はいつでも裸足だが、桜は、親切な旦那が買い与えてくれた革草履を誇らしげにしている。この旦那は桜のことを本当に好いていて、蛇女でもいいから妾にしたいと持参金までさげてきた。お父さんは断り、あとで僕らにこう言った。(私たちをまるごと買い取らないかぎり、小屋のなかでの幻は手に入らないよ。それをあの方はご存じない)
清子さんはリヤカーの上で、まだお父さんを説得しようとしている。(くだんは気味が悪いわ。未来も言い当てるのよ。お前は死ぬまで貧乏だとか、いつごろ死ぬって教えられるかもしれないのに、そんなことにお金を払うお客がいると思う?)
(たくさんいるだろうね)
(じゃあお父さんは、自分がいつ死ぬと知ったら嬉しいの)
(目前のこととして言われたなら動揺はするだろうが、それでも、聞かねば良かったとは思うまいね。清子をからかっているんじゃないんだよ。私に自分の寿命が分かれば、お前たちに遺すべきものを、どのくらいの間に準備すればいいかも分かるじゃないか)
夏の遠出は一苦労だ。とりわけ僕と桜は、見世物としての価値を下げないよう、どんなに暑くとも一張羅を着込んで、僕はただ懐手をしているように、桜は肌を見せぬようにしていないといけない。そのうえリヤカーまで重いときて、僕らの歩みはひどく遅かった。朝のうちに出立したにもかかわらず、岩国までには野宿をはさまねばならず、やっと街場に着いたのは、翌日の昼近くだった。
お父さんと兄さんだけなら半分の時間で済んだろうに、それでもお父さんが一家総出を望んだのは、内心ではどこか、くだんを怖がっていたのだろうと今にして思う。だから、たとえ買えるとなっても、最後の答は全員で出したかったのではないかと。 下駄屋が乳を採るために大切にしてきた牝牛が、種牛を乗せてもいないのに急に産んだのだと聞いた。(きっと下駄屋の親爺か若いのが、種を入れたんだろう)とお父さんは笑う。それでくだんを産ませたのだとしたら、大したお手柄だ。
乞食に教えてもらった坂道を上っていくと、それらしき一軒の前に、軍の自動車が連なっているのが見えてきた。帆布で荷台を被ったトラックもあり、けっこうな数の軍人や軍属がそれらの間を行き来している。
(さきを越された。くだんは軍に持っていかれる)そう口惜しそうに叫んだお父さんだったが、やがて吐息をもらして、(未来を予言するというのだから、考えてみれば無理もない。大枚を叩いたあとで接収されるよりはましか。幸運だったと思うことにしよう)
(お父さん、犬飼先生だ)兄さんが叫んで、(あそこ、あそこ)と指を差す。
(先生)(犬飼先生)僕らは懸命に坂を上がった。追い払おうと、下士たちが迫ってくると、かえって盛んに、(先生、先生)(犬飼さま!) こちらに気付いた先生が、(患者だ)と叫びながら下士たちを追い越した。普通の人は罹らない病気に悩まされがちな僕らを、ほかの患者がいないときに限られるものの、快く診てくれる先生だ。今は、元々の専門だった黴菌への知識を買われ、兵器補給廠の研究室に勤めている。
兵隊たちの手前だからか、その日の先生は芝居がかって見えるほど厳めしかった。
(どうしてここに君たちがいる。なにをしに来た)
(くだんを買いに来たのです)とお父さんが答える。
(あれは噂に過ぎない。諦めて帰りたまえ)
(ではあのトラックは?)
(特別なものは乗っていない。不要な牛を実験用に買い取っただけだ)
(分かりました、そう納得いたします)そうお父さんは頷いたものの、相手への気易さから微笑まじりに、(犬飼さま、ひとつだけ教えてください、くだんは本当に喋るのですか)
(私に分かるか)と、先生は冷水を浴びせるように返してきた。(そんな生き物は世に存在しないというのに)
お父さんは唇をむすんで先生を見つめた。先生も見つめ返した。
(そうでした)
お父さんが引き下がると、先生はようやっと表情をゆるめて、
(ここまで来られたのだから、みな体調は悪くないようだ)
(お蔭さまで)
(道中、気をつけて帰りたまえ)
……土埃を巻き上げてトラックが坂を下っていく。犬飼先生を乗せた自動車もそれに続き、居残っていた下士や軍属も走り去った。見送っていた主人や家人たちが、門口を閉ざしはじめる。
(本当のところはどうなんだって、あの人たちに訊いてみようか)兄さんがお父さんを振り返る。
(どうせ口止めされているだろう)
僕らもまた、坂道を下りはじめた。またこれまでどおりの日々に帰っていくのだ。お父さんの落胆は察しながらも、正直なところ僕はほっとしていた。
くだんは得られそうもないとなり、気持ちに余裕の生まれた清子さんが、さっきまでとは一変、その姿を拝めなかったことを残念がっている。(いくら兵隊さんたちの手前とはいえ、犬飼先生の態度は変だった。やっぱりあのトラックに乗っていたのよ。私たちが苦労してやって来たのは分かってるんだから、後学のために覗かせてくれても良さそうなものじゃない)
(後学って、清子はくだんから何を教わりたかったんだい)とお父さん。
(ふるまいや声や、いくらでも為になるわ。本物のあいのこなんだから)
(そういう話か。私はまた、お前も自分の寿命を知りたいのかと思ったよ)
(それは御免)
(たとえくだんを買えたとしても、私と桜以外は近付かせないつもりだった。桜なら、くだんの言葉も通じないだろうからね)
(和ちゃんにも聞えないわ)
(和郎は最も遠ざけないといけない。声が聞えなくとも人がなにを言っているのか解る子なんだから、くだんと目が合っただけでも、きっとおかしくなってしまうよ)
このお父さんの言葉に、僕は震え上がった。本当にトラックにくだんが乗っていたんだとしたら、これは大変なことになったと思った。
お父さんが犬飼先生と話している最中、僕はちらちら、トラックの荷台へと視線を向けていた。なにとはなし、呼ばれているような気がしたのだ。格別な呼ばれ方ではなくて、知らない人から不意に(腕無し)とか(化け物)と呼ばれたときのような、つまり僕にとっては普通な感じだった。
帆布の薄い隙間に、荷台を囲むあおり板が覗いている。内には檻でも収まっているのか、ただ黄色っぽい薄闇だけがあった。何度も見直しているうち、ふと、その闇が濃くなった。確かだ。
それでいて、小さな水たまりのような一点だけが、外の光を撥ね返していた。
本当に乗っていたのなら、僕を見ているくだんの眼だったことになる。
僕は同じような夢ばかりみるようになった。くだんとは無関係な夢だったが、それが続くほど、くだんの仕業に違いないという確信は深まった。
海の夢だった。兄さんや桜と浅蜊や石蒓を採りにいく、いつもの海岸ではなく、ずっと沖合の夢だ。
家族はみな舟上にいる。半開きにされた雨除けの被いの向こうには、低い曇り空、黒ずんだ波、そして白い泡。どの方角を向いても同じ景色だった。僕らは舟ごと、海原を漂っている。
どこか遠くを目指しているようだが、僕らの舟に帆を掛ける柱はなく、誰かが漕いでいる様子もない。ひたすら波まかせの、いつどう終わるとも知れない舟旅の途上に、僕らはいた。
遠い波間にふと、こちらと似たような舟影が現れる。(ほかの舟だ)(舟?)とみな驚いて被いの外に顔を突き出す。とても珍しい事態らしい。
さらに波の悪戯か、舟同士が急接近する。ともに急な川でも下っているかのように、相手はみるみる迫ってくる。いざ間近にすると、こちらより遥かに立派な舟だ。長さも幅も倍はありそうだ。
激突を避けるべく、昭助兄さんが竹竿を構えて舳先に立つ。二艘はなお距離を縮め、とうとう兄さんの竹竿がつっかえる。竿が激しく撓る。兄さんが跳ね飛ばされやしまいかと、僕は心配になる。
(なに、滅多にあることじゃないさ)竿と格闘しながらも、兄さんはこの椿事を楽しんでいるようだ。
(こんなに近付くなんてねえ)と清子さんが歌うように言う。
先方の船頭が、なにかをこちらに投げようとしているのに気付いて、僕も雨除けから出ていく。投げ込まれてみれば襤褸にくるまれた石で、それに赤い縄を縛り付けてある。ぶつかって舟が破損する前に、引き合って互いを繫留しようという提案だろう。
僕は縄を足で押さえ込み、口で結び目をほどきはじめる。
お父さんが躄ってくる。繫留を手伝ってくれるのだと思い、僕は場所を空ける。
僕の予想ははずれる。お父さんは手早く縄をほどくや、その端で自分の身を縛ってしまう。(今を逃したら、こんな機は二度と巡ってこない)
一瞬、お父さんは僕に笑いかける。それから海に飛び込む。舟同士がまた離れはじめる。 新しい舟に引き上げられていくお父さんを見つめながら、僕は、またこうなってしまった、と嘆息する。しばらく泣く。別の夢では清子さんが、また別の夢では昭助兄さんが、同じようにして海に飛び込んだ。そして新しい舟に引き上げられるのだった。
夢には、より奇妙な続きがある。相手の舟影が波間に消えてしまうまで見つめたあと、僕がしょんぼりと雨除けの下に戻っていくと、そこにはちゃんと家族全員が揃っている。ほかの舟とぶつかりかけたことなど噓のように、それ以前となんら変わらぬ、物静かな風情で。
さっきのは、どこか余所の世界での出来事だったらしい。僕はそう納得して、ほっとする。かといって去っていったほうの家族のことも、忘れてはいない。忘れられるはずがない。
僕は夢を数えていた。四十九回続いて、この明け方には五十回めをみるのだろうと思っていた月の明るい晩、不意に犬飼先生が僕らの舟を訪れた。
(夜分に失礼するよ。雪之助をお借りしたい)
お父さんのことだ。脱疽にかかる以前は旅芝居の花形だった。そして犬飼先生はその時代、一番の御贔屓だったのだそうだ。京都より西の興行なら、必ず初日に駆けつけてくれたという。
先生の態度には、岩国で会ったときの厳めしさとはまた違う、どこか悲しげな重苦しさが漂っていた。(折り入っての話がある。ちょっと医院まで来てもらえまいか。上に車を待たせてある)
(診察でしょうか)
(そうではない。ただ話をするだけだ)
(では、いまここで済ませてはいただけませんか)すでに眠りかけていたお父さんは、外出を億劫がった。(もしご内密なら、子供たちは小屋の方へ払います)
興行に必要な資材や道具は、近くの橋の下の掘建て小屋にしまってある。僕らの別宅といったところだが、河が増すと床上まで水が上がってくるので、寝泊まりには向かない。
(無理をさせたくはないのだが)先生はちらりと僕を見た。(和郎はどのくらいの距離までなら、その)
(人の心を読めるか、でございますか)
(うん)
(私にも見当がつきません。傍にいるものと思い込んで呼びかけたら、河原から上がってくることもあります。しかし口もきけませんし、読み書きもできませんから、誰に伝わる気遣いもございません)
お父さんはそう言ったが、本当は桜とだったら話せる。隠しているつもりはなかった。ふたりとも周囲にそう説明できないだけだった。
先生はかぶりを振って、(やはり来てもらいたい)
(昭助は同行させても? さもないと犬飼さまにおぶっていただくことに)
(同行は構わないが、話の間は外で待たせてほしい)
お父さんは了承し、留守を頼もうとして清子さんを呼んだ。どこからも返事がない。こっそり出掛けてしまったようだ。お父さんは僕に留守番を頼んで、寝入っていた昭助兄さんを揺り起こした。
兄さんは生返事をして雨除けの外に出ていき、河に小便をしてから戻ってきた。お父さんを背負ってからも、はんぶん眠っているように見えた。
三人が舟を降りて河原を横切り、土手を上がっていくのを、僕はじっと見送った。
「和郎さん」
呼びかけられて振り向くと、とうに眠ったものと思っていた桜が、頭を起こしてこっちを見ていた。
「お父さん、ほかの舟に乗ってしまう?」
そのとき悟った。桜もまた、僕と同じ夢をみ続けてきたことを。桜もくだんと目が合ったのだ。
僕は舟から飛び出し、土手を駆け上がった。すぐ下の道路に、走り去っていく自動車のランプが見えた。追い付くべくもない灯りを追って、僕は夜道を駆けた。裸も同然の格好だったが、そんなことは忘れていた。
いま引き留めなかったら、お父さんはほかの舟に移ってしまう。そのあとも僕らの舟に姿を留めてくれるかもしれないが、それはもはや、これまでのお父さんではないのだ。
犬飼医院の位置は分かっている。自動車を見失ってからは、思いつくかぎりの近道をとった。月の下を駆け抜けていく腕の無い影に、通行者は足を竦め、自動車は急停止した。どこか誇らしい思いが胸に満ちはじめる。誰しもが足を止めるのは、僕が特別な子供だからだ。
特別な子供が、特別なお父さんのために走っているからだ。
医院の玄関先に人影は見えなかった。庭に入り、隣家とを隔てる木塀が照らされている箇所を見出して、その隙間に入っていく。あかりは間違いなく、お父さんの気配を含んでいた。
(和郎じゃないか)と後ろから呼ばれて、身を竦める。昭助兄さんだった。(急患かと思って灯籠の陰に隠れていたよ。追いかけてきたのか。どうした)
僕は窓の下まで、ぴょんぴょんと後退って見せた。人を招くときの合図である。
(覗きたいのか)
頷く。
(見つかるなよ。俺まで叱られるから)
兄さんも窓の下に来た。差し出された掌に足を掛け、その肩に上がる。
診察室の続きの、犬飼先生の居室だった。僕がちょうど見下ろせる位置に長椅子があり、先生とお父さんが、後ろ向きに隣り合っている。
(とどのつまり、どういう生き物であると、犬飼さまはお考えなので?)
(分からない。私の知識の及ぶ範囲ではない)
(では、それこそ、真実しか語らないというくだんならば、問えば正直に教えてくれるのではありませんか)
(もちろん何度も訊いたし、説明もされた。しかし話の基底が違いすぎて、論理的に理解するのが難しいのだ。無理に私たちの科学で割り切ろうとすれば、牛に寄生している何らかに過ぎない、ということになろう。しかしそれが学習してもいない人語で、我々の歴史の仔細を語る、まったく未知の現象ということになり、所詮は謎だらけだ)
(そんな謎めいた獣の言い分を、軍の上層は真剣に信じているのですね)
(鵜吞みではない。くだんの弁には上層部しか知らぬ事実が、あまりにも多く含まれているのだ。この世界の未来を知るからこそ、まるで千里眼のように、いまどこで何が起きているのか悟れるというわけだ)
(たとえば、たとえばですが、上層部に曲者がいて、周囲を意の儘にするため、からくりを弄しているといった可能性は)
(何度も言ってきたとおり、くだんは確かに生きている。心臓は鼓動し、糞も小便も垂れ、怪我をすれば血を流す。そんなからくりが作れるものか)
(何を食べるのですか)
(仔牛と同じだ。牛の乳をやたらと欲しがる。あとは大概、鼾をかいて眠っている)
(その同じ口が、やがて本土に恐るべき爆弾が落ちると言っているのですね、都市がまるごと消えてしまうような。そして日本は負けると)
(あくまでこの世界での話だ。すでに上層のほとんどが補給廠を訪れ、くだんに導かれて別の世界に逃げていったよ、日本が勝ち残る世界に。私もそろそろ腹を括るべきかと思う。次にお前と会うとき、今と同じ私であるという自信はない)
(そこが分からないのでございます。犬飼さまが別の世界にお逃げになったとして、でも相変わらずこちらの世界にも犬飼さまはおられる。さっきそう仰有った。いったいそれで、犬飼さまの世界が変わったということになるのでしょうか)
(心の置きどころの問題、と、そう解釈しているよ。こう例えたらどうだろう。雪之助が脱疽に罹らず、花形でい続けられた世界があるとしよう。想像してみることはあろうね。そちらこそ本当の自分であって、脱疽のこちらは幻に過ぎないと、もしお前が確信できたなら、あとはそれこそ夢のなかにいるように、怪我をしても病気をしても痛くも苦しくもない。かりそめと思える痛み苦しみを、人は深刻には捉えないものだ。死も恐ろしくない。死んだら、次は本当の自分として目覚めるのだろうから)
(なにごとも気の持ちよう。そういうお話にしか、私には聞えません)
(私にだってそう聞える。しかしくだんがそう語るのだ、人智を超えた存在が。雪之助、この世界は過酷なうえ、医術にも限界がある。私はなんとしてでも、どこの世界ででも、お前を長く生かしたい)先生はお父さんを抱き寄せた。
(くだんは、確かに導いてくれるのですか)
(私は信じる。信じることにした)
先生はお父さんに接吻しはじめ、あとはまともな会話を成さなかった。居た堪れなくなった僕は、兄さんの肩から飛び降りた。
やはり僕と桜は、くだんから何かを受け取ったらしい。窓の向こうのやりとりには分からない言葉も多々あったが、大筋は理解できた。それでいて驚きを感じなかったのは、すでに僕らが別なかたちで、その内容を知っていたからだ。
お父さんを待たねばならない兄さんを残して、僕はふたたび河まで走った。いざ辿り着くと、舟の上に戻るのが怖くなった。きっと桜は起きたまま、僕の報告を待っていることだろう。最悪の結果を報告する勇気が、僕にはまだなかった。
舟の横を行き過ぎ、橋の下の掘建て小屋に向かった。しばらくその内に籠もって、気持ちを整理したかった。帰ってきたお父さんと兄さんが僕を探すとして、最初に覗いてみるのはあの小屋だろう。だからたとえ寝入ってしまっても、余計な心配をかけずに済む。
やがて清子さんと鉢合わせした。
(あら和ちゃん、小屋に行くの)
問われ、近付いていくと、湯を浴びてきた人独特の、なんとも言えない良い香りが漂ってきた。
僕の表情の変化に気付いたのか、彼女は急に態度を変え、(なに。お父さんに告げ口でもする? お前がどうやって?)とせせら笑った。
桜を抱きたがる旦那も後を絶たないが、それは清子さんにしても同じだった。彼女がこっそりと彼らに声をかけ、陰で身をひさいでいるのに気付いたお父さんは、二度三度、激しい調子で彼女を叱責した。
でも清子さんはやめない。お金が好きなのだ。それこそくだんが買えそうなほどたくさんのお金を、草陰で嬉しそうに数えているのを見たことがある。ふだんどこに隠しているのかは、誰も知らない。
僕らはいったん離れたが、(ちょっと和ちゃん)とまた呼び止められた。(ちょっとこっち向きなさい。お向きなさい。聞えてる?)
僕は振り返り、頷いた。
(今は私を莫迦にしているがいいよ。でも私がこうして必死に稼いでいるのは、お前を聾学校にやるお金だからね)
弟分に侮られまいとしての口から出任せだったのかもしれないが、ともかく彼女が発してきた言葉のうち、これほどまでに僕を啞然とさせたものはなかった。
(たぶん家族のなかで、お前がいちばん頭がいい。だからご時世が変わったら、お前は学校に行くんだよ、私が貯めたお金で)
僕はかぶりを振った。よりによってその晩だ。お前も舟を降りろと言われているようにしか感じなかった。冗談ではなかった。
(どうせそのときは来る。そのときじっくりと考えてみるがいい、自分の頭でね。お父さんだって、きっと長くはないんだから)
いっそう強くかぶりを振って、僕は小屋へと駆けた。そして翌朝兄さんが探しにくるまで、そのなかで踞って眠っていた。
(俺やお父さんに放っとかれて、ふて腐れてたのか? あのあと酒をご馳走になって、蒲団で寝かせてもらったんだよ。お父さんもそうしろって)
兄さんはすまなそうに言い訳したが、べつに羨ましくはなかった。家族が揃った舟の上のほうが寝心地がいいに決まっている。
陽の下に出てしばらくしてから、五十回めの夢をみなかったことに気が付いた。
犬飼先生は頻繁にお父さんを連れ出すようになった。お父さんのほうも億劫がらなかったし、酒にありつきたい昭助兄さんに至っては、お伴が楽しみでならない様子だった。
ふたりが帰ってくるたび、僕と桜は怖々とお父さんのふるまいや顔色を窺っては、出掛ける前と変わりないかどうかを討議した。しかし、たぶん変わっていない、という確証のない期待ぶくみの結論に至るばかりだった。念のため、兄さんに変化がないかどうかも僕らは観察していた。こちらはお父さん以上に、まったく変わるところなく見えた。
いま何が起きているのかを兄さんと清子さんに伝えるべく、僕と桜はそのための手段を検討した。ふたりとも喋れないし、読み書きもできない。読み書きを学びたくとも、人にそう伝えるすべを持たない。
しかし僕には絵が描ける。足の指で筆を握れば、そればかりはそんじょそこらの手のある人々より、遥かに上手いという自負があった。桜は耳が聞える。僕とは違い、音による会話とはどういったものなのか、想像ではなく事実として知っている。真似をする余地がある。 「できるとは思えない」と桜は及び腰だった。「自分でも何度も試してきた。でも私の舌はほかの人たちのようには動かない。動かし方が分からない」
昭助兄さんや僕のように、清子さんのように、たんに特別に生まれついたというのではなく、二人として生まれたあとで半分にされてしまった桜には、生来無いところをほかが勝手に補ってしまうような、いわば野生の逞しさがない。蛙を吞もうが彫り物を入れようが、それらは見世物の蛇女を補うだけのものであって、桜を補ってきたわけではなかった。
彼女の賛同を待たずに、僕は小屋に籠もっては、不要な板きれに絵を描くようになった。海原に浮かぶ僕らの舟。近付いてくる別の舟。それに移るお父さん。夢の情景を幾つにも分けて描いて、かつて昭助兄さんに連れられて遠くから眺めた、紙芝居のようなものに仕立てようとしていた。
桜の決意を僕がじかに聞くことはなかったが、彼女なり陰での努力を始めていることは、家族が喋っているさまを見つめる、そのまなざしから明らかだった。ある夕方、兄さんと僕が河原で炊事をしているとき、おもむろに舟から降りてきて、 「聞いていて」と僕に呼びかけた。
(どうした桜。腹でも痛いのか)と兄さんが心配して尋ねる。
それほどに、桜は緊張で青ざめていた。ひょっこひょっこと僕らの近くまで来ると、振り返って舟を指差して、(舟)と言った。
どの程度の出来映えだったのか、僕にはそれを知るすべがない。兄さんはきょとんとしていた。桜の顔に落胆の色がひろがる。俯く。そのうち兄さんは、なにか思い出したような素振りで舟に戻ってしまった。僕と桜は河原に取り残された。桜は泣きはじめた。
奇妙に長い静寂のあと、(桜)という呼びかけに顔をあげると、お父さんを背負った兄さんが、舟から降りかけていた。
後ろに清子さんもいた。(桜、喋ったんだって?)
(舟と言ったよ。言ったよな? お父さんにも聞かせてあげてくれ)
そう明るく兄さんに促されて、桜はかろうじて気をとりなおし、やがて再び、浮き世の言葉を発したのだった。
(舟)と。
秘かな練習の成果は、それだけではなかった。次いでお父さんを指差して(お父さん)と言った。
(お父さん、聞えたかい)
(うん、聞えた)
(俺は? 俺は?)
(昭助さん)と桜は言い、さらに清子さんと僕とを続けて指しながら、(清子さん、和郎さん)
兄さんはお父さんを背負ったまま小躍りした。(この人は?)
(お父さん)
(俺は?)
(昭助さん)
(この人は?)
(清子さん)
(あいつは?)
(和郎さん)
(あれは?)
(舟)
調子に乗った兄さんは、空や対岸や河原の上のあちこちを指しては(あれは?)(これは?)とも尋ねたが、桜は笑いながらかぶりを振った。最初は、五つだけだった。お父さん。昭助さん。清子さん。和郎さん。舟。
他方、僕の制作も順調だった。絵具の種類が乏しかったため彩色には不満足ながら、細長い板二枚続きの、ちょっとした絵物語のていを成すに至っていた。まず桜に見せると、彼女の夢もおおむねその通りだったと言う。
僕らは小屋に昭助兄さんを招いた。絵を見せた。
兄さんは僕の画力を称賛してくれた。桜が絵に指を添えては言葉を発するたび、彼女の頭を撫でたり抱き締めたりもした。しかし残念ながら、僕らの本来の目的は果たしえなかった。兄さんは僕らの一連の行動を、新しい遊びとしか捉えてくれなかった。単語を羅列するばかりの桜の言語能力は、煩瑣な概念の説明にはあまりにも不向きだったのだ。
彼女は癇癪を起こし、また泣きはじめた。絵が拙いせいだと僕は彼女を慰め、描き直しを約束した。
約束が果たされるときは訪れなかった。少なくとも僕の認識においては。 その夕方、また犬飼先生がやって来たのだ。そして僕らを呼び集め、こう言った。(岩国ではすまなかった。くだんは補給廠にいるよ。さあ、みんなで会いにいこう。それが君らのお父さんの希望だ)と。
ぞろぞろと土手を上がっていく途中、例の、不意に呼びかけられたような感覚があって、僕は河のほうを振り向いた。しかし眼下にひろがっているのは、草が揺れ、河面が揺れ、僕らの舟がゆったりと上下しているだけの、普段と変わらぬ景色だった。
繕いものが得意な清子さんが、薄い箇所を見つけては新しい布を縫いつけてきた雨除けが、強い夕陽に照らされ、戦争がひどくなる前に物陰から覗いたことしかない縁日の参道のような、なんとも言えない色彩の饗宴をなしていた。自分が最も満たされた気持ちにつつまれるのは、この土手からあの舟を見下ろすときだったことを、僕はあらためて思い出した。
犬飼医院で、先生とその腹心らしい若い兵士の手により、僕らは輸送用の木箱一つに詰め込まれた。お父さんと僕に腕や脚が無く、昭助兄さんは一寸法師、桜も最初から体が曲がっているから、辛うじて入れたようなもので、犬飼先生とその家族だったら二人で限界だったろう。
肌という肌がすべて家族と密着しているような状態で、持ち上げられ、落とされ、横倒され、また横倒され、延々と揺さぶられ、落とされ、揺られ、また落とされ、長いこと待たされ……ようやっと僕らは釘抜きの音を聞いた。箱の一方が開き、僕らは外に這い出た。さっきまで一つの肉塊のようだったのが、五つの肉体へと戻った。
はじめ戸外かと思ったのだが、塀だと感じていたものを見上げていくと、ずいぶんな高さに天井の梁があった。あちこちに大量の木箱が積まれている。全貌が分からないほど広大な倉庫の片隅に、僕らはいた。
いっそう隅に、まるで僕らが興行のために建てるような掘建てがあり、その周囲にだけ電灯が点っていた。
(窮屈な思いをさせたね。くだんはあのなかだ)と先生が僕らに言った。(そろそろ夜が冷えてくるし、それなりに臭いもあるんで、急拵えしたんだよ)
兵士が筵をまくり、その次の覆いもまくって電灯を点す。柵の向こうにくだんがいた。膝を折って藁の上に寝そべっていた。想像していたよりずっと大きかった。体も、顔も。
人の顔をしているとは、僕は感じなかった。赤い、鬼の面に似ていた。褐色の毛皮を割るように、それが肩の下ににゅっと生えているさまは不気味だったが、必ずしも恐ろしくはなかった。眠たげに瞼を動かしている大きな眼と、固くむすばれた口許が、一切を諦めているような静けさを湛えていた。
(話をしても?)
お父さんが先生に問い、先生も頷いたが、
(お久し振り)と、くだんのほうがさきに挨拶してきた。低く深い声だった。(岩国でお会いして以来ですね)
(私たちを見ていたのか。憶えているのか)とお父さんが驚く。
(トラックの荷台の、被いの隙間からお姿を拝見しました。どこへなりとお連れしましょう。そして私は殺されましょう)
僕らは顔を見合わせた。
犬飼先生が問う。(誰がお前を殺すというのだ)
くだんはかしらを巡らせ、(そちらの若い兵隊さんです。私のことを、戦意を喪失させるために敵国から送り込まれた兵器であると、本気で考えておられます)
(斐坂くん、事実か)
兵士はぎょっと目を見開いたまま、直立不動となった。
(本当にそういう腹積もりだったのか)先生が重ねて訊く。
すると兵士は震え声で、(僭越ながら、只今の弁も、我々の攪乱が目的かと)
(決して独断するな。くだんを殺してはならん。返事は?)
(はい)
(雪之助、くだんに問いたいことがあれば)先生はそこで言葉を選んだ。(手短に)
お父さんは昭助兄さんに指示して、自分をくだんに近付けさせた。(お前は真実しか語らないと聞いた)
(あえて噓偽りを申し上げることはありません。そうすべき理由が私にはありませんから)
(その言葉を信じて問おう。お前はなぜ、私たちをほかの世界に導こうとするんだい?)
(導こうという意図はありません。私はそういう装置であると、皆さんにご説明しているだけです)
(装置? お前は機械なのか)
(いま問われました意味においては、機械ではなく生物です。しかし自然繁殖はしません。個体ごと人手によって生まれ、そして死にます)
(人の手で創られた生き物ということか)
(いかにも)
(それは未来での話かい)
(内海を巡回する航路があるとします。すると海上の一点は、船の前とも後ろともつきません。しかし私の生まれた座標が、ここからは未来と感じられやすい、というふうには申せましょう)
(それが歴史の姿なのか。ぐるぐると内海を巡るというのが)
(単純な円環とは限りませんが、どうあれ内海からは出られません。正確に言えば、外のことを私たちは感知できません。しかし航路は無数に存在します。そのさまを俯瞰し、意図的な乗換えをおこなうための装置が、私です)
(未来の人々が自分たちのためにお前を拵えたのだとしたら、なぜお前は私たちの前に現れ、今も留まっているんだろう)
(私は最初から海上の一点を漂っているに過ぎないのです。傍をさまざまな船が通過していきます)
(そのうちの一艘が、この私たちの歴史だというのだね)
(いかにも)
(凄まじい爆弾が落ちて、日本は負けると聞いた)
(この航路においては、その通りです)
(日本人は全滅かい)
(いいえ、全滅はしません)
(では)お父さんは大きく息をして、(ここにいる私たちのうち、いちばん早く死ぬのは誰だろう)
(犬飼先生です)
お父さんは愕然と、先生のほうを向いた。
(心配するな)と先生が硬い表情で応じる。(黙っていたが、私もすでに別の世界に逃げている)
僕がまたくだんに視線を戻した瞬間、その額にぽっと穴が生じた。くだんが撃たれた。そう気付いて振り返ると、兵士が拳銃を握ったまま身を震わせていた。
(斐坂、貴様)
犬飼先生が摑みかからんばかりの勢いで迫り、ふと後ろざまにひっくり返った。先生も撃たれたのだ。昭助兄さんが慌ててお父さんを下ろして、兵士に体当たりする。兵士は掘建ての壁の一枚ごと吹っ飛ばされた。
(さあ参りましょう)と、くだんが落ち着きはらった調子で言う。
(私はまだしばらく死にません)
(次は誰だ。次に死ぬのは)
(斐坂さんです。いま私を撃った兵隊さんです)
(次は)
(腕の無い坊ちゃんと、彫り物のお嬢さんです。同じ爆弾で)
(和郎、桜)お父さんは僕らを見上げ、切羽詰まった調子で、(行きなさい、急いで)
(本当は分かっているのですが、ご納得いただくため、その手続きとしてお尋ねします。おふたりをどういった世界にお連れしましょうか)
(和郎が学校に行けるところ)と清子さんが叫んだ。
(ふたりが長く幸せに生きられる世界だ。こんな要望でいいのかい)
「みんなも。ほかのみんなも幸せに!」と桜が叫ぶ。
(承りました。和郎さん、桜さん、背中にお乗りください)
予想外の展開に、僕は茫然自失していた。舟を乗り換えるのは、僕と桜だったのだ。
(行きなさい)
お父さんの強い命令に、僕はただ従うほかなかった。柵を乗り越え、くだんの背中に跨る。後ろに桜が乗った。
牛馬に乗った経験がなかったので、くだんが立ち上がったとき、ふっと意識が遠のくような感覚に襲われた。直後、尻の下が大きく揺れて、はたと我に返った。くだんが倒れかけているのだと気付いて、咄嗟に藁の上へと飛び降りた。
くだんは前肢を折り、後肢も折った。横向きに、藁のなかへと身を沈めた。赤く大きな顔に僕は足を近付けてみたが、すでに呼吸していなかった。
(今ので、もう?)とお父さんは犬飼先生の許に躄ったが、そちらもすでに息を引き取っているようだった。
兵士も、くだんの予言どおり掘建ての外で死んでいた。先生を強く慕ってきた兄さんが、怒りのあまり渾身の怪力で殴り続けたせいだ。
以後の、僕らが帰属してきた歴史は、誰しもご存じのとおりだ。恐らくは犬飼先生が兵器として開発中だった細菌に、補給廠を訪れた誰かが感染しており、軍の上層に謎の死病が蔓延した。戦闘不能に陥った日本は、余力を残しながらも連合国に無条件降伏、国土は長い占領時代へと入った。
のちにGHQの総司令官となる男が、厚木海軍飛行場に降り立った瞬間の写真は、日本国民をおおいに驚かせた。アメリカ極東軍の司令官時代、乗っていたボーイング機を日本の戦闘機群に撃ち落とされ九死に一生を得た彼は、片方の腕と片方の脚を完全に欠いていたのだ。
にもかかわらず私怨を感じさせない彼の良心的な統治は、国民の絶大な支持を得た。チェコスロヴァキアの作家カレル・チャペックの愛読者でもあった彼は、同作家の戯曲に登場する人造人間の実現を確信しており、その意向は戦後の日本に、代替臓器、代替四肢の技術を花開かせる原動力となった。
僕たち一家には、うんざりするほどたくさんの大学や企業から、慈善の手が差し伸べられた。新技術に対する恰好の被験者の集まりだったからだ。
まず終戦五年めにして、お父さんが新しい両脚を得た。現在の代替肢と較べたらじつにお粗末、そのくせ維持にはやたらと手間のかかる代物だったが、そのお蔭で彼は余生において三度も、大きな舞台に立つことができた。
次に清子さんが新しい膝を得た。頭から角を取り去り、鼻の余計な穴も塞いだ彼女は、特別な経歴も手伝って新聞や雑誌に引っ張り凧となり、やがて映画にも出演した。
日進月歩の戦後医療も、昭助兄さんの背を伸ばす打出の小槌とはならなかった。だけど技術が生まれていたとしても、兄さんは断固として断ったろう。日本に最初のプロレス団体が出来るや、すぐさまスカウトマンが彼の許を訪れていた。泣く子も黙る世紀の悪漢、ドワーフ昭助、誕生の瞬間だった。
僕と桜は、清子さんの出資で聾学校に通った。桜は聾者ではないが、話す技術を知らないということで生徒に相応しいと認められた。今の僕は二本の腕も得ている。しかし活用しているとは言いがたい。絵が仕事だ。細かい作業だ。新しい人工の指先が、使い慣れた足以上に役立つはずもない。日常の大概のことも、鍛えあげてきた足や歯や、あえて肩に残してもらった小さな指で事足りてしまう。
桜に新しい皮膚をという勧めも後を絶たなかったが、彼女は断り続けた。僕が下絵を描いた彫り物に愛着があって、取り替える気がしないと言う。ただし背骨だけはまっすぐにしてもらった。
お父さんとは死別、清子さんや昭助兄さんも今は離れて暮らしているけれど、桜と僕だけは一緒にいる。仲がいいときも悪いときもあるが、お互い自在に話せる相手と、簡単に離れられるものではない。
あの河原の近くに住んでいる。散歩で土手の上を通るたび、ふたりして僕らの舟が浮かんでいた場所を見下ろす。今の僕らの、最も幸福で、最もせつない時間だ。
心の置きどころの問題だと、犬飼先生はお父さんに解説していた。だとしたら、くだんは僕らを運びきれなかったに違いない。運びきる前に死んでしまったのだ。だって僕らの気持ちは相変わらず、あの悲惨な世界にある。僕と桜にとってはやがて爆弾によって終わってしまう、短く虚しい世界だったのかもしれないが、こちらのかりそめの自分が死んだら、また心はあそこに戻っていくという、確信めいた想いから僕らは逃れられずにいる。
色とりどりの襤褸をまとった、あの美しい舟の上に。